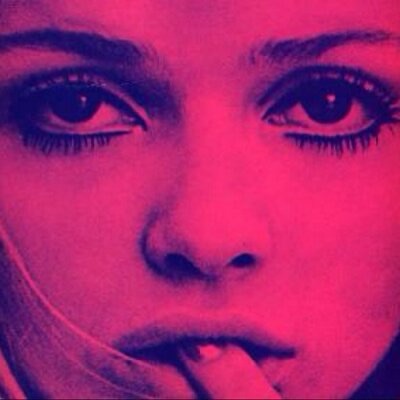大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる改訂

大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる改訂
トリップ
プロイスラー
オットフリート・プロイスラー
フランツ・ヨーゼフ・トリップ
中村浩三
偕成社
1990年7月1日
4件の記録
 中根龍一郎@ryo_nakane2025年6月26日かつて読んだ読み返したザワークラウトという食べ物をはじめて知ったのは小学生のころに読んだこの本だった。カスパールのおばあさんが毎週木曜日につくる、なべいっぱいのほかほかのザワークラウトと、じゅうじゅう音をたてる焼きソーセージ……子供の私はもちろんザワークラウトを食べたい、ということを母にリクエストした。ザワークラウトって酸っぱいキャベツだよ、と母は困惑しながらも用意してくれた。でもそれは瓶詰めのしんなりしたキャベツで、ホッツェンプロッツで読んだような、なべでほかほかのゆげをたちのぼらせる食べ物ではなかった。なにかへんだな、もしかするといろいろなザワークラウトがあるのだろうか、といぶかしみながら、母のつくってくれた焼きソーセージとザワークラウトを食べた。そのあとザワークラウトが食卓に並ぶことはなかったのを思うと、あまり私の反応はかんばしくなかったのかもしれない(母は私が喜んだ食事は定番にしてくれるのが常だった)。 大きくなってから、東欧にビゴスというザワークラウトの煮込みがあることを知った。でもビゴスはザワークラウトとソーセージを一緒に煮込むものだそうだから、ザワークラウトだけをなべいっぱいに煮ているカスパールのおばあさんの料理とはすこし違う。木曜日だけザワークラウトとソーセージの料理をするというのは、なにかの宗教性を感じさせもするけれど、しっくりくるものは見当たらない。プロイセン、ハンガリー、ポーランドといった大きな文化圏にまたがり、近接していた、ドイツ語圏のどこかに由来を持ち、どこかで変形していった家庭料理ということなのかもしれない。 ホッツェンプロッツのシリーズは好きで、3冊読んだけれど、とりわけ思い出深いのが『ふたたびあらわる』で、それはザワークラウトによるところと、ホッツェンプロッツが変装をする話だというのが大きい(子供のころから、「変装」はとても好きなモチーフだった)。でもいま改めて読み返すと、当時は素通りしていた、ホッツェンプロッツの大きな鼻とひげもじゃの風貌がとても気になってくる。 ホッツェンプロッツは典型的な「悪人の顔」だ。なるほど、これは悪いやつだな、と子供心に思わせる人相をしている。でもそこで強調されている特徴は、実は、ユダヤ人的なものでもある。ただ、そこには積極的なユダヤ人差別というより、素朴な文化的図像の継承があるのかなということも思わせる。悪人として表象されるものが典型的にはどんな人相をしているのか。そしてその人相はどんな人種を代表しているのか。 読み返しているうちに、もうひとつ、子供のころ印象深かったシーンを思い出した。ホッツェンプロッツはカスパールとゼッペルへの復讐心を胸に独白する。 まず、カスパールとゼッペルだ。やつらがおれをぶちこみゃあがったのだから、ただですませるものか! あしたにでも、さっそくまちぶせしてやろう。そして、つかまえたらさいご、やつら二ひきでシチュー用の肉をつくってやる! そうだ——シチュー肉だぞ、へ、へ、へ、へへへ…… (『大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる』p.67) 邪悪な存在が人肉食をするという見方、つまり共同体の外部の存在を「人食い」として名指す文化はどこにでもある。でもホッツェンプロッツはそうした共同体の外部の、理解不能な怪物のようなものというより、子供としても感情移入できるようなキャラクターだった。そのホッツェンプロッツがとつぜん人肉食への欲望を口にするというのは、なかなかショッキングだった。 トカゲ人間が子供の生き血を飲んでいるという陰謀論でも、ユダヤ人の血の中傷でも、「コミュニケーション可能な存在が実は人間を食べている」というストーリーの類型がこの世にはある。そのフォークロア的な偏見がたまたま子供向けの作品にあらわれたのだろう。でも児童文学にはそうした「悪の典型」についての偏見が、しばしば素朴な形であらわれてしまう。すこし考えさせられた。 物語はホッツェンプロッツがきのこのスープを食べることによって終わる。ザワークラウトのなべ、人肉のシチュー、きのこのスープ、汁物をめぐるストーリーだ。読んでいるうちになにかなべでつくりたくなってくる。
中根龍一郎@ryo_nakane2025年6月26日かつて読んだ読み返したザワークラウトという食べ物をはじめて知ったのは小学生のころに読んだこの本だった。カスパールのおばあさんが毎週木曜日につくる、なべいっぱいのほかほかのザワークラウトと、じゅうじゅう音をたてる焼きソーセージ……子供の私はもちろんザワークラウトを食べたい、ということを母にリクエストした。ザワークラウトって酸っぱいキャベツだよ、と母は困惑しながらも用意してくれた。でもそれは瓶詰めのしんなりしたキャベツで、ホッツェンプロッツで読んだような、なべでほかほかのゆげをたちのぼらせる食べ物ではなかった。なにかへんだな、もしかするといろいろなザワークラウトがあるのだろうか、といぶかしみながら、母のつくってくれた焼きソーセージとザワークラウトを食べた。そのあとザワークラウトが食卓に並ぶことはなかったのを思うと、あまり私の反応はかんばしくなかったのかもしれない(母は私が喜んだ食事は定番にしてくれるのが常だった)。 大きくなってから、東欧にビゴスというザワークラウトの煮込みがあることを知った。でもビゴスはザワークラウトとソーセージを一緒に煮込むものだそうだから、ザワークラウトだけをなべいっぱいに煮ているカスパールのおばあさんの料理とはすこし違う。木曜日だけザワークラウトとソーセージの料理をするというのは、なにかの宗教性を感じさせもするけれど、しっくりくるものは見当たらない。プロイセン、ハンガリー、ポーランドといった大きな文化圏にまたがり、近接していた、ドイツ語圏のどこかに由来を持ち、どこかで変形していった家庭料理ということなのかもしれない。 ホッツェンプロッツのシリーズは好きで、3冊読んだけれど、とりわけ思い出深いのが『ふたたびあらわる』で、それはザワークラウトによるところと、ホッツェンプロッツが変装をする話だというのが大きい(子供のころから、「変装」はとても好きなモチーフだった)。でもいま改めて読み返すと、当時は素通りしていた、ホッツェンプロッツの大きな鼻とひげもじゃの風貌がとても気になってくる。 ホッツェンプロッツは典型的な「悪人の顔」だ。なるほど、これは悪いやつだな、と子供心に思わせる人相をしている。でもそこで強調されている特徴は、実は、ユダヤ人的なものでもある。ただ、そこには積極的なユダヤ人差別というより、素朴な文化的図像の継承があるのかなということも思わせる。悪人として表象されるものが典型的にはどんな人相をしているのか。そしてその人相はどんな人種を代表しているのか。 読み返しているうちに、もうひとつ、子供のころ印象深かったシーンを思い出した。ホッツェンプロッツはカスパールとゼッペルへの復讐心を胸に独白する。 まず、カスパールとゼッペルだ。やつらがおれをぶちこみゃあがったのだから、ただですませるものか! あしたにでも、さっそくまちぶせしてやろう。そして、つかまえたらさいご、やつら二ひきでシチュー用の肉をつくってやる! そうだ——シチュー肉だぞ、へ、へ、へ、へへへ…… (『大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる』p.67) 邪悪な存在が人肉食をするという見方、つまり共同体の外部の存在を「人食い」として名指す文化はどこにでもある。でもホッツェンプロッツはそうした共同体の外部の、理解不能な怪物のようなものというより、子供としても感情移入できるようなキャラクターだった。そのホッツェンプロッツがとつぜん人肉食への欲望を口にするというのは、なかなかショッキングだった。 トカゲ人間が子供の生き血を飲んでいるという陰謀論でも、ユダヤ人の血の中傷でも、「コミュニケーション可能な存在が実は人間を食べている」というストーリーの類型がこの世にはある。そのフォークロア的な偏見がたまたま子供向けの作品にあらわれたのだろう。でも児童文学にはそうした「悪の典型」についての偏見が、しばしば素朴な形であらわれてしまう。すこし考えさせられた。 物語はホッツェンプロッツがきのこのスープを食べることによって終わる。ザワークラウトのなべ、人肉のシチュー、きのこのスープ、汁物をめぐるストーリーだ。読んでいるうちになにかなべでつくりたくなってくる。