日本の「安心」はなぜ、消えたのか 社会心理学から見た現代日本の問題点

2件の記録
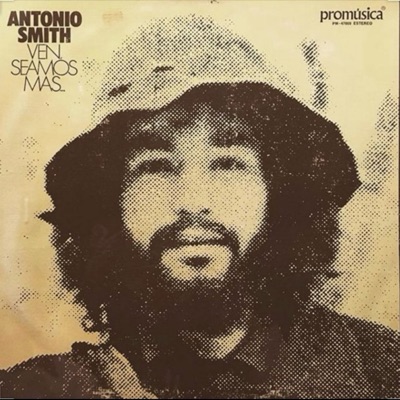 J.B.@hermit_psyche2026年2月12日読み終わった日本社会が長らく自明視してきた「われわれは道徳的で、誠実で、互いに配慮し合う民族である」という自己像を、社会心理学の実験的知見と理論枠組みによって静かに、しかし容赦なく解体していく書物である。 本書が射程に収めているのは、単なる治安悪化やモラル低下といった通俗的言説ではない。 安心という感覚が成立していた条件そのものが、構造的に失効したにもかかわらず、日本社会がなお過去の前提にしがみつき続けているという認識の遅延、その心理的・制度的な歪みが、いかに現代日本の諸問題を連鎖的に生み出しているかを描き出す点に、本書の知的強度がある。 山岸の議論の核心は、安心社会と信頼社会という二項対立にある。 ここで言う安心とは、他者が善意を持っているから安全なのではなく、裏切りや逸脱が事実上不可能、あるいは極端に不利になるように制度や人間関係が閉じている状態を指す。 村落共同体、終身雇用、年功序列、家族主義的企業文化といった戦後日本を支えた諸制度は、個々人の徳性に依拠せずとも、行動を安全な範囲に閉じ込めることで、結果として高い秩序と協調を生み出していた。 つまり日本の安心は、道徳の勝利ではなく、選択肢を狭めた社会設計の副産物だったという逆説が、ここで提出される。 しかし社会が流動化し、関係が開かれ、選択肢が増えたとき、この安心は脆く崩れる。 山岸が一貫して主張するのは、日本社会は信頼社会への移行に失敗したのではなく、そもそも移行しようとすらしていない、という点である。 信頼とは、相手が裏切る可能性を前提にしつつ、それでもなお相互行為を成立させるための制度的・認知的装置であり、透明性、契約、説明責任、制裁可能性といった要素を必要とする。 ところが日本では、安心社会の記憶が規範意識として温存され、「本来人は正直であるはずだ」「空気を読めば分かるはずだ」という期待が、開かれた社会の不確実性を処理する代替物として使われてしまう。 その結果、裏切りの可能性を制度で管理する代わりに、道徳的非難や同調圧力が過剰に動員され、むしろ信頼を破壊する方向に作用する。 本書が鋭いのは、日本人の行動を文化本質論に還元する誘惑を徹底して拒否している点にある。 日本人が正直に見えるのは、正直であることが得だった環境に長く置かれてきたからであり、和を重んじるのも、対立が高コストになる閉鎖的関係の中で合理的な戦略だったからにすぎない。 環境が変われば行動も変わる。 この冷徹なまでに反ロマン主義的な視線は、日本文化論にありがちな情緒的自己肯定を一掃し、日本人を例外的存在ではなく、状況に適応する合理的行為者として位置づけ直す。 その意味で本書は、日本人論であると同時に、日本人論の終焉を告げる書でもある。 いじめ、企業不祥事、若者の空気読みといった具体的問題の分析も、単なる社会批評に堕していない。 いじめの存続条件を臨界質量という概念で捉え、少数の行動変化が全体の力学を転換しうることを示す議論は、道徳的説教よりもはるかに実践的である。 また企業の嘘を個人の倫理欠如に帰するのではなく、内部告発が合理的選択にならない制度設計そのものを問題化する視点は、日本社会に根深い心がけ信仰を正面から否定する。 ここで繰り返し示されるのは、善意や精神論に期待する社会ほど、実は不正に脆弱だという逆説である。 とりわけ挑発的なのは、武士道精神や美徳として語られてきた自己犠牲的モラルが、現代社会では信頼形成を阻害しうるという指摘である。 黙って耐えること、空気を乱さないこと、内面の善を信じることは、閉じた共同体では秩序を支えたが、開かれた社会では問題を不可視化し、責任の所在を曖昧にし、結果として誰も信頼できない状況を生む。 この転倒を直視しない限り、日本社会は安心が失われたと嘆き続けながら、その原因を永遠に誤認し続けるだろう。 本書を貫く知性は、悲観主義でも楽観主義でもない。 山岸は、日本社会が信頼社会へ移行することは可能だと示唆するが、それは文化を称揚することでも、道徳を復活させることでもなく、冷静に人間を信用しない制度を設計することによってのみ達成される。 人を信じるためには、まず人を信じなくても社会が回る仕組みを作らねばならないという、この一見矛盾した命題こそ、本書の到達点である。 本書は、失われた安心をノスタルジーとして回収する書ではない。 それは、安心という幻想が成立していた条件を解剖し、その終焉を受け入れた先にしか信頼は生まれないことを、知的誠実さをもって示す書である。 読後に残るのは慰めではなく、構造を変えよという無言の要請であり、その冷たさこそが、本書を単なる時評ではなく、長期的に参照される思想書へと押し上げている。
J.B.@hermit_psyche2026年2月12日読み終わった日本社会が長らく自明視してきた「われわれは道徳的で、誠実で、互いに配慮し合う民族である」という自己像を、社会心理学の実験的知見と理論枠組みによって静かに、しかし容赦なく解体していく書物である。 本書が射程に収めているのは、単なる治安悪化やモラル低下といった通俗的言説ではない。 安心という感覚が成立していた条件そのものが、構造的に失効したにもかかわらず、日本社会がなお過去の前提にしがみつき続けているという認識の遅延、その心理的・制度的な歪みが、いかに現代日本の諸問題を連鎖的に生み出しているかを描き出す点に、本書の知的強度がある。 山岸の議論の核心は、安心社会と信頼社会という二項対立にある。 ここで言う安心とは、他者が善意を持っているから安全なのではなく、裏切りや逸脱が事実上不可能、あるいは極端に不利になるように制度や人間関係が閉じている状態を指す。 村落共同体、終身雇用、年功序列、家族主義的企業文化といった戦後日本を支えた諸制度は、個々人の徳性に依拠せずとも、行動を安全な範囲に閉じ込めることで、結果として高い秩序と協調を生み出していた。 つまり日本の安心は、道徳の勝利ではなく、選択肢を狭めた社会設計の副産物だったという逆説が、ここで提出される。 しかし社会が流動化し、関係が開かれ、選択肢が増えたとき、この安心は脆く崩れる。 山岸が一貫して主張するのは、日本社会は信頼社会への移行に失敗したのではなく、そもそも移行しようとすらしていない、という点である。 信頼とは、相手が裏切る可能性を前提にしつつ、それでもなお相互行為を成立させるための制度的・認知的装置であり、透明性、契約、説明責任、制裁可能性といった要素を必要とする。 ところが日本では、安心社会の記憶が規範意識として温存され、「本来人は正直であるはずだ」「空気を読めば分かるはずだ」という期待が、開かれた社会の不確実性を処理する代替物として使われてしまう。 その結果、裏切りの可能性を制度で管理する代わりに、道徳的非難や同調圧力が過剰に動員され、むしろ信頼を破壊する方向に作用する。 本書が鋭いのは、日本人の行動を文化本質論に還元する誘惑を徹底して拒否している点にある。 日本人が正直に見えるのは、正直であることが得だった環境に長く置かれてきたからであり、和を重んじるのも、対立が高コストになる閉鎖的関係の中で合理的な戦略だったからにすぎない。 環境が変われば行動も変わる。 この冷徹なまでに反ロマン主義的な視線は、日本文化論にありがちな情緒的自己肯定を一掃し、日本人を例外的存在ではなく、状況に適応する合理的行為者として位置づけ直す。 その意味で本書は、日本人論であると同時に、日本人論の終焉を告げる書でもある。 いじめ、企業不祥事、若者の空気読みといった具体的問題の分析も、単なる社会批評に堕していない。 いじめの存続条件を臨界質量という概念で捉え、少数の行動変化が全体の力学を転換しうることを示す議論は、道徳的説教よりもはるかに実践的である。 また企業の嘘を個人の倫理欠如に帰するのではなく、内部告発が合理的選択にならない制度設計そのものを問題化する視点は、日本社会に根深い心がけ信仰を正面から否定する。 ここで繰り返し示されるのは、善意や精神論に期待する社会ほど、実は不正に脆弱だという逆説である。 とりわけ挑発的なのは、武士道精神や美徳として語られてきた自己犠牲的モラルが、現代社会では信頼形成を阻害しうるという指摘である。 黙って耐えること、空気を乱さないこと、内面の善を信じることは、閉じた共同体では秩序を支えたが、開かれた社会では問題を不可視化し、責任の所在を曖昧にし、結果として誰も信頼できない状況を生む。 この転倒を直視しない限り、日本社会は安心が失われたと嘆き続けながら、その原因を永遠に誤認し続けるだろう。 本書を貫く知性は、悲観主義でも楽観主義でもない。 山岸は、日本社会が信頼社会へ移行することは可能だと示唆するが、それは文化を称揚することでも、道徳を復活させることでもなく、冷静に人間を信用しない制度を設計することによってのみ達成される。 人を信じるためには、まず人を信じなくても社会が回る仕組みを作らねばならないという、この一見矛盾した命題こそ、本書の到達点である。 本書は、失われた安心をノスタルジーとして回収する書ではない。 それは、安心という幻想が成立していた条件を解剖し、その終焉を受け入れた先にしか信頼は生まれないことを、知的誠実さをもって示す書である。 読後に残るのは慰めではなく、構造を変えよという無言の要請であり、その冷たさこそが、本書を単なる時評ではなく、長期的に参照される思想書へと押し上げている。


