遊びと人間

4件の記録
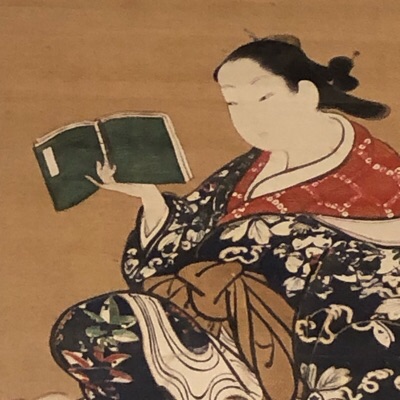 勝村巌@katsumura2025年10月27日読み終わった1958年にフランスで出版され1971年に翻訳版として出版された講談社版の文庫である。「遊び」を分析した本。 先行書としてホイジンガの『ホモ・ルーデンス』やシラーの『人間の美的教育について』を置き、そこで語られる遊びについて、カイヨワなりの批判的な補足説明を行なっている。 カイヨワによると遊びは競争、運、模擬、眩暈の4つに分類され、それらの組み合わせによって読み解くことができるという。 これを起点に文明や文化の発達を考察していく、という内容。 例えば原始的な文明では仮面を被り超自然な神的なものを模擬した存在がイニシエーションなどの眩暈を伴う活動で集団をまとめているが、そこがギリシアやローマ的に発展していくと、集団の母数が増えるため、よりルール化され、競争や運などに支配されることで合理化されていく、みたいなことが書かれていた。 競争は自力本願、運は他力本願という側面を持ち、自由な遊びの中にも、結果に対してフェアな態度が求められる、というか結果的にそうならざるを得ない、というようなことが書かれていたり、非常に面白い視点の本だった。 特に遊びの要素の中に身体的な眩暈の観点が含まれているのが独創的に思った。ジェットコースターに乗ってクラクラしたり、犬が自分の尻尾を追いかけたりする、というような行動を根源的な遊びの表れとして位置付けている。 遊びは自由だがルールがないと成立しない、とか、そういう考えだけだと身体性が薄れる。純粋な自己破壊的なシミュレーションのような形での眩暈は僕もよくやった。 何もない一本道で目を瞑ってどこまで歩けるか、とか、自転車に乗っているのに目を瞑ったり、手放しでどこまで行けるかとか試してみたくなる気持ちは眩暈の希求だと思う。 それがなんだ、という話はあるが、そういう事象が文明論にまつわる感じでスケール大きめに語られている。 少し時間は掛かるが、興味のある人は読んでみてください。
勝村巌@katsumura2025年10月27日読み終わった1958年にフランスで出版され1971年に翻訳版として出版された講談社版の文庫である。「遊び」を分析した本。 先行書としてホイジンガの『ホモ・ルーデンス』やシラーの『人間の美的教育について』を置き、そこで語られる遊びについて、カイヨワなりの批判的な補足説明を行なっている。 カイヨワによると遊びは競争、運、模擬、眩暈の4つに分類され、それらの組み合わせによって読み解くことができるという。 これを起点に文明や文化の発達を考察していく、という内容。 例えば原始的な文明では仮面を被り超自然な神的なものを模擬した存在がイニシエーションなどの眩暈を伴う活動で集団をまとめているが、そこがギリシアやローマ的に発展していくと、集団の母数が増えるため、よりルール化され、競争や運などに支配されることで合理化されていく、みたいなことが書かれていた。 競争は自力本願、運は他力本願という側面を持ち、自由な遊びの中にも、結果に対してフェアな態度が求められる、というか結果的にそうならざるを得ない、というようなことが書かれていたり、非常に面白い視点の本だった。 特に遊びの要素の中に身体的な眩暈の観点が含まれているのが独創的に思った。ジェットコースターに乗ってクラクラしたり、犬が自分の尻尾を追いかけたりする、というような行動を根源的な遊びの表れとして位置付けている。 遊びは自由だがルールがないと成立しない、とか、そういう考えだけだと身体性が薄れる。純粋な自己破壊的なシミュレーションのような形での眩暈は僕もよくやった。 何もない一本道で目を瞑ってどこまで歩けるか、とか、自転車に乗っているのに目を瞑ったり、手放しでどこまで行けるかとか試してみたくなる気持ちは眩暈の希求だと思う。 それがなんだ、という話はあるが、そういう事象が文明論にまつわる感じでスケール大きめに語られている。 少し時間は掛かるが、興味のある人は読んでみてください。







