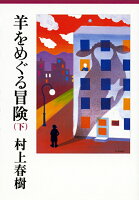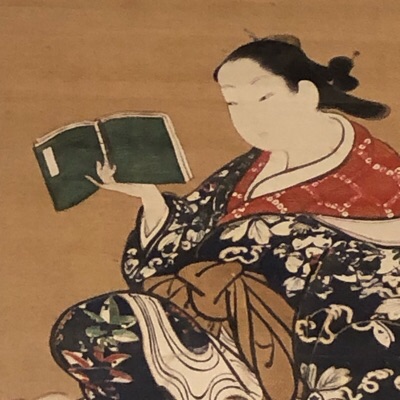
勝村巌
@katsumura
- 2026年2月1日
 虚言の国 アメリカ・ファンタスティカティム・オブライエン,村上春樹読み終わったアメリカの現代作家ティムオブライエンの約20年ぶりの長編小説。訳者はこれまでも日本で出版されたオブライエン作品を多く訳してきた村上春樹。600ページくらいある大長編だが、楽しく読めた。 『カチアートを追跡して』『本当の戦争の話をしよう』『ニュークリアエイジ』などの1970年代〜90年代に書かれた初期作品はいずれもベトナム戦争をテーマにした社会派な作品として評価が高く、訳書もしっかり出ているので、僕も読んだ。いずれもマジックリアリズム的な幻想的な部分はあるものの、戦争や核の問題に鋭く切り込んだ、大変に強い小説だったように記憶している。 血管か何かの病気があって、思うように執筆できないというようなことがあるらしいが、作家本人が「自分の最後の小説」として20年ぶりに上梓したのが本作品となる。 ストーリーは大変現代的で、最近のポールトーマスアンダーソン監督の『ワンバトルアフターアナザー』とかコーエン兄弟の映画なんかに通じる、現代風刺的な、クライムコメディ感があり、ナウい感じと思った。これまでのベトナムものとはだいぶ違う。映画のノベライズ、もしくはそのまま映画にできるような感じだった。 時は第1期トランプ政権の頃。フェイクニュースのでっちあげの発信者として過ごしていたボイドが、過去の精算もしくは復讐に乗り出すために銀行強盗を行い、そこの女性銀行員を誘拐して、復讐の旅に出るというのが発端。 誘拐した女性銀行員アンジーは熱心なペンテコステ派で、ボイドのファムファタールとなっていく。 その後、アンジーのフィアンセ、ボイドの元妻、そのセレブな親族、強盗された銀行の支配人などが入り乱れて、ガンガン人死などが出つつ、クライムコメディとして話がうねっていく、という流れ。 トランプ政権下のアメリカ、コロナ禍のアメリカがフェイクという切り口でまとめられており、真実や本質というものが全く意味のないものとして扱われていくのが特徴。 主人公のボイド自身がそもそも虚言癖の持ち主であり、それはある種の訂正可能性のような感じでも示されるのだが、さまざまな絶対的な事実が現実の中で捉えようによって変質していく。 虚言は過酷な現実を覆い隠すためのものとして描かれており、それぞれの登場人物はそういう側面である程度感情移入ができるように描かれてもいて、ボイドの虚言には過酷な過去の家族関係や息子の死などが関連しており、そこにある種の救いがある。そこらへんのストーリーの作り方は巧みだと思った。 最終的には血が繋がっている、いないに関わらず家族というものがテーマになっているようにも思った。家族からは逃れられないが、その関係を主体的に構築していくこともできる、ということも示されていると感じた。 父子の関係というのも一つの大きなテーマとなっており、高校生の子供がいる親としては感情移入して読めた。 600ページを超える大長編ですが、人物の動きはコーエン兄弟映画的なドタバタが続く感じで非常に映像的で、現代を移している鏡のような作品と思いました。 オブライエンさんは「これで最後の作品」宣言をされていますが、そんなこと言わず、もっと書いておくれよ、という気持ちになりました。 オススメです!
虚言の国 アメリカ・ファンタスティカティム・オブライエン,村上春樹読み終わったアメリカの現代作家ティムオブライエンの約20年ぶりの長編小説。訳者はこれまでも日本で出版されたオブライエン作品を多く訳してきた村上春樹。600ページくらいある大長編だが、楽しく読めた。 『カチアートを追跡して』『本当の戦争の話をしよう』『ニュークリアエイジ』などの1970年代〜90年代に書かれた初期作品はいずれもベトナム戦争をテーマにした社会派な作品として評価が高く、訳書もしっかり出ているので、僕も読んだ。いずれもマジックリアリズム的な幻想的な部分はあるものの、戦争や核の問題に鋭く切り込んだ、大変に強い小説だったように記憶している。 血管か何かの病気があって、思うように執筆できないというようなことがあるらしいが、作家本人が「自分の最後の小説」として20年ぶりに上梓したのが本作品となる。 ストーリーは大変現代的で、最近のポールトーマスアンダーソン監督の『ワンバトルアフターアナザー』とかコーエン兄弟の映画なんかに通じる、現代風刺的な、クライムコメディ感があり、ナウい感じと思った。これまでのベトナムものとはだいぶ違う。映画のノベライズ、もしくはそのまま映画にできるような感じだった。 時は第1期トランプ政権の頃。フェイクニュースのでっちあげの発信者として過ごしていたボイドが、過去の精算もしくは復讐に乗り出すために銀行強盗を行い、そこの女性銀行員を誘拐して、復讐の旅に出るというのが発端。 誘拐した女性銀行員アンジーは熱心なペンテコステ派で、ボイドのファムファタールとなっていく。 その後、アンジーのフィアンセ、ボイドの元妻、そのセレブな親族、強盗された銀行の支配人などが入り乱れて、ガンガン人死などが出つつ、クライムコメディとして話がうねっていく、という流れ。 トランプ政権下のアメリカ、コロナ禍のアメリカがフェイクという切り口でまとめられており、真実や本質というものが全く意味のないものとして扱われていくのが特徴。 主人公のボイド自身がそもそも虚言癖の持ち主であり、それはある種の訂正可能性のような感じでも示されるのだが、さまざまな絶対的な事実が現実の中で捉えようによって変質していく。 虚言は過酷な現実を覆い隠すためのものとして描かれており、それぞれの登場人物はそういう側面である程度感情移入ができるように描かれてもいて、ボイドの虚言には過酷な過去の家族関係や息子の死などが関連しており、そこにある種の救いがある。そこらへんのストーリーの作り方は巧みだと思った。 最終的には血が繋がっている、いないに関わらず家族というものがテーマになっているようにも思った。家族からは逃れられないが、その関係を主体的に構築していくこともできる、ということも示されていると感じた。 父子の関係というのも一つの大きなテーマとなっており、高校生の子供がいる親としては感情移入して読めた。 600ページを超える大長編ですが、人物の動きはコーエン兄弟映画的なドタバタが続く感じで非常に映像的で、現代を移している鏡のような作品と思いました。 オブライエンさんは「これで最後の作品」宣言をされていますが、そんなこと言わず、もっと書いておくれよ、という気持ちになりました。 オススメです! - 2026年1月17日
 読み終わった正月に親子で本屋行ったら玄が読みたいと持ってきたので購入。面白かったというので、僕も読んでみた。筆者は『ソース焼きそばの謎』『あんかけ焼きそばの謎』といった焼きそば関連の前書が2冊もあるという焼きそばのエキスパートで、三部作の完結編がこの『カップ焼きそばの謎』だという。 もちろん、この本から読んでも全然OKで、カップ焼きそばの知られざる秘密がこれでもかと列挙され、目からウロコが那智の滝のようにこぼれ落ちた。 本の内容としては即席麺としてのカップ焼きそばの誕生から、現在までの約50年の歴史を各社の代表的カップ麺の特徴と経営や販売方針を経済誌などの情報を丹念に調べて、大変に上手く分類して流れを作っている内容だった。 マーケティングや経営についての良書として読んだ。 元祖カップ焼きそばのエビスカップ焼きそば、東日本の雄ペヤングソース焼きそば、妥当カップヌードルを狙う日清の日清焼きそばUFO、大盛りで市場を席巻したスーパーカップ大盛りイカ焼きそば、袋麺の王者が放ったヒット作、サッポロ一番おたふくソース焼きそば、からしマヨネーズを発明した明星一平ちゃんの店の焼きそば、オープン価格帯の頂点に立つマルちゃんごつ盛りソース焼きそばなど、の誰もがコンビニやスーパーなどでみたことや食べたことのある商品の開発から、味や容器などのコンセプト、販売戦略などを細かく分類して紹介している。 即席麺には袋麺とカップ麺があり、その販売数はカップ麺が6割を占め、そのカップ麺の中でもシェアトップは実は焼きそば味なのだという。 確かに自分もあの独特のソース味が無性に食べたくなることがある。昔、知り合いだった人でカップ麺の味だけで銘柄を当てられるという人がいて、すごい才能だと思ったものだが、この本を読んだ今となっては、各種カップ焼きそばの個性は明白になったので、僕だって少し食べ比べればそれはできそうなものだ。 とはいえ、1974年に初めて市場に出たカップ焼きそばなので、2024年には発売50周年を迎えている。その間に生まれては消えたり、まだ生き残っている味について、綿密なリサーチがなされているのはたいへんに読み応えがある。 マルカのペヤングは異物混入などで危機的状況もあったが、基本の味はほとんど買えずに、基本は東日本だけで変わらぬ味を守っている、とか、カップヌードルで全国シェアの強い大企業日清の焼きそばUFOはこまめに味を変えたり、パッケージを変えたり、大規模なCMを打ったりしてシェア一位をまもっているということ、またからしマヨネーズで一世を風靡した明星は現在は日清の子会社になっていること。 同様に大盛りで知られるエースコックも実はサッポロ一番ブランドで知られるサンヨー食品の子会社となっている。 食品会社の同系列商品ブランドの子会社かは業界ではカニバリズム(共食い)とも言われて嫌悪されることが多いようだが、これらの業務提携はお互いのブランドを尊重する良い関係を維持する友好的な買収になっていることも多い。 この辺りの情報も業界誌のインタビュー記事などをよく拾っており感心する。 結果、カップ焼きそば戦国史というようなたいへんにエキサイティングな流れを楽しむことができた。経営とかに興味ある人は読んでみるといいと思います。 また、この本の中で述べられている話ですが、カップ焼きそばは焼いてないのに焼きそばと言っていいのか? という点についてですが、筆者は言い切って良い、というスタンス。 調理において焼くというのは直火で焼くことであり、直火の焼き魚とか焼き鳥は焼きだが、鉄板で熱を通すのは通常は炒めである、と。 そうなると元々の焼きそばも本来は炒めそばなので、そう考えると細かいことは気にしなくて良い、という考え方、という見地らしい。 確かにそういうものかもしれないが、カップ焼きそばには独特のカップ焼きそば味というものが明確に存在しているとは確信をもっていえる僕でした。
読み終わった正月に親子で本屋行ったら玄が読みたいと持ってきたので購入。面白かったというので、僕も読んでみた。筆者は『ソース焼きそばの謎』『あんかけ焼きそばの謎』といった焼きそば関連の前書が2冊もあるという焼きそばのエキスパートで、三部作の完結編がこの『カップ焼きそばの謎』だという。 もちろん、この本から読んでも全然OKで、カップ焼きそばの知られざる秘密がこれでもかと列挙され、目からウロコが那智の滝のようにこぼれ落ちた。 本の内容としては即席麺としてのカップ焼きそばの誕生から、現在までの約50年の歴史を各社の代表的カップ麺の特徴と経営や販売方針を経済誌などの情報を丹念に調べて、大変に上手く分類して流れを作っている内容だった。 マーケティングや経営についての良書として読んだ。 元祖カップ焼きそばのエビスカップ焼きそば、東日本の雄ペヤングソース焼きそば、妥当カップヌードルを狙う日清の日清焼きそばUFO、大盛りで市場を席巻したスーパーカップ大盛りイカ焼きそば、袋麺の王者が放ったヒット作、サッポロ一番おたふくソース焼きそば、からしマヨネーズを発明した明星一平ちゃんの店の焼きそば、オープン価格帯の頂点に立つマルちゃんごつ盛りソース焼きそばなど、の誰もがコンビニやスーパーなどでみたことや食べたことのある商品の開発から、味や容器などのコンセプト、販売戦略などを細かく分類して紹介している。 即席麺には袋麺とカップ麺があり、その販売数はカップ麺が6割を占め、そのカップ麺の中でもシェアトップは実は焼きそば味なのだという。 確かに自分もあの独特のソース味が無性に食べたくなることがある。昔、知り合いだった人でカップ麺の味だけで銘柄を当てられるという人がいて、すごい才能だと思ったものだが、この本を読んだ今となっては、各種カップ焼きそばの個性は明白になったので、僕だって少し食べ比べればそれはできそうなものだ。 とはいえ、1974年に初めて市場に出たカップ焼きそばなので、2024年には発売50周年を迎えている。その間に生まれては消えたり、まだ生き残っている味について、綿密なリサーチがなされているのはたいへんに読み応えがある。 マルカのペヤングは異物混入などで危機的状況もあったが、基本の味はほとんど買えずに、基本は東日本だけで変わらぬ味を守っている、とか、カップヌードルで全国シェアの強い大企業日清の焼きそばUFOはこまめに味を変えたり、パッケージを変えたり、大規模なCMを打ったりしてシェア一位をまもっているということ、またからしマヨネーズで一世を風靡した明星は現在は日清の子会社になっていること。 同様に大盛りで知られるエースコックも実はサッポロ一番ブランドで知られるサンヨー食品の子会社となっている。 食品会社の同系列商品ブランドの子会社かは業界ではカニバリズム(共食い)とも言われて嫌悪されることが多いようだが、これらの業務提携はお互いのブランドを尊重する良い関係を維持する友好的な買収になっていることも多い。 この辺りの情報も業界誌のインタビュー記事などをよく拾っており感心する。 結果、カップ焼きそば戦国史というようなたいへんにエキサイティングな流れを楽しむことができた。経営とかに興味ある人は読んでみるといいと思います。 また、この本の中で述べられている話ですが、カップ焼きそばは焼いてないのに焼きそばと言っていいのか? という点についてですが、筆者は言い切って良い、というスタンス。 調理において焼くというのは直火で焼くことであり、直火の焼き魚とか焼き鳥は焼きだが、鉄板で熱を通すのは通常は炒めである、と。 そうなると元々の焼きそばも本来は炒めそばなので、そう考えると細かいことは気にしなくて良い、という考え方、という見地らしい。 確かにそういうものかもしれないが、カップ焼きそばには独特のカップ焼きそば味というものが明確に存在しているとは確信をもっていえる僕でした。 - 2026年1月5日
 戦争の美術史宮下規久朗読み終わった古今東西の戦争を主題にした絵画作品を紹介している本。絵画というものが写真とは異なり、主題性に則って画家の意図を持って描かれるという観点から戦争画は単なる記録ではなく多様な観点を内包可能な記憶でもある、という切り口で読み解かれており、大変に興味深い視点を得ることができた。 2023年に神戸大学の文学部で行われた「戦争と美術」という通年の講義を圧縮してまとめたものとのこと。 古くはメソポタミアやシュメール、エジプトなどの壁画からローマ時代、ビザンツ帝国などにおける戦争描写から、ルネサンス期の表現などを経て近世の戦争表現なども大量の図版とともに代表的な作品が紹介されている。 日本においては蒙古襲来絵詞をはじめ、戦国時代および江戸時代の錦絵の主題としての戦争が紹介され、日清日露を経て第一次大戦を皮切りにした作戦記録画としての戦争の記録が紹介される。 近代以降は世界的な二度の大戦において各国が従軍画家を現地に派遣していた事実が紹介されて驚いた。驚いたが。それはそうだよなとも思った。写真の発明以前ではやはり記録は絵画が主流なわけなので。 イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、アメリカなどでは、それぞれの時代によって未来派とか印象派とかそういうイズムがあるわけですが、さまざまなアーティストがイズムに基づいて様式的に戦争をとらえたりしているのも興味深い。 また、イタリアの未来派などは従軍した中心人物が根こそぎ戦死したりして運動が下火になったりしているというのも興味深い。 第二次大戦における作戦記録画における画家の心理についてかなり突っ込んだ分析をしているのが白眉で、特に藤田嗣治の筆の走りについては、人間の極限という画題にぶつかり、軍からの依頼もあったとは思うが、自己の画力と合わせて、どこまで描けるかを限界まで探求した画家の業として捉えており、ここは文体も熱くなっていて読み応えがあった。 東近美の常設展の戦争画のコーナーがしっかりと整備されてきたのはここ数年のことだという。僕は東近美に行くたびに見ているが、やはり藤田嗣治の戦争画には圧倒される。東京にお住まいの方はぜひ見に行かれたし。 黒田清輝なども従軍はしておりスケッチなどは描いていたが油絵のタブローにはしていない。この辺り、日本の戦局を政治家として冷静に見ていたのかもしれず、何か手記などはないのか気になる。 戦後の戦争美術については世界各地に残る戦没慰霊碑や戦争記念碑をはじめ丸木夫妻の原爆絵画やリヒターのビルケナウやキーファーの作品などについて触れられている。 ベトナム戦争のアメリカ国内の表現なども含めて戦争の負の記憶をいかに継承していくかというところに、戦争美術は公的な性格が強く、過去をどのように記憶して忘却するかは共同体が決める、として、戦争美術が集団的記憶を形成する、と述べている。 これは大変に興味深かった。 戦争の記憶は写真や映画、文学などにも表されているが、それらも含めて、どのような記憶や忘却を自分らが背負っていくべきか、考えていかないといけないと思った。 大変良い本でした。
戦争の美術史宮下規久朗読み終わった古今東西の戦争を主題にした絵画作品を紹介している本。絵画というものが写真とは異なり、主題性に則って画家の意図を持って描かれるという観点から戦争画は単なる記録ではなく多様な観点を内包可能な記憶でもある、という切り口で読み解かれており、大変に興味深い視点を得ることができた。 2023年に神戸大学の文学部で行われた「戦争と美術」という通年の講義を圧縮してまとめたものとのこと。 古くはメソポタミアやシュメール、エジプトなどの壁画からローマ時代、ビザンツ帝国などにおける戦争描写から、ルネサンス期の表現などを経て近世の戦争表現なども大量の図版とともに代表的な作品が紹介されている。 日本においては蒙古襲来絵詞をはじめ、戦国時代および江戸時代の錦絵の主題としての戦争が紹介され、日清日露を経て第一次大戦を皮切りにした作戦記録画としての戦争の記録が紹介される。 近代以降は世界的な二度の大戦において各国が従軍画家を現地に派遣していた事実が紹介されて驚いた。驚いたが。それはそうだよなとも思った。写真の発明以前ではやはり記録は絵画が主流なわけなので。 イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、アメリカなどでは、それぞれの時代によって未来派とか印象派とかそういうイズムがあるわけですが、さまざまなアーティストがイズムに基づいて様式的に戦争をとらえたりしているのも興味深い。 また、イタリアの未来派などは従軍した中心人物が根こそぎ戦死したりして運動が下火になったりしているというのも興味深い。 第二次大戦における作戦記録画における画家の心理についてかなり突っ込んだ分析をしているのが白眉で、特に藤田嗣治の筆の走りについては、人間の極限という画題にぶつかり、軍からの依頼もあったとは思うが、自己の画力と合わせて、どこまで描けるかを限界まで探求した画家の業として捉えており、ここは文体も熱くなっていて読み応えがあった。 東近美の常設展の戦争画のコーナーがしっかりと整備されてきたのはここ数年のことだという。僕は東近美に行くたびに見ているが、やはり藤田嗣治の戦争画には圧倒される。東京にお住まいの方はぜひ見に行かれたし。 黒田清輝なども従軍はしておりスケッチなどは描いていたが油絵のタブローにはしていない。この辺り、日本の戦局を政治家として冷静に見ていたのかもしれず、何か手記などはないのか気になる。 戦後の戦争美術については世界各地に残る戦没慰霊碑や戦争記念碑をはじめ丸木夫妻の原爆絵画やリヒターのビルケナウやキーファーの作品などについて触れられている。 ベトナム戦争のアメリカ国内の表現なども含めて戦争の負の記憶をいかに継承していくかというところに、戦争美術は公的な性格が強く、過去をどのように記憶して忘却するかは共同体が決める、として、戦争美術が集団的記憶を形成する、と述べている。 これは大変に興味深かった。 戦争の記憶は写真や映画、文学などにも表されているが、それらも含めて、どのような記憶や忘却を自分らが背負っていくべきか、考えていかないといけないと思った。 大変良い本でした。 - 2026年1月4日
 平和と愚かさ東浩紀読み終わったゲンロンのサイン回配信でサイン本を購入。2025年の年末から2026年の年始にかけて読んだ。2026年の1冊目としては年初から濃厚な読書体験ができた。 東浩紀は数年前から突発配信などの長時間の1人語りをかなり聴いてきた。会社経営者という立場を鑑みるとかなり正直な本当のことを語る、好きな語り手の1人だが、著作も大変によく、古いものから最近のものまである程度は読んでいるが、どれも素晴らしい。 この本は戦争が止まず、SNSでは分断が止まない、この世界で平和とは一体、何なのか、どのような状態を平和と考えるとよいのか、ということを、東浩紀が実際に訪れた世界中の都市への紀行文と哲学的思索がつづれおりに重なっている、という構成になっている。 ほぼ500ページという大著で著者も哲学者ということで難解な言葉の羅列かと思いきや、そんなことはなく、難しい概念を紀行文と合わせて、とても分かりやすく平易な文章で書いてあり、非常に読み口が軽いのも特徴。大切なことが書かれているので広い読者に届いてほしいと感じる。 さて、言いたいことを言いすぎて友と敵を、明確に分断しがちなこんなポイズンな世の中で東浩紀が訴えるのは、平和というのは、政治について考えないでよい範囲がより広く担保されている状況のこと、なのではないか、ということである。 例えばパンダを見て、これは中国による外交政策の一環なのだ、と感じたり、スタバを楽しんでいる人を見てあんたはイスラエル支持者よね、とレッテルを貼ったりする行為からは分断こそ生まれるが平和からは遠ざかる、という考え方である。 政治的に考えない、というのは愚かさに通じる、という言説があるが、哲学的に考えないことを考える、ということに挑戦していて、そこは大変にエキサイティングに感じる。 紀行文としてはサラエヴォ、ウクライナ、チェルノブイリ、中国、広島、どこかのリゾート地などを訪問して、そこの戦争や人災の負の記録と向き合って、その表象を探り、記録と記憶について思索を深めている。 逍遥、というのとは少し違うが、移動して見知らぬ土地へ赴き、そこで気づいたことをきっかけに論を展開しており、これはわかりやすい。 負の記録としては現地の博物館などに訪れて虐殺や戦争などについての表現の仕方をとらえている。 記録と記憶、というのは起きた事実をどう捉えるか、という点で重要な観点となる。 記録的な側面は、その記録は事実だが例えば博物館などに展示される場合、その表現は博物館側の意図により大幅な訂正可能性を持つ。例えばコップの中に水が半分あるとして、これをあと半分しかない、と表現するか、まだ半分も残っている、と表現するかによって、観衆の捉え方はコントロールできる。文脈を持たない人たちにとってはそこに批評性を持ち込むのはなかなか難しい。 また、博物館の展示はコンセプトによって訂正可能性があり、その表現は流動的となる。 記憶についていうと、人間の寿命は短いため、当事者というのは世代を同じくするため同じような時期にパタっといなくなってしまう。日本においても戦時中の記憶を保っている人々はほぼいなくなってしまっている。この流動性は人間という種の限界と言ってもいいのかもしれない。 つまり、世界中に残る負の出来事を次世代に残していくということは常に訂正可能な事象として曖昧な形で継承されていく、というわけだ。 それに対して、複雑な記録と記憶をどのように繋いでいくか、というところに東浩紀が注目したのが、文学における方法とインスタレーション的な展示による方法となる。 文学については村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』と大江健三郎の『治療塔』『治療塔惑星』の2篇を例に挙げて語っていてとても興味深かった。 『ねじまき鳥クロニクル』は学生の頃から大変好きな作品で繰り返し読んできた。人間が抱えている暴力についての物語と捉えているのだが、物語の中に唐突に第二次大戦中の1939年のノモンハン事件に関連する特殊作戦の展開が描かている。 現代を生きる主人公は様々な偶然に導かれて、その記憶の蓋を開けて、深い井戸に潜ることにその記憶と直結していく、という流れがある。 これは失われた記憶というものをキーに、ある種の戦争加害と我々は無関係ではない、ということを小説的な手法で表現している構成だ。 マジックリアリズム的にも読めるこの構成をかなりシリアスに忘却への具体的アプローチにしているのが、この小説のすごいところなのだろう。またその視点を忘れずに読み込んでみよう。 『ねじまき鳥クロニクル』では、主人公はいろいろと考えて行動を起こすが基本的には意図しないところで意図が達成されたり、徒手空拳に待っていると向こうから答えがやってくるというような状況設定が多い。現実に翻弄される、ということと忘却された事実に導かれている、というところが裏で結びついているようで、そこを読み解くとまた見え方が変わってくる気がする。 村上春樹では2000年刊行の『神の子どもたちはみな踊る』の中に「かえるくん、東京を救う」という短編があって、これは村上春樹さんによると、なぜか大変に人気のある短編なのだそうですが、ここでも近いテーマが別のアプローチで描かれている気がしている。 東京の地下にいる巨大なミミズである「なめくじら」が大地震を起こそうとしている。それをかえるくんと主人公の片桐が片桐の夢の中で協力して退けるという話なのですが、夢というのは記憶であって事実ではない。しかし、それは現実に対しても確かに効力を持ち得る、というようなテーマというか、こちらは大変に前向きで勇気や責任について直接的に書いている、気持ちの良い話(ラストは少しダークですが)なので、興味のある方はぜひご一読あれ。 また大江健三郎の作品でも広島や原水爆をテーマにしたSFが近いような記録や記憶を元にそういった負の遺産をどのように人間が消化(昇華?)していくのかを扱った作品がある。 大江健三郎と村上春樹の村上初期の作品に対する大江健三郎の拒否反応を知っていると、その後の村上春樹の小説家としてのキャリアを見てきた自分としてはこの2人がこのようにある意味、並列に扱われているのを見るのは嬉しいことだ。 AIなどの発展により、逆に人間の持つ小説や文学などの人文学的な価値は高まるだろうと東浩紀は書いているが、これらの小説に触れてきた自分としては、それは確かにそうだ、その通りだ、と思う。 また、記録や記憶にとって博物館の展示、特にノンバーバルなインスタレーション的な展示がものごとの持つ複雑な多様性を表すために効果的だ、という指摘があり、そこは大変に共感した。 例えばワシントンにある国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館では、アメリカの憲法に人間の平等の一文を書いた3代大統領のジェファーソンの像があり、彼は独立宣言の父などと称されつつも、自身は600人にものぼる大量の奴隷所有者で、あまつさえ当時、自身の奴隷だった女性との間に複数の子を設け、その子供も奴隷として扱ったということが歴史的事実として広く認識されているそうだ。 かなり矛盾を孕んだ人物像だが、それをこの歴史文化博物館ではそのジェファーソンの背後に600個のレンガの壁をたて、そこに奴隷の名を記すことで表現しているのだという。 言葉でジェファーソンの矛盾を説明すると恣意的になる。そこで、本人の像とレンガの壁、そして記名による個人の顕現により、様々な両義性を表しているのだろう。 戦争についての美術としてはゲルハルトリヒターの『ビルケナウ』やミハ・ウルマンの『空の図書館』など、優れたものがあるが、単に激烈な表現をするだけでなく、ノンバーバルなだけに形や色で表現することの可能性について言及されているのは様々な博物館や美術館を歩いた東浩紀ならではの視点と感じた。 またウクライナの現代美術家ジャンナ・カディロワについての言及があった。ジャンナは愛国に基づき、自身の作品の売り上げをウクライナに寄付して戦争協力している、ということが展示内で明言されており、そこについて東浩紀は否定的だった。 アートの持つ価値が平和に結びつくことを知っているからこその違和感だと思う。強いメッセージだった。 かなり長くなってしまった。この『平和と愚かさ』にはこのような人文学やアートが思考を政治から解放する装置として機能するということが力強く述べられていると思う。 僕は自分の興味の赴くところで、上記の部分について感想を書いたが、それ以外にも、サラエヴォ包囲、731部隊、チェルノブイリ原発事故などについても詳細な歴史と哲学的な思索が述べられており、そちらも現代を捉えるのに大変参考になる論説となっている。 大変な名著と思います。みなさん、ぜひご一読ください。
平和と愚かさ東浩紀読み終わったゲンロンのサイン回配信でサイン本を購入。2025年の年末から2026年の年始にかけて読んだ。2026年の1冊目としては年初から濃厚な読書体験ができた。 東浩紀は数年前から突発配信などの長時間の1人語りをかなり聴いてきた。会社経営者という立場を鑑みるとかなり正直な本当のことを語る、好きな語り手の1人だが、著作も大変によく、古いものから最近のものまである程度は読んでいるが、どれも素晴らしい。 この本は戦争が止まず、SNSでは分断が止まない、この世界で平和とは一体、何なのか、どのような状態を平和と考えるとよいのか、ということを、東浩紀が実際に訪れた世界中の都市への紀行文と哲学的思索がつづれおりに重なっている、という構成になっている。 ほぼ500ページという大著で著者も哲学者ということで難解な言葉の羅列かと思いきや、そんなことはなく、難しい概念を紀行文と合わせて、とても分かりやすく平易な文章で書いてあり、非常に読み口が軽いのも特徴。大切なことが書かれているので広い読者に届いてほしいと感じる。 さて、言いたいことを言いすぎて友と敵を、明確に分断しがちなこんなポイズンな世の中で東浩紀が訴えるのは、平和というのは、政治について考えないでよい範囲がより広く担保されている状況のこと、なのではないか、ということである。 例えばパンダを見て、これは中国による外交政策の一環なのだ、と感じたり、スタバを楽しんでいる人を見てあんたはイスラエル支持者よね、とレッテルを貼ったりする行為からは分断こそ生まれるが平和からは遠ざかる、という考え方である。 政治的に考えない、というのは愚かさに通じる、という言説があるが、哲学的に考えないことを考える、ということに挑戦していて、そこは大変にエキサイティングに感じる。 紀行文としてはサラエヴォ、ウクライナ、チェルノブイリ、中国、広島、どこかのリゾート地などを訪問して、そこの戦争や人災の負の記録と向き合って、その表象を探り、記録と記憶について思索を深めている。 逍遥、というのとは少し違うが、移動して見知らぬ土地へ赴き、そこで気づいたことをきっかけに論を展開しており、これはわかりやすい。 負の記録としては現地の博物館などに訪れて虐殺や戦争などについての表現の仕方をとらえている。 記録と記憶、というのは起きた事実をどう捉えるか、という点で重要な観点となる。 記録的な側面は、その記録は事実だが例えば博物館などに展示される場合、その表現は博物館側の意図により大幅な訂正可能性を持つ。例えばコップの中に水が半分あるとして、これをあと半分しかない、と表現するか、まだ半分も残っている、と表現するかによって、観衆の捉え方はコントロールできる。文脈を持たない人たちにとってはそこに批評性を持ち込むのはなかなか難しい。 また、博物館の展示はコンセプトによって訂正可能性があり、その表現は流動的となる。 記憶についていうと、人間の寿命は短いため、当事者というのは世代を同じくするため同じような時期にパタっといなくなってしまう。日本においても戦時中の記憶を保っている人々はほぼいなくなってしまっている。この流動性は人間という種の限界と言ってもいいのかもしれない。 つまり、世界中に残る負の出来事を次世代に残していくということは常に訂正可能な事象として曖昧な形で継承されていく、というわけだ。 それに対して、複雑な記録と記憶をどのように繋いでいくか、というところに東浩紀が注目したのが、文学における方法とインスタレーション的な展示による方法となる。 文学については村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』と大江健三郎の『治療塔』『治療塔惑星』の2篇を例に挙げて語っていてとても興味深かった。 『ねじまき鳥クロニクル』は学生の頃から大変好きな作品で繰り返し読んできた。人間が抱えている暴力についての物語と捉えているのだが、物語の中に唐突に第二次大戦中の1939年のノモンハン事件に関連する特殊作戦の展開が描かている。 現代を生きる主人公は様々な偶然に導かれて、その記憶の蓋を開けて、深い井戸に潜ることにその記憶と直結していく、という流れがある。 これは失われた記憶というものをキーに、ある種の戦争加害と我々は無関係ではない、ということを小説的な手法で表現している構成だ。 マジックリアリズム的にも読めるこの構成をかなりシリアスに忘却への具体的アプローチにしているのが、この小説のすごいところなのだろう。またその視点を忘れずに読み込んでみよう。 『ねじまき鳥クロニクル』では、主人公はいろいろと考えて行動を起こすが基本的には意図しないところで意図が達成されたり、徒手空拳に待っていると向こうから答えがやってくるというような状況設定が多い。現実に翻弄される、ということと忘却された事実に導かれている、というところが裏で結びついているようで、そこを読み解くとまた見え方が変わってくる気がする。 村上春樹では2000年刊行の『神の子どもたちはみな踊る』の中に「かえるくん、東京を救う」という短編があって、これは村上春樹さんによると、なぜか大変に人気のある短編なのだそうですが、ここでも近いテーマが別のアプローチで描かれている気がしている。 東京の地下にいる巨大なミミズである「なめくじら」が大地震を起こそうとしている。それをかえるくんと主人公の片桐が片桐の夢の中で協力して退けるという話なのですが、夢というのは記憶であって事実ではない。しかし、それは現実に対しても確かに効力を持ち得る、というようなテーマというか、こちらは大変に前向きで勇気や責任について直接的に書いている、気持ちの良い話(ラストは少しダークですが)なので、興味のある方はぜひご一読あれ。 また大江健三郎の作品でも広島や原水爆をテーマにしたSFが近いような記録や記憶を元にそういった負の遺産をどのように人間が消化(昇華?)していくのかを扱った作品がある。 大江健三郎と村上春樹の村上初期の作品に対する大江健三郎の拒否反応を知っていると、その後の村上春樹の小説家としてのキャリアを見てきた自分としてはこの2人がこのようにある意味、並列に扱われているのを見るのは嬉しいことだ。 AIなどの発展により、逆に人間の持つ小説や文学などの人文学的な価値は高まるだろうと東浩紀は書いているが、これらの小説に触れてきた自分としては、それは確かにそうだ、その通りだ、と思う。 また、記録や記憶にとって博物館の展示、特にノンバーバルなインスタレーション的な展示がものごとの持つ複雑な多様性を表すために効果的だ、という指摘があり、そこは大変に共感した。 例えばワシントンにある国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館では、アメリカの憲法に人間の平等の一文を書いた3代大統領のジェファーソンの像があり、彼は独立宣言の父などと称されつつも、自身は600人にものぼる大量の奴隷所有者で、あまつさえ当時、自身の奴隷だった女性との間に複数の子を設け、その子供も奴隷として扱ったということが歴史的事実として広く認識されているそうだ。 かなり矛盾を孕んだ人物像だが、それをこの歴史文化博物館ではそのジェファーソンの背後に600個のレンガの壁をたて、そこに奴隷の名を記すことで表現しているのだという。 言葉でジェファーソンの矛盾を説明すると恣意的になる。そこで、本人の像とレンガの壁、そして記名による個人の顕現により、様々な両義性を表しているのだろう。 戦争についての美術としてはゲルハルトリヒターの『ビルケナウ』やミハ・ウルマンの『空の図書館』など、優れたものがあるが、単に激烈な表現をするだけでなく、ノンバーバルなだけに形や色で表現することの可能性について言及されているのは様々な博物館や美術館を歩いた東浩紀ならではの視点と感じた。 またウクライナの現代美術家ジャンナ・カディロワについての言及があった。ジャンナは愛国に基づき、自身の作品の売り上げをウクライナに寄付して戦争協力している、ということが展示内で明言されており、そこについて東浩紀は否定的だった。 アートの持つ価値が平和に結びつくことを知っているからこその違和感だと思う。強いメッセージだった。 かなり長くなってしまった。この『平和と愚かさ』にはこのような人文学やアートが思考を政治から解放する装置として機能するということが力強く述べられていると思う。 僕は自分の興味の赴くところで、上記の部分について感想を書いたが、それ以外にも、サラエヴォ包囲、731部隊、チェルノブイリ原発事故などについても詳細な歴史と哲学的な思索が述べられており、そちらも現代を捉えるのに大変参考になる論説となっている。 大変な名著と思います。みなさん、ぜひご一読ください。 - 2025年12月20日
 ブラック・カルチャー中村隆之読み終わった奴隷貿易や奴隷制を起点に環大西洋的な視座から、黒人の文化を音楽、文学、アートなどを横断的に捉えて読み解く内容。大変素晴らしい内容でした。 今年の初めに読んだ後藤護さんの『黒人音楽史』にも深く接続する内容でこれまで自分が見知ってきたさまざまな黒人に関連する点在する物事がシュパシュパとつながる感覚があり面白かった。 高校時代にジミヘンドリックスにハマり、大学時代はJB、スティービーワンダー、マイルスなどを聴き、それに関する評論なども読んできた。公民権運動やヒップホップの歴史などの良書もあるのでそういうものにも触れてきたわけだが、そういう知識に背骨が通ったような感覚を持った。 菊地成孔と大谷能生がどこかのラジオかドミューンかで後藤さんの『黒人音楽史』について語っていたので、それを読み、そこから中村さんのことを知り本屋で見かけて読んだわけだが、本の持つ引力やセレンディピティを感じる体験となった。 内容としては前半の6章は奴隷貿易に端を発するブラックディアスポラについて丁寧に歴史を読み解いていく。 文字を知ることが「奴隷には向かなくなる」ものとして禁止されていたため、黒人にとって口伝や口承が文化そのものとなり、そこから歌や踊りが文化としてかけがえのないものとして立ち上がっていった、というのはなるほど、と思った。 音楽について、黒人霊歌、ブルース、ジャズの成立と発展はニューオリンズからミシシッピ川遡ってシカゴへ至る流れとして大体の経緯は知っていたが、黒人奴隷からの聞き書きによる奴隷体験記をトーキングブックと呼ぶ、ということは初耳だった。それこスティービーワンダーのアルバムに『トーキングブック』というものがある。 黒人文学についてはサミュエルディレイニーを数冊読んだくらいなので、例えば黒人奴隷の年代期としてテレビドラマにもなっているアレックスヘイリーの『ルーツ』などはやがて読まねばならない作品と感じた。 またアフロフューチャリズムやアフロセントリシティなどの言及にも興味深いものが多かった。 黒人ファンクのジャケなどに時たまエジプト的な衣装が施されていることがある。アースウィンドアンドファイヤーの『太陽神』とか、アフリカバンバータの諸作品とかですが、僕はこれは単なる賑やかしというか、エジプトって面白いよね〜みたいなノリでやってたんだと感じてましたが、実は1970年代にセネガルの研究者がエジプトは黒人国家だったとする論文を発表していたのです。 公民権運動などの中でブラックアズナンバーワン的な黒人意識高揚の観点から急進的な活動家などに指示されたこの学説はアフロフューチャリズム(こっちは未来志向)などと共に過去においてもブラックはすごいんだ、という主張の拠り所となっていったらしい。このアフリカ黒人起源説はDNA鑑定的には否定されているようですが、黒人の心を掴んで離さないコンセプトとなっているらしいのです。 だからファンクの人たちって時たまエジプトっぽい衣装を着てるんだ。日本だとスペクトラムとか米米クラブとかってなんかそういう感じだけど、そこら辺の思想のなさが能天気で良いな、と思います。 そのほか黒人文化を模倣する形で取り入れる白人貧困層をホワイトニグロと呼び、非当事者として差別する流れや映画ブラックパンサーについての解釈なども大変面白かった。 また、日本の研究者は黒人奴隷問題については完全な非当事者なため、文章に大変気を遣っているところが感じ取られて気品もあり、素晴らしいなと思う反面、デリケートな問題をしっかりと正面から扱う勇気にも感動した。 広く読まれてほしい一冊です。
ブラック・カルチャー中村隆之読み終わった奴隷貿易や奴隷制を起点に環大西洋的な視座から、黒人の文化を音楽、文学、アートなどを横断的に捉えて読み解く内容。大変素晴らしい内容でした。 今年の初めに読んだ後藤護さんの『黒人音楽史』にも深く接続する内容でこれまで自分が見知ってきたさまざまな黒人に関連する点在する物事がシュパシュパとつながる感覚があり面白かった。 高校時代にジミヘンドリックスにハマり、大学時代はJB、スティービーワンダー、マイルスなどを聴き、それに関する評論なども読んできた。公民権運動やヒップホップの歴史などの良書もあるのでそういうものにも触れてきたわけだが、そういう知識に背骨が通ったような感覚を持った。 菊地成孔と大谷能生がどこかのラジオかドミューンかで後藤さんの『黒人音楽史』について語っていたので、それを読み、そこから中村さんのことを知り本屋で見かけて読んだわけだが、本の持つ引力やセレンディピティを感じる体験となった。 内容としては前半の6章は奴隷貿易に端を発するブラックディアスポラについて丁寧に歴史を読み解いていく。 文字を知ることが「奴隷には向かなくなる」ものとして禁止されていたため、黒人にとって口伝や口承が文化そのものとなり、そこから歌や踊りが文化としてかけがえのないものとして立ち上がっていった、というのはなるほど、と思った。 音楽について、黒人霊歌、ブルース、ジャズの成立と発展はニューオリンズからミシシッピ川遡ってシカゴへ至る流れとして大体の経緯は知っていたが、黒人奴隷からの聞き書きによる奴隷体験記をトーキングブックと呼ぶ、ということは初耳だった。それこスティービーワンダーのアルバムに『トーキングブック』というものがある。 黒人文学についてはサミュエルディレイニーを数冊読んだくらいなので、例えば黒人奴隷の年代期としてテレビドラマにもなっているアレックスヘイリーの『ルーツ』などはやがて読まねばならない作品と感じた。 またアフロフューチャリズムやアフロセントリシティなどの言及にも興味深いものが多かった。 黒人ファンクのジャケなどに時たまエジプト的な衣装が施されていることがある。アースウィンドアンドファイヤーの『太陽神』とか、アフリカバンバータの諸作品とかですが、僕はこれは単なる賑やかしというか、エジプトって面白いよね〜みたいなノリでやってたんだと感じてましたが、実は1970年代にセネガルの研究者がエジプトは黒人国家だったとする論文を発表していたのです。 公民権運動などの中でブラックアズナンバーワン的な黒人意識高揚の観点から急進的な活動家などに指示されたこの学説はアフロフューチャリズム(こっちは未来志向)などと共に過去においてもブラックはすごいんだ、という主張の拠り所となっていったらしい。このアフリカ黒人起源説はDNA鑑定的には否定されているようですが、黒人の心を掴んで離さないコンセプトとなっているらしいのです。 だからファンクの人たちって時たまエジプトっぽい衣装を着てるんだ。日本だとスペクトラムとか米米クラブとかってなんかそういう感じだけど、そこら辺の思想のなさが能天気で良いな、と思います。 そのほか黒人文化を模倣する形で取り入れる白人貧困層をホワイトニグロと呼び、非当事者として差別する流れや映画ブラックパンサーについての解釈なども大変面白かった。 また、日本の研究者は黒人奴隷問題については完全な非当事者なため、文章に大変気を遣っているところが感じ取られて気品もあり、素晴らしいなと思う反面、デリケートな問題をしっかりと正面から扱う勇気にも感動した。 広く読まれてほしい一冊です。 - 2025年12月6日
 四百字のデッサン新装版野見山暁治読み終わった2023年に102歳で没した画家、野見山暁治さんの1976年に出版されたエッセイ。東京美術学校の話や藤田嗣治の話、坂本繁二郎、和田英作、駒井哲郎、義弟田中小実昌など、もはや伝説上の人物との交流などが生き生きと描かれている。 戦時中に東京美術学校に入学し、卒業後、徴兵されるもの病で帰国、なんとなく生き抜いてきてしまった、というような感情を踏まえた回顧もあり、淡々としているが時たま、ある種の燻りを感じさせる瞬間もあり、文章は非常に上手い。 たくさんの死に向き合ってきたこともあり、人間観察が鋭く、妥協やウソのない文章になっている。 先日、『東京美術学校物語』を読んだばかりだったので、和田英作や自由美術の話も大変興味深かった。『東京美術学校物語』では単に記録されているだけだった人物が、生きた人間として回顧されていて、立体的な人間として立ち上がってきて、読書のセレンディピティを感じた。 淡々とした中に味わい深いギャグとかも入っていて、クセのある面白い方だったのであろうな、と感じた。エッセイはたくさん出ているようなので、もう少し読んでみたい。
四百字のデッサン新装版野見山暁治読み終わった2023年に102歳で没した画家、野見山暁治さんの1976年に出版されたエッセイ。東京美術学校の話や藤田嗣治の話、坂本繁二郎、和田英作、駒井哲郎、義弟田中小実昌など、もはや伝説上の人物との交流などが生き生きと描かれている。 戦時中に東京美術学校に入学し、卒業後、徴兵されるもの病で帰国、なんとなく生き抜いてきてしまった、というような感情を踏まえた回顧もあり、淡々としているが時たま、ある種の燻りを感じさせる瞬間もあり、文章は非常に上手い。 たくさんの死に向き合ってきたこともあり、人間観察が鋭く、妥協やウソのない文章になっている。 先日、『東京美術学校物語』を読んだばかりだったので、和田英作や自由美術の話も大変興味深かった。『東京美術学校物語』では単に記録されているだけだった人物が、生きた人間として回顧されていて、立体的な人間として立ち上がってきて、読書のセレンディピティを感じた。 淡々とした中に味わい深いギャグとかも入っていて、クセのある面白い方だったのであろうな、と感じた。エッセイはたくさん出ているようなので、もう少し読んでみたい。 - 2025年12月3日
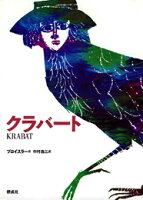 クラバート改訂ヘルベルト・ホルツィンク,ヘルベルト=ホルツィング,オトフリート・プロイスラー,オトフリート=プロイスラー,中村浩三読み終わったドイツの児童文学者、オスフリートプロイスラーによるファンタジー長編。かなり真っ当なジュブナイル。 プロイスラーと言えば『大泥棒ホッツェンプロッツ』3部作が殊に有名だが、他の作品も日本語に訳されているものは大変素晴らしい。 この前、水戸芸術館に磯崎新展見に行ったら、ホッツェンプロッツシリーズと一緒にこの『クラバート』が売っていたので、思わず買ってしまった。 いかがわしく何やら謎めいた魔法使いの親方のもとで粉挽き職人として働きながら魔法使いの修行をする12人の青年たち。 しかし、その12人は毎年大晦日に1人ずつ謎の死を迎える慣わしになっていた。ひょんな偶然から親方に弟子入りすることになったクラバートは、仲間の職人たちと奇妙な魔法使いの弟子生活を送りながら、仲間の死の謎に迫っていくという話。 ホッツェンプロッツのようなギャグはなく、正統的なファンタジージュブナイルという趣き。ドイツの深い森や雪深い冬、魔法の持つ神秘性が格調高く描かれている。 ザクソン選帝侯みたいな肩書とか、シュバルツコルムみたいな森の呼び名、そのほかも地名とかもドイツ的で大変魅力的だ。 ドイツの粉挽職人の生活と魔術的な人間関係や謎解きの面白さなど、派手さはないがしみじみと良いファンタジー感に触れることができる。 『千と千尋の神隠し』の元ネタの一つということはよく言われているが、魔法使いの弟子が皆、鳥になるシーンなどは『君たちはどう生きるか』にもイメージの一部が引き継がれているようにも感じた。ジブリ好きの人は是非一読を勧めたい。 ホッツェンプロッツは幼い玄にせがまれて何度も読み聞かせしたけど、青年になった彼とまたプロイスラーについて一緒に話し合えるのは素敵な体験だと感じている。
クラバート改訂ヘルベルト・ホルツィンク,ヘルベルト=ホルツィング,オトフリート・プロイスラー,オトフリート=プロイスラー,中村浩三読み終わったドイツの児童文学者、オスフリートプロイスラーによるファンタジー長編。かなり真っ当なジュブナイル。 プロイスラーと言えば『大泥棒ホッツェンプロッツ』3部作が殊に有名だが、他の作品も日本語に訳されているものは大変素晴らしい。 この前、水戸芸術館に磯崎新展見に行ったら、ホッツェンプロッツシリーズと一緒にこの『クラバート』が売っていたので、思わず買ってしまった。 いかがわしく何やら謎めいた魔法使いの親方のもとで粉挽き職人として働きながら魔法使いの修行をする12人の青年たち。 しかし、その12人は毎年大晦日に1人ずつ謎の死を迎える慣わしになっていた。ひょんな偶然から親方に弟子入りすることになったクラバートは、仲間の職人たちと奇妙な魔法使いの弟子生活を送りながら、仲間の死の謎に迫っていくという話。 ホッツェンプロッツのようなギャグはなく、正統的なファンタジージュブナイルという趣き。ドイツの深い森や雪深い冬、魔法の持つ神秘性が格調高く描かれている。 ザクソン選帝侯みたいな肩書とか、シュバルツコルムみたいな森の呼び名、そのほかも地名とかもドイツ的で大変魅力的だ。 ドイツの粉挽職人の生活と魔術的な人間関係や謎解きの面白さなど、派手さはないがしみじみと良いファンタジー感に触れることができる。 『千と千尋の神隠し』の元ネタの一つということはよく言われているが、魔法使いの弟子が皆、鳥になるシーンなどは『君たちはどう生きるか』にもイメージの一部が引き継がれているようにも感じた。ジブリ好きの人は是非一読を勧めたい。 ホッツェンプロッツは幼い玄にせがまれて何度も読み聞かせしたけど、青年になった彼とまたプロイスラーについて一緒に話し合えるのは素敵な体験だと感じている。 - 2025年11月29日
 芸術論宮島達男読み終わった現代美術アーティスト、宮島達男の21世紀に入ってからのさまざまな論考を集めたものに、Twitter(現X)でのポストや書き下ろしを加えた本。 芸術家として、また東北芸術工科大学における教育者としての宮島達男の言葉が綴られている。 美術教育についてその必要性や意義をかなり前向きに実践的に語ってくれている。 作品には仏教的な世界観が取り入れられているが、現世においてはかなり実践的で具体的なコンセプトを持って望んでいることがわかり、大変興味深かった。 とても人間的な文章で共感しました。
芸術論宮島達男読み終わった現代美術アーティスト、宮島達男の21世紀に入ってからのさまざまな論考を集めたものに、Twitter(現X)でのポストや書き下ろしを加えた本。 芸術家として、また東北芸術工科大学における教育者としての宮島達男の言葉が綴られている。 美術教育についてその必要性や意義をかなり前向きに実践的に語ってくれている。 作品には仏教的な世界観が取り入れられているが、現世においてはかなり実践的で具体的なコンセプトを持って望んでいることがわかり、大変興味深かった。 とても人間的な文章で共感しました。 - 2025年11月29日
 東京美術学校物語新関公子読み終わった明治から昭和にかけての美術界の動向が東京藝術大学の前身である、東京美術学校の歴史を中心に語られる本。 1876〜83までの工部美学校に続いて1889〜1949までの東京美術大学のたどった歴史をコンパクトにまとめている。 日本の美術の歴史を国粋主義的な日本がの流れ(岡倉天心やフェノロサ→横山大観などの日本画的傾向)と海外留学経験のある国際主義的な流れ(黒田清輝などによる洋画的傾向)の対立で読み解く流れは、それぞれの作家を明治〜昭和初期の作家についてそれぞれ調べるにおいて、なんとなく知ってはいたが、東京美術学校における人事の流れなどを読み解くと非常にわかりやすく、面白かった。 国際社会において、海外に対峙する日本の独自性を日本的なアイデンティティの形成として目指した岡倉天心的な考え方と、海外の文化を取り入れて折衷しつつ認めさせる黒田などの思想が対立するのは必然な気がするが、黒田の代表作と言える『知情感』のコンセプト作成に岡倉が関与していたのではないか、という見立ては非常に面白かったし、その背景が金箔による絶対空間であるがため、ヨーロッパでは下書きとみなされてしまったかもしれない、という点などは大変面白かった。 当時の万博などへの出品目録のデータなどもあり、そこから読み取れるもの色々とあり、大変面白かった。 それ以外でも、資料から読み取れる各プレーヤー(歴史的人物)の思惑などの、感情的側面が想定と共に記されているのも面白かった。 浅井忠なんかの日記を基にした、万博の日本展示への絶望的な否定感だとか、官展や文展、そのほかの在野団体の感情のもつれなど、歴史というのは人間の感情に結びつくと途端に下世話な面白さを帯びるな、と感じた。 岡倉天心など、心意気は良いんだが、下半身がだらしないとことか、いくらいいこと言っていても、それでいろんな物事が振り出しに戻ったりして、いかがなものかとも思うし、横山大観なんかの戦時中の国粋的な感覚からの戦意高揚に向けての舵取りなど、なかなかシビアなものがあった。 とはいえ、そういう点を画業と合わせて肯定的に捉える文章の説得力もあり、そういう見方もあるのか、と思った。 とにかく団体やイデオロギーなどの衝突や小賢しい政治的な思惑で人を失脚させたりとか、そういう話も多く、こういう人間関係は昔から変わらないのね、とも感じた。 作品ばかり知っていたさまざまな明治以降の伝説的作家の割と赤裸々な感情的思惑や失敗や成功なども記されており、大変面白かったです。
東京美術学校物語新関公子読み終わった明治から昭和にかけての美術界の動向が東京藝術大学の前身である、東京美術学校の歴史を中心に語られる本。 1876〜83までの工部美学校に続いて1889〜1949までの東京美術大学のたどった歴史をコンパクトにまとめている。 日本の美術の歴史を国粋主義的な日本がの流れ(岡倉天心やフェノロサ→横山大観などの日本画的傾向)と海外留学経験のある国際主義的な流れ(黒田清輝などによる洋画的傾向)の対立で読み解く流れは、それぞれの作家を明治〜昭和初期の作家についてそれぞれ調べるにおいて、なんとなく知ってはいたが、東京美術学校における人事の流れなどを読み解くと非常にわかりやすく、面白かった。 国際社会において、海外に対峙する日本の独自性を日本的なアイデンティティの形成として目指した岡倉天心的な考え方と、海外の文化を取り入れて折衷しつつ認めさせる黒田などの思想が対立するのは必然な気がするが、黒田の代表作と言える『知情感』のコンセプト作成に岡倉が関与していたのではないか、という見立ては非常に面白かったし、その背景が金箔による絶対空間であるがため、ヨーロッパでは下書きとみなされてしまったかもしれない、という点などは大変面白かった。 当時の万博などへの出品目録のデータなどもあり、そこから読み取れるもの色々とあり、大変面白かった。 それ以外でも、資料から読み取れる各プレーヤー(歴史的人物)の思惑などの、感情的側面が想定と共に記されているのも面白かった。 浅井忠なんかの日記を基にした、万博の日本展示への絶望的な否定感だとか、官展や文展、そのほかの在野団体の感情のもつれなど、歴史というのは人間の感情に結びつくと途端に下世話な面白さを帯びるな、と感じた。 岡倉天心など、心意気は良いんだが、下半身がだらしないとことか、いくらいいこと言っていても、それでいろんな物事が振り出しに戻ったりして、いかがなものかとも思うし、横山大観なんかの戦時中の国粋的な感覚からの戦意高揚に向けての舵取りなど、なかなかシビアなものがあった。 とはいえ、そういう点を画業と合わせて肯定的に捉える文章の説得力もあり、そういう見方もあるのか、と思った。 とにかく団体やイデオロギーなどの衝突や小賢しい政治的な思惑で人を失脚させたりとか、そういう話も多く、こういう人間関係は昔から変わらないのね、とも感じた。 作品ばかり知っていたさまざまな明治以降の伝説的作家の割と赤裸々な感情的思惑や失敗や成功なども記されており、大変面白かったです。 - 2025年11月24日
 読み終わった大塚英志の新刊。新書だが470ページとかある大部。とはいえ、内容は非常にエキサイティングで大変面白く、結構時間を忘れて読んだ。 1930年代にエイゼンシュテインが自身の映画技術であるモンタージュ論を日本の伝統表現と結び付けた評論がキネ旬により日本に紹介されたことをきっかけにこ、日本的🟰モンタージュという概念が市井にも広がった。 モンタージュは映像表現におけるカットと時系列のカットアップによる演出方法だが、それはロシア構成主義などによる平面のグラフモンタージュとも関連していく。 1937年のウィーン万博には日本も出展しており、これは日本国としては公式初参加の万博だが、そこには金のシャチホコなどと一緒に、観光日本と称された、高さ2.35m、長さ18mに及ぶ写真壁画が展示されていたという。 これは大仏や芸者などをあしらったフォトモンタージュ作品だったが、そういうものが展示された経緯や、その後、戦時下にプロパガンダとして国策で作られたグラフ誌「front』などの成立やピープルツリーを細かく紹介し、戦時下のプロパガンダとグラフモンタージュなどがどのように成立していったかを解説している。 そもそも、僕は美術教科書の編集の仕事をしているわけですが、自分の問題意識として、この美術教科書のレイアウトの形式ってどこからきたのか、意識したことはなかったのですが、なんかそれを想像させてくれるような資料的側面が強く、大変に惹きつけられました。 戦中のプロパガンダ誌には原弘とか名取洋之助とか木村伊兵衛、土門拳なんかも絡んでいるわけですが、それ以前には日本にはいわゆる雑誌などはなかったわけで、この辺りが今の雑誌レイアウトに与えた影響は大きく、そのあたりの人たちは戦後も出版や写真の世界で生き残っていくわけなので、もしかしたら美術教科書の源流はここかもしれないな、などと考えさせられた。 社内にある古い教科書の関係者にこういう人らが入っているかどうかを少しリサーチしてみようかと思う。 それ以外にも柳田國男とか手塚治虫とかの話もあって、大変に勉強になりました。面白い本なので、オススメです。
読み終わった大塚英志の新刊。新書だが470ページとかある大部。とはいえ、内容は非常にエキサイティングで大変面白く、結構時間を忘れて読んだ。 1930年代にエイゼンシュテインが自身の映画技術であるモンタージュ論を日本の伝統表現と結び付けた評論がキネ旬により日本に紹介されたことをきっかけにこ、日本的🟰モンタージュという概念が市井にも広がった。 モンタージュは映像表現におけるカットと時系列のカットアップによる演出方法だが、それはロシア構成主義などによる平面のグラフモンタージュとも関連していく。 1937年のウィーン万博には日本も出展しており、これは日本国としては公式初参加の万博だが、そこには金のシャチホコなどと一緒に、観光日本と称された、高さ2.35m、長さ18mに及ぶ写真壁画が展示されていたという。 これは大仏や芸者などをあしらったフォトモンタージュ作品だったが、そういうものが展示された経緯や、その後、戦時下にプロパガンダとして国策で作られたグラフ誌「front』などの成立やピープルツリーを細かく紹介し、戦時下のプロパガンダとグラフモンタージュなどがどのように成立していったかを解説している。 そもそも、僕は美術教科書の編集の仕事をしているわけですが、自分の問題意識として、この美術教科書のレイアウトの形式ってどこからきたのか、意識したことはなかったのですが、なんかそれを想像させてくれるような資料的側面が強く、大変に惹きつけられました。 戦中のプロパガンダ誌には原弘とか名取洋之助とか木村伊兵衛、土門拳なんかも絡んでいるわけですが、それ以前には日本にはいわゆる雑誌などはなかったわけで、この辺りが今の雑誌レイアウトに与えた影響は大きく、そのあたりの人たちは戦後も出版や写真の世界で生き残っていくわけなので、もしかしたら美術教科書の源流はここかもしれないな、などと考えさせられた。 社内にある古い教科書の関係者にこういう人らが入っているかどうかを少しリサーチしてみようかと思う。 それ以外にも柳田國男とか手塚治虫とかの話もあって、大変に勉強になりました。面白い本なので、オススメです。 - 2025年11月24日
- 2025年11月4日
 読み終わった現代のインクルーシブ教育まで連綿と続く第二次大戦後から1980年までの「特別なニーズを持つ子ども」に対応する教育の歴史を調べた本。 占領下の日本に対して米国式の教育を導入させた第一次、第二次の米国使節団の報告書、日教組の「分けない教育」に関連する実践報告、文部省の中央教育審議会の答申や大阪府豊中中の実践報告などが細かく時系列で述べられている。 いわゆる障害児教育では可能な限り一般教室で障害のある子どもを包摂して分けない教育と養護学校に押し込めて分ける教育という2つの方向性があり、戦後直後は福祉制度が未分化だったこともあり分けない教育が志向され、高度経済成長とともに田中角栄内閣による1972年の「重度障害児の全員収容制度」の公約など分ける教育に舵取りがされたが、やがて普通教育から障害児を排除する意識への警鐘から、共同教育の機運が高まり、分けない教育に再び目が向けられた。 この本は1980年代頃までをカバーしているが、2024年の障害者差別解消法の施行など、社会でも広く多様性や共生的な社会が望まれている側面もあり、そういう点で「合理的配慮」の基本的な考え方に結びつく歴史が学べる本だった。
読み終わった現代のインクルーシブ教育まで連綿と続く第二次大戦後から1980年までの「特別なニーズを持つ子ども」に対応する教育の歴史を調べた本。 占領下の日本に対して米国式の教育を導入させた第一次、第二次の米国使節団の報告書、日教組の「分けない教育」に関連する実践報告、文部省の中央教育審議会の答申や大阪府豊中中の実践報告などが細かく時系列で述べられている。 いわゆる障害児教育では可能な限り一般教室で障害のある子どもを包摂して分けない教育と養護学校に押し込めて分ける教育という2つの方向性があり、戦後直後は福祉制度が未分化だったこともあり分けない教育が志向され、高度経済成長とともに田中角栄内閣による1972年の「重度障害児の全員収容制度」の公約など分ける教育に舵取りがされたが、やがて普通教育から障害児を排除する意識への警鐘から、共同教育の機運が高まり、分けない教育に再び目が向けられた。 この本は1980年代頃までをカバーしているが、2024年の障害者差別解消法の施行など、社会でも広く多様性や共生的な社会が望まれている側面もあり、そういう点で「合理的配慮」の基本的な考え方に結びつく歴史が学べる本だった。 - 2025年11月3日
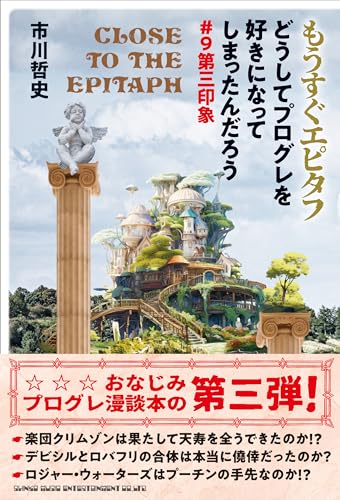 読み終わった同僚の大久保さんに差し入れてもらった音楽評論本。480ページもあるがスルスルと一晩で読んでしまった。 タイトルにある通りプログレッシブロックにまつわる音楽評論。ロッキングオンで1993年まで原稿を書いていたというので、それはちょうど僕の高2までとなり、ネットや携帯のない青森の田舎者だった僕がクロスビートなどと並んで数少ない洋楽の情報源としてロッキングオンを1番読んでいた頃なので、かなりデジャビュ感があった。 90年代の僕はかなり素朴なハードロック小僧だったが、当時のロッキングオンにはツェッペリンやクリムゾンの記事はまだまだ載っていた気がする。そんなものを何度も何度も読み返したものだ。 この本では2010年代以降のトリプルドラム期→2010年代後半のダブルカルテット期→ライブ引退にかけてのキングクリムゾンのメンバーやフリップの考えていたことが解釈されていて大変学びが多かった。 ロバートフリップという人はキングクリムゾンの音楽的なコンセプトをかなりしっかりした方向性を持って演出しているが、案外共演者たるメンバーによってやることやできることが制限されたり、大きく舵取りされる人なんだなと感じた。 特にライブバンドとして70年代の初期クリムゾンの古典的名曲を今のキングクリムゾンで再解釈/再演したあたりは、ビルリーフリンの存在が大きかったということがよく分かった。 また、70年代のクリムゾンの楽曲というのはほとんど演奏されることがなかったというのも、フリップの性格からするとそうであろうな、とは思うものの、それをしっかりやり切ることをクリムゾンでやり切る、というのはある種の答え合わせのようで素晴らしい。 『ポセイドンの目醒め』とか高校生の頃、故郷の八戸の寒い冬の間、布団の中でよく聞いたアルバムなので、その辺りが大変な技量で再演されているのを聞くのは大変まともな体験に思える。 『暗黒の世界』とか『レッド』の楽曲の最近のライブでの演奏も好きでよく聞いていたので、そういう背景に触れられたのも良かった。 それ以外ではデビットシルヴィアンの話やピンク・フロイド、ニナ・ハーゲンの話なども僕ら世代向けの真っ当に軽薄な文体の音楽評論という感じで大変に楽しめました。 この本を片手に記述されている音源を片っ端からアップルミュージックで聴けるなんて、大変な時代ですわな。 そういえば、最近新しい音楽に触れていないのは、詰まるところ音楽評論を読んでないから、という考えに至った。昔は文章で読んで妄想して音楽に触れる、という順番だったですね。そういえば。 今、49歳ですけど、同世代の方におすすめです。
読み終わった同僚の大久保さんに差し入れてもらった音楽評論本。480ページもあるがスルスルと一晩で読んでしまった。 タイトルにある通りプログレッシブロックにまつわる音楽評論。ロッキングオンで1993年まで原稿を書いていたというので、それはちょうど僕の高2までとなり、ネットや携帯のない青森の田舎者だった僕がクロスビートなどと並んで数少ない洋楽の情報源としてロッキングオンを1番読んでいた頃なので、かなりデジャビュ感があった。 90年代の僕はかなり素朴なハードロック小僧だったが、当時のロッキングオンにはツェッペリンやクリムゾンの記事はまだまだ載っていた気がする。そんなものを何度も何度も読み返したものだ。 この本では2010年代以降のトリプルドラム期→2010年代後半のダブルカルテット期→ライブ引退にかけてのキングクリムゾンのメンバーやフリップの考えていたことが解釈されていて大変学びが多かった。 ロバートフリップという人はキングクリムゾンの音楽的なコンセプトをかなりしっかりした方向性を持って演出しているが、案外共演者たるメンバーによってやることやできることが制限されたり、大きく舵取りされる人なんだなと感じた。 特にライブバンドとして70年代の初期クリムゾンの古典的名曲を今のキングクリムゾンで再解釈/再演したあたりは、ビルリーフリンの存在が大きかったということがよく分かった。 また、70年代のクリムゾンの楽曲というのはほとんど演奏されることがなかったというのも、フリップの性格からするとそうであろうな、とは思うものの、それをしっかりやり切ることをクリムゾンでやり切る、というのはある種の答え合わせのようで素晴らしい。 『ポセイドンの目醒め』とか高校生の頃、故郷の八戸の寒い冬の間、布団の中でよく聞いたアルバムなので、その辺りが大変な技量で再演されているのを聞くのは大変まともな体験に思える。 『暗黒の世界』とか『レッド』の楽曲の最近のライブでの演奏も好きでよく聞いていたので、そういう背景に触れられたのも良かった。 それ以外ではデビットシルヴィアンの話やピンク・フロイド、ニナ・ハーゲンの話なども僕ら世代向けの真っ当に軽薄な文体の音楽評論という感じで大変に楽しめました。 この本を片手に記述されている音源を片っ端からアップルミュージックで聴けるなんて、大変な時代ですわな。 そういえば、最近新しい音楽に触れていないのは、詰まるところ音楽評論を読んでないから、という考えに至った。昔は文章で読んで妄想して音楽に触れる、という順番だったですね。そういえば。 今、49歳ですけど、同世代の方におすすめです。 - 2025年10月31日
- 2025年10月31日
 羊をめぐる冒険(上)村上春樹読み終わった村上春樹の『羊をめぐる冒険』をオーディブルでフル視聴した。フル視聴という言葉はフルシチョフと韻が踏めるな。ソビエト的である。 朗読は染谷将太で非常に巧みな朗読でした。男性の声と女性の声を上手く語りわけていて、感心した。それ以外にも完璧な耳を持つ彼女や、黒いスーツの男、羊博士、指が3本しかないトルフィンホテルの支配人、運転手などをしっかり演じ分けていて、素晴らしかった。 いわゆるネズミ三部作の最終作である。ネズミ三部作ではピンボールのやつが1番好きなのですが、久しぶりに読み直し(聞き直し)してみたらこちらも趣があってよかった。 最近の技巧を感じさせないすっきりした成熟みのある村上春樹も良いが、この頃のある種の迷いみたいなものを抱えたぎこちなさも大変によい。 構成力みたいなものが少し弱いが、戦争とかその後の『ねじまき鳥クロニクル』に流れ着くモチーフがすでに出ているのも良い。 ホテルの中でエレベーターでどこかの間の階に止まるみたいな印象的なシーンがあったと思っていたが、なかった。それは『ダンスダンスダンス』の方だったのかもしれない。 レイモンドチャンドラーの構成や雰囲気を出そうとした、というインタビューがあるようだが、そういったハードボイルドな雰囲気はよく出ている。 あとは秋口から冬の北海道の感じが感じられて大変よかった。お話の中で会社をたたむ話が出ているが、これは同時期に村上春樹が自分の経営していたジャズバー「ピーターキャット」を専業作家になるために畳んだことが影響しているのかな。 久しぶりに読み返して(聞き返して)、色々発見もあった。同じ本を繰り返し読むのは楽しいな。
羊をめぐる冒険(上)村上春樹読み終わった村上春樹の『羊をめぐる冒険』をオーディブルでフル視聴した。フル視聴という言葉はフルシチョフと韻が踏めるな。ソビエト的である。 朗読は染谷将太で非常に巧みな朗読でした。男性の声と女性の声を上手く語りわけていて、感心した。それ以外にも完璧な耳を持つ彼女や、黒いスーツの男、羊博士、指が3本しかないトルフィンホテルの支配人、運転手などをしっかり演じ分けていて、素晴らしかった。 いわゆるネズミ三部作の最終作である。ネズミ三部作ではピンボールのやつが1番好きなのですが、久しぶりに読み直し(聞き直し)してみたらこちらも趣があってよかった。 最近の技巧を感じさせないすっきりした成熟みのある村上春樹も良いが、この頃のある種の迷いみたいなものを抱えたぎこちなさも大変によい。 構成力みたいなものが少し弱いが、戦争とかその後の『ねじまき鳥クロニクル』に流れ着くモチーフがすでに出ているのも良い。 ホテルの中でエレベーターでどこかの間の階に止まるみたいな印象的なシーンがあったと思っていたが、なかった。それは『ダンスダンスダンス』の方だったのかもしれない。 レイモンドチャンドラーの構成や雰囲気を出そうとした、というインタビューがあるようだが、そういったハードボイルドな雰囲気はよく出ている。 あとは秋口から冬の北海道の感じが感じられて大変よかった。お話の中で会社をたたむ話が出ているが、これは同時期に村上春樹が自分の経営していたジャズバー「ピーターキャット」を専業作家になるために畳んだことが影響しているのかな。 久しぶりに読み返して(聞き返して)、色々発見もあった。同じ本を繰り返し読むのは楽しいな。 - 2025年10月27日
 遊びと人間ロジェ・カイヨワ,塚崎幹夫,多田道太郎読み終わった1958年にフランスで出版され1971年に翻訳版として出版された講談社版の文庫である。「遊び」を分析した本。 先行書としてホイジンガの『ホモ・ルーデンス』やシラーの『人間の美的教育について』を置き、そこで語られる遊びについて、カイヨワなりの批判的な補足説明を行なっている。 カイヨワによると遊びは競争、運、模擬、眩暈の4つに分類され、それらの組み合わせによって読み解くことができるという。 これを起点に文明や文化の発達を考察していく、という内容。 例えば原始的な文明では仮面を被り超自然な神的なものを模擬した存在がイニシエーションなどの眩暈を伴う活動で集団をまとめているが、そこがギリシアやローマ的に発展していくと、集団の母数が増えるため、よりルール化され、競争や運などに支配されることで合理化されていく、みたいなことが書かれていた。 競争は自力本願、運は他力本願という側面を持ち、自由な遊びの中にも、結果に対してフェアな態度が求められる、というか結果的にそうならざるを得ない、というようなことが書かれていたり、非常に面白い視点の本だった。 特に遊びの要素の中に身体的な眩暈の観点が含まれているのが独創的に思った。ジェットコースターに乗ってクラクラしたり、犬が自分の尻尾を追いかけたりする、というような行動を根源的な遊びの表れとして位置付けている。 遊びは自由だがルールがないと成立しない、とか、そういう考えだけだと身体性が薄れる。純粋な自己破壊的なシミュレーションのような形での眩暈は僕もよくやった。 何もない一本道で目を瞑ってどこまで歩けるか、とか、自転車に乗っているのに目を瞑ったり、手放しでどこまで行けるかとか試してみたくなる気持ちは眩暈の希求だと思う。 それがなんだ、という話はあるが、そういう事象が文明論にまつわる感じでスケール大きめに語られている。 少し時間は掛かるが、興味のある人は読んでみてください。
遊びと人間ロジェ・カイヨワ,塚崎幹夫,多田道太郎読み終わった1958年にフランスで出版され1971年に翻訳版として出版された講談社版の文庫である。「遊び」を分析した本。 先行書としてホイジンガの『ホモ・ルーデンス』やシラーの『人間の美的教育について』を置き、そこで語られる遊びについて、カイヨワなりの批判的な補足説明を行なっている。 カイヨワによると遊びは競争、運、模擬、眩暈の4つに分類され、それらの組み合わせによって読み解くことができるという。 これを起点に文明や文化の発達を考察していく、という内容。 例えば原始的な文明では仮面を被り超自然な神的なものを模擬した存在がイニシエーションなどの眩暈を伴う活動で集団をまとめているが、そこがギリシアやローマ的に発展していくと、集団の母数が増えるため、よりルール化され、競争や運などに支配されることで合理化されていく、みたいなことが書かれていた。 競争は自力本願、運は他力本願という側面を持ち、自由な遊びの中にも、結果に対してフェアな態度が求められる、というか結果的にそうならざるを得ない、というようなことが書かれていたり、非常に面白い視点の本だった。 特に遊びの要素の中に身体的な眩暈の観点が含まれているのが独創的に思った。ジェットコースターに乗ってクラクラしたり、犬が自分の尻尾を追いかけたりする、というような行動を根源的な遊びの表れとして位置付けている。 遊びは自由だがルールがないと成立しない、とか、そういう考えだけだと身体性が薄れる。純粋な自己破壊的なシミュレーションのような形での眩暈は僕もよくやった。 何もない一本道で目を瞑ってどこまで歩けるか、とか、自転車に乗っているのに目を瞑ったり、手放しでどこまで行けるかとか試してみたくなる気持ちは眩暈の希求だと思う。 それがなんだ、という話はあるが、そういう事象が文明論にまつわる感じでスケール大きめに語られている。 少し時間は掛かるが、興味のある人は読んでみてください。 - 2025年10月27日
 東京奇譚集村上春樹読み終わったAmazonオーディブルにあるイッセー尾形の朗読で聞いた。品川猿の話が好きで突然聞きたくなって聞いたら、面白かったので、全編聴いてしまった。 品川猿以外には、ゲイのピアノ調律士がひょんな偶然から仲違いしていた姉と仲直りする話、自分にとって本当に大切な女性と出会う話、高層マンションの26階から行方不明になった男の行方を探す探偵の話、サメに足を食いちぎられて死んだ息子がいる母親の話などが含まれている。 品川猿と大抵の話が個人的には好きである。
東京奇譚集村上春樹読み終わったAmazonオーディブルにあるイッセー尾形の朗読で聞いた。品川猿の話が好きで突然聞きたくなって聞いたら、面白かったので、全編聴いてしまった。 品川猿以外には、ゲイのピアノ調律士がひょんな偶然から仲違いしていた姉と仲直りする話、自分にとって本当に大切な女性と出会う話、高層マンションの26階から行方不明になった男の行方を探す探偵の話、サメに足を食いちぎられて死んだ息子がいる母親の話などが含まれている。 品川猿と大抵の話が個人的には好きである。 - 2025年10月12日
 戦争とデザイン松田行正読み終わった戦争におけるデザイン、特に配色、シンボル、言葉の使い分けについて細かく解説してくれる本。初版は2022年の7月。プーチン・ロシアによるウクライナ侵攻の直後に書かれた論考がメインなので、第二次対戦中のナチスドイツの、デザインの話をしていても、どうしてもウクライナ戦争に話題が惹かれていってしまうような印象があった。 古くは十字軍の頃からキリスト教とイスラム教の間での戦いではお互いを認識できるように配色が工夫されていたとか、そういう話が続く。 また星のマークは識別のデザインとしてよく使われるが、形はともかく色で認識していたとか、ナチスの鉤十字をスワスチカと呼ぶのはなぜかとか、ユダヤ教のダビデの星についての話とか、さまざまなシンボルの由来やら使い方や受け入れられ方などが様々に語られていて興味深い。 とはいえ筆者の興味の赴くところなので、第二次大戦のナチスドイツが中心的に語られているので、網羅的ではない。 たとえば日本の戦国時代の旗印に関する言及などもあまりない。 戦争とデザインというタイトルではあるが、現在のウクライナ戦争に対する反対の気持ちが強く、その辺りのジャーナリズム的な言及がむしろ内容の大きな部分を占めているように感じた。
戦争とデザイン松田行正読み終わった戦争におけるデザイン、特に配色、シンボル、言葉の使い分けについて細かく解説してくれる本。初版は2022年の7月。プーチン・ロシアによるウクライナ侵攻の直後に書かれた論考がメインなので、第二次対戦中のナチスドイツの、デザインの話をしていても、どうしてもウクライナ戦争に話題が惹かれていってしまうような印象があった。 古くは十字軍の頃からキリスト教とイスラム教の間での戦いではお互いを認識できるように配色が工夫されていたとか、そういう話が続く。 また星のマークは識別のデザインとしてよく使われるが、形はともかく色で認識していたとか、ナチスの鉤十字をスワスチカと呼ぶのはなぜかとか、ユダヤ教のダビデの星についての話とか、さまざまなシンボルの由来やら使い方や受け入れられ方などが様々に語られていて興味深い。 とはいえ筆者の興味の赴くところなので、第二次大戦のナチスドイツが中心的に語られているので、網羅的ではない。 たとえば日本の戦国時代の旗印に関する言及などもあまりない。 戦争とデザインというタイトルではあるが、現在のウクライナ戦争に対する反対の気持ちが強く、その辺りのジャーナリズム的な言及がむしろ内容の大きな部分を占めているように感じた。 - 2025年10月11日
 夜になるまえにレイナルド・アレナス,Reinaldo Arenas,安藤哲行読み終わった(注意:ちょっと性的な表現があります) 1943年生まれ、キューバ出身の作家レイナルドアレナスが1990年にエイズで自死する前に、亡命先のニューヨークで書き上げた自伝的小説。キューバ革命の真っ只中でホモセクシュアルとして青春を過ごした作家の人生が凝縮して描かれている。 幼少期の記憶は朧げなところもあるのか、多少マジックリアリズム的な筆致だが、長ずるにつれて非常にリアリズムで妥協のない世界へ突入していく。 キューバ革命を経て成立したカストロ政権による、文学者や芸術家への弾圧と相互監視的な政策とその内情がほぼ実名で暴露されている。 ガルシア・マルケスなどはアレナスから見ると政権御用達作家でノーベル文学賞は獲ったものの、いかほどなものか、という感じ。他にもバルガスリョサとかボルヘスについても実名で言及あり。 自分が捉えていた評価とのズレに当事者性と視点というものについて考えさせられる。 また、若く反体制的な文学者が捕縛され拷問を受けて転向し、周囲の仲間を巻き込んで衆目の中で、団体的に総括させられる場面などは痛々しくて読んではおれない残酷さだった。しかし、そういうことがあったのだろう。現実はディストピア的だ。 また、夜景国家的社会主義政権下でのホモセクシャルのあり方もかなり赤裸々に描かれている。 社会は真っ暗だがホントに当時のキューバンホモセクシャルは奔放だな! という感じで、公衆トイレといえばハッテンするし、長距離バスの中とかチャットでも男と長時間一緒になるシチュエーションが来るとペニをしゃぶりまくるという有様。 本当にこんなに奔放にできるのかな? 性的快楽に対する文化の違いを思い知らされるが、まさに背徳、という感じで素晴らしい。 亡命後のニューヨークで、現地のホモセクシャルは細分化されており、原始的パワーに貧する、みたいな批判を繰り広げたりしており、そこは正直なところなのだろうな、と思った。海を越えると文化も違うというわけで。 ホモセクシャルの表現については、色々な愛の形があることは分かるが、そこにあったと思われるロマンス的な心情の昂りは直接的には描かれていない感じがして、面白かった。愛の感覚が欠如している感じ。ないわけではないのだが。 それは自伝的な小説なので、それぞれの人たちへの配慮なのだろうか。肉体的快楽、事象としてのセックスが描かれるのみなに感じた。しかし、それは僕の読み込みの浅さかもしれない。読まれた方の意見を聞きたい。 個人的にはヘンリーミラーの『南回帰線』や『北回帰線』、ジャックケルアックの『路上』とかを読んだ時の読後感。素晴らしく好みの小説。こういうのばかり読みたい。自由に生きることを希求し、そう生きた人だけが描ける小説だと思った。 素晴らしい本なので、今の世の中を生きる人にはあまねく読んでもらいたい。
夜になるまえにレイナルド・アレナス,Reinaldo Arenas,安藤哲行読み終わった(注意:ちょっと性的な表現があります) 1943年生まれ、キューバ出身の作家レイナルドアレナスが1990年にエイズで自死する前に、亡命先のニューヨークで書き上げた自伝的小説。キューバ革命の真っ只中でホモセクシュアルとして青春を過ごした作家の人生が凝縮して描かれている。 幼少期の記憶は朧げなところもあるのか、多少マジックリアリズム的な筆致だが、長ずるにつれて非常にリアリズムで妥協のない世界へ突入していく。 キューバ革命を経て成立したカストロ政権による、文学者や芸術家への弾圧と相互監視的な政策とその内情がほぼ実名で暴露されている。 ガルシア・マルケスなどはアレナスから見ると政権御用達作家でノーベル文学賞は獲ったものの、いかほどなものか、という感じ。他にもバルガスリョサとかボルヘスについても実名で言及あり。 自分が捉えていた評価とのズレに当事者性と視点というものについて考えさせられる。 また、若く反体制的な文学者が捕縛され拷問を受けて転向し、周囲の仲間を巻き込んで衆目の中で、団体的に総括させられる場面などは痛々しくて読んではおれない残酷さだった。しかし、そういうことがあったのだろう。現実はディストピア的だ。 また、夜景国家的社会主義政権下でのホモセクシャルのあり方もかなり赤裸々に描かれている。 社会は真っ暗だがホントに当時のキューバンホモセクシャルは奔放だな! という感じで、公衆トイレといえばハッテンするし、長距離バスの中とかチャットでも男と長時間一緒になるシチュエーションが来るとペニをしゃぶりまくるという有様。 本当にこんなに奔放にできるのかな? 性的快楽に対する文化の違いを思い知らされるが、まさに背徳、という感じで素晴らしい。 亡命後のニューヨークで、現地のホモセクシャルは細分化されており、原始的パワーに貧する、みたいな批判を繰り広げたりしており、そこは正直なところなのだろうな、と思った。海を越えると文化も違うというわけで。 ホモセクシャルの表現については、色々な愛の形があることは分かるが、そこにあったと思われるロマンス的な心情の昂りは直接的には描かれていない感じがして、面白かった。愛の感覚が欠如している感じ。ないわけではないのだが。 それは自伝的な小説なので、それぞれの人たちへの配慮なのだろうか。肉体的快楽、事象としてのセックスが描かれるのみなに感じた。しかし、それは僕の読み込みの浅さかもしれない。読まれた方の意見を聞きたい。 個人的にはヘンリーミラーの『南回帰線』や『北回帰線』、ジャックケルアックの『路上』とかを読んだ時の読後感。素晴らしく好みの小説。こういうのばかり読みたい。自由に生きることを希求し、そう生きた人だけが描ける小説だと思った。 素晴らしい本なので、今の世の中を生きる人にはあまねく読んでもらいたい。 - 2025年10月7日
 宗教とデザイン松田行正読み終わったキリスト教、イスラム教、仏教の三つの宗教がその成立過程からどのように形や色を活用してきたかについてを包括的に扱っている本。 いろんなところで読んだ本などで得た僕にとっての既習事項が総合的な知の力によって構成されているように感じた。 物事ってこういうふうに結びつくのか〜という感じ。マレーヴィチの黒い四角形が、究極の偶像表現だ、みたいな近現代美術の切り口もしっかり入っていて素晴らしいと思った。 松岡正剛さんからの引用も多かったので、こういう学際的な領域を攻める人たちにとっての巨人はやはり松岡さんなのかもしれない。一度お会いしていろいろ聞いてみたかったです。 車のマツダあるじゃないですか、あれってアルファベットではMAZDAですけど、その表記はゾロアスター教の最高神、アフラ・マズダー(Ahura Mazdā)から来ているんだって。というのもアフラ・マズダーは光明神なのでエジソンじゃない方のイギリスのゼネラルエレクトリックカンパニーが自社の作った電球をMAZDAと命名してたので、マツダがアメリカ進出するときに、アメリカ人にも読みやすいようにその表記を採用したからなんだって。こういう話は面白いですよね。 なんかいろんなところで役に立つおもしろ知識が満載でした。『戦争とデザイン』という先行書もあるようなので、それも読むつもり。 いい本でした。おすすめです。
宗教とデザイン松田行正読み終わったキリスト教、イスラム教、仏教の三つの宗教がその成立過程からどのように形や色を活用してきたかについてを包括的に扱っている本。 いろんなところで読んだ本などで得た僕にとっての既習事項が総合的な知の力によって構成されているように感じた。 物事ってこういうふうに結びつくのか〜という感じ。マレーヴィチの黒い四角形が、究極の偶像表現だ、みたいな近現代美術の切り口もしっかり入っていて素晴らしいと思った。 松岡正剛さんからの引用も多かったので、こういう学際的な領域を攻める人たちにとっての巨人はやはり松岡さんなのかもしれない。一度お会いしていろいろ聞いてみたかったです。 車のマツダあるじゃないですか、あれってアルファベットではMAZDAですけど、その表記はゾロアスター教の最高神、アフラ・マズダー(Ahura Mazdā)から来ているんだって。というのもアフラ・マズダーは光明神なのでエジソンじゃない方のイギリスのゼネラルエレクトリックカンパニーが自社の作った電球をMAZDAと命名してたので、マツダがアメリカ進出するときに、アメリカ人にも読みやすいようにその表記を採用したからなんだって。こういう話は面白いですよね。 なんかいろんなところで役に立つおもしろ知識が満載でした。『戦争とデザイン』という先行書もあるようなので、それも読むつもり。 いい本でした。おすすめです。
読み込み中...