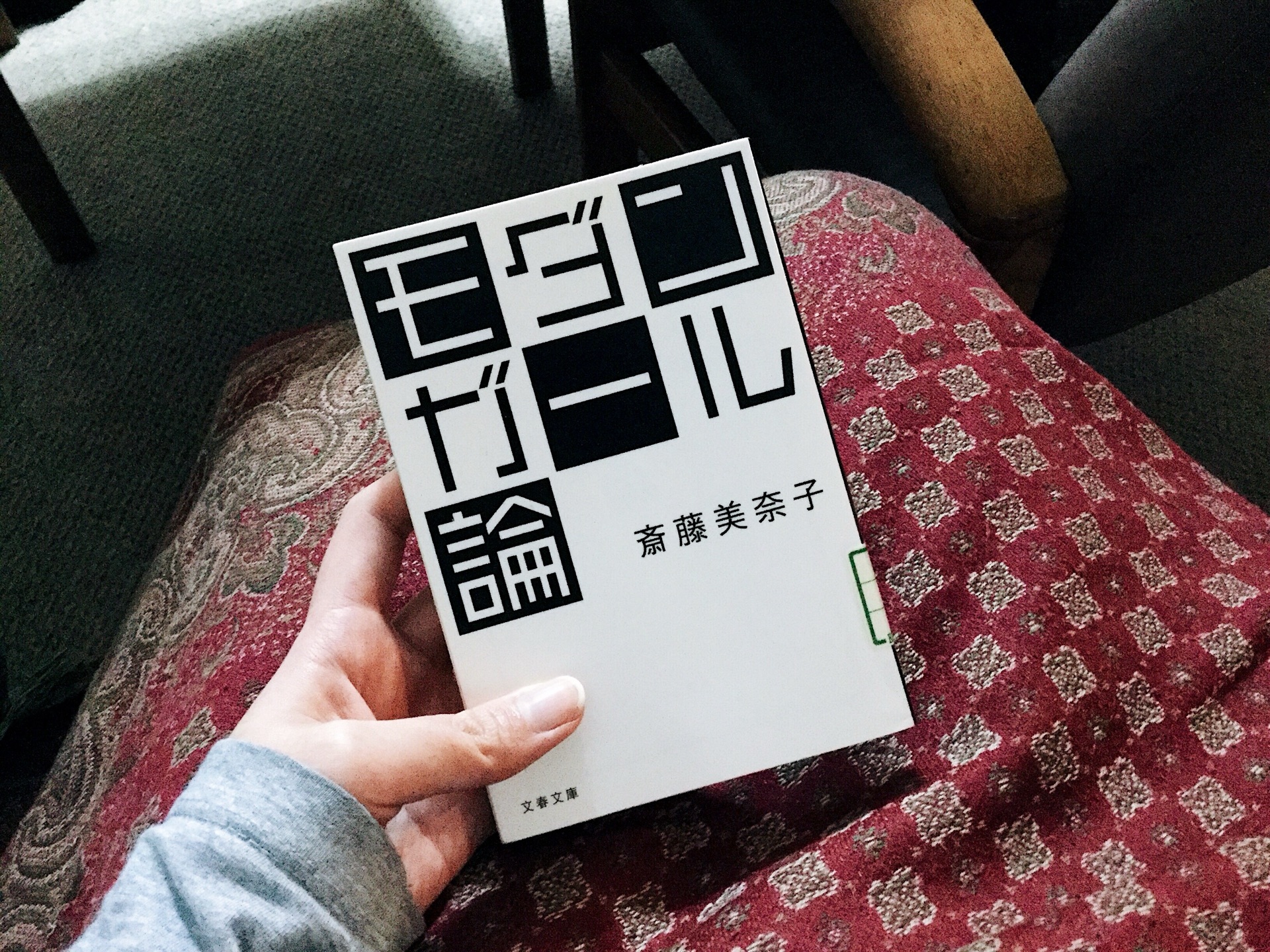モダンガール論

2件の記録
 🌜🫖@gn8tea2018年2月10日読み終わった借りてきた「戦争には「階級差別」と「性差別」という平時における二つの差別を忘れさせる効用がある。国民皆働のかけ声と物資不足からくる耐久生活は「国民みな平等」の錯覚をおこさせる。さらに「男は戦争/女は労働」の戦時政策は、「女性の社会進出→婦人解放」の幻想をいだかせる。 戦争=銃後の暮らしは女性に「出世」を疑似体験させるのだ。本土決戦にならない限り、非戦闘員である女性に戦火はおよばない。それがますます好戦的な気分を煽る。戦争中の「出世欲」をくすぐるトピックは、ほかにもこと欠かない。精動運動の指導部には市川房枝のような婦人運動のリーダーはじめ多くの女性が登用され、国政に女性が参画している高揚感があった。満州移民が推奨され、新天地の大陸で働く女性が新しい生き方として喧伝された。 働く女性の急増と主婦の社会活動の広がりは、思わぬ副産物も生みだした。「家庭と仕事の両立」という問題を、みんなが考えざるをえなくなったのである。国民皆働(勤労動員)と早婚多産(母性の強化)を並列させるもくろみは、もとより矛盾をはらんでいる。政府は苦しまぎれに「まず母の役目を優先し、余力があったら働きなさいね」てなことをいっていたが、民間の女性団体(たとえば羽仁もと子の婦人之友社や奥むめおの職業婦人社)では、家事育児の分担や社会化の問題が浮上し、共同炊事や共同保育の可能性を探る試みもはじまっていた。 だから戦争はよかったのだ、といいたいわけではもちろんない。「軍国婦人」の頭の中身は私たちと何もかわらなかった、という点がポイントなのである。 (中略) 空襲がはじまる戦争末期には、さすがにこんな浮かれた気分は一掃されたにちがいない。が、重要なのは、戦争がどんなに悲惨な結末を迎えたかじゃなく、人々がどんな気分で戦争をスタートさせたか、だ。戦争責任とはそういうことじゃないんだろうか。」
🌜🫖@gn8tea2018年2月10日読み終わった借りてきた「戦争には「階級差別」と「性差別」という平時における二つの差別を忘れさせる効用がある。国民皆働のかけ声と物資不足からくる耐久生活は「国民みな平等」の錯覚をおこさせる。さらに「男は戦争/女は労働」の戦時政策は、「女性の社会進出→婦人解放」の幻想をいだかせる。 戦争=銃後の暮らしは女性に「出世」を疑似体験させるのだ。本土決戦にならない限り、非戦闘員である女性に戦火はおよばない。それがますます好戦的な気分を煽る。戦争中の「出世欲」をくすぐるトピックは、ほかにもこと欠かない。精動運動の指導部には市川房枝のような婦人運動のリーダーはじめ多くの女性が登用され、国政に女性が参画している高揚感があった。満州移民が推奨され、新天地の大陸で働く女性が新しい生き方として喧伝された。 働く女性の急増と主婦の社会活動の広がりは、思わぬ副産物も生みだした。「家庭と仕事の両立」という問題を、みんなが考えざるをえなくなったのである。国民皆働(勤労動員)と早婚多産(母性の強化)を並列させるもくろみは、もとより矛盾をはらんでいる。政府は苦しまぎれに「まず母の役目を優先し、余力があったら働きなさいね」てなことをいっていたが、民間の女性団体(たとえば羽仁もと子の婦人之友社や奥むめおの職業婦人社)では、家事育児の分担や社会化の問題が浮上し、共同炊事や共同保育の可能性を探る試みもはじまっていた。 だから戦争はよかったのだ、といいたいわけではもちろんない。「軍国婦人」の頭の中身は私たちと何もかわらなかった、という点がポイントなのである。 (中略) 空襲がはじまる戦争末期には、さすがにこんな浮かれた気分は一掃されたにちがいない。が、重要なのは、戦争がどんなに悲惨な結末を迎えたかじゃなく、人々がどんな気分で戦争をスタートさせたか、だ。戦争責任とはそういうことじゃないんだろうか。」