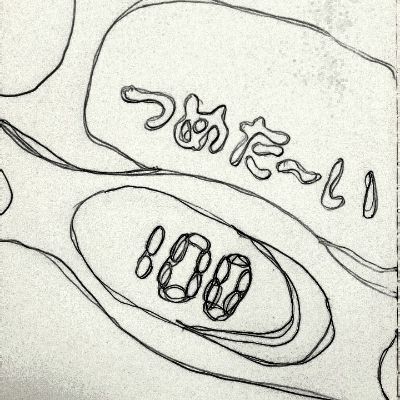世代とは何か

11件の記録
 めめん堂@memendo_tokachi2025年10月18日読み終わったものすごい本だということは確かなんだけど、詩的で暗号めいた独特なインゴルド節で人を選ぶかもしれない。自分はむしろその節回しに酔いたいタイプではあるものの、やっぱり体力が要るので、休み休み「応答し、つづけよ。」も読んでいく。現役世代概念への批判と、瓦礫に向けられる「歴史の天使」の眼差し
めめん堂@memendo_tokachi2025年10月18日読み終わったものすごい本だということは確かなんだけど、詩的で暗号めいた独特なインゴルド節で人を選ぶかもしれない。自分はむしろその節回しに酔いたいタイプではあるものの、やっぱり体力が要るので、休み休み「応答し、つづけよ。」も読んでいく。現役世代概念への批判と、瓦礫に向けられる「歴史の天使」の眼差し いっちー@icchii3172025年7月3日また読みたいちょっと読んだ返した奥野克巳さんの解説?が面白かった。1〜5章の解説は特に、難しくて何回も読みながらようやく頭に入ってくる感じ。 4章が面白そうだった。 「本章でインゴルドはまず、私たちは、現在の時点で踵を返して生を後ろ向きに歩き、そうしていなければ目の前に広がっていたはずの未来を見ないことを選んでいるという、第2章で提起した議論にいったん戻っています。この後ろ向きの視点からは、自分がどこへ向かっているのかが見えないため、私たちが思いつくどんな計画やプロジェクトも不確実性を孕んでいるように見えてしまうと言うのです。 インゴルドによれば、未来が不確実だということは、私たちの知識にはまだはめ込むべきパズルのピースが欠けている。その絵を完成させるために「科学」に目が向けられるのです。科学とは儀礼と修辞に基礎づけられた制度装置であり、その存在意義は、不確実性の穴を埋め、現役世代のうちの先駆者が自肩を持って、未来を予測できるようにすることにあるのだと言います。 しかし、インゴルドは、不確実性の穴を詰めるのではなく、そこを可能性が大波のように流れていくことが大切なのだと唱えます。その上で、可能性の領域としての未来に向き合うにはいったい何が必要なのかを問うています。 今日の若者は、生の流れを、みずからの可能性を最大限に発揮する過程であると考えています。つまりあらゆる可能な道が次第に、実際に取られるひとつの道にせばめられていく動きであると捉えているのです。」(p187-188) 世代の捉え方が未来の考え方や、科学信仰にも関係するのが興味深かったし、未来が不確実であるという考えすらも、近代化の流れの中で主流になっていったのかもしれない、というのは怖いことだ。その感覚を当たり前だと思っているから。仕事を自由に選べることが権利だと思いつつも、自分の頭の中にある生き方や働き方しか描けないし、将来の不安は尽きない。だからいろんな働き方を知ったり、本を読んだりする。求人に応募もする。 そう思うと江戸時代とか、自分の仕事が生まれつき決まっていた頃は“生を後ろ向きに”は歩いていなかっただろうし、インゴルドの世代についてのある意味で前時代的なものを取り入れてのアイデアに近いのかな。このへんもあんま読めてないから曖昧なままだ。 そういえば、小さなお店を持っているような人が一番死ぬ時に腹が据わっているって読んだっけな。逆に医者とかが死ぬ時に一番往生際が悪いみたいな。死生観も、世代の捉え方に大きく影響を受けていそうだ。 ---------------------------------------- あとは「アーカイブ」ならぬ「アナーカイブ」という概念にも初めて出会った。ほんまかいな、と思った。いかにも紛い物みたいな雰囲気をまとってるけど正式な概念らしい。アーカイブは、イメージとしては地層のようなもので、古いものほど底に眠っていく。会話をテキストにし、場を土地にし、家庭を家にし、と生を奪い過去のものにする。対してアナーカイブは、地層とは逆に、未来に向かうにつれて古いものが地上に上がってくるようなイメージ。過去の生を埋没させずに、むしろ未来になるほど新鮮に味わう。例として、マレー半島の先住民バテッは狩猟採集をしながら、生活する場である森を歩く中で亡くなった人を生の記憶のまま呼び起こす。「憧れる」という感覚になるそうだ。 「場所が亡くなった人の記憶を呼び起こす場合、バテッの人々はこみあげる感情を指す「憧れる」という言葉を使います。 バテッにとって、生の道に沿って旅することは、以前に去ってしまった人々を覚えていることです。下草の中に消えようとしている先人たちの小道は今や地面と同化しつつあるように見えるのですが、注意を払えば、先人たちの後を追うことができます。 バテッの人たちは、憧れるのです。憧れることは、なじむことでもあります。人々は古老たちの導きに従って、古老たちになじんでいく。バテッにとって到来することは、なることです。 到来することと憧れることは、長い道のりを行くことと覚えていることであって、それらは同じ根源的な動きの表と裏なのです。バテッは、到来しながら憧れ、長い道のりを行きながら覚えているのです。」(p185) これを読んで、森には例えばその人が育てた木とかが育っていった時にそういう感覚になりえるかもな、と思った。森という生活空間自体が生そのものだし、どんどん変化している。対して今私を取り巻く世界は、例えばインターネット空間はテキストを打った瞬間から過去になっていくし、働くのも給料をもらうためで、額面を見る生活。古老のした仕事の上で生活はしているけど、それを感じる機会はとても少ない。ましてや顔の見える人の仕事は、自分の父親であってもあまり知らない。 とか書いてると田舎で暮らしたくなってくる。影響されやすい。笑 日本でも古語の「あくがる」のように、過去と現在?の時制両方に対して同じ感覚を扱う表現があったらしい。それが失われてしまったということらしい。憧れるという感覚は、自分では手に入れられない何かに対して羨む感覚に近いと思っていたからそれが“なじむ”や“なる”に近いというのは不思議だけど、でもなんだか豊かな感じがする。 ------------------------------ 4章をインゴルドの文章を読むためにもう一回借りようと思う。
いっちー@icchii3172025年7月3日また読みたいちょっと読んだ返した奥野克巳さんの解説?が面白かった。1〜5章の解説は特に、難しくて何回も読みながらようやく頭に入ってくる感じ。 4章が面白そうだった。 「本章でインゴルドはまず、私たちは、現在の時点で踵を返して生を後ろ向きに歩き、そうしていなければ目の前に広がっていたはずの未来を見ないことを選んでいるという、第2章で提起した議論にいったん戻っています。この後ろ向きの視点からは、自分がどこへ向かっているのかが見えないため、私たちが思いつくどんな計画やプロジェクトも不確実性を孕んでいるように見えてしまうと言うのです。 インゴルドによれば、未来が不確実だということは、私たちの知識にはまだはめ込むべきパズルのピースが欠けている。その絵を完成させるために「科学」に目が向けられるのです。科学とは儀礼と修辞に基礎づけられた制度装置であり、その存在意義は、不確実性の穴を埋め、現役世代のうちの先駆者が自肩を持って、未来を予測できるようにすることにあるのだと言います。 しかし、インゴルドは、不確実性の穴を詰めるのではなく、そこを可能性が大波のように流れていくことが大切なのだと唱えます。その上で、可能性の領域としての未来に向き合うにはいったい何が必要なのかを問うています。 今日の若者は、生の流れを、みずからの可能性を最大限に発揮する過程であると考えています。つまりあらゆる可能な道が次第に、実際に取られるひとつの道にせばめられていく動きであると捉えているのです。」(p187-188) 世代の捉え方が未来の考え方や、科学信仰にも関係するのが興味深かったし、未来が不確実であるという考えすらも、近代化の流れの中で主流になっていったのかもしれない、というのは怖いことだ。その感覚を当たり前だと思っているから。仕事を自由に選べることが権利だと思いつつも、自分の頭の中にある生き方や働き方しか描けないし、将来の不安は尽きない。だからいろんな働き方を知ったり、本を読んだりする。求人に応募もする。 そう思うと江戸時代とか、自分の仕事が生まれつき決まっていた頃は“生を後ろ向きに”は歩いていなかっただろうし、インゴルドの世代についてのある意味で前時代的なものを取り入れてのアイデアに近いのかな。このへんもあんま読めてないから曖昧なままだ。 そういえば、小さなお店を持っているような人が一番死ぬ時に腹が据わっているって読んだっけな。逆に医者とかが死ぬ時に一番往生際が悪いみたいな。死生観も、世代の捉え方に大きく影響を受けていそうだ。 ---------------------------------------- あとは「アーカイブ」ならぬ「アナーカイブ」という概念にも初めて出会った。ほんまかいな、と思った。いかにも紛い物みたいな雰囲気をまとってるけど正式な概念らしい。アーカイブは、イメージとしては地層のようなもので、古いものほど底に眠っていく。会話をテキストにし、場を土地にし、家庭を家にし、と生を奪い過去のものにする。対してアナーカイブは、地層とは逆に、未来に向かうにつれて古いものが地上に上がってくるようなイメージ。過去の生を埋没させずに、むしろ未来になるほど新鮮に味わう。例として、マレー半島の先住民バテッは狩猟採集をしながら、生活する場である森を歩く中で亡くなった人を生の記憶のまま呼び起こす。「憧れる」という感覚になるそうだ。 「場所が亡くなった人の記憶を呼び起こす場合、バテッの人々はこみあげる感情を指す「憧れる」という言葉を使います。 バテッにとって、生の道に沿って旅することは、以前に去ってしまった人々を覚えていることです。下草の中に消えようとしている先人たちの小道は今や地面と同化しつつあるように見えるのですが、注意を払えば、先人たちの後を追うことができます。 バテッの人たちは、憧れるのです。憧れることは、なじむことでもあります。人々は古老たちの導きに従って、古老たちになじんでいく。バテッにとって到来することは、なることです。 到来することと憧れることは、長い道のりを行くことと覚えていることであって、それらは同じ根源的な動きの表と裏なのです。バテッは、到来しながら憧れ、長い道のりを行きながら覚えているのです。」(p185) これを読んで、森には例えばその人が育てた木とかが育っていった時にそういう感覚になりえるかもな、と思った。森という生活空間自体が生そのものだし、どんどん変化している。対して今私を取り巻く世界は、例えばインターネット空間はテキストを打った瞬間から過去になっていくし、働くのも給料をもらうためで、額面を見る生活。古老のした仕事の上で生活はしているけど、それを感じる機会はとても少ない。ましてや顔の見える人の仕事は、自分の父親であってもあまり知らない。 とか書いてると田舎で暮らしたくなってくる。影響されやすい。笑 日本でも古語の「あくがる」のように、過去と現在?の時制両方に対して同じ感覚を扱う表現があったらしい。それが失われてしまったということらしい。憧れるという感覚は、自分では手に入れられない何かに対して羨む感覚に近いと思っていたからそれが“なじむ”や“なる”に近いというのは不思議だけど、でもなんだか豊かな感じがする。 ------------------------------ 4章をインゴルドの文章を読むためにもう一回借りようと思う。 いっちー@icchii3172025年7月1日図書館で借りた図書館で借りてきたけどもう期限が来て慌てて手に取る。 「解説に代えて」という50ページほどもある奥野克巳さんの文章がリッチで良い。 …やっぱり明日返す直前に読む。
いっちー@icchii3172025年7月1日図書館で借りた図書館で借りてきたけどもう期限が来て慌てて手に取る。 「解説に代えて」という50ページほどもある奥野克巳さんの文章がリッチで良い。 …やっぱり明日返す直前に読む。