
いっちー
@icchii317
本の読める店fuzkueのファンです。シェアハウス歴10年。さいきん1人で住み始めてから家でも本が読めるようになってきました。
- 2026年2月26日
 スナック墓場嶋津輝7分の3読了借りてきた短編集というだけでハードルが低くなって、結局読み終わっちゃう現象に名前をつけたい。 ミーハーなので直木賞のニュースで知った作家さん。しかもこれまたミーハーなので41歳から小説を書き始めたというのが希望だなと思って確か借りれる本を探したのだった。 「ラインのふたり」、表題作「スナック墓場」、そして「一等賞」読了。 背表紙の裏にラインのふたりと一等賞が注目されてると書いてあったのを、「スナック墓場」を読んだ後に見つけた。 「ラインのふたり」と「スナック墓場」はなんだか不思議な読後感だった。終わり方がなんだか不思議で、期待をわざとずらしてくるというか、でもなんとなくほっこりというか。それに対して「一等賞」はすごかった。短篇ベストコレクション2019に選ばれたらしい。主人公が子供だった頃の世界の捉え方の描き方も見事だし、何よりそんなことよく思いつくなっていう設定だし、笑える。これは選ばれるくらいだから、終わり方も他と違って?綺麗。結構心が温かくなって、いい作品に出会えたな〜という感想。
スナック墓場嶋津輝7分の3読了借りてきた短編集というだけでハードルが低くなって、結局読み終わっちゃう現象に名前をつけたい。 ミーハーなので直木賞のニュースで知った作家さん。しかもこれまたミーハーなので41歳から小説を書き始めたというのが希望だなと思って確か借りれる本を探したのだった。 「ラインのふたり」、表題作「スナック墓場」、そして「一等賞」読了。 背表紙の裏にラインのふたりと一等賞が注目されてると書いてあったのを、「スナック墓場」を読んだ後に見つけた。 「ラインのふたり」と「スナック墓場」はなんだか不思議な読後感だった。終わり方がなんだか不思議で、期待をわざとずらしてくるというか、でもなんとなくほっこりというか。それに対して「一等賞」はすごかった。短篇ベストコレクション2019に選ばれたらしい。主人公が子供だった頃の世界の捉え方の描き方も見事だし、何よりそんなことよく思いつくなっていう設定だし、笑える。これは選ばれるくらいだから、終わり方も他と違って?綺麗。結構心が温かくなって、いい作品に出会えたな〜という感想。 - 2026年2月25日
 働くということ 「能力主義」を超えて勅使川原真衣借りてきた読書会候補本うーん。読書会候補本ではあったけどこれは違うかな。働いている人で、能力主義に違和感がある人にとってはよくぞ言ってくれた!みたいな感じだと思うけど、あまりに著者の主張的、というか。そもそも私はあんまりちゃんと会社で働いた経験もないから、そうだよね、みたいな話だった。 多分、読書会に向いているのは主張的ではなくて、むしろ事実を淡々と書いているような本な気がする。事実の描き方はルポのようなラフなものでもいいし(ただしその場合はなるべく未知のものの方がよい)、研究成果としてデータを書いているものでも良い。要は、新しい考え方を持つきっかけになるようなもの。私のやってる読書会はそういう意図だからという前提ですが。
働くということ 「能力主義」を超えて勅使川原真衣借りてきた読書会候補本うーん。読書会候補本ではあったけどこれは違うかな。働いている人で、能力主義に違和感がある人にとってはよくぞ言ってくれた!みたいな感じだと思うけど、あまりに著者の主張的、というか。そもそも私はあんまりちゃんと会社で働いた経験もないから、そうだよね、みたいな話だった。 多分、読書会に向いているのは主張的ではなくて、むしろ事実を淡々と書いているような本な気がする。事実の描き方はルポのようなラフなものでもいいし(ただしその場合はなるべく未知のものの方がよい)、研究成果としてデータを書いているものでも良い。要は、新しい考え方を持つきっかけになるようなもの。私のやってる読書会はそういう意図だからという前提ですが。 - 2026年2月24日
 欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里『格差の“格”ってなんですか?』にも出てきたオープンダイアログを、こっちでは批判している。 「自分の無意識に向き合うというよりは、無意識を拡散させ、霧散させる」「古典的な精神分析の立場から言えば、それは、自分の無意識と向き合っていないわけです。オープンダイアローグは、まさにSNS時代の、なんでもシェアするという状況た対応しているパラダイムだと僕は思います。」p268
欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里『格差の“格”ってなんですか?』にも出てきたオープンダイアログを、こっちでは批判している。 「自分の無意識に向き合うというよりは、無意識を拡散させ、霧散させる」「古典的な精神分析の立場から言えば、それは、自分の無意識と向き合っていないわけです。オープンダイアローグは、まさにSNS時代の、なんでもシェアするという状況た対応しているパラダイムだと僕は思います。」p268 - 2026年2月24日
 欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里p263にあった千葉さんのツイート。自覚がありすぎてつらい。あの子は、まさに「他の制度の中で主体化している人」であり、「自分の主体化の正当性を脅かされるような気になり、過度に攻撃的な態度をとること」まではないにしても、ジェラシーのような他になかなか抱かない感情が出てくる。仲がよくて、その人のキラキラした部分だけでないところも見ていても、そういう感情がたまにある。なるほどな。メタに見れば良い。世界99のことも思い出す。メタしすぎはそれはそれでデイズトピアのような気もするけど、あれは描き方の問題もあるのと、あとあの主人公は肝心の主体がなかったから、ディストピアのようになっていた。自分の身体性が今回の話の要だからな。 https://x.com/masayachiba/status/1049676932827103235?s=46&t=pJldM2CASAMBJLeo4bR5sg
欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里p263にあった千葉さんのツイート。自覚がありすぎてつらい。あの子は、まさに「他の制度の中で主体化している人」であり、「自分の主体化の正当性を脅かされるような気になり、過度に攻撃的な態度をとること」まではないにしても、ジェラシーのような他になかなか抱かない感情が出てくる。仲がよくて、その人のキラキラした部分だけでないところも見ていても、そういう感情がたまにある。なるほどな。メタに見れば良い。世界99のことも思い出す。メタしすぎはそれはそれでデイズトピアのような気もするけど、あれは描き方の問題もあるのと、あとあの主人公は肝心の主体がなかったから、ディストピアのようになっていた。自分の身体性が今回の話の要だからな。 https://x.com/masayachiba/status/1049676932827103235?s=46&t=pJldM2CASAMBJLeo4bR5sg - 2026年2月24日
 欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里明日返すちらっと読んだ最初にこれを図書館で借りて、あとから単行本を借りたら、文庫には増補版があるだけであとは内容が同じだということを理解して、増補版から読んだ。ら、あんまり内容が入ってこなかったので、単行本も目次を見ながら興味ありそうなところだけさらっと目を通してみたけど、同じくあんまり入ってこなかった。多分内容が想像より観念的でふわふわしているように思えたのと、あとは興味の移ろいが早くて既に自分のドーパミンがあんまり出なくなってしまったのと、今生理前で集中して読むというよりは、パンチラインがないと文字が入ってこない精神状態だから。 ただ最後のほうに自分にとってのパンチラインあった。読書会が終わって恋愛の好奇心が早々に薄れた代わりに、最近の自分のテーマである身体性に惹かれて。 「(千葉)#MeTooは、交換の論理なんですよ。言い換えれば、グローバル資本主義の論理であり、ドゥルーズ+ガタリの言葉を使えば「脱コード化」だということになる。コード化された傷つきが蔓延することによって、古い意味での非対照的で個人的でプライベートな傷と言うものがなくなっていく。それが前回話した身体の喪失ということですね。 (柴田)、自分のガワがないんですよね。境界線となる皮膚みたいなものがないから、#MeToo でみんなつながってしまう。皮膚や境界線があったら、「理解はできるけど、私とは違うな」と、同感はできるけど共感にはならないんですよね。SNS的な共感のつながりって、もう自他の認知がぐちゃぐちゃで、「私は子供の時にレイプされました」と言う人がいただけで、それを聞いた人は子供の時にレイプされていないにもかかわらず、「この傷は私のものでもある」となってしまう。事故の境界がなくて、もうスライムみたいに溶け出している。私は、「もうちょっと自分に引きこもれよ」と思います。 (中略) (千葉)個体が別々であると言うことが僕は重要だと思うんですが、最近の風潮ではそうではなく、何でもかんでもケアの関係で結びつけていこうとする。その中で、エロティシズムが失われていく。なぜなら、エロティシズムと言うのは、一定の防御壁を持っているものの間で展開される、ある種の暴力のドラマだからです。」(p261-263) ケアが流行ってる理由がこうして指摘されてて震えた。自他境界がはっきりしていない、身体性がないからこそ、必要以上に共感してしまっている人が増えているのではないか。それには弱さや、SNSの世界のような恐ろしさもあるはずなのに、ケアという聞き心地のよい言葉でくるみとられてしまっているのではないか。もっと危機感を持った方が良いかもしれない。かく言う自分も、頭でっかちで身体性があまりなく、坂口恭平氏の言うところの「躁鬱人」に相対的には近い。それはやはり少し危険なことな気がする。一方で、人よりも自他境界ははっきりしているとも言われる。もしくは、人との距離が少し遠い。それは両立するのだろうか。いずれにしても、前にシェアハウスに住んでたときはだいぶ「ケア」という言葉に凝っていたけど、でもその時は結局ケアについてなんにもつかめなかった。なのでこういう方向からケアを見通してくれるのはとてもありがたい。
欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里明日返すちらっと読んだ最初にこれを図書館で借りて、あとから単行本を借りたら、文庫には増補版があるだけであとは内容が同じだということを理解して、増補版から読んだ。ら、あんまり内容が入ってこなかったので、単行本も目次を見ながら興味ありそうなところだけさらっと目を通してみたけど、同じくあんまり入ってこなかった。多分内容が想像より観念的でふわふわしているように思えたのと、あとは興味の移ろいが早くて既に自分のドーパミンがあんまり出なくなってしまったのと、今生理前で集中して読むというよりは、パンチラインがないと文字が入ってこない精神状態だから。 ただ最後のほうに自分にとってのパンチラインあった。読書会が終わって恋愛の好奇心が早々に薄れた代わりに、最近の自分のテーマである身体性に惹かれて。 「(千葉)#MeTooは、交換の論理なんですよ。言い換えれば、グローバル資本主義の論理であり、ドゥルーズ+ガタリの言葉を使えば「脱コード化」だということになる。コード化された傷つきが蔓延することによって、古い意味での非対照的で個人的でプライベートな傷と言うものがなくなっていく。それが前回話した身体の喪失ということですね。 (柴田)、自分のガワがないんですよね。境界線となる皮膚みたいなものがないから、#MeToo でみんなつながってしまう。皮膚や境界線があったら、「理解はできるけど、私とは違うな」と、同感はできるけど共感にはならないんですよね。SNS的な共感のつながりって、もう自他の認知がぐちゃぐちゃで、「私は子供の時にレイプされました」と言う人がいただけで、それを聞いた人は子供の時にレイプされていないにもかかわらず、「この傷は私のものでもある」となってしまう。事故の境界がなくて、もうスライムみたいに溶け出している。私は、「もうちょっと自分に引きこもれよ」と思います。 (中略) (千葉)個体が別々であると言うことが僕は重要だと思うんですが、最近の風潮ではそうではなく、何でもかんでもケアの関係で結びつけていこうとする。その中で、エロティシズムが失われていく。なぜなら、エロティシズムと言うのは、一定の防御壁を持っているものの間で展開される、ある種の暴力のドラマだからです。」(p261-263) ケアが流行ってる理由がこうして指摘されてて震えた。自他境界がはっきりしていない、身体性がないからこそ、必要以上に共感してしまっている人が増えているのではないか。それには弱さや、SNSの世界のような恐ろしさもあるはずなのに、ケアという聞き心地のよい言葉でくるみとられてしまっているのではないか。もっと危機感を持った方が良いかもしれない。かく言う自分も、頭でっかちで身体性があまりなく、坂口恭平氏の言うところの「躁鬱人」に相対的には近い。それはやはり少し危険なことな気がする。一方で、人よりも自他境界ははっきりしているとも言われる。もしくは、人との距離が少し遠い。それは両立するのだろうか。いずれにしても、前にシェアハウスに住んでたときはだいぶ「ケア」という言葉に凝っていたけど、でもその時は結局ケアについてなんにもつかめなかった。なのでこういう方向からケアを見通してくれるのはとてもありがたい。 - 2026年2月17日
 借りてきた読み始めた自分もちょうどこれから引越しなのと、一応まだシェアハウス暮らしなので家具をほとんど持ってなくて、そしてシェアハウス暮らしは生活改善運動とは真逆の世界線なので、数ページ読んだだけでも面白かった。カルチャーショックかも。私も、部屋に対して自我がなかった。(シェアハウスの、しかも相部屋では、自我を持とうとしたら発狂すると思う)頑張って、自我を持って、自分にとって好きだと思えるものを選んでいこうと思った。家電は人からもらうけど、家具は自分で選ぼう。いやー、だから、それこそ、お金がないのを言い訳に、自我を持つのを後回しにしてただけなのかもしれない。もらいもので生きてた。でも、自分の好きなものには、そのために頑張って稼ぐのに値する価値があるってことか。まじで、少しずつカルチャーショックがある。 あとは、家はかなりいい場所を見つけてて、庭付きで、眺めがまあまあ良くて(畑とかが見える)というのを共感した。でも駅からの距離とか、今までまあまあこだわってたけど、それは家から駅までの間をただの無駄な時間として捉えてたからだな、と思った。もっと豊かな時間として捉えれば良いのか。 あと住む街の決め方、この人は幸運だ。そんなふうに(作家として)、活動的な本屋さんと関わることって、二足の草鞋?で活動してないとできないことなので、羨ましい。妙蓮寺、行ったことあるけど確かにこじんまりしたいい街。
借りてきた読み始めた自分もちょうどこれから引越しなのと、一応まだシェアハウス暮らしなので家具をほとんど持ってなくて、そしてシェアハウス暮らしは生活改善運動とは真逆の世界線なので、数ページ読んだだけでも面白かった。カルチャーショックかも。私も、部屋に対して自我がなかった。(シェアハウスの、しかも相部屋では、自我を持とうとしたら発狂すると思う)頑張って、自我を持って、自分にとって好きだと思えるものを選んでいこうと思った。家電は人からもらうけど、家具は自分で選ぼう。いやー、だから、それこそ、お金がないのを言い訳に、自我を持つのを後回しにしてただけなのかもしれない。もらいもので生きてた。でも、自分の好きなものには、そのために頑張って稼ぐのに値する価値があるってことか。まじで、少しずつカルチャーショックがある。 あとは、家はかなりいい場所を見つけてて、庭付きで、眺めがまあまあ良くて(畑とかが見える)というのを共感した。でも駅からの距離とか、今までまあまあこだわってたけど、それは家から駅までの間をただの無駄な時間として捉えてたからだな、と思った。もっと豊かな時間として捉えれば良いのか。 あと住む街の決め方、この人は幸運だ。そんなふうに(作家として)、活動的な本屋さんと関わることって、二足の草鞋?で活動してないとできないことなので、羨ましい。妙蓮寺、行ったことあるけど確かにこじんまりしたいい街。 - 2026年2月17日
- 2026年2月16日
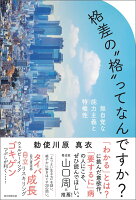 格差の“格”ってなんですか?勅使川原真衣読み終わった後半、面白かった。14章「本当に困っている人-絶望選手権と化す裏の顔」に、「「限られた原資」という問題設定が案外すでに〈「助け合わない」ことへのもっともらしい理屈〉になってしまっているのではないか?」(p152)とあって痺れた。そうかもしれない。そして「助け合い」の一歩は「かけ合う」ことなのだとも。 15章で、オープンダイアログとは権力勾配に加え、情報格差も排除したうえで行われる手法と書いてあってめっちゃ分かりやすかった。逆に、権力差を放置したまま「忌憚なき」対話を求めるのはかなり危うい、緊張感のある場になる。対話は時間差があってもいい。「対話」に隠れた特権性という話を読んで、ゆる言語学ラジオで紹介されていた「論理的基盤の文化的構造」(だったっけな、うろ覚え)を読もうと思った。日本の企業の文化における「対話」でしかないと思う。 就活についてぶった斬ってる章は前半にもあったけど、16章で「必要な問いは、「誰と誰、誰と何を組み合わせると、スゴい景色を皆で見ることができそうか?」だ。」(p176)とあってなるほど確かにとなった。社員の凹凸に合わせて、求める人材を見極めたいところ。ただ、やっぱりそういうのも含めてオールマイティな人が重宝しちゃう世界線になるのは分かる。 17章、ウェルビーイングをぶった斬ってくれてて気持ちがいい。笑 18章、勅使川原さんの本を2冊読んだインタビュアーが「これから必要なのは赦し、寛容な心だと思うのですが…」は地獄すぎた。その枠から外れよ!!!そのインタビュアーが、本当に分かってくれるよう願う。
格差の“格”ってなんですか?勅使川原真衣読み終わった後半、面白かった。14章「本当に困っている人-絶望選手権と化す裏の顔」に、「「限られた原資」という問題設定が案外すでに〈「助け合わない」ことへのもっともらしい理屈〉になってしまっているのではないか?」(p152)とあって痺れた。そうかもしれない。そして「助け合い」の一歩は「かけ合う」ことなのだとも。 15章で、オープンダイアログとは権力勾配に加え、情報格差も排除したうえで行われる手法と書いてあってめっちゃ分かりやすかった。逆に、権力差を放置したまま「忌憚なき」対話を求めるのはかなり危うい、緊張感のある場になる。対話は時間差があってもいい。「対話」に隠れた特権性という話を読んで、ゆる言語学ラジオで紹介されていた「論理的基盤の文化的構造」(だったっけな、うろ覚え)を読もうと思った。日本の企業の文化における「対話」でしかないと思う。 就活についてぶった斬ってる章は前半にもあったけど、16章で「必要な問いは、「誰と誰、誰と何を組み合わせると、スゴい景色を皆で見ることができそうか?」だ。」(p176)とあってなるほど確かにとなった。社員の凹凸に合わせて、求める人材を見極めたいところ。ただ、やっぱりそういうのも含めてオールマイティな人が重宝しちゃう世界線になるのは分かる。 17章、ウェルビーイングをぶった斬ってくれてて気持ちがいい。笑 18章、勅使川原さんの本を2冊読んだインタビュアーが「これから必要なのは赦し、寛容な心だと思うのですが…」は地獄すぎた。その枠から外れよ!!!そのインタビュアーが、本当に分かってくれるよう願う。 - 2026年2月15日
 借りてきたちらっと読んだ最近は、1人で生活してるし、そんなに働いてもないから、だいぶ休めていて、苦手な朝も早起きしなくていい生活をしてるから、自己否定をすることはほとんどない。でも、なんでだが借りてきた。久々に坂口節を読みたくなったときに、最新刊なのにたまたま予約数が少なかったから借りてきたんだな、きっと。 目次をパラパラ見てみて、「元気なときの自己否定」というタイトルが気になってちらっと読んでみた。「もっとできる」は確かに自己否定、正確に言うと今の自分の否定に違いない。 あの坂口さんも、成長という病にかかっていたんだな。というか、他の思想が独特であんまり気付いてなかったけど誰よりも成長主義で、貯蓄主義というか、自分の手一つで生きていく、みたいな気概がすごかったよな、確かに。鬱になってもただじゃ起き上がらないみたいな、鬱になりながらも書いたり、料理したり、自分の人生を丸ごと全て作品にしてしまうような芸当は坂口さんくらいしかできないけど、きっとそれは苦しいことでもあっただろう。そういう意味で、ある種の危うさがあった。「絵を毎日描くと決めてたけど、やりたくない日は描かないことも増えた」、みたいなところを読んでなんだかほっとした。坂口さんがそういうことを選べるようになって良かった。
借りてきたちらっと読んだ最近は、1人で生活してるし、そんなに働いてもないから、だいぶ休めていて、苦手な朝も早起きしなくていい生活をしてるから、自己否定をすることはほとんどない。でも、なんでだが借りてきた。久々に坂口節を読みたくなったときに、最新刊なのにたまたま予約数が少なかったから借りてきたんだな、きっと。 目次をパラパラ見てみて、「元気なときの自己否定」というタイトルが気になってちらっと読んでみた。「もっとできる」は確かに自己否定、正確に言うと今の自分の否定に違いない。 あの坂口さんも、成長という病にかかっていたんだな。というか、他の思想が独特であんまり気付いてなかったけど誰よりも成長主義で、貯蓄主義というか、自分の手一つで生きていく、みたいな気概がすごかったよな、確かに。鬱になってもただじゃ起き上がらないみたいな、鬱になりながらも書いたり、料理したり、自分の人生を丸ごと全て作品にしてしまうような芸当は坂口さんくらいしかできないけど、きっとそれは苦しいことでもあっただろう。そういう意味で、ある種の危うさがあった。「絵を毎日描くと決めてたけど、やりたくない日は描かないことも増えた」、みたいなところを読んでなんだかほっとした。坂口さんがそういうことを選べるようになって良かった。 - 2026年2月15日
- 2026年2月15日
 生命式村田沙耶香読み終わった返した
生命式村田沙耶香読み終わった返した - 2026年2月15日
 ゼロから12ヵ国語マスターした私の最強の外国語習得法Kazu Languages借りてきた読み終わった良き。とりあえず英語、という発想は、無自覚に成長という圧力に飲み込まれていたのではと思わされる。いや、英語も楽しいし、高校までの貯金もあるからとっかかりやすいし、英語が初めての外国人とのコミュニケーションツールとして機能したときに楽しいと思えたからなんだけど。でも、ほんと、他の言語を学んでみたいと思えた。 とりあえず、デュオリンゴで一日5分でも触れておくのはいいなと思えた。むしろ、英語で第三外国語を学んでみようかな。一石二鳥と言うし。
ゼロから12ヵ国語マスターした私の最強の外国語習得法Kazu Languages借りてきた読み終わった良き。とりあえず英語、という発想は、無自覚に成長という圧力に飲み込まれていたのではと思わされる。いや、英語も楽しいし、高校までの貯金もあるからとっかかりやすいし、英語が初めての外国人とのコミュニケーションツールとして機能したときに楽しいと思えたからなんだけど。でも、ほんと、他の言語を学んでみたいと思えた。 とりあえず、デュオリンゴで一日5分でも触れておくのはいいなと思えた。むしろ、英語で第三外国語を学んでみようかな。一石二鳥と言うし。 - 2026年2月14日
- 2026年2月14日
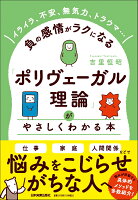 借りてきた読み終わったこちらの方がいくらか簡単だった。赤青緑、という概念が導入されるだけで、それこそハウツー本からの脱却や、白黒思考からの脱却、毒親からの脱却も?可能性が無限にある。逆に自責などの思考の癖も。意識ではなく無意識の反応にも触れられてて、原始反射へのアプローチとか。 「体力がない」ってよく言うけど、これは多分迷走神経の働きの話であって、エネルギー量の話ではないと思った。(もちろん、食事のエネルギーが足りてなかったら低血糖になってそれが赤を引き起こし、青になるという流れは想像できるけど。)単純に緑の神経が育ってなくて、青になってしまうということを「体力がない」と表現することが多そう。イコール、安全基地が増えれば体力も増える可能性があるということ。 あと今日本では子どもの数よりペットの数の方が多い(猫に限った話だったかな、忘れた)というけれど、それも緑を買ってるんだな笑 もちろん子どもでも緑になれるはず。 あとは夏になるとほんとに動けなくなってしまう友人は、真っ青になってしまってると理解できた。それがわかれば、アプローチのしがいがある。あと、青になると自責してしまうとも書いてあった。厄介だ。本人がそのことに気づければ希望がある。
借りてきた読み終わったこちらの方がいくらか簡単だった。赤青緑、という概念が導入されるだけで、それこそハウツー本からの脱却や、白黒思考からの脱却、毒親からの脱却も?可能性が無限にある。逆に自責などの思考の癖も。意識ではなく無意識の反応にも触れられてて、原始反射へのアプローチとか。 「体力がない」ってよく言うけど、これは多分迷走神経の働きの話であって、エネルギー量の話ではないと思った。(もちろん、食事のエネルギーが足りてなかったら低血糖になってそれが赤を引き起こし、青になるという流れは想像できるけど。)単純に緑の神経が育ってなくて、青になってしまうということを「体力がない」と表現することが多そう。イコール、安全基地が増えれば体力も増える可能性があるということ。 あと今日本では子どもの数よりペットの数の方が多い(猫に限った話だったかな、忘れた)というけれど、それも緑を買ってるんだな笑 もちろん子どもでも緑になれるはず。 あとは夏になるとほんとに動けなくなってしまう友人は、真っ青になってしまってると理解できた。それがわかれば、アプローチのしがいがある。あと、青になると自責してしまうとも書いてあった。厄介だ。本人がそのことに気づければ希望がある。 - 2026年2月14日
 生命式村田沙耶香借りてきた読んでる5/12読了。世界99を読んだあとに読むと、世界99がいかに多様なテーマを扱っているかわかるな。 「素晴らしい食卓」は、さながら星新一の読後感だった。すごいなぁ、小説家は。こういうショートショートが書けるようになったらさぞ楽しそうだ。村田さん、こういうのもいけるんだなぁ。
生命式村田沙耶香借りてきた読んでる5/12読了。世界99を読んだあとに読むと、世界99がいかに多様なテーマを扱っているかわかるな。 「素晴らしい食卓」は、さながら星新一の読後感だった。すごいなぁ、小説家は。こういうショートショートが書けるようになったらさぞ楽しそうだ。村田さん、こういうのもいけるんだなぁ。 - 2026年2月12日
- 2026年2月10日
 借りてきた読んでる図書館で予約待ちしただけあって分かりやすい。 ・心と体が良い状態で機能するには、交感神経と副交感神経がどちらも高いレベルで働いていることが重要。活動的なときには交感神経がやや優位、リラックスしているときには、副交感神経がやや良いと言うように、微妙なバランスで保たれる必要がある ・血管そのものにもポンプのような働きがあり、交感神経が優位になると収縮し、副交感神経が優位の時は拡張する。バランスが乱れると血液の流れが淀んでしまい、心臓の負担も大きくなる →脳や内臓にまでダメージが及ぶ。(眠れない、疲れが取れない、頭が痛い、便秘、気分が沈むなど!) ・低気圧の時は、交感神経と副交感神経の働きが低下したり、ストレスは交感神経のスイッチをオンにする。自律神経は常に乱れるものと思っておいた方が良い。 ・迷走神経は、内臓の状態を脳に伝えて、脳からの指令を内蔵に届ける直通回線(体のなかを突き抜ける高速道路のイメージ)であり、副交感神経を支配する力を持っている。 →迷走神経をしっかり働かせることで、過剰に高ぶっている交感神経が抑えられ、自律神経のバランスの均衡が保たれる
借りてきた読んでる図書館で予約待ちしただけあって分かりやすい。 ・心と体が良い状態で機能するには、交感神経と副交感神経がどちらも高いレベルで働いていることが重要。活動的なときには交感神経がやや優位、リラックスしているときには、副交感神経がやや良いと言うように、微妙なバランスで保たれる必要がある ・血管そのものにもポンプのような働きがあり、交感神経が優位になると収縮し、副交感神経が優位の時は拡張する。バランスが乱れると血液の流れが淀んでしまい、心臓の負担も大きくなる →脳や内臓にまでダメージが及ぶ。(眠れない、疲れが取れない、頭が痛い、便秘、気分が沈むなど!) ・低気圧の時は、交感神経と副交感神経の働きが低下したり、ストレスは交感神経のスイッチをオンにする。自律神経は常に乱れるものと思っておいた方が良い。 ・迷走神経は、内臓の状態を脳に伝えて、脳からの指令を内蔵に届ける直通回線(体のなかを突き抜ける高速道路のイメージ)であり、副交感神経を支配する力を持っている。 →迷走神経をしっかり働かせることで、過剰に高ぶっている交感神経が抑えられ、自律神経のバランスの均衡が保たれる - 2026年2月10日
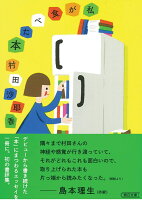 私が食べた本村田沙耶香借りてきた読んでる「もう1人の自分との日常」という章が面白い。小説を書くのがとても好きでも、目を離すとサボってゴロゴロして自分の世界に閉じこもってしまう。締め切りがあると捗る。そのためにコンビニでバイトをする。→自由業の経験がある人はバイトの締め切り効果(始まりと終わりの時間が決まっていること)がとってもありがたいの、分かると思う。 自分にとって一番早い朝は2時。一時は徹夜という感覚 まじで、何かを作り出せる人や、自分で自分を楽しませられる人は尊敬する。私は友達と会って話すか、よくて読書会。空想癖なんてないから仕方ない笑
私が食べた本村田沙耶香借りてきた読んでる「もう1人の自分との日常」という章が面白い。小説を書くのがとても好きでも、目を離すとサボってゴロゴロして自分の世界に閉じこもってしまう。締め切りがあると捗る。そのためにコンビニでバイトをする。→自由業の経験がある人はバイトの締め切り効果(始まりと終わりの時間が決まっていること)がとってもありがたいの、分かると思う。 自分にとって一番早い朝は2時。一時は徹夜という感覚 まじで、何かを作り出せる人や、自分で自分を楽しませられる人は尊敬する。私は友達と会って話すか、よくて読書会。空想癖なんてないから仕方ない笑 - 2026年2月9日
 欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里読んでる
欲望会議 性とポリコレの哲学二村ヒトシ,千葉雅也,柴田英里読んでる - 2026年2月3日
 グループと瞑想野田俊作読み終わったグループセラピーについて。下火になってしまったけど、野田先生は好きでやっている。現実との落差が極端すぎると、実社会で通用しない。あくまでよきコモンセンスに則ってデザインしなければならない。 共同体感覚を育むためのグループセラピー 気分と感情は異なる。気分に対して感情的になる。「抑うつの感情さえ消えれば、抑うつ気分のほうはそう耐えがたいものではないようです」p89 不安は未来に対して、抑うつは過去に対しての感情。怒りは今。怒りは悲しみ。 変わった時に人は洞察する。 感情は、対人関係の中で使われる道具であり、しかも陰性の感情は使わなくても生きていけるので、別のレパートリーを使えるようにしてあげる。 瞑想とは目覚めていること。状況をちゃんと認知でき、目的追求をストップさせ(欲は捨てれないが目的は捨てられる。人生目標とは理想の自分のこと。劣等感は理想の自分とのギャップ。瞑想的になるとただの幻想だとわかる。)、他人や世界全体に対する態度が根本的に変わる。ライフスタイルも自分で選べるようになる。
グループと瞑想野田俊作読み終わったグループセラピーについて。下火になってしまったけど、野田先生は好きでやっている。現実との落差が極端すぎると、実社会で通用しない。あくまでよきコモンセンスに則ってデザインしなければならない。 共同体感覚を育むためのグループセラピー 気分と感情は異なる。気分に対して感情的になる。「抑うつの感情さえ消えれば、抑うつ気分のほうはそう耐えがたいものではないようです」p89 不安は未来に対して、抑うつは過去に対しての感情。怒りは今。怒りは悲しみ。 変わった時に人は洞察する。 感情は、対人関係の中で使われる道具であり、しかも陰性の感情は使わなくても生きていけるので、別のレパートリーを使えるようにしてあげる。 瞑想とは目覚めていること。状況をちゃんと認知でき、目的追求をストップさせ(欲は捨てれないが目的は捨てられる。人生目標とは理想の自分のこと。劣等感は理想の自分とのギャップ。瞑想的になるとただの幻想だとわかる。)、他人や世界全体に対する態度が根本的に変わる。ライフスタイルも自分で選べるようになる。
読み込み中...

