ボディ・サイレント: 病いと障害の人類学

ボディ・サイレント: 病いと障害の人類学
ロバート・F.マーフィー
Robert F.Murphy
辻信一
新宿書房
1997年6月30日
3件の記録
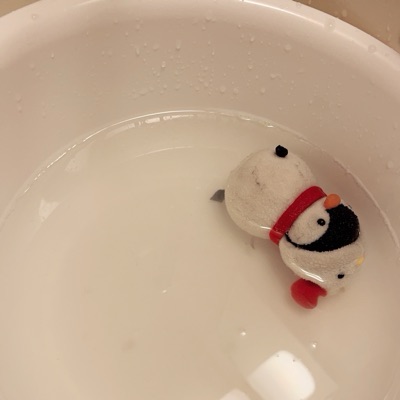 DMK@DMK_penguin2025年4月30日また読みたい積読中人類学入門講義の課題文献。この本の第4章「損なわれた自己」を読んだ。Readsに「部分的に読んだ」タグがあればいいのに。 アメリカの人類学者であり全身麻痺著患者でもある著者は、障がい者になったことによってアメリカ社会から異化されることで、「表面上の文化的差異の奥にある全人類共通の原理にまで達したい」(p.135)という強い願望を抱くようになったという。「健常な」身体と全身麻痺を経験した彼がこの章においておこなった仕事は、身体障害が人間の心に及ぼすものの考察を通して、人間の意識や行動の向かう方向性と、それに身体が与える影響を解明することだと私は捉えた。 著者曰く、身障者が経験するのは真の意味での「変身」、つまり元の身体に他者が侵入してくることだという。 心を身体と結びつける哲学者たちの議論に足場を起きつつ著者が主張するのは、身体の一部を欠損させた人びとは、「その人と世界を繋いでいた関係の環」(p.131)を一部失うということだった。彼らは自身の障害に合わせて「再身体化」せねばならず、欠損が激しい場合は「脱身体化」すら起こり(著者がそうらしい)、身体と繋がっていた思考は脳に閉じ込められる。 著者は身障者がぼんやりと感じる罪の意識について議論する際に、各種神話における不具化をヒントに、性的・社会的に失うもののメタファーとして「去勢」という考え方を導入する。大多数の者は立ちはだかる身体的・社会的壁を乗り越えられず、社会の片隅に追いやられる。 人間には、社会に向かう外向きの求心力と、自分の殻に閉じこもろうとする内向きの求心力があると著者は考える。身障者においては、欠損した身体を持つことにより生じる社会との摩擦や、罪と恥の感覚によって後者の求心力が増すのである。 * * * 私が一つ疑問に思ったことは、著者が頭蓋が半分しかない「知恵遅れのティーンエイジャー」と話しているのを見て見舞客が絶叫したというエピソードから生まれた彼の疑問と、それ以降展開する議論のずれだ。彼はコロンビア大学の教授であり、身体障害を負った後も文章から分かる通り非常に明晰な思考を(その仕方は変わったかもしれないが)している。彼の展開する議論は、健常者が脳以外の身体を欠損した事例を基に進んでいる趣があり、「知恵遅れのティーンエイジャー」のような脳の欠損者の話は出てこない。脳が欠損したら、そして脳の欠損者に対して、果たしてこのような議論が展開しうるだろうか。短絡的な考えかもしれないが、身体のさまざまな部位の欠損を全て「身体障害」とひとまとめにして議論して良いのだろうかという疑問が湧くのである。
DMK@DMK_penguin2025年4月30日また読みたい積読中人類学入門講義の課題文献。この本の第4章「損なわれた自己」を読んだ。Readsに「部分的に読んだ」タグがあればいいのに。 アメリカの人類学者であり全身麻痺著患者でもある著者は、障がい者になったことによってアメリカ社会から異化されることで、「表面上の文化的差異の奥にある全人類共通の原理にまで達したい」(p.135)という強い願望を抱くようになったという。「健常な」身体と全身麻痺を経験した彼がこの章においておこなった仕事は、身体障害が人間の心に及ぼすものの考察を通して、人間の意識や行動の向かう方向性と、それに身体が与える影響を解明することだと私は捉えた。 著者曰く、身障者が経験するのは真の意味での「変身」、つまり元の身体に他者が侵入してくることだという。 心を身体と結びつける哲学者たちの議論に足場を起きつつ著者が主張するのは、身体の一部を欠損させた人びとは、「その人と世界を繋いでいた関係の環」(p.131)を一部失うということだった。彼らは自身の障害に合わせて「再身体化」せねばならず、欠損が激しい場合は「脱身体化」すら起こり(著者がそうらしい)、身体と繋がっていた思考は脳に閉じ込められる。 著者は身障者がぼんやりと感じる罪の意識について議論する際に、各種神話における不具化をヒントに、性的・社会的に失うもののメタファーとして「去勢」という考え方を導入する。大多数の者は立ちはだかる身体的・社会的壁を乗り越えられず、社会の片隅に追いやられる。 人間には、社会に向かう外向きの求心力と、自分の殻に閉じこもろうとする内向きの求心力があると著者は考える。身障者においては、欠損した身体を持つことにより生じる社会との摩擦や、罪と恥の感覚によって後者の求心力が増すのである。 * * * 私が一つ疑問に思ったことは、著者が頭蓋が半分しかない「知恵遅れのティーンエイジャー」と話しているのを見て見舞客が絶叫したというエピソードから生まれた彼の疑問と、それ以降展開する議論のずれだ。彼はコロンビア大学の教授であり、身体障害を負った後も文章から分かる通り非常に明晰な思考を(その仕方は変わったかもしれないが)している。彼の展開する議論は、健常者が脳以外の身体を欠損した事例を基に進んでいる趣があり、「知恵遅れのティーンエイジャー」のような脳の欠損者の話は出てこない。脳が欠損したら、そして脳の欠損者に対して、果たしてこのような議論が展開しうるだろうか。短絡的な考えかもしれないが、身体のさまざまな部位の欠損を全て「身体障害」とひとまとめにして議論して良いのだろうかという疑問が湧くのである。








