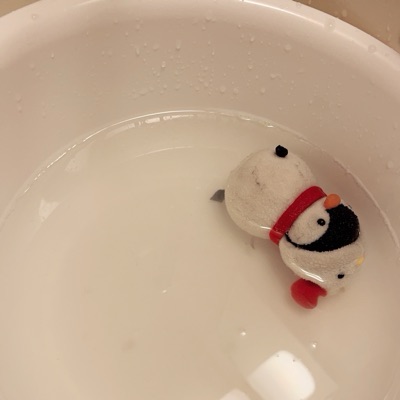
DMK
@DMK_penguin
かわいいペンギンです
- 2026年1月11日
- 2026年1月11日
 内在的多様性批判久保明教気になる
内在的多様性批判久保明教気になる - 2026年1月11日
 人類史のなかの定住革命西田正規気になる
人類史のなかの定住革命西田正規気になる - 2026年1月11日
- 2026年1月11日
- 2026年1月10日
- 2026年1月10日
 記憶現象の心理学ベネット・L・シュワルツ,アン・M・クリアリー,山本晃輔,槙洋一,清水寛之,瀧川真也気になる
記憶現象の心理学ベネット・L・シュワルツ,アン・M・クリアリー,山本晃輔,槙洋一,清水寛之,瀧川真也気になる - 2026年1月10日
 世論と群衆ガブリエル・タルド気になる
世論と群衆ガブリエル・タルド気になる - 2026年1月6日
 住宅貧乏都市モスクワ道上真有読み終わった今年2冊目の本(ブックレット)。 社会主義住宅建築大好きマンなので、類似の本を何冊か読んでいるけども読むたびに新しい発見があるし楽しい。 社会主義建築史の内容の点では本田晃子『革命と住宅』の方が詳しいが(そもそもページ数がかなり違うし)、こちらのブックレットは著者の現地調査とインタビューに基づいて取材当時の人びとの生活や住宅に関わる悩み・喜びがリアルに描かれている。駅徒歩圏内に住みたいのは2000年代のモスクワ住民も現在の東京都民も似たようなものらしい。 モスクワでは道路渋滞はひどいが、このブックレットを読む限り電車は快適のようだ。ロシア留学時、講師が私を含む日本人学生に対して「なぜ東京の電車は遅延するのか?電車は(路線別に線路に沿って人を運ぶだけだから)遅れないはずだけど」と本気で分からないと言った顔をしながら質問してきたことを思い出した。
住宅貧乏都市モスクワ道上真有読み終わった今年2冊目の本(ブックレット)。 社会主義住宅建築大好きマンなので、類似の本を何冊か読んでいるけども読むたびに新しい発見があるし楽しい。 社会主義建築史の内容の点では本田晃子『革命と住宅』の方が詳しいが(そもそもページ数がかなり違うし)、こちらのブックレットは著者の現地調査とインタビューに基づいて取材当時の人びとの生活や住宅に関わる悩み・喜びがリアルに描かれている。駅徒歩圏内に住みたいのは2000年代のモスクワ住民も現在の東京都民も似たようなものらしい。 モスクワでは道路渋滞はひどいが、このブックレットを読む限り電車は快適のようだ。ロシア留学時、講師が私を含む日本人学生に対して「なぜ東京の電車は遅延するのか?電車は(路線別に線路に沿って人を運ぶだけだから)遅れないはずだけど」と本気で分からないと言った顔をしながら質問してきたことを思い出した。 - 2026年1月4日
 資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのかナンシー・フレイザー,江口泰子読み終わった2026年最初の一冊は、昨年11月に購入して少し齧り読みして積読していた本。今年は積読本を減らす都市にしたい。 この本の要点は、資本主義は単なる経済体制ではなく、人種・(女性に偏りがちな)ケア・自然・公権力に支えられながらもそれらを喰いつくす社会秩序だ、ということである。資本主義がいかに上記の要素に対価を支払うことなく搾取・収奪しているのか、各要素間がいかに関連しているかが一章ずつ掘り下げられている。 著者は、限界を迎えている資本主義社会への対抗ヘゲモニーとして21世紀の社会主義を提案する。これは、過去のソ連などの「社会主義」国家への肯定や回帰ではなく、資本主義社会が疲弊させた様々なものを回復させるための概念あるいは仕組みのことを「社会主義」という概念に込めているらしい。 読後、正直世界への絶望感に溢れてしまい正月早々落ち込んだ。だが、改善あるいは転換すべきシステムが数多く指摘されており、自分の安易な消費行動を見直すきっかけになった。 執筆期間が2023年までということもあり文中にはAIの話題がほとんど出てこなかったが、AIがどのように資本主義を変化させるのか、本テーマに関連する論者はどう論じるのかが気になった。
資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのかナンシー・フレイザー,江口泰子読み終わった2026年最初の一冊は、昨年11月に購入して少し齧り読みして積読していた本。今年は積読本を減らす都市にしたい。 この本の要点は、資本主義は単なる経済体制ではなく、人種・(女性に偏りがちな)ケア・自然・公権力に支えられながらもそれらを喰いつくす社会秩序だ、ということである。資本主義がいかに上記の要素に対価を支払うことなく搾取・収奪しているのか、各要素間がいかに関連しているかが一章ずつ掘り下げられている。 著者は、限界を迎えている資本主義社会への対抗ヘゲモニーとして21世紀の社会主義を提案する。これは、過去のソ連などの「社会主義」国家への肯定や回帰ではなく、資本主義社会が疲弊させた様々なものを回復させるための概念あるいは仕組みのことを「社会主義」という概念に込めているらしい。 読後、正直世界への絶望感に溢れてしまい正月早々落ち込んだ。だが、改善あるいは転換すべきシステムが数多く指摘されており、自分の安易な消費行動を見直すきっかけになった。 執筆期間が2023年までということもあり文中にはAIの話題がほとんど出てこなかったが、AIがどのように資本主義を変化させるのか、本テーマに関連する論者はどう論じるのかが気になった。 - 2025年12月27日
 絶望と熱狂のピアサポート横山紗亜耶読み終わったReadsのPCアプリがあることを今日知ってDLした。スマホの容量がすぐいっぱいになるので、生活に必須なアプリ以外消していたのでReadsを開くのは久しぶり。 この本は2025年最後に読んだ本。読書スピードが遅いのと最近集中力が切れやすいことで、この一年は一日に一冊読了できなかったのだが、この本は冷静な熱量に溢れていて、この熱量を中断させたくないと思いその日中に読み切った。 著者をナビゲート役として、いきなりわけが分からないまま始まる〈お祭り〉、具体的な固有名として登場する人びと、そして登場人物かつ一人称視点の語り手としての著者の存在が、著者とともに自分も〈お祭り〉の場に参加しているような感覚になった。
絶望と熱狂のピアサポート横山紗亜耶読み終わったReadsのPCアプリがあることを今日知ってDLした。スマホの容量がすぐいっぱいになるので、生活に必須なアプリ以外消していたのでReadsを開くのは久しぶり。 この本は2025年最後に読んだ本。読書スピードが遅いのと最近集中力が切れやすいことで、この一年は一日に一冊読了できなかったのだが、この本は冷静な熱量に溢れていて、この熱量を中断させたくないと思いその日中に読み切った。 著者をナビゲート役として、いきなりわけが分からないまま始まる〈お祭り〉、具体的な固有名として登場する人びと、そして登場人物かつ一人称視点の語り手としての著者の存在が、著者とともに自分も〈お祭り〉の場に参加しているような感覚になった。 - 2025年7月3日
 生きていることティム・インゴルド,柴田崇ちょっと開いた買った
生きていることティム・インゴルド,柴田崇ちょっと開いた買った - 2025年7月3日
 女が先に移り住むときシバ・M・ジョージ,伊藤るりまたいつかちょっと開いた講義の課題図書として1-2章と最終章を読んだ。移民研究とジェンダー研究の交点を学ぶことができた。著者自身、この本でメインで描かれるケーララ出身アメリカ人コミュニティに属する人だそう。この本はある意味、Elliotらが2025年にAAAで論じていたオートエスノグラフィーの範疇に近いところにいるのかもしれない(自分の立ち位置を明示してそれに基づく記述ではなかったけれど)。
女が先に移り住むときシバ・M・ジョージ,伊藤るりまたいつかちょっと開いた講義の課題図書として1-2章と最終章を読んだ。移民研究とジェンダー研究の交点を学ぶことができた。著者自身、この本でメインで描かれるケーララ出身アメリカ人コミュニティに属する人だそう。この本はある意味、Elliotらが2025年にAAAで論じていたオートエスノグラフィーの範疇に近いところにいるのかもしれない(自分の立ち位置を明示してそれに基づく記述ではなかったけれど)。 - 2025年6月19日
- 2025年6月19日
- 2025年6月12日
 ブルーノ・ラトゥールの取説久保明教まだ読んでる
ブルーノ・ラトゥールの取説久保明教まだ読んでる - 2025年6月8日
 愛と孤独のフォルクローレ相田豊読みたい
愛と孤独のフォルクローレ相田豊読みたい - 2025年6月8日
 他者の帝国染田秀藤,関雄二読みたい
他者の帝国染田秀藤,関雄二読みたい - 2025年6月4日
 科学が作られているときブルーノ・ラトゥール,Bruno Latour,川崎勝,高田紀代志読んでる
科学が作られているときブルーノ・ラトゥール,Bruno Latour,川崎勝,高田紀代志読んでる - 2025年6月2日
 反政治機械ジェームス・ファーガソン読み終わった国際援助団体の報告書を読んで分析する前に必読だと思って手に取った。 ファーガソンは、「開発」の言説を矯正すべき全く間違った開発対象地域についての説明として価値判断を下すのではない。それよりも、開発を実施する上でのその言説必要性や開発が地域に与えた影響を、フーコーの装置概念を使って明らかにしていく。 1970年代レソトの農村開発に関する「開発」言説とプロジェクトの進行の分析において、ファーガソンは「レソトに関する学術論文ではありふれている多くの見方や思考の方向性が「開発」言説からは実質的に排除されている」(p.65)と指摘した。しかし、他地域や他の時代の「開発」言説において開発と学術の言説は常にこのような関係とは限らないのではないだろうか?(ファーガソン自身、レソトの事例を一般化して論じるわけではないと明示しているけども)
反政治機械ジェームス・ファーガソン読み終わった国際援助団体の報告書を読んで分析する前に必読だと思って手に取った。 ファーガソンは、「開発」の言説を矯正すべき全く間違った開発対象地域についての説明として価値判断を下すのではない。それよりも、開発を実施する上でのその言説必要性や開発が地域に与えた影響を、フーコーの装置概念を使って明らかにしていく。 1970年代レソトの農村開発に関する「開発」言説とプロジェクトの進行の分析において、ファーガソンは「レソトに関する学術論文ではありふれている多くの見方や思考の方向性が「開発」言説からは実質的に排除されている」(p.65)と指摘した。しかし、他地域や他の時代の「開発」言説において開発と学術の言説は常にこのような関係とは限らないのではないだろうか?(ファーガソン自身、レソトの事例を一般化して論じるわけではないと明示しているけども)
読み込み中...





