サイコロジカル・ボディ・ブルース解凍 (白夜ライブラリー001)

1件の記録
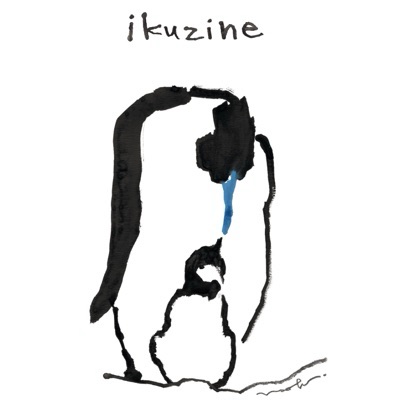 Yamada Keisuke@afro1082025年8月5日読み終わった著者の本は見かけるたびに読んでおり、その中でもあまり見かけたことのない一冊をゆとぴやぶっくすで発見。積んであったので読んだ。著者の見識の広さはもはや言うまでもないが、そこに格闘技まで含まれていることを知ったのは『あなたの前の彼女だって、むかしはヒョードルだのミルコだの言っていた筈だ』を読んだときだった。なぜ今読んだかといえば『1984年のUWF』『2000年の桜庭和志』を読んで下地が整ったからである。そのおかげで、著者のバイブスをふんだんに味わうことができた。 副題にあるとおり、著者が神経病を患ったことも影響してか、格闘技から五年ほど離れていた中、著者の格闘技語りに目をつけた編集者が執筆を打診。そして、2004年大晦日のPRIDE観戦をきっかけに「解凍」され、格闘技語りを再開するという背景で書かれた本となっている。前半はインターネット掲示板(!)で著者が書いていた格闘批評、後半はPRIDEを含め実際に会場で観戦したライブレポート&論考という構成だ。 「成孔節」という文体が明確に存在し、こと批評において、これだけオリジナリティを出せる人が今どれだけいるのだろうかと、いつもどおり打ちのめされた。2000年代前半で、著者が比較的若いこともあいまってノリノリで今読むとオモシロい。(それゆえにキワドイ発言も多いのだが…)特に注釈量が異常で、なおかつその注釈では収まり切らないほどに言いたいことがあるようで、紙面の都合で割愛されている見立てがたくさんあった。また、まえがきのあまりの見事さに「粋な夜電波」の口上をレミニス…復活しないのだろうか。(定期n回目) プロレス、格闘技と与太話は相性がよく、なんなら与太話がしたくて見ているところだってあるわけだが、その相性の良さが抜群に発揮されており、他のジャンルを語るときよりも好き勝手に、縦横無尽に語っている印象を持った。その中心となっているのはPRIDE語りである。ピーク期の大晦日でカードの並びがエグい。今では定番となった「大晦日に判定、駄目だよ。KOじゃなきゃ!」が五味から発せられたり、ノゲイラ vs ヒョードルがあったり。特にミルコ、シウバに対する批評的な見方が興味深かった。 『1984年のUWF』は佐山史観であったが、著者はどちらかといえば前田史観でUWFを捉えている。本著を読んだことで両方の視座を得ることができた点は収穫だった。『1984年〜』では総合格闘技の始祖としての佐山を神聖化していたが、佐山は佐山で彼なりのきな臭さがあることを知った。そして、前田の煮え切らなさを父殺しの神話でアナライズしている様が見事でうなりまくった。さらに終盤にかけてHERO'sで前田が前線復帰。HERO'sのポジションを考察しながら、その崩壊を予想しつつ、それでも前田の孤独を受け入れるというエモい文章は批評の中でも抑えきれない前田への愛に溢れていた。 上記の前田に関する言論然り、日本ではプロレスが発展していく流れで、総合格闘技が誕生してきたわけだが、その歴史を踏まえているかどうかは総合格闘技に対する見方に違いが出ることに気付かされた。たとえば、RIZINにおける皇治の色物カードはガチの人からすればノイズでしかないだろう。しかし、プロレス的な思考があれば、その戦いから導き出されるストーリーや意味を紐解こうとする。そこにロマンを感じるかどうか。今の社会情勢からすると「正しさ」を希求するあまりに「ガチ」が正義となりがちだが、そこを迂回できる余裕がほしいものだ。 文庫解説でも触れられているように、一種の文明論にまでリーチしているあたり、著者の慧眼に打ちのめされた。なかでも世界を「途中から見る連続テレビドラマ」であるとする人生論からプロレス論へ展開していく流れは最高だった。 格闘技はツイッターを中心とした言論空間がシーンの中心なので、こういうまとまった批評を読む機会はほとんどない。(強いていうなら青木のnoteか)だからこそ昔のものだとしても、こういった本を読むことで自分の目や見識を養っていきたい。
Yamada Keisuke@afro1082025年8月5日読み終わった著者の本は見かけるたびに読んでおり、その中でもあまり見かけたことのない一冊をゆとぴやぶっくすで発見。積んであったので読んだ。著者の見識の広さはもはや言うまでもないが、そこに格闘技まで含まれていることを知ったのは『あなたの前の彼女だって、むかしはヒョードルだのミルコだの言っていた筈だ』を読んだときだった。なぜ今読んだかといえば『1984年のUWF』『2000年の桜庭和志』を読んで下地が整ったからである。そのおかげで、著者のバイブスをふんだんに味わうことができた。 副題にあるとおり、著者が神経病を患ったことも影響してか、格闘技から五年ほど離れていた中、著者の格闘技語りに目をつけた編集者が執筆を打診。そして、2004年大晦日のPRIDE観戦をきっかけに「解凍」され、格闘技語りを再開するという背景で書かれた本となっている。前半はインターネット掲示板(!)で著者が書いていた格闘批評、後半はPRIDEを含め実際に会場で観戦したライブレポート&論考という構成だ。 「成孔節」という文体が明確に存在し、こと批評において、これだけオリジナリティを出せる人が今どれだけいるのだろうかと、いつもどおり打ちのめされた。2000年代前半で、著者が比較的若いこともあいまってノリノリで今読むとオモシロい。(それゆえにキワドイ発言も多いのだが…)特に注釈量が異常で、なおかつその注釈では収まり切らないほどに言いたいことがあるようで、紙面の都合で割愛されている見立てがたくさんあった。また、まえがきのあまりの見事さに「粋な夜電波」の口上をレミニス…復活しないのだろうか。(定期n回目) プロレス、格闘技と与太話は相性がよく、なんなら与太話がしたくて見ているところだってあるわけだが、その相性の良さが抜群に発揮されており、他のジャンルを語るときよりも好き勝手に、縦横無尽に語っている印象を持った。その中心となっているのはPRIDE語りである。ピーク期の大晦日でカードの並びがエグい。今では定番となった「大晦日に判定、駄目だよ。KOじゃなきゃ!」が五味から発せられたり、ノゲイラ vs ヒョードルがあったり。特にミルコ、シウバに対する批評的な見方が興味深かった。 『1984年のUWF』は佐山史観であったが、著者はどちらかといえば前田史観でUWFを捉えている。本著を読んだことで両方の視座を得ることができた点は収穫だった。『1984年〜』では総合格闘技の始祖としての佐山を神聖化していたが、佐山は佐山で彼なりのきな臭さがあることを知った。そして、前田の煮え切らなさを父殺しの神話でアナライズしている様が見事でうなりまくった。さらに終盤にかけてHERO'sで前田が前線復帰。HERO'sのポジションを考察しながら、その崩壊を予想しつつ、それでも前田の孤独を受け入れるというエモい文章は批評の中でも抑えきれない前田への愛に溢れていた。 上記の前田に関する言論然り、日本ではプロレスが発展していく流れで、総合格闘技が誕生してきたわけだが、その歴史を踏まえているかどうかは総合格闘技に対する見方に違いが出ることに気付かされた。たとえば、RIZINにおける皇治の色物カードはガチの人からすればノイズでしかないだろう。しかし、プロレス的な思考があれば、その戦いから導き出されるストーリーや意味を紐解こうとする。そこにロマンを感じるかどうか。今の社会情勢からすると「正しさ」を希求するあまりに「ガチ」が正義となりがちだが、そこを迂回できる余裕がほしいものだ。 文庫解説でも触れられているように、一種の文明論にまでリーチしているあたり、著者の慧眼に打ちのめされた。なかでも世界を「途中から見る連続テレビドラマ」であるとする人生論からプロレス論へ展開していく流れは最高だった。 格闘技はツイッターを中心とした言論空間がシーンの中心なので、こういうまとまった批評を読む機会はほとんどない。(強いていうなら青木のnoteか)だからこそ昔のものだとしても、こういった本を読むことで自分の目や見識を養っていきたい。


