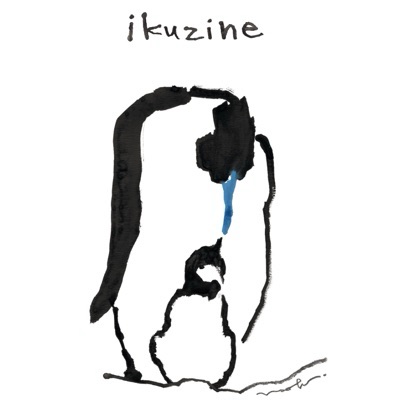
Yamada Keisuke
@afro108
乱読の地層。
- 2026年2月23日
 本と偶然カン・バンファ,キム・チョヨプ読み終わったフェイバリットなSF作家であるキム・チョヨプの初エッセイ。去年読んだ『サイボーグになる』が興味深かったので楽しみにしていたが、その期待を上回る素晴らしいSFエッセイだった。SFを読むのも好きなのだが、他人の語るSF論も好きなのでドンズバな内容だった。 エッセイ集ではあるものの、生活の話というより著者の読書遍歴と作家論が中心となっている。これまでの作品を読んできた読者からすれば、作品や彼女自身の背景を知ることができる最高のビハインド・ザ・ストーリーものである。 『サイボーグになる』もノンフィクションという点では共通しているが、内容もあいまって文章が硬かった。それに比べて本著は柔らかく読みやすい。自然体で自身のことを語っており、著者の誠実さが文章からヒシヒシと伝わってくるエッセイらしいエッセイだ。 著者の小説はSFではあるが、いわゆるハードSFではなく、現代社会とどこかしら地続きなものが多い。ゆえに私を含めてコアなSFファンに限らず、広い読者層に届いているのだろう。意図的に柔らかいSFを書いているのかと思いきや、実際には結果としてそうなっているようで、本人は思いのほかSFというジャンルにこだわりを持っている。自分の作品評価や業界での相対的なポジションについて極めて自覚的で、その視点の鋭さに唸った。 前述のとおり、制作裏話がところどころに挟まれており、ファンにとってはありがたい。なかでも『サイボーグになる』は執筆における苦労に関してかなりの分量で書かれており個人的に嬉しかった。そもそも著者が「SF作家によるエッセイ」を愛読してきており、その系譜を自覚的に引き受けているのだろう。 SF作家のエッセイは作家の日常をのぞき見できるばかりか、当人のジャンルと作法に関する話までたっぷり聞けてしまう、作家仲間としてはまことにありがたい秘蔵の玉手箱なのである。 興味深いのは、著者が必ずしも熱心なSF読者として作家になったわけではないという点だ。作家になってから、どうやってキャッチアップしていったか、読書遍歴と共に語られる。とにかく科学ノンフィクションの素養がハンパない。玉石混合の割に分量が多く、本屋では取扱いも少なく単価も高い科学ノンフィクション。こういったいくつものハードルがあるにも関わらず、著者のアンテナはバリサン。タイトルだけで読みたくなる本がわんさか登場する。さらに著者の柔和で真摯な語り口も読みたくなる気にさせてくれる。 著者は、自身の創作を「内面から湧き出る想像力」だけでなく、「外部から集めた素材を積み上げていく営み」に近いと語る。その比喩は料理や建築に例えられていたが、私にはサンプリングから始まったヒップホップの方法論とも重なって見えた。ラッパーのC.O.S.A、プロデューサーのKMなど、著者の作品が局地的にヒップホップ業界で人気があるのは、こういった背景も影響しているのかもしれない。 また、大学院で研究に挫折した経験も率直に語られている。著者の言うとおり、科学的なものが好きなことと、実際の科学の現場、特に研究業務には大きなギャップがある。レベル感は違うが、私も高校で理系科目が他より得意だったから大学で専攻したものの、まったく好きになれなかった。結果的に現在の仕事が研究職ではない自分に負い目がある。そんな負い目について著者も繰り返し吐露しており、そんな葛藤を乗り越えて、作家として確固たる地位を確立しているのだからかっこいい。 書評に関するチャプターは踏み込んでいる印象を受けた。本の評価に対するアンビバレントな感情を結構な分量で書いており、小説家がここまで踏み込んで書いているものを読むのが初めてだった。書評が単純な感想に閉じずに脈絡を構築し、誰かの読書に貢献する可能性についてはまったくもって同意で、その気持ちでこのブログを延々と書いている。(著者が書評集を出そうとして、友人から「黒歴史になるからやめとめけ」と止められた話は、個人で書評ZINEを作った身としては耳が痛かった…) 本を通じた作者と読者のコミュニケーションへの言及が最も興味深かった。そもそも小説を通じてメッセージを伝え、それを読者が受け取るという手段は、効率だけを基準にすれば信じられないほど非効率である。しかも今は、作者の意図から逸脱する読解が許されにくい「考察の時代」でもある。そんな中で、著者がコミュニケーションの失敗にこそ可能性があると言っている点に、安易な逆張りではない本への愛を感じたのだった。 作家が読者に意味を伝えつくすことに失敗し、読者が作家の意図を把握しつくすことに失敗することで、本は本来より拡張した存在となる。(中略)読むことを試み、読むことに失敗し、時に誤読が拡張の可能性へと変貌する個然の瞬間を期待しつつ、誤解と理解のあいだを行きつ戻りつしながら本に無数の意味を盛り重ねていくその作業を、わたしは喜ばしい気持ちで追いかけたい。 最後に語られている現代社会における科学の立ち位置についての視座も新鮮だった。陰謀論や疑似科学はくだらないものだと科学の合理的な価値観から説明することは可能だが、結局は科学も人間の営みだからこそ、どこまでいっても非合理性からは抜け出せない。そんな悲観的な視点から、正直さ、誠実さ、明確さ、開放性といった「科学的価値」を選び取る姿勢を示しており、今の時代に必要な態度だと感じた。 巻末には本著で紹介されたブックリストがついていて、日本語への翻訳状況も含めて一覧で見れるのは本好きにとって貴重な資料である。そんな本への愛に溢れた最高の一冊だった。
本と偶然カン・バンファ,キム・チョヨプ読み終わったフェイバリットなSF作家であるキム・チョヨプの初エッセイ。去年読んだ『サイボーグになる』が興味深かったので楽しみにしていたが、その期待を上回る素晴らしいSFエッセイだった。SFを読むのも好きなのだが、他人の語るSF論も好きなのでドンズバな内容だった。 エッセイ集ではあるものの、生活の話というより著者の読書遍歴と作家論が中心となっている。これまでの作品を読んできた読者からすれば、作品や彼女自身の背景を知ることができる最高のビハインド・ザ・ストーリーものである。 『サイボーグになる』もノンフィクションという点では共通しているが、内容もあいまって文章が硬かった。それに比べて本著は柔らかく読みやすい。自然体で自身のことを語っており、著者の誠実さが文章からヒシヒシと伝わってくるエッセイらしいエッセイだ。 著者の小説はSFではあるが、いわゆるハードSFではなく、現代社会とどこかしら地続きなものが多い。ゆえに私を含めてコアなSFファンに限らず、広い読者層に届いているのだろう。意図的に柔らかいSFを書いているのかと思いきや、実際には結果としてそうなっているようで、本人は思いのほかSFというジャンルにこだわりを持っている。自分の作品評価や業界での相対的なポジションについて極めて自覚的で、その視点の鋭さに唸った。 前述のとおり、制作裏話がところどころに挟まれており、ファンにとってはありがたい。なかでも『サイボーグになる』は執筆における苦労に関してかなりの分量で書かれており個人的に嬉しかった。そもそも著者が「SF作家によるエッセイ」を愛読してきており、その系譜を自覚的に引き受けているのだろう。 SF作家のエッセイは作家の日常をのぞき見できるばかりか、当人のジャンルと作法に関する話までたっぷり聞けてしまう、作家仲間としてはまことにありがたい秘蔵の玉手箱なのである。 興味深いのは、著者が必ずしも熱心なSF読者として作家になったわけではないという点だ。作家になってから、どうやってキャッチアップしていったか、読書遍歴と共に語られる。とにかく科学ノンフィクションの素養がハンパない。玉石混合の割に分量が多く、本屋では取扱いも少なく単価も高い科学ノンフィクション。こういったいくつものハードルがあるにも関わらず、著者のアンテナはバリサン。タイトルだけで読みたくなる本がわんさか登場する。さらに著者の柔和で真摯な語り口も読みたくなる気にさせてくれる。 著者は、自身の創作を「内面から湧き出る想像力」だけでなく、「外部から集めた素材を積み上げていく営み」に近いと語る。その比喩は料理や建築に例えられていたが、私にはサンプリングから始まったヒップホップの方法論とも重なって見えた。ラッパーのC.O.S.A、プロデューサーのKMなど、著者の作品が局地的にヒップホップ業界で人気があるのは、こういった背景も影響しているのかもしれない。 また、大学院で研究に挫折した経験も率直に語られている。著者の言うとおり、科学的なものが好きなことと、実際の科学の現場、特に研究業務には大きなギャップがある。レベル感は違うが、私も高校で理系科目が他より得意だったから大学で専攻したものの、まったく好きになれなかった。結果的に現在の仕事が研究職ではない自分に負い目がある。そんな負い目について著者も繰り返し吐露しており、そんな葛藤を乗り越えて、作家として確固たる地位を確立しているのだからかっこいい。 書評に関するチャプターは踏み込んでいる印象を受けた。本の評価に対するアンビバレントな感情を結構な分量で書いており、小説家がここまで踏み込んで書いているものを読むのが初めてだった。書評が単純な感想に閉じずに脈絡を構築し、誰かの読書に貢献する可能性についてはまったくもって同意で、その気持ちでこのブログを延々と書いている。(著者が書評集を出そうとして、友人から「黒歴史になるからやめとめけ」と止められた話は、個人で書評ZINEを作った身としては耳が痛かった…) 本を通じた作者と読者のコミュニケーションへの言及が最も興味深かった。そもそも小説を通じてメッセージを伝え、それを読者が受け取るという手段は、効率だけを基準にすれば信じられないほど非効率である。しかも今は、作者の意図から逸脱する読解が許されにくい「考察の時代」でもある。そんな中で、著者がコミュニケーションの失敗にこそ可能性があると言っている点に、安易な逆張りではない本への愛を感じたのだった。 作家が読者に意味を伝えつくすことに失敗し、読者が作家の意図を把握しつくすことに失敗することで、本は本来より拡張した存在となる。(中略)読むことを試み、読むことに失敗し、時に誤読が拡張の可能性へと変貌する個然の瞬間を期待しつつ、誤解と理解のあいだを行きつ戻りつしながら本に無数の意味を盛り重ねていくその作業を、わたしは喜ばしい気持ちで追いかけたい。 最後に語られている現代社会における科学の立ち位置についての視座も新鮮だった。陰謀論や疑似科学はくだらないものだと科学の合理的な価値観から説明することは可能だが、結局は科学も人間の営みだからこそ、どこまでいっても非合理性からは抜け出せない。そんな悲観的な視点から、正直さ、誠実さ、明確さ、開放性といった「科学的価値」を選び取る姿勢を示しており、今の時代に必要な態度だと感じた。 巻末には本著で紹介されたブックリストがついていて、日本語への翻訳状況も含めて一覧で見れるのは本好きにとって貴重な資料である。そんな本への愛に溢れた最高の一冊だった。 - 2026年2月16日
 読み終わったいくつかKindleで積んでいる柳澤健による『〇〇年の〜』シリーズ。先月、コンビニでプロレス雑誌を見かけたのだが、そこに踊っていたのは「棚橋、引退」の文字だった。それをきっかけに本著を読んだ。著者の作品を読むのは5冊目になるが、これが一番好きだった。なぜなら、自分が子どもの頃にど真ん中で見ていた新日本プロレスの物語だったから。当時は理解できていなかった背景、新日本プロレス再生の道程を知り打ち震えた。 本著は、棚橋弘至と中邑真輔という二人のレスラーを軸に、2000年代から2010年代の新日本プロレスを描くドキュメンタリーである。当時の新日本は総合格闘技(MMA)隆盛のあおりを受け、その棲み分けの過渡期にあり、厳しい状況が続いていた。そんな中で二人の若者が文字どおり地べたを這いつくばって、自らの愛する団体を再び輝かせるために試行錯誤する。その歩みが、個別の章から徐々に交差し、やがて結実していく構成は見事というほかない。 黒いショートタイツと黒いリングシューズに象徴されるストロングスタイル。そのストイックに強さを誇示していく姿勢に惹かれ、カール・ゴッチを始祖としたストロングスタイルを継承する西村、柴田、後藤らがマイフェイバリットレスラーだった。ゆえに当時の棚橋はアウトオブ眼中で、彼が新日本の中心に来たころ、ちょうどMMAが隆盛するタイミングでプロレスから離れてしまったが、その後にこんなにアツい展開があったなんて…やはり冬の時代だとしても、自分が好きなら変わらず見続けることが大事だと痛感した。底辺から頂点までかけ上がっていくのを一緒に伴走することは、お金で買えない時間がもたらす最高の醍醐味だからだ。 太陽と月のような二人だからこそ、プロレス観の陰影がくっきりと浮かび上がり、その対照性に魅了される。そして、その中心にどう転んでも存在するのがアントニオ猪木だ。棚橋は一貫して反猪木でエンタメとしてのプロレスを追求していた。一方、中邑は猪木の掲げる「プロレスラーが最強」という思想を体現する舎弟として登場したものの、総合格闘技をマージしたスタイルでは結果を出し切れない。しかし、そこから自分のプロレスラーとしての自我をか獲得していき、最終的にエンタメプロレス最高峰であるWWEまで到達するのだから人生どうなるかわからないものである。しかも、必殺技の名前が「ボマイェ(今はキンシャサ)」という猪木へのオマージュという逆説も素晴らしい。つまり、「King of Strong style」という中邑オリジナルのスタイルで、猪木の象徴であるストロングスタイルを再定義、更新しているのだ。 棚橋パートで最も興味深かったのは、本人の卓越した言語化能力である。現役レスラーとして連載を持ち、そこで現状のプロレスを高い解像度で自ら分析、言語化していたことには驚いた。本著では、彼の思考を思う存分、堪能できる。ビジネス論であり、アート論でもあり、プロレスをあらゆる角度から検証し、「自分に何ができるか?」を考え続ける姿勢から深いプロレス愛をひしひしと感じた。引退後、新日本プロレスの代表取締役に就任したというのも、レスラーよりも天職かもしれないと思わされた。 様々な第三者の視点も二人の物語を肉付けする重要なファクターだ。不遇の世代である永田や真壁の客観的評価や、観客代表であるユリオカ超特Q、ハチミツ二郎まで取り入れる大胆さ。特に中邑のチャプターへ突入する直前のユリオカ超特Q(と著者)による刃牙オマージュが最高。 さらに当人たちのインタビューをふんだんに取り入れていることも、私がこれまで読んできた柳澤作品になかった特徴である。たとえば『1984年のUWF』では当人取材なしのアプローチが議論を呼んだわけだが、本著はプロレスファンの多くが納得するであろう圧巻の情報量と整理力で目から鱗だった。試合描写はもちろんこれまでの作品と同じく素晴らしい。前半は試合描写を抑えめにして、ここぞという場面で細かく描いていくあたりの緩急も抜群で、著者の作品を読んでいると、試合を見ていないにも関わらず、毎回見たような気持ちになるのだから不思議である。 今回は評伝的要素ももちろんあるが、新日本プロレス史でもある。特に子どもの頃に理解できていなかったプロレスにおける表向き人事の裏でうごめく政治的力学が興味深かった。橋本小川の件、猪木の横暴っぷり、坂口から藤浪への権限移行、武藤と小島の全日移籍など、すべてに意味があり、そこには泥臭い人間ドラマが背景にある。 大人になった今その背景を知ると会社人事そのものだ。プロレスは「勝ち負け決まっているヤラセでしょ?」と揶揄されるが、会社の人事も一事が万事、「根回し」という名のヤラセが事前に行われた上で決裁される。MMAが等身大の人間ドラマだとすれば、プロレスには「政治」という別ベクトルの人間ドラマがあることに今さらながら気づかされた。 ラストの西加奈子の解説も素晴らしい。プロレスファンが抱えてきたアンビバレントな感情を見事に言語化している。彼女がかつて同じタイミングでプロレスから離れていたこと、そして再び魅了された理由が、棚橋と中邑の切り拓いた「開かれた世界」にあったこと。プロレスを改めて見てみようかなと、プロレス熱に再びを火を灯してくれる最高にアツい一冊だった。
読み終わったいくつかKindleで積んでいる柳澤健による『〇〇年の〜』シリーズ。先月、コンビニでプロレス雑誌を見かけたのだが、そこに踊っていたのは「棚橋、引退」の文字だった。それをきっかけに本著を読んだ。著者の作品を読むのは5冊目になるが、これが一番好きだった。なぜなら、自分が子どもの頃にど真ん中で見ていた新日本プロレスの物語だったから。当時は理解できていなかった背景、新日本プロレス再生の道程を知り打ち震えた。 本著は、棚橋弘至と中邑真輔という二人のレスラーを軸に、2000年代から2010年代の新日本プロレスを描くドキュメンタリーである。当時の新日本は総合格闘技(MMA)隆盛のあおりを受け、その棲み分けの過渡期にあり、厳しい状況が続いていた。そんな中で二人の若者が文字どおり地べたを這いつくばって、自らの愛する団体を再び輝かせるために試行錯誤する。その歩みが、個別の章から徐々に交差し、やがて結実していく構成は見事というほかない。 黒いショートタイツと黒いリングシューズに象徴されるストロングスタイル。そのストイックに強さを誇示していく姿勢に惹かれ、カール・ゴッチを始祖としたストロングスタイルを継承する西村、柴田、後藤らがマイフェイバリットレスラーだった。ゆえに当時の棚橋はアウトオブ眼中で、彼が新日本の中心に来たころ、ちょうどMMAが隆盛するタイミングでプロレスから離れてしまったが、その後にこんなにアツい展開があったなんて…やはり冬の時代だとしても、自分が好きなら変わらず見続けることが大事だと痛感した。底辺から頂点までかけ上がっていくのを一緒に伴走することは、お金で買えない時間がもたらす最高の醍醐味だからだ。 太陽と月のような二人だからこそ、プロレス観の陰影がくっきりと浮かび上がり、その対照性に魅了される。そして、その中心にどう転んでも存在するのがアントニオ猪木だ。棚橋は一貫して反猪木でエンタメとしてのプロレスを追求していた。一方、中邑は猪木の掲げる「プロレスラーが最強」という思想を体現する舎弟として登場したものの、総合格闘技をマージしたスタイルでは結果を出し切れない。しかし、そこから自分のプロレスラーとしての自我をか獲得していき、最終的にエンタメプロレス最高峰であるWWEまで到達するのだから人生どうなるかわからないものである。しかも、必殺技の名前が「ボマイェ(今はキンシャサ)」という猪木へのオマージュという逆説も素晴らしい。つまり、「King of Strong style」という中邑オリジナルのスタイルで、猪木の象徴であるストロングスタイルを再定義、更新しているのだ。 棚橋パートで最も興味深かったのは、本人の卓越した言語化能力である。現役レスラーとして連載を持ち、そこで現状のプロレスを高い解像度で自ら分析、言語化していたことには驚いた。本著では、彼の思考を思う存分、堪能できる。ビジネス論であり、アート論でもあり、プロレスをあらゆる角度から検証し、「自分に何ができるか?」を考え続ける姿勢から深いプロレス愛をひしひしと感じた。引退後、新日本プロレスの代表取締役に就任したというのも、レスラーよりも天職かもしれないと思わされた。 様々な第三者の視点も二人の物語を肉付けする重要なファクターだ。不遇の世代である永田や真壁の客観的評価や、観客代表であるユリオカ超特Q、ハチミツ二郎まで取り入れる大胆さ。特に中邑のチャプターへ突入する直前のユリオカ超特Q(と著者)による刃牙オマージュが最高。 さらに当人たちのインタビューをふんだんに取り入れていることも、私がこれまで読んできた柳澤作品になかった特徴である。たとえば『1984年のUWF』では当人取材なしのアプローチが議論を呼んだわけだが、本著はプロレスファンの多くが納得するであろう圧巻の情報量と整理力で目から鱗だった。試合描写はもちろんこれまでの作品と同じく素晴らしい。前半は試合描写を抑えめにして、ここぞという場面で細かく描いていくあたりの緩急も抜群で、著者の作品を読んでいると、試合を見ていないにも関わらず、毎回見たような気持ちになるのだから不思議である。 今回は評伝的要素ももちろんあるが、新日本プロレス史でもある。特に子どもの頃に理解できていなかったプロレスにおける表向き人事の裏でうごめく政治的力学が興味深かった。橋本小川の件、猪木の横暴っぷり、坂口から藤浪への権限移行、武藤と小島の全日移籍など、すべてに意味があり、そこには泥臭い人間ドラマが背景にある。 大人になった今その背景を知ると会社人事そのものだ。プロレスは「勝ち負け決まっているヤラセでしょ?」と揶揄されるが、会社の人事も一事が万事、「根回し」という名のヤラセが事前に行われた上で決裁される。MMAが等身大の人間ドラマだとすれば、プロレスには「政治」という別ベクトルの人間ドラマがあることに今さらながら気づかされた。 ラストの西加奈子の解説も素晴らしい。プロレスファンが抱えてきたアンビバレントな感情を見事に言語化している。彼女がかつて同じタイミングでプロレスから離れていたこと、そして再び魅了された理由が、棚橋と中邑の切り拓いた「開かれた世界」にあったこと。プロレスを改めて見てみようかなと、プロレス熱に再びを火を灯してくれる最高にアツい一冊だった。 - 2026年2月12日
 読み終わった大阪帰省の際、blackbird booksで見かけてタイトル買いした一冊。タイトルに掲げられた事実を踏まえ、自分はどう振る舞うべきかを考えさせられる内容だった。 著者は三児の父。関西出身で神奈川郊外の海辺に住み、都内でサラリーマンとして働いている。そんなペルソナの父親が、育児とどう関わっているかが記録されている。遊ぶ時間が短いとわかっていればこそ、日々の関わりは本来尊いもののはずだが、その瞬間にはなかなか実感できない。その前提を踏まえた著者なりの育児奮闘記であり、ノウハウ本というより「こんなことしてます」という日記的なものなのでグイグイ読めた。 自分の今の状況とは子どもの人数や就労状況などが異なるので、単純に重ね合わせることはできないけれども、著者が子どもと一緒に何かをすることに重きを置き、それに全力で応える子どもたちの元気いっぱいな姿が目微笑ましい。 本著で繰り返し唱えていることは、子どもと遊ぶときの「準備」の大切さだ。ただでさえ子どもは色んなことでまごついてしまう。だからこそ、大人サイドの準備不足による時間浪費を最小化して、いかにスムーズに導入し、楽しくできるか。時間があると、つい自分のことに時間を使ってしまいがちだが、子どものいないところで子どもを思って事前に行動しておく必要性を感じた。 読み応えが最もあったのは、子ども二人を連れての四万十川を川下りするパートだった。新宿から夜行バスで高知へ向かい、河原でキャンプをしながら数日かけて川を下る。その冒険譚はどこか椎名誠的だと思っていたら、実際に本人が帯を書いていて腑に落ちた。著者のような行動力はなく、無類のインドア派で行動に移せないことが多いので見習いたい。 本著は2016年の刊行であり、この十年で父親の育児参加を取り巻く状況は大きく変化した。育児休業の実質的な義務化もあいまってコミットする男性は確実に増えている。当時はまだ父親の育児参加が珍しかったこともあってか、「父親」であることを強調する構成は今読むと違和感を感じた。(著者が一人称を「オトン」としていることも、違和感を助長している気がした。)つまり、父と子どもの時間が中心で「家庭の育児」という全体像が見えづらいのだ。育児にコミットしていることは伝わるのだが「非日常はオトン、日常はオカン」という性別役割分担に映るのだった。 当然、男性サイドが育児に参加していなかった状況なので、それを打破するためには男性に育児に対して目を向けさせる必要がある。その認識を基にして、ウェブサイトを作ったり、そこでの連載が本著という形で本になったり、他にも巻末で紹介されているような施策を事業として企画している。そういった草の根の活動があってこそ今があるのは間違いない。 一方で男性が育児を語ることの難しさは、自分が育児のZINEを作って初めて認識したことだった。「男性」という属性が付与されるだけで、もともと女性が日常的に担ってきたことが特別視されてしまう。ある種、下駄を履かされている状態である。自分では、そのあたりのドヤ感が出ないように配慮したつもりでも、本というスタティックな情報になると、そのニュアンスが出てしまう。「育児本」と一言で圧縮してしまうと、こぼれ落ちてしまう話でバランスを取ったつもりだったが、機能しないこともあるのが現状で、結果的にイクメン文脈に回収されてしまう状況について、本著を読んで改めて考えさせられた。
読み終わった大阪帰省の際、blackbird booksで見かけてタイトル買いした一冊。タイトルに掲げられた事実を踏まえ、自分はどう振る舞うべきかを考えさせられる内容だった。 著者は三児の父。関西出身で神奈川郊外の海辺に住み、都内でサラリーマンとして働いている。そんなペルソナの父親が、育児とどう関わっているかが記録されている。遊ぶ時間が短いとわかっていればこそ、日々の関わりは本来尊いもののはずだが、その瞬間にはなかなか実感できない。その前提を踏まえた著者なりの育児奮闘記であり、ノウハウ本というより「こんなことしてます」という日記的なものなのでグイグイ読めた。 自分の今の状況とは子どもの人数や就労状況などが異なるので、単純に重ね合わせることはできないけれども、著者が子どもと一緒に何かをすることに重きを置き、それに全力で応える子どもたちの元気いっぱいな姿が目微笑ましい。 本著で繰り返し唱えていることは、子どもと遊ぶときの「準備」の大切さだ。ただでさえ子どもは色んなことでまごついてしまう。だからこそ、大人サイドの準備不足による時間浪費を最小化して、いかにスムーズに導入し、楽しくできるか。時間があると、つい自分のことに時間を使ってしまいがちだが、子どものいないところで子どもを思って事前に行動しておく必要性を感じた。 読み応えが最もあったのは、子ども二人を連れての四万十川を川下りするパートだった。新宿から夜行バスで高知へ向かい、河原でキャンプをしながら数日かけて川を下る。その冒険譚はどこか椎名誠的だと思っていたら、実際に本人が帯を書いていて腑に落ちた。著者のような行動力はなく、無類のインドア派で行動に移せないことが多いので見習いたい。 本著は2016年の刊行であり、この十年で父親の育児参加を取り巻く状況は大きく変化した。育児休業の実質的な義務化もあいまってコミットする男性は確実に増えている。当時はまだ父親の育児参加が珍しかったこともあってか、「父親」であることを強調する構成は今読むと違和感を感じた。(著者が一人称を「オトン」としていることも、違和感を助長している気がした。)つまり、父と子どもの時間が中心で「家庭の育児」という全体像が見えづらいのだ。育児にコミットしていることは伝わるのだが「非日常はオトン、日常はオカン」という性別役割分担に映るのだった。 当然、男性サイドが育児に参加していなかった状況なので、それを打破するためには男性に育児に対して目を向けさせる必要がある。その認識を基にして、ウェブサイトを作ったり、そこでの連載が本著という形で本になったり、他にも巻末で紹介されているような施策を事業として企画している。そういった草の根の活動があってこそ今があるのは間違いない。 一方で男性が育児を語ることの難しさは、自分が育児のZINEを作って初めて認識したことだった。「男性」という属性が付与されるだけで、もともと女性が日常的に担ってきたことが特別視されてしまう。ある種、下駄を履かされている状態である。自分では、そのあたりのドヤ感が出ないように配慮したつもりでも、本というスタティックな情報になると、そのニュアンスが出てしまう。「育児本」と一言で圧縮してしまうと、こぼれ落ちてしまう話でバランスを取ったつもりだったが、機能しないこともあるのが現状で、結果的にイクメン文脈に回収されてしまう状況について、本著を読んで改めて考えさせられた。 - 2026年2月10日
 なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読み終わったタナハシ・コーツの新作でこのタイトルとなれば読まざるを得ないと思って読んだ。『世界と僕のあいだに』で好きになって、そのあと小説『ウォーターダンサー』を読んだが、アフリカ系アメリカンの立場からアメリカの過去から現在をリリカルに描き出す書き手だという印象を持っている。本著も紀行文の形式でありながら、彼自身の思考をユニークな表現で提示してくれている一冊だった。 第1章ではタイトルどおり「書くこと」に関する論考が展開されるが、それ以降はセネガル、パレスチナ、アメリカ南部を訪れ、自身の目で見て、耳で聴いて得た知見を基に、彼ならではのパースペクティブで現状を分析している。インターネットのおかげで、なんでもわかったような気にはなっていても実際に訪問して見える景色は別物だと痛感させられる。上記の訪問場所は、時間的、精神的にもコストを伴うものであり、コーツほどの筆力であれば行かずとも素晴らしい文章を書けるだろうが、きちんと取材して自分の中で腹落ちしたものがアウトプットとして出てきている書きっぷりに彼の真髄を見た。 邦題は「書くこと」に寄せているが、著者が最初に提示するのは読む必要性である。試合中の不慮の事故で四肢麻痺となったアメフトのワイドレシーバーの話や、シェイクスピアとラキムへの言及を通して、読むことの意味とナラティブの力が語られる。独自の視点でツカミはバッチリだ。 第二章は初めて訪れるアフリカの地・セネガルの旅行記であり、同時にアフリカ論でもある。ワンドロップルールの不条理さをアフリカの視点で、おもしろおかしく描いているところにウィットを感じる。さらにトニ・モリスン『青い目が欲しい』を引用しながら、外見と人種の問題へと接続していく。アフリカを訪れた経験によって西洋的価値観が相対化され、「西洋の枠組みの外側にもカルチャーがある」という主張は、自分の好きなヒップホップやR&Bの在り方を考えさせるものだった。 私たち自身の人生や文化ー音楽、ダンス、書くことーはすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。 ちょうど選挙のタイミングで読んでいたこともあり、サウス・カロライナ州を訪れて教育委員会の会議に参加する第三章が一番グッときた。著作である『世界と僕のあいだに』が禁書になりそうという話を聞きつけて、現場に自ら足を運ぶ。そこでは賛成派、反対派による派手な衝突が起こるわけではないのだが、禁書に反対する市民がその場で意思表示を行い、誤った判断が是正されていく。そんな当たり前とも言える場面が印象に残った。こういった市民活動の成功体験が政治との距離を縮め、市民の連帯が民主主義を支えているのだと感じた。今の日本に必要なことはこうした生身の横の連帯なのではないか。必要以上に個別化が進み、接触頻度の高いSNSの情報に振り回される現状が、本著を読むと空虚に映った。 そして、もっともページ数を割いているのが、パレスチナ訪問に関する4章である。今に至るまで続く紛争以前のパレスチナの日常や社会の空気といったリアルな実情を手記で読めることが貴重である。外形的な情報はネットや専門書で得ることができるかもしれないが、パーソナルな視点と論考を行き来する構成だからこそ地に足がついている印象を持った。 著者ならではの視点といえば、アメリカにおけるアフリカ系アメリカンと、イスラエルにおけるパレスチナ人の立場の比較であろう。人種差別の被害者であった歴史を持つユダヤ人が、パレスチナ人に対して加害者として振る舞っている現実に驚いた。真綿で首を締めるようなイスラエルからパレスチナ人に対する迫害の状況に読んでいて苦しい。さらにアメリカとイスラエルの複雑な関係性が、アフリカ系アメリカンである著者がパレスチナを訪れる過程のなかで徐々に立ち現れる。読者は著者に伴走するように未知の過酷な現実を知っていくことになりスリリングだった。 著者は過去と現在を接続して自分のリアルな手触りを語り下ろしていく手腕が本当に見事だなと今回も感じた。調査能力もありながら、その結果を噛み砕き、さらには自分の経験もスムーズに混ぜ込んでいく、エッセイ以上論文未満のこの塩梅が、個人的にはとても心地よい。このブログや日本語ラップのnoteも著者のようなスタイルでやっていきたい。 書くこと、書き直してゆくことは、たんに真実を伝えるだけでなく、真実がもたらす恍惚をも伝えようとする営みなのだ。私にとっては、読者に私の主張を納得させるだけでは十分ではない。私が一人で感じているあの特別な歓びをともに感じてほしいのだ。世のなかで、誰かがその歓びの一部でも共有したと聞くことは嬉しいものだ。
なぜ書くのかタナハシ・コーツ,池田年穂読み終わったタナハシ・コーツの新作でこのタイトルとなれば読まざるを得ないと思って読んだ。『世界と僕のあいだに』で好きになって、そのあと小説『ウォーターダンサー』を読んだが、アフリカ系アメリカンの立場からアメリカの過去から現在をリリカルに描き出す書き手だという印象を持っている。本著も紀行文の形式でありながら、彼自身の思考をユニークな表現で提示してくれている一冊だった。 第1章ではタイトルどおり「書くこと」に関する論考が展開されるが、それ以降はセネガル、パレスチナ、アメリカ南部を訪れ、自身の目で見て、耳で聴いて得た知見を基に、彼ならではのパースペクティブで現状を分析している。インターネットのおかげで、なんでもわかったような気にはなっていても実際に訪問して見える景色は別物だと痛感させられる。上記の訪問場所は、時間的、精神的にもコストを伴うものであり、コーツほどの筆力であれば行かずとも素晴らしい文章を書けるだろうが、きちんと取材して自分の中で腹落ちしたものがアウトプットとして出てきている書きっぷりに彼の真髄を見た。 邦題は「書くこと」に寄せているが、著者が最初に提示するのは読む必要性である。試合中の不慮の事故で四肢麻痺となったアメフトのワイドレシーバーの話や、シェイクスピアとラキムへの言及を通して、読むことの意味とナラティブの力が語られる。独自の視点でツカミはバッチリだ。 第二章は初めて訪れるアフリカの地・セネガルの旅行記であり、同時にアフリカ論でもある。ワンドロップルールの不条理さをアフリカの視点で、おもしろおかしく描いているところにウィットを感じる。さらにトニ・モリスン『青い目が欲しい』を引用しながら、外見と人種の問題へと接続していく。アフリカを訪れた経験によって西洋的価値観が相対化され、「西洋の枠組みの外側にもカルチャーがある」という主張は、自分の好きなヒップホップやR&Bの在り方を考えさせるものだった。 私たち自身の人生や文化ー音楽、ダンス、書くことーはすべてこの「文明」の壁の外側という不条理な空間で形作られてきた。これが私たちの団結した力となる。 ちょうど選挙のタイミングで読んでいたこともあり、サウス・カロライナ州を訪れて教育委員会の会議に参加する第三章が一番グッときた。著作である『世界と僕のあいだに』が禁書になりそうという話を聞きつけて、現場に自ら足を運ぶ。そこでは賛成派、反対派による派手な衝突が起こるわけではないのだが、禁書に反対する市民がその場で意思表示を行い、誤った判断が是正されていく。そんな当たり前とも言える場面が印象に残った。こういった市民活動の成功体験が政治との距離を縮め、市民の連帯が民主主義を支えているのだと感じた。今の日本に必要なことはこうした生身の横の連帯なのではないか。必要以上に個別化が進み、接触頻度の高いSNSの情報に振り回される現状が、本著を読むと空虚に映った。 そして、もっともページ数を割いているのが、パレスチナ訪問に関する4章である。今に至るまで続く紛争以前のパレスチナの日常や社会の空気といったリアルな実情を手記で読めることが貴重である。外形的な情報はネットや専門書で得ることができるかもしれないが、パーソナルな視点と論考を行き来する構成だからこそ地に足がついている印象を持った。 著者ならではの視点といえば、アメリカにおけるアフリカ系アメリカンと、イスラエルにおけるパレスチナ人の立場の比較であろう。人種差別の被害者であった歴史を持つユダヤ人が、パレスチナ人に対して加害者として振る舞っている現実に驚いた。真綿で首を締めるようなイスラエルからパレスチナ人に対する迫害の状況に読んでいて苦しい。さらにアメリカとイスラエルの複雑な関係性が、アフリカ系アメリカンである著者がパレスチナを訪れる過程のなかで徐々に立ち現れる。読者は著者に伴走するように未知の過酷な現実を知っていくことになりスリリングだった。 著者は過去と現在を接続して自分のリアルな手触りを語り下ろしていく手腕が本当に見事だなと今回も感じた。調査能力もありながら、その結果を噛み砕き、さらには自分の経験もスムーズに混ぜ込んでいく、エッセイ以上論文未満のこの塩梅が、個人的にはとても心地よい。このブログや日本語ラップのnoteも著者のようなスタイルでやっていきたい。 書くこと、書き直してゆくことは、たんに真実を伝えるだけでなく、真実がもたらす恍惚をも伝えようとする営みなのだ。私にとっては、読者に私の主張を納得させるだけでは十分ではない。私が一人で感じているあの特別な歓びをともに感じてほしいのだ。世のなかで、誰かがその歓びの一部でも共有したと聞くことは嬉しいものだ。 - 2026年2月5日
 フェミニズム入門大越愛子読み終わったずっと読もうと思っていた中で友人からレコメンドしてもらって、ついに読んだ。今読むと新書とは到底思えないほど専門的内容が詰まっており、フェミニズムの学問的側面を知る上で興味深い一冊だった。 フェミニズム研究者である著者によるタイトルどおりの入門書。初版は1996年で、ちょうど30年前の本になる。正直、本著を読むまでは「フェミニズム」と聞いても「女性が奪われてきた権利を奪還していくための思想体系」くらいの印象しか持っていなかった。しかし、実際にはフェミニズムと一言にいっても多様な立場が存在する。思想体系という横の広がりと、歴史という縦の深さ、両方をカバーしてくれているので、2000年直前までのフェミニズムの全体像とグラデーションを把握することが可能となっている。 冒頭、<女性に関することなら何でもフェミニズムであると誤解しているお気楽な輩>とあり、いきなり首根っこを掴まれたような気持ちになった。第一章は当時のフェミニズムの立脚点を宣言するような文章であり、未来への期待も感じさせる。 本著を読んで最初に驚いたのは、第二章で紹介されているフェミニズムの多様さである。9つもの潮流が紹介されており、これらをすべて一括りに考えてしまうから、理解が進まないのかもしれない。個人的には「精神分析派フェミニズム」における、ナンシー・チョドロウの主張が印象的だった。性的役割分業が従来から変わらず、母親のみが育児を担うという性的役割分業がジェンダー差異を生み、性別意識を再生産するという指摘は、男性の育児参加がフェミニズムと接続していることを示している。男性として育児ZINEまで作った身としては驚いたのだった。 チョドロウは、このようなプロセスで形成される心理的性差は、性別役割分業体制の産物であるから、分業の解体、特に「初期の親業を男女で分かち合う」ことが、男女間の情緒の非対称性を変えていくことになると示唆している。彼女の理論は、性別役割分業の改変が、男女の外的存在形態のみならず、心理的存在形態も変革せしめるという、実践的な問題提起を行っていて、大きな影響力をもっている。 日本におけるフェミニズムの歴史を深堀りしてくれている点も勉強になった。平塚らいてうなんて、学生の頃の教科書で見た歴史上の人物の一人でしかなかったが、本著を読むと彼女の来歴や思想を具体的に知ることができて興味深かった。母性主義を掲げているがゆえに近代天皇制の家族主義に取り込まれ、フェミニズムが弱体化していく流れは全く知らず、国ごとの社会背景によってフェミニズムの様相が大きく異なることを知った。 そのあと、戦後のフェミニズムへと流れていくのだが、日本のフェミニズムが他責ではなく自責に向かってしまったという見立ても興味深い。新左翼の影響を受け、自己否定や自己批判を基に、女性自身の内面分析へと向かっていく。外部の制度的抑圧が問題であるにもかかわらず、社会制度を批判するのではなく、自身の内部に解決を求める姿勢は、どこか日本的にも思える。 日本のフェミニズムといえば上野千鶴子が頭に思い浮かぶが、本著では彼女の功罪を冷静に分析している。フェミニズムを女性の問題から家族の問題へと転換し、性別役割分担という男女関係の問題として提示したことで大衆化に成功した一方、女性の搾取構造そのものが見えにくくなったという指摘は新鮮だった。こうした学問的対立の存在を知れたことも収穫であり、上野自身の議論も読んでみたいと思わされた。このように興味の射程を広げてくれる点で、本著は確かに入門書として機能している。 最後の章では家父長制、ジェンダー、性暴力といったテーマがフェミニズムの理論的解釈と共に紹介されている。このパートが一番興味深かった。当然、フェミニズムの実践となれば、具体的な行動がなければ現実は変わらない。それゆえ、具体的な事象について取り上げる場面を多く見るが、その事象の背景にどういった学問的理論があるか。それを知っているか、知らないかで解像度は変わるだろう。そういった意味で、本著はフェミニズム的問題を新しい切り口から理解するための視点を与えてくれる。 ただ、著者はむすびで、理論に傾倒することがフェミニズムではないと述べている。繰り返しになるが、あくまで日常的な実践を伴ってこそ現実は変化していくからだ。 フェミニズムは、人間的現実を突きつけて、何重にも錯綜した欺瞞や仮象の体系を解体しようとする、日常的、理論的実践である。解体の後に何がくるのか、それを発見していくことにこそ、尽きせぬ快楽の泉があるといえるかもしれない。 女性の首相が誕生したこと自体はジェンダーバランスの上では歓迎すべきことだが、彼女が日本の歪なジェンダーバランスの是正に積極的かといえば、そうとは言えない状況である。これだけではないけども、今回の選挙までの流れふくめて、国民は舐められまくっているわけで、選挙で自分の民意を示していきたい。みんな選挙いこ!(定期)
フェミニズム入門大越愛子読み終わったずっと読もうと思っていた中で友人からレコメンドしてもらって、ついに読んだ。今読むと新書とは到底思えないほど専門的内容が詰まっており、フェミニズムの学問的側面を知る上で興味深い一冊だった。 フェミニズム研究者である著者によるタイトルどおりの入門書。初版は1996年で、ちょうど30年前の本になる。正直、本著を読むまでは「フェミニズム」と聞いても「女性が奪われてきた権利を奪還していくための思想体系」くらいの印象しか持っていなかった。しかし、実際にはフェミニズムと一言にいっても多様な立場が存在する。思想体系という横の広がりと、歴史という縦の深さ、両方をカバーしてくれているので、2000年直前までのフェミニズムの全体像とグラデーションを把握することが可能となっている。 冒頭、<女性に関することなら何でもフェミニズムであると誤解しているお気楽な輩>とあり、いきなり首根っこを掴まれたような気持ちになった。第一章は当時のフェミニズムの立脚点を宣言するような文章であり、未来への期待も感じさせる。 本著を読んで最初に驚いたのは、第二章で紹介されているフェミニズムの多様さである。9つもの潮流が紹介されており、これらをすべて一括りに考えてしまうから、理解が進まないのかもしれない。個人的には「精神分析派フェミニズム」における、ナンシー・チョドロウの主張が印象的だった。性的役割分業が従来から変わらず、母親のみが育児を担うという性的役割分業がジェンダー差異を生み、性別意識を再生産するという指摘は、男性の育児参加がフェミニズムと接続していることを示している。男性として育児ZINEまで作った身としては驚いたのだった。 チョドロウは、このようなプロセスで形成される心理的性差は、性別役割分業体制の産物であるから、分業の解体、特に「初期の親業を男女で分かち合う」ことが、男女間の情緒の非対称性を変えていくことになると示唆している。彼女の理論は、性別役割分業の改変が、男女の外的存在形態のみならず、心理的存在形態も変革せしめるという、実践的な問題提起を行っていて、大きな影響力をもっている。 日本におけるフェミニズムの歴史を深堀りしてくれている点も勉強になった。平塚らいてうなんて、学生の頃の教科書で見た歴史上の人物の一人でしかなかったが、本著を読むと彼女の来歴や思想を具体的に知ることができて興味深かった。母性主義を掲げているがゆえに近代天皇制の家族主義に取り込まれ、フェミニズムが弱体化していく流れは全く知らず、国ごとの社会背景によってフェミニズムの様相が大きく異なることを知った。 そのあと、戦後のフェミニズムへと流れていくのだが、日本のフェミニズムが他責ではなく自責に向かってしまったという見立ても興味深い。新左翼の影響を受け、自己否定や自己批判を基に、女性自身の内面分析へと向かっていく。外部の制度的抑圧が問題であるにもかかわらず、社会制度を批判するのではなく、自身の内部に解決を求める姿勢は、どこか日本的にも思える。 日本のフェミニズムといえば上野千鶴子が頭に思い浮かぶが、本著では彼女の功罪を冷静に分析している。フェミニズムを女性の問題から家族の問題へと転換し、性別役割分担という男女関係の問題として提示したことで大衆化に成功した一方、女性の搾取構造そのものが見えにくくなったという指摘は新鮮だった。こうした学問的対立の存在を知れたことも収穫であり、上野自身の議論も読んでみたいと思わされた。このように興味の射程を広げてくれる点で、本著は確かに入門書として機能している。 最後の章では家父長制、ジェンダー、性暴力といったテーマがフェミニズムの理論的解釈と共に紹介されている。このパートが一番興味深かった。当然、フェミニズムの実践となれば、具体的な行動がなければ現実は変わらない。それゆえ、具体的な事象について取り上げる場面を多く見るが、その事象の背景にどういった学問的理論があるか。それを知っているか、知らないかで解像度は変わるだろう。そういった意味で、本著はフェミニズム的問題を新しい切り口から理解するための視点を与えてくれる。 ただ、著者はむすびで、理論に傾倒することがフェミニズムではないと述べている。繰り返しになるが、あくまで日常的な実践を伴ってこそ現実は変化していくからだ。 フェミニズムは、人間的現実を突きつけて、何重にも錯綜した欺瞞や仮象の体系を解体しようとする、日常的、理論的実践である。解体の後に何がくるのか、それを発見していくことにこそ、尽きせぬ快楽の泉があるといえるかもしれない。 女性の首相が誕生したこと自体はジェンダーバランスの上では歓迎すべきことだが、彼女が日本の歪なジェンダーバランスの是正に積極的かといえば、そうとは言えない状況である。これだけではないけども、今回の選挙までの流れふくめて、国民は舐められまくっているわけで、選挙で自分の民意を示していきたい。みんな選挙いこ!(定期) - 2026年2月3日
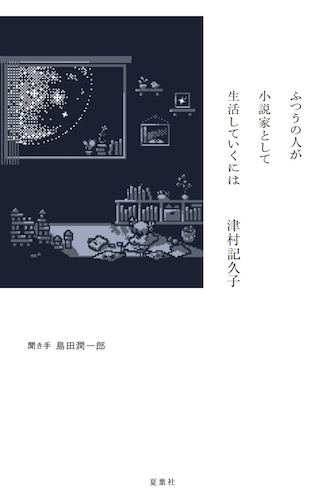 ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった@ 1003 -センサン-大阪帰省のタイミングで1003に立ち寄った際に友人共々購入した。買ったときは気づいてなかったが、実は感慨深い出来事だった。というのも、著者の熱烈なファンだった、その友人にレコメンドされて著者の小説を読んできたからだ。そんな運命論めいた話はさておき、対談本として無類の面白さだった。一日で読み切れるようなボリュームながらも、人生の土台になるような大事なことが詰まっており、友人全員に読んで欲しいと思う本だった。 本著は夏葉社からリリースされており、同社代表である島崎潤一郎自らが相手を務める対談本となっている。津村記久子といえば、先述の通り、2010年代の日本文学を代表する作家の一人だ。大仰な物語を振りかざすのではなく、卑近な日常や労働のリアルを淡々と描くタイプの作家だ。特に労働に関する小説群はリアリティが高く、前述のとおり当時好んで読んでいた。 そんな著者の人生を振り返りながら、タイトルどおり小説家として、どうやって生きてきたのか、ざっくばらんに対談しているのだが、このざっくばらん感がたまらない。かしこまったインタビューではなく、同世代の二人が就職氷河期という時代背景を共有しながら、脱線しつつ「ふつうの会話」を繰り広げ、その中で顔をのぞかせる本質の数々は、人生で大切にしたいと思えることばかりだ。 一番グッときたことは好きなものを見つけること、ディグ力に関する話だった。最近はレコード文化以外でも「ディグる」という言葉が一般的になっているが、若い頃に好きなものを自力で見つけた経験があるかどうかが大事で、それは知識量とは関係がない。あくまで自分が好きかどうかの琴線を作る姿勢の大切さが説かれていた。 また、その琴線を作り上げるのにギャンブルが必要という指摘も今の時代だからこそ腑に落ちた。今はレコメンド技術が発達しすぎて、失敗せずに「正解」に辿り着けてしまう。しかし、予定調和ではないもの、自分にとって「好きじゃないもの」に遭遇することには、意味と尊さがある。タイパ重視の若い世代からすれば「うぜーな、おっさん」と一言で瞬殺されるかもしれないが、「無駄な出会い」こそが血肉になる感覚は、世代的に納得感があった。インスタントでポップなものだけを消費するのと、自分の直感を信じて泥臭く好きなものを追いかけるのとでは、二者間のギャップは大きくなるなと大人になればなるほど感じることだ。こういった根源的な部分について、改めて小説家と出版人という職業の方が語っていることに意味がある。 そして、ディグ力=見つける力こそが、小説家として著者の原動力だという主張も興味深かった。小説家というのは、どちらかと言えば、多くの場合スルーされるような日常の場面でも、鋭い観察眼で新たな側面を拾い出すイメージが強い。それは掬い取る、いわば水平方向の能力だが、垂直方向の能力であるディグを重要視しているのは意外だった。 小説執筆の具体的な話が本著のハイライトであろう。テーマ設定、アプローチといった抽象的な話にとどまらず「具体的にどの時間にどうやって書いているか」を包み隠さず開陳してくれており、小説執筆に限らない広い意味での仕事におけるプロダクティビティ論になっており読んでいて楽しい。なかでもニュースサイトの「ライフハッカー」を読んでいた話や、独自のポモドーロテクニックへと至る流れが元会社員らしさを感じるエピソードだった。「ライフハッカー」を読んでいた著者らしい表現として、自らを「オープンソースで形成されている」と言っている場面は笑った。それを踏まえて放たれる「コントロールできるのは自分の人生だけ」という言葉には説得力があった。 著者が『アレグリアとは仕事はできない』という作品で、コピー機のことを書いた経緯が興味深かった。自分にしか書けない身の回りのディテールをアートに昇華させること。これは私の好きなラッパーであるSEEDAによる「けん玉理論」の小説による実践であり、ここがリンクするとは思わず興奮した。また、著者は生来のなにか、才能などに興味はなく「行動」を書きたいという主張から、なぜ著者の仕事小説が面白いのか納得した。未読の作品がまだまだあるので、これをきっかけに色々読んでいきたい。
ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった@ 1003 -センサン-大阪帰省のタイミングで1003に立ち寄った際に友人共々購入した。買ったときは気づいてなかったが、実は感慨深い出来事だった。というのも、著者の熱烈なファンだった、その友人にレコメンドされて著者の小説を読んできたからだ。そんな運命論めいた話はさておき、対談本として無類の面白さだった。一日で読み切れるようなボリュームながらも、人生の土台になるような大事なことが詰まっており、友人全員に読んで欲しいと思う本だった。 本著は夏葉社からリリースされており、同社代表である島崎潤一郎自らが相手を務める対談本となっている。津村記久子といえば、先述の通り、2010年代の日本文学を代表する作家の一人だ。大仰な物語を振りかざすのではなく、卑近な日常や労働のリアルを淡々と描くタイプの作家だ。特に労働に関する小説群はリアリティが高く、前述のとおり当時好んで読んでいた。 そんな著者の人生を振り返りながら、タイトルどおり小説家として、どうやって生きてきたのか、ざっくばらんに対談しているのだが、このざっくばらん感がたまらない。かしこまったインタビューではなく、同世代の二人が就職氷河期という時代背景を共有しながら、脱線しつつ「ふつうの会話」を繰り広げ、その中で顔をのぞかせる本質の数々は、人生で大切にしたいと思えることばかりだ。 一番グッときたことは好きなものを見つけること、ディグ力に関する話だった。最近はレコード文化以外でも「ディグる」という言葉が一般的になっているが、若い頃に好きなものを自力で見つけた経験があるかどうかが大事で、それは知識量とは関係がない。あくまで自分が好きかどうかの琴線を作る姿勢の大切さが説かれていた。 また、その琴線を作り上げるのにギャンブルが必要という指摘も今の時代だからこそ腑に落ちた。今はレコメンド技術が発達しすぎて、失敗せずに「正解」に辿り着けてしまう。しかし、予定調和ではないもの、自分にとって「好きじゃないもの」に遭遇することには、意味と尊さがある。タイパ重視の若い世代からすれば「うぜーな、おっさん」と一言で瞬殺されるかもしれないが、「無駄な出会い」こそが血肉になる感覚は、世代的に納得感があった。インスタントでポップなものだけを消費するのと、自分の直感を信じて泥臭く好きなものを追いかけるのとでは、二者間のギャップは大きくなるなと大人になればなるほど感じることだ。こういった根源的な部分について、改めて小説家と出版人という職業の方が語っていることに意味がある。 そして、ディグ力=見つける力こそが、小説家として著者の原動力だという主張も興味深かった。小説家というのは、どちらかと言えば、多くの場合スルーされるような日常の場面でも、鋭い観察眼で新たな側面を拾い出すイメージが強い。それは掬い取る、いわば水平方向の能力だが、垂直方向の能力であるディグを重要視しているのは意外だった。 小説執筆の具体的な話が本著のハイライトであろう。テーマ設定、アプローチといった抽象的な話にとどまらず「具体的にどの時間にどうやって書いているか」を包み隠さず開陳してくれており、小説執筆に限らない広い意味での仕事におけるプロダクティビティ論になっており読んでいて楽しい。なかでもニュースサイトの「ライフハッカー」を読んでいた話や、独自のポモドーロテクニックへと至る流れが元会社員らしさを感じるエピソードだった。「ライフハッカー」を読んでいた著者らしい表現として、自らを「オープンソースで形成されている」と言っている場面は笑った。それを踏まえて放たれる「コントロールできるのは自分の人生だけ」という言葉には説得力があった。 著者が『アレグリアとは仕事はできない』という作品で、コピー機のことを書いた経緯が興味深かった。自分にしか書けない身の回りのディテールをアートに昇華させること。これは私の好きなラッパーであるSEEDAによる「けん玉理論」の小説による実践であり、ここがリンクするとは思わず興奮した。また、著者は生来のなにか、才能などに興味はなく「行動」を書きたいという主張から、なぜ著者の仕事小説が面白いのか納得した。未読の作品がまだまだあるので、これをきっかけに色々読んでいきたい。 - 2026年1月31日
 すべての罪は血を流すS・A・コスビー,加賀山卓朗読み終わったPEPCEE&YOSHIMARLによる新しいアルバム『STONE COLD』に触発されて積んであったクライムノベルを読んだ。著者の作品を読むのは二作目だが、今回もページターナーっぷりは健在で他の追随を許さない圧倒的なレベルだった。 主人公は保安官のタイタス。アフリカ系アメリカンによる高校での銃撃事件を発端に、次々と発覚していく陰惨な事件を追っていく物語である。舞台がアメリカ南部ということもあり、宗教や人種という現代アメリカの根深い問題をメインテーマに据えつつ、銃、ドラッグ、ペドファイルといった個別の具体的な問題がその上に乗っかってくる。プロットの面白さだけではなく、南部の空気を体感できる点が、本著が並のクライムノベルと異なるところだ。 警察官を主人公に据えると、勧善懲悪の単純な構図に陥りがちだが、タイタスはFBI勤務時代の暗い過去を引きずっており、清廉潔白な正義漢ではない。グレーなニュアンスがあるからこそ、物語にスムーズに乗ることができた。一方で追いかける犯人の悪っぷりは今まで読んできたクライムノベルの中でも屈指の悪。タイトルどおり血が流れまくりだし、描かれる殺人はいずれも陰惨極まりない。情状酌量できる余地がないほどおぞましいからこそ、誰が犯人なのか、どんな結末を迎えるのかと読む手がドライブさせられた。 アクション描写も圧巻だった。特に犯人とのバトルはいずれも手に汗を握る展開で、終盤まで積み上げられてきた凄惨な犯行描写によって膨れ上がった犯人像が明らかになった挙句のバトルなので読み応えがあった。 今回は宗教が大きなテーマということもあり、以前に読んだ『黒き荒野の果て』よりも著者の筆が乗っている印象を受けた。聖書やシェイクスピアといったクラシックの引用が物語に厚みを加え、それに呼応するような著者独特の言い回しもかっこいい。たとえば、主人公の母の格言として語られる「真実がズポンを引き上げているあいだに、嘘は地球を半周する」SNS以後のポストトゥルースな状況をこんな短い言葉で的確に表現していて、ラッパーさながらである。 アフリカ系アメリカンが白人を銃殺したけれども、その白人が実はペドフィリアで…といった具合に、問題がインターセクションしていく構造も印象的だった。安易な二元論に回収されることを拒む、著者なりの工夫であろう。アフリカ系アメリカンが置かれてきた不遇な立場を大前提としながらも、それだけに閉じない人間同士による凄惨な争いが展開するゆえ、業の深さを感じさせられた。 「宗教もドラッグも依存という観点では変わらない」と考えるタイタスが、登場人物の中で一番と言っていいほど聖書に詳しい人物として描かれている点は皮肉と言える。どれほど神の存在を信じていても、母親は早くに亡くなり、子どもたちは無惨に命を奪われる。こんなひどい状況でも「すべては神の御心」という言葉で腹落ちさせる信仰に、一体どんな意味があるのか。タイタスは深く信仰していたからこそ裏切られた気持ちが強く、それゆえに秩序、忍耐という新たな信仰へと向かわせる。この姿勢は実質的に無宗教な人が多い日本人には刺さりやすいだろう。そして、犯人は別ベクトルで信仰に付随した裏切りを受けた結果の末路であることを考えれば、宗教に振り回された人生という観点で二人は似たもの同士かもしれない。次は『頬に哀しみを刻め』を読みたい。
すべての罪は血を流すS・A・コスビー,加賀山卓朗読み終わったPEPCEE&YOSHIMARLによる新しいアルバム『STONE COLD』に触発されて積んであったクライムノベルを読んだ。著者の作品を読むのは二作目だが、今回もページターナーっぷりは健在で他の追随を許さない圧倒的なレベルだった。 主人公は保安官のタイタス。アフリカ系アメリカンによる高校での銃撃事件を発端に、次々と発覚していく陰惨な事件を追っていく物語である。舞台がアメリカ南部ということもあり、宗教や人種という現代アメリカの根深い問題をメインテーマに据えつつ、銃、ドラッグ、ペドファイルといった個別の具体的な問題がその上に乗っかってくる。プロットの面白さだけではなく、南部の空気を体感できる点が、本著が並のクライムノベルと異なるところだ。 警察官を主人公に据えると、勧善懲悪の単純な構図に陥りがちだが、タイタスはFBI勤務時代の暗い過去を引きずっており、清廉潔白な正義漢ではない。グレーなニュアンスがあるからこそ、物語にスムーズに乗ることができた。一方で追いかける犯人の悪っぷりは今まで読んできたクライムノベルの中でも屈指の悪。タイトルどおり血が流れまくりだし、描かれる殺人はいずれも陰惨極まりない。情状酌量できる余地がないほどおぞましいからこそ、誰が犯人なのか、どんな結末を迎えるのかと読む手がドライブさせられた。 アクション描写も圧巻だった。特に犯人とのバトルはいずれも手に汗を握る展開で、終盤まで積み上げられてきた凄惨な犯行描写によって膨れ上がった犯人像が明らかになった挙句のバトルなので読み応えがあった。 今回は宗教が大きなテーマということもあり、以前に読んだ『黒き荒野の果て』よりも著者の筆が乗っている印象を受けた。聖書やシェイクスピアといったクラシックの引用が物語に厚みを加え、それに呼応するような著者独特の言い回しもかっこいい。たとえば、主人公の母の格言として語られる「真実がズポンを引き上げているあいだに、嘘は地球を半周する」SNS以後のポストトゥルースな状況をこんな短い言葉で的確に表現していて、ラッパーさながらである。 アフリカ系アメリカンが白人を銃殺したけれども、その白人が実はペドフィリアで…といった具合に、問題がインターセクションしていく構造も印象的だった。安易な二元論に回収されることを拒む、著者なりの工夫であろう。アフリカ系アメリカンが置かれてきた不遇な立場を大前提としながらも、それだけに閉じない人間同士による凄惨な争いが展開するゆえ、業の深さを感じさせられた。 「宗教もドラッグも依存という観点では変わらない」と考えるタイタスが、登場人物の中で一番と言っていいほど聖書に詳しい人物として描かれている点は皮肉と言える。どれほど神の存在を信じていても、母親は早くに亡くなり、子どもたちは無惨に命を奪われる。こんなひどい状況でも「すべては神の御心」という言葉で腹落ちさせる信仰に、一体どんな意味があるのか。タイタスは深く信仰していたからこそ裏切られた気持ちが強く、それゆえに秩序、忍耐という新たな信仰へと向かわせる。この姿勢は実質的に無宗教な人が多い日本人には刺さりやすいだろう。そして、犯人は別ベクトルで信仰に付随した裏切りを受けた結果の末路であることを考えれば、宗教に振り回された人生という観点で二人は似たもの同士かもしれない。次は『頬に哀しみを刻め』を読みたい。 - 2026年1月26日
 鹽津城飛浩隆読み終わったSFの本を選ぶとき、国内SFが選択肢に入ることが少ない。私はヒップホップが好きなのだが、それに例えればUSのヒップホップばかり聞いて日本のヒップホップを聞いていないことになり「それはちゃうやろ」という気持ちで国内SFを少しずつ読むようになった。本著はマイフェイバリットポッドキャストであり、私にとって数少ない国内SFガイドである『美玉ラジオ』で知ったのだった。これぞ国産SF!というドメスティックな要素、展開の数々を楽しく読んだ。 本著は基本的には短編集であり、タイトル作が中篇となっている。全体の特徴としてまず挙げたいのは、登場人物や作中内の現象の名称が、見たことない漢字だらけであることだ。これだけ「読んだことがない漢字」に遭遇するのも久しぶりで小説という表現の自由さを味わった。また、複数の時間軸を並行して描き、それらの関係性を構築することに注力していることが伺える。その構築においては、わかりやすさよりも、著者本人にとっての確からしさを重視しているように伝わってきた。さらに、物語に明確なカタルシスを用意していない点も特徴的だ。なにかが始まるかもしれない期待だけが差し出され、読者には想像できる余地が残されているので余韻がある。 著者の作品を読むのは初めてだし、ポッドキャストでもタイトル作中心に話されていたので、冒頭の「羊の木」の得体の知れなさに面食らった。新海誠『君の名は。』のアダルティ版とも言える、時空を超えた交錯劇。続く「ジュブナイル」もサイエンスフィクションというよりも少し不思議な話であり、こういうトーンなのかと思いきや、「流下の日」でギアが変わって一気にSF色が濃くなっていく。 「流下の日」は、近未来の功利主義や管理社会を描いた作品で、一番好きな話だ。日本が独自のテクノロジーで唯我独尊で発展を成し遂げてきたように描写しながら、後半にかけて、実態はビッグブラザーだったという裏切り方が巧みだった。また、同性愛を含めて「家族」の範囲を拡張しつつも、家という組織単位をより強固にしていくという設定も興味深い。一見、リベラルなのだが、実のところは保守という構図から、現実ではいまだに「家族」の範囲さえ広がらないディストピアというアイロニーにも映った。 SFを読むときにもっとも楽しみにしているのは、どのような近未来テクノロジーが導入されているか、という点だ。「流下の日」では生物学的なアプローチで、身体に埋め込まれたバングルによって、あらゆる行動が制御され、また制御されてしまう。政府が個人の思想や活動に干渉する社会の中で、主人公たちはレジスタンスとして、バングルに支配されない世界を心の中に構築する。それを「中庭」と呼ぶネーミングがかっこいい。英語ではなく、漢字二文字でSF的概念を表現していくところに国産SFらしさがあるし、実在する中庭から展開していく仕掛けもオモシロかった。インターネットを通じて、私たちは心の「中庭」を他人にどんどん開放しているが、誰にも入らせない思考の「中庭」を持つことの重要さを教えてもらった気がした。 もっとも壮大な話がタイトル作の「鹽津城」である。三つの時間軸が並行し、シンクロしながら物語が進行していく。ここでテーマになるのは海と塩である。海水中の塩化ナトリウムが突如結晶化して街を破壊していく現象と、身体の中に塩分濃度の異常に高い、細い線条が形成される病気、二つの謎を中心として物語が描かれる。原発を絡めていることから、東日本大震災をモチーフにしていることはあきらかだが、あの出来事かこれほど跳躍力のある物語を紡げるのは、日本のSF作家ならではの視点だと思う。そこに『ワンピース』的な漫画の要素が合わさってくることで、こういった物語こそが本当の意味での「クールジャパン」なのではないか、と感じた。 塩化ナトリウムだけが海水から分離、凝固する科学的背景として「マックスウェルの悪魔」が引用されており、ネタ元を明示してくれる点も興味深い。さらに同じ分子挙動の不思議さについて、チューリングによる反応拡散方程式による生物の模様形成にも接続し、思考がどんどん広がっていく。それに呼応した表紙はさすがの川名潤ワークスだし、このように科学的想像力を足場にして物語が展開するSFならではの醍醐味があった。 マックスウェル、どこかで聞いた覚えがあるなと思ったら、「マクスウェル分布」のことだった。久しぶりにWikipediaでそれを眺めていると大学院入試で勉強した記憶がよみがえった。当時は本当に嫌だったし、今数式を見てもぼんやりとしか思い出せないが、こうやってSFの題材として出てくると「どういう意味なんだろう?」と興味が湧くのだから、エデュテイメントとしてのSFは偉大さである。寡作な作家のようなので、他も読んでみる。
鹽津城飛浩隆読み終わったSFの本を選ぶとき、国内SFが選択肢に入ることが少ない。私はヒップホップが好きなのだが、それに例えればUSのヒップホップばかり聞いて日本のヒップホップを聞いていないことになり「それはちゃうやろ」という気持ちで国内SFを少しずつ読むようになった。本著はマイフェイバリットポッドキャストであり、私にとって数少ない国内SFガイドである『美玉ラジオ』で知ったのだった。これぞ国産SF!というドメスティックな要素、展開の数々を楽しく読んだ。 本著は基本的には短編集であり、タイトル作が中篇となっている。全体の特徴としてまず挙げたいのは、登場人物や作中内の現象の名称が、見たことない漢字だらけであることだ。これだけ「読んだことがない漢字」に遭遇するのも久しぶりで小説という表現の自由さを味わった。また、複数の時間軸を並行して描き、それらの関係性を構築することに注力していることが伺える。その構築においては、わかりやすさよりも、著者本人にとっての確からしさを重視しているように伝わってきた。さらに、物語に明確なカタルシスを用意していない点も特徴的だ。なにかが始まるかもしれない期待だけが差し出され、読者には想像できる余地が残されているので余韻がある。 著者の作品を読むのは初めてだし、ポッドキャストでもタイトル作中心に話されていたので、冒頭の「羊の木」の得体の知れなさに面食らった。新海誠『君の名は。』のアダルティ版とも言える、時空を超えた交錯劇。続く「ジュブナイル」もサイエンスフィクションというよりも少し不思議な話であり、こういうトーンなのかと思いきや、「流下の日」でギアが変わって一気にSF色が濃くなっていく。 「流下の日」は、近未来の功利主義や管理社会を描いた作品で、一番好きな話だ。日本が独自のテクノロジーで唯我独尊で発展を成し遂げてきたように描写しながら、後半にかけて、実態はビッグブラザーだったという裏切り方が巧みだった。また、同性愛を含めて「家族」の範囲を拡張しつつも、家という組織単位をより強固にしていくという設定も興味深い。一見、リベラルなのだが、実のところは保守という構図から、現実ではいまだに「家族」の範囲さえ広がらないディストピアというアイロニーにも映った。 SFを読むときにもっとも楽しみにしているのは、どのような近未来テクノロジーが導入されているか、という点だ。「流下の日」では生物学的なアプローチで、身体に埋め込まれたバングルによって、あらゆる行動が制御され、また制御されてしまう。政府が個人の思想や活動に干渉する社会の中で、主人公たちはレジスタンスとして、バングルに支配されない世界を心の中に構築する。それを「中庭」と呼ぶネーミングがかっこいい。英語ではなく、漢字二文字でSF的概念を表現していくところに国産SFらしさがあるし、実在する中庭から展開していく仕掛けもオモシロかった。インターネットを通じて、私たちは心の「中庭」を他人にどんどん開放しているが、誰にも入らせない思考の「中庭」を持つことの重要さを教えてもらった気がした。 もっとも壮大な話がタイトル作の「鹽津城」である。三つの時間軸が並行し、シンクロしながら物語が進行していく。ここでテーマになるのは海と塩である。海水中の塩化ナトリウムが突如結晶化して街を破壊していく現象と、身体の中に塩分濃度の異常に高い、細い線条が形成される病気、二つの謎を中心として物語が描かれる。原発を絡めていることから、東日本大震災をモチーフにしていることはあきらかだが、あの出来事かこれほど跳躍力のある物語を紡げるのは、日本のSF作家ならではの視点だと思う。そこに『ワンピース』的な漫画の要素が合わさってくることで、こういった物語こそが本当の意味での「クールジャパン」なのではないか、と感じた。 塩化ナトリウムだけが海水から分離、凝固する科学的背景として「マックスウェルの悪魔」が引用されており、ネタ元を明示してくれる点も興味深い。さらに同じ分子挙動の不思議さについて、チューリングによる反応拡散方程式による生物の模様形成にも接続し、思考がどんどん広がっていく。それに呼応した表紙はさすがの川名潤ワークスだし、このように科学的想像力を足場にして物語が展開するSFならではの醍醐味があった。 マックスウェル、どこかで聞いた覚えがあるなと思ったら、「マクスウェル分布」のことだった。久しぶりにWikipediaでそれを眺めていると大学院入試で勉強した記憶がよみがえった。当時は本当に嫌だったし、今数式を見てもぼんやりとしか思い出せないが、こうやってSFの題材として出てくると「どういう意味なんだろう?」と興味が湧くのだから、エデュテイメントとしてのSFは偉大さである。寡作な作家のようなので、他も読んでみる。 - 2026年1月22日
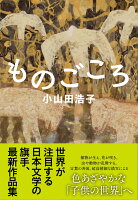 ものごころ小山田浩子読み終わった毎年友人とやってる本に関する年間BESTエピソードの中で、友人が著者の作品を1位にしていて、入門編として勧められたので読んだ。いわゆるステレオタイプの小説の形式から逸脱し、話というよりも構造の妙を追求している作家に惹かれがちなので、著者がその道を極めしものであることをこの一冊で十分理解した。 本著は、各文芸誌に掲載されていた短編をまとめたもので、さまざまな設定の話があるのだが、中心にあるのは子どもとコロナ禍である。子どもは普遍的なテーマである一方で、コロナ禍は局所的なテーマ。この二つが掛け合わさることで、日常と非日常のコントラストが鮮やかに立ち上がる。特に子ども、学生たちの人生で1回しかない貴重な瞬間がコロナ禍で失われてしまったことに気付かされた。こうやって小説という時代を超えて残りやすいフォーマットで書かれているのは意義深い。 著者の小説を読むのは初めてだったのだが、圧倒的な改行の少なさに驚かされる。紙面にパツパツに満ちている文字の密度は活字中毒者からすれば眼福である。そのスタイルを可能にしているのは、すべての出来事を並列に扱う態度である。場所、人称、時間、平文と会話など、それらのスイッチングを何の予告もなく行なわれる様は、まるで一筆書きで書いたようである。 読んでいるあいだに勝手にスイッチする構造は、人によっては不親切に映るかもしれないが、予定調和の小説に飽きている人にとって、これほどスリリングな文体はないだろう。しかも、この変則的な文体だからこそ表現できる「心の機微」があることに読めば気付かされる。読む前までは著者のギミックだけが耳に入り、勝手に出オチのように扱ってしまっていたが、これほど内容と相関しているだなんて、やはり読まないと実のところは何もわからないものだ。 ギミックの観点でいえば「おおしめり」がダントツにぶっ飛んでいた。句点なしで突っ走る水をめぐる物語。大学生の平凡な日常の話が、見せ方次第でこんなに非現実的に見えることに、表現の可能性を大いに感じた。中華料理屋に行くたびにこの話を思い出しそう。最後の主語のスイッチングの大胆さにも心底驚いた。あと同世代の方ならわかってくれると思うが、昔のはごろもフーズのCMインスパイアな水の王冠描写は、タイトルよろしく「ものごころ」がついた頃の記憶をフラッシュバックした。 本著を象徴するのは、宏とエイジを主人公にした、冒頭の「心臓」と巻末の「ものごころごろ」だろう。二つは繋がっていて、少年が青年への階段を歩み始める話なのだが、躍動感と閉塞感の対比が素晴らしい。前者については、河原で犬を追いかけるという極めてプリミティブな昭和世代直撃な原風景なのだが、出来事が収束していく先に待つ大人という杓子定規な存在、つまりは閉塞感の元凶の書き方が見事。大人になれば、宏の母親の言葉はすべて「正論」で何も間違ってないのだが、そのおもんなさたるや。後者では中学受験が本格化し、そのおもんなさに拍車がかかるのだが、それを野犬が人間にとって「いい犬」に順化していくことと対比させている点が残酷に映った。 一番心に突き刺さったのは「種」だった。子どもの身体に何かトラブルが起こった際の思考、行動のフローがシームレスな文体ゆえに巧みに表現されていて唸った。トラブルが起こるたびにググって玉石混合のネット情報の海を彷徨い、自分を納得させる落とし所を探る行為は現代に生きる親たちが皆やっていることだろう。それを小説でこんなふうに落とし込むアイデアが素晴らしい。今後はAIに聞くことがデフォルトになると思うので、このように逡巡する機会はなくなっていくだろうから時代の記録としても貴重と言える。しかも、終盤に「大便手掴み」という怒涛の展開が待っていてシビれた。さらに「大便掴み」が短編同士をゆるやかに繋ぐキーとなっているギミックにニヤニヤした。(子どもの排泄周りは色々と苦労しているところなので、余計に刺さったところもある。) 「作家性」という言葉を安直に使うことは許されない、まごうことなきオリジナリティに久しぶりに打ち震えたので、著作を順々に読んでいきたい。
ものごころ小山田浩子読み終わった毎年友人とやってる本に関する年間BESTエピソードの中で、友人が著者の作品を1位にしていて、入門編として勧められたので読んだ。いわゆるステレオタイプの小説の形式から逸脱し、話というよりも構造の妙を追求している作家に惹かれがちなので、著者がその道を極めしものであることをこの一冊で十分理解した。 本著は、各文芸誌に掲載されていた短編をまとめたもので、さまざまな設定の話があるのだが、中心にあるのは子どもとコロナ禍である。子どもは普遍的なテーマである一方で、コロナ禍は局所的なテーマ。この二つが掛け合わさることで、日常と非日常のコントラストが鮮やかに立ち上がる。特に子ども、学生たちの人生で1回しかない貴重な瞬間がコロナ禍で失われてしまったことに気付かされた。こうやって小説という時代を超えて残りやすいフォーマットで書かれているのは意義深い。 著者の小説を読むのは初めてだったのだが、圧倒的な改行の少なさに驚かされる。紙面にパツパツに満ちている文字の密度は活字中毒者からすれば眼福である。そのスタイルを可能にしているのは、すべての出来事を並列に扱う態度である。場所、人称、時間、平文と会話など、それらのスイッチングを何の予告もなく行なわれる様は、まるで一筆書きで書いたようである。 読んでいるあいだに勝手にスイッチする構造は、人によっては不親切に映るかもしれないが、予定調和の小説に飽きている人にとって、これほどスリリングな文体はないだろう。しかも、この変則的な文体だからこそ表現できる「心の機微」があることに読めば気付かされる。読む前までは著者のギミックだけが耳に入り、勝手に出オチのように扱ってしまっていたが、これほど内容と相関しているだなんて、やはり読まないと実のところは何もわからないものだ。 ギミックの観点でいえば「おおしめり」がダントツにぶっ飛んでいた。句点なしで突っ走る水をめぐる物語。大学生の平凡な日常の話が、見せ方次第でこんなに非現実的に見えることに、表現の可能性を大いに感じた。中華料理屋に行くたびにこの話を思い出しそう。最後の主語のスイッチングの大胆さにも心底驚いた。あと同世代の方ならわかってくれると思うが、昔のはごろもフーズのCMインスパイアな水の王冠描写は、タイトルよろしく「ものごころ」がついた頃の記憶をフラッシュバックした。 本著を象徴するのは、宏とエイジを主人公にした、冒頭の「心臓」と巻末の「ものごころごろ」だろう。二つは繋がっていて、少年が青年への階段を歩み始める話なのだが、躍動感と閉塞感の対比が素晴らしい。前者については、河原で犬を追いかけるという極めてプリミティブな昭和世代直撃な原風景なのだが、出来事が収束していく先に待つ大人という杓子定規な存在、つまりは閉塞感の元凶の書き方が見事。大人になれば、宏の母親の言葉はすべて「正論」で何も間違ってないのだが、そのおもんなさたるや。後者では中学受験が本格化し、そのおもんなさに拍車がかかるのだが、それを野犬が人間にとって「いい犬」に順化していくことと対比させている点が残酷に映った。 一番心に突き刺さったのは「種」だった。子どもの身体に何かトラブルが起こった際の思考、行動のフローがシームレスな文体ゆえに巧みに表現されていて唸った。トラブルが起こるたびにググって玉石混合のネット情報の海を彷徨い、自分を納得させる落とし所を探る行為は現代に生きる親たちが皆やっていることだろう。それを小説でこんなふうに落とし込むアイデアが素晴らしい。今後はAIに聞くことがデフォルトになると思うので、このように逡巡する機会はなくなっていくだろうから時代の記録としても貴重と言える。しかも、終盤に「大便手掴み」という怒涛の展開が待っていてシビれた。さらに「大便掴み」が短編同士をゆるやかに繋ぐキーとなっているギミックにニヤニヤした。(子どもの排泄周りは色々と苦労しているところなので、余計に刺さったところもある。) 「作家性」という言葉を安直に使うことは許されない、まごうことなきオリジナリティに久しぶりに打ち震えたので、著作を順々に読んでいきたい。 - 2026年1月16日
 自然のものはただ育つイーユン・リー,篠森ゆりこ読み終わった「イーユン・リーのエッセイ出たんや」と本屋で知り、積んでいた『水曜生まれの子』を読んでから本著を読んだ。前情報を何も知らなかったので、彼女の生活の機微を知れるのかなと軽い気持ちで読み始めたら、長男に続いて次男も自殺で亡くなったことをきっかけに書かれたエッセイと知り愕然…奈落の底にいる彼女が綴るドライな感情と思考の数々が心の奥底まで沁みてきた。 本著は次男ジェームズを亡くしたあと、彼女がどう考え、どう行動しているか、22章から構成されるエッセイ集。長男ヴィンセントを亡くした際には、彼とのやりとりをオマージュした小説『理由のない場所』を書いた著者だが、今回はフィクションではなくノンフィクションを選んだ。それは子どもたちの特性に合わせた選択だったという。 子ども二人を自死で失う。作家である彼女でさえ小説には使わないであろう、あまりに現実味のない出来事であり、その気持ちを想像することなんて到底できない。育児に正解はないと思いつつ子どもと向き合いながら、どうすればいいか試行錯誤しているわけだが、この日々の積み重ねが自死によって唐突に終わりを告げてしまうだなんて想像しただけで辛すぎる。 読み進めるにつれ、ヴィンセント、ジェームズを中心としたリー家の関係性、家族の風景が断片的に浮かび上がってくる。家族は外から見れば、どこも特異に映るのは世の常だが、リー家の子どもたちが、それぞれ異なるベクトルで社会と距離を取っていたことが伝わってきた。なかでもヴィンセントが10歳の頃に著者に伝えた言葉は、彼女の小説をずっと読んでいる身からすると、あまりにも悲しすぎて涙がボロボロとでてきた。 苦しみをわかってて、苦しみについてそんなに上手に書くのに、どうしてぼくたちを生んだの 神話や戯曲、小説を引き合いに出しながら、ジェームズの死について考えている様は作家らしい。古典ゆえだからこそ真理をついた言葉と、著者の論考が交じわり、さながら読書会の様相を呈している。また、物語が人生を救済する可能性について露骨には言及せず、引用を重ねることで、物語の存在意義そのものを示していく点に著者らしさを感じた。 なかでも象徴的なのは『シーシュポスの神話』である。「真に哲学的な問題は一つしかない。それは自殺についてである」というラインから始まる一冊であり、ジェームズは亡くなる数週間前に読んでいたという。神話に登場する「シーシュポスの岩」は日本の賽の河原に近い話で、大きな岩を何度も山頂に押して運ぶものの、運び終えると岩は転がり落ちる。一般には終わりのない徒労の象徴とされるこの岩を、著者は時間のメタファーと捉え、「時間を運ぶことの辛さ」を語っていた。つまり、育児をしていると時間があっという間に過ぎることに比べて、亡くなった後は時間が全く過ぎていかないことを示しており、さらに亡くなった子どもを「別種の新生児」と呼ぶあたりに並々ならない言語感覚を感じた。 さらに、「小石」という比喩も登場し、それはふい浮かんでくる思考のメタファーだ。この小石に逐一反応していると身が持たないから、小石を蹴飛ばしていながら生きていく。シーシュポスの岩との対比としても鮮やかだった。 先日読んだ『水曜生まれの子』でもパンチラインのつるべ打ちに圧倒されたが、エッセイゆえに切れ味はさらに鋭く、なおかつテーマがテーマなだけに心に強く響く。 直感とは、将来の可能性や起こりうることや別の選択肢をめぐる物語だ。そういう意味では、直感はフィクションだ。そして人生に裏づけられると、事実になる。 やる価値があることとやれることには隔たりがあり、その隔たりこそ若者に野心が宿り、老人に衰えが待ち構えているところなのだ。 こんな鋭い言葉を連発する彼女にとって、言葉こそがすべてなのだと読み進めるうちにわかってくる。それを裏付けるように言葉に関してさまざまな思索が展開される。世界でここでしか読めない洞察の連発に息を呑んだ。息子たちの自死という悲劇から導き出される言葉の奥行きは、他の追随を許さないものがある。そして、それは安易な救済の物語ではなく、彼女が今後の人生で考え続けていくだろうことの序章とも言える。 本著は一種の育児論としても読むことができて、子どもを失ったからこそ見えてくる、親が普段気づいていないことが言語化されている。特に育児における直感を信じるべきか、どの程度、楽観視するか、といった問いは奥深い。赤ちゃんのあいだは四六時中、見守る必要があるが、大きくなるにつれて、子どもの一挙手一投足を把握することはできない。そのとき親は、ある種の直感に従い、子どもを信じるしかなくなる。「どこまで信じるべきなのか?」と著者から問われると不安になった。目に見える行動や親にとって都合のいいことだけ信じるのではなく、子どもの内面についても思いを馳せていく必要性に気付かされた。そして、これはタイトルにも繋がり「ただ育つ」という楽観性と、一方で「自然に死んでしまう」という諦念。この相反する感情を、徹底的受容により引き受けている。 他にも「子どもが健康でいてくれるだけでいい」とよく言われるが、「存在」が当たり前になってくると「行動」ばかりに目を取られる。「存在」そのもののありがたみを理解できている親がどれだけいるのかと言われてドキッとした。「子どもは死ぬ」という強烈な言葉と、著者のドライな視点の数々は彼女以外に書きえない。 なんでこんなことが起こってしまったのか?と考えると、著者自身に自殺未遂の経験があることが、どうしても頭をよぎってしまう。そんな私の下世話な考えを見透かすように、終盤では彼女自身の自殺未遂についても言及されていた。そこまで言葉にする必要があるのかと思いつつ、彼女が公人であるがゆえとはいえ、あまりにも心ない報道や周辺の対応には言葉を失った。悪意がなくても、彼女の辛い状況に寄り添うために自分の経験を引き合いに出すことの不毛さを語っており、彼女の言葉で言われるとかなり重たかった。 私の悲哀に終わりはいらない。子どもの死は熱波でも吹雪でもなく、急いで駆け抜けて勝つべき障害物競走でも、治すべき急性や慢性の病気でもない。悲しみとは言葉であり省略化であり、その言葉よりはるかに大きなものの単純化にほかならない。 何よりも心身を大切にしてほしいが、著者は悲しむ母親として振る舞うことに否定的であり、止まることはないようだ。訳者あとがきによれば、今は大河小説を執筆中らしく、それが今から待ち遠しい。
自然のものはただ育つイーユン・リー,篠森ゆりこ読み終わった「イーユン・リーのエッセイ出たんや」と本屋で知り、積んでいた『水曜生まれの子』を読んでから本著を読んだ。前情報を何も知らなかったので、彼女の生活の機微を知れるのかなと軽い気持ちで読み始めたら、長男に続いて次男も自殺で亡くなったことをきっかけに書かれたエッセイと知り愕然…奈落の底にいる彼女が綴るドライな感情と思考の数々が心の奥底まで沁みてきた。 本著は次男ジェームズを亡くしたあと、彼女がどう考え、どう行動しているか、22章から構成されるエッセイ集。長男ヴィンセントを亡くした際には、彼とのやりとりをオマージュした小説『理由のない場所』を書いた著者だが、今回はフィクションではなくノンフィクションを選んだ。それは子どもたちの特性に合わせた選択だったという。 子ども二人を自死で失う。作家である彼女でさえ小説には使わないであろう、あまりに現実味のない出来事であり、その気持ちを想像することなんて到底できない。育児に正解はないと思いつつ子どもと向き合いながら、どうすればいいか試行錯誤しているわけだが、この日々の積み重ねが自死によって唐突に終わりを告げてしまうだなんて想像しただけで辛すぎる。 読み進めるにつれ、ヴィンセント、ジェームズを中心としたリー家の関係性、家族の風景が断片的に浮かび上がってくる。家族は外から見れば、どこも特異に映るのは世の常だが、リー家の子どもたちが、それぞれ異なるベクトルで社会と距離を取っていたことが伝わってきた。なかでもヴィンセントが10歳の頃に著者に伝えた言葉は、彼女の小説をずっと読んでいる身からすると、あまりにも悲しすぎて涙がボロボロとでてきた。 苦しみをわかってて、苦しみについてそんなに上手に書くのに、どうしてぼくたちを生んだの 神話や戯曲、小説を引き合いに出しながら、ジェームズの死について考えている様は作家らしい。古典ゆえだからこそ真理をついた言葉と、著者の論考が交じわり、さながら読書会の様相を呈している。また、物語が人生を救済する可能性について露骨には言及せず、引用を重ねることで、物語の存在意義そのものを示していく点に著者らしさを感じた。 なかでも象徴的なのは『シーシュポスの神話』である。「真に哲学的な問題は一つしかない。それは自殺についてである」というラインから始まる一冊であり、ジェームズは亡くなる数週間前に読んでいたという。神話に登場する「シーシュポスの岩」は日本の賽の河原に近い話で、大きな岩を何度も山頂に押して運ぶものの、運び終えると岩は転がり落ちる。一般には終わりのない徒労の象徴とされるこの岩を、著者は時間のメタファーと捉え、「時間を運ぶことの辛さ」を語っていた。つまり、育児をしていると時間があっという間に過ぎることに比べて、亡くなった後は時間が全く過ぎていかないことを示しており、さらに亡くなった子どもを「別種の新生児」と呼ぶあたりに並々ならない言語感覚を感じた。 さらに、「小石」という比喩も登場し、それはふい浮かんでくる思考のメタファーだ。この小石に逐一反応していると身が持たないから、小石を蹴飛ばしていながら生きていく。シーシュポスの岩との対比としても鮮やかだった。 先日読んだ『水曜生まれの子』でもパンチラインのつるべ打ちに圧倒されたが、エッセイゆえに切れ味はさらに鋭く、なおかつテーマがテーマなだけに心に強く響く。 直感とは、将来の可能性や起こりうることや別の選択肢をめぐる物語だ。そういう意味では、直感はフィクションだ。そして人生に裏づけられると、事実になる。 やる価値があることとやれることには隔たりがあり、その隔たりこそ若者に野心が宿り、老人に衰えが待ち構えているところなのだ。 こんな鋭い言葉を連発する彼女にとって、言葉こそがすべてなのだと読み進めるうちにわかってくる。それを裏付けるように言葉に関してさまざまな思索が展開される。世界でここでしか読めない洞察の連発に息を呑んだ。息子たちの自死という悲劇から導き出される言葉の奥行きは、他の追随を許さないものがある。そして、それは安易な救済の物語ではなく、彼女が今後の人生で考え続けていくだろうことの序章とも言える。 本著は一種の育児論としても読むことができて、子どもを失ったからこそ見えてくる、親が普段気づいていないことが言語化されている。特に育児における直感を信じるべきか、どの程度、楽観視するか、といった問いは奥深い。赤ちゃんのあいだは四六時中、見守る必要があるが、大きくなるにつれて、子どもの一挙手一投足を把握することはできない。そのとき親は、ある種の直感に従い、子どもを信じるしかなくなる。「どこまで信じるべきなのか?」と著者から問われると不安になった。目に見える行動や親にとって都合のいいことだけ信じるのではなく、子どもの内面についても思いを馳せていく必要性に気付かされた。そして、これはタイトルにも繋がり「ただ育つ」という楽観性と、一方で「自然に死んでしまう」という諦念。この相反する感情を、徹底的受容により引き受けている。 他にも「子どもが健康でいてくれるだけでいい」とよく言われるが、「存在」が当たり前になってくると「行動」ばかりに目を取られる。「存在」そのもののありがたみを理解できている親がどれだけいるのかと言われてドキッとした。「子どもは死ぬ」という強烈な言葉と、著者のドライな視点の数々は彼女以外に書きえない。 なんでこんなことが起こってしまったのか?と考えると、著者自身に自殺未遂の経験があることが、どうしても頭をよぎってしまう。そんな私の下世話な考えを見透かすように、終盤では彼女自身の自殺未遂についても言及されていた。そこまで言葉にする必要があるのかと思いつつ、彼女が公人であるがゆえとはいえ、あまりにも心ない報道や周辺の対応には言葉を失った。悪意がなくても、彼女の辛い状況に寄り添うために自分の経験を引き合いに出すことの不毛さを語っており、彼女の言葉で言われるとかなり重たかった。 私の悲哀に終わりはいらない。子どもの死は熱波でも吹雪でもなく、急いで駆け抜けて勝つべき障害物競走でも、治すべき急性や慢性の病気でもない。悲しみとは言葉であり省略化であり、その言葉よりはるかに大きなものの単純化にほかならない。 何よりも心身を大切にしてほしいが、著者は悲しむ母親として振る舞うことに否定的であり、止まることはないようだ。訳者あとがきによれば、今は大河小説を執筆中らしく、それが今から待ち遠しい。 - 2026年1月14日
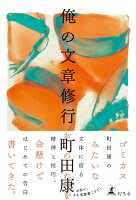 俺の文章修行町田康読み終わった『私の文学史』で自分自身について語っていたことに驚いた訳だが、さらに文章の書き方にフォーカスした一冊が出たということで読んだ。2020年代に突入してから、文章に対する広い意味での「校正」が行われるようになり、生成AIの台頭で、その傾向が顕著になっている今、「文章を書くこと」へのパッションの高さにめちゃくちゃ煽られた。当ブログでも生成AIによる手直しは一部行っているわけだが「果たしてそんなことに意味があるのか?」と著者から問われているような読書体験だった。 2021〜2024年までの連載が一冊にまとまったものとなっており、どのようにして文章が上手くなるか、著者のテクニックを紹介してくれている。当然、町田康が文章の書き方をまっすぐ丁寧に教えてくれるわけもなく、彼でしかあり得ない文体の連続の中、文章を書く上で何が大切で、どうやって書くのか、具体的に教えてくれる。なお、全体の構成自体はブレイクダウンがきちんと行われており、そのブレイクダウンした各ブロックの中で縦横無尽に暴れている。そのため要素だけ抜き出すと、至極真っ当なことを説明してくれており、結果的に「町田康的文章の書き方」という話になっている。文体はフリーキーなのに、語られていることは論理的というギャップが著者らしい。 冒頭で書き方ではなく、本を読むこと、および繰り返し読むことの重要性を語っていて、これは至極もっとも。幼少期のエピソードトークと共に語られる読書遍歴は読んでいて楽しい。個人的には繰り返し読むことが苦手で、何回も読んでいる本は特にないし、世の中には無数の読みたい本があるから、何度も同じ本を読む気にはあまりなれない。しかし、「文章が上手くなる」といった具体的な目標があれば読めそうな気がするので、好きな作家でトライしてみようかと思えた。というか、なんのためにデカい本棚買って、そこに置いているかといえば、いつか読み直すためやろ? 2021年からなので、生成AIの台頭を受けて書き下ろしたわけではない点に驚いた。というのも、前半において、あたかもそれを想定していたかのような内容になっているためだ。具体的には、外付け変換装置、内蔵変換装置という話だ。外部のデータに基づいた外付け変換装置は、自分の言いたいことをきれいに整えてくれる快楽をもたらしてくれる。しかも、生成AIは手軽かつ高精度だからこそ、どうしても使ってしまいがちではある。『birnglife Radio』というポッドキャスト番組を聞いているのだが、生成AIで文章をリバイスされた結果について「こういうことが書きたかった」と人間側が勝手に思い込んでいるだけと喝破していて、言い得て妙だった。それと同じく重要視されているのは、内蔵変換装置であり、自分の読書経験による自分の文体があり、それはさまざまなパラメーターによって構築されている。それらを訓練によって上手に使えるようになることがオモシロい文章を書くステップであると著者は主張していた。以下のパラグラフを読んで付き合い方を考え直すことを決意した。 つまり。外付け変換装置は使ってもよいが、使う際はその使用範囲に限界があることを称して、それが唯一無二、「正しい日本語」と思ってたら、多くのことを見逃し、結果的に、貧しい語彙だけを信じて、綺麗事だけを言うて儲けてる層にかもられてそれにも気がつかないアホのまま老いて死にますよ 町田康の小説をインプットデータとしてすべて放り込んで、同じような文体を形成することは今の技術で可能だろう。しかし、彼はそこから抜けて出していくように、明らかなエラーを定期的に文中にボムしている点がオモシロい。さながらタギングである。「一度書いたら戻らない」を徹底しているからか、「つまり」が多用されながら、徐々に核心へ近づいていくスタイル。結論だけ知りたい、とにかくコスパよく文章を上手く書けるようになりたい、そんな志の低いクソ野郎を置いていくかのように冗長に語り倒していることが最高だし、そんなコスパ野郎に「クソ」と文中で明言していく、こんなこともAIにはできないだろう。あと文章が上手く書けない人間が野垂れ死んでいくパターンも豊富で最高だった。 著者の小説を読んでいると声出して笑ってしまうことが頻繁にあるのだが、その種明かしもされており、「他人を笑かす」という意識で書くのではなく、自分が笑えるかどうかが大事という指摘はもっともだ。文字だけで人を笑わせるには相当なスキルが必要だと思っていたが、自分が笑えることを基準にするというのはシンプルかつ盲点だった。 町田康が町田康たるゆえんがさまざま書かれているのだが、もっともクリティカルな教訓は読みながら書く「裏表理論」だろう。文章を書くとき、とりあえずざーっと書いて、あとで整えればいいというのは王道の書き方だと思うが、著者はそれを良しとしない。「もっと文章を書く一瞬にフォーカスしろや!」と鼓舞してくる。読んで、書いての裏表を無限にリピートしながら、一発で自分のグルーヴを作らんかい!と。ここで投入されるクオンタイズの例えが特に刺さった。J.DillaやBudamunkのビートが大好きなのに、生成AIで文章を校正することはクオンタイズかけて自分の文章のグルーヴを殺してしまっているからだ。別に商業出版でもなんでもない個人のブログで何を外ヅラ気にして書いとんねん、もっと好き放題やってもええやんけと思わされました。 終盤にかけては、内容の話となっていき、熱い話も増えてくる。彼が「糸くず」と呼ぶ、文章を書く際のピュアな部分をいかに大切にしているか懇々と説明してくれていた。自分が書きたいことを書くことが何よりも大切で、それは他者が価値を決めるのではないという言葉に勇気をもらった。また、文章を書くことが自己救済と思いきや、利他的行為でもあるという話や、「技法」は奪い取れても「姿勢」は奪えないといった話はまさにその通りである。彼の技法や姿勢を頭に入れた上で読むと、これまでと違った読み方で小説が読めそうなので、積読している『古事記』を近いうちに読む。
俺の文章修行町田康読み終わった『私の文学史』で自分自身について語っていたことに驚いた訳だが、さらに文章の書き方にフォーカスした一冊が出たということで読んだ。2020年代に突入してから、文章に対する広い意味での「校正」が行われるようになり、生成AIの台頭で、その傾向が顕著になっている今、「文章を書くこと」へのパッションの高さにめちゃくちゃ煽られた。当ブログでも生成AIによる手直しは一部行っているわけだが「果たしてそんなことに意味があるのか?」と著者から問われているような読書体験だった。 2021〜2024年までの連載が一冊にまとまったものとなっており、どのようにして文章が上手くなるか、著者のテクニックを紹介してくれている。当然、町田康が文章の書き方をまっすぐ丁寧に教えてくれるわけもなく、彼でしかあり得ない文体の連続の中、文章を書く上で何が大切で、どうやって書くのか、具体的に教えてくれる。なお、全体の構成自体はブレイクダウンがきちんと行われており、そのブレイクダウンした各ブロックの中で縦横無尽に暴れている。そのため要素だけ抜き出すと、至極真っ当なことを説明してくれており、結果的に「町田康的文章の書き方」という話になっている。文体はフリーキーなのに、語られていることは論理的というギャップが著者らしい。 冒頭で書き方ではなく、本を読むこと、および繰り返し読むことの重要性を語っていて、これは至極もっとも。幼少期のエピソードトークと共に語られる読書遍歴は読んでいて楽しい。個人的には繰り返し読むことが苦手で、何回も読んでいる本は特にないし、世の中には無数の読みたい本があるから、何度も同じ本を読む気にはあまりなれない。しかし、「文章が上手くなる」といった具体的な目標があれば読めそうな気がするので、好きな作家でトライしてみようかと思えた。というか、なんのためにデカい本棚買って、そこに置いているかといえば、いつか読み直すためやろ? 2021年からなので、生成AIの台頭を受けて書き下ろしたわけではない点に驚いた。というのも、前半において、あたかもそれを想定していたかのような内容になっているためだ。具体的には、外付け変換装置、内蔵変換装置という話だ。外部のデータに基づいた外付け変換装置は、自分の言いたいことをきれいに整えてくれる快楽をもたらしてくれる。しかも、生成AIは手軽かつ高精度だからこそ、どうしても使ってしまいがちではある。『birnglife Radio』というポッドキャスト番組を聞いているのだが、生成AIで文章をリバイスされた結果について「こういうことが書きたかった」と人間側が勝手に思い込んでいるだけと喝破していて、言い得て妙だった。それと同じく重要視されているのは、内蔵変換装置であり、自分の読書経験による自分の文体があり、それはさまざまなパラメーターによって構築されている。それらを訓練によって上手に使えるようになることがオモシロい文章を書くステップであると著者は主張していた。以下のパラグラフを読んで付き合い方を考え直すことを決意した。 つまり。外付け変換装置は使ってもよいが、使う際はその使用範囲に限界があることを称して、それが唯一無二、「正しい日本語」と思ってたら、多くのことを見逃し、結果的に、貧しい語彙だけを信じて、綺麗事だけを言うて儲けてる層にかもられてそれにも気がつかないアホのまま老いて死にますよ 町田康の小説をインプットデータとしてすべて放り込んで、同じような文体を形成することは今の技術で可能だろう。しかし、彼はそこから抜けて出していくように、明らかなエラーを定期的に文中にボムしている点がオモシロい。さながらタギングである。「一度書いたら戻らない」を徹底しているからか、「つまり」が多用されながら、徐々に核心へ近づいていくスタイル。結論だけ知りたい、とにかくコスパよく文章を上手く書けるようになりたい、そんな志の低いクソ野郎を置いていくかのように冗長に語り倒していることが最高だし、そんなコスパ野郎に「クソ」と文中で明言していく、こんなこともAIにはできないだろう。あと文章が上手く書けない人間が野垂れ死んでいくパターンも豊富で最高だった。 著者の小説を読んでいると声出して笑ってしまうことが頻繁にあるのだが、その種明かしもされており、「他人を笑かす」という意識で書くのではなく、自分が笑えるかどうかが大事という指摘はもっともだ。文字だけで人を笑わせるには相当なスキルが必要だと思っていたが、自分が笑えることを基準にするというのはシンプルかつ盲点だった。 町田康が町田康たるゆえんがさまざま書かれているのだが、もっともクリティカルな教訓は読みながら書く「裏表理論」だろう。文章を書くとき、とりあえずざーっと書いて、あとで整えればいいというのは王道の書き方だと思うが、著者はそれを良しとしない。「もっと文章を書く一瞬にフォーカスしろや!」と鼓舞してくる。読んで、書いての裏表を無限にリピートしながら、一発で自分のグルーヴを作らんかい!と。ここで投入されるクオンタイズの例えが特に刺さった。J.DillaやBudamunkのビートが大好きなのに、生成AIで文章を校正することはクオンタイズかけて自分の文章のグルーヴを殺してしまっているからだ。別に商業出版でもなんでもない個人のブログで何を外ヅラ気にして書いとんねん、もっと好き放題やってもええやんけと思わされました。 終盤にかけては、内容の話となっていき、熱い話も増えてくる。彼が「糸くず」と呼ぶ、文章を書く際のピュアな部分をいかに大切にしているか懇々と説明してくれていた。自分が書きたいことを書くことが何よりも大切で、それは他者が価値を決めるのではないという言葉に勇気をもらった。また、文章を書くことが自己救済と思いきや、利他的行為でもあるという話や、「技法」は奪い取れても「姿勢」は奪えないといった話はまさにその通りである。彼の技法や姿勢を頭に入れた上で読むと、これまでと違った読み方で小説が読めそうなので、積読している『古事記』を近いうちに読む。 - 2026年1月6日
 置き配的福尾匠読み終わった『シットとシッポ』というポッドキャストを最近聞いており、そのパーソナリティを務める著者の新刊ということで読んだ。一度、本屋で立ち読みした際、その哲学的な語り口に気後れしてしまったのだが、最近知り合った友人と飲んだ帰りに立ち寄ったジュンク堂で、背中を押してもらったのだった。実際、理解が追いつかない部分もあったものの、ものの捉え方の一つ一つが新鮮で興味深く読んだ。 もともと文芸誌『群像』での連載をまとめた一冊ということもあり、各章はエッセイ的な導入から始まり、そこから哲学的思考が折展開していく。構成面で特に印象的なのは、A面/B面という二部構成を採用している点だ。一つのキーワードやテーマについて、A面では「言葉」、B面では「物」という異なる観点から考察がなされ、議論は並行して進んでいく。 多くの書籍が章をリレーのようにつなぎ、一冊を通して一つのメッセージへと収束させる構造を取るのに対し、著者は本書を「ハンマー投げ」に喩える。つまり、各章は互いに直接接続されることなく、独立した投擲として存在する。しかし、それらは完全に孤立しているわけではなく、フィードバックとして相互に影響し合っている。さらに、その独立性と関係性を、将棋や囲碁のアナロジーを用いて説明するくだりは見事だし、タイトルにある「置き」とも結びつく。あまりにも鮮やかな見立てに読み終わったあとに唸った。 タイトルにもなっている「置き配的」とは、著者が提唱する新たな概念である。今となっては当たり前となった宅配便における「置き配」の特徴を拝借しながら、そのラディカルさ、奇妙さを抽出して論理を構築している。置き配では、従来のように宅配業者が荷受人に直接手渡すわけではなく、「置いた」という事実(=玄関前に置かれた荷物の写真、もしくはメール通知)を持って配達完了となる。つまり、実質的なやり取りは発生しないが、「置いた」という事実が完結性を担保する。こういった「置き配的」な観点で現在の言論空間、特にネット上でのコミュニケーションについて分析していく。 連載ということもあり、論述パートに入る前には導入をきちんと用意してくれているので、最初に想像していたよりは議論に振り落とされるケースは少なかったとはいえ、哲学的な基礎知識や思考能力の不足を正直感じた。それでも、この手の議論に関する本を読むための「大リーグボール養成ギプス」として捉えれば、本著はかなり機能的である。それは単純に自分の見識や論理を開陳するだけではなく、興味関心を哲学のフィルターを通じて見たときにどう見えるのか。思考を深めていく様を横目で見てOJT的に学べるからである。 「置き配的」という概念がもっともわかりやすく機能するのは、ネット上のコミュニケーション、とりわけX(旧ツイッター)をめぐる議論である。本書はツイッター論として読める側面を強く持っている。 アマゾンが置いたという事実を持ち帰るために荷物を運ぶように、人々は言ってやった・言われたという事実を持ち帰り自陣にアピールするために、ハッシュタグ、引用リツイート、スクリーンショットといった諸々の引用の技術を駆使する。その意味で「置き配的」とは、コミュニケーションを偽装した内向きのパフォーマンスである。 アテンションも欲しい、ポジションも欲しい。しかしアテンションやポジションを取りに行く身振り自体が私の表現から内実を骨抜きにしてしまうので、誰かの表現を示成的なパフォーマンスとして見なすことにおいて、私は私の表現が実のあるものであると、感じることができる。これが「注意の時代」の心性であるだろう。 数十字のチャット、ツイート、コメントから、一日数百字の日記へ。それはたんなる量的な変化ではなく、テキストボックスという閉じられた箱からテキストエディタあるいは日記帳という平面への移行である。そしてこの移行によって言葉は、言うべきことが<疎>である空間のなかで分散し、出来事はあらかじめこしらえられたパッケージから解放され、自伝には書かれようのない<私>の生(life)が、人生(life)にはカウントされない生活(life)として切り出される。 ツイッター論として、これだけ鋭いことを言える書き手はどれほどいるだろうか。こういった思考の背景にあるドゥールズを筆頭とした哲学者たちの金言も現代を象徴しているように感じることが多かった。そこに時代を超越した、抽象性の高い「哲学」という学問の価値と可能性を垣間見たのだった。つまり、具体的な内容ではなく、論旨の骨組みを抜き出した抽象的なものだからこそ、さまざまなものに転用することが可能だからだ。それはまさに著者が「置き配」という具体的な事象から概念を抽出し、別の領域に適用していく実践そのものであり、これが哲学の醍醐味なのだなと納得した。 その最たる例が「犬をバギーに乗せて歩くことは犬にとって散歩と言えるのか?」という命題である。日常の些細なことでも哲学的な眼鏡を通じて眺め直してみると、そこには膨大な思考の糸口が転がっている。「蛙化現象」に関する考察も同じく著者ならではの視点が輝いていた。特に村上春樹の小説と接続した瞬間に自分の中でイマイチ像を結ばなかった「蛙化現象」について霧が晴れていくように理解が進んでいった。 こういった文章を読むと「SNSにおいて自分がどう思われるか?」「他人が何を考えているか?」よりも、もっと愉快で楽しい思考のきっかけが目の前に転がっていることに気付かされるし、注意の払い方については、過去に読んだ「何もしない」で学んだはずなのに喉元過ぎればなんとやらである。やはり思考するためには、フローする情報よりもスタティックな情報に目を通したいものである。自戒の念をこめて。。。 個人的に特に興味深かったのは、批評圏に関する議論、なかでも批評が抱える二重の「ジャンルレスネス」という指摘である。批評の限界は嘆かれて久しいが、批評がどうして厳しいのか?これだけロジカルに語られたものを読むのが初めてで、目から鱗だった。そして、批評空間よりも感想空間の再構築が必要という主張には納得した。 というのも、私は日本語ラップのアルバムについて昨年からレビューしているのだが、そこで意識しているのは「批評」というより「感想」だからだ。それゆえ最初に始める際、「日本語ラップ日記」と題して「批評」と受け取られる可能性を回避したことは、著者が日記を重要視している点と少なからず響き合う部分があった。また、批評が内政問題に終始してしまうという指摘も、ヒップホップの現状を見れば頷ける。ゴシップや英語警察、即時的なリアクションばかりが目につく状況に辟易し、私はnoteで書いている。わかりやすい反応がなくても、同じ密度のコミュニケーションを求める誰かに届けばいいなと思いながら、毎週文章を書いている。 現在のヒップホップの書き手の多くは商業ライターであり、アーティスト本人へのインタビューが主な仕事となっている。その意味では一次情報にアクセスできるが、それは著者の言葉を借りれば「密」な言説空間でもある。そこでは「置き配的」なポジショントークが蔓延しやすい。しかし、「密」ではなく「疎」なものに批評の可能性を見出す。つまり、物や作品と遭遇したときに起こってくる言説が批評たりうるのだと。さらに、作品が作品たりうるのは、それが誕生した瞬間ではなく「あとからやってきたものがそこに表現を見出したとき」という主張は、自分が感想を書いている意味を代弁してくれていた。ネットで何かを書くことは誰でもできる今、どこで何をどうやって書くか。その指針となる一冊だった。
置き配的福尾匠読み終わった『シットとシッポ』というポッドキャストを最近聞いており、そのパーソナリティを務める著者の新刊ということで読んだ。一度、本屋で立ち読みした際、その哲学的な語り口に気後れしてしまったのだが、最近知り合った友人と飲んだ帰りに立ち寄ったジュンク堂で、背中を押してもらったのだった。実際、理解が追いつかない部分もあったものの、ものの捉え方の一つ一つが新鮮で興味深く読んだ。 もともと文芸誌『群像』での連載をまとめた一冊ということもあり、各章はエッセイ的な導入から始まり、そこから哲学的思考が折展開していく。構成面で特に印象的なのは、A面/B面という二部構成を採用している点だ。一つのキーワードやテーマについて、A面では「言葉」、B面では「物」という異なる観点から考察がなされ、議論は並行して進んでいく。 多くの書籍が章をリレーのようにつなぎ、一冊を通して一つのメッセージへと収束させる構造を取るのに対し、著者は本書を「ハンマー投げ」に喩える。つまり、各章は互いに直接接続されることなく、独立した投擲として存在する。しかし、それらは完全に孤立しているわけではなく、フィードバックとして相互に影響し合っている。さらに、その独立性と関係性を、将棋や囲碁のアナロジーを用いて説明するくだりは見事だし、タイトルにある「置き」とも結びつく。あまりにも鮮やかな見立てに読み終わったあとに唸った。 タイトルにもなっている「置き配的」とは、著者が提唱する新たな概念である。今となっては当たり前となった宅配便における「置き配」の特徴を拝借しながら、そのラディカルさ、奇妙さを抽出して論理を構築している。置き配では、従来のように宅配業者が荷受人に直接手渡すわけではなく、「置いた」という事実(=玄関前に置かれた荷物の写真、もしくはメール通知)を持って配達完了となる。つまり、実質的なやり取りは発生しないが、「置いた」という事実が完結性を担保する。こういった「置き配的」な観点で現在の言論空間、特にネット上でのコミュニケーションについて分析していく。 連載ということもあり、論述パートに入る前には導入をきちんと用意してくれているので、最初に想像していたよりは議論に振り落とされるケースは少なかったとはいえ、哲学的な基礎知識や思考能力の不足を正直感じた。それでも、この手の議論に関する本を読むための「大リーグボール養成ギプス」として捉えれば、本著はかなり機能的である。それは単純に自分の見識や論理を開陳するだけではなく、興味関心を哲学のフィルターを通じて見たときにどう見えるのか。思考を深めていく様を横目で見てOJT的に学べるからである。 「置き配的」という概念がもっともわかりやすく機能するのは、ネット上のコミュニケーション、とりわけX(旧ツイッター)をめぐる議論である。本書はツイッター論として読める側面を強く持っている。 アマゾンが置いたという事実を持ち帰るために荷物を運ぶように、人々は言ってやった・言われたという事実を持ち帰り自陣にアピールするために、ハッシュタグ、引用リツイート、スクリーンショットといった諸々の引用の技術を駆使する。その意味で「置き配的」とは、コミュニケーションを偽装した内向きのパフォーマンスである。 アテンションも欲しい、ポジションも欲しい。しかしアテンションやポジションを取りに行く身振り自体が私の表現から内実を骨抜きにしてしまうので、誰かの表現を示成的なパフォーマンスとして見なすことにおいて、私は私の表現が実のあるものであると、感じることができる。これが「注意の時代」の心性であるだろう。 数十字のチャット、ツイート、コメントから、一日数百字の日記へ。それはたんなる量的な変化ではなく、テキストボックスという閉じられた箱からテキストエディタあるいは日記帳という平面への移行である。そしてこの移行によって言葉は、言うべきことが<疎>である空間のなかで分散し、出来事はあらかじめこしらえられたパッケージから解放され、自伝には書かれようのない<私>の生(life)が、人生(life)にはカウントされない生活(life)として切り出される。 ツイッター論として、これだけ鋭いことを言える書き手はどれほどいるだろうか。こういった思考の背景にあるドゥールズを筆頭とした哲学者たちの金言も現代を象徴しているように感じることが多かった。そこに時代を超越した、抽象性の高い「哲学」という学問の価値と可能性を垣間見たのだった。つまり、具体的な内容ではなく、論旨の骨組みを抜き出した抽象的なものだからこそ、さまざまなものに転用することが可能だからだ。それはまさに著者が「置き配」という具体的な事象から概念を抽出し、別の領域に適用していく実践そのものであり、これが哲学の醍醐味なのだなと納得した。 その最たる例が「犬をバギーに乗せて歩くことは犬にとって散歩と言えるのか?」という命題である。日常の些細なことでも哲学的な眼鏡を通じて眺め直してみると、そこには膨大な思考の糸口が転がっている。「蛙化現象」に関する考察も同じく著者ならではの視点が輝いていた。特に村上春樹の小説と接続した瞬間に自分の中でイマイチ像を結ばなかった「蛙化現象」について霧が晴れていくように理解が進んでいった。 こういった文章を読むと「SNSにおいて自分がどう思われるか?」「他人が何を考えているか?」よりも、もっと愉快で楽しい思考のきっかけが目の前に転がっていることに気付かされるし、注意の払い方については、過去に読んだ「何もしない」で学んだはずなのに喉元過ぎればなんとやらである。やはり思考するためには、フローする情報よりもスタティックな情報に目を通したいものである。自戒の念をこめて。。。 個人的に特に興味深かったのは、批評圏に関する議論、なかでも批評が抱える二重の「ジャンルレスネス」という指摘である。批評の限界は嘆かれて久しいが、批評がどうして厳しいのか?これだけロジカルに語られたものを読むのが初めてで、目から鱗だった。そして、批評空間よりも感想空間の再構築が必要という主張には納得した。 というのも、私は日本語ラップのアルバムについて昨年からレビューしているのだが、そこで意識しているのは「批評」というより「感想」だからだ。それゆえ最初に始める際、「日本語ラップ日記」と題して「批評」と受け取られる可能性を回避したことは、著者が日記を重要視している点と少なからず響き合う部分があった。また、批評が内政問題に終始してしまうという指摘も、ヒップホップの現状を見れば頷ける。ゴシップや英語警察、即時的なリアクションばかりが目につく状況に辟易し、私はnoteで書いている。わかりやすい反応がなくても、同じ密度のコミュニケーションを求める誰かに届けばいいなと思いながら、毎週文章を書いている。 現在のヒップホップの書き手の多くは商業ライターであり、アーティスト本人へのインタビューが主な仕事となっている。その意味では一次情報にアクセスできるが、それは著者の言葉を借りれば「密」な言説空間でもある。そこでは「置き配的」なポジショントークが蔓延しやすい。しかし、「密」ではなく「疎」なものに批評の可能性を見出す。つまり、物や作品と遭遇したときに起こってくる言説が批評たりうるのだと。さらに、作品が作品たりうるのは、それが誕生した瞬間ではなく「あとからやってきたものがそこに表現を見出したとき」という主張は、自分が感想を書いている意味を代弁してくれていた。ネットで何かを書くことは誰でもできる今、どこで何をどうやって書くか。その指針となる一冊だった。 - 2025年12月28日
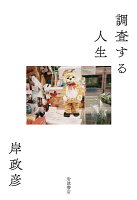 調査する人生岸政彦読み終わった社会学者である著者と、同じく社会学を専門とする研究者たちとの対談集ということで読んだ。データから傾向を見出し、圧縮、抽出することが価値とされがちな現代において、著者が「再現不能な、一回性の科学」と呼ぶ社会学の一側面の奥深さを知るには、まさにうってつけの一冊だった。 本著は著者と六人の社会学者との対談集。著者が聞き手となり、各人のこれまでの調査や活動をたどりながら、その中で社会学のあり方そのものが語られている。社会学がここまで広く認知されるようになった背景には、間違いなく著者の功績がある。そのフロントランナーが、他の社会学者たちと向き合い、彼らの調査対象やスタンスを当人の言葉で引き出していくため、議論は自然と頭に入ってくる。すでに読んだことのある研究者については理解が深まり、未読の著作については今すぐ手に取りたくなる。特に石岡氏の『ローカルボクサーと貧困世界』は格闘技好きとして絶対に読みたい一冊だ。 議論の中心となるのは、社会学における質的調査である。量的調査がデータから確からしさを抽出するアプローチだとすれば、それはデータ社会である現代の価値観と親和性が高い。一方で、数を稼げない質的調査をどのように行い、その結果をどう解釈するのか。本書では、沖縄の若者、部落差別、女性ホームレス、フィリピンのボクサー、在日韓国人など、対象は千差万別でありながら、それぞれが自分なりのスタイルで対象との距離を模索している様子が浮かび上がる。 質的調査と一口にいっても、著者のようにワンショットサーベイで強い関係性を結ばないスタイルに対して、参与観察で特定の対象と距離を縮めながら、話を聞いていくスタイルでは考え方が異なる。その差分が繰り返し言語化されることで理解が深まっていく。なかでも、著者が沖縄で出会ったおじいさんのエピソードを通じて語られる「他者の合理性」は、人の一側面だけを見て安易に判断してしまいがちな現代において、強く考えさせられるテーマだった。 タイトルにもある「人生」というのは、本著を貫く重要なテーマである。インタビューにおいて、研究に必要な情報だけを切り取るのではなく、より広い領域で話を聞くことで、想定外の枝葉から多層的で豊かな語りが立ち上がる。この感覚は、自分で『IN OUR LIFE』と名づけたポッドキャスト番組を運営していることもあり、実感を伴って理解できた。7年前にポッドキャストを始めたのは、SNSの窮屈さが最大の理由だったが、大事にしていたのは特定のテーマになるべく収束させず、話者同士の関心に委ねて会話を広げていくことだった。非圧縮でだらだらと話す中で話題は発散していくが、それこそが「人生」なのだと思っている。本著の言葉を借りれば、我々は「重層的な生」を営んでいるのだ。 事実関係とディテールの違いについての議論も印象的だった。事実偏重の態度では、その場のやり取りだけがすべてだと誤解されがちだが、語りを文字に起こし、理論を重ねることで、出来事はより立体的に、伝わる形になる。理論だけでは手詰まりになり、現場だけでは一過性の話にとどまる。そのバランスを取ることで真理に近づこうとする営みこそが学問だ。 打越氏、上間氏、朴氏の著作は読んでいたため、その前提を踏まえて読むことで各人の社会学に対するスタンスや対象との距離感を知ることができた。とくに沖縄を調査対象とする著者、打越氏、上間氏の議論では、沖縄特有の空気や風習が深く掘り下げられ、それぞれの著作の「ビハインド・ザ・ストーリー」を覗くような感覚があった。単なる読み物ではなく、学問なのだという当たり前の事実にここでも気付かされた。 一方で朴氏とは他のメンバーとくらべて議論が平行線を辿る場面があり、興味深かった。「わかる」ということへの認識の違い、エモーショナルになることへの慎重な姿勢。感情に流されてしまいがちな自分にとって、ここまで整然とした態度は簡単に真似できるものではないと感じた。本著を読むと『ヘルシンキ 生活の練習』シリーズで著者が淡々とした描写に徹している理由もよくわかった。 普遍的にいえば「人に話を聞くこと」が本著のテーマであり、その行為について対話するという構成はメタ的と言える。相手の話を受けて、自分の見解を足して返していくスタイルで、これだけ議論をスイングさせられるのは著者の力量に他ならない。十年ほど前、サイン会でほんの一瞬言葉を交わしたことがある。短い時間にもかかわらず、緊張するこちらの話を引き出し、そこから会話を膨らませてくれた。そんな記憶が、本書を読みながら蘇ったのであった。
調査する人生岸政彦読み終わった社会学者である著者と、同じく社会学を専門とする研究者たちとの対談集ということで読んだ。データから傾向を見出し、圧縮、抽出することが価値とされがちな現代において、著者が「再現不能な、一回性の科学」と呼ぶ社会学の一側面の奥深さを知るには、まさにうってつけの一冊だった。 本著は著者と六人の社会学者との対談集。著者が聞き手となり、各人のこれまでの調査や活動をたどりながら、その中で社会学のあり方そのものが語られている。社会学がここまで広く認知されるようになった背景には、間違いなく著者の功績がある。そのフロントランナーが、他の社会学者たちと向き合い、彼らの調査対象やスタンスを当人の言葉で引き出していくため、議論は自然と頭に入ってくる。すでに読んだことのある研究者については理解が深まり、未読の著作については今すぐ手に取りたくなる。特に石岡氏の『ローカルボクサーと貧困世界』は格闘技好きとして絶対に読みたい一冊だ。 議論の中心となるのは、社会学における質的調査である。量的調査がデータから確からしさを抽出するアプローチだとすれば、それはデータ社会である現代の価値観と親和性が高い。一方で、数を稼げない質的調査をどのように行い、その結果をどう解釈するのか。本書では、沖縄の若者、部落差別、女性ホームレス、フィリピンのボクサー、在日韓国人など、対象は千差万別でありながら、それぞれが自分なりのスタイルで対象との距離を模索している様子が浮かび上がる。 質的調査と一口にいっても、著者のようにワンショットサーベイで強い関係性を結ばないスタイルに対して、参与観察で特定の対象と距離を縮めながら、話を聞いていくスタイルでは考え方が異なる。その差分が繰り返し言語化されることで理解が深まっていく。なかでも、著者が沖縄で出会ったおじいさんのエピソードを通じて語られる「他者の合理性」は、人の一側面だけを見て安易に判断してしまいがちな現代において、強く考えさせられるテーマだった。 タイトルにもある「人生」というのは、本著を貫く重要なテーマである。インタビューにおいて、研究に必要な情報だけを切り取るのではなく、より広い領域で話を聞くことで、想定外の枝葉から多層的で豊かな語りが立ち上がる。この感覚は、自分で『IN OUR LIFE』と名づけたポッドキャスト番組を運営していることもあり、実感を伴って理解できた。7年前にポッドキャストを始めたのは、SNSの窮屈さが最大の理由だったが、大事にしていたのは特定のテーマになるべく収束させず、話者同士の関心に委ねて会話を広げていくことだった。非圧縮でだらだらと話す中で話題は発散していくが、それこそが「人生」なのだと思っている。本著の言葉を借りれば、我々は「重層的な生」を営んでいるのだ。 事実関係とディテールの違いについての議論も印象的だった。事実偏重の態度では、その場のやり取りだけがすべてだと誤解されがちだが、語りを文字に起こし、理論を重ねることで、出来事はより立体的に、伝わる形になる。理論だけでは手詰まりになり、現場だけでは一過性の話にとどまる。そのバランスを取ることで真理に近づこうとする営みこそが学問だ。 打越氏、上間氏、朴氏の著作は読んでいたため、その前提を踏まえて読むことで各人の社会学に対するスタンスや対象との距離感を知ることができた。とくに沖縄を調査対象とする著者、打越氏、上間氏の議論では、沖縄特有の空気や風習が深く掘り下げられ、それぞれの著作の「ビハインド・ザ・ストーリー」を覗くような感覚があった。単なる読み物ではなく、学問なのだという当たり前の事実にここでも気付かされた。 一方で朴氏とは他のメンバーとくらべて議論が平行線を辿る場面があり、興味深かった。「わかる」ということへの認識の違い、エモーショナルになることへの慎重な姿勢。感情に流されてしまいがちな自分にとって、ここまで整然とした態度は簡単に真似できるものではないと感じた。本著を読むと『ヘルシンキ 生活の練習』シリーズで著者が淡々とした描写に徹している理由もよくわかった。 普遍的にいえば「人に話を聞くこと」が本著のテーマであり、その行為について対話するという構成はメタ的と言える。相手の話を受けて、自分の見解を足して返していくスタイルで、これだけ議論をスイングさせられるのは著者の力量に他ならない。十年ほど前、サイン会でほんの一瞬言葉を交わしたことがある。短い時間にもかかわらず、緊張するこちらの話を引き出し、そこから会話を膨らませてくれた。そんな記憶が、本書を読みながら蘇ったのであった。 - 2025年12月26日
 ブロッコリー・レボリューション岡田利規読み終わったPalmbooksの作品で著者のことを知り、他の小説も読んでみようと文庫で手に入りやすい本著を読んだ。既存の小説の形式を脱構築していくようなスタイルが印象的だった。 著者はもともと劇作家であり、小説も書いている。本著はタイトル作を含む短編、中編を交えた作品集となっている。どの作品もテーマ自体は他愛のないことであり、物語的な大きな起伏は用意されていないものの、語り口のユニークさにぐいぐい引き込まれた。 オープニングを飾る「楽観的な方のケース」は最初こそ女性の一人称で進んでいくのだが、急にカメラが彼女から離れる瞬間が訪れる。しかし、語り口は女性のままで、彼女の視点から見たパン屋の様子、彼氏の視点が語られていく。ぼーっと読んでいると見落としそうなほどシームレスに話が進んでいくのだが、ここで明らかになるのは、著者が「小説の語り手」についてかなり自覚的であるということだ。カップルが同棲を始める話にも関わらず、一般的な会話体が一切なく、それぞれの視点から見た彼、彼女に対する内面の感情が細かく描かれている。それは小説だからこそ書けることであり「演劇」という会話の塊のようなフォーマットでは描けない領域を小説で模索している様が伝わってきた。 ヒップホップ好きとしては「ショッピングモールで過ごせなかった日」を興味深く読んだ。一つのモチーフとしてラップを取り上げているのだが、「ストリート」と「ショッピングモール」を対比させつつ、どちらも同じくらいにお飾りなものでしかなく、存在自体に必然性がないことを描いている。Tohjiが提示したMall boyzの世界観を小説にしたら、こうなるかもしれないと思わされた。ただそれにしては「ストリート」に対する視点が冷めすぎており、それに呼応させるようにストリート側をダサすぎるラップ描写でラベリングしている点には抵抗があった。 「黄金期」は終わらない都市開発を舞台にした、頭のいかれた人間の話で読んでいてワクワクした。作中では横浜だが、最近渋谷に行くたびに感じる「一体何がしたいのか?」という気持ちが端的に表現されていて膝を打った。 *利便性を高めたい一心でアイデアが労力が資金が、よかれと思って投入された結果が裏目に出たということなのか、無視できない副作用が出てしまったということなのか、ずいぶんとやさぐれた場所、剝き出しになる寸前の殺気がしれっと色濃く漂う場所へと、ここをすっかり変貌させた。* そして、渋谷駅を通るたびに感じるのは、殺気だったのかと気づいた。 *各々の目的の優先を妨害してくる他の人間どもの意志を斥け合う。その意志の存在を互いにそもそも認知しないという仕方による、意志の排斥合戦によって、絶えずそこかしこで小さな火花が生じ、こうしてこの場は常時一定以上の濃度の殺気を保つ。* 三島由紀夫賞を受賞した表題作は、ここまで紹介した語り口のユニークさと暴力性が「文学」という形で結晶化した作品となっていた。話の筋としては、妻が家を出ていってしまい、タイでバカンスを一人過ごしているというもの。このとき、妻の一人称でバカンスの様子が語られるのではなく、残された夫が、妻のバカンスでの様子を二人称で語っている。残された側が「こんなバカンスを過ごしているに違いない」という妄想の羅列ともいえるのだが、小説の本質、つまり、小説とは誰かの頭の中で行われる想像の一種なのだということを、人称によって改めて明示している。それは冒頭を飾り、文中で執拗に繰り返される「ぼくはいまだにそのことを知らないでいるしこの先も知ることは決してないけれども」というセリフに象徴されているのだった。 巻末に多和田葉子との対談が収録されており、そこでも人称の話題になっていた。著者がタイで印象に残った風景や出来事を小説に落とし込むにあたり、一人称だと自分との距離が近すぎるから、このスタイルになったと語っており納得した。二人とも王道というより革新派ゆえのメタ視点の数々が興味深い。特に二人称の「あなた」から「彼方」に派生させて、近しさと距離の話に変換していく多和田葉子はラッパーだなと改めて感じた。 タイでのバカンス描写は村上春樹を彷彿とさせる洒落たものが多い。それは食事、音楽、プールというテーマに引っ張られているからそう見えるのだろう。なかでも文中で紹介される[タイのインディーポップバンド](https://music.apple.com/jp/album/lucid-dream/1191823166)が甘酸っぱいサウンドでピッタリだった。一方で、このバカンスの妄想を繰り広げてる語り手の男が暴力的というのが新鮮だ。この結果、バカンスシーンが冗長になりすぎず、物語がキュッと締まっていた。 『わたしたちに許された特別な時間の終わり』も読みたいが絶版してるようで、Kindleでリリースして欲しい。
ブロッコリー・レボリューション岡田利規読み終わったPalmbooksの作品で著者のことを知り、他の小説も読んでみようと文庫で手に入りやすい本著を読んだ。既存の小説の形式を脱構築していくようなスタイルが印象的だった。 著者はもともと劇作家であり、小説も書いている。本著はタイトル作を含む短編、中編を交えた作品集となっている。どの作品もテーマ自体は他愛のないことであり、物語的な大きな起伏は用意されていないものの、語り口のユニークさにぐいぐい引き込まれた。 オープニングを飾る「楽観的な方のケース」は最初こそ女性の一人称で進んでいくのだが、急にカメラが彼女から離れる瞬間が訪れる。しかし、語り口は女性のままで、彼女の視点から見たパン屋の様子、彼氏の視点が語られていく。ぼーっと読んでいると見落としそうなほどシームレスに話が進んでいくのだが、ここで明らかになるのは、著者が「小説の語り手」についてかなり自覚的であるということだ。カップルが同棲を始める話にも関わらず、一般的な会話体が一切なく、それぞれの視点から見た彼、彼女に対する内面の感情が細かく描かれている。それは小説だからこそ書けることであり「演劇」という会話の塊のようなフォーマットでは描けない領域を小説で模索している様が伝わってきた。 ヒップホップ好きとしては「ショッピングモールで過ごせなかった日」を興味深く読んだ。一つのモチーフとしてラップを取り上げているのだが、「ストリート」と「ショッピングモール」を対比させつつ、どちらも同じくらいにお飾りなものでしかなく、存在自体に必然性がないことを描いている。Tohjiが提示したMall boyzの世界観を小説にしたら、こうなるかもしれないと思わされた。ただそれにしては「ストリート」に対する視点が冷めすぎており、それに呼応させるようにストリート側をダサすぎるラップ描写でラベリングしている点には抵抗があった。 「黄金期」は終わらない都市開発を舞台にした、頭のいかれた人間の話で読んでいてワクワクした。作中では横浜だが、最近渋谷に行くたびに感じる「一体何がしたいのか?」という気持ちが端的に表現されていて膝を打った。 *利便性を高めたい一心でアイデアが労力が資金が、よかれと思って投入された結果が裏目に出たということなのか、無視できない副作用が出てしまったということなのか、ずいぶんとやさぐれた場所、剝き出しになる寸前の殺気がしれっと色濃く漂う場所へと、ここをすっかり変貌させた。* そして、渋谷駅を通るたびに感じるのは、殺気だったのかと気づいた。 *各々の目的の優先を妨害してくる他の人間どもの意志を斥け合う。その意志の存在を互いにそもそも認知しないという仕方による、意志の排斥合戦によって、絶えずそこかしこで小さな火花が生じ、こうしてこの場は常時一定以上の濃度の殺気を保つ。* 三島由紀夫賞を受賞した表題作は、ここまで紹介した語り口のユニークさと暴力性が「文学」という形で結晶化した作品となっていた。話の筋としては、妻が家を出ていってしまい、タイでバカンスを一人過ごしているというもの。このとき、妻の一人称でバカンスの様子が語られるのではなく、残された夫が、妻のバカンスでの様子を二人称で語っている。残された側が「こんなバカンスを過ごしているに違いない」という妄想の羅列ともいえるのだが、小説の本質、つまり、小説とは誰かの頭の中で行われる想像の一種なのだということを、人称によって改めて明示している。それは冒頭を飾り、文中で執拗に繰り返される「ぼくはいまだにそのことを知らないでいるしこの先も知ることは決してないけれども」というセリフに象徴されているのだった。 巻末に多和田葉子との対談が収録されており、そこでも人称の話題になっていた。著者がタイで印象に残った風景や出来事を小説に落とし込むにあたり、一人称だと自分との距離が近すぎるから、このスタイルになったと語っており納得した。二人とも王道というより革新派ゆえのメタ視点の数々が興味深い。特に二人称の「あなた」から「彼方」に派生させて、近しさと距離の話に変換していく多和田葉子はラッパーだなと改めて感じた。 タイでのバカンス描写は村上春樹を彷彿とさせる洒落たものが多い。それは食事、音楽、プールというテーマに引っ張られているからそう見えるのだろう。なかでも文中で紹介される[タイのインディーポップバンド](https://music.apple.com/jp/album/lucid-dream/1191823166)が甘酸っぱいサウンドでピッタリだった。一方で、このバカンスの妄想を繰り広げてる語り手の男が暴力的というのが新鮮だ。この結果、バカンスシーンが冗長になりすぎず、物語がキュッと締まっていた。 『わたしたちに許された特別な時間の終わり』も読みたいが絶版してるようで、Kindleでリリースして欲しい。 - 2025年12月25日
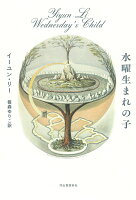 水曜生まれの子イーユン・リー,篠森ゆりこ読み終わった近年、イーユン・リーの翻訳版がコンスタントにリリースされている。小説を手にする機会が減った今も、彼女だけは例外として追い続けている。久しぶりの短編集は、短いからこその切れ味が冴え渡り、一編読み終えるたびに思わず遠い目をしてしまう、そんな余韻の深い一冊であった。 本著は2009〜2023年の14年のあいだに発表された短編をまとめた作品である。その歳月を感じさせないほど、まとまりのある短編集という印象だ。それは壮年もしくは中年の女性が主人公であり、子どもの不在を中心に思い悩む姿が繰り返し描かれるからだ。最近の長編においては、自身の出自と距離のある登場人物の小説に挑戦しているが、今回は「中国からの移民女性」という主人公が多く、著者の気配が色濃く漂っていた。 訳者あとがきにもある通り、著者の人物描写は最小限に抑えられているゆえに切れ味鋭いフレーズが際立つ。長編でも同様なのだが、短編で話の密度が大きくなることに比例するかのようにフレーズの威力も増しており、これほど付箋だらけになる小説もそうそうない。エンパワメントされる言葉もあれば、心の隙間に入り込んでくる言葉もある。 科学では妥当と考えた仮説だけを追究する。人生は、それではすまない。 人生は、死への控えの間だ。 家というのはどれほど照明がついていても、どれも同じであることを思い出させる。すべての家が、無関心な暗闇の中にある。 あたしが人間のどこが嫌いか知ってる?"これはあなたの学びになる"ってすぐ言いたがるところ。だって、学んで何の意味があるの。人生で何かに失敗しても追試は受けられないんだよ 『理由のない場所』から続く、自死によって子を失った母親の物語がやはり重く響く。先日読んだ『Θの散歩』でも書かれていたが、私自身、親となって以来、我が子か否かに関わらず、幼い命や若い命が失われることへの恐怖は増すばかりだ。そんな中で取り残された親側の心情の繊細な描写の数々は、著者の実体験と筆力がかけ合わさった結果、唯一無二のなんともいえない味わいがある。書くことでしか消化も昇華もできない感情の澱があるのだろう。子育てめぐる以下のアナロジーは、彼女の重たい心境を端的に表している。 子育てとは裁きだ。運のいい者は慎重な、あるいはやみくもな楽観主義のまま、自らの正しさを主張し続けている。 子育てはギャンブルなので、はったりをきかすしか手がないのだ。 なかでも「幸せだった頃、私たちには別の名前があった」は子どもを失って直後の短編ということもあり、感情の生々しさが他の作品よりも強烈だ。主人公はエクセルシートに記憶にある限り、自身周辺の死者を書き出して、それぞれの死を回想しながら、我が子の死を相対化しようと試みる。アプローチ自体はドライなんだけども、奥にあるウェットな感情が夫との会話のラリーで表現されていて胸が詰まった。積読していた本著をこのタイミングで読んだのはエッセイがリリースされていることを本屋で知ったから。早々にそちらも読みたい。
水曜生まれの子イーユン・リー,篠森ゆりこ読み終わった近年、イーユン・リーの翻訳版がコンスタントにリリースされている。小説を手にする機会が減った今も、彼女だけは例外として追い続けている。久しぶりの短編集は、短いからこその切れ味が冴え渡り、一編読み終えるたびに思わず遠い目をしてしまう、そんな余韻の深い一冊であった。 本著は2009〜2023年の14年のあいだに発表された短編をまとめた作品である。その歳月を感じさせないほど、まとまりのある短編集という印象だ。それは壮年もしくは中年の女性が主人公であり、子どもの不在を中心に思い悩む姿が繰り返し描かれるからだ。最近の長編においては、自身の出自と距離のある登場人物の小説に挑戦しているが、今回は「中国からの移民女性」という主人公が多く、著者の気配が色濃く漂っていた。 訳者あとがきにもある通り、著者の人物描写は最小限に抑えられているゆえに切れ味鋭いフレーズが際立つ。長編でも同様なのだが、短編で話の密度が大きくなることに比例するかのようにフレーズの威力も増しており、これほど付箋だらけになる小説もそうそうない。エンパワメントされる言葉もあれば、心の隙間に入り込んでくる言葉もある。 科学では妥当と考えた仮説だけを追究する。人生は、それではすまない。 人生は、死への控えの間だ。 家というのはどれほど照明がついていても、どれも同じであることを思い出させる。すべての家が、無関心な暗闇の中にある。 あたしが人間のどこが嫌いか知ってる?"これはあなたの学びになる"ってすぐ言いたがるところ。だって、学んで何の意味があるの。人生で何かに失敗しても追試は受けられないんだよ 『理由のない場所』から続く、自死によって子を失った母親の物語がやはり重く響く。先日読んだ『Θの散歩』でも書かれていたが、私自身、親となって以来、我が子か否かに関わらず、幼い命や若い命が失われることへの恐怖は増すばかりだ。そんな中で取り残された親側の心情の繊細な描写の数々は、著者の実体験と筆力がかけ合わさった結果、唯一無二のなんともいえない味わいがある。書くことでしか消化も昇華もできない感情の澱があるのだろう。子育てめぐる以下のアナロジーは、彼女の重たい心境を端的に表している。 子育てとは裁きだ。運のいい者は慎重な、あるいはやみくもな楽観主義のまま、自らの正しさを主張し続けている。 子育てはギャンブルなので、はったりをきかすしか手がないのだ。 なかでも「幸せだった頃、私たちには別の名前があった」は子どもを失って直後の短編ということもあり、感情の生々しさが他の作品よりも強烈だ。主人公はエクセルシートに記憶にある限り、自身周辺の死者を書き出して、それぞれの死を回想しながら、我が子の死を相対化しようと試みる。アプローチ自体はドライなんだけども、奥にあるウェットな感情が夫との会話のラリーで表現されていて胸が詰まった。積読していた本著をこのタイミングで読んだのはエッセイがリリースされていることを本屋で知ったから。早々にそちらも読みたい。 - 2025年12月14日
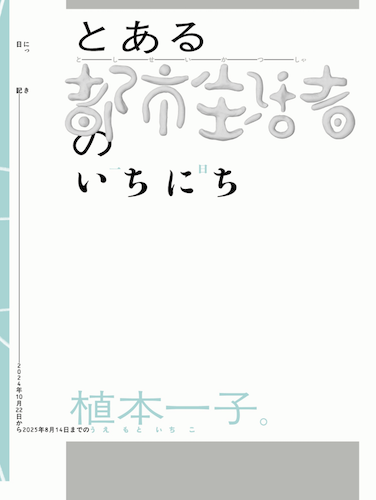 とある都市生活者のいちにち植本一子読み終わった日記ブームが続く中、そのフロントランナーである植本さんの久しぶりの日記。近作はエッセイ集が続いていたこともあり、原点回帰を感じさせる内容で興味深かった。 もともとnoteに掲載されていた日記がベースであり、読むだけなら無料で読める。それでも一冊の本としてまとめられたことで、416ページ、約13万字という特大ボリュームとなっておりファンとしては嬉しい仕様だ。そんな重さを感じさせない軽やかで読みやすい文体は健在だ。出版用に書いた日記ではなく、ウェブで不特定多数に向けて書かれたことによる「コミュニケーションとしての文章」という性質が、この軽やかさの理由なのだろう。 ウェブでは味わえない本が持つモノとしての魅力が素晴らしい。基本、車で移動しない都市生活者は荷物が少なければ少ないほどいいわけで、ポケットや鞄に入れてさっと読める文庫サイズは理にかなっている。今回最も驚いたのはフォントだ。日付、数字、引用、アルファベットなどなど多様なフォントが入り乱れており、これだけ派手な紙面は新鮮だった。表紙のタイトルはその象徴であり、特にクネクネした文字が最高。自費出版ゆえの自由さが存分に発揮されている。装丁については、植本さんの作品に頻出している高橋さんの解説に詳しい。(上記商品リンクの中で読めます。) そして、肝心の内容だが、正直に言えば、今回の最大のトピックは自分が登場していることだ。一介のファンボーイに過ぎない自分が、日記に名前が載る日が来るとは夢にも思わなかった。文学フリマに誘っていただいたこと、図々しくも「ZINEFESTに出ましょう」と自分から提案したこと、さらに自分のZINEのタイトルまで印字されているなんて…これは一生の宝物になった。 日記ブームと比例するように、「書くことの暴力性」が語られる機会も増えた。実際、他者を書く際に求められる配慮は十年前とは比べ物にならないほど高まっている。だが、その暴力性は書かれる喜びと表裏一体でもある。書いた側が忘れていたような瞬間が丁寧に掬われ、記録される。その尊さを、自分自身が書かれたことであらためて実感した。 この日記には約160人以上もの人物が登場し、都市で生き生きと暮らす人々の日常が植本さんの視点を通じて記録されている。前述した文体の軽やかさは、フットワークの軽さ、どんな人でも受けとめる懐の深さを体現していると言えるだろう。象徴的なのは自転車による移動である。縦横無尽に街を駆け、次々と人に会い、その都度日常が更新されていく姿はイメージする都市生活者そのものだった。 また、印象的だったのは、植本さんがこれまでの著作で訴えていた「さびしさ」に自分を重ね合わせる読者たちの存在だ。しかし植本さんは安易には寄り添わない。その距離感にこそ、ほんとうの優しさが宿っているように思えた。 さびしく思う読者の人もいるのだろうか?確かにいるかもしれないけれど、どうだろう。だからといって変わらないわけにはいかない。変わったようで変わっていないところもある。そうじゃない? 個人的に一番グッときたのは、ナルゲンのボトルの巡り合わせだった。ECD氏が使っていたボトルがなくなり、なんとなく覗いたガレージセールで再び同じようなボトルと遭遇する。日々の生活で、こういった運命的な瞬間はいくらでもあり、正直それは特段意味のない偶然でもあるわけだが、それが日記として記録されることで、夜空に輝く星から星座を紡ぎ出すように意味を見出すことができる。(日付がジャスト1ヶ月後…!)ここに日記の醍醐味が詰まっていた。 自費出版の流れが2作品分、掲載されており、どのように制作、営業、販売しているかを知ることができる点もこれまでの日記にない特徴である。自ら本を作る人が増えた今、多くの作り手にとって貴重なリファレンスになるだろう。その手つきは極めて丁寧かつ自分を追い込むプロフェッショナルでもある。作家は締切に追われて書く人が多いイメージを抱きがちだが、植本さんの場合、締切を意識しつつも、それ以前に「書くこと」が大事で好きなんだろうなと伝わってくる。だからこそ、ここ二作のエッセイの完成度に納得できたし、それが実現している背景は、書かされているのではなく、書いている「発注なき書き手」だからなのかもしれない。さらに日記内でも言及されている通り、場当たり的にどんどんコネクトしていって、いつのまにか何かができあがり、そこに人が集まり、ものを売っていく。そんな巻き込み力にも圧倒された。 私が作ったZINEについて、ありがたいことに植本さんからたくさんご意見をいただいた。そこでプロの洗礼を味わったことも書いておきたい。苦くもいい経験だったから。自分は内容さえ良ければ読んでもらえると思い込んでおり「どうすれば確実に読まれ、届くのか」という視点をまったく持っていなかったのだ。確かに売上だけ見れば、一度買ってもらえれば数字上はそれで終わりである。しかし、実際に読まれ、人の心を動かすことがさまざまな可能性を生み出す。本が連れて行ってくれる未来は、読まれて初めて開けるからだ。 今回の日記を読むと、植本さんは、そうして多くの人に読まれた結果、そこから生まれる人間関係に支えられながら都市で暮らしている姿が克明に刻まれている。家族という閉じた枠組みではなくとも、互助のネットワークを自ら築くことで、家族観を拡張していく実践の記録でもある。限定特典のエッセイも、まさに既存の家族観を越境していく内容で、この日記集にふさわしいものと言えるだろう。今後は日記というよりエッセイにシフトしていくようなので、日記をまとまった形で読める機会は少なくなるかもしれない。それでも植本さんの日記だからこそ味わえる日記の面白さは間違いなくあるので、またいつか出して欲しい。
とある都市生活者のいちにち植本一子読み終わった日記ブームが続く中、そのフロントランナーである植本さんの久しぶりの日記。近作はエッセイ集が続いていたこともあり、原点回帰を感じさせる内容で興味深かった。 もともとnoteに掲載されていた日記がベースであり、読むだけなら無料で読める。それでも一冊の本としてまとめられたことで、416ページ、約13万字という特大ボリュームとなっておりファンとしては嬉しい仕様だ。そんな重さを感じさせない軽やかで読みやすい文体は健在だ。出版用に書いた日記ではなく、ウェブで不特定多数に向けて書かれたことによる「コミュニケーションとしての文章」という性質が、この軽やかさの理由なのだろう。 ウェブでは味わえない本が持つモノとしての魅力が素晴らしい。基本、車で移動しない都市生活者は荷物が少なければ少ないほどいいわけで、ポケットや鞄に入れてさっと読める文庫サイズは理にかなっている。今回最も驚いたのはフォントだ。日付、数字、引用、アルファベットなどなど多様なフォントが入り乱れており、これだけ派手な紙面は新鮮だった。表紙のタイトルはその象徴であり、特にクネクネした文字が最高。自費出版ゆえの自由さが存分に発揮されている。装丁については、植本さんの作品に頻出している高橋さんの解説に詳しい。(上記商品リンクの中で読めます。) そして、肝心の内容だが、正直に言えば、今回の最大のトピックは自分が登場していることだ。一介のファンボーイに過ぎない自分が、日記に名前が載る日が来るとは夢にも思わなかった。文学フリマに誘っていただいたこと、図々しくも「ZINEFESTに出ましょう」と自分から提案したこと、さらに自分のZINEのタイトルまで印字されているなんて…これは一生の宝物になった。 日記ブームと比例するように、「書くことの暴力性」が語られる機会も増えた。実際、他者を書く際に求められる配慮は十年前とは比べ物にならないほど高まっている。だが、その暴力性は書かれる喜びと表裏一体でもある。書いた側が忘れていたような瞬間が丁寧に掬われ、記録される。その尊さを、自分自身が書かれたことであらためて実感した。 この日記には約160人以上もの人物が登場し、都市で生き生きと暮らす人々の日常が植本さんの視点を通じて記録されている。前述した文体の軽やかさは、フットワークの軽さ、どんな人でも受けとめる懐の深さを体現していると言えるだろう。象徴的なのは自転車による移動である。縦横無尽に街を駆け、次々と人に会い、その都度日常が更新されていく姿はイメージする都市生活者そのものだった。 また、印象的だったのは、植本さんがこれまでの著作で訴えていた「さびしさ」に自分を重ね合わせる読者たちの存在だ。しかし植本さんは安易には寄り添わない。その距離感にこそ、ほんとうの優しさが宿っているように思えた。 さびしく思う読者の人もいるのだろうか?確かにいるかもしれないけれど、どうだろう。だからといって変わらないわけにはいかない。変わったようで変わっていないところもある。そうじゃない? 個人的に一番グッときたのは、ナルゲンのボトルの巡り合わせだった。ECD氏が使っていたボトルがなくなり、なんとなく覗いたガレージセールで再び同じようなボトルと遭遇する。日々の生活で、こういった運命的な瞬間はいくらでもあり、正直それは特段意味のない偶然でもあるわけだが、それが日記として記録されることで、夜空に輝く星から星座を紡ぎ出すように意味を見出すことができる。(日付がジャスト1ヶ月後…!)ここに日記の醍醐味が詰まっていた。 自費出版の流れが2作品分、掲載されており、どのように制作、営業、販売しているかを知ることができる点もこれまでの日記にない特徴である。自ら本を作る人が増えた今、多くの作り手にとって貴重なリファレンスになるだろう。その手つきは極めて丁寧かつ自分を追い込むプロフェッショナルでもある。作家は締切に追われて書く人が多いイメージを抱きがちだが、植本さんの場合、締切を意識しつつも、それ以前に「書くこと」が大事で好きなんだろうなと伝わってくる。だからこそ、ここ二作のエッセイの完成度に納得できたし、それが実現している背景は、書かされているのではなく、書いている「発注なき書き手」だからなのかもしれない。さらに日記内でも言及されている通り、場当たり的にどんどんコネクトしていって、いつのまにか何かができあがり、そこに人が集まり、ものを売っていく。そんな巻き込み力にも圧倒された。 私が作ったZINEについて、ありがたいことに植本さんからたくさんご意見をいただいた。そこでプロの洗礼を味わったことも書いておきたい。苦くもいい経験だったから。自分は内容さえ良ければ読んでもらえると思い込んでおり「どうすれば確実に読まれ、届くのか」という視点をまったく持っていなかったのだ。確かに売上だけ見れば、一度買ってもらえれば数字上はそれで終わりである。しかし、実際に読まれ、人の心を動かすことがさまざまな可能性を生み出す。本が連れて行ってくれる未来は、読まれて初めて開けるからだ。 今回の日記を読むと、植本さんは、そうして多くの人に読まれた結果、そこから生まれる人間関係に支えられながら都市で暮らしている姿が克明に刻まれている。家族という閉じた枠組みではなくとも、互助のネットワークを自ら築くことで、家族観を拡張していく実践の記録でもある。限定特典のエッセイも、まさに既存の家族観を越境していく内容で、この日記集にふさわしいものと言えるだろう。今後は日記というよりエッセイにシフトしていくようなので、日記をまとまった形で読める機会は少なくなるかもしれない。それでも植本さんの日記だからこそ味わえる日記の面白さは間違いなくあるので、またいつか出して欲しい。 - 2025年12月8日
 Θの散歩富田ララフネ読み終わった帯にある「本を読むことが子育てに与える影響について」という言葉にひかれて読んだ。まさに今の自分のすべてといっても過言ではないトピックなので、それはもう楽しく読み、このまま終わらないで欲しいと願うほどだった。本を読むことと、子どもを育てることが有機的に結びつき、それぞれが深い論考として展開される、唯一無二な小説だった。 主人公は著者と同名で、妻Qと子どもΘの三人家族。主人公が一年間の育休を取得し、妻が働いているという状況の中で、主人公が0歳の子どもと東京を中心に街を徘徊しながら、子どもが寝る隙間の時間で本を読んでいる。それだけの小説なのだが、これが滅法オモシロい。 古今東西の小説やエッセイをひたすら読み、その断片を思考の足場にしながら、自身の育児へとフィードバックしていく。エッセイは実体験に根ざしているからまだ理解できるとしても、小説の一節を切り取り、貼り付け、自らの解釈を上書きし、さらに自身の物語を構築していく様は、まさしくサンプリングであり、ヒップホップ的手法と言えるだろう。 サンプリング元になる本のチョイスも2025年とは思えないラインナップで興味深い。大江健三郎、田中小実昌、カフカ、井戸川斜子など、主人公は縦横無尽に読みまくっている。なかでも中心を担うのは大江健三郎である。正直「大江と育児」なんて想像もしていなかったが、大江には知的障害をもつ息子がいて、その子どもをモチーフにした小説がある。そういった小説の視点を借りて、育児を考察していく点が新鮮だった。こうした引用スタイルそのものが大江の特徴でもあるらしく、引用するスタイルをさらに引用する、まるでマトリョーシカのようだ。 さまざまな論考が展開される中でも興味深いのは、人が生まれてから「人間」になるまでの過程に関するものである。「人間になったなぁ」と思う瞬間が0〜2歳くらいまで毎日のように訪れる。それは身体、言語能力、心といった具体的な成長であるが、著者が考察しているのはもっと抽象的なものだ。 赤ちゃんの段階では「考える」ことはない。それは、主人公親子が頻繁に訪れる上野動物園にいる盲目のポニーのようで、赤ちゃんには空洞があるだけ。しかし、成長していく中で、空洞が何かで満たされていくことを「人間化」と称し、その意味を主人公はずっと考えている。この抽象的な感覚およびその思考過程をこんなに言葉にできるなんて、著者の言語感覚がいかに鋭いか。そして、「育児は見ることなのではないか?」という主張は、今年読んだ一連の育児に関する本に通ずるものがあった。 Θの中身、つまり私たちが「考える」という行為を取得してしまったことにより「考える」にとって代わられてしまったもので、幼いΘの内面がまだそれで満ちているものというのは、実はΘの外身にこそ孕まれているのではないか?だったら私がすべきことは、Θが何を考えているんだろうと無理やり私たちの側に引きつけて想像するよりも、ただΘのことをじっと、よく見ていなければならないんじゃないか? また、男性である主人公が当たり前のように育児全般を担っている描写が画期的だ。実際に著者が育児に主体的に関わっていないと書けないだろう、ディテールの細かさに驚く。なかでも「ベビーカーだから重い本でも平気である」というのは、著者の明確な経験がそこには宿っていた。 一日中、赤子を相手にすることは確かに大変ではある。しかし、そのわずかな間隙をありがたがるように、ひたすら読書を続けていく。実質、読書日記の様相を呈しているので、ここまで述べてきた育児の話は、本著の両輪のうちの一つでしかなく、本が好きな人にとっては至福の瞬間の連続である。つまり、本を読んでいるときに時代や立場を超越し、自分の思考に何か違う視座をもたらす、あの瞬間がたくさん描かれているのだ。今や多くの人の余暇がSNSやゲームを中心としたスマホを眺める時間に捧げられているのだろうが、本著はそういった人たちに本を再び手に取らせる可能性さえ含んだ「本の小説」である。 育児に献身したことを子ども本人は覚えていない事実に主人公は戸惑いを覚えている。しかし、大江の小説を読み続けた先に待っていた「ご褒美」のような、そのことに関する解釈が飛び出す瞬間が描かれ、思わず膝を打った。自身の子どもの協調性について色々思うことが増える中で、その視座は大きな示唆となった。いい意味で諦念を抱きながら、子どもの姿を眺めることができるようになった。(大江の小説を読まずに獲得していることについて、この小説の主人公はいい気持ちはしないだろうが。)子どもの言動に思いをめぐらせて、もうすぐ4年。こうして自分の言葉で考えることこそが育児の喜びであり、苦悩でもあるということを改めて気づかせてくれる小説だった。
Θの散歩富田ララフネ読み終わった帯にある「本を読むことが子育てに与える影響について」という言葉にひかれて読んだ。まさに今の自分のすべてといっても過言ではないトピックなので、それはもう楽しく読み、このまま終わらないで欲しいと願うほどだった。本を読むことと、子どもを育てることが有機的に結びつき、それぞれが深い論考として展開される、唯一無二な小説だった。 主人公は著者と同名で、妻Qと子どもΘの三人家族。主人公が一年間の育休を取得し、妻が働いているという状況の中で、主人公が0歳の子どもと東京を中心に街を徘徊しながら、子どもが寝る隙間の時間で本を読んでいる。それだけの小説なのだが、これが滅法オモシロい。 古今東西の小説やエッセイをひたすら読み、その断片を思考の足場にしながら、自身の育児へとフィードバックしていく。エッセイは実体験に根ざしているからまだ理解できるとしても、小説の一節を切り取り、貼り付け、自らの解釈を上書きし、さらに自身の物語を構築していく様は、まさしくサンプリングであり、ヒップホップ的手法と言えるだろう。 サンプリング元になる本のチョイスも2025年とは思えないラインナップで興味深い。大江健三郎、田中小実昌、カフカ、井戸川斜子など、主人公は縦横無尽に読みまくっている。なかでも中心を担うのは大江健三郎である。正直「大江と育児」なんて想像もしていなかったが、大江には知的障害をもつ息子がいて、その子どもをモチーフにした小説がある。そういった小説の視点を借りて、育児を考察していく点が新鮮だった。こうした引用スタイルそのものが大江の特徴でもあるらしく、引用するスタイルをさらに引用する、まるでマトリョーシカのようだ。 さまざまな論考が展開される中でも興味深いのは、人が生まれてから「人間」になるまでの過程に関するものである。「人間になったなぁ」と思う瞬間が0〜2歳くらいまで毎日のように訪れる。それは身体、言語能力、心といった具体的な成長であるが、著者が考察しているのはもっと抽象的なものだ。 赤ちゃんの段階では「考える」ことはない。それは、主人公親子が頻繁に訪れる上野動物園にいる盲目のポニーのようで、赤ちゃんには空洞があるだけ。しかし、成長していく中で、空洞が何かで満たされていくことを「人間化」と称し、その意味を主人公はずっと考えている。この抽象的な感覚およびその思考過程をこんなに言葉にできるなんて、著者の言語感覚がいかに鋭いか。そして、「育児は見ることなのではないか?」という主張は、今年読んだ一連の育児に関する本に通ずるものがあった。 Θの中身、つまり私たちが「考える」という行為を取得してしまったことにより「考える」にとって代わられてしまったもので、幼いΘの内面がまだそれで満ちているものというのは、実はΘの外身にこそ孕まれているのではないか?だったら私がすべきことは、Θが何を考えているんだろうと無理やり私たちの側に引きつけて想像するよりも、ただΘのことをじっと、よく見ていなければならないんじゃないか? また、男性である主人公が当たり前のように育児全般を担っている描写が画期的だ。実際に著者が育児に主体的に関わっていないと書けないだろう、ディテールの細かさに驚く。なかでも「ベビーカーだから重い本でも平気である」というのは、著者の明確な経験がそこには宿っていた。 一日中、赤子を相手にすることは確かに大変ではある。しかし、そのわずかな間隙をありがたがるように、ひたすら読書を続けていく。実質、読書日記の様相を呈しているので、ここまで述べてきた育児の話は、本著の両輪のうちの一つでしかなく、本が好きな人にとっては至福の瞬間の連続である。つまり、本を読んでいるときに時代や立場を超越し、自分の思考に何か違う視座をもたらす、あの瞬間がたくさん描かれているのだ。今や多くの人の余暇がSNSやゲームを中心としたスマホを眺める時間に捧げられているのだろうが、本著はそういった人たちに本を再び手に取らせる可能性さえ含んだ「本の小説」である。 育児に献身したことを子ども本人は覚えていない事実に主人公は戸惑いを覚えている。しかし、大江の小説を読み続けた先に待っていた「ご褒美」のような、そのことに関する解釈が飛び出す瞬間が描かれ、思わず膝を打った。自身の子どもの協調性について色々思うことが増える中で、その視座は大きな示唆となった。いい意味で諦念を抱きながら、子どもの姿を眺めることができるようになった。(大江の小説を読まずに獲得していることについて、この小説の主人公はいい気持ちはしないだろうが。)子どもの言動に思いをめぐらせて、もうすぐ4年。こうして自分の言葉で考えることこそが育児の喜びであり、苦悩でもあるということを改めて気づかせてくれる小説だった。 - 2025年12月2日
 湖まで大崎清夏読み終わった著者の名前をいろんな場面で拝見するものの、馴染みのない詩ということもあり実際の作品を読んだことがなかった中で、palm booksから小説がリリースされたということで読んだ。連作小説集で、つながりは緩やかにありつつ、それぞれ後味が異なっていて楽しく読んだ。 最初の短編は少し不思議なトーンで、目の前で起こる具体的な出来事と心象風景の重なりが独特の世界として立ち上がる。その意外性に驚かされたが、続く短編は一転して地に足のついたリアリティがあり、詩人である著者の「つかみ」としての配置なのかもしれない。 「別れと自立」が一つのテーマとして映った。誰かと生きていても、ふとしたきっかけで一人になる可能性はいつも身近にある。しかし、ただちに孤独が訪れるわけではなく、ゆるりとした連帯、それは既存の「家族」ではない、もっと広い概念で誰かと生きることについて書かれている。 私が特に好きだった短編は「次の足を出すところ」。五月の自然を捉えた冒頭の描写に心を掴まれた。状況説明ではなく、余白に満ちた情景描写こそ小説の醍醐味であり、久々に小説を読むことも相まって癒やされた。悲劇的な出来事を扱いつつも、それ以上に「足を踏み出す」という動作のアナロジーが強く胸を打った。でこぼこの地面を歩くとき、転ばずに前へ進むための一歩。車を運転するときにアクセルを踏み出す行為。それらが物語の冒頭と終わりで響き合い、美しい円環構造となっていた。 また、自立することは移動することを意味し、どの短編でも歩いている場面が多い。等高線が印象的なブックカバーは「移動」が本著の象徴であることを端的に表現した素晴らしいブックデザインだ。本著では詩歌、日記という著者の武器が小説の中へフィードバックされていて、著者の見本市のようでもあった。 「眼鏡のバレリーナのために」を読んだとき、どこかで見覚えがあると感じたが、既刊『palmstories あなた』に収録されていた短編の再録だった。前回はアンソロジーの一編として縦の比較ができる読み方だったが、今回は同じ主人公の周辺に焦点を当てた横展開で、小説の自由さとタイムレス性を楽しめた。 感触を大切にしている描写が印象的だった。陶器やギターといった曲線に人間がフィットする、何ともいえない運命的な瞬間が表現されている。確かに陶器やギターは見た目も大事だが、日々使うものだからこそ、手触りこそが大事で、「人生の手触り」がテーマの一つだとも感じられ、文字通りしっくりきた。AIなど実態のない価値がもてはやされる今、物体として存在することの意味を柔らかく表現してくれていた。次は日記を読んでみたい。
湖まで大崎清夏読み終わった著者の名前をいろんな場面で拝見するものの、馴染みのない詩ということもあり実際の作品を読んだことがなかった中で、palm booksから小説がリリースされたということで読んだ。連作小説集で、つながりは緩やかにありつつ、それぞれ後味が異なっていて楽しく読んだ。 最初の短編は少し不思議なトーンで、目の前で起こる具体的な出来事と心象風景の重なりが独特の世界として立ち上がる。その意外性に驚かされたが、続く短編は一転して地に足のついたリアリティがあり、詩人である著者の「つかみ」としての配置なのかもしれない。 「別れと自立」が一つのテーマとして映った。誰かと生きていても、ふとしたきっかけで一人になる可能性はいつも身近にある。しかし、ただちに孤独が訪れるわけではなく、ゆるりとした連帯、それは既存の「家族」ではない、もっと広い概念で誰かと生きることについて書かれている。 私が特に好きだった短編は「次の足を出すところ」。五月の自然を捉えた冒頭の描写に心を掴まれた。状況説明ではなく、余白に満ちた情景描写こそ小説の醍醐味であり、久々に小説を読むことも相まって癒やされた。悲劇的な出来事を扱いつつも、それ以上に「足を踏み出す」という動作のアナロジーが強く胸を打った。でこぼこの地面を歩くとき、転ばずに前へ進むための一歩。車を運転するときにアクセルを踏み出す行為。それらが物語の冒頭と終わりで響き合い、美しい円環構造となっていた。 また、自立することは移動することを意味し、どの短編でも歩いている場面が多い。等高線が印象的なブックカバーは「移動」が本著の象徴であることを端的に表現した素晴らしいブックデザインだ。本著では詩歌、日記という著者の武器が小説の中へフィードバックされていて、著者の見本市のようでもあった。 「眼鏡のバレリーナのために」を読んだとき、どこかで見覚えがあると感じたが、既刊『palmstories あなた』に収録されていた短編の再録だった。前回はアンソロジーの一編として縦の比較ができる読み方だったが、今回は同じ主人公の周辺に焦点を当てた横展開で、小説の自由さとタイムレス性を楽しめた。 感触を大切にしている描写が印象的だった。陶器やギターといった曲線に人間がフィットする、何ともいえない運命的な瞬間が表現されている。確かに陶器やギターは見た目も大事だが、日々使うものだからこそ、手触りこそが大事で、「人生の手触り」がテーマの一つだとも感じられ、文字通りしっくりきた。AIなど実態のない価値がもてはやされる今、物体として存在することの意味を柔らかく表現してくれていた。次は日記を読んでみたい。 - 2025年11月28日
 読み終わったDJ PATSAT『平凡な生活』を読んで、ずっと積んであった本著を読んだ。著者はDJ PATSATこと土井さんが経営するタマウマラで共に働いていた方で、日記に何度も登場する重要人物だ。自転車屋で二人とも文筆業を行っていること自体驚きだが、あまりにもブロークンな著者のスタイルが衝撃的な読書体験だった。 本著は、著者が大阪で過ごしていた日々を中心に書かれたエッセイ集。冒頭「ダルク体験記」から始まり、あまりにカジュアルなドラッグ描写に度肝を抜かれる。その描写は単にドラッグを嗜んでいるというだけではなく、どういった人がダルクにきているのか、薬物遍歴からその人たちの日常まで、細かく描かれており、こんな人が世の中にいるのかと何度も驚いた。(猫フーさんのエスタック中毒…!) 一方で友人や彼女といった周辺人物のバックグラウンドはほとんど紹介されないまま、過去と現在を行き来するような散文スタイルで自身の思いが朴訥なスタイルで綴られていく。文章に起承転結はなく、時間軸もバラバラで、何度も場面をスイッチしていく。著者はラッパーでもあるので、リリックのように書いているとも言えるが、正直読みにくかった。しかし、そんな中でも急に具体的なシーンが脳内に突如想起され、心にパーンと入ってくるラインがやってくる。そして、その何かを追い求めるように読み進めてしまう。まさにドラッグのような文章と言える。部分的に抜き出しても伝わらないかもしれないが、コンテキストの中に埋め込まれた瞬間に輝く、著者独自の筆力がなせる技だ。 仕事をして、お金がある程度あって、大事な人が笑っていて、これは当たり前というか、その暮らしの中でもほんの一瞬だけの、幸せなこと、気持ちのいいこと、目を見開くこと、息をのむこと、感動して涙が出ることなど、これらは本当に一瞬で、一瞬でなければ良いのにといつも思うけど絶対に一瞬だから、毎日を丁寧にそっと生きなくてはいけないと思う。 一緒なことは安心だった。暮らしの中で、そうやって定規を他に頼ってやっていると、時々どうしようもなく自分に立ち返ってしまう瞬間に、さてそれを引き剥がさないといけない。 自分の好きや嫌いが反射して、その返ってくる速度で自分というものを計って、その上で、その世界の中で、してもおかしくないことを決めていくような感じ。 私は大阪出身で著者とほぼ同世代、なおかつ出入りしていた場所が似通っており、あの頃、身近なところでこんなに破天荒な出来事が起こっていただなんて信じられなかった。ラッパーゆえのヒップホップ的なエピソードがいくつかあって、そこにもアガった。ダルクにK-MOONことGradice Niceのビート集があった話、MOBB DEEPの音が流れる中、部屋の壁に頭をぶつける姉、釜ヶ崎の夏祭りでの出番の話など。SHINGO★西成がいうところの「ズルムケ」のヒップホップ的な人生がそこにあり、著者が世で生きていくためにヒップホップや文学があるように映った。 表題作は宗教二世に関する話で、安倍晋三を殺害した山上被告の裁判が始まった今、タイムリーな話だ。統一教会ではないが、おなじく宗教にのめりこんだ親から子どもがどういった影響を受けるのか、なかなか知り得ない現実ばかりだった。自分たちと異なる信仰を持つ人を「世の人」と呼び、蔑んでいるエホバの思想と、著者が「世の人」に向ける眼差しのかけ算によってマジックが起こっていた。小説みたいな現実の話がたくさん読めたので、次は著者による小説を読んでみたい。
読み終わったDJ PATSAT『平凡な生活』を読んで、ずっと積んであった本著を読んだ。著者はDJ PATSATこと土井さんが経営するタマウマラで共に働いていた方で、日記に何度も登場する重要人物だ。自転車屋で二人とも文筆業を行っていること自体驚きだが、あまりにもブロークンな著者のスタイルが衝撃的な読書体験だった。 本著は、著者が大阪で過ごしていた日々を中心に書かれたエッセイ集。冒頭「ダルク体験記」から始まり、あまりにカジュアルなドラッグ描写に度肝を抜かれる。その描写は単にドラッグを嗜んでいるというだけではなく、どういった人がダルクにきているのか、薬物遍歴からその人たちの日常まで、細かく描かれており、こんな人が世の中にいるのかと何度も驚いた。(猫フーさんのエスタック中毒…!) 一方で友人や彼女といった周辺人物のバックグラウンドはほとんど紹介されないまま、過去と現在を行き来するような散文スタイルで自身の思いが朴訥なスタイルで綴られていく。文章に起承転結はなく、時間軸もバラバラで、何度も場面をスイッチしていく。著者はラッパーでもあるので、リリックのように書いているとも言えるが、正直読みにくかった。しかし、そんな中でも急に具体的なシーンが脳内に突如想起され、心にパーンと入ってくるラインがやってくる。そして、その何かを追い求めるように読み進めてしまう。まさにドラッグのような文章と言える。部分的に抜き出しても伝わらないかもしれないが、コンテキストの中に埋め込まれた瞬間に輝く、著者独自の筆力がなせる技だ。 仕事をして、お金がある程度あって、大事な人が笑っていて、これは当たり前というか、その暮らしの中でもほんの一瞬だけの、幸せなこと、気持ちのいいこと、目を見開くこと、息をのむこと、感動して涙が出ることなど、これらは本当に一瞬で、一瞬でなければ良いのにといつも思うけど絶対に一瞬だから、毎日を丁寧にそっと生きなくてはいけないと思う。 一緒なことは安心だった。暮らしの中で、そうやって定規を他に頼ってやっていると、時々どうしようもなく自分に立ち返ってしまう瞬間に、さてそれを引き剥がさないといけない。 自分の好きや嫌いが反射して、その返ってくる速度で自分というものを計って、その上で、その世界の中で、してもおかしくないことを決めていくような感じ。 私は大阪出身で著者とほぼ同世代、なおかつ出入りしていた場所が似通っており、あの頃、身近なところでこんなに破天荒な出来事が起こっていただなんて信じられなかった。ラッパーゆえのヒップホップ的なエピソードがいくつかあって、そこにもアガった。ダルクにK-MOONことGradice Niceのビート集があった話、MOBB DEEPの音が流れる中、部屋の壁に頭をぶつける姉、釜ヶ崎の夏祭りでの出番の話など。SHINGO★西成がいうところの「ズルムケ」のヒップホップ的な人生がそこにあり、著者が世で生きていくためにヒップホップや文学があるように映った。 表題作は宗教二世に関する話で、安倍晋三を殺害した山上被告の裁判が始まった今、タイムリーな話だ。統一教会ではないが、おなじく宗教にのめりこんだ親から子どもがどういった影響を受けるのか、なかなか知り得ない現実ばかりだった。自分たちと異なる信仰を持つ人を「世の人」と呼び、蔑んでいるエホバの思想と、著者が「世の人」に向ける眼差しのかけ算によってマジックが起こっていた。小説みたいな現実の話がたくさん読めたので、次は著者による小説を読んでみたい。 - 2025年11月17日
 平凡な生活 / DJ PATSATの日記DJ PATSAT読み終わったずいぶん前に、Riverside Reading Clubの投稿で『DJ PATSATの日記』の存在を知り、買いたいと思ったときには既に入手できなくなっていたvol.1 & vol.2が文庫サイズで一冊にまとまり、書き下ろしも加わってリイシューということで読んだ。『PATSATSHIT』『ほんまのきもち』も楽しく読んだので期待していたが、本著はまさに原点にして頂点と言える。日記ブームの中、さまざまなスタイルの日記があるものの、この唯一無二性は他の追随を許さない。本著の言葉を借りるならば、「読む前と読んだ後では確実に見える景色が違う」、そういう類の本だった。 本著は、2020年の vol.1、2022年の vol.2、そして日付のない日記の三部構成。まず、装丁のかっこよさに目を奪われる。モノクロの版画のような写真(?)が外カバーとして巻かれた角ばった文庫。外で本を読むときは大抵ブックカバーしているが、装丁がかっこいいし、持ち歩きには最高のサイズなので、かばんにそのままポンと入れて、移動の合間に読むことが多かった。それは著者が一貫して伝え、実践し、語っている「街で生きる」というテーゼと響き合う行為であり、装丁によって行動が駆動される。そんな本という物体の魅力を改めて感じた。 vol.1 はコロナ禍真っ只中の日記。当時、人々がどう過ごしているのか知りたくて多くの日記を読んだが、今読むとまるでSFの世界であり、改めてあの頃の特異さを再認識した。著者は大阪・淡路で自転車屋を経営し、人と接して初めて成り立つ仕事をしている。そんな状況の中で、家族、同僚、街の人たちとどのように日々生きていたのかが描かれている。お店をやっていることで、いろんな人が訪ねてくるシーンが特に興味深い。自転車という誰もが使う交通手段、さらには土地柄もあいまって、個性豊かな人たちが続々とお店にやってくる。『PATSATSHIT』を読んだときも感じたが、鋭い観察眼と描写力に基づいた独特の文体は、まるで小説を読んでいるかのようだ。また、変わった客や悪意のある客のことを単に「わるい人」として一面的に描くのではなく、多面的に描いていることから、著者の優しさが伝わってきた。 本著は店舗日誌、読書日記、さまざまな日記的側面を持ち合わせているのだが、なかでも一番心に残ったのは、育児日記としての側面だった。著者には二人の子どもがおり、小学校・保育園で起こる悲喜交々に何度も感情を揺さぶられた。子どもたちが成長し、自分たちのコミュニティ、関係性を作っていく様をこんなに豊かに書けるのかと何度も唸らされた。特に長男のエピソードは、何気ない話なのだが、著者の筆力もあいまって忘れられないものばかりだ。友人とのけん玉バトルの顛末や、学校に行きたがらない場面で友人たちが登場する場面は涙してしまった。また、長男が周囲と協調しない姿を目にして、自身の「空気を読んできた」過去と照らし合わせ、自分を超えたと認識する場面は、なかなかできない思考の展開だ。 次男をめぐっては、保育園との関係性の構築が印象的だった。私自身も毎日の送り迎えの中で、保育園、幼稚園という場所の尊さを痛感する日々なわけだが、著者は自分とは別ベクトルで保育園をとらえている点が興味深かった。やはりここでも、お店に来るお客さんに対する眼差しと同様に圧倒的な鋭さと優しさが発揮されていた。先日読んだ『それがやさしさじゃ困る』にも通ずるが、大人は子どもを甘く見るのではなく、しっかり観察した結果に基づいてフィードバックする必要があると思うし、著者は自分の子どもだけではなく、子どもたち全体を本当の意味で「見ている」のだなと読んでいて何度も感じた。その眼差しを前に、自分が一体どれだけ見れているのだろうかと考えさせられた。 日々の出来事を記録するだけでも日記は面白いが、本著では、各出来事を起点に思想が展開していく点が、並の日記と一線を画している。読んでいるあいだ、インディペンデントであることの意義について何度も考えさせられた。本の引用も含め、これだけ自分の考えを言語化できて、さらには実践できる人間がどれだけいるだろうか。「ストリートナレッジ」とは本著のような作品のために用意された言葉だろう。このラインにハッとした人は全員読むべきクラシックだ。 *誰であれ、どのような行為であれ、人が人に手を差し伸べるということには、ある確実な物質的基盤があり、秩序があり、意味がある。その懸命な営みには、素直に美しいと思わせるものがある。瞬間的に芽生えた愛にはそれ自体としての目的はない。しかし思いやりの気持ちを積み重ねることによって、社会という本当に捉えどころのないものに対する観察と考えが深まってゆく。*
平凡な生活 / DJ PATSATの日記DJ PATSAT読み終わったずいぶん前に、Riverside Reading Clubの投稿で『DJ PATSATの日記』の存在を知り、買いたいと思ったときには既に入手できなくなっていたvol.1 & vol.2が文庫サイズで一冊にまとまり、書き下ろしも加わってリイシューということで読んだ。『PATSATSHIT』『ほんまのきもち』も楽しく読んだので期待していたが、本著はまさに原点にして頂点と言える。日記ブームの中、さまざまなスタイルの日記があるものの、この唯一無二性は他の追随を許さない。本著の言葉を借りるならば、「読む前と読んだ後では確実に見える景色が違う」、そういう類の本だった。 本著は、2020年の vol.1、2022年の vol.2、そして日付のない日記の三部構成。まず、装丁のかっこよさに目を奪われる。モノクロの版画のような写真(?)が外カバーとして巻かれた角ばった文庫。外で本を読むときは大抵ブックカバーしているが、装丁がかっこいいし、持ち歩きには最高のサイズなので、かばんにそのままポンと入れて、移動の合間に読むことが多かった。それは著者が一貫して伝え、実践し、語っている「街で生きる」というテーゼと響き合う行為であり、装丁によって行動が駆動される。そんな本という物体の魅力を改めて感じた。 vol.1 はコロナ禍真っ只中の日記。当時、人々がどう過ごしているのか知りたくて多くの日記を読んだが、今読むとまるでSFの世界であり、改めてあの頃の特異さを再認識した。著者は大阪・淡路で自転車屋を経営し、人と接して初めて成り立つ仕事をしている。そんな状況の中で、家族、同僚、街の人たちとどのように日々生きていたのかが描かれている。お店をやっていることで、いろんな人が訪ねてくるシーンが特に興味深い。自転車という誰もが使う交通手段、さらには土地柄もあいまって、個性豊かな人たちが続々とお店にやってくる。『PATSATSHIT』を読んだときも感じたが、鋭い観察眼と描写力に基づいた独特の文体は、まるで小説を読んでいるかのようだ。また、変わった客や悪意のある客のことを単に「わるい人」として一面的に描くのではなく、多面的に描いていることから、著者の優しさが伝わってきた。 本著は店舗日誌、読書日記、さまざまな日記的側面を持ち合わせているのだが、なかでも一番心に残ったのは、育児日記としての側面だった。著者には二人の子どもがおり、小学校・保育園で起こる悲喜交々に何度も感情を揺さぶられた。子どもたちが成長し、自分たちのコミュニティ、関係性を作っていく様をこんなに豊かに書けるのかと何度も唸らされた。特に長男のエピソードは、何気ない話なのだが、著者の筆力もあいまって忘れられないものばかりだ。友人とのけん玉バトルの顛末や、学校に行きたがらない場面で友人たちが登場する場面は涙してしまった。また、長男が周囲と協調しない姿を目にして、自身の「空気を読んできた」過去と照らし合わせ、自分を超えたと認識する場面は、なかなかできない思考の展開だ。 次男をめぐっては、保育園との関係性の構築が印象的だった。私自身も毎日の送り迎えの中で、保育園、幼稚園という場所の尊さを痛感する日々なわけだが、著者は自分とは別ベクトルで保育園をとらえている点が興味深かった。やはりここでも、お店に来るお客さんに対する眼差しと同様に圧倒的な鋭さと優しさが発揮されていた。先日読んだ『それがやさしさじゃ困る』にも通ずるが、大人は子どもを甘く見るのではなく、しっかり観察した結果に基づいてフィードバックする必要があると思うし、著者は自分の子どもだけではなく、子どもたち全体を本当の意味で「見ている」のだなと読んでいて何度も感じた。その眼差しを前に、自分が一体どれだけ見れているのだろうかと考えさせられた。 日々の出来事を記録するだけでも日記は面白いが、本著では、各出来事を起点に思想が展開していく点が、並の日記と一線を画している。読んでいるあいだ、インディペンデントであることの意義について何度も考えさせられた。本の引用も含め、これだけ自分の考えを言語化できて、さらには実践できる人間がどれだけいるだろうか。「ストリートナレッジ」とは本著のような作品のために用意された言葉だろう。このラインにハッとした人は全員読むべきクラシックだ。 *誰であれ、どのような行為であれ、人が人に手を差し伸べるということには、ある確実な物質的基盤があり、秩序があり、意味がある。その懸命な営みには、素直に美しいと思わせるものがある。瞬間的に芽生えた愛にはそれ自体としての目的はない。しかし思いやりの気持ちを積み重ねることによって、社会という本当に捉えどころのないものに対する観察と考えが深まってゆく。*
読み込み中...