リヴァイアサン 1

2件の記録
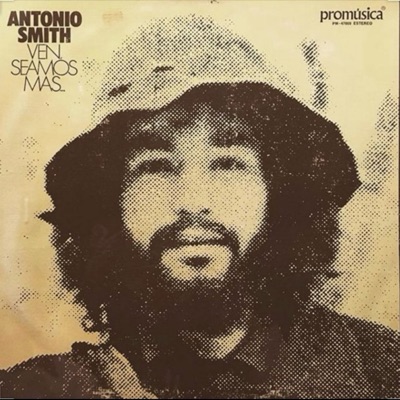 J.B.@hermit_psyche2025年10月10日読み終わった本書を読むことは単に近代政治哲学の古典を味わうという行為にとどまらない。 それは人間とは何か、社会とはいかに成立するのか、そして理性が暴力を制御できるかという文明史の根源的難問に対峙する知的儀式である。 ホッブズはこの書において神学的秩序の崩壊と市民社会の誕生をつなぐ知の橋梁を構築した。 岩波文庫版の第一巻はその設計図の部分にあたる。 ホッブズが描く万人の万人に対する闘争(bellum omnium contra omnes)は単なる悲観主義的寓話ではない。 それは社会契約という構築物を導出するための論理的起点である。 人間は平等であり同等の希望と恐怖を抱く。 この心理的平等はアリストテレス的な目的論的人間観とは正反対の非目的論的自然主義である。 この思考の転回はルネサンスの人文主義を通過した後に科学革命的世界観を政治へ転写した最初の試みであった。 すなわちホッブズは政治を物理化したのである。 「国家(コモンウェルス)は人工的人間であり、その魂は主権者である」とホッブズは言う。 この比喩の中に近代的統治の本質が凝縮されている。 ホッブズが目指したのは暴力の終焉ではなく、暴力の単一化であった。 万人の恐怖を一つの恐怖対象に集約する。 これがリヴァイアサン(主権国家)の成立条件である。 したがって主権とは暴力を正当化する力ではなく暴力を所有することの正当性を定義する権限である。 この論理構造はのちのカール・シュミットが「主権者とは例外状態を決定する者」と定義した政治神学へと連結し、さらにフーコーの統治理性(governmentality)論の伏線ともなった。 ホッブズが「リヴァイアサン」で提示したのは国家論ではなく人間存在の悲劇的方程式である。 「人間の状態は、平和のときにおいても、戦争の恐怖のなかにある。」 この洞察は、21世紀のわれわれにもなお通用する。 AIの時代にあっても人間社会の根底には信頼の不在と暴力の潜在がある。 ホッブズの理性は楽観主義的啓蒙ではなく恐怖の形而上学的構造を解体しようとする冷徹な試みなのだ。
J.B.@hermit_psyche2025年10月10日読み終わった本書を読むことは単に近代政治哲学の古典を味わうという行為にとどまらない。 それは人間とは何か、社会とはいかに成立するのか、そして理性が暴力を制御できるかという文明史の根源的難問に対峙する知的儀式である。 ホッブズはこの書において神学的秩序の崩壊と市民社会の誕生をつなぐ知の橋梁を構築した。 岩波文庫版の第一巻はその設計図の部分にあたる。 ホッブズが描く万人の万人に対する闘争(bellum omnium contra omnes)は単なる悲観主義的寓話ではない。 それは社会契約という構築物を導出するための論理的起点である。 人間は平等であり同等の希望と恐怖を抱く。 この心理的平等はアリストテレス的な目的論的人間観とは正反対の非目的論的自然主義である。 この思考の転回はルネサンスの人文主義を通過した後に科学革命的世界観を政治へ転写した最初の試みであった。 すなわちホッブズは政治を物理化したのである。 「国家(コモンウェルス)は人工的人間であり、その魂は主権者である」とホッブズは言う。 この比喩の中に近代的統治の本質が凝縮されている。 ホッブズが目指したのは暴力の終焉ではなく、暴力の単一化であった。 万人の恐怖を一つの恐怖対象に集約する。 これがリヴァイアサン(主権国家)の成立条件である。 したがって主権とは暴力を正当化する力ではなく暴力を所有することの正当性を定義する権限である。 この論理構造はのちのカール・シュミットが「主権者とは例外状態を決定する者」と定義した政治神学へと連結し、さらにフーコーの統治理性(governmentality)論の伏線ともなった。 ホッブズが「リヴァイアサン」で提示したのは国家論ではなく人間存在の悲劇的方程式である。 「人間の状態は、平和のときにおいても、戦争の恐怖のなかにある。」 この洞察は、21世紀のわれわれにもなお通用する。 AIの時代にあっても人間社会の根底には信頼の不在と暴力の潜在がある。 ホッブズの理性は楽観主義的啓蒙ではなく恐怖の形而上学的構造を解体しようとする冷徹な試みなのだ。


