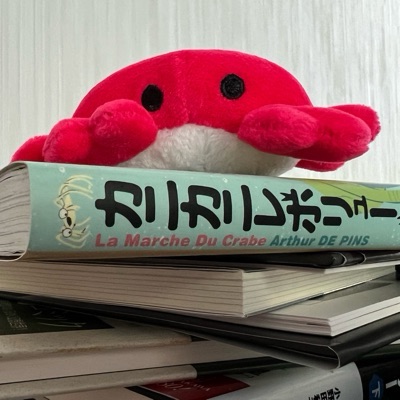映画の見方がわかる本: 2001年宇宙の旅から未知との遭遇まで (映画秘宝COLLECTION 22)

映画の見方がわかる本: 2001年宇宙の旅から未知との遭遇まで (映画秘宝COLLECTION 22)
町山智浩
洋泉社
2002年8月1日
1件の記録
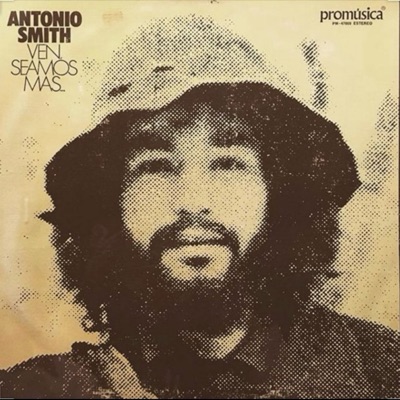 J.B.@hermit_psyche2025年10月15日読み終わった映画鑑賞をただの娯楽消費から知的実践へと昇華させることを主眼にした入門書でありながら、その到達志向は初心者向けの枠を超えている。 本書は映画の何を観るかではなくどう観るかを徹底して問う。 視覚言語、語りの構造、ジャンル的文脈、政治性、観客の立場といった多層的な分析軸を提供することで、読者に観察のための道具箱を与える。 本書の最大の貢献は具体例と一般原理の往還にある。 町山は典型的な映画論(撮像技術やナラティブ理論)に留まらず日常的な観察、ショットが寄せられるときの身体的反応、カットの速度が引き起こす時間知覚の歪み、音響が作る感情の先取りを理論化して見せる。 学術的抽象と感覚的記述の接着は均質ではないが、むしろその不均衡が読者に思考の余地を与える。 理論に厳格を期する読者は、町山の議論における一般化の瞬間に慎重な検討を要するだろうが、実務的な観察力を鍛えるという目的に関しては彼の記述様式は極めて効果的だ。 本書における重要な分析軸としてまず挙げられるのは映像言語に対する精密な考察である。 町山はショットやシークエンスの機能、レンズの選択、空間の再構成、カメラ運動が物語の意味へ及ぼす効果を具体的なシーンの参照を通して解説している。 彼はこれらの映像要素を単なる技術的装飾として扱うのではなく視覚的ディテールが語る非言語的テクストとして読み解く訓練を読者に促している点に特徴がある。 次に物語と時間の問題に関して、町山は伝統的な因果連鎖と映画特有の時間操作、フラッシュバックや反復、モンタージュといった手法との相互作用を丁寧に論じている。 その際時間の操作を演出上の技巧としてではなく観客の倫理的・感情的理解に介入する戦術として読み替える視点が提示されており、この点は特に高く評価できる。 またジャンルと文化的コードに関する章では、ジャンルを物語様式としてではなく観客の期待や解釈のプロトコルを内包した装置として捉える姿勢が貫かれている。 町山はジャンル分析を通じて映画が社会的想像力をいかに形成し、共有される文化的枠組みを再生産するかを明らかにしており、その射程は映画批評を社会思想的文脈にまで拡張している。 さらに政治性とイデオロギーについての洞察も見逃せない。 町山は映画が提示する世界像や価値判断を見逃さず政治的な読み取りを安易な決め付けに還元しないバランス感覚を維持している。 しかし一方で時に断定的な価値判断が前景化し、批評家としての立場表明がそのまま説得力に転化する局面とそうならない局面とが混在している点も指摘しておくべきである。 本書の長所としてまず挙げられるのは、その実践的な洞察である。 理論の抽象的な羅列にとどまらず、鑑賞中に即座に応用できる視点が豊富に提示されており、映画を観るという行為そのものを精密に分解して見せる手際は見事である。 加えて説得力のある比喩と記述によって映像表現の感覚を言語化する能力に優れ、読者が自らの視覚経験を再構築する助けとなっている。 さらに古典から現代に至るまでの幅広い参照範囲を通じて比較対照によって概念を立ち上げる構成力にも独自の厚みがある。 その一方でいくつかの限界や留意点も存在する。 まず理論的一貫性の欠如が挙げられる。 学術的厳密性を重視する読者にとっては概念定義の曖昧さや論の跳躍的展開がやや不満足に映るかもしれない。 また価値判断の断定性に関しても町山自身の批評的立場や価値観が分析の前提として透けて見える場面がある。 これは批評家としての個性の発露でもあるが、学術的中立を求める読者には違和感を与える可能性がある。 さらに事例依存の傾向も見受けられる。 具体例の豊富さは本書の魅力である反面、それらを異なる文脈へ一般化する際の論拠が十分に補強されていない箇所もある。 すなわちこの映画ではこう機能しているが、他の条件下でも同様に働くのかという問いに常に明確な答えが用意されているわけではないのである。 本書は映画学の専門家というよりは教養的な実践者を主たる想定読者とする。 映画祭でのキュレーション、映画教育、批評執筆、あるいは映画制作の初学者が観察眼と論説力を獲得するための良書である。 町山智浩の本は映画を何となく好きだというレジームから一歩踏み出させる力を持つ。 観客に対して観察の技術を与え、映像表現がどのように意味を編み出すかを体感させる点で実践的価値は高い。 理論的一貫性や学術的精緻化を求める向きには改善余地があるが、その短所は本書の語り口と目的意識によって部分的に補償されている。 映画をより注意深く、より思考的に観たい者に強く勧められる一冊である。
J.B.@hermit_psyche2025年10月15日読み終わった映画鑑賞をただの娯楽消費から知的実践へと昇華させることを主眼にした入門書でありながら、その到達志向は初心者向けの枠を超えている。 本書は映画の何を観るかではなくどう観るかを徹底して問う。 視覚言語、語りの構造、ジャンル的文脈、政治性、観客の立場といった多層的な分析軸を提供することで、読者に観察のための道具箱を与える。 本書の最大の貢献は具体例と一般原理の往還にある。 町山は典型的な映画論(撮像技術やナラティブ理論)に留まらず日常的な観察、ショットが寄せられるときの身体的反応、カットの速度が引き起こす時間知覚の歪み、音響が作る感情の先取りを理論化して見せる。 学術的抽象と感覚的記述の接着は均質ではないが、むしろその不均衡が読者に思考の余地を与える。 理論に厳格を期する読者は、町山の議論における一般化の瞬間に慎重な検討を要するだろうが、実務的な観察力を鍛えるという目的に関しては彼の記述様式は極めて効果的だ。 本書における重要な分析軸としてまず挙げられるのは映像言語に対する精密な考察である。 町山はショットやシークエンスの機能、レンズの選択、空間の再構成、カメラ運動が物語の意味へ及ぼす効果を具体的なシーンの参照を通して解説している。 彼はこれらの映像要素を単なる技術的装飾として扱うのではなく視覚的ディテールが語る非言語的テクストとして読み解く訓練を読者に促している点に特徴がある。 次に物語と時間の問題に関して、町山は伝統的な因果連鎖と映画特有の時間操作、フラッシュバックや反復、モンタージュといった手法との相互作用を丁寧に論じている。 その際時間の操作を演出上の技巧としてではなく観客の倫理的・感情的理解に介入する戦術として読み替える視点が提示されており、この点は特に高く評価できる。 またジャンルと文化的コードに関する章では、ジャンルを物語様式としてではなく観客の期待や解釈のプロトコルを内包した装置として捉える姿勢が貫かれている。 町山はジャンル分析を通じて映画が社会的想像力をいかに形成し、共有される文化的枠組みを再生産するかを明らかにしており、その射程は映画批評を社会思想的文脈にまで拡張している。 さらに政治性とイデオロギーについての洞察も見逃せない。 町山は映画が提示する世界像や価値判断を見逃さず政治的な読み取りを安易な決め付けに還元しないバランス感覚を維持している。 しかし一方で時に断定的な価値判断が前景化し、批評家としての立場表明がそのまま説得力に転化する局面とそうならない局面とが混在している点も指摘しておくべきである。 本書の長所としてまず挙げられるのは、その実践的な洞察である。 理論の抽象的な羅列にとどまらず、鑑賞中に即座に応用できる視点が豊富に提示されており、映画を観るという行為そのものを精密に分解して見せる手際は見事である。 加えて説得力のある比喩と記述によって映像表現の感覚を言語化する能力に優れ、読者が自らの視覚経験を再構築する助けとなっている。 さらに古典から現代に至るまでの幅広い参照範囲を通じて比較対照によって概念を立ち上げる構成力にも独自の厚みがある。 その一方でいくつかの限界や留意点も存在する。 まず理論的一貫性の欠如が挙げられる。 学術的厳密性を重視する読者にとっては概念定義の曖昧さや論の跳躍的展開がやや不満足に映るかもしれない。 また価値判断の断定性に関しても町山自身の批評的立場や価値観が分析の前提として透けて見える場面がある。 これは批評家としての個性の発露でもあるが、学術的中立を求める読者には違和感を与える可能性がある。 さらに事例依存の傾向も見受けられる。 具体例の豊富さは本書の魅力である反面、それらを異なる文脈へ一般化する際の論拠が十分に補強されていない箇所もある。 すなわちこの映画ではこう機能しているが、他の条件下でも同様に働くのかという問いに常に明確な答えが用意されているわけではないのである。 本書は映画学の専門家というよりは教養的な実践者を主たる想定読者とする。 映画祭でのキュレーション、映画教育、批評執筆、あるいは映画制作の初学者が観察眼と論説力を獲得するための良書である。 町山智浩の本は映画を何となく好きだというレジームから一歩踏み出させる力を持つ。 観客に対して観察の技術を与え、映像表現がどのように意味を編み出すかを体感させる点で実践的価値は高い。 理論的一貫性や学術的精緻化を求める向きには改善余地があるが、その短所は本書の語り口と目的意識によって部分的に補償されている。 映画をより注意深く、より思考的に観たい者に強く勧められる一冊である。