病棄て―思想としての隔離

1件の記録
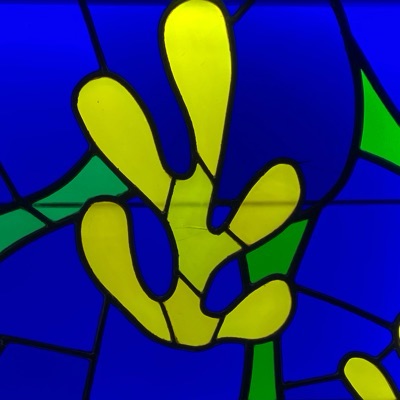 花木コヘレト@qohelet2025年11月26日読み終わった図書館本ハンセン病絶望を感じた本でした。 絶望というのは、この本が出たのが1985年で、今から40年前なのですが、収められている論文はもっと前に初出していて、だいたい50年くらい前の言説が、本書には収められています。絶望というのは、ハンセン病の論点は、この本が出ている時点で、もう出揃っていた、ということがわかることです。 本書の112ページに、 「「所得的援助によるだけでは解決のできぬ場合の非所得的援助」にたいすらニードを、患者運動はどのように自覚し、補償しようとしてきたか。経済的所得の保障や医療要求にらくらべ、それはたち遅れていたことは否めない。」 とありますが、この文章が書かれてから50年間、多分事態はほとんど進まないまま、時間が過ぎてきたのではないでしょうか? つまり、事態を省略して言えば、ハンセン病患者の地域参加は、不完全なまま、ハンセン病問題が終わりを告げようとしている、ということです。つまり、これは、光田健輔氏の、隔離政策が完遂したことを意味していると思います。簡単に言って、革命は起きなかったわけです。そして、大切なことは、反革命は患者が望んでいたことでもあったということだと思います。患者が外に出たがらなかったからです。ですから、光田健輔氏の生み出した制度は現在も生きていることになります。50年前から、問題点は出揃っていたのにも関わらずです。 光田健輔氏の制度を患者も受け入れてきたわけだと思います。つまり、彼の制度は有効に機能して来たと、私たちは反面認めざるを得ない所に立たされているのだと思います。 つまり、彼の制度は、既成事実として成立しています。既成事実として成立しているということは、これは法律的な意味においては、正しさに、正統性につながりかねません、というか繋がっているでしょう。 本書を読むことによって、私たち非ハンセン病患者は、あくまでも私たちの現実が、ハンセン病患者の呪いを受けていることであることを、深く自覚するべきだと思います。そういう視線に立ってみれば、国立ハンセン病資料館の存在意義など、あくまで史跡程度にしか過ぎません。あの建物は、私たちがハンセン病患者の自由を奪い続けて来た証左としてのみ、残存価値があるのだと思います。
花木コヘレト@qohelet2025年11月26日読み終わった図書館本ハンセン病絶望を感じた本でした。 絶望というのは、この本が出たのが1985年で、今から40年前なのですが、収められている論文はもっと前に初出していて、だいたい50年くらい前の言説が、本書には収められています。絶望というのは、ハンセン病の論点は、この本が出ている時点で、もう出揃っていた、ということがわかることです。 本書の112ページに、 「「所得的援助によるだけでは解決のできぬ場合の非所得的援助」にたいすらニードを、患者運動はどのように自覚し、補償しようとしてきたか。経済的所得の保障や医療要求にらくらべ、それはたち遅れていたことは否めない。」 とありますが、この文章が書かれてから50年間、多分事態はほとんど進まないまま、時間が過ぎてきたのではないでしょうか? つまり、事態を省略して言えば、ハンセン病患者の地域参加は、不完全なまま、ハンセン病問題が終わりを告げようとしている、ということです。つまり、これは、光田健輔氏の、隔離政策が完遂したことを意味していると思います。簡単に言って、革命は起きなかったわけです。そして、大切なことは、反革命は患者が望んでいたことでもあったということだと思います。患者が外に出たがらなかったからです。ですから、光田健輔氏の生み出した制度は現在も生きていることになります。50年前から、問題点は出揃っていたのにも関わらずです。 光田健輔氏の制度を患者も受け入れてきたわけだと思います。つまり、彼の制度は有効に機能して来たと、私たちは反面認めざるを得ない所に立たされているのだと思います。 つまり、彼の制度は、既成事実として成立しています。既成事実として成立しているということは、これは法律的な意味においては、正しさに、正統性につながりかねません、というか繋がっているでしょう。 本書を読むことによって、私たち非ハンセン病患者は、あくまでも私たちの現実が、ハンセン病患者の呪いを受けていることであることを、深く自覚するべきだと思います。そういう視線に立ってみれば、国立ハンセン病資料館の存在意義など、あくまで史跡程度にしか過ぎません。あの建物は、私たちがハンセン病患者の自由を奪い続けて来た証左としてのみ、残存価値があるのだと思います。


