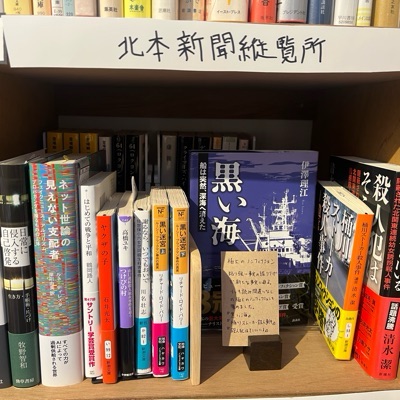おふみ
@ofumino
2025年5月1日

推し、燃ゆ
宇佐見りん
読み終わった
「推しとわたし」がテーマの、全て一人称視点の自伝。そしてとても現実的な内容。妄想も暴走も山も谷もない、ただ生きづらさを抱える中で推しに生かされていると勘違いしている女子高生の話。
実際生きていられているのは親がお金を稼ぎ食わせてくれて身の回りの世話をしてくれているからなのに、そのことにはいまいち気づいていない。いや気づいているのだろうが、元々そうだったのか、もしくは今に至るまでに確執があったのか、家族には感謝するどころか目を向けようともしない。
一見いびつに見えるが、誰しもがわかる感覚だと思う。物資的に生かされているのと、精神的に生かされているのとでは意味も重みも違う。往々にして精神的支柱の方が重い、大体の人は。だから推しを見て「神!」と言うのだろう。推しを神に据えた信仰なのだ。
この親は毒親だとかいうレビューも見かけたが、そういう話ではないと思うし、とくに毒親とは感じなかった。うん、そういう話ではない。そこは別に大事じゃない。
それにしても文体…言葉の転がり方が見事だと思った。喋り言葉に近いので口の中でころころ転がってサクサク読める。
さらに、徹底的して「主人公の視点」を外れないため主人公の感じ方をそのまま体験できるのが本作の最も面白いところだと感じた。
例えば、主人公はたびたび部屋を散らかしてしまうが、その一つ一つの描写の輪郭はぼやけていて曖昧だ。
こういうとき一般的には「どんな理由あって何をどのように散らかしてしまったか」を描写するのが普通の書き方だと思うが、本作にそのような説明はない。主人公は「気づいたらものを散らかしてしまう」し、「なぜ散らかるのか」「普通にできないのか」本心でわからない、つまり「散らかしたこと」を適切に認識できていない。主人公が認識できていないことなので、具体に書かれていない。
そういう徹底した主人公視点が所々に溢れて、むず痒さのような曖昧さを生んでいるのが好ましかった。そうそう人の主観ってこんな感じだよねっていう。こうして客観的に見ると歪んでいるように思うけど、ほんと実際こんなもんだと思うんだ。
バイトのシーンは特に、主人公から見た世界、ぐるぐる目がまわるような見え方がよくわかる。身も蓋もない言い方をすると「ADHDの脳内ってこうだよね、わかる〜!」という共感でもある。笑 ADHDじゃない人にとっては理解不能な書かれ方をしているかも?
「推し、燃ゆ」と題しながら、作中ずっと、燃えたことに目を向けていないのもこの徹底された主人公視点のためだと思った。だからこそ最後の力が抜けたような吐露がちょっと辛かった。
彼女は生きづらすぎて、理解者もいなくて、人とわかり合うことはもうとっくに諦めてしまったのかもしれない。だからわかり「合う」必要のない神を信仰して心の支えにしていた。
でも推しはあくまでも人間。神と崇めるには危うすぎた。彼女の信仰対象が神であれば、まだ彼女に背骨はあったのかもしれないな。もしくは仕事とか、この世で実益とされるものならば。
それでも人を求めてしまうのは、人の性なのかもしれないな。