
明庭社
@meiteisha
2025年7月15日
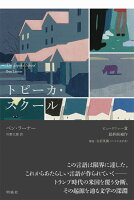
トピーカ・スクール
ベン・ラーナー,
川野太郎
出版社より
2025年7月28日、アメリカの詩人・小説家ベン・ラーナーによる長篇小説『トピーカ・スクール』(川野太郎訳)を刊行いたします。
本書は、ひとり出版社である明庭社の創業第一作となります。
著者にとって三作目の長篇小説にあたる本作は、2019年に原書『The Topeka School』として刊行され、翌2020年、ピューリツァー賞の最終候補に選ばれました。
日本ではこれまでに『10:04』(木原善彦訳、白水社)が刊行されています。
『トピーカ・スクール』はベン・ラーナー自身をモデルとした主人公アダム・ゴードンと、ともに臨床心理士である彼の両親、そしてクラスメートであり共同体から阻害された少年ダレンの視点から交互に語られる構成になっています。
言葉の限界と可能性、有害な男性性、論破と対話、詩とレトリック、共同体と世代を超えた反復——それらの主題が、精緻に、そして美しく交差しながら、ひとつの物語として編まれていきます。
海外では原書『The Topeka School』のいくつかの書評が公開されています。この作品に触れる小さな入口として、ご紹介します。
■海外の書評(抜粋)
小説が「人生を変える」と宣言するのには、私は現代社会に囚われすぎているかもしれない。けれど、この小説が近年の米国が生み出した最高傑作のひとつであることには自信を持っている。我々の言語活動と経済活動いずれにおいても、そこにある「余剰」がその根底では無意味でしかない時代において、「深遠な芸術的体験」(1作目に登場する表現)に何らかの意味があるといえるだろうか? この小説はそれに「イエス」と答えている。 Garth Risk Hallberg「Ben Lerner’s ‘The Topeka School’ Revisits the Debates of the ’90s」NewYorkTimes, 2019年10月
https://www.nytimes.com/2019/10/03/books/review/topeka-school-ben-lerner.html
『10:04』が、ラーナー自身の人生とそのフィクションへの反映という二つの側面を行き来しながら読むことを求められるという意味で、「2枚折り」の小説だとするならば、『トピーカ・スクール』は「3枚折り」の作品だ。これは国家についての小説だ。そして、「あそこをつかめ(※トランプが女性に対して言ったとされる言葉)」の時代、そしてスティーブ・バノンと有害な男性性の時代についての小説だ。
Alex Preston「The Topeka School by Ben Lerner review – a work of extraordinary intelligence」Guardian, 2019年7月
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/05/the-topeka-school-ben-lerner-review
これまでの小説でラーナーは、小説の中にアイロニカルな不確定性を生じさせることで、確らしさとポストモダニズム的態度をマッチさせようとしてきた。しかし、本作はより真摯で、しかも感傷的な作品となっている。(...)『トピーカ・スクール』は、共同体の経験 (ある特定の文化が共有する比喩やイデオロギー、クリシェ) と個人的な感情(詩的表現の特殊性とその手触り) の両端を、そのいずれを変質させることなく、巧みに往復する、彼の最も成功した試みだ。
Jon Day「The Topeka School by Ben Lerner review – in a class of its own」Guardian, 2019年11月
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/08/the-topeka-school-by-ben-lerner-review
『トピーカ・スクール』は、有害な男性的文化の中で「良い息子」を育てることの困難についての興味深い物語だ。それは、公共における対話が崩壊しごろつきと新興右派が政権を担い、白人男性たちがアイデンティティの危機にある「現在」にとっての、鮮やかな前史でもある。
Granta Books
https://www.waterstones.com/book/the-topeka-school/ben-lerner/9781783785377
この小説は、ある意味では先史時代についての書物です。家族パターンが世代を超えて繰り返されたり壊されたりすること、1990年代の「歴史の終焉」という勝利主義的な言説が、トランプ主義の一つの表れである特定の白人男性の間で加速するアイデンティティの危機を覆い隠していたことなどについてです。私は、世代間の問題を捉えるために、本のレンズと文法を拡張する必要がありました。私は声を投じなければなりませんでした。
「Ben Lerner Talks to Ocean Vuong About Love, Whiteness, and Toxic Masculinity」
Literary Hub, 2019年10月
https://lithub.com/ben-lerner-talks-to-ocean-vuong-about-love-whiteness-and-toxic-masculinity/
本の帯は本作を、“有害な男性性”についての小説だと表現するだろう。けれどそれはあまりに単純で簡略化され、複雑な物語を説明するにはひどくバズワード的であるようにみえる。男らしさ、男性的、男性性、構造化された性別を巡るこうした言葉が持つ病性は、物語に不可欠な要素である。しかしトピーカ・スクールは、深い意味において、言語に関する小説でもある。言語がなり得る、脅威と欺瞞についての小説だ。そして、コミュニケーションの不安定さについての小説だ。ラーナーは言葉が本来持つ暴力と危うさ、美しい言葉の中に潜む残忍さを描いているが、その一方で、いかにその同じ言葉が愛を表現でき、不安を和らげ、必要な慰めを与えることもできるかということについて語っている。(ラーナーはこれを思いやりを持って描いている。この小説は政治的であるけれど、シニカルではない)小説は、男性がどのように言語を使うか、そして男性が逆に言語によって使われるか、ということについて語る。「僕は父親だ」アダムは終章で言う。「僕は男性が持つ暴力性の古代からの媒体だ。その暴力性を、物質性を言語に置き換えることによって克服するのが文学だと思う
Greg Cwik「The Pure Present: Ben Lerner’s The Topeka School」Blooklyn Rail, 2019年12月
https://brooklynrail.org/2019/12/books/The-Pure-Present-Ben-Lerners-The-Topeka-School/
(トピーカにおける中流階級の)特権的な玄関の向こう側には、貧困、人種差別、そして過激な同性愛嫌悪が渦巻いていた。 ベン・ラーナーの『トピーカ・スクール』は、これらを見事に描いているが、それはカンザス州の州都トピーカだけを題材にしているわけではない。この小説はトランプ時代のアメリカを描いており、主流メディアでほとんど取り上げられないトピーカを、国内各地で見られる文化的・政治的分断の震源地のような存在として描いている
Amy Brady 「The Topeka of The Topeka School -How the Kansas city Ben Lerner and I grew up in transformed into ground zero for Trump’s America.」Slate










