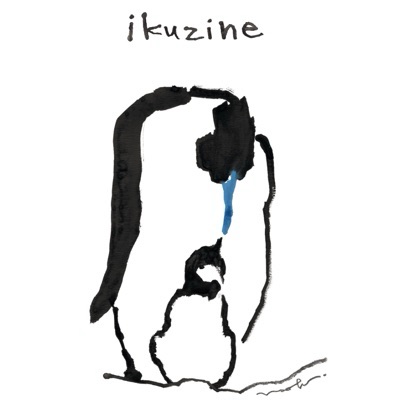
Yamada Keisuke
@afro108
2025年9月8日

読み終わった
『本の惑星』というポッドキャストで著者がゲスト出演していたエピソードを聞いて、著作がオモシロそうだったので読んだ。番組内ではビルボードジャパンが「本のヒットチャート」を構想している話が出ていたが、本著では音楽チャートについて詳細に解説されている。これまで考えたこともない視点の連続で、普段あまりチャートアクションを見て音楽を聞くタイプではないもの、思わずチャートを眺めたくなる一冊だった。
アラフォーの私にとっては、音楽のチャートといえばオリコンだが、それはCDが売れに売れた時代の話だ。いまやCDはアイドルカルチャーを中心とした「複数枚購入機会生成装置」と化してしおり、その売上枚数は世間的流行の物差しにはなりにくい。その代わりに存在感を増しているのが、ストリーミングや動画、カラオケ、CDなど複数の指標を総合するビルボードチャートである。本著は、そのビルボードチャートの立ち上げから携わってきた著者が、設立までの過程、運用の状況から実際のデータ分析まで「チャートとは何か?」「チャートから何がわかるか?」を丁寧に解き明かしてくれている。
今や当たり前に存在するビルボードチャートだが、その設立までの紆余曲折の過程が詳細に書かれていた。本家USビルボードのロジックをそのまま持ってきているだけかと思いきや、USサイドはあくまでアドバイザー的立場でしかなく、日本サイドでロジック構築、チューニングしていることに驚いた。ガラパゴス的とも言われる日本の音楽産業は、配信解禁の遅れなどステイクホルダーの思惑に左右されており、今となっては、ストリーミングがほぼ全面開放ではあるものの、それが数年遅れたことによるインパクトの大きさについて、チャートを作る立場から憂いていた。既得権益がその構造を維持したがる態度は、音楽業界に限らず、日本全体の風習とも言えるわけだが、それを一つずつ打破して今のビルボードチャートがある。合間合間にある著者の過去のエピソードを読む度に、同じサラリーマンとして胸が打たれるものがあった。
後半は実際のアーティストのデータ分析に踏み込んでいる。アーティストファンダム、楽曲ファンダムという大きく二つのタイプで分けて、各アーティストの過去、現在をあぶり出していく様に、音楽に対しても想像以上にデータ分析の波が押し寄せている現実を改めて突きつけられた。最近、ツイッターでYOASOBIの地方巡業について話題になっていたが、なぜ彼らがそういったアプローチをしているのか、本著に答えが載っている。また、ストリーミングの台頭によってCD販売で見えなかった過去曲の聞かれ方も分析対象となっている点も興味深かった。手元の資産を有効活用して利益を最大化していくにはどうすればいいかデータが教えてくれる、というのはデータ分析の基本であり醍醐味だが、それをふんだんに味わうことができる。特に著者はビルボードの最大の特徴である複数指標を重視しており、単純な実数だけではない考察も含めて興味深かった。
「音楽はアートだ」といってもやはりトップアーティストになれば、アーティストは商材であり、その商材で会社、ひいては多くの人を支えなければならない。素晴らしい音楽を作ることがアーティストの役目であれば、それを最大化するには、データを軸とした細かいマーケティングが必要であることがよく理解できた。
著者が、音楽ジャーナリストの柴 那典と、BMSG社長のSKY-HIとそれぞれ対談した内容も載っており、それらもオモシロかった。前者では音楽業界全体の構造、後者ではアイドルカルチャーとチャートについて深堀りされている。特にSKY-HIは自身がアイドル産業の当事者だった時代を経て、今度は自分がオーナーになってアイドルを売り出す側になった唯一無二な存在である。2020年代になっても、アイドルカルチャーにおいては、特典商法を通じてCDを尋常じゃない数(数10万〜100万!)を売っている事実に驚いたし、それに対してレコード会社と自分たちの双方がウィンウィンになるような打開策を検討してるあたりにビジネスマンとしての手腕を垣間見た。
ビルボードチャートだけではなく、Spotifyのバイラルヒットチャートなど、いつの時代もチャートの存在が、世のトレンドを作っていることは否定できない。そして、今の時代は以前よりもメジャー、インディペンデントの垣根なく、素晴らしいものを作れば、忖度抜きでダイレクトにチャートインされ、広がっていく素晴らしい時代である。チャートにあるからといって、その音楽を好んで聞くわけではないが、それでも、相対化された「いま」を映し出す指標としての存在意義は大きい。音楽とデータが好きな人には間違いなくおすすめできる一冊だった。


