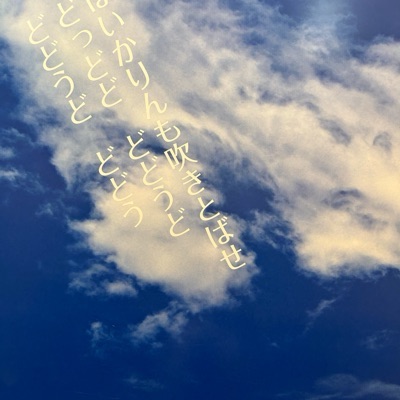
.
@azzurro
2025年9月10日

シリウス
オラフ・ステープルドン,
中村能三
読み終わった
まず最初に、読んでよかった。
ここ最近で読んだ小説の中なら、断トツで、一番良かった。
80年前の作品なのに、読書メーターの登録件数を見る限り日本ではあまり知られてない作品っぽい?
なんで知名度低いのかわからん。
絶対日本でも売れる。SFにありがちな小難しい科学描写も少ない。
良い言葉じゃないけど『万人受け』するタイプの作品だと思う。
積読してる人、気になってる人、是非読んで。
解説によれば、作者の活躍した時期は第一次世界大戦から第二次世界大戦を股にかける時代だったらしい。
8章ケンブリッジでのシリウスで、利己的な人類への軽蔑の気持ちを連ねているところを読みながら、シリウスがディオゲネスと話をしたらどう感じるんだろうと考えたあとに、そういえばキュニコスの和訳は犬儒学だったなと気づいて1人で勝手に面白くなった。
【以下ネタバレ含む】
・全体通してみて、ハイデガーの存在と時間を読む必要がありそうだと思った。
読んだことないので憶測だけど、作中で何度もシリウスが行き詰まったポイントに照らし合わせられるのは、存在と時間なんじゃないかと。読んだことないけど。
・エリザベスの死後、自分の育った家をプラクシーと2人で片付け、思い出の物を燃やし、何もなくなった家で2人で過ごすシーンは胸にくるものがある。
親しい人の死や長い年月を過ごした場所から離れることを受け入れるのには時間がかかるが、現実の時の進みは待ってはくれない。そういうときは大抵、心の折り合いがつかないまま時間に押し流されるように、大切だったものとの永遠の別れを強制される。直接的な文章があるわけじゃないけど、それを痛感するシーンだった。
それを感じられる翻訳も素晴らしい。
・シリウスを悪魔と呼び悪魔退治に勤しむ人々が、ピューの羊を殺してシリウスとプラクシーの家の前に置いていくという行為はキリスト教的ブラックジョークか?
羊はキリスト自身やキリストに従う人々の象徴なのだから、それを殺して悪魔に捧げるとは、これじゃあどっちが悪魔なんだか。
・「プラクシー=シリウス、生きていてむだじゃなかった」
どういう意味で言ったんだ。
作品の大部分は、シリウス目線の伝記をロバートが代筆した形で書かれていたからシリウスの視線をベースに進んでいたのに、最期の言葉をどう受け取るかは読者に委ねられてる。
ずるい。






