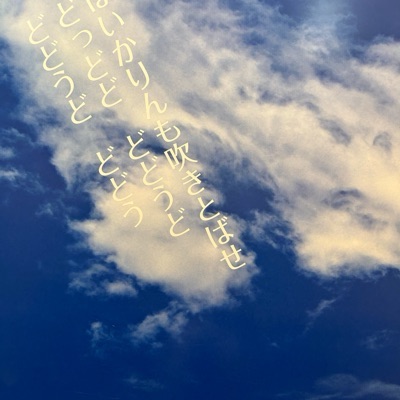
.
@azzurro
感想言うのが苦手
- 2025年10月15日
- 2025年9月30日
 寝ても覚めてもアザラシ救助隊岡崎雅子読み終わったアザラシかわいい。 イラストもめっちゃかわいい。 動物好きな人にはとてもおすすめ。 少し前にオランダのアザラシ保護施設の配信が流行したことと、つい先日城崎マリンワールドでアザラシを見たこともあり、書店で見つけて気になったので購入。 野生動物の保護と飼育、リリース、人間との共生においての問題点、環境問題。 いろんな海洋生物系のエッセイや一般向けの科学書で主張されていることと大きく差はないけど、だからこそ動物と向き合うプロたちの前に現在立ちはだかる壁は同じなのだなと思う。 自分が今、この時に環境のためにできることを少しでも良いからちゃんと行動に移していきたい。 アザラシにとって生きやすい世界とはすなわち、人間にとっても生きやすい世界であるはずだからという、著者の主張が印象的。
寝ても覚めてもアザラシ救助隊岡崎雅子読み終わったアザラシかわいい。 イラストもめっちゃかわいい。 動物好きな人にはとてもおすすめ。 少し前にオランダのアザラシ保護施設の配信が流行したことと、つい先日城崎マリンワールドでアザラシを見たこともあり、書店で見つけて気になったので購入。 野生動物の保護と飼育、リリース、人間との共生においての問題点、環境問題。 いろんな海洋生物系のエッセイや一般向けの科学書で主張されていることと大きく差はないけど、だからこそ動物と向き合うプロたちの前に現在立ちはだかる壁は同じなのだなと思う。 自分が今、この時に環境のためにできることを少しでも良いからちゃんと行動に移していきたい。 アザラシにとって生きやすい世界とはすなわち、人間にとっても生きやすい世界であるはずだからという、著者の主張が印象的。 - 2025年9月23日
 読み終わった日本書紀・古事記から日本史へのつながりをちゃんと見ていないと理解が難しい本だった。 温羅伝説の鬼が土地神のように祀られている町で育ち、鬼の装いで楽器を演奏する伝統芸能を子供の頃から10年くらいやっていたので、鬼を神として祀ることの感覚はよくわかる。 本当にただの神様なんですよね。 私も鬼の格好をして演奏したり、町を歩きながら、遭遇する町の子供達の頭を撫でたり握手したりしていた。そうすれば幸せになれるという話があるから、鬼の格好をする人はみんなそうする。特に子供に優しくするし、大人たちは鬼に自分の子を撫でてもらうために抱き上げて近づける。 富士山の神についてのくだりなんかも面白かった。
読み終わった日本書紀・古事記から日本史へのつながりをちゃんと見ていないと理解が難しい本だった。 温羅伝説の鬼が土地神のように祀られている町で育ち、鬼の装いで楽器を演奏する伝統芸能を子供の頃から10年くらいやっていたので、鬼を神として祀ることの感覚はよくわかる。 本当にただの神様なんですよね。 私も鬼の格好をして演奏したり、町を歩きながら、遭遇する町の子供達の頭を撫でたり握手したりしていた。そうすれば幸せになれるという話があるから、鬼の格好をする人はみんなそうする。特に子供に優しくするし、大人たちは鬼に自分の子を撫でてもらうために抱き上げて近づける。 富士山の神についてのくだりなんかも面白かった。 - 2025年9月21日
 読み終わった恐らく軽〜中度相貌失認で聴覚優位の自覚があり、ずっと気になっていた本。 長らく探し求めた末に、ネットで中古を見つけてようやく読み切った。 2章ガウディについての話は長いし難しい。対して3章キャロルの話は身に覚えがあるものばかりで、3章に差し掛かってからは1時間くらいで読み終えた。 人の顔の区別がつかない、景色では道が覚えられない、電車の乗り換えは数字と言葉で覚える、現在と未来のつながりがわからない、写真では区別できる顔が実物になるとわからない。 それな!ってデカい声で言いたくなる。こういうのが視覚不全だそうで。 あと車の車種なんかも私は目で見ても区別がつかず、いつもナンバーで覚える。家族や知人の車でさえ造形では判断できない。 色付きレンズや偏光フィルターで相貌失認の症状をケアできる可能性があるって本当なんですかね? それが本当なら私も色付きレンズ作りたい。でもそれって何色の何%くらいのレンズなのか、どこでどうやって検査したらいいのか、そういうことは書かれていなかった。 仕事柄、有名人に会うことも少なくなくて、著名人を顔で判断できないのは失礼だと思いつつ、かといってどんなに頑張っても本当に顔じゃ何もわからないせいで病んだこともある身からすると、少しでも症状が改善されるなら今すぐにでも作りたいくらいなんですが。
読み終わった恐らく軽〜中度相貌失認で聴覚優位の自覚があり、ずっと気になっていた本。 長らく探し求めた末に、ネットで中古を見つけてようやく読み切った。 2章ガウディについての話は長いし難しい。対して3章キャロルの話は身に覚えがあるものばかりで、3章に差し掛かってからは1時間くらいで読み終えた。 人の顔の区別がつかない、景色では道が覚えられない、電車の乗り換えは数字と言葉で覚える、現在と未来のつながりがわからない、写真では区別できる顔が実物になるとわからない。 それな!ってデカい声で言いたくなる。こういうのが視覚不全だそうで。 あと車の車種なんかも私は目で見ても区別がつかず、いつもナンバーで覚える。家族や知人の車でさえ造形では判断できない。 色付きレンズや偏光フィルターで相貌失認の症状をケアできる可能性があるって本当なんですかね? それが本当なら私も色付きレンズ作りたい。でもそれって何色の何%くらいのレンズなのか、どこでどうやって検査したらいいのか、そういうことは書かれていなかった。 仕事柄、有名人に会うことも少なくなくて、著名人を顔で判断できないのは失礼だと思いつつ、かといってどんなに頑張っても本当に顔じゃ何もわからないせいで病んだこともある身からすると、少しでも症状が改善されるなら今すぐにでも作りたいくらいなんですが。 - 2025年9月18日
- 2025年9月18日
- 2025年9月18日
- 2025年9月17日
 百年の孤独ガブリエル・ガルシア=マルケス,鼓直読み終わったこれはすごい。最後の数ページは鳥肌もの。 かなり難しい作品と噂を聞いていて、身構えて読み始めたけど、別段複雑怪奇なわけじゃなかった。エンタメ小説。 冒頭の150ページくらいはちょっと退屈してたけど、200ページに差し掛かるあたりから結構楽しく読んでいた。 ファンタジー要素が度々あるけど、本質はかなり写実的な人間ドラマ。 ところどころ、先の展開をネタバレみたいに突然吐き出してくるんだけど、なにがどうしてそこに至るのかは読み続けないと全然わからなくて、該当部分の時間軸まで読み進めた時に漸く「あの時のアレ、そういうことか〜」と思い出す感じが楽しい。伏線を敷いてるとかじゃなくて、問題文も計算式もすっ飛ばして、突然答えだけぶん投げてくるようなかんじがおもしろい。P350の1行目とか「やっときたー!」ってなる。 【以下ネタバレ含む】 ・物静かで知性的だったアウレリャノが為政者からの抑圧を受け、自由を守るために武器を取り戦争に行き、かつて自分たちが敵に見出した狂気を抱えて帰ってきて、停戦後ブエンディアの生家に戻ってからは本来の性質を取り戻しながらも戦争中にできた精神的な傷を癒せずにいる姿。 ・どこまでもいつまでも母親であるウルスラ。ステレオタイプの母親像をセメントで塗りたくって固めたかのような人。完全に群れのボス。 ・良くも悪くも執念深く、人も気持ちもなにもかも忘れることができず、他人も自分自身も拒絶して生きるアラマンタ。 ・結婚して他人との生活が始まるというのに、実家の習わしとルールを絶対に捨てたくないという図々しさでブエンディアを掻き乱すフェルナンダ。 ・幸薄すぎてかわいそかわいいピエトロ・クレスピ。それはそれとして何も自殺するほどか?とも思う。 ・クレスピの肉親も、実話のフィルムを紛い物扱いされた挙句、劇場を荒らされてかわいそう。一族揃って可哀想キャラなのはちょっと面白い。 みたいな。 登場人物が多すぎて書いてるとキリがないけど、現代日本でもよく聞く話。つまり至って普通の、よくある平凡な家族の、普通の日常の1世紀分がかいつまんで書かれた物語。 ただ、そもそもの発端であるメルキアデスとホセ・アルカディオ・ブエンディア、あと小町娘のレメディオスあたりは様子がおかしい。 ホセ・アルカディオ・ブエンディアの死ぬシーンがあまりにも幻想的で美しい。(p221) ホセ・アルカディオの死ぬシーンもかなり印象的だった。勘当した身でありながらも、唯一息子の死による血の道筋に気づいて真っ先に駆け寄るウルスラ。やっぱりあまりにもお母さん。 電話の発明を“現実の境界が果たしてどこにあるのか、誰にも定かではなくなった”と表現。比喩としてカッコ良すぎ。 p485ヘリネルド・マルケス大佐の葬列を見送るウルスラがヘリネルドへ別れの言葉を贈るシーンはかなり印象深い。 読んでいると「このキャラクターの名前久々に出てきたな。」とか「これについてのエピソードは随分前の時間軸で聞いて以来だな。」みたいなことが多々あったけど、いずれの出来事も言われてみれば思い出せるくらいには覚えてるという不思議な感覚を繰り返し体験する。後でまたストーリーに噛んでくる人物や事象は印象に残るような描かれ方をしている証拠なんだと思うと、作者の手腕に鳥肌が立つ。 「わたしよりよく心得ていると思うが、戦争裁判なんてみんな猿芝居さ。」 「軍人たちを憎みすぎたために、彼らをあまり激しく攻撃したために、そして彼らのことを考えすぎたために、連中とまったく同じ人間になってしまったことなんだ。これほどの自己犠牲に値する理想なんて、この世にないと思うんだがね。」 架空の人間の見せかけの不幸に流す涙などあるものか、自分たちの苦労だけでたくさんだ。
百年の孤独ガブリエル・ガルシア=マルケス,鼓直読み終わったこれはすごい。最後の数ページは鳥肌もの。 かなり難しい作品と噂を聞いていて、身構えて読み始めたけど、別段複雑怪奇なわけじゃなかった。エンタメ小説。 冒頭の150ページくらいはちょっと退屈してたけど、200ページに差し掛かるあたりから結構楽しく読んでいた。 ファンタジー要素が度々あるけど、本質はかなり写実的な人間ドラマ。 ところどころ、先の展開をネタバレみたいに突然吐き出してくるんだけど、なにがどうしてそこに至るのかは読み続けないと全然わからなくて、該当部分の時間軸まで読み進めた時に漸く「あの時のアレ、そういうことか〜」と思い出す感じが楽しい。伏線を敷いてるとかじゃなくて、問題文も計算式もすっ飛ばして、突然答えだけぶん投げてくるようなかんじがおもしろい。P350の1行目とか「やっときたー!」ってなる。 【以下ネタバレ含む】 ・物静かで知性的だったアウレリャノが為政者からの抑圧を受け、自由を守るために武器を取り戦争に行き、かつて自分たちが敵に見出した狂気を抱えて帰ってきて、停戦後ブエンディアの生家に戻ってからは本来の性質を取り戻しながらも戦争中にできた精神的な傷を癒せずにいる姿。 ・どこまでもいつまでも母親であるウルスラ。ステレオタイプの母親像をセメントで塗りたくって固めたかのような人。完全に群れのボス。 ・良くも悪くも執念深く、人も気持ちもなにもかも忘れることができず、他人も自分自身も拒絶して生きるアラマンタ。 ・結婚して他人との生活が始まるというのに、実家の習わしとルールを絶対に捨てたくないという図々しさでブエンディアを掻き乱すフェルナンダ。 ・幸薄すぎてかわいそかわいいピエトロ・クレスピ。それはそれとして何も自殺するほどか?とも思う。 ・クレスピの肉親も、実話のフィルムを紛い物扱いされた挙句、劇場を荒らされてかわいそう。一族揃って可哀想キャラなのはちょっと面白い。 みたいな。 登場人物が多すぎて書いてるとキリがないけど、現代日本でもよく聞く話。つまり至って普通の、よくある平凡な家族の、普通の日常の1世紀分がかいつまんで書かれた物語。 ただ、そもそもの発端であるメルキアデスとホセ・アルカディオ・ブエンディア、あと小町娘のレメディオスあたりは様子がおかしい。 ホセ・アルカディオ・ブエンディアの死ぬシーンがあまりにも幻想的で美しい。(p221) ホセ・アルカディオの死ぬシーンもかなり印象的だった。勘当した身でありながらも、唯一息子の死による血の道筋に気づいて真っ先に駆け寄るウルスラ。やっぱりあまりにもお母さん。 電話の発明を“現実の境界が果たしてどこにあるのか、誰にも定かではなくなった”と表現。比喩としてカッコ良すぎ。 p485ヘリネルド・マルケス大佐の葬列を見送るウルスラがヘリネルドへ別れの言葉を贈るシーンはかなり印象深い。 読んでいると「このキャラクターの名前久々に出てきたな。」とか「これについてのエピソードは随分前の時間軸で聞いて以来だな。」みたいなことが多々あったけど、いずれの出来事も言われてみれば思い出せるくらいには覚えてるという不思議な感覚を繰り返し体験する。後でまたストーリーに噛んでくる人物や事象は印象に残るような描かれ方をしている証拠なんだと思うと、作者の手腕に鳥肌が立つ。 「わたしよりよく心得ていると思うが、戦争裁判なんてみんな猿芝居さ。」 「軍人たちを憎みすぎたために、彼らをあまり激しく攻撃したために、そして彼らのことを考えすぎたために、連中とまったく同じ人間になってしまったことなんだ。これほどの自己犠牲に値する理想なんて、この世にないと思うんだがね。」 架空の人間の見せかけの不幸に流す涙などあるものか、自分たちの苦労だけでたくさんだ。 - 2025年9月14日
 プロダイバーのウニ駆除クエスト 環境保全に取り組んでわかった海の面白い話中村拓朗(スイチャンネル)読み終わったこれは是非多くの人に読んで欲しい。 以前YTでウニ駆除の動画を拝見し、投稿者コメントで著書を出版されているのを知って購入。 表紙にエッセイと表記があるが内容は、プロダイバーである著者が長崎の海で生じる磯焼け問題を解決するために奔走した5年間の記録。 滅茶苦茶読み応えがあるし、勉強になった。海水温度は0.5度変わるだけでまるで環境が変わってしまう。それがキッカケとなり、ドミノ倒しのようにあらゆる問題が発生し、瞬く間に特定の種が減少する。 日本各地の海で同じような磯焼けが起きているが、実際は海域の生態系ごとに原因は異なり、当然対策も変わってくるため、上手くいっている地域のやり方をただ真似したところで意味はない。 ウニ駆除の動画で有名な著者だが、長崎の大村湾ではただウニを駆除しても磯焼けは解決しないことを突き止め、紆余曲折の末に食害で姿を消してしまった大型海藻を復活させることに尽力する。ただし、同じ長崎でも他の海域ではウニ駆除だけで回復が見込める場所もあるため、ウニの駆除活動と海藻再生活動を両方続けているのだと。 驚きなのは何よりもこの活動をほぼ1人でやっているということ。色んな人からアドバイスや知恵をもらったり、手を借りているようではあるけど実質1人での活動なようで、その忍耐力と海への愛情の深さが驚異的。
プロダイバーのウニ駆除クエスト 環境保全に取り組んでわかった海の面白い話中村拓朗(スイチャンネル)読み終わったこれは是非多くの人に読んで欲しい。 以前YTでウニ駆除の動画を拝見し、投稿者コメントで著書を出版されているのを知って購入。 表紙にエッセイと表記があるが内容は、プロダイバーである著者が長崎の海で生じる磯焼け問題を解決するために奔走した5年間の記録。 滅茶苦茶読み応えがあるし、勉強になった。海水温度は0.5度変わるだけでまるで環境が変わってしまう。それがキッカケとなり、ドミノ倒しのようにあらゆる問題が発生し、瞬く間に特定の種が減少する。 日本各地の海で同じような磯焼けが起きているが、実際は海域の生態系ごとに原因は異なり、当然対策も変わってくるため、上手くいっている地域のやり方をただ真似したところで意味はない。 ウニ駆除の動画で有名な著者だが、長崎の大村湾ではただウニを駆除しても磯焼けは解決しないことを突き止め、紆余曲折の末に食害で姿を消してしまった大型海藻を復活させることに尽力する。ただし、同じ長崎でも他の海域ではウニ駆除だけで回復が見込める場所もあるため、ウニの駆除活動と海藻再生活動を両方続けているのだと。 驚きなのは何よりもこの活動をほぼ1人でやっているということ。色んな人からアドバイスや知恵をもらったり、手を借りているようではあるけど実質1人での活動なようで、その忍耐力と海への愛情の深さが驚異的。 - 2025年9月12日
 音楽が人智を超える瞬間篠崎史紀読み終わった書店でたまたま目に入ったタイトルに惹かれて購入したもの。 元N響のコンマス、篠崎さんのエッセイ。 知り合いに舞台作品を作る人がいるが、その知人とよく似てる。芸術だの作品だの音楽だのを作る人間はこれくらい自由でいい。お絵描きをしようって言われて、画用紙を破いたり、紙飛行機にしたりするくらいで丁度いい。 私は仕事以外で音楽を聞かないけど、西洋人にとってのクラシック音楽とは、歴史の一部であり、様々な時代で喜びも死も全て見てきて、今もそれを抱えている芸術であることを思い出させてもらった。 冷戦時代、ソビエト崩壊時、世界大戦時、「人智を超えた音楽」に縋って生きた人も少なくなかったのだろう。
音楽が人智を超える瞬間篠崎史紀読み終わった書店でたまたま目に入ったタイトルに惹かれて購入したもの。 元N響のコンマス、篠崎さんのエッセイ。 知り合いに舞台作品を作る人がいるが、その知人とよく似てる。芸術だの作品だの音楽だのを作る人間はこれくらい自由でいい。お絵描きをしようって言われて、画用紙を破いたり、紙飛行機にしたりするくらいで丁度いい。 私は仕事以外で音楽を聞かないけど、西洋人にとってのクラシック音楽とは、歴史の一部であり、様々な時代で喜びも死も全て見てきて、今もそれを抱えている芸術であることを思い出させてもらった。 冷戦時代、ソビエト崩壊時、世界大戦時、「人智を超えた音楽」に縋って生きた人も少なくなかったのだろう。 - 2025年9月10日
 シリウスオラフ・ステープルドン,中村能三読み終わったまず最初に、読んでよかった。 ここ最近で読んだ小説の中なら、断トツで、一番良かった。 80年前の作品なのに、読書メーターの登録件数を見る限り日本ではあまり知られてない作品っぽい? なんで知名度低いのかわからん。 絶対日本でも売れる。SFにありがちな小難しい科学描写も少ない。 良い言葉じゃないけど『万人受け』するタイプの作品だと思う。 積読してる人、気になってる人、是非読んで。 解説によれば、作者の活躍した時期は第一次世界大戦から第二次世界大戦を股にかける時代だったらしい。 8章ケンブリッジでのシリウスで、利己的な人類への軽蔑の気持ちを連ねているところを読みながら、シリウスがディオゲネスと話をしたらどう感じるんだろうと考えたあとに、そういえばキュニコスの和訳は犬儒学だったなと気づいて1人で勝手に面白くなった。 【以下ネタバレ含む】 ・全体通してみて、ハイデガーの存在と時間を読む必要がありそうだと思った。 読んだことないので憶測だけど、作中で何度もシリウスが行き詰まったポイントに照らし合わせられるのは、存在と時間なんじゃないかと。読んだことないけど。 ・エリザベスの死後、自分の育った家をプラクシーと2人で片付け、思い出の物を燃やし、何もなくなった家で2人で過ごすシーンは胸にくるものがある。 親しい人の死や長い年月を過ごした場所から離れることを受け入れるのには時間がかかるが、現実の時の進みは待ってはくれない。そういうときは大抵、心の折り合いがつかないまま時間に押し流されるように、大切だったものとの永遠の別れを強制される。直接的な文章があるわけじゃないけど、それを痛感するシーンだった。 それを感じられる翻訳も素晴らしい。 ・シリウスを悪魔と呼び悪魔退治に勤しむ人々が、ピューの羊を殺してシリウスとプラクシーの家の前に置いていくという行為はキリスト教的ブラックジョークか? 羊はキリスト自身やキリストに従う人々の象徴なのだから、それを殺して悪魔に捧げるとは、これじゃあどっちが悪魔なんだか。 ・「プラクシー=シリウス、生きていてむだじゃなかった」 どういう意味で言ったんだ。 作品の大部分は、シリウス目線の伝記をロバートが代筆した形で書かれていたからシリウスの視線をベースに進んでいたのに、最期の言葉をどう受け取るかは読者に委ねられてる。 ずるい。
シリウスオラフ・ステープルドン,中村能三読み終わったまず最初に、読んでよかった。 ここ最近で読んだ小説の中なら、断トツで、一番良かった。 80年前の作品なのに、読書メーターの登録件数を見る限り日本ではあまり知られてない作品っぽい? なんで知名度低いのかわからん。 絶対日本でも売れる。SFにありがちな小難しい科学描写も少ない。 良い言葉じゃないけど『万人受け』するタイプの作品だと思う。 積読してる人、気になってる人、是非読んで。 解説によれば、作者の活躍した時期は第一次世界大戦から第二次世界大戦を股にかける時代だったらしい。 8章ケンブリッジでのシリウスで、利己的な人類への軽蔑の気持ちを連ねているところを読みながら、シリウスがディオゲネスと話をしたらどう感じるんだろうと考えたあとに、そういえばキュニコスの和訳は犬儒学だったなと気づいて1人で勝手に面白くなった。 【以下ネタバレ含む】 ・全体通してみて、ハイデガーの存在と時間を読む必要がありそうだと思った。 読んだことないので憶測だけど、作中で何度もシリウスが行き詰まったポイントに照らし合わせられるのは、存在と時間なんじゃないかと。読んだことないけど。 ・エリザベスの死後、自分の育った家をプラクシーと2人で片付け、思い出の物を燃やし、何もなくなった家で2人で過ごすシーンは胸にくるものがある。 親しい人の死や長い年月を過ごした場所から離れることを受け入れるのには時間がかかるが、現実の時の進みは待ってはくれない。そういうときは大抵、心の折り合いがつかないまま時間に押し流されるように、大切だったものとの永遠の別れを強制される。直接的な文章があるわけじゃないけど、それを痛感するシーンだった。 それを感じられる翻訳も素晴らしい。 ・シリウスを悪魔と呼び悪魔退治に勤しむ人々が、ピューの羊を殺してシリウスとプラクシーの家の前に置いていくという行為はキリスト教的ブラックジョークか? 羊はキリスト自身やキリストに従う人々の象徴なのだから、それを殺して悪魔に捧げるとは、これじゃあどっちが悪魔なんだか。 ・「プラクシー=シリウス、生きていてむだじゃなかった」 どういう意味で言ったんだ。 作品の大部分は、シリウス目線の伝記をロバートが代筆した形で書かれていたからシリウスの視線をベースに進んでいたのに、最期の言葉をどう受け取るかは読者に委ねられてる。 ずるい。 - 2025年9月8日
- 2025年9月6日
 夜市恒川光太郎読み終わった装丁のデザインからしてもっと湿度の高い怪奇小説のようなものかと思っていたけど、ファンタジーエンタメみたいな作品だった。風の古道は、読んでいると自分の体験したことのある山道の空気や土の感触や風景を想像したくなる。
夜市恒川光太郎読み終わった装丁のデザインからしてもっと湿度の高い怪奇小説のようなものかと思っていたけど、ファンタジーエンタメみたいな作品だった。風の古道は、読んでいると自分の体験したことのある山道の空気や土の感触や風景を想像したくなる。 - 2025年9月5日
 砂の女(新潮文庫)安部公房読み終わった閉塞空間で主人公に最低限の情報しか与えられず、土地の人間たちはそれを知った上で主人公を観察飼育するように見ているというのが、どことなくSFっぽく感じる。 結局砂穴からの逃走をやめたのは子供ができたからなのか、それとも別の心情変化による物なのか。
砂の女(新潮文庫)安部公房読み終わった閉塞空間で主人公に最低限の情報しか与えられず、土地の人間たちはそれを知った上で主人公を観察飼育するように見ているというのが、どことなくSFっぽく感じる。 結局砂穴からの逃走をやめたのは子供ができたからなのか、それとも別の心情変化による物なのか。 - 2025年9月3日
 読み終わった明日天気になーれって靴を飛ばす遊びを今の子はしないのか!と衝撃だった。平成初期生まれの私は小学校の帰り道なんかに友達とよくやっていたので。SNSに書けば炎上するような恨みつらみを受け止めてくれる神様という存在は現代にこそ有用という主張に納得。三重県鳥羽市神島のゲーター祭、正直めちゃくちゃ気になる。見てみたい。コロナ禍のアマビエブームに対する著者の考えについては「へー」ってくらいだけど、何月何日になにがあったかまで記録しているのは変態すぎて面白い。自殺するときに履き物を脱ぐという行為が、遡れば十四世紀の文章から描かれているというのは驚き。それが韓国でも同じというのも初めて知った。全体的に読みやすくてユーモアのある文章だった。他の著書も読みたいなと思ったけどこれしか出版されていないようで残念。 "近世初期のひねくれものたちが見つけ出した「鰯の頭も信心から」という言葉とは、フィクションをフィクションとして受け止めながら、それでも手を合わさずにはいられない人間味が読み込まれた最小の物語" ↑お気に入り
読み終わった明日天気になーれって靴を飛ばす遊びを今の子はしないのか!と衝撃だった。平成初期生まれの私は小学校の帰り道なんかに友達とよくやっていたので。SNSに書けば炎上するような恨みつらみを受け止めてくれる神様という存在は現代にこそ有用という主張に納得。三重県鳥羽市神島のゲーター祭、正直めちゃくちゃ気になる。見てみたい。コロナ禍のアマビエブームに対する著者の考えについては「へー」ってくらいだけど、何月何日になにがあったかまで記録しているのは変態すぎて面白い。自殺するときに履き物を脱ぐという行為が、遡れば十四世紀の文章から描かれているというのは驚き。それが韓国でも同じというのも初めて知った。全体的に読みやすくてユーモアのある文章だった。他の著書も読みたいなと思ったけどこれしか出版されていないようで残念。 "近世初期のひねくれものたちが見つけ出した「鰯の頭も信心から」という言葉とは、フィクションをフィクションとして受け止めながら、それでも手を合わさずにはいられない人間味が読み込まれた最小の物語" ↑お気に入り - 2025年9月1日
 月まで三キロ(新潮文庫)伊与原新読み終わった伊与原さんの本は「オオルリ流星群」についで2冊目。 直感で買ったので読んでみて知ったけど短編集だった。 著者の作品に出てくる科学者のような大人に出会える子供時代だと人生が変わるだろうなと思う。 「アンモナイトの探し方」と「天王寺ハイエイタス」が個人的には好き。「エイリアンの食堂」は後半の水素の話のところがロマンに溢れてて最高。
月まで三キロ(新潮文庫)伊与原新読み終わった伊与原さんの本は「オオルリ流星群」についで2冊目。 直感で買ったので読んでみて知ったけど短編集だった。 著者の作品に出てくる科学者のような大人に出会える子供時代だと人生が変わるだろうなと思う。 「アンモナイトの探し方」と「天王寺ハイエイタス」が個人的には好き。「エイリアンの食堂」は後半の水素の話のところがロマンに溢れてて最高。 - 2025年8月31日
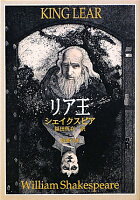 リア王シェイクスピア読み終わったリア王最初から最後まで本当に阿呆なんだけど、度々面白いことを言うのでチグハグで良いキャラクター。エドマンドは普通に気持ち悪い。 シェイクスピアの時代は今と違って明かりで夜を表現することも、効果音で嵐を表現することもできなかった。だから、今はどういう情景のなかなのかを全て台詞を通して観客に伝えなければならない。これが全然わざとらしくないのがすごい。
リア王シェイクスピア読み終わったリア王最初から最後まで本当に阿呆なんだけど、度々面白いことを言うのでチグハグで良いキャラクター。エドマンドは普通に気持ち悪い。 シェイクスピアの時代は今と違って明かりで夜を表現することも、効果音で嵐を表現することもできなかった。だから、今はどういう情景のなかなのかを全て台詞を通して観客に伝えなければならない。これが全然わざとらしくないのがすごい。 - 2025年8月29日
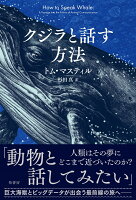 クジラと話す方法トム・マスティル,杉田真読み終わったアプリ初利用。テクノロジーと研究は人類と鯨類の会話を実現する目前まできている。だが、「そもそも人間は、クジラが言っていることを聞く準備ができているのだろうか」。ネアンデルタール人の存在を見つけた時、彼らを「愚かな人」と名付ける我々は、何かを発見すると、それを人間特有の機能だと考える。そして後に同じ機能が別の種にもあることがわかると、その機能の特殊性に疑問を持つようになる。人類は人類が特別なものであるとする人間中心社会の考え方を簡単に捨てられない。動物と会話するとはつまり、今までに(今も尚)人類が動物にしてきた事に正面から向き合う覚悟はあるのかという問題だ。著者の投げ掛けに考えさせられる。「人間性を諦めてはいけない」これは他の種との関係性だけでなく、死なないAIが台頭するこれからの世の中での人類の課題である。
クジラと話す方法トム・マスティル,杉田真読み終わったアプリ初利用。テクノロジーと研究は人類と鯨類の会話を実現する目前まできている。だが、「そもそも人間は、クジラが言っていることを聞く準備ができているのだろうか」。ネアンデルタール人の存在を見つけた時、彼らを「愚かな人」と名付ける我々は、何かを発見すると、それを人間特有の機能だと考える。そして後に同じ機能が別の種にもあることがわかると、その機能の特殊性に疑問を持つようになる。人類は人類が特別なものであるとする人間中心社会の考え方を簡単に捨てられない。動物と会話するとはつまり、今までに(今も尚)人類が動物にしてきた事に正面から向き合う覚悟はあるのかという問題だ。著者の投げ掛けに考えさせられる。「人間性を諦めてはいけない」これは他の種との関係性だけでなく、死なないAIが台頭するこれからの世の中での人類の課題である。
読み込み中...





