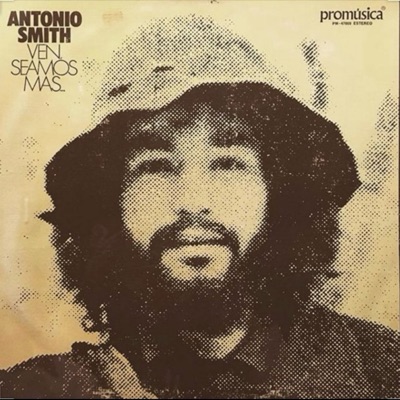
J.B.
@hermit_psyche
2025年9月16日

数学を使わない数学の講義
小室直樹
読み終わった
単なる数学の平易な入門書ではなく、思考の骨格そのものを読者に突き付ける知的挑発だと感じた。
小室が試みるのは定理や公式の紹介ではなく数学的であるとは何かを日本語の論理と社会的文脈を媒介にして掘り下げることだ。
まず印象的だったのは彼が数学を抽象化の極限として提示しながらそれを孤立した象牙の塔に閉じ込めない点である。
集合論や確率論を引き合いに出しつつも政治学・経済学・社会制度の分析へ自在に接続していく手際は数学を世界認識の言語として捉える鮮やかなデモンストレーションだった。
形式の美しさを讃えるだけではなくその形式が現実をどのように切り取るか、またどこまで切り取れるのかという限界をも同時に可視化している。
また日本の教育や文化が論理より情緒を重んじる傾向を指摘し、そこで数学的思考がなぜ育ちにくいかを分析する議論には社会学者としての小室らしい鋭さがある。
数学嫌いを単なる個人の性質に還元せず制度や歴史の問題として俯瞰する視座は数学の啓蒙書としては異例に政治的ですらある。
数学を使わないとは計算を省くことではなく数学が持つ普遍的な思考の枠組みを言語で再構築する試みだったということだ。
数学そのものへの理解というよりも世界を論理で記述しようとする姿勢そのものが自分の思考を一段引き上げてくれるような余韻が残る。
知的体力を試されつつも読者を確実に豊かにする。

