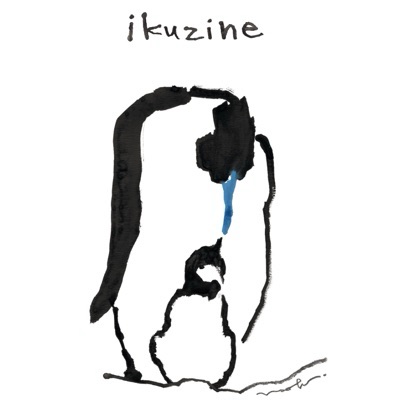
Yamada Keisuke
@afro108
2025年10月20日

ライムスター宇多丸の「ラップ史」入門
DJ YANATAKE,
宇多丸,
渡辺志保,
高橋芳朗
読み終わった
宇多丸史観の日本語ラップについて読んだので、当人が自ら語るヒップホップ史の本を読んだ。初版は2018年、私がブックオフでサルベージしたのは2024年の5刷。ヒップホップブームの中で、多くの人がまず最初にこれを手に取り、理解を深めようとしていることがうかがえる。読みやすさ、まとまり具合でいえば、入門書としてこれ以上のものはない。ヒップホップに興味を持ち始めた人にはおすすめだし、私のように長年聞いてきたヘッズでも新たな発見がたくさんあり興味深かった。
本著は2018年にNHK-FMで放送された10時間にわたるヒップホップ特番の書き起こしである。司会はRHYMSTER 宇多丸、サポートに音楽ライターの高橋芳朗&渡辺志保、音出しなどでDJ YANATAKEというメンバー編成。構成としては、アメリカのヒップホップの歴史を年代順に辿りながら、その時代の日本語ラップシーンゲストを交えつつ、歴史を振り返っていく。つまり、「アメリカで何が起きていたか」と「日本ではどう受け止め、どう応答していたか」をパラレルに描いている点が本書の大きな特徴である。
こういった構成になっているのは、日本語ラップが常にアメリカのヒップホップをリファレンスし、自分たちのスタイルを模索してきたからに他ならない。その第一人者である宇多丸、BOSE、Zeebraが語っている内容は、「どうすれば日本語がラップとしてかっこよく聞こえるか」というラップの聞こえ方の話が中心で、そこに至るまでの試行錯誤が伝わってきた。番組の締めには、当時1stアルバムを出したばかりのBAD HOPが登場し、スタジオライブで幕を閉じる。アメリカの文脈を踏まえつつ日本語で表現する、その継承と更新を象徴する構成だ。日本語ラップの現状の盛り上がりは、国内アーティストを中心としたドメスティックなものにとどまっているように最近感じる。その中で、YZERRが自らメディアを立ち上げ、超弩級のアメリカのラッパーたちと日本のラッパーというラインナップでヒップホップ特化のフェスを開催したことは、本著の意図の延長線にあると言えるだろう。本著でも語られているように、ヒップホップは時代ごとにアップデートされる共通ルールのもとで、世界規模の競争が行われるゲーム的な音楽なのだ。だからこそ、アメリカを中心としたグローバルなトレンドを常に参照し、その文脈の中で日本語ラップを位置づける視点は欠かせない。
日本語ラップのパートでスリリングだったのは、MC漢が登場する場面だ。この二人がNHK-FMで当時のことを振り返るなんて企画を立案、実行した担当者の方々にリスペクト。前述の二者は同世代かつ交流もあるわけだが、世代も信条も異なる中で、宇多丸がMC漢のオリジナリティの高いスタイルの起源を紐解いていくあたりは知らないことだらけで驚いた。今でこそYouTubeで共演するレベルの関係性だが、2018年段階では貴重な邂逅であり、文字だけども緊張感がちゃんと伝わってきた。
アメリカサイドは、基本的なヒップホップ史を改めて俯瞰できる構成になっており、自分の中のタイムラインが整理できた。特に東海岸、西海岸以外のヒップホップに理解が浅い自分にとっては、南部の歴史を流れで知ることができて勉強になった。合間に各人が持っているヒップホップ小ネタが挟まれるのがオモシロく、宇多丸はライター時代のインタビューエピソード、高橋氏はヒップホップ以外の音楽とヒップホップの関係性、渡辺氏はスラング、ゴシップなど鮮度の高い情報、DJ YANATAKEはレコ屋店員時代の経験といった形で、それぞれの得意分野が相補的に機能し、情報に厚みが増していた。
歴史の授業あるあるだが、黎明期〜2000年代までの説明が丁寧になった結果、近年の動向が相対的に弱くなってはいる。特にヒップホップは50年の歴史の中で目まぐるしくスタイルが変遷してきており、最近のトレンドについて知りたいと思って読んだ人は肩透かしをくらうかもしれない。しかし、ヒップホップのオモシロいところは、過去をサンプリングという形で何度でも再評価、再構築するところだ。ゆえにクラシックを知っていることで、新しい曲のコンテキストを深く味わうことができる。だからこそ、こういった形で体系的に歴史を網羅した一冊は定番として読み継がれていくだろう。


