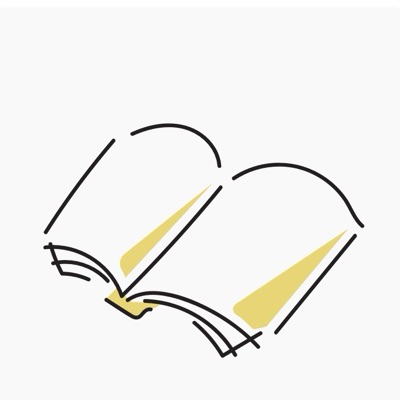
徒然
@La_Souffrance
1900年1月1日

城 (新潮文庫)
フランツ・カフカ
読み終わった
面白かった、、、ストーリー的な面白さはあんまりないかもしれないけど、それ以外の部分が凄くて読み応えがあった。時間をおいてもう一度読むと違う感想が出てきそう。
以下、現段階の感想、解釈、ネタバレを含むためご注意ください。
ストーリーの面白さが少なかったとは書いたものの、個人的にフリーダがKと別れて助手の一人とくっついたのがびっくりした。城に近づいたと思ったらフリーダとはなれる、天体みたい。
この本を読んだとき、人間が世界に放り出される瞬間を覗いているような気持ちになった。
主人公Kは測量士として村にやってくるが、仕事は始まらない。測ろうとしているのは土地ではなく、世界そのものの構造なのかもしれない。
Kの測量は、世界を理解し秩序を確かめようとする理性の営みであり、同時に自分の存在を確認する行為でもあるのかもしれない。
しかしKが出会うのは、不透明で複雑な掟の体系。村を支配する「城」の掟は論理や法則のように見えても、誰も全貌をつかめない。手続きは錯綜し、意味があると信じても、その先にたどり着くことはできない。合理的に理解しようとすればするほど、城は遠ざかる。
その構造は村人の間にも反復されている。誰もが見えない権威や慣習に従いながら互いを承認したり拒んだりしている。まるで城とKの関係のミニチュアが人間関係全体に組み込まれているみたいに。
村人が城を語る様子は、神を語る人間に似ている。信仰と懐疑、服従と諦念が入り混じっているような。近代社会における制度や社会は神の代わりとなり、人はそこに承認を求め続けるが、決して明確な返答は得られないということなのかもしれない。
Kとフリーダの関係も象徴的だ……フリーダはKが唯一承認を感じられる存在だったが、関係は崩れ、助手――Kの分身のような存在――に取って代わられる。
承認は他者の中にしか存在せず、他者もまた不確かであるため、満たされることはないということ…?
Kが求めるのは仕事や成功、愛ではなく、この世界の中で自分が存在しているという証のように思える。世界はその証を与えてはくれないんだけど…。
Kが城に承認を求めることは、
人が自分の存在の根拠を外部(社会・制度・他者)に求める構造と似てる。
その外部=城=他者は、実体のない空虚な構造体であり、承認も最終的には得られない。
ラカンの言う空虚な中心にあたるといえる…??
助手の2人はKの分身であり、同時に自分を奪う他者でもある……理性的に世界を理解しようとすればするほど、無意識が暴れ、自己の輪郭が揺らいでるみたいだ……
三人組の関係は、安定の象徴である三角構造を模倣しようとするも、常に崩れている……命令や意図は伝わらず、行動が食い違い、秩序は不安定。
Kと助手、フリーダとの関係は、他者との関係そのものが自己を分裂させることを示しているのかもしれない……
現代社会を考えると、この村や城の構造は他人事ではないんじゃないかと思った。何事をも自分に引き寄せて考えるのは良くないとは思いつつも、私もKと同じように、目に見えないルールや制度に巻き込まれながら生きてるし、存在は不確かだし…。
城の不透明さは、制度の問題と存在そのものの不透明さを描いている気がする。世界の構造が分からず、承認も得られない。それでも生き続けるしかない。Kの測量は、測れない世界を測ろうとし、承認されないまま生きる人間の姿そのものなのではないか……つらい……






