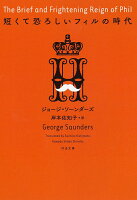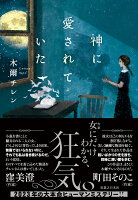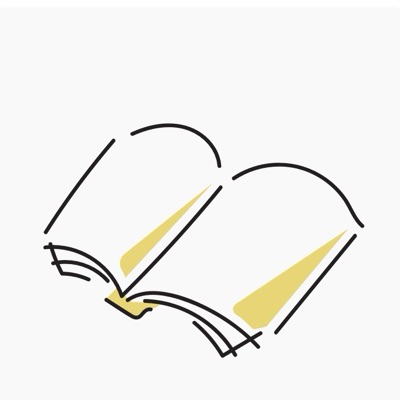
徒然
@La_Souffrance
- 1900年1月1日
- 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 犬の記憶森山大道読み終わった「いつどこへ旅しても、僕につきまとういい知れぬ不安。といえば体裁よく思われてしまいそうであるが、本人はほんとうにつらい。むろん現実からぷっつり切れ、自意識を捨て切ることなど生きている以上いかなる事態においてもありえないから、それを旅に望むことは不可能である。むしろ旅とは、そうして丸抱えにしてしまっている自分のぬきさしならなさを、未知の時空に投げ入れることによって、さまざまな擦過の過程のなかから、自分のなかにさらに新しい自意識の覚醒をはかることであろう。僕の内にひそむ、過去の経験による多くの記憶と、未知への予感から生れる記憶との交感によって、かならずしも、自覚的ばかりではない自分を発見し予見する行為のひとつのかたちが、たとえば旅である。」 寺山修司みたいだなと思ったら寺山修司出てきて激アツ。最初は鋭さが足りない気がしたけど、後半に行くにつれてどんどん良くなる。
犬の記憶森山大道読み終わった「いつどこへ旅しても、僕につきまとういい知れぬ不安。といえば体裁よく思われてしまいそうであるが、本人はほんとうにつらい。むろん現実からぷっつり切れ、自意識を捨て切ることなど生きている以上いかなる事態においてもありえないから、それを旅に望むことは不可能である。むしろ旅とは、そうして丸抱えにしてしまっている自分のぬきさしならなさを、未知の時空に投げ入れることによって、さまざまな擦過の過程のなかから、自分のなかにさらに新しい自意識の覚醒をはかることであろう。僕の内にひそむ、過去の経験による多くの記憶と、未知への予感から生れる記憶との交感によって、かならずしも、自覚的ばかりではない自分を発見し予見する行為のひとつのかたちが、たとえば旅である。」 寺山修司みたいだなと思ったら寺山修司出てきて激アツ。最初は鋭さが足りない気がしたけど、後半に行くにつれてどんどん良くなる。 - 1900年1月1日
 これはペンです円城塔以下は読みながら書いたメモ 「叔父は文字だ。文字通り。」っていう書き出しがいい 最初に思ったのは、「人間が言葉を出力する機械と何が違うのか」と同じようなテーマなのかということ。 最初は、知識の切り貼りっぽい印象をうけた。「簡単にかけてしまうと思わないかね」を体現してるのかと思った。 あるいはこれらの知識を手掛かりに、興味を持って調べ始める人がいるかもしれないから、このように知識を提示してるのかもと思った。 叔父が研究そのものの比喩で、叔父と姪の子供が叔父というのは、この小説を手掛かりに何かに興味を持って研究し始めた人なのかもしれないと思った。 研究において再現性は必須だけど、同じ手順で行っても同じ結果となることはない。小説も思考も研究も。ずっと同じ手順で同じ物質が作られていたのに、急に物質の旋光が変わってしまうこともあるし。 研究ってこうだよなってぼんやり思った。系統に連なる、家族みたいなもの。家族のどこに自分が位置しているのか。 次の短編が叔父さんの話だったの良かった。立体的になった。 ゴダールやモンタージュを思い出す。 意味が通って文章になるわけじゃない。人間は意味のわからないものにも意味を見出せる。 もちろん、完全に意味の通らない文章にすることも可能。この辺ウィトゲンシュタインの本見返すこと。 思索みたいな本だ。 ふと、翻訳の仕方の話の可能性に思い至る。 この本の解釈が人それぞれのように、あらゆる物事を自分の中でどのように翻訳するのかにかかっている。 同じ世界を誰とも共有できない悲しみがある。翻訳は人それぞれだから。 それこそ、この本の中で書かれている記憶のやり方や、本が自分の体によって変わるということもそう。 「ここには僕ひとりしかいない。僕しかいないよ」 現実では妻は他人として現れ、捉えられない。反対に、夢の中では捉えられる。それは自分の中に取り込んでるから。現実では他人なので捉えられない。 中国語の部屋の部屋になるということがわからなかったが、後の短編で判明する。姪からみた叔父と叔父のイメージが一致しなかったが、ここでは一致していたように思う。 姪にとっての叔父と、叔父の父にとっての母。 叔父にとっての父。 書き連ねていってもその人そのものにはならない。 世界が各々の翻訳で変わる 同じものを見て同じものを見れない類の孤独 ここでは孤独とは書かれない
これはペンです円城塔以下は読みながら書いたメモ 「叔父は文字だ。文字通り。」っていう書き出しがいい 最初に思ったのは、「人間が言葉を出力する機械と何が違うのか」と同じようなテーマなのかということ。 最初は、知識の切り貼りっぽい印象をうけた。「簡単にかけてしまうと思わないかね」を体現してるのかと思った。 あるいはこれらの知識を手掛かりに、興味を持って調べ始める人がいるかもしれないから、このように知識を提示してるのかもと思った。 叔父が研究そのものの比喩で、叔父と姪の子供が叔父というのは、この小説を手掛かりに何かに興味を持って研究し始めた人なのかもしれないと思った。 研究において再現性は必須だけど、同じ手順で行っても同じ結果となることはない。小説も思考も研究も。ずっと同じ手順で同じ物質が作られていたのに、急に物質の旋光が変わってしまうこともあるし。 研究ってこうだよなってぼんやり思った。系統に連なる、家族みたいなもの。家族のどこに自分が位置しているのか。 次の短編が叔父さんの話だったの良かった。立体的になった。 ゴダールやモンタージュを思い出す。 意味が通って文章になるわけじゃない。人間は意味のわからないものにも意味を見出せる。 もちろん、完全に意味の通らない文章にすることも可能。この辺ウィトゲンシュタインの本見返すこと。 思索みたいな本だ。 ふと、翻訳の仕方の話の可能性に思い至る。 この本の解釈が人それぞれのように、あらゆる物事を自分の中でどのように翻訳するのかにかかっている。 同じ世界を誰とも共有できない悲しみがある。翻訳は人それぞれだから。 それこそ、この本の中で書かれている記憶のやり方や、本が自分の体によって変わるということもそう。 「ここには僕ひとりしかいない。僕しかいないよ」 現実では妻は他人として現れ、捉えられない。反対に、夢の中では捉えられる。それは自分の中に取り込んでるから。現実では他人なので捉えられない。 中国語の部屋の部屋になるということがわからなかったが、後の短編で判明する。姪からみた叔父と叔父のイメージが一致しなかったが、ここでは一致していたように思う。 姪にとっての叔父と、叔父の父にとっての母。 叔父にとっての父。 書き連ねていってもその人そのものにはならない。 世界が各々の翻訳で変わる 同じものを見て同じものを見れない類の孤独 ここでは孤独とは書かれない - 1900年1月1日
 アサイラム・ピースアンナ・カヴァン読み終わっためっちゃ良い。こんなに刺さると思わなかった。 タイトルにもなっているアサイラム・ピースは微小妄想などの鬱症状が描かれ、それよりも前に並んでいる短編は、統合失調症の妄想や幻覚みたいだった。 そう思いながら読んだせいか、フィクションではなくエッセイを読んでいる気分だった。訳者あとがきに“フィクショナライズされた人物の生"と書いてあって、まさしくこれだと思った。感覚を捉える言葉が鋭く、作者の苦しみが私にも襲ってきて泣きそうだった。 「不満の表明」「いまひとつの失敗」「召喚」「夜に」「不愉快な警告」が特に好き。 "「私がどうすべきか、なぜ教えてくれないんです?」 面談の最後に私は憤然としてたずねた。「どうして、具体的な行動の指針を示して、私をこの苦しみから、不確実な状況から救ってくれないんですか」 「それこそまさに私があえてするまいと思っていることです」とDは言った。「最大の問題点は、あなたが常に責任を回避しているところにある。これは、あなたが、あなた自身のイニシアティヴのもとに行動しなければならない問題なんです。 不親切に思えたら申しわけないが、しかし、これだけは本気で受け止めてもらわねばなりません。私であれ、ほかの誰であれ、外からのアドバイスに盲目的に従うのではなく、自分自身でこの事態の全容をしっかり見極めることこそが、長い目で見れば、あなたにとってはるかによい結果をもたらすはずだということを━━」"
アサイラム・ピースアンナ・カヴァン読み終わっためっちゃ良い。こんなに刺さると思わなかった。 タイトルにもなっているアサイラム・ピースは微小妄想などの鬱症状が描かれ、それよりも前に並んでいる短編は、統合失調症の妄想や幻覚みたいだった。 そう思いながら読んだせいか、フィクションではなくエッセイを読んでいる気分だった。訳者あとがきに“フィクショナライズされた人物の生"と書いてあって、まさしくこれだと思った。感覚を捉える言葉が鋭く、作者の苦しみが私にも襲ってきて泣きそうだった。 「不満の表明」「いまひとつの失敗」「召喚」「夜に」「不愉快な警告」が特に好き。 "「私がどうすべきか、なぜ教えてくれないんです?」 面談の最後に私は憤然としてたずねた。「どうして、具体的な行動の指針を示して、私をこの苦しみから、不確実な状況から救ってくれないんですか」 「それこそまさに私があえてするまいと思っていることです」とDは言った。「最大の問題点は、あなたが常に責任を回避しているところにある。これは、あなたが、あなた自身のイニシアティヴのもとに行動しなければならない問題なんです。 不親切に思えたら申しわけないが、しかし、これだけは本気で受け止めてもらわねばなりません。私であれ、ほかの誰であれ、外からのアドバイスに盲目的に従うのではなく、自分自身でこの事態の全容をしっかり見極めることこそが、長い目で見れば、あなたにとってはるかによい結果をもたらすはずだということを━━」" - 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 虚言の国 アメリカ・ファンタスティカティム・オブライエン,村上春樹読み終わった面白かった!度々、「ああそういうことか!」っていう瞬間があって楽しい。 "弾丸はまだ四発残っていた。三発多すぎる。"っていうところ特に好き。 言い回しが洋画っぽくてテンポも良い。 虚言をテーマに社会問題を浮き彫りにしながら、しっかりと物語として成立させるの凄すぎる。 "「真実よ! 一度でもいいから真実を言いなさい。それで歯が痛くなったりすることもないから」 (…) 「オーケー、じゃあ何のためなの?」 「ぼくにもそれはわからない。退路を断つってことかな? 自分自身を動かしていくための」" "「あなたの問題の一部は」 (…) 「自分自身にさえ嘘をつくということなの。" "「ぼくらはみんな幻想を必要としているんだよ、アンジー。きみでさえ。ハープと光輪。 生命の永続。 UFOやら、アルコール入りのクールエイドやら、素敵な王子様やら、ぼくらを楽園に送り込んでくれるものをね。この地上のすべての人が─ぼくらを前に進ませてくれる何らかのために、現実性をトレードに出しているんだ」 「あなたは欺瞞を弁護しているわけ?」 「いや、ぼくは欺瞞を説明しているだけだ」" "「ぼくが言いたいのは、それをやめることができるかどうか、自分でもわからないということだ。やめたいかどうかさえわからない。ぼくは地虫じゃない。妄想のない人生なんて、いったい何だろう?」 「それが真実と呼ばれるものなのよ、ボイド。 それはあなたを壊したりはしない」"
虚言の国 アメリカ・ファンタスティカティム・オブライエン,村上春樹読み終わった面白かった!度々、「ああそういうことか!」っていう瞬間があって楽しい。 "弾丸はまだ四発残っていた。三発多すぎる。"っていうところ特に好き。 言い回しが洋画っぽくてテンポも良い。 虚言をテーマに社会問題を浮き彫りにしながら、しっかりと物語として成立させるの凄すぎる。 "「真実よ! 一度でもいいから真実を言いなさい。それで歯が痛くなったりすることもないから」 (…) 「オーケー、じゃあ何のためなの?」 「ぼくにもそれはわからない。退路を断つってことかな? 自分自身を動かしていくための」" "「あなたの問題の一部は」 (…) 「自分自身にさえ嘘をつくということなの。" "「ぼくらはみんな幻想を必要としているんだよ、アンジー。きみでさえ。ハープと光輪。 生命の永続。 UFOやら、アルコール入りのクールエイドやら、素敵な王子様やら、ぼくらを楽園に送り込んでくれるものをね。この地上のすべての人が─ぼくらを前に進ませてくれる何らかのために、現実性をトレードに出しているんだ」 「あなたは欺瞞を弁護しているわけ?」 「いや、ぼくは欺瞞を説明しているだけだ」" "「ぼくが言いたいのは、それをやめることができるかどうか、自分でもわからないということだ。やめたいかどうかさえわからない。ぼくは地虫じゃない。妄想のない人生なんて、いったい何だろう?」 「それが真実と呼ばれるものなのよ、ボイド。 それはあなたを壊したりはしない」" - 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 かもめのジョナサンリチャード・バック,五木寛之読み終わった"正確な飛行は、私たちの本性を表現する一つの段階なのだ。" "「きみたちの全身は、翼の端から端まで─」ジョナサンは折をみつけてはよく言ったものである。 「それは目に見える形をとった、きみたちの思考そのものにすぎない。思考の鎖を断つのだ。そうすれば肉体の鎖も断つことになる……」" 物語として面白かったけど、正直寓意がよくわからず戸惑った。今の自分はまだこの物語を必要としていないのかもしれない。 ジョナサンは食べるためではなく、飛ぶために飛ぶことを追求する。最初は単なる技術の探求に見えた飛行も、次第に「自分がどう在るか」という存在の純度の問題になっていく。飛ぶことは、単なる行為ではなく、存在の完成に近い行為なんだと思う。 飛ぶことの実利(こうやって飛べば魚が手に入るよ、とか)を教えればいいのにと思ったけれど、あえてそれをしないことで、精神的な追求を描いている気がする。
かもめのジョナサンリチャード・バック,五木寛之読み終わった"正確な飛行は、私たちの本性を表現する一つの段階なのだ。" "「きみたちの全身は、翼の端から端まで─」ジョナサンは折をみつけてはよく言ったものである。 「それは目に見える形をとった、きみたちの思考そのものにすぎない。思考の鎖を断つのだ。そうすれば肉体の鎖も断つことになる……」" 物語として面白かったけど、正直寓意がよくわからず戸惑った。今の自分はまだこの物語を必要としていないのかもしれない。 ジョナサンは食べるためではなく、飛ぶために飛ぶことを追求する。最初は単なる技術の探求に見えた飛行も、次第に「自分がどう在るか」という存在の純度の問題になっていく。飛ぶことは、単なる行為ではなく、存在の完成に近い行為なんだと思う。 飛ぶことの実利(こうやって飛べば魚が手に入るよ、とか)を教えればいいのにと思ったけれど、あえてそれをしないことで、精神的な追求を描いている気がする。 - 1900年1月1日
 複眼人呉明益,小栗山智読み終わった装丁に惹かれて読み始めたけれど、文章が想像以上に凄かった。頭の奥が痺れるような感覚。 作者が環境問題に関心のある人らしいけれど、読むあいだはそれに関連付けて読み解くことはせず、ただ流れに身を任せてページをめくった。 読後なんとなくSEKAI NO OWARIの虹色の戦争という曲を思い出した。 それから自然と、作者が環境問題をどう考えているのかに思いを馳せた。多声的に描くことで、二項対立が緩まる気がした。しかしなんというか、多くの登場人物が現れるものの、それぞれが役割的だったり、限られた人間関係の中で描かれていたりする印象もあり、それの意味を測り兼ねている(意味……というのは言葉が過ぎるけれども)。 以下は環境問題以外の感想 アトレや先住民の人々など、自然とともに生きる者たちの描写を美しいと感じると同時に、どこか後ろめたさを覚えた。 なぜなら文明の側に立つ私は、ときに自然と共にある他者を理想化し、純粋さや調和をそこに投影する。そうしたロマン化のまなざしは、一見すると共感のようでいて、支配の歴史と隣り合わせにある可能性をもつ。「自分たちは文明化された存在である」「彼らは自然に生きる原初的存在である」という上下関係や、「自然と共に生きることこそ素晴らしい」というような美化というかたちをとった支配。自分が感じた憧憬がこれに近いものなんじゃないかと思って。
複眼人呉明益,小栗山智読み終わった装丁に惹かれて読み始めたけれど、文章が想像以上に凄かった。頭の奥が痺れるような感覚。 作者が環境問題に関心のある人らしいけれど、読むあいだはそれに関連付けて読み解くことはせず、ただ流れに身を任せてページをめくった。 読後なんとなくSEKAI NO OWARIの虹色の戦争という曲を思い出した。 それから自然と、作者が環境問題をどう考えているのかに思いを馳せた。多声的に描くことで、二項対立が緩まる気がした。しかしなんというか、多くの登場人物が現れるものの、それぞれが役割的だったり、限られた人間関係の中で描かれていたりする印象もあり、それの意味を測り兼ねている(意味……というのは言葉が過ぎるけれども)。 以下は環境問題以外の感想 アトレや先住民の人々など、自然とともに生きる者たちの描写を美しいと感じると同時に、どこか後ろめたさを覚えた。 なぜなら文明の側に立つ私は、ときに自然と共にある他者を理想化し、純粋さや調和をそこに投影する。そうしたロマン化のまなざしは、一見すると共感のようでいて、支配の歴史と隣り合わせにある可能性をもつ。「自分たちは文明化された存在である」「彼らは自然に生きる原初的存在である」という上下関係や、「自然と共に生きることこそ素晴らしい」というような美化というかたちをとった支配。自分が感じた憧憬がこれに近いものなんじゃないかと思って。 - 1900年1月1日
 蝶皆川博子読み終わった戦争前後を舞台にした短編集。仄暗い現実の息遣いが聞こえる中、幻想的な情景が描き出される。思わず感嘆のため息がもれるような、惚れ惚れとする文章だった。 "二階にあがってはならぬと祖母に止められていた。階段が急で危ないからというのが理由であったが、たとえ禁止されずとも、のぼる勇気は、幼いわたしには、なかった。 上り口から見上げると、竪穴のような階段は、見果てぬ高みにいくほど闇の濃さを増し、はては暗黒に溶け入り、なにやら湿っぽく恐ろしげで、それでも怖いものほど覗き見たくもあり、下の段に両手をつき、前足を胸の前にそろえた狛犬みたいな恰好で、首をおそるおそるのばすと、闇がぞわぞわと蠢きながら、黒い霧のように階段を流れ下りてくるので、あわてて縁側で縫い物をしている祖母のそばに這いずって逃げた。"
蝶皆川博子読み終わった戦争前後を舞台にした短編集。仄暗い現実の息遣いが聞こえる中、幻想的な情景が描き出される。思わず感嘆のため息がもれるような、惚れ惚れとする文章だった。 "二階にあがってはならぬと祖母に止められていた。階段が急で危ないからというのが理由であったが、たとえ禁止されずとも、のぼる勇気は、幼いわたしには、なかった。 上り口から見上げると、竪穴のような階段は、見果てぬ高みにいくほど闇の濃さを増し、はては暗黒に溶け入り、なにやら湿っぽく恐ろしげで、それでも怖いものほど覗き見たくもあり、下の段に両手をつき、前足を胸の前にそろえた狛犬みたいな恰好で、首をおそるおそるのばすと、闇がぞわぞわと蠢きながら、黒い霧のように階段を流れ下りてくるので、あわてて縁側で縫い物をしている祖母のそばに這いずって逃げた。" - 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 城 (新潮文庫)フランツ・カフカ読み終わった面白かった、、、ストーリー的な面白さはあんまりないかもしれないけど、それ以外の部分が凄くて読み応えがあった。時間をおいてもう一度読むと違う感想が出てきそう。 以下、現段階の感想、解釈、ネタバレを含むためご注意ください。 ストーリーの面白さが少なかったとは書いたものの、個人的にフリーダがKと別れて助手の一人とくっついたのがびっくりした。城に近づいたと思ったらフリーダとはなれる、天体みたい。 この本を読んだとき、人間が世界に放り出される瞬間を覗いているような気持ちになった。 主人公Kは測量士として村にやってくるが、仕事は始まらない。測ろうとしているのは土地ではなく、世界そのものの構造なのかもしれない。 Kの測量は、世界を理解し秩序を確かめようとする理性の営みであり、同時に自分の存在を確認する行為でもあるのかもしれない。 しかしKが出会うのは、不透明で複雑な掟の体系。村を支配する「城」の掟は論理や法則のように見えても、誰も全貌をつかめない。手続きは錯綜し、意味があると信じても、その先にたどり着くことはできない。合理的に理解しようとすればするほど、城は遠ざかる。 その構造は村人の間にも反復されている。誰もが見えない権威や慣習に従いながら互いを承認したり拒んだりしている。まるで城とKの関係のミニチュアが人間関係全体に組み込まれているみたいに。 村人が城を語る様子は、神を語る人間に似ている。信仰と懐疑、服従と諦念が入り混じっているような。近代社会における制度や社会は神の代わりとなり、人はそこに承認を求め続けるが、決して明確な返答は得られないということなのかもしれない。 Kとフリーダの関係も象徴的だ……フリーダはKが唯一承認を感じられる存在だったが、関係は崩れ、助手――Kの分身のような存在――に取って代わられる。 承認は他者の中にしか存在せず、他者もまた不確かであるため、満たされることはないということ…? Kが求めるのは仕事や成功、愛ではなく、この世界の中で自分が存在しているという証のように思える。世界はその証を与えてはくれないんだけど…。 Kが城に承認を求めることは、 人が自分の存在の根拠を外部(社会・制度・他者)に求める構造と似てる。 その外部=城=他者は、実体のない空虚な構造体であり、承認も最終的には得られない。 ラカンの言う空虚な中心にあたるといえる…?? 助手の2人はKの分身であり、同時に自分を奪う他者でもある……理性的に世界を理解しようとすればするほど、無意識が暴れ、自己の輪郭が揺らいでるみたいだ…… 三人組の関係は、安定の象徴である三角構造を模倣しようとするも、常に崩れている……命令や意図は伝わらず、行動が食い違い、秩序は不安定。 Kと助手、フリーダとの関係は、他者との関係そのものが自己を分裂させることを示しているのかもしれない…… 現代社会を考えると、この村や城の構造は他人事ではないんじゃないかと思った。何事をも自分に引き寄せて考えるのは良くないとは思いつつも、私もKと同じように、目に見えないルールや制度に巻き込まれながら生きてるし、存在は不確かだし…。 城の不透明さは、制度の問題と存在そのものの不透明さを描いている気がする。世界の構造が分からず、承認も得られない。それでも生き続けるしかない。Kの測量は、測れない世界を測ろうとし、承認されないまま生きる人間の姿そのものなのではないか……つらい……
城 (新潮文庫)フランツ・カフカ読み終わった面白かった、、、ストーリー的な面白さはあんまりないかもしれないけど、それ以外の部分が凄くて読み応えがあった。時間をおいてもう一度読むと違う感想が出てきそう。 以下、現段階の感想、解釈、ネタバレを含むためご注意ください。 ストーリーの面白さが少なかったとは書いたものの、個人的にフリーダがKと別れて助手の一人とくっついたのがびっくりした。城に近づいたと思ったらフリーダとはなれる、天体みたい。 この本を読んだとき、人間が世界に放り出される瞬間を覗いているような気持ちになった。 主人公Kは測量士として村にやってくるが、仕事は始まらない。測ろうとしているのは土地ではなく、世界そのものの構造なのかもしれない。 Kの測量は、世界を理解し秩序を確かめようとする理性の営みであり、同時に自分の存在を確認する行為でもあるのかもしれない。 しかしKが出会うのは、不透明で複雑な掟の体系。村を支配する「城」の掟は論理や法則のように見えても、誰も全貌をつかめない。手続きは錯綜し、意味があると信じても、その先にたどり着くことはできない。合理的に理解しようとすればするほど、城は遠ざかる。 その構造は村人の間にも反復されている。誰もが見えない権威や慣習に従いながら互いを承認したり拒んだりしている。まるで城とKの関係のミニチュアが人間関係全体に組み込まれているみたいに。 村人が城を語る様子は、神を語る人間に似ている。信仰と懐疑、服従と諦念が入り混じっているような。近代社会における制度や社会は神の代わりとなり、人はそこに承認を求め続けるが、決して明確な返答は得られないということなのかもしれない。 Kとフリーダの関係も象徴的だ……フリーダはKが唯一承認を感じられる存在だったが、関係は崩れ、助手――Kの分身のような存在――に取って代わられる。 承認は他者の中にしか存在せず、他者もまた不確かであるため、満たされることはないということ…? Kが求めるのは仕事や成功、愛ではなく、この世界の中で自分が存在しているという証のように思える。世界はその証を与えてはくれないんだけど…。 Kが城に承認を求めることは、 人が自分の存在の根拠を外部(社会・制度・他者)に求める構造と似てる。 その外部=城=他者は、実体のない空虚な構造体であり、承認も最終的には得られない。 ラカンの言う空虚な中心にあたるといえる…?? 助手の2人はKの分身であり、同時に自分を奪う他者でもある……理性的に世界を理解しようとすればするほど、無意識が暴れ、自己の輪郭が揺らいでるみたいだ…… 三人組の関係は、安定の象徴である三角構造を模倣しようとするも、常に崩れている……命令や意図は伝わらず、行動が食い違い、秩序は不安定。 Kと助手、フリーダとの関係は、他者との関係そのものが自己を分裂させることを示しているのかもしれない…… 現代社会を考えると、この村や城の構造は他人事ではないんじゃないかと思った。何事をも自分に引き寄せて考えるのは良くないとは思いつつも、私もKと同じように、目に見えないルールや制度に巻き込まれながら生きてるし、存在は不確かだし…。 城の不透明さは、制度の問題と存在そのものの不透明さを描いている気がする。世界の構造が分からず、承認も得られない。それでも生き続けるしかない。Kの測量は、測れない世界を測ろうとし、承認されないまま生きる人間の姿そのものなのではないか……つらい…… - 1900年1月1日
 バックマン・ブックス〈4〉死のロングウォーク (扶桑社ミステリー)スティーヴン・キング,リチャード・バックマン,沼尻素子読み終わった一気に読めた……後半ドキドキしすぎて息が苦しかった。まだ心が道に取り残されている。 最後の一人になるまで歩くというシンプルな設定なのにこんなにも面白いのは流石としか……
バックマン・ブックス〈4〉死のロングウォーク (扶桑社ミステリー)スティーヴン・キング,リチャード・バックマン,沼尻素子読み終わった一気に読めた……後半ドキドキしすぎて息が苦しかった。まだ心が道に取り残されている。 最後の一人になるまで歩くというシンプルな設定なのにこんなにも面白いのは流石としか…… - 1900年1月1日
 レヴィナスを理解するためにコリーヌ・ペリュション,樋口雄哉,渡名喜庸哲,犬飼智仁読み終わっためちゃめちゃわかりやすい。レヴィナスに関する他の本を読んだことがないから、ここに書いてあることをどこまで信用していいのかわからないけど、とても読みやすいし、とても面白い。レヴィナスのことをもっと知りたくなった。 "他人を迎え入れるためには、私は、他人をさまざまなもののうちの一つとして見て、それを機能へと還元するような自然的態度を断ち切らなければならない。そのような態度は未知のものを既知のものにすること、他を同にすることだからだ。" "レヴィナスは、他人は「私の収容能力を超えている」と語っているが、それが言わんとしているのは、単に、私は他人の全容を把握できないとか他人についての十全な観念をもてないということではない。どのような概念・観念・表象であっても、他人に忠実に当てはまることはない、ということだ。"
レヴィナスを理解するためにコリーヌ・ペリュション,樋口雄哉,渡名喜庸哲,犬飼智仁読み終わっためちゃめちゃわかりやすい。レヴィナスに関する他の本を読んだことがないから、ここに書いてあることをどこまで信用していいのかわからないけど、とても読みやすいし、とても面白い。レヴィナスのことをもっと知りたくなった。 "他人を迎え入れるためには、私は、他人をさまざまなもののうちの一つとして見て、それを機能へと還元するような自然的態度を断ち切らなければならない。そのような態度は未知のものを既知のものにすること、他を同にすることだからだ。" "レヴィナスは、他人は「私の収容能力を超えている」と語っているが、それが言わんとしているのは、単に、私は他人の全容を把握できないとか他人についての十全な観念をもてないということではない。どのような概念・観念・表象であっても、他人に忠実に当てはまることはない、ということだ。" - 1900年1月1日
 バックマン・ブックス〈4〉死のロングウォーク (扶桑社ミステリー)スティーヴン・キング,リチャード・バックマン,沼尻素子読み始めた最後の1人になるまで歩き続けるデスゲーム。 映画化されたようだ。 1マイルってどれくらい?と思って調べてみたら1609mらしい……最低速度は時速4マイル。およそ時速6.4km……はやいな…… まだまだ序盤なのに、もう何マイルも歩いてる。すごい。みんなどこまで歩き続けられるんだろう……
バックマン・ブックス〈4〉死のロングウォーク (扶桑社ミステリー)スティーヴン・キング,リチャード・バックマン,沼尻素子読み始めた最後の1人になるまで歩き続けるデスゲーム。 映画化されたようだ。 1マイルってどれくらい?と思って調べてみたら1609mらしい……最低速度は時速4マイル。およそ時速6.4km……はやいな…… まだまだ序盤なのに、もう何マイルも歩いてる。すごい。みんなどこまで歩き続けられるんだろう…… - 1900年1月1日
 綺譚集津原泰水読み終わったいろいろな死が、怖さと美しさをまとって描かれていた。 短編ごとに文体も手法も違っていて、どれも精密。 生と死、残酷と無垢、日常と異界が一瞬で入れ替わる、その一瞬の美しさに心をつかまれる。 まるで生と死が切り絵みたいに左右対称に並んでいて、そのちょうど折り目に自分が立っているようだった。
綺譚集津原泰水読み終わったいろいろな死が、怖さと美しさをまとって描かれていた。 短編ごとに文体も手法も違っていて、どれも精密。 生と死、残酷と無垢、日常と異界が一瞬で入れ替わる、その一瞬の美しさに心をつかまれる。 まるで生と死が切り絵みたいに左右対称に並んでいて、そのちょうど折り目に自分が立っているようだった。 - 1900年1月1日
 モヤモヤする正義ベンジャミン・クリッツァー読み終わったトーン・ポリシング、マイクロアグレッション、適応的選好形成など、初めて知る言葉も多かった。 なるほどと思う部分と、うーん…と引っかかる部分がどちらもあり、その分考えながら読めた。 「表現の自由は大切だが攻撃的な表現は許容できない」「少数派に配慮すべきだが、多数派が無視されるのもおかしい」——多くの人が揺れるこうした正義の間で、どのように社会の規範を考えるか、という内容だった。 筆者はその指針として公共的理性の重要性を挙げ、そこから各論(キャンセル・カルチャー、弱者男性論など)を検討していく。 明快に割り切れないテーマを少し冷静に見つめ直せる一冊。
モヤモヤする正義ベンジャミン・クリッツァー読み終わったトーン・ポリシング、マイクロアグレッション、適応的選好形成など、初めて知る言葉も多かった。 なるほどと思う部分と、うーん…と引っかかる部分がどちらもあり、その分考えながら読めた。 「表現の自由は大切だが攻撃的な表現は許容できない」「少数派に配慮すべきだが、多数派が無視されるのもおかしい」——多くの人が揺れるこうした正義の間で、どのように社会の規範を考えるか、という内容だった。 筆者はその指針として公共的理性の重要性を挙げ、そこから各論(キャンセル・カルチャー、弱者男性論など)を検討していく。 明快に割り切れないテーマを少し冷静に見つめ直せる一冊。 - 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 天使佐藤亜紀読み終わった生まれながらに特殊な「感覚」を持ったジェルジュはウィーンの権力者に拾われ、諜報部員にされる。第一次大戦前夜のヨーロッパで、同じ「感覚」を持った諜報部員同士が繰り広げる壮絶なサイキック・ウォーズの結末は。 って話で、かなり厨二心くすぐられる。 ただ、感覚や舞台設定について細かな説明はない。 それこそ感覚で楽しむか、第一次世界大戦について知っていればより面白いかも。 表紙が白で、見返しが黒っていうデザインも好き。 数日経った今でもまだ余韻が残っている。
天使佐藤亜紀読み終わった生まれながらに特殊な「感覚」を持ったジェルジュはウィーンの権力者に拾われ、諜報部員にされる。第一次大戦前夜のヨーロッパで、同じ「感覚」を持った諜報部員同士が繰り広げる壮絶なサイキック・ウォーズの結末は。 って話で、かなり厨二心くすぐられる。 ただ、感覚や舞台設定について細かな説明はない。 それこそ感覚で楽しむか、第一次世界大戦について知っていればより面白いかも。 表紙が白で、見返しが黒っていうデザインも好き。 数日経った今でもまだ余韻が残っている。
読み込み中...