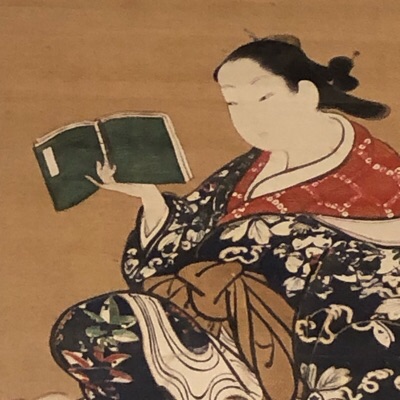
勝村巌
@katsumura
2025年11月4日

読み終わった
現代のインクルーシブ教育まで連綿と続く第二次大戦後から1980年までの「特別なニーズを持つ子ども」に対応する教育の歴史を調べた本。
占領下の日本に対して米国式の教育を導入させた第一次、第二次の米国使節団の報告書、日教組の「分けない教育」に関連する実践報告、文部省の中央教育審議会の答申や大阪府豊中中の実践報告などが細かく時系列で述べられている。
いわゆる障害児教育では可能な限り一般教室で障害のある子どもを包摂して分けない教育と養護学校に押し込めて分ける教育という2つの方向性があり、戦後直後は福祉制度が未分化だったこともあり分けない教育が志向され、高度経済成長とともに田中角栄内閣による1972年の「重度障害児の全員収容制度」の公約など分ける教育に舵取りがされたが、やがて普通教育から障害児を排除する意識への警鐘から、共同教育の機運が高まり、分けない教育に再び目が向けられた。
この本は1980年代頃までをカバーしているが、2024年の障害者差別解消法の施行など、社会でも広く多様性や共生的な社会が望まれている側面もあり、そういう点で「合理的配慮」の基本的な考え方に結びつく歴史が学べる本だった。


