
句読点
@books_qutoten
2025年11月22日
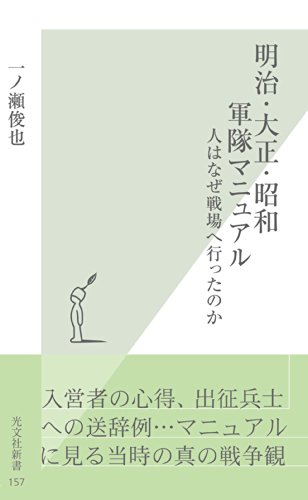
読み終わった
明治から1945年の敗戦まで、軍隊にまつわる「決まり文句」を多数収録した「軍隊マニュアル」が多数出版されていた。それらの内容を詳しく見ながら、戦時下の人々はどのように戦争を自分たち自身に納得させていたのかを探る内容。
今も昔も、国が国民に戦争を納得させる手口は変わっていない。国というか、国民自身も、自分自身に納得させないとやっていけなかったんだろうと、この本読んで思った。
高市政権がこのまま続けば、この本に出てくるような文言が繰り返されるのではないかと予想する。
日露戦争でギリギリのところで一応は「勝った」ことになり、本当はさまざまな幸運が重なった結果の辛うじての勝利にも関わらず、「圧倒的な戦力差がありながら日本が勝てたのは、日本軍の士気が高く、一人一人の能力が高かったからだ。最後は精神力が勝敗を決める、物質的に貧しくても精神力があれば勝てる」というクソみたいな言説が出来上がり、日中戦争、太平洋戦争でも繰り返され、無謀な戦争に突き進み、物資の補給が蔑ろにされ、戦死者の6割以上が餓死、戦病死という情けない結末を招いた。
この「精神力があれば勝てる」的な思考パターンは、いまだに続いていると思う。高市のあの馬車馬発言とか、午前3時から働いてるとか、そういう時代錯誤なポーズはまさにその表れではないか。
精神力はたしかに重要だが、それしか頼るものがないというのはいかがなものか。そんな状態になってる時点で負けは確定したようなものだ。別の道を探る方が遥かにマシだ。そうならないようにするのが段取りであり、リーダーのやるべきことではないか。
「マニュアル」通りに行動、発言することが「善良な国民」とされ、人々も自ら進んでその型にはまっていった。そこからはみ出そうとすれば「非国民」とされ、居場所を失った。個人だけでなく、近親者や擁護者も。典型的なムラ社会のやり口であるが、怖いのはそれが遠い過去のものとは言い切れずに、今も同じようなものが残り続けていること。軍隊でなくともあちこちでその片鱗は見ることができる。
戦争を避けるには、そうした「ミクロ」な戦争に注意し、そことはなるべく関わらずに、無効化できる場所で生きていく道を示すことではないか、と思った。

