

句読点
@books_qutoten
島根県出雲市の本屋句読点です。
- 2026年2月17日
 苦手から始める作文教室津村記久子図書館で一気読み。 小説家の津村さんが一から一緒に作文の書き方を教えてくれる。日々エッセイという作文の仕事もこなす津村さんだからこその実践的な内容でいろいろメモしたいことばかり。 小説家だから作文が得意というわけではなく、いつもすらすら書けたらいいのにと思いながら仕事をしているという。 津村さんはとにかくよくメモを取るそうである。 テレビで見かけたらレシピから、その日やることリストやら、天気のことやら、気になったニュース、部屋に小蝿が飛んでいること、などなんでも。その場でメモをしなければすぐに忘れてしまうようなことをメモしているという。そしてこのメモがなければ、津村さんは小説の仕事も、エッセイの仕事も全くできなくなるだろうという。 以下印象に残っている文章を引用。 書くことで、自分を支える。 自分もなるべくメモを取るようにしていきたい。 "自分の考えたことを書き留める行動は、自分という人間を内側から支えることにつながります。それは、自立という状態にもつながってます。その状態は、いつもいつも誰かにそばにいてもらって話を聞いてもらったり、話を整理してもらったり、話をほめてもらったり、話をほめてもらえないからといって怒ったり悲しんだりすることをせずにいられる状態でもあります。" p.47 「第4章 メモを取ろう」より。 "見栄を張れることも文章のよいところではありますが、文章を書くことは、さえない「本当のこと」「普通のこと」をみがいて光らせることも可能にします。さえない「本当のこと」「普通のこと」が光って見えるということは、「本当のこと」「普通のこと」であっても「それでいいんだ」と思えることでもあります。わたしは文章を書くことを通して、「普通のこと」も本当であればそれほど悪くないんだと思えるようになりました。" p.73「第6章 伝わる文章ってどんなもの?」より。
苦手から始める作文教室津村記久子図書館で一気読み。 小説家の津村さんが一から一緒に作文の書き方を教えてくれる。日々エッセイという作文の仕事もこなす津村さんだからこその実践的な内容でいろいろメモしたいことばかり。 小説家だから作文が得意というわけではなく、いつもすらすら書けたらいいのにと思いながら仕事をしているという。 津村さんはとにかくよくメモを取るそうである。 テレビで見かけたらレシピから、その日やることリストやら、天気のことやら、気になったニュース、部屋に小蝿が飛んでいること、などなんでも。その場でメモをしなければすぐに忘れてしまうようなことをメモしているという。そしてこのメモがなければ、津村さんは小説の仕事も、エッセイの仕事も全くできなくなるだろうという。 以下印象に残っている文章を引用。 書くことで、自分を支える。 自分もなるべくメモを取るようにしていきたい。 "自分の考えたことを書き留める行動は、自分という人間を内側から支えることにつながります。それは、自立という状態にもつながってます。その状態は、いつもいつも誰かにそばにいてもらって話を聞いてもらったり、話を整理してもらったり、話をほめてもらったり、話をほめてもらえないからといって怒ったり悲しんだりすることをせずにいられる状態でもあります。" p.47 「第4章 メモを取ろう」より。 "見栄を張れることも文章のよいところではありますが、文章を書くことは、さえない「本当のこと」「普通のこと」をみがいて光らせることも可能にします。さえない「本当のこと」「普通のこと」が光って見えるということは、「本当のこと」「普通のこと」であっても「それでいいんだ」と思えることでもあります。わたしは文章を書くことを通して、「普通のこと」も本当であればそれほど悪くないんだと思えるようになりました。" p.73「第6章 伝わる文章ってどんなもの?」より。 - 2026年2月17日
 チャンスユリ・シュルヴィッツ,原田勝読み終わった名作絵本『よあけ』などの作者である、ユリ・シュルヴィッツ(本来の発音ではウリ・シュルヴィッツの方が近いため、作中では「ウリ」と表記)が、幼少期を振り返って綴った一冊。 ウリはポーランドで生まれ、一家はユダヤ人だったため、ナチスの迫害から逃れるためポーランドからソ連に逃れた。その難民生活の中で味わった様々な苦痛。慢性的な食糧不足。難民に対する迫害、病気など、読んでいると本当に苦しくなる。 しかし、その苦しい生活の中でもウリを救ったのは絵を描くことだったという。絵を描くことで自分を支えたウリはその後フランスを経て、アメリカに移り住み、絵本作家として活躍していくことになる。 この物語の始まりはウリ4歳の頃。1939年にナチスがポーランドに侵攻を開始し、第二次世界大戦が始まった時。それから終戦まで6年間、ウリが10歳になる頃までのことを中心に描かれる。ちいさな子どもの目線に立つことで見えることがある。あとがきで明らかになることだが、父が残していた手記も参照しながら、この物語を作ったという。 図書館の児童書コーナーで見つけたけど、大人にこそ読んでほしい一冊。児童書なのでとても読みやすいし、一つ一つのエピソードが細かく分けて日記のように綴られていくのでどんどん読める。絵本作家らしく、イラストも豊富。冒頭のエピソード、住んでいたアパートが爆撃され、階段の途中に大穴が空き、梯子をそろそろと伝いながら降りるエピソード、そして中庭で配給を待つ人たちのもとに降りかかった悲劇から、一気に引き込まれる。 ユリ・シュルヴィッツの絵本もこの本を読んでから読むと違う印象を受けるかもしれない。
チャンスユリ・シュルヴィッツ,原田勝読み終わった名作絵本『よあけ』などの作者である、ユリ・シュルヴィッツ(本来の発音ではウリ・シュルヴィッツの方が近いため、作中では「ウリ」と表記)が、幼少期を振り返って綴った一冊。 ウリはポーランドで生まれ、一家はユダヤ人だったため、ナチスの迫害から逃れるためポーランドからソ連に逃れた。その難民生活の中で味わった様々な苦痛。慢性的な食糧不足。難民に対する迫害、病気など、読んでいると本当に苦しくなる。 しかし、その苦しい生活の中でもウリを救ったのは絵を描くことだったという。絵を描くことで自分を支えたウリはその後フランスを経て、アメリカに移り住み、絵本作家として活躍していくことになる。 この物語の始まりはウリ4歳の頃。1939年にナチスがポーランドに侵攻を開始し、第二次世界大戦が始まった時。それから終戦まで6年間、ウリが10歳になる頃までのことを中心に描かれる。ちいさな子どもの目線に立つことで見えることがある。あとがきで明らかになることだが、父が残していた手記も参照しながら、この物語を作ったという。 図書館の児童書コーナーで見つけたけど、大人にこそ読んでほしい一冊。児童書なのでとても読みやすいし、一つ一つのエピソードが細かく分けて日記のように綴られていくのでどんどん読める。絵本作家らしく、イラストも豊富。冒頭のエピソード、住んでいたアパートが爆撃され、階段の途中に大穴が空き、梯子をそろそろと伝いながら降りるエピソード、そして中庭で配給を待つ人たちのもとに降りかかった悲劇から、一気に引き込まれる。 ユリ・シュルヴィッツの絵本もこの本を読んでから読むと違う印象を受けるかもしれない。 - 2026年1月31日
 中村哲濱野京子読み終わった図書館で借りてきて一気に読了。 NHKオンデマンドで新プロジェクトXの中村哲の回を観て、前々から中村さんの本は読みたいと思っていたが、いよいよ読もうと思い、まずざっくりと知りたかったので、児童書コーナーに行って、伝記を借りてきた。2019年に亡くなったばかりの方がもう伝記になるのは早すぎる気もするが、(著者の方もそう書いていた)彼の業績や人柄など考えれば当然だ。しかしだからこそ余計にもっと長生きして活躍して欲しかった。 ちょっと内容から逸れるが、小学生向けの伝記の本って素晴らしいなと思う。その人のことをざっくりと知りたいという時に、こんなに便利な本はない。よくまとまってるし、本当に予備知識ゼロで読める。文字も大きいし、写真資料なども豊富で読みやすい。とにかく読みやすい。だけど内容はしっかり校閲が入っていて正確。児童書の伝記コーナーの本を片っ端から読むというのもやってみたい。大人こそそれをやるべきだと思う。児童書を舐めてはいけないと思う。 中身に戻ると、中村哲さんの原点には、昆虫好きな少年の心がある。昆虫を通った人は環境問題にも敏感になるし、自然が好きになるし、多様性の重要さも肌身で感じるのだろう。それが原点にあるから、人間中心的な見方から距離をとって考えることができる。また人間も地球で生きるさまざまな生物群の中の一つの種族という認識があるからか、国籍や宗教などの壁を乗り越えて、「人間」という視点であらゆる人と接することができるのではないか。 母方の伯父が火野葦平だったというのはこの本で初めて知った。中村哲の文才はここからきているのかも。幼い頃から火野葦平に可愛がられて、本もよく読んでいたらしい。本を読みすぎて小さい頃のあだ名は「ご隠居さん」だったらしい。 ペシャワールにいくことになったのは37歳の時。用水路建設を始めたのは56歳頃。それまでは無医者地域に診療所を開く活動をしていた。 ソ連やアメリカなどの大国に翻弄され続け、中村さんの活動もその動きに翻弄され続ける。スタッフがテロ組織に連行され殺害されたり、盗みがあったり、さまざまなことに翻弄されながらも「命を何よりも大切に」という指針はブレず、活動を続ける。その活動を支援する輪もどんどん広がる。 この本で中村哲さんの人生の概要は大掴みに知ることができたので、中村哲さん自身の本も読んでいきたい。
中村哲濱野京子読み終わった図書館で借りてきて一気に読了。 NHKオンデマンドで新プロジェクトXの中村哲の回を観て、前々から中村さんの本は読みたいと思っていたが、いよいよ読もうと思い、まずざっくりと知りたかったので、児童書コーナーに行って、伝記を借りてきた。2019年に亡くなったばかりの方がもう伝記になるのは早すぎる気もするが、(著者の方もそう書いていた)彼の業績や人柄など考えれば当然だ。しかしだからこそ余計にもっと長生きして活躍して欲しかった。 ちょっと内容から逸れるが、小学生向けの伝記の本って素晴らしいなと思う。その人のことをざっくりと知りたいという時に、こんなに便利な本はない。よくまとまってるし、本当に予備知識ゼロで読める。文字も大きいし、写真資料なども豊富で読みやすい。とにかく読みやすい。だけど内容はしっかり校閲が入っていて正確。児童書の伝記コーナーの本を片っ端から読むというのもやってみたい。大人こそそれをやるべきだと思う。児童書を舐めてはいけないと思う。 中身に戻ると、中村哲さんの原点には、昆虫好きな少年の心がある。昆虫を通った人は環境問題にも敏感になるし、自然が好きになるし、多様性の重要さも肌身で感じるのだろう。それが原点にあるから、人間中心的な見方から距離をとって考えることができる。また人間も地球で生きるさまざまな生物群の中の一つの種族という認識があるからか、国籍や宗教などの壁を乗り越えて、「人間」という視点であらゆる人と接することができるのではないか。 母方の伯父が火野葦平だったというのはこの本で初めて知った。中村哲の文才はここからきているのかも。幼い頃から火野葦平に可愛がられて、本もよく読んでいたらしい。本を読みすぎて小さい頃のあだ名は「ご隠居さん」だったらしい。 ペシャワールにいくことになったのは37歳の時。用水路建設を始めたのは56歳頃。それまでは無医者地域に診療所を開く活動をしていた。 ソ連やアメリカなどの大国に翻弄され続け、中村さんの活動もその動きに翻弄され続ける。スタッフがテロ組織に連行され殺害されたり、盗みがあったり、さまざまなことに翻弄されながらも「命を何よりも大切に」という指針はブレず、活動を続ける。その活動を支援する輪もどんどん広がる。 この本で中村哲さんの人生の概要は大掴みに知ることができたので、中村哲さん自身の本も読んでいきたい。 - 2026年1月24日
 水中の哲学者たち永井玲衣読み終わった少しずつゆっくり読んでいた本をようやく読了。 噂に違わず本当にいい本でした。 普通だったら見逃してしまうような日常の些細な出来事、ポロっと出た誰かの一言、忘れかけていた記憶、気を抜けばするすると自分の手から逃れてしまうようなものに、迷いながら、戸惑いながら言葉で輪郭を与えていくような文章。 上から目線ではなく、一緒の地平にたちながら、まさに哲学対話そのものを体験できるような本。 気が抜けているような文章かと思いきや、切れ味はかなり鋭くて、言葉も的確で、自分ではうまくモヤモヤして言葉にならないようなことも、比喩を巧みに用いながら、モヤモヤしたものに言葉で輪郭を与えてくれる。しかしその輪郭はカッチリしたものではなくて常に揺れ動いていて、ちょっと視点をずらすと全く違う姿を見せるようなものでもあり、そのことに対しても一緒に驚きながら、それでも問うことをやめない。哲学の入り口としてとても優れた一冊だと思う。 「哲学はすべてのひとに関係する。すべてのことにかかわることができる。重要でないと思われているものも、哲学対話では考えることができる。むしろ、普段は忘れられているようなものや、問われもしないようなことに耳を澄ませる。そしてまた同時に、議論の場で取るに足らないとされ、話を聞かなくてもいいとみなされているひとの話にも耳を澄ませる。人間を、ただの血の詰まった袋ではなく、宇宙の質量を持つサイコロとして扱う。ともに知を愛するために、本当の意味でともに哲学をするために。」p.88 「こわい」より。
水中の哲学者たち永井玲衣読み終わった少しずつゆっくり読んでいた本をようやく読了。 噂に違わず本当にいい本でした。 普通だったら見逃してしまうような日常の些細な出来事、ポロっと出た誰かの一言、忘れかけていた記憶、気を抜けばするすると自分の手から逃れてしまうようなものに、迷いながら、戸惑いながら言葉で輪郭を与えていくような文章。 上から目線ではなく、一緒の地平にたちながら、まさに哲学対話そのものを体験できるような本。 気が抜けているような文章かと思いきや、切れ味はかなり鋭くて、言葉も的確で、自分ではうまくモヤモヤして言葉にならないようなことも、比喩を巧みに用いながら、モヤモヤしたものに言葉で輪郭を与えてくれる。しかしその輪郭はカッチリしたものではなくて常に揺れ動いていて、ちょっと視点をずらすと全く違う姿を見せるようなものでもあり、そのことに対しても一緒に驚きながら、それでも問うことをやめない。哲学の入り口としてとても優れた一冊だと思う。 「哲学はすべてのひとに関係する。すべてのことにかかわることができる。重要でないと思われているものも、哲学対話では考えることができる。むしろ、普段は忘れられているようなものや、問われもしないようなことに耳を澄ませる。そしてまた同時に、議論の場で取るに足らないとされ、話を聞かなくてもいいとみなされているひとの話にも耳を澄ませる。人間を、ただの血の詰まった袋ではなく、宇宙の質量を持つサイコロとして扱う。ともに知を愛するために、本当の意味でともに哲学をするために。」p.88 「こわい」より。 - 2026年1月19日
 華氏451度〔新訳版〕レイ・ブラッドベリ,伊藤典夫,小野田和子読み終わった本を読むことも持つことも禁止されている近未来を描いたディストピア小説の金字塔的作品。今月の一冊読書会の課題本。前々から読んでみたかった作品の一つで今回ようやく読めた。 初版は1953年だから、今から70年以上も前。ブラッドベリは執筆当時、4、50年先の未来を想定して書いたというが、2026年の今、そのさらに先の未来を生きている。当時からしたらもう自分は未来社会に生きる未来人だ。 そして、この小説で書かれているディストピアのさらに上をいくような現象がすでにいろいろ起きている気がしてならないとこの本を読みながら思った。 流石に、本を持っているだけで家ごと焼かれることは今のところないが、たとえばトランプ政権下のアメリカでは、2023−24年で、年間4000冊もの児童向けの本が禁書扱いにされて図書館から消されたという。(『絵本戦争』堂本かおる) また、近未来として描かれている社会にはスマホもなければ、AIもない。デジタル広告もなければ、GPSなどもない。今からするとかなり古い技術がそのまま使われている未来、という感じを受ける。だから、主人公の妻が壁に流されるテレビ番組の中での劇に耽溺しているという設定は、今だったらまだかわいいものに感じられてしまう。今はもっとひどい。ちいさな携帯端末に延々と流れてくるショート動画をずっと見続けてしまう人、生成AIが作ったデマ動画を本物と信じて疑わない人も増えてきた。この作品で「巻貝」と呼ばれるイヤホンはもはや誰でもが使っていて、しかもワイヤレスのものが大半。VRゴーグルまで生まれて、寝る時もそれをつけている人もいるらしい。アバターを作って、現実世界とは違う世界で生きる人たち。もはやこれはブラッドベリの描いた近未来を遥かに超えることが起きていると思わざるを得ない。 話の筋はかなりシンプルで、何の疑いも持たずに生きてきた主人公モンターグが、クラリスや、自分で火をつけに行った家の老女のことがきっかけで自分の仕事、この社会のことについて疑問を持ち始め、本には何が書かれてあるのか気になり始め、次第に妻との間の溝が深まっていき、上司からは怪しまれ始め、いよいよそれまでいた世界から抜け出し、新たな人生を模索し始める、というもの。 第3部は急展開だが、グレンジャーの言葉が重い。かつて本が当たり前にあった時代でも、人々はその本を有効に使うことができなかった。それは中身をちゃんと記憶しようとしなかったからではないか、人間は不死鳥とは違って、過去の愚かな行いを記録し、記憶を伝えることができるはずだが、それをしてこなかった。死者に唾を吐きかけるようなことばかりしてきたと。 今世界中で反知性主義的な動きが活発になり、権威主義的体質の人が増えてきた。過去それが何をもたらしたかの記録も十分に残されているというのに、学ばない人たちの方が多い。これでは、本を燃やす必要もなく、初めから、大衆の方から本を読まなくなっていったのだ、物事を複雑な物事の連関の中で理解する態度が失われ、短く、ショートに単純化した理解、劇的で感情に訴えかけるような目立つやり方が好まれ、地味で誠実な知性の営みは軽んじられる、というのは今まさに起きていることではないか。 印象的な文章を以下メモ的に。 「本のうしろには、かならず人間がいるって気がついたんだ。本を書くためには、ものを考えなくちゃならない。考えたことを紙に書き写すには長い時間がかかる。ところが、ぼくはいままでそんなことはぜんぜん考えていなかった」モンターグp.88 「ひとつの問題に二つの側面があるなんてことは口が裂けてもいうな。ひとつだけ教えておけばいい。もっといいのは、何も教えないことだ。戦争なんてものがあることは忘れさせておけばいいんだ。たとえ政府が頭でっかちで、税金をふんだくることしか考えていない役立たずでも、国民が思い悩むような政府よりはましだ。平和がいちばんなんだ、モンターグ。国民には記憶力コンテストでもあてがっておけばいい。ポップスの歌詞だの、州都の名前だの、アイオワの去年のトウモロコシ収穫量だのをどれだけ憶えているか、競わせておけばいいんだ。不燃性のデータをめいっぱい詰めこんでやれ、もう満腹だと感じるまで“事実“をぎっしり詰めこんでやれ。ただし国民が、自分はなんと輝かしい情報収集能力を持っていることか、と感じるような事実を詰めこむんだ。そうしておけば、みんな、自分の頭で考えているような気になる。動かなくても動いているような感覚が得られる。それでみんなしあわせになれる。なぜかというと、そういうたぐいの事実は変化しないからだ。哲学だの社会学だの、物事を関連づけて考えるような、つかみどころのないものは与えてはならない。そんなものを齧ったら、待っているのは憂鬱だ。」ベイティーp.103 「いいかね、昇火士などほとんど必要ないのだよ。大衆そのものが自発的に、読むのをやめてしまったのだ。」フェーバーp.146 「近ごろはみんな、自分の身にはなにも起こらないと思っている。そう思いこんでいる。他人は死んでも、自分は無事。なんの因果関係も、なんの責任もない、とな。ところがあるんだ。だが、そんな話はやめておこう、な?因果関係がわかったときには手遅れだ、そうだろ、モンターグ?」ベイティーp.194 「人は死ぬとき、なにかを残していかねばならない、と祖父はいっていた。子どもでも、本でも、絵でも、家でも、自作の塀でも、手づくりの靴でもいい。草花を植えた庭でもいい。なにか、死んだときに魂の行き場所になるような、なんらかのかたちで手をかけたものを残すのだ。そうすれば、誰かがお前が植えた樹や花を見れば、お前はそこにいることになる。なにをしてもいい、と祖父はいっていたな。お前が手をふれる前の姿とはちがうものに、お前が手を放したあともお前らしさが残っているものに変えることができれば、なにをしてもいいと。ただ芝を刈るだけの人間と、庭師とのちがいは、ものにどうふれるかのちがいだ、ともいっていた。芝を刈るだけの人間はそこにいないも同然だが、庭師は終生、そこに存在する、とね」グレンジャーp.261
華氏451度〔新訳版〕レイ・ブラッドベリ,伊藤典夫,小野田和子読み終わった本を読むことも持つことも禁止されている近未来を描いたディストピア小説の金字塔的作品。今月の一冊読書会の課題本。前々から読んでみたかった作品の一つで今回ようやく読めた。 初版は1953年だから、今から70年以上も前。ブラッドベリは執筆当時、4、50年先の未来を想定して書いたというが、2026年の今、そのさらに先の未来を生きている。当時からしたらもう自分は未来社会に生きる未来人だ。 そして、この小説で書かれているディストピアのさらに上をいくような現象がすでにいろいろ起きている気がしてならないとこの本を読みながら思った。 流石に、本を持っているだけで家ごと焼かれることは今のところないが、たとえばトランプ政権下のアメリカでは、2023−24年で、年間4000冊もの児童向けの本が禁書扱いにされて図書館から消されたという。(『絵本戦争』堂本かおる) また、近未来として描かれている社会にはスマホもなければ、AIもない。デジタル広告もなければ、GPSなどもない。今からするとかなり古い技術がそのまま使われている未来、という感じを受ける。だから、主人公の妻が壁に流されるテレビ番組の中での劇に耽溺しているという設定は、今だったらまだかわいいものに感じられてしまう。今はもっとひどい。ちいさな携帯端末に延々と流れてくるショート動画をずっと見続けてしまう人、生成AIが作ったデマ動画を本物と信じて疑わない人も増えてきた。この作品で「巻貝」と呼ばれるイヤホンはもはや誰でもが使っていて、しかもワイヤレスのものが大半。VRゴーグルまで生まれて、寝る時もそれをつけている人もいるらしい。アバターを作って、現実世界とは違う世界で生きる人たち。もはやこれはブラッドベリの描いた近未来を遥かに超えることが起きていると思わざるを得ない。 話の筋はかなりシンプルで、何の疑いも持たずに生きてきた主人公モンターグが、クラリスや、自分で火をつけに行った家の老女のことがきっかけで自分の仕事、この社会のことについて疑問を持ち始め、本には何が書かれてあるのか気になり始め、次第に妻との間の溝が深まっていき、上司からは怪しまれ始め、いよいよそれまでいた世界から抜け出し、新たな人生を模索し始める、というもの。 第3部は急展開だが、グレンジャーの言葉が重い。かつて本が当たり前にあった時代でも、人々はその本を有効に使うことができなかった。それは中身をちゃんと記憶しようとしなかったからではないか、人間は不死鳥とは違って、過去の愚かな行いを記録し、記憶を伝えることができるはずだが、それをしてこなかった。死者に唾を吐きかけるようなことばかりしてきたと。 今世界中で反知性主義的な動きが活発になり、権威主義的体質の人が増えてきた。過去それが何をもたらしたかの記録も十分に残されているというのに、学ばない人たちの方が多い。これでは、本を燃やす必要もなく、初めから、大衆の方から本を読まなくなっていったのだ、物事を複雑な物事の連関の中で理解する態度が失われ、短く、ショートに単純化した理解、劇的で感情に訴えかけるような目立つやり方が好まれ、地味で誠実な知性の営みは軽んじられる、というのは今まさに起きていることではないか。 印象的な文章を以下メモ的に。 「本のうしろには、かならず人間がいるって気がついたんだ。本を書くためには、ものを考えなくちゃならない。考えたことを紙に書き写すには長い時間がかかる。ところが、ぼくはいままでそんなことはぜんぜん考えていなかった」モンターグp.88 「ひとつの問題に二つの側面があるなんてことは口が裂けてもいうな。ひとつだけ教えておけばいい。もっといいのは、何も教えないことだ。戦争なんてものがあることは忘れさせておけばいいんだ。たとえ政府が頭でっかちで、税金をふんだくることしか考えていない役立たずでも、国民が思い悩むような政府よりはましだ。平和がいちばんなんだ、モンターグ。国民には記憶力コンテストでもあてがっておけばいい。ポップスの歌詞だの、州都の名前だの、アイオワの去年のトウモロコシ収穫量だのをどれだけ憶えているか、競わせておけばいいんだ。不燃性のデータをめいっぱい詰めこんでやれ、もう満腹だと感じるまで“事実“をぎっしり詰めこんでやれ。ただし国民が、自分はなんと輝かしい情報収集能力を持っていることか、と感じるような事実を詰めこむんだ。そうしておけば、みんな、自分の頭で考えているような気になる。動かなくても動いているような感覚が得られる。それでみんなしあわせになれる。なぜかというと、そういうたぐいの事実は変化しないからだ。哲学だの社会学だの、物事を関連づけて考えるような、つかみどころのないものは与えてはならない。そんなものを齧ったら、待っているのは憂鬱だ。」ベイティーp.103 「いいかね、昇火士などほとんど必要ないのだよ。大衆そのものが自発的に、読むのをやめてしまったのだ。」フェーバーp.146 「近ごろはみんな、自分の身にはなにも起こらないと思っている。そう思いこんでいる。他人は死んでも、自分は無事。なんの因果関係も、なんの責任もない、とな。ところがあるんだ。だが、そんな話はやめておこう、な?因果関係がわかったときには手遅れだ、そうだろ、モンターグ?」ベイティーp.194 「人は死ぬとき、なにかを残していかねばならない、と祖父はいっていた。子どもでも、本でも、絵でも、家でも、自作の塀でも、手づくりの靴でもいい。草花を植えた庭でもいい。なにか、死んだときに魂の行き場所になるような、なんらかのかたちで手をかけたものを残すのだ。そうすれば、誰かがお前が植えた樹や花を見れば、お前はそこにいることになる。なにをしてもいい、と祖父はいっていたな。お前が手をふれる前の姿とはちがうものに、お前が手を放したあともお前らしさが残っているものに変えることができれば、なにをしてもいいと。ただ芝を刈るだけの人間と、庭師とのちがいは、ものにどうふれるかのちがいだ、ともいっていた。芝を刈るだけの人間はそこにいないも同然だが、庭師は終生、そこに存在する、とね」グレンジャーp.261 - 2026年1月6日
 読み終わった去年の9月に一冊読書会で『君たちはどう生きるか』を読んだので、池上さんはどのように解説しているのか気になって一気に読んだ。 池上彰さんによるある中学校での特別授業の内容をまとめたもの。放送は無く、書籍のみの特別編。 もう一度『君たちはどう生きるか』を読み直したくなった。 世界情勢がかなり不安定になってきている今こそ、この本をもう一度深く読み込む必要があると思う。 『君たちはどう生きるか』が書かれた時代背景や著者の思惑などを池上さんなりに読み解きながら、「こう考えなさい」と押し付けるのではなく、「池上はこう考えるが、それを踏まえて君たちはどう考えるか?」を大事にしている様子が伝わってきて、とても良かった。 それから、いい本を読むとはどういうことか、なぜ古典と呼ばれる作品を読むべきなのか、読んだだけではダメで、読み終わった後に自分の頭でちゃんとその本に書かれてあったことを咀嚼する時間を持つこと、どう感じたか、どう思ったか、をまとめる時間を持つこと、感想を人に話すことなどもサボっていてはダメだなと改めて思う。 考えることの重要さを改めて再認識させられた。こんな授業を自分も受けてみたかった。が、30過ぎた大人になっても十分面白かったので、いつからでも何回でも遅くはない。中学生以上の誰でもがこうした基本に立ち返ってみることはとても大事なことだ。 ところどころで中学生たちから質問をしてもらったり、意見を言ってもらったりするところもちゃんと入っていて、大人顔負けの読み解きをしている子たちばかりで、約10年後の今は大学院生になっている子もいれば社会人になっている子もいるだろうし、この時の授業がどんなふうにその後彼らの人生に作用していったかも知りたい。 この授業では言及されていなかったが、最後の庭の日陰に生えていた花をコペルくんが日向に植え替えてあげるシーンについて、どう解釈するかで、読書会やった時結構盛り上がったのを覚えているけど、今読み直したらどう感じるだろうか。この子たちや池上さんはどう読んでいるのだろうか、聞いてみたい。 池上さんが中学生にあるシーンについての意見を聞くところで、みんなが言っている「いま」とか「昔」って結構みんなバラバラの意味で使っているんじゃないか。同じ言葉を使っていても、それぞれが思っているその言葉の定義が曖昧だと議論が成り立たなくなってしまうから、議論をするときにはきちんと「いま」や「昔」が具体的にいつのことか確認した方がいい、というアドバイスをしていて、これはとても大事なことだと思った。 SNS上の情報などは特に、「いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どのように」の5W1Hを意識して確認していこうと思った。基本中の基本だけど、うっかり忘れてしまいがち。いやSNS上だけでなく、日常の会話でもそう。5W1H大事。
読み終わった去年の9月に一冊読書会で『君たちはどう生きるか』を読んだので、池上さんはどのように解説しているのか気になって一気に読んだ。 池上彰さんによるある中学校での特別授業の内容をまとめたもの。放送は無く、書籍のみの特別編。 もう一度『君たちはどう生きるか』を読み直したくなった。 世界情勢がかなり不安定になってきている今こそ、この本をもう一度深く読み込む必要があると思う。 『君たちはどう生きるか』が書かれた時代背景や著者の思惑などを池上さんなりに読み解きながら、「こう考えなさい」と押し付けるのではなく、「池上はこう考えるが、それを踏まえて君たちはどう考えるか?」を大事にしている様子が伝わってきて、とても良かった。 それから、いい本を読むとはどういうことか、なぜ古典と呼ばれる作品を読むべきなのか、読んだだけではダメで、読み終わった後に自分の頭でちゃんとその本に書かれてあったことを咀嚼する時間を持つこと、どう感じたか、どう思ったか、をまとめる時間を持つこと、感想を人に話すことなどもサボっていてはダメだなと改めて思う。 考えることの重要さを改めて再認識させられた。こんな授業を自分も受けてみたかった。が、30過ぎた大人になっても十分面白かったので、いつからでも何回でも遅くはない。中学生以上の誰でもがこうした基本に立ち返ってみることはとても大事なことだ。 ところどころで中学生たちから質問をしてもらったり、意見を言ってもらったりするところもちゃんと入っていて、大人顔負けの読み解きをしている子たちばかりで、約10年後の今は大学院生になっている子もいれば社会人になっている子もいるだろうし、この時の授業がどんなふうにその後彼らの人生に作用していったかも知りたい。 この授業では言及されていなかったが、最後の庭の日陰に生えていた花をコペルくんが日向に植え替えてあげるシーンについて、どう解釈するかで、読書会やった時結構盛り上がったのを覚えているけど、今読み直したらどう感じるだろうか。この子たちや池上さんはどう読んでいるのだろうか、聞いてみたい。 池上さんが中学生にあるシーンについての意見を聞くところで、みんなが言っている「いま」とか「昔」って結構みんなバラバラの意味で使っているんじゃないか。同じ言葉を使っていても、それぞれが思っているその言葉の定義が曖昧だと議論が成り立たなくなってしまうから、議論をするときにはきちんと「いま」や「昔」が具体的にいつのことか確認した方がいい、というアドバイスをしていて、これはとても大事なことだと思った。 SNS上の情報などは特に、「いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どのように」の5W1Hを意識して確認していこうと思った。基本中の基本だけど、うっかり忘れてしまいがち。いやSNS上だけでなく、日常の会話でもそう。5W1H大事。 - 2026年1月5日
- 2026年1月3日
 自分の中に毒を持て<新装版>岡本太郎読み終わった毎年正月に読み返すことにしている本。今年も読み終えた。読み返すたびに新たな発見がある。 人間は本来、無目的的に生まれてきて、生きていく上でも、目的的なことばかりではなく、無目的的な、無償の、無用の、なぜだかわからないけど無性にやりたくなってしまう何か、人間が人間である所以のところのものなしでは、人間らしく生きていくことができない。しかし近代以降、そうした人間的な側面を忘れて、あるいはそうしたことに向き合う時間や余裕を与えないほど、目的的に、効率的に資本を蓄え、物質的に豊かになることを目指してきすぎたのではないか、そうすることによって「人間」がほかでもない人間自身によって喪失させられているのではないか、という問題意識のもとに、全ての人が人間らしく生きることができる社会の実現のために芸術や言論を通して人々に訴え続けたのが岡本太郎だった。彼の主張は、没後30年が過ぎた今もまったく色褪せることなく、むしろますますその必要性が高まっているように感じる。 最後の方で主張されている、「政治、経済、芸術(人間)の三権分立」という考え方はこれからますます重要になってくるだろう。 新年に読むといつもピシッと身が引き締まる思い。「生きている」という実感を得られる時間を多く持ちたい。しかし同時にそればかりを求めるのもまた目的的に生きることになってしまうだろうから、適度に息抜き、休息、リラックス、力を抜くことも忘れずに。
自分の中に毒を持て<新装版>岡本太郎読み終わった毎年正月に読み返すことにしている本。今年も読み終えた。読み返すたびに新たな発見がある。 人間は本来、無目的的に生まれてきて、生きていく上でも、目的的なことばかりではなく、無目的的な、無償の、無用の、なぜだかわからないけど無性にやりたくなってしまう何か、人間が人間である所以のところのものなしでは、人間らしく生きていくことができない。しかし近代以降、そうした人間的な側面を忘れて、あるいはそうしたことに向き合う時間や余裕を与えないほど、目的的に、効率的に資本を蓄え、物質的に豊かになることを目指してきすぎたのではないか、そうすることによって「人間」がほかでもない人間自身によって喪失させられているのではないか、という問題意識のもとに、全ての人が人間らしく生きることができる社会の実現のために芸術や言論を通して人々に訴え続けたのが岡本太郎だった。彼の主張は、没後30年が過ぎた今もまったく色褪せることなく、むしろますますその必要性が高まっているように感じる。 最後の方で主張されている、「政治、経済、芸術(人間)の三権分立」という考え方はこれからますます重要になってくるだろう。 新年に読むといつもピシッと身が引き締まる思い。「生きている」という実感を得られる時間を多く持ちたい。しかし同時にそればかりを求めるのもまた目的的に生きることになってしまうだろうから、適度に息抜き、休息、リラックス、力を抜くことも忘れずに。 - 2026年1月2日
 生きるとは、自分の物語をつくること小川洋子,河合隼雄読み終わったとても面白かったし、大事な言葉にもたくさん出会うことができた一冊。 小川洋子さんの代表作『博士の愛した数式』を軸に対話が進んでゆく。(この小説を読んだ後でこの対談を読むことを強くお勧めする。) 小川さんも明確に意識していなかったこと、偶然と言ってもいいことが対談の中からどんどん出て来て、物語というのは作者が全知全能の神のように全てを操っているわけではなく、すでにある物語を作者が拾って来て多くの人に伝えるものである、という小川さんの小説に対する姿勢についての話。それと河合隼雄さんが患者に向き合うときの姿勢も重なる。患者さんが治るときにも、いつも「ものすごくうまいこと」が起きるという。まさかというような角度から、そういう偶然的なことが、治癒のきっかけになるという。外から見ていると患者自身がその偶然を手繰り寄せて、治療者であるカウンセラーは何もしていないように見えるが、実際には患者の中にあるそうした偶然を呼び込む力のようなものを、あるいはそうした場所を見つけるための力があると信じて、ひたすらにそれを待ち続ける力量がないとそういうことは起きない。自分の力で、治療者の物語に無理やり載せようとしてもうまくいかないという。 大きな物語の中に、それぞれの個が置かれていて、だから個人的なことも大きな流れとどこかでは接続されているという意識。生きている時よりも、生まれる前と死んだ後の方が長いという意識を持つこと。 河合隼雄さんはこの対談の続きをする前に亡くなってしまって、小川洋子さんは一人で長いあとがきを書いているのだが、それがとてつもなく良かった。『博士の愛した数式』のルートという名前にまつわるエピソードも、河合さんとの対談の後で思い当たったという。その場にいないのに、人の中から物語が出て来てしまう。聞く力、というよりも、その人の前では勝手に物語が出て来てしまう、自分も思いもよらなかった言葉がでて来てしまう、そういう人だったんだなあとよくわかる。その感じ、なんか心当たりあるなと思ったら、ミヒャエル・エンデの『モモ』の主人公、モモもそういう人の話を本当に聞くことのできる稀有な存在として描かれていた。モモもその力によって物語でとても重要な役割を果たすことになる。『モモ』ももう一度読んでみたくなったし、たしか河合隼雄さんもどこかで『モモ』について書いていたはず。河合さんの本も色々読みたいし、小川洋子さんの本も色々読みたい。 以下引用。 "人間は矛盾しているから生きている。全く矛盾性のない、整合性のあるものは、生き物ではなくて機械です。 命というのはそもそも矛盾を孕んでいるものであって、その矛盾を生きている存在として、自分はこういうふうに矛盾してるんだとか、なぜ矛盾してるんだということを、意識して生きていくよりしかたないんじゃないかと、この頃思っています。そして、それをごまかさない。"p.105 "なぜあの時、偶然にも、あんなことが起こったのだろう、と私は時々考えます。考えても答えは出ません。自分が画策したり、小細工を施したりしたわけでもないのに、何かの働きによって物事が上手い具合に収まってゆく。あるいは、無関係だったはずの出来事が知らず知らずのうちに結びつき、想像を超えた発展を見せる。人生は物語みたいだなぁ、とふと思う。その瞬間、私は現実の本質に最も接近している実感を持ちます。現実と物語が反発するのではなく、境界線をなくして一つに溶け合った時こそ、大事な真実がよく見えてくるのです。"p.143 (二人のルート/少し長すぎるあとがき)
生きるとは、自分の物語をつくること小川洋子,河合隼雄読み終わったとても面白かったし、大事な言葉にもたくさん出会うことができた一冊。 小川洋子さんの代表作『博士の愛した数式』を軸に対話が進んでゆく。(この小説を読んだ後でこの対談を読むことを強くお勧めする。) 小川さんも明確に意識していなかったこと、偶然と言ってもいいことが対談の中からどんどん出て来て、物語というのは作者が全知全能の神のように全てを操っているわけではなく、すでにある物語を作者が拾って来て多くの人に伝えるものである、という小川さんの小説に対する姿勢についての話。それと河合隼雄さんが患者に向き合うときの姿勢も重なる。患者さんが治るときにも、いつも「ものすごくうまいこと」が起きるという。まさかというような角度から、そういう偶然的なことが、治癒のきっかけになるという。外から見ていると患者自身がその偶然を手繰り寄せて、治療者であるカウンセラーは何もしていないように見えるが、実際には患者の中にあるそうした偶然を呼び込む力のようなものを、あるいはそうした場所を見つけるための力があると信じて、ひたすらにそれを待ち続ける力量がないとそういうことは起きない。自分の力で、治療者の物語に無理やり載せようとしてもうまくいかないという。 大きな物語の中に、それぞれの個が置かれていて、だから個人的なことも大きな流れとどこかでは接続されているという意識。生きている時よりも、生まれる前と死んだ後の方が長いという意識を持つこと。 河合隼雄さんはこの対談の続きをする前に亡くなってしまって、小川洋子さんは一人で長いあとがきを書いているのだが、それがとてつもなく良かった。『博士の愛した数式』のルートという名前にまつわるエピソードも、河合さんとの対談の後で思い当たったという。その場にいないのに、人の中から物語が出て来てしまう。聞く力、というよりも、その人の前では勝手に物語が出て来てしまう、自分も思いもよらなかった言葉がでて来てしまう、そういう人だったんだなあとよくわかる。その感じ、なんか心当たりあるなと思ったら、ミヒャエル・エンデの『モモ』の主人公、モモもそういう人の話を本当に聞くことのできる稀有な存在として描かれていた。モモもその力によって物語でとても重要な役割を果たすことになる。『モモ』ももう一度読んでみたくなったし、たしか河合隼雄さんもどこかで『モモ』について書いていたはず。河合さんの本も色々読みたいし、小川洋子さんの本も色々読みたい。 以下引用。 "人間は矛盾しているから生きている。全く矛盾性のない、整合性のあるものは、生き物ではなくて機械です。 命というのはそもそも矛盾を孕んでいるものであって、その矛盾を生きている存在として、自分はこういうふうに矛盾してるんだとか、なぜ矛盾してるんだということを、意識して生きていくよりしかたないんじゃないかと、この頃思っています。そして、それをごまかさない。"p.105 "なぜあの時、偶然にも、あんなことが起こったのだろう、と私は時々考えます。考えても答えは出ません。自分が画策したり、小細工を施したりしたわけでもないのに、何かの働きによって物事が上手い具合に収まってゆく。あるいは、無関係だったはずの出来事が知らず知らずのうちに結びつき、想像を超えた発展を見せる。人生は物語みたいだなぁ、とふと思う。その瞬間、私は現実の本質に最も接近している実感を持ちます。現実と物語が反発するのではなく、境界線をなくして一つに溶け合った時こそ、大事な真実がよく見えてくるのです。"p.143 (二人のルート/少し長すぎるあとがき) - 2026年1月1日
 読み終わった2026年最初に読み終わった本。 この本を最初に読めて良かった。 タイトル通り、「この世界が終わっても」その先を生きていかねばならない自分にとって、今年は昨年から引き続く不穏な世界情勢、国内の腐った政治のまんまで年が明け、全くめでたい感じのない、不安な年越しだったのだが、この本を読むことでちょっとだけ見通しができたというか、自分が進むべき道を示してくれたような、そんな本だった。 イギリスのEU離脱のことから話が始まり、アレクサンダー大王の話やソ連解体直前のことまであっちこっちに話が飛んでいきながら、最後にはそれらの点同士が見事に繋がって、「まとめ」らしきものに到達する感じ。語りおろしなので最後まで一気に読めた。実際のインタビューは毎日5時間を4日間続けられたそうで、この本に収まっていない話もたくさん出てきたのだろうが、こうして一冊の本としてまとまったのはすごい。編集が大変だっただろうな。 「心のない論理」でも、「心の論理」でもなく、「心のある論理」を持ちながら、生きていきたい。 以下気になったところの引用。 "人工知能のAIなんかはさ、人間の考え方がそんなには明確でなくて、曖味なものに満ち満ちているってことと向き合うわけでしょ。 その曖味さをなんとかクリアしようと思ってるけど、曖昧さに関しては人間の方が上だね。 はっきりとは言い切れなくて曖味な、ちょっと揺らいでたりもするものを、文科系の言葉でいうと、「頭ではなくて情感で分かれ」になるんですね。だから、理科系は、文科系に近づかざるをえないんですね。"p.169 "未だに「大きなもの」を信じている人たちは、地球を巨大な円形だと思ってて、経済が「成長と拡大」を続けて、先へ行けば行くほど、その境界が広がって、パイの皮のように薄く伸びていくと思っているらしいけど、そんなものが永遠に伸び続けるはずはないわけでさ。今や薄皮に綻びが出来て、あちこちに穴が空き始めている。伸ばして穴を空けた人たちは、自分のところにパイ皮がひだになって厚く集まっていることがその原因だってことを、どうやらあまり考えてないですね。極端な格差はそうやって生まれるんだ。"p.209 "企業が競争を生き残り、利益を上げるために、テクノロジーの進歩や、産業の海外移転を進めた結果、国内の雇用がどんどん減って、人の「働く権利」は奪われてゆく。 その結果、格差がどんどん広がって、内需の消費者だった中間層が崩壊すると、結果的に物やサービスが売れなくなって、不景気になる。そんな状況はさ、まるで、自分で自分の尻尾を呑み込もうとする「ウロボロスの蛇」じゃない。"p.213 "まずは日本人が天動説から地動説に戻って、「自分たちが社会の上に乗っかって動いている」という謙虚な意識を取り戻さないと「心のある論理」は生まれてこない。でもって「心のある論理」を持たないと、「大きなもの」を目指し続けることの限界や、経済の飽和も見えてこないし、実体経済を超えて膨れ上がる金融経済が中身のないバーチャルな幻だということも、理解出来ない。"p.217 "私はね、「損得で物事を判断しない」ことを「正義」って呼んでいるんです。 「正義」っていう言葉をやたらと使いたがる人の「正義」って聞くと、私がなんだか嫌だなっていう気がするのは、そういう人たちの「正義」って「自分の好きなあり方」を勝手に正義と呼んでいるだけだから。そうして、自分のあり方を肯定したがっているだけだから。"p.220
読み終わった2026年最初に読み終わった本。 この本を最初に読めて良かった。 タイトル通り、「この世界が終わっても」その先を生きていかねばならない自分にとって、今年は昨年から引き続く不穏な世界情勢、国内の腐った政治のまんまで年が明け、全くめでたい感じのない、不安な年越しだったのだが、この本を読むことでちょっとだけ見通しができたというか、自分が進むべき道を示してくれたような、そんな本だった。 イギリスのEU離脱のことから話が始まり、アレクサンダー大王の話やソ連解体直前のことまであっちこっちに話が飛んでいきながら、最後にはそれらの点同士が見事に繋がって、「まとめ」らしきものに到達する感じ。語りおろしなので最後まで一気に読めた。実際のインタビューは毎日5時間を4日間続けられたそうで、この本に収まっていない話もたくさん出てきたのだろうが、こうして一冊の本としてまとまったのはすごい。編集が大変だっただろうな。 「心のない論理」でも、「心の論理」でもなく、「心のある論理」を持ちながら、生きていきたい。 以下気になったところの引用。 "人工知能のAIなんかはさ、人間の考え方がそんなには明確でなくて、曖味なものに満ち満ちているってことと向き合うわけでしょ。 その曖味さをなんとかクリアしようと思ってるけど、曖昧さに関しては人間の方が上だね。 はっきりとは言い切れなくて曖味な、ちょっと揺らいでたりもするものを、文科系の言葉でいうと、「頭ではなくて情感で分かれ」になるんですね。だから、理科系は、文科系に近づかざるをえないんですね。"p.169 "未だに「大きなもの」を信じている人たちは、地球を巨大な円形だと思ってて、経済が「成長と拡大」を続けて、先へ行けば行くほど、その境界が広がって、パイの皮のように薄く伸びていくと思っているらしいけど、そんなものが永遠に伸び続けるはずはないわけでさ。今や薄皮に綻びが出来て、あちこちに穴が空き始めている。伸ばして穴を空けた人たちは、自分のところにパイ皮がひだになって厚く集まっていることがその原因だってことを、どうやらあまり考えてないですね。極端な格差はそうやって生まれるんだ。"p.209 "企業が競争を生き残り、利益を上げるために、テクノロジーの進歩や、産業の海外移転を進めた結果、国内の雇用がどんどん減って、人の「働く権利」は奪われてゆく。 その結果、格差がどんどん広がって、内需の消費者だった中間層が崩壊すると、結果的に物やサービスが売れなくなって、不景気になる。そんな状況はさ、まるで、自分で自分の尻尾を呑み込もうとする「ウロボロスの蛇」じゃない。"p.213 "まずは日本人が天動説から地動説に戻って、「自分たちが社会の上に乗っかって動いている」という謙虚な意識を取り戻さないと「心のある論理」は生まれてこない。でもって「心のある論理」を持たないと、「大きなもの」を目指し続けることの限界や、経済の飽和も見えてこないし、実体経済を超えて膨れ上がる金融経済が中身のないバーチャルな幻だということも、理解出来ない。"p.217 "私はね、「損得で物事を判断しない」ことを「正義」って呼んでいるんです。 「正義」っていう言葉をやたらと使いたがる人の「正義」って聞くと、私がなんだか嫌だなっていう気がするのは、そういう人たちの「正義」って「自分の好きなあり方」を勝手に正義と呼んでいるだけだから。そうして、自分のあり方を肯定したがっているだけだから。"p.220 - 2025年12月20日
 古本買取でたまたま入ってきて何気なく手に取って読み始めたら、とんでもなく良い本だった。 1980年に出版された本で今から45年も前だが、全く古びれていないし、今こそこの本に書かれていることが広く人々の間に広まっていくことが必要だと思った。 当時も若者の自殺が増加していることが社会問題となっているところから話が始まる。将来のためにと、現在がただの将来のための準備期間となり、生きる実感を持てないまま熾烈な受験競争に巻き込まれ、生きる意味を喪失していっていることがその原因ではないかと問いかける。ではどうすればいいか。著者は手っ取り早く解決を教えるハウツー物の答えを用意する代わりに一冊の本を紹介し、「生きる意味」「学ぶ意味」を問い直すことを提案する。その書物がフランクルの『夜と霧』。(第1章生きるということ) この紹介がとても良くて、まずこの本の大きな魅力の一つとなっている。読書会で去年読んだけど、また読み直したくなった。ナチスが権力を握ってまず行ったのが、ナチスの思想信条に反する「悪書」を焼くこと。「本を焼くものは、ついには人間を焼くようになる」というハインリヒハイネの1823年の言葉。予言していたかのような彼の本も焼かれた。フランクルが収容所の中で体験したことは壮絶なものだったが、その中で彼が見出したものは人類共通の類まれな貴重な財産となった。それはどのような状況の中であろうと、苦悩を積極的に引き受け、人生の意味をあくまでも問い続ける逞しい精神を持ったもののみが最後まで生き抜くことができたということ。あくまでも「人間」として踏みとどまり、人間としての尊厳を持って生き、そして死んでいくことを選ぶということ。「人生から何を我々はまだ期待できるかが問題ではない。むしろ、人生が何を我々から期待しているかが問題なのである」という有名な言葉をもう一度噛み締める。これは収容所のような極限状況に置かれた人だけでなく、どんな場所や時代に生きている人にも問われていることだ。人生からの問いに口先だけでなく、正しい行為によって応答していくこと。 人間に生きる意味を与えるものは様々あるが、代表的なのは創造的な仕事を行うこと。芸術家や文学社のみに限られているわけではなく、自分の持てるものを注ぎ込んで何かを生み出そうとすること。日頃の対人関係にしろ、些細なことにも。今月読む『愛するということ』は、その具体的な実践について書かれてある。フランクルも愛することの重要性を語っていた。愛するということはつまり何かを創造することだろう。『生きがいについて』の話も出てくる。これも読書会で読んだが、また再読したい。「体験価値」で、優れた本を読むことの意味についても語られる。この本もまさしくそうした一冊だった。そして、「創造価値」も「体験価値」も望めないような状況でも、なおまだ人間には人生に意味を与えることができる。それが「態度価値」。 「生きているかぎり、いかなる状況のなかでも生きる意味を発見し創造するチャンスを持っています。私たちは、その価値を実現することにたいする責任からまぬがれることはできないのです。」p.39 コルベ神父の話もこの本で初めて知った。こんなに立派な生き方をできる人もいた。 「私の人生は他の誰の人生でもなく、私の人生です。それは、他の人生と比較することも、また取り替えることもできないものであります。それぞれが独自の意味と課題を持っています。だから、ある人の人生の活動半径が大きいか小さいかということそのことは、重要ではありません。人間が自己の使命、その生きる意味をどれほど満たしているかということが、大切なのです。」p.44 (第二章現代社会に生きる) 偉人が歴史を作るのではなく、あくまでも歴史を作る主体は一人一人のその時代に生きる人々である。ナチ政権を支えたのもその当時の人々で、ヒトラーを称賛したのもその当時の人々。 「私たちのすべての行動の仕方や考え方は、いずれも政治の運命を織りなす糸となっているのです。きみたちの中には、もう政治に関わりたくないという意見の人もいるかもしれない。しかし、この政治に関わりたくないという態度もまた、実は政治にたいする一つの関わり方なのです。政治について決断しないという君たちの態度も、また一つの政治的決断なのです。たとえ君たちが、自分では中立であり、何もしていないと言い張るとしても、政治の世界では、「不作為の責任」をまぬがれることができないのです。ヒトラーやファシズムの歴史は、そのことを私たちに嫌というほど教えています。」p.64 民主主義も国民一人一人が主体的に、積極的に関わっていかなければその精神が失われてしまう。 特に日本では「成り行きに任せる」「既成事実に屈服しやすい」という性質が強く、いつでも時流のおもむくところを眺め渡して、大勢の走る方向について行こうとする曖昧な行動の仕方をしがち。実際に、戦前の歴史を振り返ると、満州事変から敗戦に至るまで、軍部の作り出した既成事実に対して目立った抗議をすることもなく、(できなかったという方が正しいかもしれないが、いや、しかしそうした状況を作り出したのもまた市民の側である)気づいた時にはもう手遅れになっていたという歴史がある。今再びそうなりつつあるのではないか、という危機感がものすごくある。 その後、日本では徹底的に議論をするという習慣がまだ根付いていないとし、コンフリクトと共に生きることが真の民主主義的な社会を作る上で重要だと語る。そのためにも個人の思想信条の自由が侵害されてはならない。 大江健三郎の想像力についての言葉。すでにあるイメージから解放し、そのイメージを作りかえさせる能力が想像力。思い込みから自由になること。見えないものを想像すること。ある出来事を自分の生きた同時代のこととして実感できるようにする力。 続いて、シュヴァイツァーの生涯を紹介しながら、人間だけでなく、生きとし生けるものと共存することについて語られる。(第3章みんなと生きる) 最後の「第4章 平和をつくり出すもの」では、「剣を取るものは剣で滅びる」という言葉を軸に、軍拡によって平和を維持するのではなく、日本国憲法の精神に則った、真に平和な軍縮による平和を目指すべきだということが語られる。当時戦後30数年の時点でもすでに戦争体験の風化が進んでいたという。核武装論や、国防軍創設の動きもあったようだ。今再び高市政権下でその動きが強まろうとしている。ベルリンの壁崩壊前の、西ドイツにおいて良心的兵役拒否をした人たちの話の流れで、非暴力闘争についても紹介。日本でも、沖縄の伊江島で阿波根昌鴻さんを筆頭に非暴力闘争が行われて、米軍基地から自分たちの土地を取り返すことに成功した事例が紹介される。これもこの本で初めて知ったこと。非暴力闘争について今とても関心があるのでもっと掘り下げていきたい。そして日本国憲法はその非戦の誓いにおいて、国民的な兵役拒否をしているのではないか、ということが語られる一方で、憲法に描かれる「日本国民は、」という言葉に注目し、やはり一人一人がこの精神を強く持たない限りどんなに立派な憲法も形骸化してしまい、簡単に崩れてしまうだろうことが述べられる。 積極的平和主義をより推し進め、世界的な軍拡を止めて、平和的外交によって軍縮を進める先頭に立つことが日本に求められていると思う。それに逆行するような動きには抗っていかねばならない。 この一冊で色々読み直したい本、新たに読みたい本が増えた。たまたま出会うこうした良書との出会いがあるから古本屋は楽しい。
古本買取でたまたま入ってきて何気なく手に取って読み始めたら、とんでもなく良い本だった。 1980年に出版された本で今から45年も前だが、全く古びれていないし、今こそこの本に書かれていることが広く人々の間に広まっていくことが必要だと思った。 当時も若者の自殺が増加していることが社会問題となっているところから話が始まる。将来のためにと、現在がただの将来のための準備期間となり、生きる実感を持てないまま熾烈な受験競争に巻き込まれ、生きる意味を喪失していっていることがその原因ではないかと問いかける。ではどうすればいいか。著者は手っ取り早く解決を教えるハウツー物の答えを用意する代わりに一冊の本を紹介し、「生きる意味」「学ぶ意味」を問い直すことを提案する。その書物がフランクルの『夜と霧』。(第1章生きるということ) この紹介がとても良くて、まずこの本の大きな魅力の一つとなっている。読書会で去年読んだけど、また読み直したくなった。ナチスが権力を握ってまず行ったのが、ナチスの思想信条に反する「悪書」を焼くこと。「本を焼くものは、ついには人間を焼くようになる」というハインリヒハイネの1823年の言葉。予言していたかのような彼の本も焼かれた。フランクルが収容所の中で体験したことは壮絶なものだったが、その中で彼が見出したものは人類共通の類まれな貴重な財産となった。それはどのような状況の中であろうと、苦悩を積極的に引き受け、人生の意味をあくまでも問い続ける逞しい精神を持ったもののみが最後まで生き抜くことができたということ。あくまでも「人間」として踏みとどまり、人間としての尊厳を持って生き、そして死んでいくことを選ぶということ。「人生から何を我々はまだ期待できるかが問題ではない。むしろ、人生が何を我々から期待しているかが問題なのである」という有名な言葉をもう一度噛み締める。これは収容所のような極限状況に置かれた人だけでなく、どんな場所や時代に生きている人にも問われていることだ。人生からの問いに口先だけでなく、正しい行為によって応答していくこと。 人間に生きる意味を与えるものは様々あるが、代表的なのは創造的な仕事を行うこと。芸術家や文学社のみに限られているわけではなく、自分の持てるものを注ぎ込んで何かを生み出そうとすること。日頃の対人関係にしろ、些細なことにも。今月読む『愛するということ』は、その具体的な実践について書かれてある。フランクルも愛することの重要性を語っていた。愛するということはつまり何かを創造することだろう。『生きがいについて』の話も出てくる。これも読書会で読んだが、また再読したい。「体験価値」で、優れた本を読むことの意味についても語られる。この本もまさしくそうした一冊だった。そして、「創造価値」も「体験価値」も望めないような状況でも、なおまだ人間には人生に意味を与えることができる。それが「態度価値」。 「生きているかぎり、いかなる状況のなかでも生きる意味を発見し創造するチャンスを持っています。私たちは、その価値を実現することにたいする責任からまぬがれることはできないのです。」p.39 コルベ神父の話もこの本で初めて知った。こんなに立派な生き方をできる人もいた。 「私の人生は他の誰の人生でもなく、私の人生です。それは、他の人生と比較することも、また取り替えることもできないものであります。それぞれが独自の意味と課題を持っています。だから、ある人の人生の活動半径が大きいか小さいかということそのことは、重要ではありません。人間が自己の使命、その生きる意味をどれほど満たしているかということが、大切なのです。」p.44 (第二章現代社会に生きる) 偉人が歴史を作るのではなく、あくまでも歴史を作る主体は一人一人のその時代に生きる人々である。ナチ政権を支えたのもその当時の人々で、ヒトラーを称賛したのもその当時の人々。 「私たちのすべての行動の仕方や考え方は、いずれも政治の運命を織りなす糸となっているのです。きみたちの中には、もう政治に関わりたくないという意見の人もいるかもしれない。しかし、この政治に関わりたくないという態度もまた、実は政治にたいする一つの関わり方なのです。政治について決断しないという君たちの態度も、また一つの政治的決断なのです。たとえ君たちが、自分では中立であり、何もしていないと言い張るとしても、政治の世界では、「不作為の責任」をまぬがれることができないのです。ヒトラーやファシズムの歴史は、そのことを私たちに嫌というほど教えています。」p.64 民主主義も国民一人一人が主体的に、積極的に関わっていかなければその精神が失われてしまう。 特に日本では「成り行きに任せる」「既成事実に屈服しやすい」という性質が強く、いつでも時流のおもむくところを眺め渡して、大勢の走る方向について行こうとする曖昧な行動の仕方をしがち。実際に、戦前の歴史を振り返ると、満州事変から敗戦に至るまで、軍部の作り出した既成事実に対して目立った抗議をすることもなく、(できなかったという方が正しいかもしれないが、いや、しかしそうした状況を作り出したのもまた市民の側である)気づいた時にはもう手遅れになっていたという歴史がある。今再びそうなりつつあるのではないか、という危機感がものすごくある。 その後、日本では徹底的に議論をするという習慣がまだ根付いていないとし、コンフリクトと共に生きることが真の民主主義的な社会を作る上で重要だと語る。そのためにも個人の思想信条の自由が侵害されてはならない。 大江健三郎の想像力についての言葉。すでにあるイメージから解放し、そのイメージを作りかえさせる能力が想像力。思い込みから自由になること。見えないものを想像すること。ある出来事を自分の生きた同時代のこととして実感できるようにする力。 続いて、シュヴァイツァーの生涯を紹介しながら、人間だけでなく、生きとし生けるものと共存することについて語られる。(第3章みんなと生きる) 最後の「第4章 平和をつくり出すもの」では、「剣を取るものは剣で滅びる」という言葉を軸に、軍拡によって平和を維持するのではなく、日本国憲法の精神に則った、真に平和な軍縮による平和を目指すべきだということが語られる。当時戦後30数年の時点でもすでに戦争体験の風化が進んでいたという。核武装論や、国防軍創設の動きもあったようだ。今再び高市政権下でその動きが強まろうとしている。ベルリンの壁崩壊前の、西ドイツにおいて良心的兵役拒否をした人たちの話の流れで、非暴力闘争についても紹介。日本でも、沖縄の伊江島で阿波根昌鴻さんを筆頭に非暴力闘争が行われて、米軍基地から自分たちの土地を取り返すことに成功した事例が紹介される。これもこの本で初めて知ったこと。非暴力闘争について今とても関心があるのでもっと掘り下げていきたい。そして日本国憲法はその非戦の誓いにおいて、国民的な兵役拒否をしているのではないか、ということが語られる一方で、憲法に描かれる「日本国民は、」という言葉に注目し、やはり一人一人がこの精神を強く持たない限りどんなに立派な憲法も形骸化してしまい、簡単に崩れてしまうだろうことが述べられる。 積極的平和主義をより推し進め、世界的な軍拡を止めて、平和的外交によって軍縮を進める先頭に立つことが日本に求められていると思う。それに逆行するような動きには抗っていかねばならない。 この一冊で色々読み直したい本、新たに読みたい本が増えた。たまたま出会うこうした良書との出会いがあるから古本屋は楽しい。 - 2025年12月14日
 読み終わったこの本を読むと、「南京大虐殺はなかった」「従軍慰安婦はいなかった」「戦後の日本人はGHQによって自虐史観を植え付けられて洗脳されている」「コミンテルンがこの世を裏で牛耳ろうとしている」「中国や韓国は日本に対して歴史戦を仕掛けてきている」などといった、いわゆるネトウヨ的な言説に対する免疫をつけることができる。 事実をまず確かめ、ちょっと考えればすぐにおかしいとわかる矛盾点を論理的に説明してくれるので、もしそうした言説を言いふらす人がいたとしても冷静に対処することができるだろう。 1890〜1947年の57年間(憲法施行期間)の大日本帝国と、それ以後の日本国は、全く異なる憲法をもったほとんど別の国といってもいいくらいだが、大日本帝国に自分のアイデンティティを重ねている人たちは、大日本帝国のさまざまな非人道的行いを批判されると、自分自身が攻撃されたように感じるのだろう。だからそうした批判者のことをかれらは「反日」とか「サヨク」などと雑に分類してしまう。彼らにとっては、大日本帝国に対する批判は「日本に対する批判」と捉えられてしまう。もし彼らから「反日め」などと言われたら「反大日本帝国です」と返したらいいのだろうか。 彼ら自身も、さまざまな場面で日本国憲法で保証された基本的人権によって守られている存在であるはずなのだが、自ら進んでそれに反する大日本帝国的価値観の方へ進んでしまうのは理解に苦しむ。 権威主義的体質が全ての根っこにあるのかもしれない。それを崩すにはどうしたらいいのだろうか。少しずつ、じっくりやっていくしかないだろう。
読み終わったこの本を読むと、「南京大虐殺はなかった」「従軍慰安婦はいなかった」「戦後の日本人はGHQによって自虐史観を植え付けられて洗脳されている」「コミンテルンがこの世を裏で牛耳ろうとしている」「中国や韓国は日本に対して歴史戦を仕掛けてきている」などといった、いわゆるネトウヨ的な言説に対する免疫をつけることができる。 事実をまず確かめ、ちょっと考えればすぐにおかしいとわかる矛盾点を論理的に説明してくれるので、もしそうした言説を言いふらす人がいたとしても冷静に対処することができるだろう。 1890〜1947年の57年間(憲法施行期間)の大日本帝国と、それ以後の日本国は、全く異なる憲法をもったほとんど別の国といってもいいくらいだが、大日本帝国に自分のアイデンティティを重ねている人たちは、大日本帝国のさまざまな非人道的行いを批判されると、自分自身が攻撃されたように感じるのだろう。だからそうした批判者のことをかれらは「反日」とか「サヨク」などと雑に分類してしまう。彼らにとっては、大日本帝国に対する批判は「日本に対する批判」と捉えられてしまう。もし彼らから「反日め」などと言われたら「反大日本帝国です」と返したらいいのだろうか。 彼ら自身も、さまざまな場面で日本国憲法で保証された基本的人権によって守られている存在であるはずなのだが、自ら進んでそれに反する大日本帝国的価値観の方へ進んでしまうのは理解に苦しむ。 権威主義的体質が全ての根っこにあるのかもしれない。それを崩すにはどうしたらいいのだろうか。少しずつ、じっくりやっていくしかないだろう。 - 2025年12月6日
 戦争と農業藤原辰史読み終わった藤原辰史先生の本の中で一番最初に読むことをお勧めしたい一冊。なぜなら藤原先生がずっと研究してきた二大テーマ「戦争」と「農業」を軸に話が進み、どんどん繋がり、藤原先生がどのような関心のもとでこれら二つのテーマに取り組んでおられるのかよくわかるからだ。講義形式で進んでいくので、藤原先生の講義を直接受けているような気分で読み進められる。 この本を最初に読むことで、先生の他の著書や、関連する本にも入りやすくなると思う。地図のような本。 前半はこれら二つのテーマがどのように繋がっているか、それぞれの具体的な話がメインですすみ、後半は、それらの根幹にある問題点、それらの問題を生むこの社会の仕組みについて考えていく内容。どうすればその仕組みを変えていけるのか、その糸口を探していく。 農業の話も、戦争の話もとても具体的で、生々しくて、モザイク無しでまざまざと現実を見せつけられる思い。だから余計に読むのが止まらない。とても面白い。これはもう直接読んでその面白さを味わうしかない。「食」を根幹に据えて考えると本当にいろんなことが見えてくる。政治も暮らしも教育も。 キーワードとなるのは「遅効性」や「待つ」こと。その場その場で即興的に対応する柔軟さを持つこと。一つの巨大なピラミッド状に支配するのではなくて、人間の脳細胞のように網目のように張り巡らされたネットワークをつくれないか、ということ。 読書も、ゆっくりと、即効性はないがじわじわと効いてくるものの代表的なものである。もっと本をたくさん読みたくなる。 店でもたくさん仕入れてお勧めしていきたい。
戦争と農業藤原辰史読み終わった藤原辰史先生の本の中で一番最初に読むことをお勧めしたい一冊。なぜなら藤原先生がずっと研究してきた二大テーマ「戦争」と「農業」を軸に話が進み、どんどん繋がり、藤原先生がどのような関心のもとでこれら二つのテーマに取り組んでおられるのかよくわかるからだ。講義形式で進んでいくので、藤原先生の講義を直接受けているような気分で読み進められる。 この本を最初に読むことで、先生の他の著書や、関連する本にも入りやすくなると思う。地図のような本。 前半はこれら二つのテーマがどのように繋がっているか、それぞれの具体的な話がメインですすみ、後半は、それらの根幹にある問題点、それらの問題を生むこの社会の仕組みについて考えていく内容。どうすればその仕組みを変えていけるのか、その糸口を探していく。 農業の話も、戦争の話もとても具体的で、生々しくて、モザイク無しでまざまざと現実を見せつけられる思い。だから余計に読むのが止まらない。とても面白い。これはもう直接読んでその面白さを味わうしかない。「食」を根幹に据えて考えると本当にいろんなことが見えてくる。政治も暮らしも教育も。 キーワードとなるのは「遅効性」や「待つ」こと。その場その場で即興的に対応する柔軟さを持つこと。一つの巨大なピラミッド状に支配するのではなくて、人間の脳細胞のように網目のように張り巡らされたネットワークをつくれないか、ということ。 読書も、ゆっくりと、即効性はないがじわじわと効いてくるものの代表的なものである。もっと本をたくさん読みたくなる。 店でもたくさん仕入れてお勧めしていきたい。 - 2025年12月2日
 生きづらい明治社会松沢裕作読み終わった現代の日本も、これまでのやり方がうまくいかなくなってきて、将来の展望も暗いものばかりで、人々の鬱屈や不安感がたまり、物価は上がり続けているのに給料は上がらず、税金は高く、生きづらい世の中である。そうした中で、今年の流行語大賞が「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。生きづらいのは、個人の努力が足りないからだ、がむしゃらに働けばこの状況を打開できるはずだ、総理自身がそうするんだから、国民もそれを見習って働け、と言われているようで本当に憂鬱だ。問題は個人の努力の問題ではない。この社会の仕組みがどこかで狂っているからだ。その大元が変わらない限り、個人の努力では限界がある。 明治時代も、単純に比較はできないものの、この種の「社会的な成功は個人の努力次第」という「通俗道徳のわな」に多くの人がはまっていたという。不安と競争が渦巻く社会の中で、下層に置かれた人々はその状況を打開するために戦争をするしかないという恐ろしい方向へ傾いていった。実際に日清・日露を経て日本も朝鮮と台湾を植民地化し、その中で経済的に成功したものも多かった。しかしそうした一部の「成功者」の裏には、相変わらず悲惨な生活を続けるしかない人が圧倒的に多かった。戦場に真っ先に送られたのもこうした人々で、上流の人間たちは自分は戦場に行かずに済んだ。 これからの日本も、どんどん戦争に傾いていってしまうのだろうか。軍事費は鰻登り、武器輸出も解禁し、非核三原則も見直し、憲法9条も変えようとしている。また同じ愚を繰り返そうとしているのか。歴史に学ぼうとしない日本。極右勢力が幅を利かせ、台湾有事もむしろ起きてほしいと願っているかのようだ。議員定数も削減の方向で動くことが決まったらしい。ますます権力者たちに都合の良い政治になっていくだろう。小さきものの声は届かなくなるだろう。抗う声も押さえつけられるだろう。政府に批判的な言動をすれば「非国民」と言われる日も近いのではないか。 ああいやだ嫌だ。どうすれば変えられるだろう。抗えるだろう。
生きづらい明治社会松沢裕作読み終わった現代の日本も、これまでのやり方がうまくいかなくなってきて、将来の展望も暗いものばかりで、人々の鬱屈や不安感がたまり、物価は上がり続けているのに給料は上がらず、税金は高く、生きづらい世の中である。そうした中で、今年の流行語大賞が「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。生きづらいのは、個人の努力が足りないからだ、がむしゃらに働けばこの状況を打開できるはずだ、総理自身がそうするんだから、国民もそれを見習って働け、と言われているようで本当に憂鬱だ。問題は個人の努力の問題ではない。この社会の仕組みがどこかで狂っているからだ。その大元が変わらない限り、個人の努力では限界がある。 明治時代も、単純に比較はできないものの、この種の「社会的な成功は個人の努力次第」という「通俗道徳のわな」に多くの人がはまっていたという。不安と競争が渦巻く社会の中で、下層に置かれた人々はその状況を打開するために戦争をするしかないという恐ろしい方向へ傾いていった。実際に日清・日露を経て日本も朝鮮と台湾を植民地化し、その中で経済的に成功したものも多かった。しかしそうした一部の「成功者」の裏には、相変わらず悲惨な生活を続けるしかない人が圧倒的に多かった。戦場に真っ先に送られたのもこうした人々で、上流の人間たちは自分は戦場に行かずに済んだ。 これからの日本も、どんどん戦争に傾いていってしまうのだろうか。軍事費は鰻登り、武器輸出も解禁し、非核三原則も見直し、憲法9条も変えようとしている。また同じ愚を繰り返そうとしているのか。歴史に学ぼうとしない日本。極右勢力が幅を利かせ、台湾有事もむしろ起きてほしいと願っているかのようだ。議員定数も削減の方向で動くことが決まったらしい。ますます権力者たちに都合の良い政治になっていくだろう。小さきものの声は届かなくなるだろう。抗う声も押さえつけられるだろう。政府に批判的な言動をすれば「非国民」と言われる日も近いのではないか。 ああいやだ嫌だ。どうすれば変えられるだろう。抗えるだろう。 - 2025年11月30日
 アンネの日記 増補新訂版アンネ・フランク,深町眞理子読み終わった11月の一冊読書会の課題本。読書会の直前に読了。 タイトルだけ知っていて、実際に読んだことのある人は少ない本の代表的な作品の一つではないか。(夏目漱石の『吾輩は猫である』とかもそうだと思う) 自分もこの読書会で初めて読んだ。 結果読むことができて本当によかったと思える一冊になった。ずっと読み継がれている理由がよくわかった。 戦争のことはむしろこの本の背景としてあり、 13歳〜15歳にかけての思春期真っ只中の少女が、 「隠れ家」生活という非日常的な環境の中で、 様々な制約や同居する他の人たちとの葛藤の中で揉まれながら 精神的に成長してゆく様が日を追うごとに実感できる貴重な記録。 読み物としてもとても面白い。13歳の少女による文章とは思えない表現力。(深町さんの翻訳も素晴らしい) なんとなく女性が読むものみたいなイメージを持っている人も多いかもしれないが、 決してそんなことはなく、思春期以上の老若男女全てが読むべき内容だと思う。 両親への愛情と反発、異性への憧れ、自らの不安や葛藤、将来の夢、日々起こるトラブルにどう対処したか、どう感じたか。「隠れ家」の中で、戦争が終わる日をひたすら待ち侘びながら、日々勉強もし、戦争が終わった後の事を夢想しながら、挫けそうになる自分を、絶望しそうになる自分を書くことで救おうとした少女の記録。読んでいると励まされる文章にも何度も出会う。隠れ家の中での「日常」の繰り返し。時折戦争の気配がするが、基本的には外の世界とは切断されている世界。 支援者の人たちの勇気と優しさにも感じ入るものがある。ミープがアンネの日記を咄嗟に拾い上げて後世に残してくれて、本当によかった。 ナチスドイツによって虐殺されたユダヤ人は600万人以上ともいわれる。 あまりに数字が膨大で、感覚が麻痺してしまう。 しかし、この『アンネの日記』のような作品を読むと、具体的な一人一人の人生や生活について想像することができるようになる。語り残されていないだけで、600万人分の人生の物語があったのだ。それぞれの生活があったのだ。その途方もなさにクラっとしてしまう。 「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」 1944年4月5日の日記。 この望みは間違いなく叶えられている。 また何度も読み返したい作品。 100分de名著での小川洋子さんの解説もとてもよかった。 小川洋子さんの作品も読んでみたくなる。
アンネの日記 増補新訂版アンネ・フランク,深町眞理子読み終わった11月の一冊読書会の課題本。読書会の直前に読了。 タイトルだけ知っていて、実際に読んだことのある人は少ない本の代表的な作品の一つではないか。(夏目漱石の『吾輩は猫である』とかもそうだと思う) 自分もこの読書会で初めて読んだ。 結果読むことができて本当によかったと思える一冊になった。ずっと読み継がれている理由がよくわかった。 戦争のことはむしろこの本の背景としてあり、 13歳〜15歳にかけての思春期真っ只中の少女が、 「隠れ家」生活という非日常的な環境の中で、 様々な制約や同居する他の人たちとの葛藤の中で揉まれながら 精神的に成長してゆく様が日を追うごとに実感できる貴重な記録。 読み物としてもとても面白い。13歳の少女による文章とは思えない表現力。(深町さんの翻訳も素晴らしい) なんとなく女性が読むものみたいなイメージを持っている人も多いかもしれないが、 決してそんなことはなく、思春期以上の老若男女全てが読むべき内容だと思う。 両親への愛情と反発、異性への憧れ、自らの不安や葛藤、将来の夢、日々起こるトラブルにどう対処したか、どう感じたか。「隠れ家」の中で、戦争が終わる日をひたすら待ち侘びながら、日々勉強もし、戦争が終わった後の事を夢想しながら、挫けそうになる自分を、絶望しそうになる自分を書くことで救おうとした少女の記録。読んでいると励まされる文章にも何度も出会う。隠れ家の中での「日常」の繰り返し。時折戦争の気配がするが、基本的には外の世界とは切断されている世界。 支援者の人たちの勇気と優しさにも感じ入るものがある。ミープがアンネの日記を咄嗟に拾い上げて後世に残してくれて、本当によかった。 ナチスドイツによって虐殺されたユダヤ人は600万人以上ともいわれる。 あまりに数字が膨大で、感覚が麻痺してしまう。 しかし、この『アンネの日記』のような作品を読むと、具体的な一人一人の人生や生活について想像することができるようになる。語り残されていないだけで、600万人分の人生の物語があったのだ。それぞれの生活があったのだ。その途方もなさにクラっとしてしまう。 「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」 1944年4月5日の日記。 この望みは間違いなく叶えられている。 また何度も読み返したい作品。 100分de名著での小川洋子さんの解説もとてもよかった。 小川洋子さんの作品も読んでみたくなる。 - 2025年11月22日
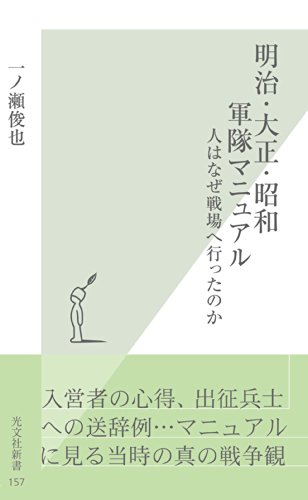 読み終わった明治から1945年の敗戦まで、軍隊にまつわる「決まり文句」を多数収録した「軍隊マニュアル」が多数出版されていた。それらの内容を詳しく見ながら、戦時下の人々はどのように戦争を自分たち自身に納得させていたのかを探る内容。 今も昔も、国が国民に戦争を納得させる手口は変わっていない。国というか、国民自身も、自分自身に納得させないとやっていけなかったんだろうと、この本読んで思った。 高市政権がこのまま続けば、この本に出てくるような文言が繰り返されるのではないかと予想する。 日露戦争でギリギリのところで一応は「勝った」ことになり、本当はさまざまな幸運が重なった結果の辛うじての勝利にも関わらず、「圧倒的な戦力差がありながら日本が勝てたのは、日本軍の士気が高く、一人一人の能力が高かったからだ。最後は精神力が勝敗を決める、物質的に貧しくても精神力があれば勝てる」というクソみたいな言説が出来上がり、日中戦争、太平洋戦争でも繰り返され、無謀な戦争に突き進み、物資の補給が蔑ろにされ、戦死者の6割以上が餓死、戦病死という情けない結末を招いた。 この「精神力があれば勝てる」的な思考パターンは、いまだに続いていると思う。高市のあの馬車馬発言とか、午前3時から働いてるとか、そういう時代錯誤なポーズはまさにその表れではないか。 精神力はたしかに重要だが、それしか頼るものがないというのはいかがなものか。そんな状態になってる時点で負けは確定したようなものだ。別の道を探る方が遥かにマシだ。そうならないようにするのが段取りであり、リーダーのやるべきことではないか。 「マニュアル」通りに行動、発言することが「善良な国民」とされ、人々も自ら進んでその型にはまっていった。そこからはみ出そうとすれば「非国民」とされ、居場所を失った。個人だけでなく、近親者や擁護者も。典型的なムラ社会のやり口であるが、怖いのはそれが遠い過去のものとは言い切れずに、今も同じようなものが残り続けていること。軍隊でなくともあちこちでその片鱗は見ることができる。 戦争を避けるには、そうした「ミクロ」な戦争に注意し、そことはなるべく関わらずに、無効化できる場所で生きていく道を示すことではないか、と思った。
読み終わった明治から1945年の敗戦まで、軍隊にまつわる「決まり文句」を多数収録した「軍隊マニュアル」が多数出版されていた。それらの内容を詳しく見ながら、戦時下の人々はどのように戦争を自分たち自身に納得させていたのかを探る内容。 今も昔も、国が国民に戦争を納得させる手口は変わっていない。国というか、国民自身も、自分自身に納得させないとやっていけなかったんだろうと、この本読んで思った。 高市政権がこのまま続けば、この本に出てくるような文言が繰り返されるのではないかと予想する。 日露戦争でギリギリのところで一応は「勝った」ことになり、本当はさまざまな幸運が重なった結果の辛うじての勝利にも関わらず、「圧倒的な戦力差がありながら日本が勝てたのは、日本軍の士気が高く、一人一人の能力が高かったからだ。最後は精神力が勝敗を決める、物質的に貧しくても精神力があれば勝てる」というクソみたいな言説が出来上がり、日中戦争、太平洋戦争でも繰り返され、無謀な戦争に突き進み、物資の補給が蔑ろにされ、戦死者の6割以上が餓死、戦病死という情けない結末を招いた。 この「精神力があれば勝てる」的な思考パターンは、いまだに続いていると思う。高市のあの馬車馬発言とか、午前3時から働いてるとか、そういう時代錯誤なポーズはまさにその表れではないか。 精神力はたしかに重要だが、それしか頼るものがないというのはいかがなものか。そんな状態になってる時点で負けは確定したようなものだ。別の道を探る方が遥かにマシだ。そうならないようにするのが段取りであり、リーダーのやるべきことではないか。 「マニュアル」通りに行動、発言することが「善良な国民」とされ、人々も自ら進んでその型にはまっていった。そこからはみ出そうとすれば「非国民」とされ、居場所を失った。個人だけでなく、近親者や擁護者も。典型的なムラ社会のやり口であるが、怖いのはそれが遠い過去のものとは言い切れずに、今も同じようなものが残り続けていること。軍隊でなくともあちこちでその片鱗は見ることができる。 戦争を避けるには、そうした「ミクロ」な戦争に注意し、そことはなるべく関わらずに、無効化できる場所で生きていく道を示すことではないか、と思った。 - 2025年11月14日
 読み終わった高校生と小学生相手に行った講演録。 以下読書メモ。 創造的な人間になるためには何が必要か、梅原猛さんが実際に会ってきたさまざまな先人たちの例をだしながら、語る。 ニーチェの三つの進化説に即して、まずはラクダのように忍耐の時期、とにかく基礎的なものをしっかり学習する期間、ライオンのように批判的精神を持って常識を疑う目を養う期間、そして赤ん坊のように自由な心で、のびのびと創造する期間。 (梅原さんが語ったわけではないが、おそらくこの三つの段階もぐるぐると行ったり来たりする必要があるのだろう。) 大きな夢を持つ人というのは、心のどこかに大きな傷を持つ人である、という話も。梅原さんの生い立ちはこの本で初めて知った。 学問の面白さとは、ものを知ることだけでなく、発見、新しい仮説の提唱である。学問とは仮説を立てること。 そのためにはまず懐疑が基礎となる。そしてあるとき直感がひらめく。それを実証的に調べる。 懐疑と直感、粘り強い演繹と帰納、体系構成。それが学問である、と簡潔にまとめる。 常に新しいものを創造しつづける。「自分の映画に傑作はない、未来に傑作がある」という黒澤明の言葉。できたもの、完成したものに未練は持たない。 これまでの時代と全く方向転換しなければならない今だからこそ、夢を見なければならない。これまでと同じようなやり方は通用しない。偏差値教育もあてにならない。社会が安定している時の方法だから。
読み終わった高校生と小学生相手に行った講演録。 以下読書メモ。 創造的な人間になるためには何が必要か、梅原猛さんが実際に会ってきたさまざまな先人たちの例をだしながら、語る。 ニーチェの三つの進化説に即して、まずはラクダのように忍耐の時期、とにかく基礎的なものをしっかり学習する期間、ライオンのように批判的精神を持って常識を疑う目を養う期間、そして赤ん坊のように自由な心で、のびのびと創造する期間。 (梅原さんが語ったわけではないが、おそらくこの三つの段階もぐるぐると行ったり来たりする必要があるのだろう。) 大きな夢を持つ人というのは、心のどこかに大きな傷を持つ人である、という話も。梅原さんの生い立ちはこの本で初めて知った。 学問の面白さとは、ものを知ることだけでなく、発見、新しい仮説の提唱である。学問とは仮説を立てること。 そのためにはまず懐疑が基礎となる。そしてあるとき直感がひらめく。それを実証的に調べる。 懐疑と直感、粘り強い演繹と帰納、体系構成。それが学問である、と簡潔にまとめる。 常に新しいものを創造しつづける。「自分の映画に傑作はない、未来に傑作がある」という黒澤明の言葉。できたもの、完成したものに未練は持たない。 これまでの時代と全く方向転換しなければならない今だからこそ、夢を見なければならない。これまでと同じようなやり方は通用しない。偏差値教育もあてにならない。社会が安定している時の方法だから。 - 2025年11月8日
 物語の役割小川洋子(小説家)読み終わったちくまプリマー新書の初期の傑作。 小川洋子さんの小説執筆の方法が具体的に開示されていて、創作をする人だけでなく読者の側にも新たな視点をもたらしてくれる。 特に第二部が素晴らしい。 テーマやストーリーをあらかじめ決めてから書き始めるのではなく、言葉になる前のイメージや風景が、自分の意思ではない偶然性によってやってくるところからしか創作は始まらないという。 もちろんそうした偶然にしか思えない創作のタネのようなものをちゃんと見つけて拾い上げるためには普段から物事をよく観察し、驚き、感動する感性がなければならない。むしろ小説家というのはそうした感性を鋭くさせ、言葉にならないものに言葉を与える仕事なのかもしれない。 小説を書いている間、小川さんは死者たちの声に耳を傾けている感覚だ、と書いていたのも印象深い。物語が起こる具体的な場所のイメージも、廃墟のようなところに自分が立ち、そこでかつてどんな人たちがどんな風に生活していたのかを幻視しながら書くのだという。 自分の中から言葉を出すのではなく、じっと耳を傾け、通路のようになる感覚。自分、という意識を持たずに、観察する透明な存在になること。 誰かが落としていったもの、落とした当人が忘れ去ってしまっているようなものを丁寧に拾い上げて、細かく観察し、そこから物語を掬いとる感覚。 これを読むと物語を書いてみたくなるし、小川さんの小説も読んでみたくなる。
物語の役割小川洋子(小説家)読み終わったちくまプリマー新書の初期の傑作。 小川洋子さんの小説執筆の方法が具体的に開示されていて、創作をする人だけでなく読者の側にも新たな視点をもたらしてくれる。 特に第二部が素晴らしい。 テーマやストーリーをあらかじめ決めてから書き始めるのではなく、言葉になる前のイメージや風景が、自分の意思ではない偶然性によってやってくるところからしか創作は始まらないという。 もちろんそうした偶然にしか思えない創作のタネのようなものをちゃんと見つけて拾い上げるためには普段から物事をよく観察し、驚き、感動する感性がなければならない。むしろ小説家というのはそうした感性を鋭くさせ、言葉にならないものに言葉を与える仕事なのかもしれない。 小説を書いている間、小川さんは死者たちの声に耳を傾けている感覚だ、と書いていたのも印象深い。物語が起こる具体的な場所のイメージも、廃墟のようなところに自分が立ち、そこでかつてどんな人たちがどんな風に生活していたのかを幻視しながら書くのだという。 自分の中から言葉を出すのではなく、じっと耳を傾け、通路のようになる感覚。自分、という意識を持たずに、観察する透明な存在になること。 誰かが落としていったもの、落とした当人が忘れ去ってしまっているようなものを丁寧に拾い上げて、細かく観察し、そこから物語を掬いとる感覚。 これを読むと物語を書いてみたくなるし、小川さんの小説も読んでみたくなる。 - 2025年10月26日
 夜間飛行・人間の大地サン=テグジュペリ,野崎歓読み終わった1週間くらい前に読み終わったのに感想を書いていなかった。明日の読書会に向けて思い出しながら書いてみる。 まず内容に入る以前に、久しぶりに分厚い骨太な小説を読んだ。先月の読書会で読んだ『君たちはどう生きるか』もまあまあ分厚かったが青少年向けというのもありとても読みやすくスラスラと読めたのだが、今回のは海外文学で、大人向けという感じで、なかなかスラスラ読むというわけにもいかず数日かけてじっくり読んだ。そして分厚い小説を読み終わった時の達成感がまずやはりとても良い。これは他のどの活動をしていてもなかなか味わえるものではない。深い満足感と余韻。もちろん内容が素晴らしかったことから来るのだけど、(でなければ最後まで読めない)この分厚い骨太な小説を読み終えた時の達成感がまず強かった。 内容であるが、さまざまな媒体に発表していた文章を「花束のように」(アンドレ・ジッドの助言)編んだ作品。中南米の聞き慣れない地名などが多く出てくるので最初はちょっと戸惑ったが、Googleアースを見ながら読んで臨場感を高めて読んだ。 飛行機乗りの先輩たちのエピソード。精神的貴族とはこういうことか、という人たち。やはり最初に印象に残るのは雪山で遭難したギヨメが、自分の遺体が少しでも早く発見されて妻に保険金が滞りなく支給されるように、という思いだけを頼りに極限状況の中一歩一歩歩いて、奇跡的に生還した話。100分de名著でも印象的だった。保険=アシュアランス=信頼。人間に対する責任=レスポンシビリティ=応答すること。極限状況の中で人を最後に動かすのは、やはり誰かのために、という思い。いや、やはり誰にでもできることじゃない。もう限界だからあとはもうどうにでもなれ、と思ってそのまま雪の中で眠る人が大半だろうが、そこでも最後の最後まで、自分が生きるためにではなく、妻のために、最後の力を振り絞って歩き続けたところに感動するのだ。他の動物にはできない一番人間らしい行動をしたのだ。 極限状況の中で現れる人間らしさについて、さまざまなエピソードとともに語られていく。 間に美しい夜の飛行の情景だったり、途中で降り立った街での出来事、出会った人たちとの思い出だったりも挟みながら。 やはり圧巻なのは最後、サン=テグジュペリ自身の砂漠での遭難の体験の話。四日間もの間灼熱の太陽のもとで、幻覚を見ながら、喉の渇きに耐えながら、歩き続けているその描写。こちらまで喉が渇いてくるような臨場感、唇の嫌な粘っこい感じとか色々伝わってきた。この分厚い本がそもそもじっくりじっくり、一歩一歩歩くように読まないと進まない、なかなか読み終わらない本。だけど最後にまたとうとう奇跡的に砂漠の民に出会うシーンの感動もすごい。「あなたの顔を忘れるだろう」という一見普通逆じゃないかということも、よくよく読んでいくと、そういうことか、と。人間の顔を見出したんだと。 そしてそれに続く最後の章。これがまた良い。第二次大戦に突入前夜、ポーランドに送り返される労働者の乗る列車に居合わせたサン=テグジュペリが、粘土のようになってしまった人たちの中でモーツァルトのような輝きを放つ子どもに出会う。しかしその子どもも粘土になってしまうだろうという予感。実際その後のポーランドでは人類史に残る大虐殺が待っていた。その未来を知っているからこそこのシーンは重たく響いた。しかし最後の一行にたどり着いた時に、この『人間の大地』というタイトルに見事に繋がる。本当に感動した。読み終わった、という達成感とともに、なんとも言えない余韻。 思いつくままに書き散らした。明日またみんなで読み直すのが楽しみ。
夜間飛行・人間の大地サン=テグジュペリ,野崎歓読み終わった1週間くらい前に読み終わったのに感想を書いていなかった。明日の読書会に向けて思い出しながら書いてみる。 まず内容に入る以前に、久しぶりに分厚い骨太な小説を読んだ。先月の読書会で読んだ『君たちはどう生きるか』もまあまあ分厚かったが青少年向けというのもありとても読みやすくスラスラと読めたのだが、今回のは海外文学で、大人向けという感じで、なかなかスラスラ読むというわけにもいかず数日かけてじっくり読んだ。そして分厚い小説を読み終わった時の達成感がまずやはりとても良い。これは他のどの活動をしていてもなかなか味わえるものではない。深い満足感と余韻。もちろん内容が素晴らしかったことから来るのだけど、(でなければ最後まで読めない)この分厚い骨太な小説を読み終えた時の達成感がまず強かった。 内容であるが、さまざまな媒体に発表していた文章を「花束のように」(アンドレ・ジッドの助言)編んだ作品。中南米の聞き慣れない地名などが多く出てくるので最初はちょっと戸惑ったが、Googleアースを見ながら読んで臨場感を高めて読んだ。 飛行機乗りの先輩たちのエピソード。精神的貴族とはこういうことか、という人たち。やはり最初に印象に残るのは雪山で遭難したギヨメが、自分の遺体が少しでも早く発見されて妻に保険金が滞りなく支給されるように、という思いだけを頼りに極限状況の中一歩一歩歩いて、奇跡的に生還した話。100分de名著でも印象的だった。保険=アシュアランス=信頼。人間に対する責任=レスポンシビリティ=応答すること。極限状況の中で人を最後に動かすのは、やはり誰かのために、という思い。いや、やはり誰にでもできることじゃない。もう限界だからあとはもうどうにでもなれ、と思ってそのまま雪の中で眠る人が大半だろうが、そこでも最後の最後まで、自分が生きるためにではなく、妻のために、最後の力を振り絞って歩き続けたところに感動するのだ。他の動物にはできない一番人間らしい行動をしたのだ。 極限状況の中で現れる人間らしさについて、さまざまなエピソードとともに語られていく。 間に美しい夜の飛行の情景だったり、途中で降り立った街での出来事、出会った人たちとの思い出だったりも挟みながら。 やはり圧巻なのは最後、サン=テグジュペリ自身の砂漠での遭難の体験の話。四日間もの間灼熱の太陽のもとで、幻覚を見ながら、喉の渇きに耐えながら、歩き続けているその描写。こちらまで喉が渇いてくるような臨場感、唇の嫌な粘っこい感じとか色々伝わってきた。この分厚い本がそもそもじっくりじっくり、一歩一歩歩くように読まないと進まない、なかなか読み終わらない本。だけど最後にまたとうとう奇跡的に砂漠の民に出会うシーンの感動もすごい。「あなたの顔を忘れるだろう」という一見普通逆じゃないかということも、よくよく読んでいくと、そういうことか、と。人間の顔を見出したんだと。 そしてそれに続く最後の章。これがまた良い。第二次大戦に突入前夜、ポーランドに送り返される労働者の乗る列車に居合わせたサン=テグジュペリが、粘土のようになってしまった人たちの中でモーツァルトのような輝きを放つ子どもに出会う。しかしその子どもも粘土になってしまうだろうという予感。実際その後のポーランドでは人類史に残る大虐殺が待っていた。その未来を知っているからこそこのシーンは重たく響いた。しかし最後の一行にたどり着いた時に、この『人間の大地』というタイトルに見事に繋がる。本当に感動した。読み終わった、という達成感とともに、なんとも言えない余韻。 思いつくままに書き散らした。明日またみんなで読み直すのが楽しみ。 - 2025年10月20日
 戦う石橋湛山新装版半藤一利読み終わった帝国主義・植民地主義に一貫して反対し続けた気骨のある言論人、石橋湛山についての評伝だが、満州事変前後、日本が国際連盟を脱退するところまでを中心に語られる。その過程でメディアがどんな役割を果たしたかが中心テーマ。 軍部が暴走した結果、日本は泥沼の戦争に突き進んだのだが、その裏ではメディアによる太鼓持ち、それに踊らされた国民の熱狂的な支持があった。その世論の後押しがなければ軍部もそこまで増長できなかったのではないか、と筆者は語る。実際、第一次対戦後の世界的な軍縮の流れの中で、軍人たちはかなり肩身の狭い思いをしていたらしく、社会的地位も低かったそうだ。 言論がいかに歴史を動かしたか、その中で毅然とした意見を発表しつづけた石橋湛山と東洋経済新報社。 はじめは軍部に批判的だったメディアがいつのまにか戦争を煽る狂気の拡声器と化してしまった。 湛山の「小日本主義」を日本がとっていたらどんな未来になっていただろうかと想像する。広島平和公園のあるところは今ではきっと広島随一の繁華街になっていただろうし、長崎も今とは違う姿だったろうし、沖縄も米軍基地のあるところはすべて沖縄人の住む町になって発展しただろうし、東京も、他の空襲被害を受けた町も、街並みが全く違っていただろうし、死なずに済んだ優秀な若者たちが多く生きながらえて数々の業績を残しただろう。日中関係も今よりずっと良好だろうし、韓国とも仲良くなっていて、アメリカのしもべのような地位にはなっていなかったのではないか。 本当に日本を破滅に追い込んだ軍部とそれを煽ったメディアの罪は重すぎる。 解説が櫻井よしこなのが唯一違和感が残った。この時からすでに日本の戦争はアメリカに仕向けられたものだったという説を展開している。一体何をこの本で読んだのだろう。学んだのだろう。
戦う石橋湛山新装版半藤一利読み終わった帝国主義・植民地主義に一貫して反対し続けた気骨のある言論人、石橋湛山についての評伝だが、満州事変前後、日本が国際連盟を脱退するところまでを中心に語られる。その過程でメディアがどんな役割を果たしたかが中心テーマ。 軍部が暴走した結果、日本は泥沼の戦争に突き進んだのだが、その裏ではメディアによる太鼓持ち、それに踊らされた国民の熱狂的な支持があった。その世論の後押しがなければ軍部もそこまで増長できなかったのではないか、と筆者は語る。実際、第一次対戦後の世界的な軍縮の流れの中で、軍人たちはかなり肩身の狭い思いをしていたらしく、社会的地位も低かったそうだ。 言論がいかに歴史を動かしたか、その中で毅然とした意見を発表しつづけた石橋湛山と東洋経済新報社。 はじめは軍部に批判的だったメディアがいつのまにか戦争を煽る狂気の拡声器と化してしまった。 湛山の「小日本主義」を日本がとっていたらどんな未来になっていただろうかと想像する。広島平和公園のあるところは今ではきっと広島随一の繁華街になっていただろうし、長崎も今とは違う姿だったろうし、沖縄も米軍基地のあるところはすべて沖縄人の住む町になって発展しただろうし、東京も、他の空襲被害を受けた町も、街並みが全く違っていただろうし、死なずに済んだ優秀な若者たちが多く生きながらえて数々の業績を残しただろう。日中関係も今よりずっと良好だろうし、韓国とも仲良くなっていて、アメリカのしもべのような地位にはなっていなかったのではないか。 本当に日本を破滅に追い込んだ軍部とそれを煽ったメディアの罪は重すぎる。 解説が櫻井よしこなのが唯一違和感が残った。この時からすでに日本の戦争はアメリカに仕向けられたものだったという説を展開している。一体何をこの本で読んだのだろう。学んだのだろう。
読み込み中...
