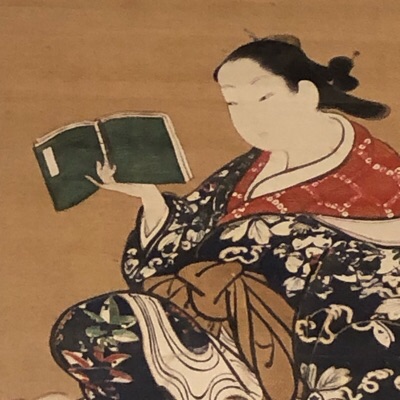
勝村巌
@katsumura
2025年11月24日

読み終わった
大塚英志の新刊。新書だが470ページとかある大部。とはいえ、内容は非常にエキサイティングで大変面白く、結構時間を忘れて読んだ。
1930年代にエイゼンシュテインが自身の映画技術であるモンタージュ論を日本の伝統表現と結び付けた評論がキネ旬により日本に紹介されたことをきっかけにこ、日本的🟰モンタージュという概念が市井にも広がった。
モンタージュは映像表現におけるカットと時系列のカットアップによる演出方法だが、それはロシア構成主義などによる平面のグラフモンタージュとも関連していく。
1937年のウィーン万博には日本も出展しており、これは日本国としては公式初参加の万博だが、そこには金のシャチホコなどと一緒に、観光日本と称された、高さ2.35m、長さ18mに及ぶ写真壁画が展示されていたという。
これは大仏や芸者などをあしらったフォトモンタージュ作品だったが、そういうものが展示された経緯や、その後、戦時下にプロパガンダとして国策で作られたグラフ誌「front』などの成立やピープルツリーを細かく紹介し、戦時下のプロパガンダとグラフモンタージュなどがどのように成立していったかを解説している。
そもそも、僕は美術教科書の編集の仕事をしているわけですが、自分の問題意識として、この美術教科書のレイアウトの形式ってどこからきたのか、意識したことはなかったのですが、なんかそれを想像させてくれるような資料的側面が強く、大変に惹きつけられました。
戦中のプロパガンダ誌には原弘とか名取洋之助とか木村伊兵衛、土門拳なんかも絡んでいるわけですが、それ以前には日本にはいわゆる雑誌などはなかったわけで、この辺りが今の雑誌レイアウトに与えた影響は大きく、そのあたりの人たちは戦後も出版や写真の世界で生き残っていくわけなので、もしかしたら美術教科書の源流はここかもしれないな、などと考えさせられた。
社内にある古い教科書の関係者にこういう人らが入っているかどうかを少しリサーチしてみようかと思う。
それ以外にも柳田國男とか手塚治虫とかの話もあって、大変に勉強になりました。面白い本なので、オススメです。




