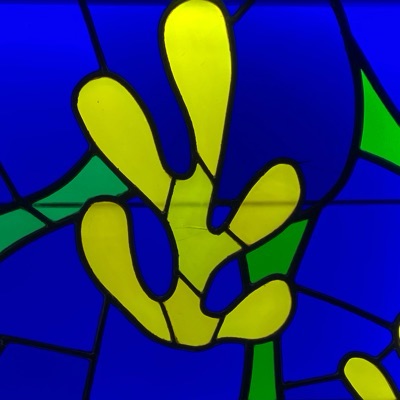
花木コヘレト
@qohelet
2025年12月1日

みな、やっとの思いで坂をのぼる
永野三智
読み終わった
図書館本
水俣病
とにかく耳が痛い本です。つまり、水俣病問題を、全く知らなかった自分が、加害者(であり当事者)と同じであることを突きつけられる本です。
本書の中で、「水俣病は教科書の中だけではない」という趣旨の言葉が繰り返されるのですが、本書を読めば、その通りだと観念するしかなくなります。つまり、自分がいかに無知であったかということにです。水俣病は、裁判結果としては「最終解決」していながら、実際はまだ終息しておらず、苦しんでいる人、未認定の人がたくさんいることが、本書からわかります。というより、まだ水俣病が続いていることに、本書の出版根拠があるのでしょう。現在形で、公害に苦しんでいる方が、国内にいるということは、そしてそれを今まで自分が知らなかったということは、二重の衝撃であります。
ですから、本書は、その理性的な文章にも関わらず、強い力でもって読者の胸をぐらぐらと揺らします。本書を読んで、私は生活態度を改めなくてはならないなと、思いました。社会人として、何が求められているのか?を、社会の構成員として、自覚しないわけにはいかないからです。水俣病は、社会システムの結び目における社会問題(もっと言えば犯罪)であるのですから、社会の一員である私も、自動的に加害者であり、また被害者であることを免れ得ないからです。
別の衝撃だったのは、水俣市周辺においては、いまだに水俣病がタブーとされているということです。なぜなら、地域住民の間で、差別する/される、水俣病に認定される/されなかった、の複雑な関係があったからのようです。しかし、そういう感覚は、匿名的で抽象的な都市部に住む私のような人間には、わりかし想像がしづらいところがあります。だから、タブーの中で患者支援を長年続けている、一般財団法人水俣病センター相思社(著者の勤務先)は、一体どんな組織なのだろうかと、関心が高まるところでもありました。
話は戻って、本書を読んで私は、無知を克服するために、もっと社会問題に関心を持とうと思いました。しかし、もっと言うと、もっと根本的に、自分の生活態度が問われているように思われました。今自宅で読書している自分が、見えないけれど、必ずどこかにいる水俣病(患者)とつながっているということ、そういう急速な接近を感じました。比喩として、隣人が水俣病であるような錯覚、それに今まで気づかなかったことへの嘆息を、覚えたのでした。
耳を閉じてしまえば届かない呻き、本書から受け取った苦しみの声を、しっかり胸にしまって、わずかでもその声に応えていく生活を、構築したいなと思いました。

