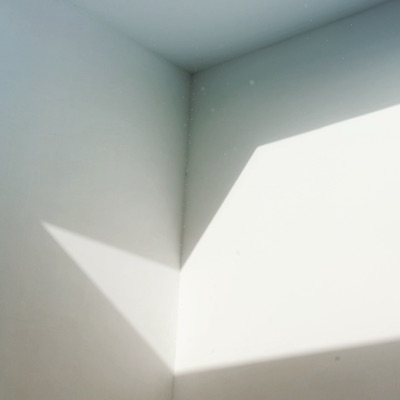暗号の子
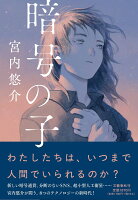
19件の記録
 ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年8月11日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、8月11日(月)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 宮内悠介『暗号の子』文藝春秋 新しい暗号通貨、分断のないSNS、超小型人工衛星――テクノロジーによって人間性が剥奪されることがある。しかしそれでも技術を使うのはあくまで人間であり、人間性を、テクノロジーを取り戻すこともできるとそう思わせてくれる作品集。最近読んだなかでいちばんおもしろかったSF短編集です。 #宮内悠介 #暗号の子 #文藝春秋 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション
ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年8月11日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、8月11日(月)オープンしております。19時まで。ご来店お待ちしております。 宮内悠介『暗号の子』文藝春秋 新しい暗号通貨、分断のないSNS、超小型人工衛星――テクノロジーによって人間性が剥奪されることがある。しかしそれでも技術を使うのはあくまで人間であり、人間性を、テクノロジーを取り戻すこともできるとそう思わせてくれる作品集。最近読んだなかでいちばんおもしろかったSF短編集です。 #宮内悠介 #暗号の子 #文藝春秋 #信州 #長野県松本市 #松本市 #本屋 #書店 #古本屋 #ブックスエコーロケーション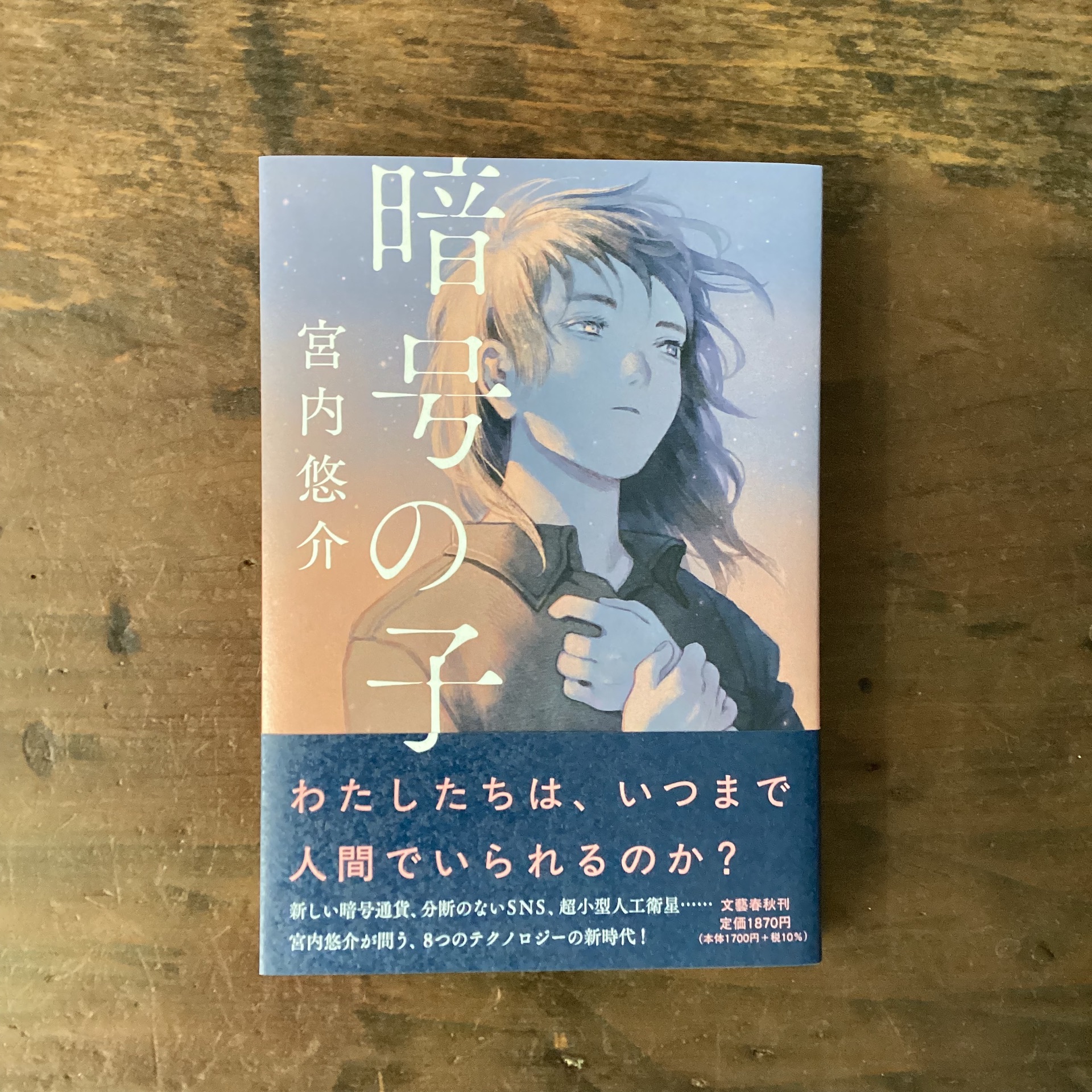
- のーとみ@notomi2025年3月5日読み終わった宮内悠介「暗号の子」読んだ。テクノロジーをテーマに、文芸誌からSF誌、トラ技まで、あちこちの媒体に書かれているので、それぞれの媒体の個性に合わせつつ、テクノロジーの現在と未来の中でウロウロする人々の物語が書かれる。そして、恐ろしいことに、収録作が全部、ものすごく面白い。 もう、冒頭に置かれた表題作「暗号の子」が凄い。作者本人もテクノロジーテーマの現時点での集大成を書こうとしたと言ってるように、現代のコンピュータ小説の最前線といった趣で、読んでいてずっと、ギブソンの「ニューロマンサー」から40年くらい経って、コンピューターの物語は、こんなところまで来てしまったのかと思っていた。サイバーパンクって、なんて牧歌的未来だったんだろうと思いつつも、しかし、こういう「サイバー・オルタナティヴ」とも言える物語が当たり前のように書かれて、しかしSFのビジュアル・イメージは、未だにサイバーパンク止まりだということ自体が、この「暗号の子」に書かれた世界の絶望かもとかも思う。よくまあ、これを短編で書いたなあ。ネタとしては上下巻1000ページクラスのアイディアだわ。さすがは「トランジスタ技術の圧縮」の作者であるw 他の収録作も、暗号通貨やNFT、ブロックチェーン技術などをネタに、ネットワークと個人についての物語が書かれていて、それぞれにヴィジョンが違ってて面白い。そこに、ほぼ全部をAIに書かせた「すべての記憶を燃やせ」の、AI詩の物語化の試みとか、実際に亡くなった伯父との記憶を、行かなかったネパール旅行の架空の紀行文に重ねた「行かなかった旅の記録」が挟まって、人とテクノロジーの関係を複層的に見ることも出来るようになってる。その上で、最後に置かれた「ペイル・ブルー・ドット」で、爽やかでさえある、宇宙への夢がアクチュアルに描かれる。ノン・シリーズ短編集として見事な構成。 これ読んでる間、オーディブルでは浦川通「AIは短歌をどう詠むか」を聴いていたのは偶然なのだけど、まるで相互補完してもらってるようで、結局のところ、今、デジタル・テクノロジーを考えるというのは、言葉について考えることなんだろうなとか思う。ともあれ、IT系ライターは、読んどくといいと思う。多分、藤井大洋「まるで渡り鳥のように」と並ぶ、サイバーパンクへのレクイエム。