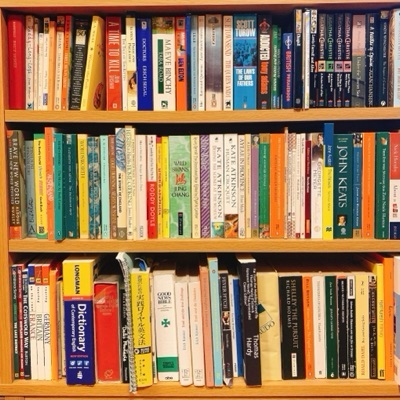ぼくはお金を使わずに生きることにした

4件の記録
 🌜🫖@gn8tea2025年8月11日読み終わった借りてきた「まわりからどう思われるかを気にして、信念のための行動を起こさないなんて、絶対もったいない。だけど、誰もが持っている(あるいはかつて持っていた)欠点をあげつらって他人を批判する権利など、ぼくにはないということも、だんだんわかってきた。たとえ小さくても地球全体のためになる変化を実現するには、お互いに助け合うほうがずっと建設的である。そうすれば、壁はとりはらわれ、本当の対話が可能になる。」 p.266 日々の暮らしのなかで、ちょっと地球環境や差別について考え行動するだけでもまわりとの摩擦が生まれると感じるのに、他者と関わりながら生きていくのは今のわたしにはとても難しいことのように感じられる。筆者のように実践を徹底して突き抜けてしまえば、逆に楽になるのかもしれないけれど。 筆者の目指すところは助け合いによる地域コミュニティの構築であり、趣旨や意義は理解しつつもわたしはその一員にはなれないな……という気持ちになってしまった。資本主義は行き過ぎた個人主義をもたらすと聞いたことがあるが、わたしの価値観もそうなのだろうか。わたしはただ、誰とも深く関らず、それでいて社会的な保証をきちんと受けられる世界を望んでいるのだが、それはあまりにも我が儘なのだろうか。心の通った相互扶助のコミュニティが合うひともいれば、ほどほどの距離感でシステマチックに衣食住が保証される世の中のほうが合うひともいるのではないか、と考えたところで、システムに頼る方式だとどのみち望まない労働に従事する存在が生まれてしまうか……?と思ったり。やっぱり、根本的に生きるのに向いていないのかもしれない。それでも、筆者のように「自分の中の理想主義者と現実主義者を対話させ」ながら、なんとかやりすごすしかない。 「おむついらずの子育て」「タダで月経に対処する」などのコラムは、筆者自身が経験したことがないであろう事柄について簡単にできるかのように(そんなつもりはなかったかもしれないけれど)書くのはちょっと嫌だなと思ったし、あくまでも「健常者」前提に感じられ、全体的にインターセクショナルな視点が欠けている印象。それでも「カネなし」実験の体験談はおもしろく、勇気づけられる本でもあった。
🌜🫖@gn8tea2025年8月11日読み終わった借りてきた「まわりからどう思われるかを気にして、信念のための行動を起こさないなんて、絶対もったいない。だけど、誰もが持っている(あるいはかつて持っていた)欠点をあげつらって他人を批判する権利など、ぼくにはないということも、だんだんわかってきた。たとえ小さくても地球全体のためになる変化を実現するには、お互いに助け合うほうがずっと建設的である。そうすれば、壁はとりはらわれ、本当の対話が可能になる。」 p.266 日々の暮らしのなかで、ちょっと地球環境や差別について考え行動するだけでもまわりとの摩擦が生まれると感じるのに、他者と関わりながら生きていくのは今のわたしにはとても難しいことのように感じられる。筆者のように実践を徹底して突き抜けてしまえば、逆に楽になるのかもしれないけれど。 筆者の目指すところは助け合いによる地域コミュニティの構築であり、趣旨や意義は理解しつつもわたしはその一員にはなれないな……という気持ちになってしまった。資本主義は行き過ぎた個人主義をもたらすと聞いたことがあるが、わたしの価値観もそうなのだろうか。わたしはただ、誰とも深く関らず、それでいて社会的な保証をきちんと受けられる世界を望んでいるのだが、それはあまりにも我が儘なのだろうか。心の通った相互扶助のコミュニティが合うひともいれば、ほどほどの距離感でシステマチックに衣食住が保証される世の中のほうが合うひともいるのではないか、と考えたところで、システムに頼る方式だとどのみち望まない労働に従事する存在が生まれてしまうか……?と思ったり。やっぱり、根本的に生きるのに向いていないのかもしれない。それでも、筆者のように「自分の中の理想主義者と現実主義者を対話させ」ながら、なんとかやりすごすしかない。 「おむついらずの子育て」「タダで月経に対処する」などのコラムは、筆者自身が経験したことがないであろう事柄について簡単にできるかのように(そんなつもりはなかったかもしれないけれど)書くのはちょっと嫌だなと思ったし、あくまでも「健常者」前提に感じられ、全体的にインターセクショナルな視点が欠けている印象。それでも「カネなし」実験の体験談はおもしろく、勇気づけられる本でもあった。
 🌜🫖@gn8tea2025年7月25日読んでる筆者のカーボンフットプリントに対するストイックな姿勢に刺激を受ける。わたしはひとり暮らしをしていた3年間、プラントベースであることを最優先に考えており、安い外国産の食品を購入することも多かった。 もちろんプラントベースを意識することは地球環境にとっていいことだし、倫理的な観点から譲れない点でもあるが、『世界から貧しさをなくす30の方法』を読んで、便利で安い暮らしがいかに外国への搾取で成り立っているかを痛感したのもあり、食にかぎらず地産地消をもっと意識したいと思うようになった。価格的な面から難しい場面も多いけれど、選べるときはなるべく近くで生産されたものを選びたい。
🌜🫖@gn8tea2025年7月25日読んでる筆者のカーボンフットプリントに対するストイックな姿勢に刺激を受ける。わたしはひとり暮らしをしていた3年間、プラントベースであることを最優先に考えており、安い外国産の食品を購入することも多かった。 もちろんプラントベースを意識することは地球環境にとっていいことだし、倫理的な観点から譲れない点でもあるが、『世界から貧しさをなくす30の方法』を読んで、便利で安い暮らしがいかに外国への搾取で成り立っているかを痛感したのもあり、食にかぎらず地産地消をもっと意識したいと思うようになった。価格的な面から難しい場面も多いけれど、選べるときはなるべく近くで生産されたものを選びたい。




 🌜🫖@gn8tea2025年7月6日読んでる借りてきた「自分の信条を象徴的に語るだけですまさず、現実世界にあてはめて実践することだ。頭と心と手の間に矛盾が少ないほど、正直な生き方に近づく。ぼくはそう信じている。」 p27 わたし自身、動物性原料を避けること、新品ではなく中古を利用すること、環境に負荷がかからない選択をすること、個人商店や小さなビジネスを利用することなどを、できる範囲ではあるけれど日々意識している。なぜなら、じぶんの思想や感情となるべく乖離しない生き方がいちばん心地いいから。この文章にはとても共感した。わたしもなるべく誠実に生きたい。 筆者が挑戦した1年間の「カネなし生活」について、事前準備から細かく書かれており、実践も2008年冬からとそこそこ最近なので、ソローの『森の生活』よりもずっと現実的に考えることができておもしろい。ただし、書影にあるとおり筆者は屈強な男性なので、その要素がかなり有利に働いたのではとつい考えてしまう。 この本にかぎらず、脱資本主義、脱消費社会を考えるうえで、他者との繋がり、助け合いが重要視されがちなのはちょっと残念。それが絶対悪だと言いたいわけではないが、誰にも好かれなくても、どこにも馴染めなくても、当然尊重されて生きる権利がある。環境の面から見れば持続可能な社会だとしても、そこで生きるひとびとが個として尊重されなければ、本当の意味での持続可能社会とは言えないだろう。思いやりだけでは差別はなくならない。だからこそ、以前の暮らしの良いところを取り入れながら、誰もが個として尊重され、環境面でも個々の尊厳という観点からも、持続可能な社会のあり方を考えなければならないのではないか。
🌜🫖@gn8tea2025年7月6日読んでる借りてきた「自分の信条を象徴的に語るだけですまさず、現実世界にあてはめて実践することだ。頭と心と手の間に矛盾が少ないほど、正直な生き方に近づく。ぼくはそう信じている。」 p27 わたし自身、動物性原料を避けること、新品ではなく中古を利用すること、環境に負荷がかからない選択をすること、個人商店や小さなビジネスを利用することなどを、できる範囲ではあるけれど日々意識している。なぜなら、じぶんの思想や感情となるべく乖離しない生き方がいちばん心地いいから。この文章にはとても共感した。わたしもなるべく誠実に生きたい。 筆者が挑戦した1年間の「カネなし生活」について、事前準備から細かく書かれており、実践も2008年冬からとそこそこ最近なので、ソローの『森の生活』よりもずっと現実的に考えることができておもしろい。ただし、書影にあるとおり筆者は屈強な男性なので、その要素がかなり有利に働いたのではとつい考えてしまう。 この本にかぎらず、脱資本主義、脱消費社会を考えるうえで、他者との繋がり、助け合いが重要視されがちなのはちょっと残念。それが絶対悪だと言いたいわけではないが、誰にも好かれなくても、どこにも馴染めなくても、当然尊重されて生きる権利がある。環境の面から見れば持続可能な社会だとしても、そこで生きるひとびとが個として尊重されなければ、本当の意味での持続可能社会とは言えないだろう。思いやりだけでは差別はなくならない。だからこそ、以前の暮らしの良いところを取り入れながら、誰もが個として尊重され、環境面でも個々の尊厳という観点からも、持続可能な社会のあり方を考えなければならないのではないか。