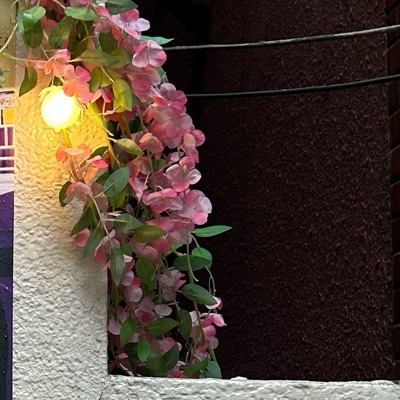日本政治学史

10件の記録
 Prtta@prtta2025年7月7日読んでる「歴史としての戦後史学」(網野善彦)と同じく、第二次大戦以降に分野(ここでは政治学)が辿ってきた道程を彫り出している。網野善彦はナラティブというかんじだが、この本はより俯瞰的・客観的で学問をみつめる学問の眼差しという印象。 「戦後内科学史」とか読んでみたいな。
Prtta@prtta2025年7月7日読んでる「歴史としての戦後史学」(網野善彦)と同じく、第二次大戦以降に分野(ここでは政治学)が辿ってきた道程を彫り出している。網野善彦はナラティブというかんじだが、この本はより俯瞰的・客観的で学問をみつめる学問の眼差しという印象。 「戦後内科学史」とか読んでみたいな。
 かとー@katodayo2025年3月16日読み終わった大学で政治学(正確には公共政策学)を専攻していたというと「政治学ってどんなことを勉強するの?」と聞かれることがあり、そのたびに悩むことが多い。メジャーどころは政治思想、国際政治、比較政治あたりだけど、私がとくに関心をもったEBPM(Evidence Based Policy Making)や熟議民主主義などは決して王道ではないから説明しずらいという理由もある。 それ以上に悩ましいのは、詳しく説明しようとすればするほど、結局私は自分の思い描く社会像のための論拠を集めているだけではないのか?それは学問ではなく、都合のいい手段にしているのではないか?という地味〜〜な葛藤。知的に誠実でいたいと思う一方で、学べば学ぶほど自分の価値観に直面化させられる。政治学を学ぶことは自己を知る喜びもありつつ、視点の偏りを感じる葛藤もあった。 ※別に今は政治家なわけでも、政治学者なわけでもなく、つまりは王道の政治アクターではないのでそこまで悩む必要はないけど、今でも年に数回このことを考えるときがある(執念)。 本書は戦後直後に学会を創設し現代に至るまで、政治学を学問として成立させてきた政治学者たちによる学史だ。 ある知的領域が学問として成立するには、理論や分析方法が再現可能でなければならない。要は「科学」である必要がある。ただし、政治という領域はあまりにも広範で多様であり、再現性を持たせることに苦労するうえに、ハイディガーがそうであったように政治思想はそれ自体が容易に政治を動かす道具にもなる。 そうした宿命のもと日本の政治学者たちがどのように「科学としての政治学」を実現しようとしたか、あるいは科学を否定してきたかという論争に、僭越(×1000!!)ながら自身が感じた葛藤を投影してしまった。 本書の第6章では1990代の政治学の風景として、実験政治学が登場したことで、熟議民主主義を含めた規範理論と科学化がブリッジされたことが書かれている。ただ、結局は演繹的に構築された理論を検証するためにデータが用いられており、「発展」しているようには描かれていない。 「科学の理念は、ある時点で完成する建造物よりは、不断の発展と再構成を求める民主主義のそれに近いのではないか」(終章 p.258) 知的に誠実であることと、何のための誠実さなのかを問うこと。その葛藤の中に政治学があるように読んだ。
かとー@katodayo2025年3月16日読み終わった大学で政治学(正確には公共政策学)を専攻していたというと「政治学ってどんなことを勉強するの?」と聞かれることがあり、そのたびに悩むことが多い。メジャーどころは政治思想、国際政治、比較政治あたりだけど、私がとくに関心をもったEBPM(Evidence Based Policy Making)や熟議民主主義などは決して王道ではないから説明しずらいという理由もある。 それ以上に悩ましいのは、詳しく説明しようとすればするほど、結局私は自分の思い描く社会像のための論拠を集めているだけではないのか?それは学問ではなく、都合のいい手段にしているのではないか?という地味〜〜な葛藤。知的に誠実でいたいと思う一方で、学べば学ぶほど自分の価値観に直面化させられる。政治学を学ぶことは自己を知る喜びもありつつ、視点の偏りを感じる葛藤もあった。 ※別に今は政治家なわけでも、政治学者なわけでもなく、つまりは王道の政治アクターではないのでそこまで悩む必要はないけど、今でも年に数回このことを考えるときがある(執念)。 本書は戦後直後に学会を創設し現代に至るまで、政治学を学問として成立させてきた政治学者たちによる学史だ。 ある知的領域が学問として成立するには、理論や分析方法が再現可能でなければならない。要は「科学」である必要がある。ただし、政治という領域はあまりにも広範で多様であり、再現性を持たせることに苦労するうえに、ハイディガーがそうであったように政治思想はそれ自体が容易に政治を動かす道具にもなる。 そうした宿命のもと日本の政治学者たちがどのように「科学としての政治学」を実現しようとしたか、あるいは科学を否定してきたかという論争に、僭越(×1000!!)ながら自身が感じた葛藤を投影してしまった。 本書の第6章では1990代の政治学の風景として、実験政治学が登場したことで、熟議民主主義を含めた規範理論と科学化がブリッジされたことが書かれている。ただ、結局は演繹的に構築された理論を検証するためにデータが用いられており、「発展」しているようには描かれていない。 「科学の理念は、ある時点で完成する建造物よりは、不断の発展と再構成を求める民主主義のそれに近いのではないか」(終章 p.258) 知的に誠実であることと、何のための誠実さなのかを問うこと。その葛藤の中に政治学があるように読んだ。