支配について(1)

7件の記録
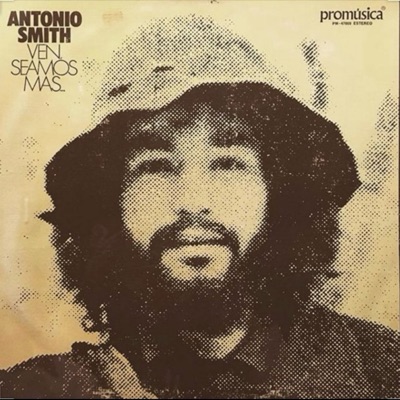 J.B.@hermit_psyche2026年1月1日読み終わった社会学史上において支配という概念を初めて厳密な理論対象として定義し、その内在構造を分析可能な形式へと引き上げた書物である。 本書は一般に知られる三類型支配論の単なる整理ではなく、支配がいかにして成立し、いかなる条件のもとで持続し、なぜ人々がそれに服従するのかという問いを、制度・慣習・経済・心理の交点で徹底的に解剖する試みである。 ここで扱われるのは抽象的理念ではなく、歴史的に実在してきた支配形態の論理的骨格そのものであり、野口雅弘訳によって提示される日本語は、その思考の精度をほとんど損なうことなく伝達している。 ヴェーバーが本巻で明確にする最大の転回点は、支配を単なる暴力や強制力の行使としてではなく、命令が服従される蓋然性として定義した点にある。 この定義によって、支配は力関係ではなく、意味と正当性の問題へと転換される。 人はなぜ命令に従うのか。恐怖ゆえなのか、利害ゆえなのか、それともその命令が「正しい」「当然である」と信じられているからなのか。 本書はこの問いに対し、支配の正統性がいかなる根拠に支えられているかを分析することで応答する。 官僚制の分析において、ヴェーバーは近代社会に特有の合理的・法的支配の完成形を描き出す。 そこでは支配は人格から切り離され、規則と職務に埋め込まれる。 命令するのは個人ではなく、法的に定義された地位であり、服従の対象もまた個人ではなく制度である。 この非人格化された支配は、効率性と予測可能性を極限まで高めるが、同時に人間を機能へと還元し、価値判断を制度の外部へと追放する。 官僚制は合理性の勝利であると同時に、人間が自ら作り出した秩序に拘束される逆説の象徴として描かれる。 これに対し、家産制的支配は支配と生活、権力と人格が未分化のまま結合した形態として提示される。 ここでは支配者の権威は伝統と慣習に根ざし、服従は家族的忠誠や私的関係を媒介として成立する。 官僚制が制度による支配であるならば、家産制は人による支配であり、支配の正当性は合理性ではなく昔からそうであったという時間の厚みによって保証される。 この形態は前近代的な遺制としてではなく、むしろ現代においても繰り返し再生産される支配の原型として描かれている。 封建制の分析において、ヴェーバーは支配を経済的・軍事的相互依存関係として捉える。 封建的支配は命令と服従の単線的関係ではなく、土地と忠誠、保護と奉仕の交換によって成立する重層的な構造を持つ。 ここでは支配は絶対的ではなく、分権化され、契約的要素を含みながら持続する。 この点で封建制は、官僚制の中央集権性とも家産制の私的支配とも異なる独自の論理を持つ支配形態として位置づけられる。 本巻の重要性は、これら三つの支配形態を歴史的段階として序列化することではなく、それぞれが異なる正当性の原理に基づいて成立していることを示した点にある。 支配は常に正当化されなければ持続しない。 そしてその正当化の形式は、合理性、伝統、相互義務といった異なる原理によって構成される。 本書は、支配を道徳的に評価するのではなく、支配が成立する条件そのものを冷徹に分析することで、政治や権力を思考するための概念的装置を提供する。 野口雅弘の訳業は、この理論的密度の高いテクストを、日本語として破綻させることなく提示している点で特筆される。 ヴェーバー特有の長大で屈折した文構造は、思考の運動そのものであり、それを安易に平坦化しない訳文は、本書を単なる概説書ではなく、思考の現場として読者に突きつける。 『支配について I』は、統治論や政治制度論のための書物ではない。 それは、人間がいかにして他者の命令を受け入れてしまう存在であるのかを解明する、人間理解の書である。 官僚制の合理性に安住する者にも、伝統的権威を無批判に受け入れる者にも、本書は支配が成立する条件を暴露することで思考の足場を揺さぶる。 この単巻だけでも、ヴェーバーがなぜ二十世紀社会科学の臨界点に位置する思想家であるのかは、十分すぎるほど明らかになる。
J.B.@hermit_psyche2026年1月1日読み終わった社会学史上において支配という概念を初めて厳密な理論対象として定義し、その内在構造を分析可能な形式へと引き上げた書物である。 本書は一般に知られる三類型支配論の単なる整理ではなく、支配がいかにして成立し、いかなる条件のもとで持続し、なぜ人々がそれに服従するのかという問いを、制度・慣習・経済・心理の交点で徹底的に解剖する試みである。 ここで扱われるのは抽象的理念ではなく、歴史的に実在してきた支配形態の論理的骨格そのものであり、野口雅弘訳によって提示される日本語は、その思考の精度をほとんど損なうことなく伝達している。 ヴェーバーが本巻で明確にする最大の転回点は、支配を単なる暴力や強制力の行使としてではなく、命令が服従される蓋然性として定義した点にある。 この定義によって、支配は力関係ではなく、意味と正当性の問題へと転換される。 人はなぜ命令に従うのか。恐怖ゆえなのか、利害ゆえなのか、それともその命令が「正しい」「当然である」と信じられているからなのか。 本書はこの問いに対し、支配の正統性がいかなる根拠に支えられているかを分析することで応答する。 官僚制の分析において、ヴェーバーは近代社会に特有の合理的・法的支配の完成形を描き出す。 そこでは支配は人格から切り離され、規則と職務に埋め込まれる。 命令するのは個人ではなく、法的に定義された地位であり、服従の対象もまた個人ではなく制度である。 この非人格化された支配は、効率性と予測可能性を極限まで高めるが、同時に人間を機能へと還元し、価値判断を制度の外部へと追放する。 官僚制は合理性の勝利であると同時に、人間が自ら作り出した秩序に拘束される逆説の象徴として描かれる。 これに対し、家産制的支配は支配と生活、権力と人格が未分化のまま結合した形態として提示される。 ここでは支配者の権威は伝統と慣習に根ざし、服従は家族的忠誠や私的関係を媒介として成立する。 官僚制が制度による支配であるならば、家産制は人による支配であり、支配の正当性は合理性ではなく昔からそうであったという時間の厚みによって保証される。 この形態は前近代的な遺制としてではなく、むしろ現代においても繰り返し再生産される支配の原型として描かれている。 封建制の分析において、ヴェーバーは支配を経済的・軍事的相互依存関係として捉える。 封建的支配は命令と服従の単線的関係ではなく、土地と忠誠、保護と奉仕の交換によって成立する重層的な構造を持つ。 ここでは支配は絶対的ではなく、分権化され、契約的要素を含みながら持続する。 この点で封建制は、官僚制の中央集権性とも家産制の私的支配とも異なる独自の論理を持つ支配形態として位置づけられる。 本巻の重要性は、これら三つの支配形態を歴史的段階として序列化することではなく、それぞれが異なる正当性の原理に基づいて成立していることを示した点にある。 支配は常に正当化されなければ持続しない。 そしてその正当化の形式は、合理性、伝統、相互義務といった異なる原理によって構成される。 本書は、支配を道徳的に評価するのではなく、支配が成立する条件そのものを冷徹に分析することで、政治や権力を思考するための概念的装置を提供する。 野口雅弘の訳業は、この理論的密度の高いテクストを、日本語として破綻させることなく提示している点で特筆される。 ヴェーバー特有の長大で屈折した文構造は、思考の運動そのものであり、それを安易に平坦化しない訳文は、本書を単なる概説書ではなく、思考の現場として読者に突きつける。 『支配について I』は、統治論や政治制度論のための書物ではない。 それは、人間がいかにして他者の命令を受け入れてしまう存在であるのかを解明する、人間理解の書である。 官僚制の合理性に安住する者にも、伝統的権威を無批判に受け入れる者にも、本書は支配が成立する条件を暴露することで思考の足場を揺さぶる。 この単巻だけでも、ヴェーバーがなぜ二十世紀社会科学の臨界点に位置する思想家であるのかは、十分すぎるほど明らかになる。



