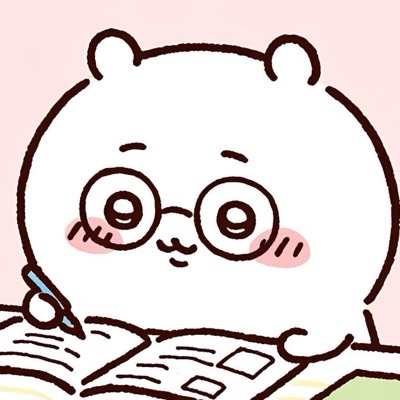方丈記私記
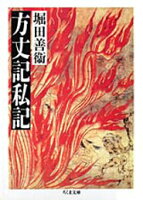
12件の記録
 comi_inu@pandarabun2025年3月7日かつて読んだ堀田善衛は自身が20代の頃に経験した東京大空襲を追憶する。燃え盛る都市、そして燃え尽きた都市を見て思い出したことは方丈記の一節だったという。 方丈記には安元の大火(1177年)や元暦の地震(1185年)について記されている。これらを体験した当時鴨長明は20代、そして方丈記を記したのは50代に入ってから。つまり方丈記は、鴨長明が30年前の"あの頃"を振り返りつつ当時の資料と付き合わせたり足で情報を集めたりしながら書いた回顧録でありルポルタージュであるのだ。 堀田善衛、鴨長明、ふたりがかつて見た燃える都の景色。800年あまりの時間を行き来することで、天変地異や大きな戦乱におけるニホン人の思想へ分け入っていく。 鴨長明というひとは不思議だ。孤児となり後ろ盾がないまま、芸の才能で成り上がる。そして華々しいキャリアをあっさり捨てて山に庵を構える。さみしい暮らしの中で書くことは遷都によって京都がどう変わったかとか、建物の変化や住むひとの移り変わりだとか、都市の災害の弱さと貧困の連鎖についてだ。まるで社会学者のような視線を感じる。家と都市およびそこに生きるひとへ視点をあてるところに鴨長明のヒトトナリがある。皮肉屋で、アウトサイダーで、弱くある存在やひとの衰弱に気がつくひとなんじゃないかと思う。 「歴史は"歴史的"なことだけで出来ているのではない。歴史は、実は"歴史的"なことよりもむしろ、その端っこの方に『この年』とか『この春』だとかとひっくるめるような具合にまとめられてしまっているものの、その具体的内容こそが基調になっている」 作中でいちばんすきな箇所だ。 堀田善衛は鴨長明と友達になろうと本気で思ってこの作品を書いたのだろう。そんな風に思う。
comi_inu@pandarabun2025年3月7日かつて読んだ堀田善衛は自身が20代の頃に経験した東京大空襲を追憶する。燃え盛る都市、そして燃え尽きた都市を見て思い出したことは方丈記の一節だったという。 方丈記には安元の大火(1177年)や元暦の地震(1185年)について記されている。これらを体験した当時鴨長明は20代、そして方丈記を記したのは50代に入ってから。つまり方丈記は、鴨長明が30年前の"あの頃"を振り返りつつ当時の資料と付き合わせたり足で情報を集めたりしながら書いた回顧録でありルポルタージュであるのだ。 堀田善衛、鴨長明、ふたりがかつて見た燃える都の景色。800年あまりの時間を行き来することで、天変地異や大きな戦乱におけるニホン人の思想へ分け入っていく。 鴨長明というひとは不思議だ。孤児となり後ろ盾がないまま、芸の才能で成り上がる。そして華々しいキャリアをあっさり捨てて山に庵を構える。さみしい暮らしの中で書くことは遷都によって京都がどう変わったかとか、建物の変化や住むひとの移り変わりだとか、都市の災害の弱さと貧困の連鎖についてだ。まるで社会学者のような視線を感じる。家と都市およびそこに生きるひとへ視点をあてるところに鴨長明のヒトトナリがある。皮肉屋で、アウトサイダーで、弱くある存在やひとの衰弱に気がつくひとなんじゃないかと思う。 「歴史は"歴史的"なことだけで出来ているのではない。歴史は、実は"歴史的"なことよりもむしろ、その端っこの方に『この年』とか『この春』だとかとひっくるめるような具合にまとめられてしまっているものの、その具体的内容こそが基調になっている」 作中でいちばんすきな箇所だ。 堀田善衛は鴨長明と友達になろうと本気で思ってこの作品を書いたのだろう。そんな風に思う。