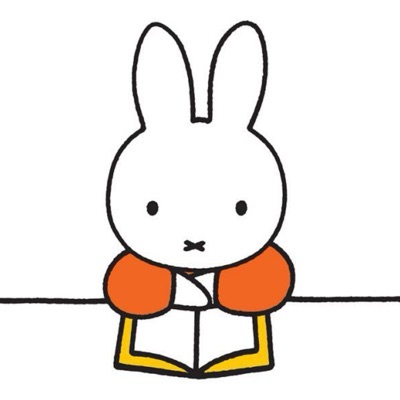シンデレラはどこへ行ったのか

14件の記録
 うゆ@otameshi_8302025年10月10日読み終わった(まず前提として、実際の『シンデレラ』の物語というか伝承?は死と再生の物語であり多分に神話性の強いものだと思うが、本書ではそこでなくいわゆる現代でいうシンデレラストーリー、シンデレラ・コンプレックスという枠組みで『シンデレラ』を扱っている)。 シンデレラ·コンプレックスからジェイン·エア·シンドロームへ。少女小説に受け継がれ生き続けるジェイン·エアの娘たちを追う。そしてシンデレラとシンデレラの姉たちもアップデイトされてゆく。 野心や克己心で道を切り拓くジェイン・エア型のアンの物語を書いたモンゴメリはまったく正反対のタイプの少女パットを主人公にした物語もまた魅力的に仕上げているのは流石。幸せの形って一つじゃないのだ。 『木曜生まれの子どもたち』はこの本の序文で知り読んでみました。読んでいて『魔女と暮らせば』の強烈な姉グウェンドリンのことをしきりに思い出していた。これらはシンデレラの姉の物語でもあるのだなと。類まれな才能に恵まれた弟を持った姉の苛立ち。グウェンドリンの場合は行動を制限されている!私はもっと自分の力を思う存分に使って好きなように生きたいのに!という強すぎる欲望があった。邪悪な性格をしていたけれど何故か憎めないのはどこかで少女たちの、女性たちの心の叫びが重なるからなのだろう。ここではシンデレラ役のキャットも最後には自分から湧き出る力を自らに取り返し反撃する。夢を見て待っているだけのシンデレラはもういない。 私はずっと少女小説を愛し必要として生きてきた。この世に「少女」という枠組みがなくなる新しい地平は来るのだろうか。少女だからこその悩みや葛藤、危険…そういうったものを超克して個々の存在としての物語が描かれる日が?少しずつその枠組みあるいは檻は溶解していくかもしれないしそうなる方が望ましいとも思うが、完全にはなくならないし、男女の差違に目を瞑るのはそれはそれで違う気もする。 著者が最後に文学には力があるから影響を受けても客観性を保たなければ良くない結果になることもあるよ…と述べているのに頷いた。
うゆ@otameshi_8302025年10月10日読み終わった(まず前提として、実際の『シンデレラ』の物語というか伝承?は死と再生の物語であり多分に神話性の強いものだと思うが、本書ではそこでなくいわゆる現代でいうシンデレラストーリー、シンデレラ・コンプレックスという枠組みで『シンデレラ』を扱っている)。 シンデレラ·コンプレックスからジェイン·エア·シンドロームへ。少女小説に受け継がれ生き続けるジェイン·エアの娘たちを追う。そしてシンデレラとシンデレラの姉たちもアップデイトされてゆく。 野心や克己心で道を切り拓くジェイン・エア型のアンの物語を書いたモンゴメリはまったく正反対のタイプの少女パットを主人公にした物語もまた魅力的に仕上げているのは流石。幸せの形って一つじゃないのだ。 『木曜生まれの子どもたち』はこの本の序文で知り読んでみました。読んでいて『魔女と暮らせば』の強烈な姉グウェンドリンのことをしきりに思い出していた。これらはシンデレラの姉の物語でもあるのだなと。類まれな才能に恵まれた弟を持った姉の苛立ち。グウェンドリンの場合は行動を制限されている!私はもっと自分の力を思う存分に使って好きなように生きたいのに!という強すぎる欲望があった。邪悪な性格をしていたけれど何故か憎めないのはどこかで少女たちの、女性たちの心の叫びが重なるからなのだろう。ここではシンデレラ役のキャットも最後には自分から湧き出る力を自らに取り返し反撃する。夢を見て待っているだけのシンデレラはもういない。 私はずっと少女小説を愛し必要として生きてきた。この世に「少女」という枠組みがなくなる新しい地平は来るのだろうか。少女だからこその悩みや葛藤、危険…そういうったものを超克して個々の存在としての物語が描かれる日が?少しずつその枠組みあるいは檻は溶解していくかもしれないしそうなる方が望ましいとも思うが、完全にはなくならないし、男女の差違に目を瞑るのはそれはそれで違う気もする。 著者が最後に文学には力があるから影響を受けても客観性を保たなければ良くない結果になることもあるよ…と述べているのに頷いた。




 うゆ@otameshi_8302025年10月10日読んでるそうか、『赤毛のアン』のアンの喋り方や言葉がどこか仰々しく大袈裟なのは、孤独な生い立ちで本を友として生きてきたからなのか…。つまり人間相手に会話する経験が少なく育ってきたってこと…涙。 本好きが喋り口調もちょっと書き言葉に近くなってしまうのはあるあるなのでわかるな。 松本侑子や河合祥一郎が作品に引用されている文学の徹底解説?をしてくれているらしいから改めて読んでみたくなった。 「少女小説」に『ジェイン・エア』の影響をみるこの本、とても面白いです。今日か明日には読み終えたいな!
うゆ@otameshi_8302025年10月10日読んでるそうか、『赤毛のアン』のアンの喋り方や言葉がどこか仰々しく大袈裟なのは、孤独な生い立ちで本を友として生きてきたからなのか…。つまり人間相手に会話する経験が少なく育ってきたってこと…涙。 本好きが喋り口調もちょっと書き言葉に近くなってしまうのはあるあるなのでわかるな。 松本侑子や河合祥一郎が作品に引用されている文学の徹底解説?をしてくれているらしいから改めて読んでみたくなった。 「少女小説」に『ジェイン・エア』の影響をみるこの本、とても面白いです。今日か明日には読み終えたいな!

 あまね@sennadasilva2025年9月15日読み終わった図書館本シンデレラに始まり、少女小説を経て英米文学からHQを経て新文芸やラノベに手を出した私は、かなり王道なのでは🤫 著者はシンデレラを打開した変換点の女性(白馬の王子様を待たずに自立する女性)としてジェインエアをあげている。そしてそ影響は海を渡り、オルコット、ポーター、ウェブスターが生まれている。 私は童話の後、若草物語、あしながおじさん(氷室冴子氏のマイディアストーリーに載っている家庭小説もしくは少女小説)の後にジェインエアや嵐ヶ丘、高慢と偏見、風と共にという。よくよく顧みれば日本の小説がない😳我が国の場合、少女漫画が補って余り合ってるのではないだろうか🤔 シンデレラにせよジェインエアにせよ、受動か能動か、家庭に入るか働くか、違いはあれども「真実の愛(ラノベでは愚者の決め台詞だがw)」に巡り合う話は色んなパターンで生み出され続けるだろう。 オルコットやウェブスターと別格にカナダ産の不滅の大ベストセラーについても丸々一章述べられている。が、個人的に何度も読んで、全巻読んでもお友達になりたくないという感想しかこの小説には持っていない😓
あまね@sennadasilva2025年9月15日読み終わった図書館本シンデレラに始まり、少女小説を経て英米文学からHQを経て新文芸やラノベに手を出した私は、かなり王道なのでは🤫 著者はシンデレラを打開した変換点の女性(白馬の王子様を待たずに自立する女性)としてジェインエアをあげている。そしてそ影響は海を渡り、オルコット、ポーター、ウェブスターが生まれている。 私は童話の後、若草物語、あしながおじさん(氷室冴子氏のマイディアストーリーに載っている家庭小説もしくは少女小説)の後にジェインエアや嵐ヶ丘、高慢と偏見、風と共にという。よくよく顧みれば日本の小説がない😳我が国の場合、少女漫画が補って余り合ってるのではないだろうか🤔 シンデレラにせよジェインエアにせよ、受動か能動か、家庭に入るか働くか、違いはあれども「真実の愛(ラノベでは愚者の決め台詞だがw)」に巡り合う話は色んなパターンで生み出され続けるだろう。 オルコットやウェブスターと別格にカナダ産の不滅の大ベストセラーについても丸々一章述べられている。が、個人的に何度も読んで、全巻読んでもお友達になりたくないという感想しかこの小説には持っていない😓
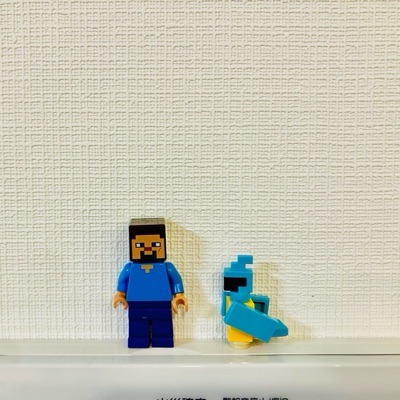 さおり@prn9909082025年6月28日読み終わった赤毛のアンの内容をさらっているところで、知ってる話のはずなのに改めてあらすじだけでも読むとなんだかじんわり泣いてしまった…「木曜日の子どもたち」という物語をわたしは知らなかったけど内容を知って「胸アツ…」となった.「ジェイン・エア」が当時もたらした新しさや可能性の評価をしつつそれが持つ「危うさ」についても触れているところが誠実で良いなと思う. つい先日100分de名著の「侍女の物語」「誓願」の特集をみていて、その物語のなかで禁書とされている本のなかに「ジェイン・エア」があることにニヤリとしていたけど、「ジェイン・エア」がイギリスではそこまでウケなくてアメリカやカナダで受け入れられて、少女小説の発展に一躍買った、みたいなことを知ると、いまアメリカで「侍女の物語」と「誓願」が発禁扱いになっていることがすごく皮肉というか薄ら怖い気もするなと思った. あと心に刻んでおこうと思ったのは「文学は影響力が大きいからこそ素晴らしい。しかし影響を受けている自分を客観的に引き離して見ることが出来なければそれはあらぬ方向へと引っ張っていく呪縛ともなりかねないし逆に、たんにノスタルジーに浸って愛好するだけの消費の対象に成り下がって終わることもあるだろう。その結果当の文学作品を正当に評価することができなくなるのは、実に残念なことである」という言葉、ひとつの作品に触れるときに忘れずにいたいなと思う.
さおり@prn9909082025年6月28日読み終わった赤毛のアンの内容をさらっているところで、知ってる話のはずなのに改めてあらすじだけでも読むとなんだかじんわり泣いてしまった…「木曜日の子どもたち」という物語をわたしは知らなかったけど内容を知って「胸アツ…」となった.「ジェイン・エア」が当時もたらした新しさや可能性の評価をしつつそれが持つ「危うさ」についても触れているところが誠実で良いなと思う. つい先日100分de名著の「侍女の物語」「誓願」の特集をみていて、その物語のなかで禁書とされている本のなかに「ジェイン・エア」があることにニヤリとしていたけど、「ジェイン・エア」がイギリスではそこまでウケなくてアメリカやカナダで受け入れられて、少女小説の発展に一躍買った、みたいなことを知ると、いまアメリカで「侍女の物語」と「誓願」が発禁扱いになっていることがすごく皮肉というか薄ら怖い気もするなと思った. あと心に刻んでおこうと思ったのは「文学は影響力が大きいからこそ素晴らしい。しかし影響を受けている自分を客観的に引き離して見ることが出来なければそれはあらぬ方向へと引っ張っていく呪縛ともなりかねないし逆に、たんにノスタルジーに浸って愛好するだけの消費の対象に成り下がって終わることもあるだろう。その結果当の文学作品を正当に評価することができなくなるのは、実に残念なことである」という言葉、ひとつの作品に触れるときに忘れずにいたいなと思う.