
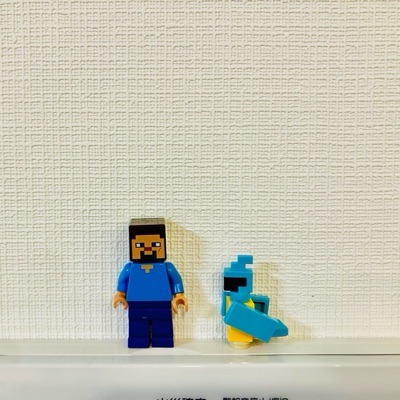
さおり
@prn990908
だって本はさみしがりやさんだから…
- 2026年2月23日
 すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった雪ににている.しろく、つめたく、やわらかい. 舞い降りてくるそのときに、思わず手をのばしてしまう、手をのばして、つめたい、と思ったそのときには、手のひらで溶けて透明になってしまっている.そういう美しさ、かなしくて、さみしい気配.溶けて、ひとつになる.くりかえして、くりかえして、それでもまた、舞い降りるそれに、ふれる.ただ、それだけ、ただ、それだけなのに、いとおしい、と思う.悲しい、と書いて、いとしい、とも読むのだった、と思い返した.
すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった雪ににている.しろく、つめたく、やわらかい. 舞い降りてくるそのときに、思わず手をのばしてしまう、手をのばして、つめたい、と思ったそのときには、手のひらで溶けて透明になってしまっている.そういう美しさ、かなしくて、さみしい気配.溶けて、ひとつになる.くりかえして、くりかえして、それでもまた、舞い降りるそれに、ふれる.ただ、それだけ、ただ、それだけなのに、いとおしい、と思う.悲しい、と書いて、いとしい、とも読むのだった、と思い返した. - 2026年2月23日
 庭の話宇野常寛読み終わったなるほどな〜と思いながら読んでいたら突然(?)「ないなら作るしかない」(by Y2K新書)みたいな話になり二次創作の話題が出てきて面食らってしまった.え、マジでそういう話ですか?と思いながら読んでいたらけど結構真面目にそういう話だった.読んでたらY2K新書聞き直したくなってしまった、聞き直そう. この本読んだあとにこれが読めて良かったな〜という自分だけの流れみたいなものがあり、今回は安吾ちゃんの「堕落論・日本文化私観」のあとにこの「庭の話」が読めてよかったな〜と思った.安吾ちゃんの「戦争と一人の女」と「続戦争と一人の女」に触れられているところがあって、わたしはまだこのふたつを読めてはいないが、でも、堕落論・続堕落論にも通じるところがあって、そしてそういうところを見つめなくてはいけない、みたいなことが書かれており、ちょっと話は逸れるが、やはり坂口安吾というひとの、剥き出しというか嘘のなさ、誤魔化しのなさみたいなところを感じてどうしてか嬉しかった. 連帯、という言葉をよくみかける.わたしのなかにも連帯したい、という気持ちがある、けれどもそれと同じくらいに「分断されられずにいる」ということも大事なんじゃないかなと思った.連帯、というとわたしはつよく手を握る光景を思い浮かべる、でも「分断されずにいる」というのは、視界にとどめておく、くらいのイメージで、「否定をしない」くらいの感覚 つよく手をにぎりたい、という気持ちはたぶん手を取る相手を(わたしが意識していようがいまいが)選んでしまう気がする、どうしても、でも「視界にとどめておく」というか「なんかいるな〜」みたいな感じだったらもっとゆるい感じでつながることができるのではないか、そういうつながりかたもなしにしなくても良いのではないか、そんなふうに思わされる. 「まあどう云う工合になるか、試しに電燈を消してみることだ」 という陰翳礼讃の最後の一文を反芻している
庭の話宇野常寛読み終わったなるほどな〜と思いながら読んでいたら突然(?)「ないなら作るしかない」(by Y2K新書)みたいな話になり二次創作の話題が出てきて面食らってしまった.え、マジでそういう話ですか?と思いながら読んでいたらけど結構真面目にそういう話だった.読んでたらY2K新書聞き直したくなってしまった、聞き直そう. この本読んだあとにこれが読めて良かったな〜という自分だけの流れみたいなものがあり、今回は安吾ちゃんの「堕落論・日本文化私観」のあとにこの「庭の話」が読めてよかったな〜と思った.安吾ちゃんの「戦争と一人の女」と「続戦争と一人の女」に触れられているところがあって、わたしはまだこのふたつを読めてはいないが、でも、堕落論・続堕落論にも通じるところがあって、そしてそういうところを見つめなくてはいけない、みたいなことが書かれており、ちょっと話は逸れるが、やはり坂口安吾というひとの、剥き出しというか嘘のなさ、誤魔化しのなさみたいなところを感じてどうしてか嬉しかった. 連帯、という言葉をよくみかける.わたしのなかにも連帯したい、という気持ちがある、けれどもそれと同じくらいに「分断されられずにいる」ということも大事なんじゃないかなと思った.連帯、というとわたしはつよく手を握る光景を思い浮かべる、でも「分断されずにいる」というのは、視界にとどめておく、くらいのイメージで、「否定をしない」くらいの感覚 つよく手をにぎりたい、という気持ちはたぶん手を取る相手を(わたしが意識していようがいまいが)選んでしまう気がする、どうしても、でも「視界にとどめておく」というか「なんかいるな〜」みたいな感じだったらもっとゆるい感じでつながることができるのではないか、そういうつながりかたもなしにしなくても良いのではないか、そんなふうに思わされる. 「まあどう云う工合になるか、試しに電燈を消してみることだ」 という陰翳礼讃の最後の一文を反芻している - 2026年2月18日
 堕落論・日本文化私観 他二十二篇坂口安吾読み終わった読んでよかった-2026読めば読むほどこのひとのことを好きになってしまった.そもそも立ち読みしたときに、ひとつめの「ピエロ伝道者」の「空にある星を一つ欲しいと思いませんか?」というところがとても気に入って、ほぼ衝動買いしたし、ふたつめの「FARCEに就て」で括弧のなかでめちゃくちゃ喋ってて、そこで非常に親近感が湧いてしまい、もう安吾ちゃんと呼んでいる.安吾ちゃん、ずっと剥き出しで、大丈夫なのかと勝手に心配になるくらい、自分のこころを、感情をさらけ出していて、そういうところがすごく、すごく刺さってしまった.繰り返して読みたいところがたくさんある.これを開いたらこのひとに会える、みたいなものはたくさんあるけれども、これは、もう「いる」という感じだ、それくらいに腸からの言葉ばかりがあって、安吾ちゃんがここにいる.ここにいてずっと、バカヤロウ、みたいに叫んでいる、ひとりの女のひとのことをめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ未練がましくて、太宰の死をめちゃくちゃ悲しんでいて落ち込んでいて、なんかもうそういうの全部ひっくるめて「人間」で、アア〜、好きだな〜ってなってしまう、好きです、うん、これはもう何度でも安吾ちゃんに会いたくなっちゃうやつだな、と思った.
堕落論・日本文化私観 他二十二篇坂口安吾読み終わった読んでよかった-2026読めば読むほどこのひとのことを好きになってしまった.そもそも立ち読みしたときに、ひとつめの「ピエロ伝道者」の「空にある星を一つ欲しいと思いませんか?」というところがとても気に入って、ほぼ衝動買いしたし、ふたつめの「FARCEに就て」で括弧のなかでめちゃくちゃ喋ってて、そこで非常に親近感が湧いてしまい、もう安吾ちゃんと呼んでいる.安吾ちゃん、ずっと剥き出しで、大丈夫なのかと勝手に心配になるくらい、自分のこころを、感情をさらけ出していて、そういうところがすごく、すごく刺さってしまった.繰り返して読みたいところがたくさんある.これを開いたらこのひとに会える、みたいなものはたくさんあるけれども、これは、もう「いる」という感じだ、それくらいに腸からの言葉ばかりがあって、安吾ちゃんがここにいる.ここにいてずっと、バカヤロウ、みたいに叫んでいる、ひとりの女のひとのことをめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ未練がましくて、太宰の死をめちゃくちゃ悲しんでいて落ち込んでいて、なんかもうそういうの全部ひっくるめて「人間」で、アア〜、好きだな〜ってなってしまう、好きです、うん、これはもう何度でも安吾ちゃんに会いたくなっちゃうやつだな、と思った. - 2026年2月13日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わった読んでよかった-2026下巻も「ワァァァァァァァァ〜?!?!?!」ってなりながら読了、終盤にいくにつれ友情に泣かされた.いやもう全人類プロジェクト・ヘイル・メアリーを読んでください.わたしたちはわかりあえる、わかちあえる、助け合うことができる、しょうもない分断になんか屈している場合ではない、目の前にあるその手を取れ
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子読み終わった読んでよかった-2026下巻も「ワァァァァァァァァ〜?!?!?!」ってなりながら読了、終盤にいくにつれ友情に泣かされた.いやもう全人類プロジェクト・ヘイル・メアリーを読んでください.わたしたちはわかりあえる、わかちあえる、助け合うことができる、しょうもない分断になんか屈している場合ではない、目の前にあるその手を取れ - 2026年2月7日
- 2026年1月31日
 名著でひらく男性学 <男>のこれからを考える天野諭,川口遼,杉田俊介,西井開読み終わった読んでよかった-2026ふ、複雑だ〜!でもこの複雑さをちゃんと見つめていきたいなと思った.内容としては複雑だけど対話という形をとって記されているからスラスラ頭に入ってきやすい.1章は4人それぞれの発表とそのあとに少し補足みたいな形がとられていて、1人1冊自分が語りたいテーマについての本の内容とそれについて自分の論を話されていてそこで紹介された本4冊とも読みたくなってしまった.テーマが保育の現場の話から戦争というところまでとても幅広く「うわ〜そっかそうだよな、言われてみたらそういうところに全然考えが及んでなかったよな…」みたいにたくさん思わされた.戦争では男も女も「客体化」される、男は「兵士」として徴兵され、女は「慰安婦」として働かされる、でも男は一瞬まがいものではあるが主体性を取り戻せるときがある、それが慰安婦と肉体関係を結ぶ時だ、という内容を目にしたときに「うわ〜、もう……うわ〜」となってしまった.そのあとに、強制的に徴兵されたという点においては確かに被害者であるといえるかもしれないが、そのことで慰安婦への加害がなかったことになるわけではない、というようなことが書かれていて、いやまじ…まじでそこなんよ…という気持ちになったし、男性学、決してフェミニズムと敵対するようなものではないなと強く感じたし、こういうところをちゃんと深く掘っていけばわたしたちはもっと力強く手を取り合うことができる、そう思う.2章は4人の対話という形で進められて、そこでも昨今のバックラッシュのことやメンズリブの孕んでいるリスクのことや、「キモイ」という言葉のこととかテーマは多岐に渡っていて、読みながらずっと「ンンンンン」と小さく唸っていた.西井さんが「僕はキモイって言われるの嫌です!」と言い切っていてそこがとても良いなと思った.
名著でひらく男性学 <男>のこれからを考える天野諭,川口遼,杉田俊介,西井開読み終わった読んでよかった-2026ふ、複雑だ〜!でもこの複雑さをちゃんと見つめていきたいなと思った.内容としては複雑だけど対話という形をとって記されているからスラスラ頭に入ってきやすい.1章は4人それぞれの発表とそのあとに少し補足みたいな形がとられていて、1人1冊自分が語りたいテーマについての本の内容とそれについて自分の論を話されていてそこで紹介された本4冊とも読みたくなってしまった.テーマが保育の現場の話から戦争というところまでとても幅広く「うわ〜そっかそうだよな、言われてみたらそういうところに全然考えが及んでなかったよな…」みたいにたくさん思わされた.戦争では男も女も「客体化」される、男は「兵士」として徴兵され、女は「慰安婦」として働かされる、でも男は一瞬まがいものではあるが主体性を取り戻せるときがある、それが慰安婦と肉体関係を結ぶ時だ、という内容を目にしたときに「うわ〜、もう……うわ〜」となってしまった.そのあとに、強制的に徴兵されたという点においては確かに被害者であるといえるかもしれないが、そのことで慰安婦への加害がなかったことになるわけではない、というようなことが書かれていて、いやまじ…まじでそこなんよ…という気持ちになったし、男性学、決してフェミニズムと敵対するようなものではないなと強く感じたし、こういうところをちゃんと深く掘っていけばわたしたちはもっと力強く手を取り合うことができる、そう思う.2章は4人の対話という形で進められて、そこでも昨今のバックラッシュのことやメンズリブの孕んでいるリスクのことや、「キモイ」という言葉のこととかテーマは多岐に渡っていて、読みながらずっと「ンンンンン」と小さく唸っていた.西井さんが「僕はキモイって言われるの嫌です!」と言い切っていてそこがとても良いなと思った. - 2026年1月27日
 女優エヴリンの七人の夫テイラー・ジェンキンス・リード,喜須海理子読み終わった読んでよかった-2026エヴリン〜;;終盤にかけてぽろぽろ泣いた…1人の人間の生きた証だった.フィクションだとか実在しないとかそういうことは関係なくこれは1人のひとの人生の話だと思った.間違えて正しくないこともしてそれでもどうしても欲しいものがあって守りたいものがあってときには矛盾が生まれたりする.エヴリン・ヒューゴというひとに、 「世の中のなにもかもがそんなに簡単に割り切れるものではないでしょう?」 とずっと言われている気がした. 人生において彼女がしてきたことの償いのためとか、彼女のいわゆる属性だとかそういうことを軸に語られるのをエヴリンは全く望んでいなくて、ずっとずっとひとりのエヴリン・ヒューゴとしてそこにいて、そこがすごくカッコよかったんだ. 好きとか嫌いとか良い人とか悪い人とかそういう枠組みをこえて、エヴリン・ヒューゴというひとのことを、わたしはこれからふとしたときに思い出すんだろうな、と思った.
女優エヴリンの七人の夫テイラー・ジェンキンス・リード,喜須海理子読み終わった読んでよかった-2026エヴリン〜;;終盤にかけてぽろぽろ泣いた…1人の人間の生きた証だった.フィクションだとか実在しないとかそういうことは関係なくこれは1人のひとの人生の話だと思った.間違えて正しくないこともしてそれでもどうしても欲しいものがあって守りたいものがあってときには矛盾が生まれたりする.エヴリン・ヒューゴというひとに、 「世の中のなにもかもがそんなに簡単に割り切れるものではないでしょう?」 とずっと言われている気がした. 人生において彼女がしてきたことの償いのためとか、彼女のいわゆる属性だとかそういうことを軸に語られるのをエヴリンは全く望んでいなくて、ずっとずっとひとりのエヴリン・ヒューゴとしてそこにいて、そこがすごくカッコよかったんだ. 好きとか嫌いとか良い人とか悪い人とかそういう枠組みをこえて、エヴリン・ヒューゴというひとのことを、わたしはこれからふとしたときに思い出すんだろうな、と思った. - 2026年1月19日
 卍(まんじ)谷崎潤一郎読み終わった全員自分の欲望むきだしで自分の望みをかなえるためだけにしか動いていなくてそれがもう清々しくて良かった、全員自分勝手すぎる〜!でもこうその自分勝手さを取り繕おうとしてないところが潔いというか、変に言い訳しようとしてなくて良い.もとからみんなやばいから出だしからやばいし最後やばさにやばさが加速して「ヒェェ〜」ってなるけどそんな風になりながらも結局読んでしまっている、引力、引力がすごい.延々とひとりの女のひとが自分の身の上のことを話してるだけの構成なのに、そしてそれが普通に普段の話言葉(当時の大阪人からはこの大阪弁が未熟だと評価されたみたいなことが解説にも書いてあったけど、わたしは若干クドさをかんじるところがあるものの普通に上手くない?!と思った.)を使っているのにここまでグッと引き込まれるのどんな文章力なんだよ…と思ってしまった、ちくしょ〜!文章がうまいな!好き!そんで1ページごとにえろいの本当に何?なんなんだよ本当に〜!純文学なのにこんなにどぎまぎしてしまうの謎の罪悪感があるよ!何?本当に?開始40ページで「ああ、憎たらしい、こんな綺麗な体してて!うちあんた殺してやりたい」「殺して、殺して、うちあんたに殺されたい」というやりとりしてるの何なんですかなんでこんなニジソーサクみたいなやりとりが序盤でかわされているんだよ、それでまたギリギリの上品さみたいなのが損なわれていないの本当にすごいななんなんだよなんだこのとんでもない文体は、本当にうらやましいよもう、こういうふうな文章が書きたい
卍(まんじ)谷崎潤一郎読み終わった全員自分の欲望むきだしで自分の望みをかなえるためだけにしか動いていなくてそれがもう清々しくて良かった、全員自分勝手すぎる〜!でもこうその自分勝手さを取り繕おうとしてないところが潔いというか、変に言い訳しようとしてなくて良い.もとからみんなやばいから出だしからやばいし最後やばさにやばさが加速して「ヒェェ〜」ってなるけどそんな風になりながらも結局読んでしまっている、引力、引力がすごい.延々とひとりの女のひとが自分の身の上のことを話してるだけの構成なのに、そしてそれが普通に普段の話言葉(当時の大阪人からはこの大阪弁が未熟だと評価されたみたいなことが解説にも書いてあったけど、わたしは若干クドさをかんじるところがあるものの普通に上手くない?!と思った.)を使っているのにここまでグッと引き込まれるのどんな文章力なんだよ…と思ってしまった、ちくしょ〜!文章がうまいな!好き!そんで1ページごとにえろいの本当に何?なんなんだよ本当に〜!純文学なのにこんなにどぎまぎしてしまうの謎の罪悪感があるよ!何?本当に?開始40ページで「ああ、憎たらしい、こんな綺麗な体してて!うちあんた殺してやりたい」「殺して、殺して、うちあんたに殺されたい」というやりとりしてるの何なんですかなんでこんなニジソーサクみたいなやりとりが序盤でかわされているんだよ、それでまたギリギリの上品さみたいなのが損なわれていないの本当にすごいななんなんだよなんだこのとんでもない文体は、本当にうらやましいよもう、こういうふうな文章が書きたい - 2026年1月11日
 世界の適切な保存永井玲衣読み終わったじぶんが孤独であるということを確かめるためにわたしはきっとこの本を何度も読むんだろうなと思う.孤独がある.ひとつひとつの孤独はとても近くなってでもすぐに離れていってしまう、でもそれでいいんだ、たぶん.孤独を分かち合うことはできない、それはとても痛い、痛い、と思ってそれから寂しい、と思って、じわじわと涙が出た.涙が出るときに目頭があつくなって、それで視界はひとときだけぼやけて、痛みが、寂しさが溶け合った気がしたけど、涙を拭うとまた世界の輪郭はもどる、そういうことのくりかえしなんだ、たぶん. SNSをつかうなら、どうせなら、世界を、わたしに見えた世界を、適切に保存できるようにつかいたい、と思った.伏線回収のされないことば、子どもがふわっとこぼしたことば、いいまつがい、みたいなもの、そういうものを拾ってゆきたいなと思う. 安藤さんのことを教えてくれてありがとうございました.
世界の適切な保存永井玲衣読み終わったじぶんが孤独であるということを確かめるためにわたしはきっとこの本を何度も読むんだろうなと思う.孤独がある.ひとつひとつの孤独はとても近くなってでもすぐに離れていってしまう、でもそれでいいんだ、たぶん.孤独を分かち合うことはできない、それはとても痛い、痛い、と思ってそれから寂しい、と思って、じわじわと涙が出た.涙が出るときに目頭があつくなって、それで視界はひとときだけぼやけて、痛みが、寂しさが溶け合った気がしたけど、涙を拭うとまた世界の輪郭はもどる、そういうことのくりかえしなんだ、たぶん. SNSをつかうなら、どうせなら、世界を、わたしに見えた世界を、適切に保存できるようにつかいたい、と思った.伏線回収のされないことば、子どもがふわっとこぼしたことば、いいまつがい、みたいなもの、そういうものを拾ってゆきたいなと思う. 安藤さんのことを教えてくれてありがとうございました. - 2026年1月8日
 やりなおし世界文学津村記久子読み終わった人の感想を読むのはやっぱり面白いよ.感想を書くひとの眼差しが色濃いものであればあるほどめちゃくちゃ面白いしそれがプロの作家さんならもう間違いない、めちゃくちゃ贅沢な本だった.読んだことある本より読んだことない本のほうが圧倒的に多いのにするする感想が入ってくる、知らない話なのにめちゃくちゃ楽しい、なんなんだこれは〜!最高だ〜!と思いながら読んだし、ちょくちょくでてくる関西弁に「ここで関西弁出てしまうかんじなんですか^^」と関西人としてもちょっと嬉しくなりつつ(?)読んだ.「ペスト」「灯台へ」「遠い部屋遠い声」「マイアントーニア」「怪談」は「え〜ちょっとぜったい読みます…」ってなったし正岡子規のところではちょっともらい泣き(?)してしまったし、緋文字とかリア王とかフィリップ・マーロウのことに触れられてると「ね〜!そう思いますよね!」みたいに思ったし、ジキルとハイドのところでもまだ若干宝島のこと引きずってる(?)話題にしてる(?)(比較対象とはいえ …)ところを読むと「めっちゃ宝島気に入ってはるやん」みたいなね、あともう敦(中島敦)のことはもう津村さんに聞いた方が面白いんとちゃうんかみたいに思ってしまったな〜、なんというか「本を読むのは楽しいんですよ!」ということを全身で伝えてくれるような本だった、新年一発目に幸先の良い読書ができて良いな〜と思えたし、文庫化にあたり追加されたあとがきがとても真摯でぐっときた.解説も解説でめっちゃ良いし本の最後(?)のところに「こういう本でてますよ」みたいな紹介のページあるじゃないですか、あれも「粋〜!蔦重めっちゃこういうことしそう〜!(べらぼう観てたんで…すみません…)」と思った.
やりなおし世界文学津村記久子読み終わった人の感想を読むのはやっぱり面白いよ.感想を書くひとの眼差しが色濃いものであればあるほどめちゃくちゃ面白いしそれがプロの作家さんならもう間違いない、めちゃくちゃ贅沢な本だった.読んだことある本より読んだことない本のほうが圧倒的に多いのにするする感想が入ってくる、知らない話なのにめちゃくちゃ楽しい、なんなんだこれは〜!最高だ〜!と思いながら読んだし、ちょくちょくでてくる関西弁に「ここで関西弁出てしまうかんじなんですか^^」と関西人としてもちょっと嬉しくなりつつ(?)読んだ.「ペスト」「灯台へ」「遠い部屋遠い声」「マイアントーニア」「怪談」は「え〜ちょっとぜったい読みます…」ってなったし正岡子規のところではちょっともらい泣き(?)してしまったし、緋文字とかリア王とかフィリップ・マーロウのことに触れられてると「ね〜!そう思いますよね!」みたいに思ったし、ジキルとハイドのところでもまだ若干宝島のこと引きずってる(?)話題にしてる(?)(比較対象とはいえ …)ところを読むと「めっちゃ宝島気に入ってはるやん」みたいなね、あともう敦(中島敦)のことはもう津村さんに聞いた方が面白いんとちゃうんかみたいに思ってしまったな〜、なんというか「本を読むのは楽しいんですよ!」ということを全身で伝えてくれるような本だった、新年一発目に幸先の良い読書ができて良いな〜と思えたし、文庫化にあたり追加されたあとがきがとても真摯でぐっときた.解説も解説でめっちゃ良いし本の最後(?)のところに「こういう本でてますよ」みたいな紹介のページあるじゃないですか、あれも「粋〜!蔦重めっちゃこういうことしそう〜!(べらぼう観てたんで…すみません…)」と思った. - 2025年12月30日
 読み終わったお金というのはインフラで、それは私たちの生活に直結している、もちろん戦時中であろうがそれが変わるはずもなく、そのインフラをどうにかして生活者のために守り、滞りなく流れるように努力してくれた銀行員さんたちの姿が見えた. 一般職員のひとはどうにかして生活者である庶民のひとの財産を守ろうとしてくれたり、それなりの役職についている人たちは和平交渉とか終戦にこぎつけようとしてくれてるのに全部軍のゴミクズみたいなプライドのせいで後手後手に回ったり水泡に帰していたりしてマジで大日本帝国と戦争はマジでクソ、クソ以下でしかない、戦争はただただ愚行、勝っても負けてもリターンがゼロどころかマイナスしか残らない.誰得なんですか?少なくとも私たち一般市民になんの利益ももたらさないよ. 8月6日に広島に原子爆弾が落とされて、9日に一番電車が走ったことを私はポルノとNHKの企画で初めて知ったけれど、その一番電車が走る一日前、8月8日に、銀行はもう営業を開始していたことを、私はこの本で初めて知りました.原爆が落ちたあと火事になって、そのなかで、諸々の資産を守ろうとして消火活動をしていたのは女子行員さんたち(男性はほぼ徴兵されていた…)という記述を読んでじんわり泣いた…それだけじゃなくて外地(日本の植民地であったところ)の銀行員さんたちも自分たちのことは二の次三の次でそこで暮らす人たち、それは日本人であるとかそうではないとか関係なく、ただそこで生活をしている人たちのために、ギリギリまで通常通りの営業をしてくれようとしていたりだとか、読み進めるたびにいちいちグッときてしまって、なんかもう感情がダメでした.たぶん正義感とかそういうことじゃなくて一番電車のときのインタビュー晴一さんが「 だって仕事やもん、という感覚なのだったと思う」と言っていたように、自分の仕事として全うしようとしていたんだろうな、と思って、そう思うと余計泣けてしまった. 読めてよかったです. できたらドラマにしてほしい、大河ドラマ、どうですか…
読み終わったお金というのはインフラで、それは私たちの生活に直結している、もちろん戦時中であろうがそれが変わるはずもなく、そのインフラをどうにかして生活者のために守り、滞りなく流れるように努力してくれた銀行員さんたちの姿が見えた. 一般職員のひとはどうにかして生活者である庶民のひとの財産を守ろうとしてくれたり、それなりの役職についている人たちは和平交渉とか終戦にこぎつけようとしてくれてるのに全部軍のゴミクズみたいなプライドのせいで後手後手に回ったり水泡に帰していたりしてマジで大日本帝国と戦争はマジでクソ、クソ以下でしかない、戦争はただただ愚行、勝っても負けてもリターンがゼロどころかマイナスしか残らない.誰得なんですか?少なくとも私たち一般市民になんの利益ももたらさないよ. 8月6日に広島に原子爆弾が落とされて、9日に一番電車が走ったことを私はポルノとNHKの企画で初めて知ったけれど、その一番電車が走る一日前、8月8日に、銀行はもう営業を開始していたことを、私はこの本で初めて知りました.原爆が落ちたあと火事になって、そのなかで、諸々の資産を守ろうとして消火活動をしていたのは女子行員さんたち(男性はほぼ徴兵されていた…)という記述を読んでじんわり泣いた…それだけじゃなくて外地(日本の植民地であったところ)の銀行員さんたちも自分たちのことは二の次三の次でそこで暮らす人たち、それは日本人であるとかそうではないとか関係なく、ただそこで生活をしている人たちのために、ギリギリまで通常通りの営業をしてくれようとしていたりだとか、読み進めるたびにいちいちグッときてしまって、なんかもう感情がダメでした.たぶん正義感とかそういうことじゃなくて一番電車のときのインタビュー晴一さんが「 だって仕事やもん、という感覚なのだったと思う」と言っていたように、自分の仕事として全うしようとしていたんだろうな、と思って、そう思うと余計泣けてしまった. 読めてよかったです. できたらドラマにしてほしい、大河ドラマ、どうですか… - 2025年12月20日
- 2025年12月6日
 考察する若者たち三宅香帆読み終わった読み進めながら「そ、それでも私は自分で考えたいし選びたいよ…🥲」という気持ちが強くなったので最終章の「最適化に抗う」がとてもグッときた;;報われたいと思うのは悪いことじゃなく否定することでもなくきっと皆持っているものでででもそれをやらたに増幅させてしまう、そこを求めざるを得なくなってしまうというの、社会全体として疲れて弱っちゃってるんだろうな…と思ってしまった🥲ひらやすみの最終回を観たばかりだから「やはり一人ひとりにとって『ひらやすみ』みたいなものが必要…」と思ってしまった.あとがきが優しかった.
考察する若者たち三宅香帆読み終わった読み進めながら「そ、それでも私は自分で考えたいし選びたいよ…🥲」という気持ちが強くなったので最終章の「最適化に抗う」がとてもグッときた;;報われたいと思うのは悪いことじゃなく否定することでもなくきっと皆持っているものでででもそれをやらたに増幅させてしまう、そこを求めざるを得なくなってしまうというの、社会全体として疲れて弱っちゃってるんだろうな…と思ってしまった🥲ひらやすみの最終回を観たばかりだから「やはり一人ひとりにとって『ひらやすみ』みたいなものが必要…」と思ってしまった.あとがきが優しかった. - 2025年12月4日
 デスチェアの殺人 下M・W・クレイヴン,東野さやか読み終わった「こんな最低最悪なことある⁉️」がずっと更新され続ける.地獄という言葉も凄惨という言葉もこの物語の展開を前にするとむちゃくちゃ軽々しく薄っぺらいものに思えてしまう.悲惨なピタゴラスイッチすぎるしその間に挟まれるふとした文言に「いやそれは我が国のことでは…」みたいになって「グェ……」とそこでも精神的にやられてしまう. ティリーがポーの隣にいてくれる日がこんなに心強く思える日がくるなんて…😭ティリー本当にポーの相棒でいてくれてありがとう…😭一緒に壁壊すシーンが最高に相棒でここ描いてくれてマジでありがとうございます…😭🙏🏻と思った.2人の間に恋はまったくないけど相棒としての絶対的な信頼と愛がそこにあり、この物語において光だ…となった、絶対絶対絶対また2人に戻ってきてほしい😭
デスチェアの殺人 下M・W・クレイヴン,東野さやか読み終わった「こんな最低最悪なことある⁉️」がずっと更新され続ける.地獄という言葉も凄惨という言葉もこの物語の展開を前にするとむちゃくちゃ軽々しく薄っぺらいものに思えてしまう.悲惨なピタゴラスイッチすぎるしその間に挟まれるふとした文言に「いやそれは我が国のことでは…」みたいになって「グェ……」とそこでも精神的にやられてしまう. ティリーがポーの隣にいてくれる日がこんなに心強く思える日がくるなんて…😭ティリー本当にポーの相棒でいてくれてありがとう…😭一緒に壁壊すシーンが最高に相棒でここ描いてくれてマジでありがとうございます…😭🙏🏻と思った.2人の間に恋はまったくないけど相棒としての絶対的な信頼と愛がそこにあり、この物語において光だ…となった、絶対絶対絶対また2人に戻ってきてほしい😭 - 2025年11月29日
- 2025年11月20日
 あなたが政治について語る時平野啓一郎読み終わった世情が世情だしこのタイトルだし読みながらめちゃくちゃヒリヒリしてしまった😭口は絶対に噤まないぞ、と思う.おかしいなと思った事を言える人でありたいし、日常の小さな違和感をやり過ごしてしまわないようにしたいなと思った…
あなたが政治について語る時平野啓一郎読み終わった世情が世情だしこのタイトルだし読みながらめちゃくちゃヒリヒリしてしまった😭口は絶対に噤まないぞ、と思う.おかしいなと思った事を言える人でありたいし、日常の小さな違和感をやり過ごしてしまわないようにしたいなと思った… - 2025年11月13日
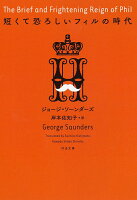 短くて恐ろしいフィルの時代ジョージ・ソーンダーズ,岸本佐知子読み終わったドンズバで今、今すぎる、読み進める度にそう思ってしまったな.単行本が11年だから14年前なのか〜ってなって人の芯にあるものは美しいものも醜いものも本当に変わらないんだろうなと思ったしだったらもうそうであると認めた上で優しく穏やかに生きたいよと思いました.
短くて恐ろしいフィルの時代ジョージ・ソーンダーズ,岸本佐知子読み終わったドンズバで今、今すぎる、読み進める度にそう思ってしまったな.単行本が11年だから14年前なのか〜ってなって人の芯にあるものは美しいものも醜いものも本当に変わらないんだろうなと思ったしだったらもうそうであると認めた上で優しく穏やかに生きたいよと思いました. - 2025年11月10日
 本はどう読むか清水幾太郎読み終わったこのタイトルでまさか大杉栄と伊藤野枝について触れられると思ってなくてしかもその内容がセンセーショナルで「いやちょっと待って待って話のイントロとして引きが強すぎる😭」とまず思いました😭いやこのタイトルで歴史のうねりみたいなものをダイレクトに感じるとか思ってなくて…戦時中に「東京もうなくなるっぽいからもう持っててもしょうがない」と思って手持ちの本大量に売った話とか読んで胸が痛くなった…いやもう本当に勘弁してくれよと思う.「読み方」についても当たり前だけど)ちゃんと語ってくれているんだけどこういう話のインパクトがところどころ強くて「ちょっと待ってくれ」みたいな気持ちになるところがなかなかあった.で、「どう読むか」というところについて「自分が面白いと思ったものを読んだらいいよ」「とちゅうで読むの止めてもいいよ」「読書だけじゃなくて楽しいと思ったことしたらいいよ」みたいなことが書かれていて「や、やさしい…」と思いました.最後に『華氏451』について書いてあって「え…予言?」と.思った.
本はどう読むか清水幾太郎読み終わったこのタイトルでまさか大杉栄と伊藤野枝について触れられると思ってなくてしかもその内容がセンセーショナルで「いやちょっと待って待って話のイントロとして引きが強すぎる😭」とまず思いました😭いやこのタイトルで歴史のうねりみたいなものをダイレクトに感じるとか思ってなくて…戦時中に「東京もうなくなるっぽいからもう持っててもしょうがない」と思って手持ちの本大量に売った話とか読んで胸が痛くなった…いやもう本当に勘弁してくれよと思う.「読み方」についても当たり前だけど)ちゃんと語ってくれているんだけどこういう話のインパクトがところどころ強くて「ちょっと待ってくれ」みたいな気持ちになるところがなかなかあった.で、「どう読むか」というところについて「自分が面白いと思ったものを読んだらいいよ」「とちゅうで読むの止めてもいいよ」「読書だけじゃなくて楽しいと思ったことしたらいいよ」みたいなことが書かれていて「や、やさしい…」と思いました.最後に『華氏451』について書いてあって「え…予言?」と.思った. - 2025年11月9日
 さよならジャバウォック伊坂幸太郎読み終わったさよならジャバウォック〜‼️面白かった〜‼️伊坂作品を読んでいるときのこう「どこに連れていかれるんだろう?」というワクワク感がめっちゃ好きだ〜‼️となったし鏡の国のアリスが下敷きにされてるっぽくて「それ〜‼️」と思った.伊坂作品に出てくるキャラクター割と過去が重かったりとかとんでもない事情を抱えていたりするんだけどそういう面だけではなくてあるところでは軽やかであったりとか、ユーモアのあることをぽろっと言ったりするところとか、そういうところがめっちゃ好きなんだわたしは〜‼️とめっちゃ思った‼️
さよならジャバウォック伊坂幸太郎読み終わったさよならジャバウォック〜‼️面白かった〜‼️伊坂作品を読んでいるときのこう「どこに連れていかれるんだろう?」というワクワク感がめっちゃ好きだ〜‼️となったし鏡の国のアリスが下敷きにされてるっぽくて「それ〜‼️」と思った.伊坂作品に出てくるキャラクター割と過去が重かったりとかとんでもない事情を抱えていたりするんだけどそういう面だけではなくてあるところでは軽やかであったりとか、ユーモアのあることをぽろっと言ったりするところとか、そういうところがめっちゃ好きなんだわたしは〜‼️とめっちゃ思った‼️ - 2025年11月7日
 教養主義の没落竹内洋読み終わった1章〜2章くらいまでは「へ〜そうなんですね……」としかならなくて「これは完走できるのか…?」と思いながら読んでいたけど3章からは「おもしろいな…」となり読めた.最終章のアンティ・クライマックスのところがとくに面白いなと思った.「教養主義」というもののブランド力がどう培われていったのか、そしてどういう流れのなかでその求心力を失ってしまったのかということを順序立てて書いてくれていて良かった.でも「ハビトゥス」という言葉に関しては「え…?何…?」ってなったままだった.
教養主義の没落竹内洋読み終わった1章〜2章くらいまでは「へ〜そうなんですね……」としかならなくて「これは完走できるのか…?」と思いながら読んでいたけど3章からは「おもしろいな…」となり読めた.最終章のアンティ・クライマックスのところがとくに面白いなと思った.「教養主義」というもののブランド力がどう培われていったのか、そしてどういう流れのなかでその求心力を失ってしまったのかということを順序立てて書いてくれていて良かった.でも「ハビトゥス」という言葉に関しては「え…?何…?」ってなったままだった.
読み込み中...


