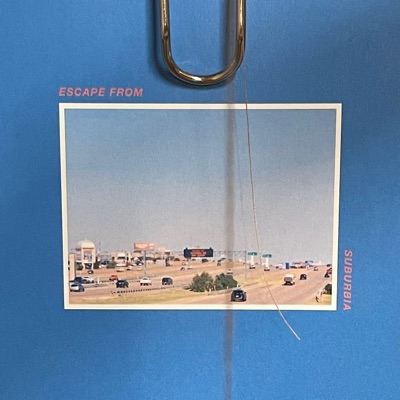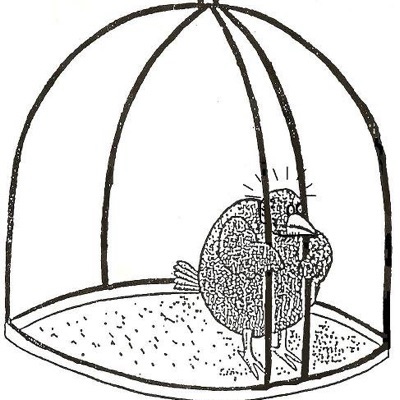やがて哀しき外国語

13件の記録
- ハル@harubooks2026年1月22日読み終わった何回めかの再読。 1990年代にアメリカにいた村上春樹のエッセイ。 「現在の一般的アメリカ人が感じている深い疲弊の感覚は、現在の日本人が感じているむずむずした居心地の悪さと裏表をなすものではないかという気がする。単純に言ってしまえば、明確な理念のある疲れと、明確な理念のない居心地の悪さ、ということになるかもしれない。」 —『やがて哀しき外国語 (講談社文庫)』村上春樹著 2026年に読むと アメリカという社会の変化と、鏡としての日本の変容ぶりがわかる。 村上春樹はそこに横たわっていただろう構造に触れるのが上手いなと思う。

 ゆうと@yuto072026年1月19日読み終わった「外野席に寝ころんでビールを飲んでいて、ヒルトンが二塁打を打ったときに、突然「そうだ、小説を書こう」と思ったこと。そのようにして僕が小説を書くようになったことを。」
ゆうと@yuto072026年1月19日読み終わった「外野席に寝ころんでビールを飲んでいて、ヒルトンが二塁打を打ったときに、突然「そうだ、小説を書こう」と思ったこと。そのようにして僕が小説を書くようになったことを。」
 ゆうと@yuto072026年1月18日読み終わった「遠い太鼓」に続いてとても面白い海外滞在エッセイ 「僕に必要だったのは自分というものを確立するための時間であり、経験であったんだ。それは何もとくべつな経験である必要はないんだ。それはごく普通の経験でかまわないんだ。でもそれは自分のからだにしっかりとしみこんでいく経験でなくてはならないんだ。学生だったころ、僕は何かを書きたかったけど、何を書けばいいのかわからなかった。何を書けばいいのかを発見するために、僕には七年という歳月とハード・ワークが必要だったんだよ、たぶん」
ゆうと@yuto072026年1月18日読み終わった「遠い太鼓」に続いてとても面白い海外滞在エッセイ 「僕に必要だったのは自分というものを確立するための時間であり、経験であったんだ。それは何もとくべつな経験である必要はないんだ。それはごく普通の経験でかまわないんだ。でもそれは自分のからだにしっかりとしみこんでいく経験でなくてはならないんだ。学生だったころ、僕は何かを書きたかったけど、何を書けばいいのかわからなかった。何を書けばいいのかを発見するために、僕には七年という歳月とハード・ワークが必要だったんだよ、たぶん」
 中根龍一郎@ryo_nakane2025年5月14日かつて読んだ読み返したプリンストン大学の名前をはじめて意識したのは村上春樹の赴任先としてだった。その村上はプリンストン大学訪問のきっかけを、F・スコット・フィッツジェラルドの母校だったからと書く。異郷の地名はそのように、しばしば、自分が思い入れを持っているだれだれゆかりの地だ、という形で記憶される。村上春樹がエッセイに書いていたな、というふうにプリンストンを記憶しているように。 きのう読み終わった『知られざるコンピューターの思想史』は、プリンストン大学創立200周年の会議、『The Problems of Mathematics(数学の諸問題)』に集まった数学者たちの写真からはじまる。そこにはフォン・ノイマン、ゲーデル、クワイン、タルスキをはじめ、現代史に重要人物として名を残す学者たちがならんでいて、当時のプリンストンにおける数理論理学の隆興を思わせる。でも『やがて哀しき外国語』のなかで、そうした数学者、論理学者たちの名前が語られることはない。もちろん人には興味関心や好む分野の違いというものがあるからで、その「不記載」はべつに大きな問題ではない。ただ、プリンストンの歴史をすこし知ってから改めてこの村上のプリンストン記を読み返すと、意外と以前は気づかなかったところで立ち止まる。 「ラトガーズという州立大学(ここはもっと庶民的な大学である)の学生と話していたら」という感じで、さらりと村上に記される、プリンストンの近くの大学がある。一見まるで印象に残らない(私も忘れていた)。でもそんなラトガーズ(ラトガース)大学は、『知られざるコンピューターの思想史』の掉尾をかざる、分析哲学のはじまりにはずみをつけた、デイヴィドソン会議の舞台だ。 『知られざるコンピューターの思想史』によると、ラトガーズ大学の哲学科は、ハーヴァードやプリンストンをおさえて全米2位に位置づけられることもあるという。そのランクインは哲学科に限った話で、ラトガーズにおいてはただ哲学科だけが、デイヴィドソン会議をきっかけに、学科としてぬきんでたのだという。 村上がプリンストンに赴任したのは1990年だから、1984年のデイヴィドソン会議から6年後だ。そのインパクトは村上にいまひとつ届いていないようにみえる。ラトガーズ大学はプリンストン大学より「もっと庶民的な大学」だ。そういうふうにして見過ごされる地名、だれかの思い入れと結びついた、けれど筆者にはとくに関係のない地名が、たぶん旅行記にはたくさんある。そして旅行者もそういうふうにしてたくさんの地名を通り過ぎている。 もうひとつ、1990年代当時のプリンストン大学のインテリたちのスノッブな感じについて、村上がすこし冗談めかして、コレクトなビールとコレクトでないビール、という形で語る一幕がある。ここでいうコレクトは、もちろんビール生産における倫理性といったような問題ではなくて、インテリとして飲んでいて恥ずかしくないビール、というくらいのニュアンスだ。 僕が見たところでは、プリンストン大学の関係者はだいたいにおいて輸入ビールを好んで飲むようである。ハイネケンか、ギネスか、ベックか、そのあたりを飲んでおけば「正しきこと」とみなされる。アメリカン・ビールでもボストンの「サミュエル・アダムズ」やらサンフランシスコの「アンカー・スティーム」あたりだと、あまり一般的なブランドではないから許される。 (『やがて哀しき外国語』文庫版p.42) はじめて読んだときは、そういうものなんだ、まあ感覚としてはわからなくはない、大手の、誰もが知っているビールより、マイナーな地ビールを飲んでいるほうが、「わかってる」感じが出るという話かな、と思った。でもニュージャージーやアメリカの歴史を知ってくると、すこし受け取り方がちがってくる。 ニュージャージー州は、隣のニューヨーク州がかつてオランダ領だったことで、オランダ移民が多かった。プリンストンという地名も、オランダ王家がオラニエ公だったため、公(prince)のタウン、として呼ばれていたためだという。プリンストン大学はそんなニュージャージー州に生まれた大学で、1920年代以降の発展のなかで、ドイツやオーストリアから優れた数学者を招聘した。ハイネケンはオランダのビールだ。ベックはドイツビール。ギネスはアイルランドビールだが、これはアイルランド系移民がアメリカの北東部に多く住んだことに由来するのかもしれない。『知られざるコンピューターの思想史』でアイルランドについて語られることはなかったので、これは想像になるけれど、まず歴史的事実として、19世紀にアメリカへ流入していくアイルランド系移民は基本的にカトリックだ。そうしてプロテスタント国家のアメリカでかれらを受け入れたのは、宗教的に寛容なオランダの風土を残す北東部だったのかもしれない。そういうニュージャージー州の歴史を考えると、プリンストン大学のインテリたちの、ヨーロッパとの結びつきは、単に気取りのようなものとしてとらえるよりも、もうすこし地縁的なものを想像させる。かれらに教える先生たちの故郷や、親たちの祖国や、友達の家族のルーツや、そうした郷愁と共感から生まれる愛着のようなものを連想する。 固有名詞の知識が変わっていくと、その固有名詞の位置づけが変わってくる。位置づけが変わってくると、むかし接した固有名詞の見え方が変わってくる。それはとても楽しいものだ。 でも一方で、ある文化のつくりについて、きれいな原因と結果を想像して、その起源を再構築しようとする態度は、けっこう危険なものだということも忘れてはいけない。歴史的な整理というのはものごとを関係の総体に還元してしまう。そのようにしてきれいに整理された関係というのは、かならずたくさんの余剰物を見落としてしまうだろう。プリンストン大学のインテリたちのビールの趣味だって、ほんとうに、村上が報告しているように、マイナー趣味を尊ぶ文化だったり、あるいはアメリカナイゼーションを内省する左翼っぽい行動原理かもしれない。そこには複数の物語を想像できる。 大切なのはたぶん、そのように想像できる物語の数を増やしていくことであり、その複数性をたわむれながら、単一性にからめとられないようにすることだ。
中根龍一郎@ryo_nakane2025年5月14日かつて読んだ読み返したプリンストン大学の名前をはじめて意識したのは村上春樹の赴任先としてだった。その村上はプリンストン大学訪問のきっかけを、F・スコット・フィッツジェラルドの母校だったからと書く。異郷の地名はそのように、しばしば、自分が思い入れを持っているだれだれゆかりの地だ、という形で記憶される。村上春樹がエッセイに書いていたな、というふうにプリンストンを記憶しているように。 きのう読み終わった『知られざるコンピューターの思想史』は、プリンストン大学創立200周年の会議、『The Problems of Mathematics(数学の諸問題)』に集まった数学者たちの写真からはじまる。そこにはフォン・ノイマン、ゲーデル、クワイン、タルスキをはじめ、現代史に重要人物として名を残す学者たちがならんでいて、当時のプリンストンにおける数理論理学の隆興を思わせる。でも『やがて哀しき外国語』のなかで、そうした数学者、論理学者たちの名前が語られることはない。もちろん人には興味関心や好む分野の違いというものがあるからで、その「不記載」はべつに大きな問題ではない。ただ、プリンストンの歴史をすこし知ってから改めてこの村上のプリンストン記を読み返すと、意外と以前は気づかなかったところで立ち止まる。 「ラトガーズという州立大学(ここはもっと庶民的な大学である)の学生と話していたら」という感じで、さらりと村上に記される、プリンストンの近くの大学がある。一見まるで印象に残らない(私も忘れていた)。でもそんなラトガーズ(ラトガース)大学は、『知られざるコンピューターの思想史』の掉尾をかざる、分析哲学のはじまりにはずみをつけた、デイヴィドソン会議の舞台だ。 『知られざるコンピューターの思想史』によると、ラトガーズ大学の哲学科は、ハーヴァードやプリンストンをおさえて全米2位に位置づけられることもあるという。そのランクインは哲学科に限った話で、ラトガーズにおいてはただ哲学科だけが、デイヴィドソン会議をきっかけに、学科としてぬきんでたのだという。 村上がプリンストンに赴任したのは1990年だから、1984年のデイヴィドソン会議から6年後だ。そのインパクトは村上にいまひとつ届いていないようにみえる。ラトガーズ大学はプリンストン大学より「もっと庶民的な大学」だ。そういうふうにして見過ごされる地名、だれかの思い入れと結びついた、けれど筆者にはとくに関係のない地名が、たぶん旅行記にはたくさんある。そして旅行者もそういうふうにしてたくさんの地名を通り過ぎている。 もうひとつ、1990年代当時のプリンストン大学のインテリたちのスノッブな感じについて、村上がすこし冗談めかして、コレクトなビールとコレクトでないビール、という形で語る一幕がある。ここでいうコレクトは、もちろんビール生産における倫理性といったような問題ではなくて、インテリとして飲んでいて恥ずかしくないビール、というくらいのニュアンスだ。 僕が見たところでは、プリンストン大学の関係者はだいたいにおいて輸入ビールを好んで飲むようである。ハイネケンか、ギネスか、ベックか、そのあたりを飲んでおけば「正しきこと」とみなされる。アメリカン・ビールでもボストンの「サミュエル・アダムズ」やらサンフランシスコの「アンカー・スティーム」あたりだと、あまり一般的なブランドではないから許される。 (『やがて哀しき外国語』文庫版p.42) はじめて読んだときは、そういうものなんだ、まあ感覚としてはわからなくはない、大手の、誰もが知っているビールより、マイナーな地ビールを飲んでいるほうが、「わかってる」感じが出るという話かな、と思った。でもニュージャージーやアメリカの歴史を知ってくると、すこし受け取り方がちがってくる。 ニュージャージー州は、隣のニューヨーク州がかつてオランダ領だったことで、オランダ移民が多かった。プリンストンという地名も、オランダ王家がオラニエ公だったため、公(prince)のタウン、として呼ばれていたためだという。プリンストン大学はそんなニュージャージー州に生まれた大学で、1920年代以降の発展のなかで、ドイツやオーストリアから優れた数学者を招聘した。ハイネケンはオランダのビールだ。ベックはドイツビール。ギネスはアイルランドビールだが、これはアイルランド系移民がアメリカの北東部に多く住んだことに由来するのかもしれない。『知られざるコンピューターの思想史』でアイルランドについて語られることはなかったので、これは想像になるけれど、まず歴史的事実として、19世紀にアメリカへ流入していくアイルランド系移民は基本的にカトリックだ。そうしてプロテスタント国家のアメリカでかれらを受け入れたのは、宗教的に寛容なオランダの風土を残す北東部だったのかもしれない。そういうニュージャージー州の歴史を考えると、プリンストン大学のインテリたちの、ヨーロッパとの結びつきは、単に気取りのようなものとしてとらえるよりも、もうすこし地縁的なものを想像させる。かれらに教える先生たちの故郷や、親たちの祖国や、友達の家族のルーツや、そうした郷愁と共感から生まれる愛着のようなものを連想する。 固有名詞の知識が変わっていくと、その固有名詞の位置づけが変わってくる。位置づけが変わってくると、むかし接した固有名詞の見え方が変わってくる。それはとても楽しいものだ。 でも一方で、ある文化のつくりについて、きれいな原因と結果を想像して、その起源を再構築しようとする態度は、けっこう危険なものだということも忘れてはいけない。歴史的な整理というのはものごとを関係の総体に還元してしまう。そのようにしてきれいに整理された関係というのは、かならずたくさんの余剰物を見落としてしまうだろう。プリンストン大学のインテリたちのビールの趣味だって、ほんとうに、村上が報告しているように、マイナー趣味を尊ぶ文化だったり、あるいはアメリカナイゼーションを内省する左翼っぽい行動原理かもしれない。そこには複数の物語を想像できる。 大切なのはたぶん、そのように想像できる物語の数を増やしていくことであり、その複数性をたわむれながら、単一性にからめとられないようにすることだ。