
ミキ
@miki___63
2025年3月23日
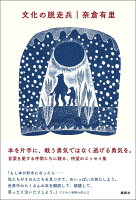
文化の脱走兵
奈倉有里
読み終わった
印象的だった箇所メモ
“ 好きなもの、好きなことを気前よくふるまうこと、「好き」を分かちあうことを快く思う人が、その基準を確固たるものとして持っているのは、これからの世界の子供たちにとってすごく大切なことなのだろう。その基準が国という行政単位のしがらみに曇らないように、ものや人を愛しく守る人々の存在が。”(p17-18)
“ 詩を読むのは時間軸を変えることだーと、モスクワの文学大学で詩を教えていた先生が話していたことがある。「詩のなかに流れる時間は、たとえば十六行という決まった行数のなかでも、数千年にわたっていることもあれば、気づかないほど短い一瞬のあいだに人の頭のなかに起きる変化を語っている場合もある。詩を読むとにには、一定のリズムと韻律に身をゆだねながら、その詩の時間軸に感覚を合わせることが必要になる。私たちはそうして詩を読むことで、たくさんの時間軸を己に内包できるようになる」と。” (p23-24)
“ だからこそーだからこそ詩を、本をきちんと読まなければいけないのだ。甘美な抒情が権力に利用されても気づけるように。”(p46)
“ そういう作者にとって彼らが編みだす文学作品というのは、いくら遅くなってしまってもいいから伝えたかった言葉や、書きたかった手紙のようなものでもあるのかもしれない。即時的には表現することができないからこそ伝えたい思いが残り、それは次第にいくつかのテーマや時代の周囲に積み重なり、芯の部分が熟していく。そうして生みだされた作品は本となり、思いがけないところに別の、あらかじめ埋め合う可能性を担った特別な「余白」を生みだしもするーたとえばウリツカヤの本を読んだ私と友達が、その読書の体験や解釈について、認識を確認しあったりすることによって。”(p54)
“ ありがとう、信じてくれ、ごめんねと言って、風に途切れるように詩は終わる。私たちは子供時代の町に戻ることはできない。けれどもその破片は、ときにやぶれた絵本のページのように、ときにタイムマシンに乗ってやってきた台所用品のように、ちらりちらりと顔をみせる。” (p196-197)







