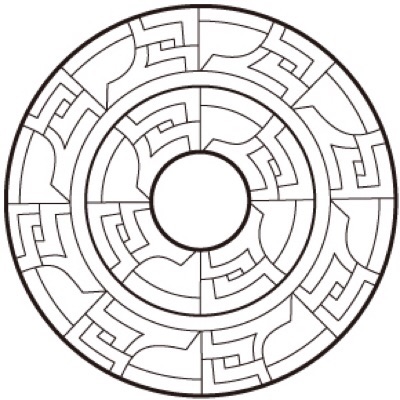渡辺洋介
@yskw0514
2025年3月31日

読み終わった
「社会的連帯経済」(SSE=Social and Solidarity Economy)とは
企業間の競争による利潤の追求とそれを基盤とする経済成長よりも、社会的利益のために連帯して、人と(地球)環境を軸にした経済を指す。さまざまな協同組合やNPO、共済組合、財団、フェアトレード、社会的企業、有機農業、地域通貨のような「補完通貨」の運営などに携わる者がその担い手だ。P.15
本書は「社会的連帯経済」を日本で実践している人々を取材したルポルタージュだ。
経済成長を追求した結果の競争社会、広がる格差など息詰まる資本主義の末期的症状に
ほんとうにこれでよいのだろうか?もっと別の道はないのだろうかと自身思っている中
実際に行っている人々の姿を通すことによって理念がより具体化してイメージしやすくなり
これならできるかもと一歩を踏み出す手掛かりになるのではないだろうかと考えさせてくれる。
こども食堂「だんだん」店長が語るこの言葉がとても良い
「子どもたちには、地域の大人はみんな応援しているよ、ということを伝えたい。そしてさまざまな大人や社会とのつながりを通じて、いろんなことを自分ごととして考えられる人になってほしいですね」P.160
自分ごととして捉える、社会を成員する大人として最低限意識すべきことだと思う。
本書の結びにもこうある
「私たち市民の一人ひとりが、当事者意識を抱き、SSEの理念を周りへと拡散、浸透させていけば、地域社会は市民による自治の実践空間へと変わっていく。そんな動きが市民と自治体の協働によって各地に広がれば、経済はもちろん、社会全体がより民主的で豊かなものになるだろう。世界には、そんな社会を目指して活動するSSEの仲間がそこそこにいる。」p.236