
あんどん書房
@andn
2025年4月19日
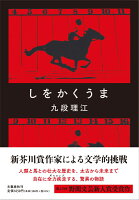
しをかくうま
九段理江
読み終わった
@ 自宅
正直言って今の自分にこの作品の何かを語ることは不可能ではないか……と思って他の人の感想を調べたらだいたい「分からん」って書いてあって参考にならなかった。
なのでとりあえず、明らかに読み取れることと、そこからぼんやり考えたことを書き連ねておく。
一読しただけでも分かる明らかなことは、
①「言葉」が大きなテーマであること、②「過去」「現在」「未来」という時間軸を行き来していること、③現代的な人間のありかた(特に言葉への感覚)に批判的であること……といったところか。
ネアンデルタール(ビ)とホモ・サピエンス(ヒ)が馬(マ)を乗りこなそうとする太古と、アナウンサーである「わたし」が馬の声を聞けるようになるため模索する現代とが交互に描かれる。現代の「わたし」の前に現れる馬の声を代弁する人々は「根安堂」一族である……ということで明らかに現代人の対比にネアンデルタールがある。似て非なるもの(特に言語的感覚において)というところで対比されているのだろうか。
作品のタイトルである「しをかくうま」と同名の競走馬「シヲカクウマ」が作中には登場していて、主人公は特に彼女を愛し、その声を理解したいと熱望する(シヲカクウマに会うためであれば、愛していない年上の女性とも性行為を行う)。
「シヲカクウマ」の名付け親で馬主の根安堂ターレンシスによると、彼女はただ走っているのではなく詩を書いているのだ。
往年の競馬名実況がいくつか引用されているが、それでもまだ馬の本質を表現するには何か足りないのだ……と。
やっぱり全体として現代人の詩的感覚の欠乏を批判しているような感じがする。最後の場面が、未来人のTRANSSNARTが「ニューブレイン(=AI)」をOFFにして「オールドブレイン」で詩を描こうとした場面なのも、そういう風に読めるよね。AIに頼んな。自分で考えろ。競走馬の登録名が十文字になる、という見方によっては非常に些細な問題から出発しているのも、言葉を徹底的に疑った詩人である谷川俊太郎が引用されるのも。
ところどころ明らかに笑いを誘う描写もあって、バランスがいいなぁと思う。





