

あんどん書房
@andn
まとまりのない私的な感想をダラダラと書くのが好きです(長ければ長いほどいいと思っていがち)。買い速度に読み速度が明らか伴ってないのに借り本まであって大変です。
- 2026年2月22日
 猫社会学、はじめます出口剛司,斎藤環,新島典子,柄本三代子,秦美香子,赤川学読み終わった猫本の皮を被った社会学入門書である。進路選択に迷う高校生や専攻を決めかねている大学生にめちゃくちゃよさそう。 第1章「猫はなぜ可愛いのか?」では質的統合法によりインタビューから猫の可愛さの七要素を抜き出して整理する。猫に対する愛情が表面的な可愛さからだんだんお猫様…になっていくというのが面白い。 第2章「私たちは猫カフェから何を得ているのか?」には興味深いデータがいくつか出てきていた。例えば犬はペットショップ購入が圧倒的に多いが、猫は(令和4年時点では)「野良猫を拾った」のが一番多いとか、江戸時代にも「花鳥茶屋」なるものがあったとか、猫カフェに行く客層は猫を飼っている人が多いとか。猫を介したコミュニケーションの可能性からサードプレイスとしての猫カフェの効能についてなども。 第3章「ふつうの猫しかいない「猫島」に人はなぜ訪れるのか?」は観光社会学の知見。猫島を訪れる人々は事前に予習するがゆえに猫島としてだけ現地を見てしまい、過疎地域の抱える問題が不可視化されているという指摘。最近よく見るアーリの名前も。 第4章「猫から見た「サザエさん」」はサザエさん全7193話から「家族」としての猫のイメージの変遷を辿る大変そうな研究の賜物。高度成長期には「ネズミ捕り」として半ば放し飼いされていた猫が、「純粋なペット」として家族の一員になるという時代の変化。その兆候をサザエさんの描写のなかに見つけるという試みだ。 一番意外だったのは「タマ」はアニメ版だけで、原作では特定の猫を飼っている描写がないということ。そうなんだ。 第5章「人と猫は、いかにして互いを理解し合っているのか?」は理論社会学からの研究で、なかなか難しい。人間(文明)と対立する自然という観念のなかで、そのどちらにも属し得る猫という存在。 “猫と和解するということは、文明が自然に対して振るう暴力を抑制し、自然と和解する第一歩になり得るということです。”(p173) どうしてもあの看板を思い浮かべてしまうけれど…。 最終的にそもそもコミュニケーションとは何なのか?という話になり、猫と人間との「相互行為秩序」とか猫がコミュニケーションのパートナーたる「主観的他者」である(と人間から認識される)要因とか専門性が深まってきて???となってしまったが、ざっくり言うと「猫社会学を掘り下げることは、人間中心主義や理解できることへの信仰を解きほぐすのではないか」ということか。 最後は特別対談として赤川さんとオープンダイアローグ第一人者の斎藤環さんの対談。猫を飼うことは社会との接点回復やケアとしての効能があるかもしれないが(もちろんその道具として猫を利用することには反対されている)、独身男性は保護猫の里親になるハードルがめちゃくちゃ高いらしいという話も。飼育費の増加とかも、ペット家族化の難しい面だなぁと思う。 装丁:鈴木千佳子 本文書体:筑紫明朝
猫社会学、はじめます出口剛司,斎藤環,新島典子,柄本三代子,秦美香子,赤川学読み終わった猫本の皮を被った社会学入門書である。進路選択に迷う高校生や専攻を決めかねている大学生にめちゃくちゃよさそう。 第1章「猫はなぜ可愛いのか?」では質的統合法によりインタビューから猫の可愛さの七要素を抜き出して整理する。猫に対する愛情が表面的な可愛さからだんだんお猫様…になっていくというのが面白い。 第2章「私たちは猫カフェから何を得ているのか?」には興味深いデータがいくつか出てきていた。例えば犬はペットショップ購入が圧倒的に多いが、猫は(令和4年時点では)「野良猫を拾った」のが一番多いとか、江戸時代にも「花鳥茶屋」なるものがあったとか、猫カフェに行く客層は猫を飼っている人が多いとか。猫を介したコミュニケーションの可能性からサードプレイスとしての猫カフェの効能についてなども。 第3章「ふつうの猫しかいない「猫島」に人はなぜ訪れるのか?」は観光社会学の知見。猫島を訪れる人々は事前に予習するがゆえに猫島としてだけ現地を見てしまい、過疎地域の抱える問題が不可視化されているという指摘。最近よく見るアーリの名前も。 第4章「猫から見た「サザエさん」」はサザエさん全7193話から「家族」としての猫のイメージの変遷を辿る大変そうな研究の賜物。高度成長期には「ネズミ捕り」として半ば放し飼いされていた猫が、「純粋なペット」として家族の一員になるという時代の変化。その兆候をサザエさんの描写のなかに見つけるという試みだ。 一番意外だったのは「タマ」はアニメ版だけで、原作では特定の猫を飼っている描写がないということ。そうなんだ。 第5章「人と猫は、いかにして互いを理解し合っているのか?」は理論社会学からの研究で、なかなか難しい。人間(文明)と対立する自然という観念のなかで、そのどちらにも属し得る猫という存在。 “猫と和解するということは、文明が自然に対して振るう暴力を抑制し、自然と和解する第一歩になり得るということです。”(p173) どうしてもあの看板を思い浮かべてしまうけれど…。 最終的にそもそもコミュニケーションとは何なのか?という話になり、猫と人間との「相互行為秩序」とか猫がコミュニケーションのパートナーたる「主観的他者」である(と人間から認識される)要因とか専門性が深まってきて???となってしまったが、ざっくり言うと「猫社会学を掘り下げることは、人間中心主義や理解できることへの信仰を解きほぐすのではないか」ということか。 最後は特別対談として赤川さんとオープンダイアローグ第一人者の斎藤環さんの対談。猫を飼うことは社会との接点回復やケアとしての効能があるかもしれないが(もちろんその道具として猫を利用することには反対されている)、独身男性は保護猫の里親になるハードルがめちゃくちゃ高いらしいという話も。飼育費の増加とかも、ペット家族化の難しい面だなぁと思う。 装丁:鈴木千佳子 本文書体:筑紫明朝 - 2026年2月7日
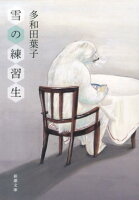 雪の練習生多和田葉子読み終わった多和田葉子作品は初めてだったけれど、極力説明せずに納得させていく感じが独特だなぁと思った。 ホッキョクグマを主役にした三世代の物語。最終章に出てくる「クヌート」はドイツに実在したクマらしく、絶妙にリアルとフィクションが交差している。 序章の「祖母の退化論」に出てくる(クヌートにとって祖母である)「私」はサーカスを引退してから、さまざまな会議に引っ張りだこになっている。この時点ですでに何かが不思議なのだが、かといって完全に人間化されている訳ではなく、サーカスで芸を覚える前は普通に檻で飼われていたりして、この世界の人間と動物の微妙な立ち位置がなかなか把握できずにもどかしい。 第二章の「死の接吻」に出てくるトスカは言葉を喋れずより動物的な存在として描かれており(ただし、クマたちが組合を作ってストをするような世界線ではある)、第三章のクヌートまで来ると完全にクマである。たぶんこの時代の人間は動物と喋るなんて全く想像していない。 (もう一つややこしい点としては、クヌートの母である「トスカ」と「祖母」の娘である「トスカ」は魂を引き継いだ別個体…というようなところ) 一体どういうことなの…? と思ってしまうが、この三世代には時代的な隔たりと文化的な隔たりがあって、つまるところこれは「東側」から「西側」への、近代から現代への移行の物語として書かれているのだろうなということは理解できた。 個人的には文化的移行期的な時代のシスターフッドを描いた二章が好きだが、序章はユーモアと「作家」としての葛藤といった著者自身とのリンクもあり面白く、第三章のラストはジョイスを思わせる余韻があって良い。 歴史や東欧文化を知っていればもう少し深く楽しめるのだろうなと思う。 装画:庄野ナホコ 本文書体:秀英明朝
雪の練習生多和田葉子読み終わった多和田葉子作品は初めてだったけれど、極力説明せずに納得させていく感じが独特だなぁと思った。 ホッキョクグマを主役にした三世代の物語。最終章に出てくる「クヌート」はドイツに実在したクマらしく、絶妙にリアルとフィクションが交差している。 序章の「祖母の退化論」に出てくる(クヌートにとって祖母である)「私」はサーカスを引退してから、さまざまな会議に引っ張りだこになっている。この時点ですでに何かが不思議なのだが、かといって完全に人間化されている訳ではなく、サーカスで芸を覚える前は普通に檻で飼われていたりして、この世界の人間と動物の微妙な立ち位置がなかなか把握できずにもどかしい。 第二章の「死の接吻」に出てくるトスカは言葉を喋れずより動物的な存在として描かれており(ただし、クマたちが組合を作ってストをするような世界線ではある)、第三章のクヌートまで来ると完全にクマである。たぶんこの時代の人間は動物と喋るなんて全く想像していない。 (もう一つややこしい点としては、クヌートの母である「トスカ」と「祖母」の娘である「トスカ」は魂を引き継いだ別個体…というようなところ) 一体どういうことなの…? と思ってしまうが、この三世代には時代的な隔たりと文化的な隔たりがあって、つまるところこれは「東側」から「西側」への、近代から現代への移行の物語として書かれているのだろうなということは理解できた。 個人的には文化的移行期的な時代のシスターフッドを描いた二章が好きだが、序章はユーモアと「作家」としての葛藤といった著者自身とのリンクもあり面白く、第三章のラストはジョイスを思わせる余韻があって良い。 歴史や東欧文化を知っていればもう少し深く楽しめるのだろうなと思う。 装画:庄野ナホコ 本文書体:秀英明朝 - 2026年1月14日
 激しく煌めく短い命綿矢りさ読み終わった『文學界』の連載で最後の数回だけ読んだけど、やはり最初から通して読みたいと思って手に取った。悠木久乃と朱村綸、二人の少女が出会い、恋に落ち、別れ、そして再び出会うまでを描く大作。 辞書並みの厚さになっているのは中学時代と再会後32歳の今を描く二部構成になっていることもあるが、何よりも圧倒的なディテールの描写によるものだろう。たとえば序盤には90年代の京都の中学における同和教育の授業風景が出てくる。恋だけでなく、その周囲にある時代性や社会を描くことへの並々ならぬ熱量が伺える。 『文學界』のインタビューによると、綿矢さんは本作を意識的に「百合小説」として書かれたという。一方で、百合にありがちな「きれいごと」だけで終わってしまう展開にはしたくなかったとも。 個人的に百合というと日常系アニメのゆるふわ系やSNS漫画の関係性重視のようなものを思い浮かべてしまうが、当事者性を娯楽として消費してしまっていいのかという後ろめたさもある。そこを誠実に向き合われている綿矢さんはすごいと思う。 二人の人物像として、久乃は家庭のこともあって、周りから変に思われたりルールを破って怒られないことにものすごく気を遣っている。綸の影響でだんだん遊ぶようにはなってくるけれど、それでも中心の部分は変わらずにいる。一方の綸は周囲の目なんて知ったこっちゃないという溌剌なタイプ。この微妙な噛み合わなさが後々亀裂をもたらしてしまうのだが、それを20年越しに乗り越える展開にはやはりカタルシスがあった。 作品のメインテーマが恋であるならば、もう一つの大きなテーマが「世代」だろうか。90年代というギリギリ昭和の価値観のなかで育ってきた人たちが、急速に変わってゆく時代に取り残されてゆく。どちからというとおじさんメインの作品に多いテーマだが、そんな社会に適応してきてしまったバリキャリとしての久乃もまた、その流れの中で戸惑っている。 “時代性とはそういうものだ。無関係に生きていたように見える人間さえ、その時代の空気に飲み込まれ、溶け込んでいる。”(P528) 戸惑いの中で疲弊してゆく久乃を救ってくれるのは、やはり綸しかいないのだった。 二人は中学生の頃にできなかったことのその先へと進むが、合間合間で中学時代の(書かれなかった)記憶が挟まれていて、あの頃も確かに豊かな時間だったんだなぁと伺えるのが良い。 本文書体:凸版文久明朝 写真:釜谷洋史 装丁:野中深雪
激しく煌めく短い命綿矢りさ読み終わった『文學界』の連載で最後の数回だけ読んだけど、やはり最初から通して読みたいと思って手に取った。悠木久乃と朱村綸、二人の少女が出会い、恋に落ち、別れ、そして再び出会うまでを描く大作。 辞書並みの厚さになっているのは中学時代と再会後32歳の今を描く二部構成になっていることもあるが、何よりも圧倒的なディテールの描写によるものだろう。たとえば序盤には90年代の京都の中学における同和教育の授業風景が出てくる。恋だけでなく、その周囲にある時代性や社会を描くことへの並々ならぬ熱量が伺える。 『文學界』のインタビューによると、綿矢さんは本作を意識的に「百合小説」として書かれたという。一方で、百合にありがちな「きれいごと」だけで終わってしまう展開にはしたくなかったとも。 個人的に百合というと日常系アニメのゆるふわ系やSNS漫画の関係性重視のようなものを思い浮かべてしまうが、当事者性を娯楽として消費してしまっていいのかという後ろめたさもある。そこを誠実に向き合われている綿矢さんはすごいと思う。 二人の人物像として、久乃は家庭のこともあって、周りから変に思われたりルールを破って怒られないことにものすごく気を遣っている。綸の影響でだんだん遊ぶようにはなってくるけれど、それでも中心の部分は変わらずにいる。一方の綸は周囲の目なんて知ったこっちゃないという溌剌なタイプ。この微妙な噛み合わなさが後々亀裂をもたらしてしまうのだが、それを20年越しに乗り越える展開にはやはりカタルシスがあった。 作品のメインテーマが恋であるならば、もう一つの大きなテーマが「世代」だろうか。90年代というギリギリ昭和の価値観のなかで育ってきた人たちが、急速に変わってゆく時代に取り残されてゆく。どちからというとおじさんメインの作品に多いテーマだが、そんな社会に適応してきてしまったバリキャリとしての久乃もまた、その流れの中で戸惑っている。 “時代性とはそういうものだ。無関係に生きていたように見える人間さえ、その時代の空気に飲み込まれ、溶け込んでいる。”(P528) 戸惑いの中で疲弊してゆく久乃を救ってくれるのは、やはり綸しかいないのだった。 二人は中学生の頃にできなかったことのその先へと進むが、合間合間で中学時代の(書かれなかった)記憶が挟まれていて、あの頃も確かに豊かな時間だったんだなぁと伺えるのが良い。 本文書体:凸版文久明朝 写真:釜谷洋史 装丁:野中深雪 - 2026年1月8日
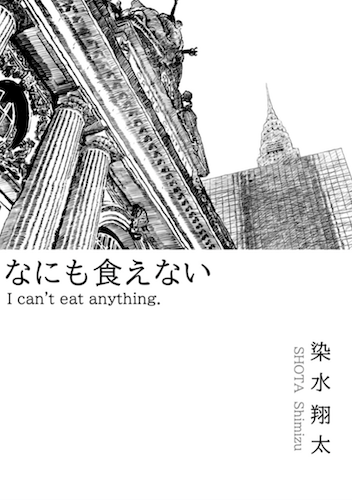 なにも食えない染水翔太読み終わった“いつもおれは、ビザやパスタのある国や都市だけを選んで行く。”(P7) 前回の東京文フリはカタログを隅々まで読み込んで行ったのだけれど、そんな中でも特に異彩を放っていたのが本書。 世界各地に行って、現地の名物を、食べないのだ。シンガポールでは海南鶏飯を食べず(奇妙な光沢と色が変)、上海では上海蟹を食べない(蟹味噌はセメントみたい)。 なんか垂れていたり、よく分からないものは基本ダメ。食べられそうであっても、ピザやパスタがあればそちらを選ぶ…。 “騙されたと思って、の意味がわからない。食べてみたところでふつうに不味い。自分の舌を信じている。”(P62) 食わず嫌いも極まるとコンテンツになるんだなぁ。そしてこの太々しさみたいなものが、全体に独特のユーモアを纏わせていて良い。 さらに、謎に冷めているのは食に対してだけではない。インフィニティプールは冷たすぎて楽しめなかったり、間欠泉の写真は汚い噴水みたいになったり…。なぜかそういう記憶ばかりが続いてゆく。 自分なぞはせっかく旅に来たのだからと名産や名所を求めてしまうほうの人間だが、本書はそんな「当たり前」に一石を投じるような紀行エッセイになっていると思う。(頭木さんの「共食圧力」みたいな話も思い出す) しかし、何より一番興味深いのは、そんな食えないもんだらけでも海外に行くことをやめない著者のスタイルだろう。 “夜、風呂から上がり髪を乾かし、夜風に当たりながらコンビニへ向かう、そのときいつもの道なのに少しばかり心が浮つく、ともすると来たことのない場所に来てしまったという感覚さえある、そういうときにふと、このまま海外にでも行きたいな、と思うことがある”(P11) 日常にひびをいれるために、海外へゆく。その発想は自分には全く無いものだからこそ、著者のことをもっと知りたくなる。 ぜひ活躍されて色々書いてほしいお一人だ。 (経歴を見るとカフカショートストーリーコンテストで優秀賞を獲られていて、『文學界』ですでに出会っている方だった…!) 本文書体:游明朝体 著者・装幀・発行者:染水翔太
なにも食えない染水翔太読み終わった“いつもおれは、ビザやパスタのある国や都市だけを選んで行く。”(P7) 前回の東京文フリはカタログを隅々まで読み込んで行ったのだけれど、そんな中でも特に異彩を放っていたのが本書。 世界各地に行って、現地の名物を、食べないのだ。シンガポールでは海南鶏飯を食べず(奇妙な光沢と色が変)、上海では上海蟹を食べない(蟹味噌はセメントみたい)。 なんか垂れていたり、よく分からないものは基本ダメ。食べられそうであっても、ピザやパスタがあればそちらを選ぶ…。 “騙されたと思って、の意味がわからない。食べてみたところでふつうに不味い。自分の舌を信じている。”(P62) 食わず嫌いも極まるとコンテンツになるんだなぁ。そしてこの太々しさみたいなものが、全体に独特のユーモアを纏わせていて良い。 さらに、謎に冷めているのは食に対してだけではない。インフィニティプールは冷たすぎて楽しめなかったり、間欠泉の写真は汚い噴水みたいになったり…。なぜかそういう記憶ばかりが続いてゆく。 自分なぞはせっかく旅に来たのだからと名産や名所を求めてしまうほうの人間だが、本書はそんな「当たり前」に一石を投じるような紀行エッセイになっていると思う。(頭木さんの「共食圧力」みたいな話も思い出す) しかし、何より一番興味深いのは、そんな食えないもんだらけでも海外に行くことをやめない著者のスタイルだろう。 “夜、風呂から上がり髪を乾かし、夜風に当たりながらコンビニへ向かう、そのときいつもの道なのに少しばかり心が浮つく、ともすると来たことのない場所に来てしまったという感覚さえある、そういうときにふと、このまま海外にでも行きたいな、と思うことがある”(P11) 日常にひびをいれるために、海外へゆく。その発想は自分には全く無いものだからこそ、著者のことをもっと知りたくなる。 ぜひ活躍されて色々書いてほしいお一人だ。 (経歴を見るとカフカショートストーリーコンテストで優秀賞を獲られていて、『文學界』ですでに出会っている方だった…!) 本文書体:游明朝体 著者・装幀・発行者:染水翔太 - 2026年1月7日
 超楽器高野裕子,鷲田清一読み終わった京都コンサートホールの周年記念エッセイ集なのだが、鷲田清一編で三宅香帆、岸田繁という執筆陣に惹かれた。音楽と建築の観点で書かれた文章が主。 堀江敏幸「一度しかない出来事を繰り返すよろこび」はオーディオとコンサートホールの音響について。こういう繊細なテーマを表現するのがそりゃもう上手い。 “ながらくFM放送で親しみ、場内の音を想像しつづけてきた空間にはじめて腰を下ろしたとき、開演前のノイズのうつくしさに陶然となった。[…]すぐれた演奏の下地に、こういう空気の層が擦れ合うような音の網がひろがっていたのか。”(P34) 小説の一節みたい。 そして、そういったホールの音響は「演奏家や観客の、体温と呼吸の研磨」によって成長し、成熟してゆくものだともいう。 その違いを感じ取れるような繊細な感性がすごいと思う。 佐渡裕「第九から始まる心と街の復興」より。 “僕は、「第九」は決しておめでたい曲ではないと思っている。たとえば、有名な「歓喜の歌」が現れた後、男声合唱が厳しく「Seid umschlungen(抱き合いなさい)」と歌う箇所が出てくる。僕は、この歌詞が「抱き合いなさい、抱き合うことができなければ、この歓喜は手に入らないのですよ」ということを示唆していると解釈した。” 何となくおめでたニューイヤーで聴いてるだけではこういう鑑賞はできないだろうなぁ。知ることの大切さ。 三宅香帆「奏でるよりも聴くことで」にも興味深い話が出てくる。ピアノの上手さについて、 “「ピアノが上手い」を私なりに定義すると——自分の理想の音楽が脳内に存在しており、その理想が的確で、さらに現実でその理想に届くことができている状態——なのである。”(P49) 話はさらにそこから敷衍されて、才能とは理想をイメージできることだ…と三宅さんは書かれている。なるほどなぁ。自分にはあらゆる才能がねぇってことですね。。 岡田暁生さんも堀江さんと似たような趣旨のことを書かれている。 “ホールが「機能」ではなくて「文化」だとするなら、「古くなれば建て替えればいい」というわけにはいかない。重要なのはむしろ、古い寺社や教会と同じく、ホールが街並から切り取ることのできない風景の一部となるまで、それを熟成させることである。”(P58) 昨今のお金のない自治体にはなかなか厳しいところがあるとは思うけれど、理想はそうなのだろうなぁ。 世界の名だたるコンサートホールは19世紀末ごろのバブル&都市改造ブームの産物というのも初めて知った。 彬子女王「神々に届く音」は割と気軽で現代的なところもありつつ、尊敬語がものすごく多い上品な文章はさすがの皇室エッセイ。音楽の来歴としてちゃんと天岩戸神話に繋げていくところも、非常に完璧な一編だと感じる。 岸田繁「魔法の音楽」。ホールについてというお題に真正面から向き合った文章だ。 “私たちは音楽の船に乗ったまま甲板で海図を確認しながら、耳と心を微調整する。休憩時間はコンサートにとって大きな意味を持つのだ。”(P91) 休憩のあるような格式高いコンサート、ほとんど行ったことがないなぁ…。 交響曲を書いたことについて。 “私は元々ブルース・ギタリストであり、今もなおバンドマンでシンガー・ソングライターである。ただ、それ以前に私はあらゆるジャンルの、あらゆる地域の音楽を愛する駆け出しの作曲家だ。”(P95) うーんかっこいい。 鷲田清一さんは「初源」というキーワードから始まる音楽の話。民族音楽学者・小泉文夫の「生活と音楽が分離してしまった」という言葉を引用しながら、それでも純化し突きつめられた「ふつう」の音楽と、流行歌や戯れ歌、歌謡など生活の音楽の間にある「ぶれ」こそが、音楽をたえず進化させてきたものだという。 山極寿一さんのゴリラの音楽の話から始まって鷲田さんの初源の音楽の話で終わる構成がいいなと思った。 鷲田さん、編者紹介で好きな楽器は「エレクトリック・ギター」と書かれている笑 本文書体:リュウミンオールド 装丁:大倉真一郎
超楽器高野裕子,鷲田清一読み終わった京都コンサートホールの周年記念エッセイ集なのだが、鷲田清一編で三宅香帆、岸田繁という執筆陣に惹かれた。音楽と建築の観点で書かれた文章が主。 堀江敏幸「一度しかない出来事を繰り返すよろこび」はオーディオとコンサートホールの音響について。こういう繊細なテーマを表現するのがそりゃもう上手い。 “ながらくFM放送で親しみ、場内の音を想像しつづけてきた空間にはじめて腰を下ろしたとき、開演前のノイズのうつくしさに陶然となった。[…]すぐれた演奏の下地に、こういう空気の層が擦れ合うような音の網がひろがっていたのか。”(P34) 小説の一節みたい。 そして、そういったホールの音響は「演奏家や観客の、体温と呼吸の研磨」によって成長し、成熟してゆくものだともいう。 その違いを感じ取れるような繊細な感性がすごいと思う。 佐渡裕「第九から始まる心と街の復興」より。 “僕は、「第九」は決しておめでたい曲ではないと思っている。たとえば、有名な「歓喜の歌」が現れた後、男声合唱が厳しく「Seid umschlungen(抱き合いなさい)」と歌う箇所が出てくる。僕は、この歌詞が「抱き合いなさい、抱き合うことができなければ、この歓喜は手に入らないのですよ」ということを示唆していると解釈した。” 何となくおめでたニューイヤーで聴いてるだけではこういう鑑賞はできないだろうなぁ。知ることの大切さ。 三宅香帆「奏でるよりも聴くことで」にも興味深い話が出てくる。ピアノの上手さについて、 “「ピアノが上手い」を私なりに定義すると——自分の理想の音楽が脳内に存在しており、その理想が的確で、さらに現実でその理想に届くことができている状態——なのである。”(P49) 話はさらにそこから敷衍されて、才能とは理想をイメージできることだ…と三宅さんは書かれている。なるほどなぁ。自分にはあらゆる才能がねぇってことですね。。 岡田暁生さんも堀江さんと似たような趣旨のことを書かれている。 “ホールが「機能」ではなくて「文化」だとするなら、「古くなれば建て替えればいい」というわけにはいかない。重要なのはむしろ、古い寺社や教会と同じく、ホールが街並から切り取ることのできない風景の一部となるまで、それを熟成させることである。”(P58) 昨今のお金のない自治体にはなかなか厳しいところがあるとは思うけれど、理想はそうなのだろうなぁ。 世界の名だたるコンサートホールは19世紀末ごろのバブル&都市改造ブームの産物というのも初めて知った。 彬子女王「神々に届く音」は割と気軽で現代的なところもありつつ、尊敬語がものすごく多い上品な文章はさすがの皇室エッセイ。音楽の来歴としてちゃんと天岩戸神話に繋げていくところも、非常に完璧な一編だと感じる。 岸田繁「魔法の音楽」。ホールについてというお題に真正面から向き合った文章だ。 “私たちは音楽の船に乗ったまま甲板で海図を確認しながら、耳と心を微調整する。休憩時間はコンサートにとって大きな意味を持つのだ。”(P91) 休憩のあるような格式高いコンサート、ほとんど行ったことがないなぁ…。 交響曲を書いたことについて。 “私は元々ブルース・ギタリストであり、今もなおバンドマンでシンガー・ソングライターである。ただ、それ以前に私はあらゆるジャンルの、あらゆる地域の音楽を愛する駆け出しの作曲家だ。”(P95) うーんかっこいい。 鷲田清一さんは「初源」というキーワードから始まる音楽の話。民族音楽学者・小泉文夫の「生活と音楽が分離してしまった」という言葉を引用しながら、それでも純化し突きつめられた「ふつう」の音楽と、流行歌や戯れ歌、歌謡など生活の音楽の間にある「ぶれ」こそが、音楽をたえず進化させてきたものだという。 山極寿一さんのゴリラの音楽の話から始まって鷲田さんの初源の音楽の話で終わる構成がいいなと思った。 鷲田さん、編者紹介で好きな楽器は「エレクトリック・ギター」と書かれている笑 本文書体:リュウミンオールド 装丁:大倉真一郎 - 2026年1月4日
 BOXBOXBOXBOX坂本湾読み終わった宅配荷物をトラックに積み込みする物流倉庫「宅配所」。午前中は向かい側のレーンも見えなくなるほど深い霧が入り込んでくるこの場所で働く四人の視点から描かれる作品。 単純作業の退屈を紛らわすために「箱の中身を想像する」という遊びをしていたが、ある出来事を境に盗みの快楽に溺れてしまう安。妻の入院費を稼ぐために働くものの、介護のストレスから仕事中に飲むほど酒に溺れてしまう斎藤。派遣の仕事を切られ、次への繋ぎの間だけと働くが、初日からレーンを蹴飛ばすほど仕事が嫌になっている稲森。盗品や破損など不始末の尻拭いやさまざまな雑務を押し付けられ、頭痛が止まらない契約社員の神代。 これは令和のプロレタリア文学。 レーンの一部となって人間らしさを剥奪される人々。彼ら彼女らはそれぞれ何らかの方法で抵抗を試みているのだが(間接的に描かれる技能実習生たちのストライキなども)、何か不気味で巨大な、霧に包まれる宅配所という存在の中で有耶無耶にされていってしまう。 最終的にはそれぞれ四人が向かう未来が描かれていて、そこは一瞬希望を持てるものの、根本的にはなにも解決してないよねというところ。そりゃまあ、この物流を要求する社会の側の問題なのだから、そんな簡単に変わらないだろう。 「鳩」たちはそんなアホらしい人間たちに対する自然の象徴なのかなぁと思った。 本文書体:イワタ明朝体オールド 装画:杉野ギーノス 装丁:川名潤
BOXBOXBOXBOX坂本湾読み終わった宅配荷物をトラックに積み込みする物流倉庫「宅配所」。午前中は向かい側のレーンも見えなくなるほど深い霧が入り込んでくるこの場所で働く四人の視点から描かれる作品。 単純作業の退屈を紛らわすために「箱の中身を想像する」という遊びをしていたが、ある出来事を境に盗みの快楽に溺れてしまう安。妻の入院費を稼ぐために働くものの、介護のストレスから仕事中に飲むほど酒に溺れてしまう斎藤。派遣の仕事を切られ、次への繋ぎの間だけと働くが、初日からレーンを蹴飛ばすほど仕事が嫌になっている稲森。盗品や破損など不始末の尻拭いやさまざまな雑務を押し付けられ、頭痛が止まらない契約社員の神代。 これは令和のプロレタリア文学。 レーンの一部となって人間らしさを剥奪される人々。彼ら彼女らはそれぞれ何らかの方法で抵抗を試みているのだが(間接的に描かれる技能実習生たちのストライキなども)、何か不気味で巨大な、霧に包まれる宅配所という存在の中で有耶無耶にされていってしまう。 最終的にはそれぞれ四人が向かう未来が描かれていて、そこは一瞬希望を持てるものの、根本的にはなにも解決してないよねというところ。そりゃまあ、この物流を要求する社会の側の問題なのだから、そんな簡単に変わらないだろう。 「鳩」たちはそんなアホらしい人間たちに対する自然の象徴なのかなぁと思った。 本文書体:イワタ明朝体オールド 装画:杉野ギーノス 装丁:川名潤 - 2025年12月31日
 文学は何の役に立つのか?平野啓一郎読み終わった冒頭に収録されている表題の講演と、様々な媒体で発表された批評・エッセイがまとまった一冊。 講演では「人は皆自分の悩みに価値があると思っていないので、ちょっと憧れるような登場人物とか立派な人の中に共感を見出すと、心地良く共感できる」(P27)といった興味深い話もいろいろありつつ、特に印象に残ったのが後半の不幸を「機因化」してしまうという問題。 貧困を描いた作品が当事者にとって救いになるかもしれないが、それは一方で現状の肯定に繋がってしまうのではないか…というようなことだと思う。これは「生きてるだけでいいんだよ」みたいな言説にありがちなやつだ。その言葉が必要な時もあれば、それだけ(最低限の生存)で満足ってわけじゃないでしょ?という時もある。 これは東畑さんの「贅沢な悩み」ともリンクする話だなぁ。 そこから軽めのエッセイを挟みつつ、ドストエフスキー論や三島由紀夫論など骨太な批評が並んでいる。 ドスト論はさすがに読んでいないとなかなか理解できない。「分人」が現れている登場人物もいれば、ほとんど分化できない姿で描かれる人物もいる、みたいなところがあるのはわかった。 続いての「三島戯曲の世界」も三島を読んでないのでほーん…という感じで読んでしまうが、戦後日本人に海外旅行が解禁されたのが1964年というのを初めて知った。オリンピックなんかより全然重大事項じゃないか。 追悼エッセイ「瀬戸内文学の再評価に向けて」では、日本の文壇の男性中心主義批判や瀬戸内作品のフェミニズム的批評の必要性が指摘されている。ここを読んでいて、確かに自分の中でもフェミニズム文学っていうとどうしても現代作家ばかりイメージしてしまうなぁと思った。現代に至るまでの女性作家の作品がすっぽり抜け落ちている。読まなきゃなぁ。 “私たちは、瀬戸内さんのケータイ小説などの取り組みを、単なる新しいもの好き、と見るのではなく、この枠組みを踏まえた上で評価する必要がある。” (P189) 女性の性という主題から、評伝の仕事を通して「社会道徳と自由及び欲望とな軋轢」の探究に至る。やがて宗教との出会いから「個と社会変革、個と魂の救済」という瀬戸内文学の骨格が完成してゆく…というように平野さんは整理されている。 やはり一時期だけ見て作家を理解するのじゃなくて、ライフヒストリーも踏まえて見ていく必要があるんだなぁ。 『オッペンハイマー』論は特に気合い入ってる感じがしたが、依頼原稿ではなく本人の希望で書かれたものらしい。被爆国である日本から見るとモヤモヤしてしまうであろう作品でありながら、ノーラン監督がいかに原作にはない要素で批判的視点を加えようとしたのか、というのが興味深い。また最終的にオッペンハイマーとの対比で林京子の作品に触れているのがさすが作家だと思う。 ノーラン作品全体に共通する時系列のあり方についても解説されてあて、観ていないのでネタバレも多少あるものの、でもこの複雑さは初見じゃ理解できなかろうなぁと思った。 本文書体:リュウミンオールド
文学は何の役に立つのか?平野啓一郎読み終わった冒頭に収録されている表題の講演と、様々な媒体で発表された批評・エッセイがまとまった一冊。 講演では「人は皆自分の悩みに価値があると思っていないので、ちょっと憧れるような登場人物とか立派な人の中に共感を見出すと、心地良く共感できる」(P27)といった興味深い話もいろいろありつつ、特に印象に残ったのが後半の不幸を「機因化」してしまうという問題。 貧困を描いた作品が当事者にとって救いになるかもしれないが、それは一方で現状の肯定に繋がってしまうのではないか…というようなことだと思う。これは「生きてるだけでいいんだよ」みたいな言説にありがちなやつだ。その言葉が必要な時もあれば、それだけ(最低限の生存)で満足ってわけじゃないでしょ?という時もある。 これは東畑さんの「贅沢な悩み」ともリンクする話だなぁ。 そこから軽めのエッセイを挟みつつ、ドストエフスキー論や三島由紀夫論など骨太な批評が並んでいる。 ドスト論はさすがに読んでいないとなかなか理解できない。「分人」が現れている登場人物もいれば、ほとんど分化できない姿で描かれる人物もいる、みたいなところがあるのはわかった。 続いての「三島戯曲の世界」も三島を読んでないのでほーん…という感じで読んでしまうが、戦後日本人に海外旅行が解禁されたのが1964年というのを初めて知った。オリンピックなんかより全然重大事項じゃないか。 追悼エッセイ「瀬戸内文学の再評価に向けて」では、日本の文壇の男性中心主義批判や瀬戸内作品のフェミニズム的批評の必要性が指摘されている。ここを読んでいて、確かに自分の中でもフェミニズム文学っていうとどうしても現代作家ばかりイメージしてしまうなぁと思った。現代に至るまでの女性作家の作品がすっぽり抜け落ちている。読まなきゃなぁ。 “私たちは、瀬戸内さんのケータイ小説などの取り組みを、単なる新しいもの好き、と見るのではなく、この枠組みを踏まえた上で評価する必要がある。” (P189) 女性の性という主題から、評伝の仕事を通して「社会道徳と自由及び欲望とな軋轢」の探究に至る。やがて宗教との出会いから「個と社会変革、個と魂の救済」という瀬戸内文学の骨格が完成してゆく…というように平野さんは整理されている。 やはり一時期だけ見て作家を理解するのじゃなくて、ライフヒストリーも踏まえて見ていく必要があるんだなぁ。 『オッペンハイマー』論は特に気合い入ってる感じがしたが、依頼原稿ではなく本人の希望で書かれたものらしい。被爆国である日本から見るとモヤモヤしてしまうであろう作品でありながら、ノーラン監督がいかに原作にはない要素で批判的視点を加えようとしたのか、というのが興味深い。また最終的にオッペンハイマーとの対比で林京子の作品に触れているのがさすが作家だと思う。 ノーラン作品全体に共通する時系列のあり方についても解説されてあて、観ていないのでネタバレも多少あるものの、でもこの複雑さは初見じゃ理解できなかろうなぁと思った。 本文書体:リュウミンオールド - 2025年12月16日
 フクロウ 地球上で最も謎めいた鳥の科学ジェニファー・アッカーマン,ナショナル・ジオグラフィック,樋口亜紀,鍛原多惠子読み終わったフクロウとみみずくの違いも知らなければ、エッホエッホのフクロウがどの種類で何をしているのかも知らない… そんな無知な自分が初めてフクロウという鳥にじっくり向き合ってみた読書だった。 まず構成については、海外の科学本にありがちな「研究者の〇〇は〜という発見をし」みたいなのが羅列されていく読みにくさはあり、次々とフクロウの名前が出てきてもなかなか頭に入ってこないのだが、DNA周りの技術向上で類縁関係が見直されたというのは鳥展で見たやつだなぁと思った。猛禽や夜行性鳥類の仲間と思われていたが、実は昼行性の鳥類から分岐したらしい。 色素によって重さが違うから羽の暗い部分が効率的に配置されている、みたいな話(P63)も興味深い。色で重さが違うとか考えたこともなかったなぁ。 “ヘンリー・デイヴィッド・ソローは、アメリカオオコノハズクの求愛の歌は、自殺願望のある恋人たちが互いを慰めているように聞こえると思った。” (P184) ソロー積んだままなのでわかんないけど、森の生活とかにそんなこと書いてるんかな。印象的だがいまいちイメージしにくい。 飛んで7章「捕らわれのフクロウ」より。 “日本は世界最大のフクロウ輸入国であり、何千羽に及ぶ輸入フクロウの90パーセント以上を占める。[…]日本の法律は人間によって育てられたフクロウのみ販売を許可すると明確に定めているが、業者は捏造文書や古い許可証を違法に使い回して法の穴をくぐりぬける。” (P315-316) ここまで読んできたらフクロウを飼うことの困難は十分に感じられるものなので、当然そんな気軽に飼っていいもんじゃない。あのナイチンゲールでさえ死なせてしまったのだから…。 刷り込みについても意外な事実が書かれていた。なんとなく人間が刷り込まれた動物は友好的になるようなイメージもあるが、フクロウにとって人間の顔は自分達と似ている故に、縄張りを主張して攻撃的になるのだとか。 本書のメッセージとして最も大きいのは「知ることの大切さ」である。たとえばフクロウの保全については次のような観点が考えられる。 “まだ生きている木を切るか剪定する前に、樹洞がないかどうか確かめる。立ち枯れ木や死んだ木はリスクがなければそのままにする。巣箱を設置する。ネズミ胎児には毒ではなく罠を使う。周囲にいるフクロウについてできる限り学ぶ。どんなフクロウが暮らしているか。どこで暮らしているのか。彼らが直面する脅威は何か。外に出て地元のフクロウを見つける。でも、自分がフクロウに与えるかもしれない影響を認識しておく。フクロウの鳴き声の録音を流すのは、すでにストレスを抱えているフクロウにさらにストレスを与えることになると知る。” (P424) 改めて、フクロウについてほとんど何にも知らないんだなぁということがよく分かった。 本文書体:秀英明朝 装幀・組版:佐々木暁 日本版カバー写真:ジョエル・サートレイ「PHOTO ARK(動物の箱舟)」より
フクロウ 地球上で最も謎めいた鳥の科学ジェニファー・アッカーマン,ナショナル・ジオグラフィック,樋口亜紀,鍛原多惠子読み終わったフクロウとみみずくの違いも知らなければ、エッホエッホのフクロウがどの種類で何をしているのかも知らない… そんな無知な自分が初めてフクロウという鳥にじっくり向き合ってみた読書だった。 まず構成については、海外の科学本にありがちな「研究者の〇〇は〜という発見をし」みたいなのが羅列されていく読みにくさはあり、次々とフクロウの名前が出てきてもなかなか頭に入ってこないのだが、DNA周りの技術向上で類縁関係が見直されたというのは鳥展で見たやつだなぁと思った。猛禽や夜行性鳥類の仲間と思われていたが、実は昼行性の鳥類から分岐したらしい。 色素によって重さが違うから羽の暗い部分が効率的に配置されている、みたいな話(P63)も興味深い。色で重さが違うとか考えたこともなかったなぁ。 “ヘンリー・デイヴィッド・ソローは、アメリカオオコノハズクの求愛の歌は、自殺願望のある恋人たちが互いを慰めているように聞こえると思った。” (P184) ソロー積んだままなのでわかんないけど、森の生活とかにそんなこと書いてるんかな。印象的だがいまいちイメージしにくい。 飛んで7章「捕らわれのフクロウ」より。 “日本は世界最大のフクロウ輸入国であり、何千羽に及ぶ輸入フクロウの90パーセント以上を占める。[…]日本の法律は人間によって育てられたフクロウのみ販売を許可すると明確に定めているが、業者は捏造文書や古い許可証を違法に使い回して法の穴をくぐりぬける。” (P315-316) ここまで読んできたらフクロウを飼うことの困難は十分に感じられるものなので、当然そんな気軽に飼っていいもんじゃない。あのナイチンゲールでさえ死なせてしまったのだから…。 刷り込みについても意外な事実が書かれていた。なんとなく人間が刷り込まれた動物は友好的になるようなイメージもあるが、フクロウにとって人間の顔は自分達と似ている故に、縄張りを主張して攻撃的になるのだとか。 本書のメッセージとして最も大きいのは「知ることの大切さ」である。たとえばフクロウの保全については次のような観点が考えられる。 “まだ生きている木を切るか剪定する前に、樹洞がないかどうか確かめる。立ち枯れ木や死んだ木はリスクがなければそのままにする。巣箱を設置する。ネズミ胎児には毒ではなく罠を使う。周囲にいるフクロウについてできる限り学ぶ。どんなフクロウが暮らしているか。どこで暮らしているのか。彼らが直面する脅威は何か。外に出て地元のフクロウを見つける。でも、自分がフクロウに与えるかもしれない影響を認識しておく。フクロウの鳴き声の録音を流すのは、すでにストレスを抱えているフクロウにさらにストレスを与えることになると知る。” (P424) 改めて、フクロウについてほとんど何にも知らないんだなぁということがよく分かった。 本文書体:秀英明朝 装幀・組版:佐々木暁 日本版カバー写真:ジョエル・サートレイ「PHOTO ARK(動物の箱舟)」より - 2025年12月10日
- 2025年12月10日
 曇る眼鏡を拭きながらくぼたのぞみ,斎藤真理子気になる
曇る眼鏡を拭きながらくぼたのぞみ,斎藤真理子気になる - 2025年12月9日
 南光中村加代子,朱和之読み終わった台湾出身の写真家・南光こと鄧騰煇の生涯を描く。 大日本帝国統治下の台湾から法政大学に入学し、友人からお古のライカを買うというところが物語の冒頭。 当然当時のカメラはマニュアルなので、距離感とか露出をその場その場で判断しなければならない。そのために日常の中でひたすら物体や人物との距離を考え続け、無意識のクセになっていく…というカメラ初心者の努力がここまで描かれる小説はたぶん初めて読んだ。マニュアルで撮る練習とかをしてた頃を思い出して懐かしくなる。 時系列を行ったり来たりしつつ、鄧騰煇以外の視点も所々に挟まれてゆく。同じように日本で写真を学びながら、より芸術的側面や技法に価値を置いた彭瑞麟。海外の写真家がとらえる中国像に違和感を抱き、理想的なイメージを追求した郎静山…などなど、さまざまな立場の写真家によるモノローグが描かれる。中心にあるのは絵画主義/リアリズム/新興写真的な対立だけれど、それぞれにとっての写真論=人生観が物語の奥行きを出しているような気がした。 “時々考えた。自分が東京で勉強できているのは、家の財産に頼っているからであり、父の許可があってこそライカが買えるのだと。それでいて日本で見聞したすべてが、彼をどんどん故郷から引き離すのだった。” (P174) 出自である客家の伝統的な価値観と、都会で身に付けた近代的価値観の対立。作中の鄧騰煇の人生には、このようなアイデンティティの分裂の経験が何度か登場する。台湾人でありながら、日本の総督府によって身分を保障された写真家であるという分裂。戦後の国民党政権の元での外省人と本省人の分裂(二二八事件)。 これらはそのまま台湾という国が経験してきたさまざまな分断の歴史でもある。そして自分はそういった歴史を一切知らなかった。 “中国撮影学会は政府の反共坑俄〔反共産主義、反ソ連〕文化政策に呼応して、明るく前向きで、純潔かつ崇高な作品を撮るように会員に求めた。反対に頽廃、ロマンチック、赤、黄〔ポルノ〕、黒〔堕落〕の作品は否定された。その定義の下では、写実的、郷土的、人びとの真の生活を反映したものはもちろん、社会の不公正を告発する作品なども否定の対象だった。” (P316) 日本に都合の良いプロパガンダ的な写真を求められた戦時中から光復を経て自由になったかと思いきや、今度は反共の嵐の中で別の制約が……という状況。もちろんこの「中国」は中華民国のこと。 写真を撮るということについても色々と示唆的な記述が多く、考えさせられる。 “理屈からすれば、肖像写真はその個人を表すものだ。[…]だが彼は懐疑的だった。虚な目でこわばった表情をしたこんな写真が、本当に誰かを表し得るのだろうか。” (P256) これは作家としての写真と仕事としての写真の葛藤だと思うんだけれど、似たようなことは考えたことがあるなぁと思った。証明写真とか撮ってると考えるよな。 その辺の意識の問題をうまいこと折り合いをつけていたのが植田正治だと思う。 “写真とは、言わば撮影者の心象を映す鏡だ。だが心象を完璧に映した情景に出会えるかどうかは、運次第だ。それは往々にして電光石火のごとき一瞬で、百分の一秒の間にシャッターを切らなければ、過ぎ去ったきり二度とは戻らない。初心者でも一度か二度はその瞬間を捉えることができるかもしれない。しかしツバメが風雨を察知するように、あるいはナマズが地震を予知するように、神秘の瞬間が近づいていると直感し、鏡のように澄んだ心でそれを捉えることができるのは、しっかりと準備を整えた写真家だけだ。 つまるところ写真というのは、カメラで何を捉えたかではなく、何に心を捕らわれたかだという人がいるのは、そういう意味なのだ。” (P348) 時代に翻弄されさまざまな写真を撮ってきた主人公が最終的にこういった真理に至るところは読み応えがある。写真を作品として発表することから、より純粋に撮ること自体へとフォーカスしていく。 一応補足すると南光自身は写真以外に文章などはほとんど残していないようなので、こういう写真論とかは作家が南光の写真と向き合って導き出したものであるらしい。 本文書体:リュウミンオールド 装幀:佐野裕哉 装画:柳智之 写真:鄧南光(Te Nan-Kua)
南光中村加代子,朱和之読み終わった台湾出身の写真家・南光こと鄧騰煇の生涯を描く。 大日本帝国統治下の台湾から法政大学に入学し、友人からお古のライカを買うというところが物語の冒頭。 当然当時のカメラはマニュアルなので、距離感とか露出をその場その場で判断しなければならない。そのために日常の中でひたすら物体や人物との距離を考え続け、無意識のクセになっていく…というカメラ初心者の努力がここまで描かれる小説はたぶん初めて読んだ。マニュアルで撮る練習とかをしてた頃を思い出して懐かしくなる。 時系列を行ったり来たりしつつ、鄧騰煇以外の視点も所々に挟まれてゆく。同じように日本で写真を学びながら、より芸術的側面や技法に価値を置いた彭瑞麟。海外の写真家がとらえる中国像に違和感を抱き、理想的なイメージを追求した郎静山…などなど、さまざまな立場の写真家によるモノローグが描かれる。中心にあるのは絵画主義/リアリズム/新興写真的な対立だけれど、それぞれにとっての写真論=人生観が物語の奥行きを出しているような気がした。 “時々考えた。自分が東京で勉強できているのは、家の財産に頼っているからであり、父の許可があってこそライカが買えるのだと。それでいて日本で見聞したすべてが、彼をどんどん故郷から引き離すのだった。” (P174) 出自である客家の伝統的な価値観と、都会で身に付けた近代的価値観の対立。作中の鄧騰煇の人生には、このようなアイデンティティの分裂の経験が何度か登場する。台湾人でありながら、日本の総督府によって身分を保障された写真家であるという分裂。戦後の国民党政権の元での外省人と本省人の分裂(二二八事件)。 これらはそのまま台湾という国が経験してきたさまざまな分断の歴史でもある。そして自分はそういった歴史を一切知らなかった。 “中国撮影学会は政府の反共坑俄〔反共産主義、反ソ連〕文化政策に呼応して、明るく前向きで、純潔かつ崇高な作品を撮るように会員に求めた。反対に頽廃、ロマンチック、赤、黄〔ポルノ〕、黒〔堕落〕の作品は否定された。その定義の下では、写実的、郷土的、人びとの真の生活を反映したものはもちろん、社会の不公正を告発する作品なども否定の対象だった。” (P316) 日本に都合の良いプロパガンダ的な写真を求められた戦時中から光復を経て自由になったかと思いきや、今度は反共の嵐の中で別の制約が……という状況。もちろんこの「中国」は中華民国のこと。 写真を撮るということについても色々と示唆的な記述が多く、考えさせられる。 “理屈からすれば、肖像写真はその個人を表すものだ。[…]だが彼は懐疑的だった。虚な目でこわばった表情をしたこんな写真が、本当に誰かを表し得るのだろうか。” (P256) これは作家としての写真と仕事としての写真の葛藤だと思うんだけれど、似たようなことは考えたことがあるなぁと思った。証明写真とか撮ってると考えるよな。 その辺の意識の問題をうまいこと折り合いをつけていたのが植田正治だと思う。 “写真とは、言わば撮影者の心象を映す鏡だ。だが心象を完璧に映した情景に出会えるかどうかは、運次第だ。それは往々にして電光石火のごとき一瞬で、百分の一秒の間にシャッターを切らなければ、過ぎ去ったきり二度とは戻らない。初心者でも一度か二度はその瞬間を捉えることができるかもしれない。しかしツバメが風雨を察知するように、あるいはナマズが地震を予知するように、神秘の瞬間が近づいていると直感し、鏡のように澄んだ心でそれを捉えることができるのは、しっかりと準備を整えた写真家だけだ。 つまるところ写真というのは、カメラで何を捉えたかではなく、何に心を捕らわれたかだという人がいるのは、そういう意味なのだ。” (P348) 時代に翻弄されさまざまな写真を撮ってきた主人公が最終的にこういった真理に至るところは読み応えがある。写真を作品として発表することから、より純粋に撮ること自体へとフォーカスしていく。 一応補足すると南光自身は写真以外に文章などはほとんど残していないようなので、こういう写真論とかは作家が南光の写真と向き合って導き出したものであるらしい。 本文書体:リュウミンオールド 装幀:佐野裕哉 装画:柳智之 写真:鄧南光(Te Nan-Kua) - 2025年12月4日
 移動と階級伊藤将人読み終わった移動格差の実態と、それをめぐるさまざまな研究の紹介の本。 格差の実態についてはまあ想像通りな感じで、たとえば過去一年以内の居住都府県外への旅行経験は、年収300万円未満と600万円以上では27%の差がある(P66)。あるいは海外旅行経験では、300万円未満の人々では2人に1が一年に一度も経験しないが、600万円以上では5人に1人である……といったふうに。 その最低ラインの半分にも満たずにやっている自分としては当然海外なんて選択肢にも上がらないし、「旅行」的な旅行も2年に一度行ければ良いぐらいの感じではある。でもこれは現在の金銭的な問題というよりも、本書でいう「移動資本」に含まれる潜在的な移動可能性(今までの経験なども踏まえた移動することへのハードルみたいな)が低いからと言えそうだ。海外一人旅なんて絶対ムリムリ! 個人的にはそういう経済状況以外でも、移動をめぐる困難についてのアンケート(P83)で「副鼻腔炎」の辛さを語っている人に大いに共感する。めっちゃ鼻ズビズビの状態で電車とか乗ることにちょっと躊躇いを感じてしまう。花粉の時期ならまだしも、年がら年中なので……。 “政治学者の山本圭は『嫉妬論』のなかで、人類学者のガッサン・ハージの議論から、現代においては、空間的な移動や、社会階層を上昇するといった移動をめぐる「移動性への妬み」が存在すると指摘する(山本:2024)。背景には、人生がうまくいっていると感じられる(「見込みのある人生」)ためには、その人が「どこかに向かっている」と前進している感覚(「想像的な移動性」)が不可欠であるという現代の状況がある(Hage:2015、山本:2024)” (P86) 孫引きの引用みたいになっちゃうけど(本書はかなり引用が多い)、ここは感覚的にすごい分かるな。やっぱり動いてる人ってすごそうに見えちゃうんだよな。だからこそ「移動が関心を集めるからこそ、逆に地域の伝統やナショナリズムが強まっている部分もある」(P41)ということにもなってくるのだろう。 あと個人的には書店のトークイベントに参加できる人が羨ましい。 一方で、そういう心情とも密接に繋がってくるであろう「成功したいなら移動せよ」的な価値観。これはそもそも「移動したから成功する」というより、能力や「移動資本」(お金、移動しようとしたときに移動できる環境、過去の移動経験の蓄積…などのさまざまな要素)を元から持つ人が成功するという能力主義の価値観なので、批判されている。 フッ軽は正義、を信じられる時点で恵まれてるということだ。 また、そういう価値観で語られがちな「ノマド」に関しても、全く逆のイメージが提示されている。『ノマドランド』に出てくるような現代アメリカのノマドは、定住を手放さなければならなかった「下層ノマド」なのだ。(そしてさらに、そういう生活でさえほとんどが白人にしかできないという状況もあるという) 移動をめぐる論点の一つとして「移民」についても書かれているが、国境をまたいで受け入れられる移民にも格差が存在するという。 “高度人材を移民として積極的に受け入れる一方で、「役立たない」「使えない」移民は、積極的に受け入れずに拒もうとする移民政策を「選別的移民政策」という。” (P165) ここでもまた能力主義。これはもちろん移民に限らず移住でもあるんじゃないかな。スキルを持った人だけ地方に来て欲しい、子を産むつもりのある人だけ来て欲しい……。 また、ジェンダーの観点からは「女性のほうが運転中のケガのリスクが高い」という指摘もあり、その理由が安全設計のベースが男性基準であったから…というのはめちゃくちゃ制度の問題だなぁと思った。万人向けの設計は難しいのかもしれないが(アメ車が日本に不向きなように)、選択肢としてもっとバランスが良くなるのが望ましいだろう。 他にも移住マーケティングが長年男性稼ぎ主モデルばかりだったとか、移動という分野でもさまざまなギャップが存在していることが分かった。 あとテーマとは直接関係ないけど、個人的には「移動とメンタル」というテーマについても読みたいなと思う。 本文書体:秀英明朝 装幀:中島英樹/中島デザイン
移動と階級伊藤将人読み終わった移動格差の実態と、それをめぐるさまざまな研究の紹介の本。 格差の実態についてはまあ想像通りな感じで、たとえば過去一年以内の居住都府県外への旅行経験は、年収300万円未満と600万円以上では27%の差がある(P66)。あるいは海外旅行経験では、300万円未満の人々では2人に1が一年に一度も経験しないが、600万円以上では5人に1人である……といったふうに。 その最低ラインの半分にも満たずにやっている自分としては当然海外なんて選択肢にも上がらないし、「旅行」的な旅行も2年に一度行ければ良いぐらいの感じではある。でもこれは現在の金銭的な問題というよりも、本書でいう「移動資本」に含まれる潜在的な移動可能性(今までの経験なども踏まえた移動することへのハードルみたいな)が低いからと言えそうだ。海外一人旅なんて絶対ムリムリ! 個人的にはそういう経済状況以外でも、移動をめぐる困難についてのアンケート(P83)で「副鼻腔炎」の辛さを語っている人に大いに共感する。めっちゃ鼻ズビズビの状態で電車とか乗ることにちょっと躊躇いを感じてしまう。花粉の時期ならまだしも、年がら年中なので……。 “政治学者の山本圭は『嫉妬論』のなかで、人類学者のガッサン・ハージの議論から、現代においては、空間的な移動や、社会階層を上昇するといった移動をめぐる「移動性への妬み」が存在すると指摘する(山本:2024)。背景には、人生がうまくいっていると感じられる(「見込みのある人生」)ためには、その人が「どこかに向かっている」と前進している感覚(「想像的な移動性」)が不可欠であるという現代の状況がある(Hage:2015、山本:2024)” (P86) 孫引きの引用みたいになっちゃうけど(本書はかなり引用が多い)、ここは感覚的にすごい分かるな。やっぱり動いてる人ってすごそうに見えちゃうんだよな。だからこそ「移動が関心を集めるからこそ、逆に地域の伝統やナショナリズムが強まっている部分もある」(P41)ということにもなってくるのだろう。 あと個人的には書店のトークイベントに参加できる人が羨ましい。 一方で、そういう心情とも密接に繋がってくるであろう「成功したいなら移動せよ」的な価値観。これはそもそも「移動したから成功する」というより、能力や「移動資本」(お金、移動しようとしたときに移動できる環境、過去の移動経験の蓄積…などのさまざまな要素)を元から持つ人が成功するという能力主義の価値観なので、批判されている。 フッ軽は正義、を信じられる時点で恵まれてるということだ。 また、そういう価値観で語られがちな「ノマド」に関しても、全く逆のイメージが提示されている。『ノマドランド』に出てくるような現代アメリカのノマドは、定住を手放さなければならなかった「下層ノマド」なのだ。(そしてさらに、そういう生活でさえほとんどが白人にしかできないという状況もあるという) 移動をめぐる論点の一つとして「移民」についても書かれているが、国境をまたいで受け入れられる移民にも格差が存在するという。 “高度人材を移民として積極的に受け入れる一方で、「役立たない」「使えない」移民は、積極的に受け入れずに拒もうとする移民政策を「選別的移民政策」という。” (P165) ここでもまた能力主義。これはもちろん移民に限らず移住でもあるんじゃないかな。スキルを持った人だけ地方に来て欲しい、子を産むつもりのある人だけ来て欲しい……。 また、ジェンダーの観点からは「女性のほうが運転中のケガのリスクが高い」という指摘もあり、その理由が安全設計のベースが男性基準であったから…というのはめちゃくちゃ制度の問題だなぁと思った。万人向けの設計は難しいのかもしれないが(アメ車が日本に不向きなように)、選択肢としてもっとバランスが良くなるのが望ましいだろう。 他にも移住マーケティングが長年男性稼ぎ主モデルばかりだったとか、移動という分野でもさまざまなギャップが存在していることが分かった。 あとテーマとは直接関係ないけど、個人的には「移動とメンタル」というテーマについても読みたいなと思う。 本文書体:秀英明朝 装幀:中島英樹/中島デザイン - 2025年11月28日
 まず最初の方でZINEの作り手のことを「zinester(ジンスタ)」と呼ぶ話が出てくる。これは前に読んだ『日本のZINEについて知っていることすべて』でも出てきたが、日本ではまったく浸透していないよな。まあそれはさておき、この「ster」は「ギャングスタ」と同じ接尾語で、蔑称的なニュアンスのつく「〜する人」という意味らしい。zineカルチャーではそのニュアンスを逆手にとって自ら名乗っているということだ。「クィア」などと同じカウンターカルチャー。 これが日本で普及しないのはやっぱりそのカウンター精神が抜け落ちちゃってるんかなとも思う。というか普通にギャングスタもお星さま(スターダム)のほうで思ってる人が絶対に多い。自分もここを読んで「あ、そっか…」となったし。 “ジンを作る人たちに「自分のことを伝えるなんて恥ずかしい」だとか「自己満足」だとか「ガス抜きにすぎない」だとかの意地悪を言う人たちもいる。だけど私は「伝えてみないと何もはじまらないのでは?」と思う。ジン活動は自分の人生を主体的に生きるための練習であり、同時にかけがえのない本番。” (P15) 第一章のはじめに書かれているこの文章がとても良い。もしかしたら本書が一番伝えたいのはここなのかもしれない。 自分自身、紙ものを作り始めた頃は鬱深く、誰かと繋がりたいけれどコミュニケーションがしんどい……というような時期だった。余計なこと(クオリティ、反応の過多や批判など)を考えずに、ただ作ってみる。ZINEづくりにはセルフケアとしての面もあるんだなと思った。 そして、メディアを作ることも一つのコミュニケーションである。時間はかかるかもしれないが、誰かに届くという可能性もある。それは直接的なコミュニケーションが困難な状態でも何らかの希望になり得るかもしれない。 “自分のことで頭がいっぱいで他人に興味を持てない人、すなわちあまりにも読者を意識できない人、恨みや憎しみや悲しみを伝えたいのにうまく表現できない人……ジンってそう言う不器用な人たちのためのメディアでもあるのに、自分にはそれを受け止めきれる度量がない。” (P61) オンラインショップもされていて、作るだけじゃなく他人の作品を扱う立場でもあった野中さんの、正直な胸中が語られている箇所である。 まず前半の部分が刺さった。ZINEづくりにはセルフケアの効果があり、「自分のことで頭がいっぱい」な人(私である)にもZINEの世界は開かれている。自分語りしかできなくても、センスなくても、ZINEを作ってもいいんだ。そのことがまず、救いになる。 一方の後半部分は、こう繋がっていく。 “ジンのいいところは誰でも作りたかったら簡単に作れるところ。作者がいまこの時点でどれだけ評価されているかは関係ない。でも、だからこそごまかしが効かないし、技能やセンスが問われてしまって残酷な面もあると思います。” (同前) これはたぶん、ZINEを取り扱う方は誰しも感じる葛藤じゃなかろうか。個人的には好き、でも大衆ウケはしないので商売としては取り扱えない……というような。 あるいは、イベントでZINEを販売したけれど全く売れなかったという経験がある方には、痛いほど分かるかもしれない。圧倒的なセンスの差。 でも正直、制作者側がそこまで気に病むことではないような気がしてきた。だってしょうがないんだもん。(野中さんも「タイミングと相性」と書かれている) もちろんその挫折をバネにデザインやセンスを磨いていける人はそれでいいと思う。そのままビッグになってくれ。 でも売れないで病んじゃってZINEから離れてしまうのは、やっぱりなんか違うと思う。「惨敗でした」とか投稿見ると、悲しくなる。それは完全に場の空気に飲まれてしまっているのではないか。売れることが良いことだ、という。 ZINEブームの功罪なのかもしれない。市場が大きくなるにつれて、こういうのがZINEだというようなイメージが形成されつつある。多くの独立系書店で取り扱われ、SNSでたびたび目にする作品。デザインが良く、内容が充実していて、のちに書き手が商業デビュー……というようなもの。それはもう「軽出版」という表現が合っているのではないかと個人的には思う。 で、そこと同じ土俵で勝負…いや戦ってるわけじゃないんだけど、同列にあることに違和感を感じたり、疲れたりしてしまう時はどうすれば良いのか。 もうちょっと小規模なイベントや場所に出してみる、という手があると思う。3000ブースの文フリでは誰の目にも止まらずとも、2〜30ブース規模のイベントならば、もしかしたら誰かが立ち止まってくれるかもしれない。正直これはめちゃくちゃ心が回復する。 そしてもう一つは、あえてフリペでやってみる……というのはどうだろう? 本書で紹介されている手作り感のあるペラもの、文フリなどで売られていることは少ないが、配られているフリペには割と近しいものがあったりする。販促ツールとして商品紹介や試し読みだけのフリペも多いのだが、中には案外パーソナルなことが書かれていたりするものも、あるにはある。クオリティを突き詰めて商品を作ったけれど、ちょっと息抜き的なものも作りたい。気軽なコミュニケーションも行いたい。そういう思いで作られている方もいるのかもしれない。これはまさに「贈与文化としてのZINE」と言えるのではないだろうか。 本文書体:筑紫明朝、筑紫オールドゴシック ブックデザイン:大原大次郎/宮添浩司 カバー・本文イラスト:おおきなお
まず最初の方でZINEの作り手のことを「zinester(ジンスタ)」と呼ぶ話が出てくる。これは前に読んだ『日本のZINEについて知っていることすべて』でも出てきたが、日本ではまったく浸透していないよな。まあそれはさておき、この「ster」は「ギャングスタ」と同じ接尾語で、蔑称的なニュアンスのつく「〜する人」という意味らしい。zineカルチャーではそのニュアンスを逆手にとって自ら名乗っているということだ。「クィア」などと同じカウンターカルチャー。 これが日本で普及しないのはやっぱりそのカウンター精神が抜け落ちちゃってるんかなとも思う。というか普通にギャングスタもお星さま(スターダム)のほうで思ってる人が絶対に多い。自分もここを読んで「あ、そっか…」となったし。 “ジンを作る人たちに「自分のことを伝えるなんて恥ずかしい」だとか「自己満足」だとか「ガス抜きにすぎない」だとかの意地悪を言う人たちもいる。だけど私は「伝えてみないと何もはじまらないのでは?」と思う。ジン活動は自分の人生を主体的に生きるための練習であり、同時にかけがえのない本番。” (P15) 第一章のはじめに書かれているこの文章がとても良い。もしかしたら本書が一番伝えたいのはここなのかもしれない。 自分自身、紙ものを作り始めた頃は鬱深く、誰かと繋がりたいけれどコミュニケーションがしんどい……というような時期だった。余計なこと(クオリティ、反応の過多や批判など)を考えずに、ただ作ってみる。ZINEづくりにはセルフケアとしての面もあるんだなと思った。 そして、メディアを作ることも一つのコミュニケーションである。時間はかかるかもしれないが、誰かに届くという可能性もある。それは直接的なコミュニケーションが困難な状態でも何らかの希望になり得るかもしれない。 “自分のことで頭がいっぱいで他人に興味を持てない人、すなわちあまりにも読者を意識できない人、恨みや憎しみや悲しみを伝えたいのにうまく表現できない人……ジンってそう言う不器用な人たちのためのメディアでもあるのに、自分にはそれを受け止めきれる度量がない。” (P61) オンラインショップもされていて、作るだけじゃなく他人の作品を扱う立場でもあった野中さんの、正直な胸中が語られている箇所である。 まず前半の部分が刺さった。ZINEづくりにはセルフケアの効果があり、「自分のことで頭がいっぱい」な人(私である)にもZINEの世界は開かれている。自分語りしかできなくても、センスなくても、ZINEを作ってもいいんだ。そのことがまず、救いになる。 一方の後半部分は、こう繋がっていく。 “ジンのいいところは誰でも作りたかったら簡単に作れるところ。作者がいまこの時点でどれだけ評価されているかは関係ない。でも、だからこそごまかしが効かないし、技能やセンスが問われてしまって残酷な面もあると思います。” (同前) これはたぶん、ZINEを取り扱う方は誰しも感じる葛藤じゃなかろうか。個人的には好き、でも大衆ウケはしないので商売としては取り扱えない……というような。 あるいは、イベントでZINEを販売したけれど全く売れなかったという経験がある方には、痛いほど分かるかもしれない。圧倒的なセンスの差。 でも正直、制作者側がそこまで気に病むことではないような気がしてきた。だってしょうがないんだもん。(野中さんも「タイミングと相性」と書かれている) もちろんその挫折をバネにデザインやセンスを磨いていける人はそれでいいと思う。そのままビッグになってくれ。 でも売れないで病んじゃってZINEから離れてしまうのは、やっぱりなんか違うと思う。「惨敗でした」とか投稿見ると、悲しくなる。それは完全に場の空気に飲まれてしまっているのではないか。売れることが良いことだ、という。 ZINEブームの功罪なのかもしれない。市場が大きくなるにつれて、こういうのがZINEだというようなイメージが形成されつつある。多くの独立系書店で取り扱われ、SNSでたびたび目にする作品。デザインが良く、内容が充実していて、のちに書き手が商業デビュー……というようなもの。それはもう「軽出版」という表現が合っているのではないかと個人的には思う。 で、そこと同じ土俵で勝負…いや戦ってるわけじゃないんだけど、同列にあることに違和感を感じたり、疲れたりしてしまう時はどうすれば良いのか。 もうちょっと小規模なイベントや場所に出してみる、という手があると思う。3000ブースの文フリでは誰の目にも止まらずとも、2〜30ブース規模のイベントならば、もしかしたら誰かが立ち止まってくれるかもしれない。正直これはめちゃくちゃ心が回復する。 そしてもう一つは、あえてフリペでやってみる……というのはどうだろう? 本書で紹介されている手作り感のあるペラもの、文フリなどで売られていることは少ないが、配られているフリペには割と近しいものがあったりする。販促ツールとして商品紹介や試し読みだけのフリペも多いのだが、中には案外パーソナルなことが書かれていたりするものも、あるにはある。クオリティを突き詰めて商品を作ったけれど、ちょっと息抜き的なものも作りたい。気軽なコミュニケーションも行いたい。そういう思いで作られている方もいるのかもしれない。これはまさに「贈与文化としてのZINE」と言えるのではないだろうか。 本文書体:筑紫明朝、筑紫オールドゴシック ブックデザイン:大原大次郎/宮添浩司 カバー・本文イラスト:おおきなお - 2025年11月14日
 レンブラントの帽子バーナード・マラマッド読み終わった
レンブラントの帽子バーナード・マラマッド読み終わった - 2025年11月12日
 女性差別はどう作られてきたか中村敏子読み終わったタイトルの通り、差別は自然に広がったものではなく、人為的に広められてきたものである。 “差別の根底には、自分と異なる他者に対し自分の方が優れていると思いたいという感覚があります。[…]こうした感覚だけでは社会的な差別構造は成立しません。それが当たり前で正しいのだという明確な説明が必要です” (P19) 本書は女性差別を後ろ盾する根拠となった制度がどのように成立したのかを、西洋と日本それぞれの歴史から解説する。 まず西洋ではキリスト教における聖書解釈から男>女という価値観が根付いていたとされる。それを近代社会にまで持ち込んで制度に組み込んでしまったのがジョン・ロックの「社会契約論」なのだ。 ロックが王権を否定するために持ち出した自然状態では、女性は当然男性に従属するものとされていた。また、国家と家族が分離された結果、女性は私的領域に閉じ込められることとなった。 このような女性の立場をより固定化してきたのが、コモン・ローにおける「カバチャー(coverture」」である。この法のもとでは、妻は財産や自身の肉体に対して無権利状態とみなされる。 さらに18世紀、ウィリアム・ブラックストンが「契約」の概念を適用したことにより、この差別構造は20世紀まで引き継がれてしまった。 一方の日本においては、徳川幕府が儒教にもとづいた政治を行ったため女性差別の構造を作ったとしばしば説明される。しかし、実際江戸時代までの日本の「家」構造は夫婦が共同で運営する中小企業のようなものであり、西洋のように女性が無権利状態におかれているわけではなかった。 日本において西洋的な女性差別構造がもたらされたのは、明治時代の民法制定の際に西洋のものを参照したこと、その後の法整備において戸主=男性の権利を優遇したことが差別構造を生み出した要因である。 また、本書ではこれらの制度のなかにおいて、男女平等的な価値観を唱えたホッブスと福沢諭吉の論も紹介されている。それぞれの制度が生み出される際、女性差別的でない方法が可能であったということが、現実的に選択された制度を批判する形となっている。 以下、感想。 まずすべての根源的な創世記の価値観。ここは実際聖書を読んだときにも違和感を覚えた気がするが、この解釈のために生み出された何世紀もの差別を思うとやり切れない。 日本の「家」構造や夫婦のあり方に関しては何となく昔からそうだったんだろうなと思っていたので、意外だった(もちろんこれはあくまで「ある面においては制度的に西洋よりマシだった」というだけの話で、女性の役割は限りなく固定化されていたのだろうが)。 歴史にほとんど関心を抱いてこなかったので難しかったが、構造を知るためには制度のことももっと知らなければならないなと思った。 本文書体:リュウミン 装幀:原研哉
女性差別はどう作られてきたか中村敏子読み終わったタイトルの通り、差別は自然に広がったものではなく、人為的に広められてきたものである。 “差別の根底には、自分と異なる他者に対し自分の方が優れていると思いたいという感覚があります。[…]こうした感覚だけでは社会的な差別構造は成立しません。それが当たり前で正しいのだという明確な説明が必要です” (P19) 本書は女性差別を後ろ盾する根拠となった制度がどのように成立したのかを、西洋と日本それぞれの歴史から解説する。 まず西洋ではキリスト教における聖書解釈から男>女という価値観が根付いていたとされる。それを近代社会にまで持ち込んで制度に組み込んでしまったのがジョン・ロックの「社会契約論」なのだ。 ロックが王権を否定するために持ち出した自然状態では、女性は当然男性に従属するものとされていた。また、国家と家族が分離された結果、女性は私的領域に閉じ込められることとなった。 このような女性の立場をより固定化してきたのが、コモン・ローにおける「カバチャー(coverture」」である。この法のもとでは、妻は財産や自身の肉体に対して無権利状態とみなされる。 さらに18世紀、ウィリアム・ブラックストンが「契約」の概念を適用したことにより、この差別構造は20世紀まで引き継がれてしまった。 一方の日本においては、徳川幕府が儒教にもとづいた政治を行ったため女性差別の構造を作ったとしばしば説明される。しかし、実際江戸時代までの日本の「家」構造は夫婦が共同で運営する中小企業のようなものであり、西洋のように女性が無権利状態におかれているわけではなかった。 日本において西洋的な女性差別構造がもたらされたのは、明治時代の民法制定の際に西洋のものを参照したこと、その後の法整備において戸主=男性の権利を優遇したことが差別構造を生み出した要因である。 また、本書ではこれらの制度のなかにおいて、男女平等的な価値観を唱えたホッブスと福沢諭吉の論も紹介されている。それぞれの制度が生み出される際、女性差別的でない方法が可能であったということが、現実的に選択された制度を批判する形となっている。 以下、感想。 まずすべての根源的な創世記の価値観。ここは実際聖書を読んだときにも違和感を覚えた気がするが、この解釈のために生み出された何世紀もの差別を思うとやり切れない。 日本の「家」構造や夫婦のあり方に関しては何となく昔からそうだったんだろうなと思っていたので、意外だった(もちろんこれはあくまで「ある面においては制度的に西洋よりマシだった」というだけの話で、女性の役割は限りなく固定化されていたのだろうが)。 歴史にほとんど関心を抱いてこなかったので難しかったが、構造を知るためには制度のことももっと知らなければならないなと思った。 本文書体:リュウミン 装幀:原研哉 - 2025年11月12日
 読み終わった@ 自宅最近、ZINEが分からなくなってきたので。 1960年代〜2010年代の自費出版史を概観する一冊。7割ぐらいが実際の刊行物の紹介になっているビジュアル本であり、フルカラーで書影を見ることができる。年代ごとに章が立てられており、扉にはその時代の作風をざっと俯瞰するような対談が載せられている。また後半には関係者諸氏へのインタビューも収録。 もちろん星の数ほどある自費出版物を網羅するなんて到底無理なので、あくまでお二人の蔵書や知識に基づいた内容にはなっているが、なんとなく時代の雰囲気みたいなのは感じ取れて面白い。 “つまりDIYというのは世界的な高度経済成長の最中に,余暇に楽しむ趣味性の高いモノづくりのことだった。趣味がスタート地点だからこそ画一的な大量生産に抗うものが作れる。[…]大資本に依存し過ぎて潰されないようにする術が“趣味”にはあると思う。選択肢の多様性を広げることが独占への対抗手段だから。” (P13) 元来のDIYについて、ばるぼらさん。これは健全なZINEづくりマインドのヒントになりそう。昨今の赤字を出さないことを重視する風潮について、野中さんは「チープな贈与文化としてあるZINEのことも忘れないで! って言いたくなっちゃう」(P13)とも。 中村公彦さん・BELENEさん・山川直人さんの鼎談「コミティアという場所/マンガの周縁に在りつづけて」(P217-220)の中に、森博嗣さんが三重大助手時代参加されていた同人誌『JET PLOPOST』の話が出てきている。そのサークルの「東京支部長みたいな感じ」がコミティア初代代表・土屋真志さんだったとか。そんな繋がりもあるんだなぁ。 “「私は店で取り扱うにあたって,見栄えがしっかりしてることをすごく重視してました。手作りのものは本屋として扱いにくいんです。いろんな紙切れが袋に入ってるとかね。重ねられへんし,棚にも差せないし” 誠光社・堀部篤史さんのインタビューより。これはやっぱり、お店側からするとそうだよな〜と思う。逆に言うと独立系書店をフォローするだけでは出会えないZINEも限りなくある。 ZINEという言葉にはまだまだ「最近流行りの」という枕詞がつきがちだけれど、広く見ればもっと歴史はあるはずだよな〜と思っていた。ので、本書でその辺のことを色々と知れたのが良かった。 ポリティカルなもの、音楽的なもの、ファッション的なもの、サブカル的なもの……とそれぞれに歴史があって、デザイン性なんかは今の各ジャンルにも引き継がれているような気がした。 一方で、圧倒的に都会中心の文化だった。70年代以降のタウン誌の流れも、東京のカルチャーに触発されてという部分があるらしいし。そして現代では「タウン誌」っていったら毎月ポストに投函されてる、お店の広告とクーポンが付いてる冊子というイメージしかない。正直広告だけならSNSでもう十分なのだから、あえて紙でやるなら違ったことをやって欲しいな。 自分の納得感の落とし所としては、「自己表現」と「コミュニケーション」のバランスみたいなところを考えるのが良さそうだなと思った。読んでもらう、お店に置いてもらう、売れる……などを追求すると現在の最適解はエッセイアンソロジーみたいになるけど、もっとミニなコミュニケーションでいいのであれば古本市で五部配るでも全然いいわけで。派閥は違えども、そのどちらも「ZINE」と捉えるのに十分な歴史はあるということ。 最近はZINEイベントも細分化してきたので、ここらで「コピー本オンリー」があっても面白いかも。 本文書体:?(分かる方教えてください。本欄に似てるが濁点の処理が違う…。方正黒体には似てる) 装丁・デザイン:山田和寛(nipponia) イラスト:丹野杏香
読み終わった@ 自宅最近、ZINEが分からなくなってきたので。 1960年代〜2010年代の自費出版史を概観する一冊。7割ぐらいが実際の刊行物の紹介になっているビジュアル本であり、フルカラーで書影を見ることができる。年代ごとに章が立てられており、扉にはその時代の作風をざっと俯瞰するような対談が載せられている。また後半には関係者諸氏へのインタビューも収録。 もちろん星の数ほどある自費出版物を網羅するなんて到底無理なので、あくまでお二人の蔵書や知識に基づいた内容にはなっているが、なんとなく時代の雰囲気みたいなのは感じ取れて面白い。 “つまりDIYというのは世界的な高度経済成長の最中に,余暇に楽しむ趣味性の高いモノづくりのことだった。趣味がスタート地点だからこそ画一的な大量生産に抗うものが作れる。[…]大資本に依存し過ぎて潰されないようにする術が“趣味”にはあると思う。選択肢の多様性を広げることが独占への対抗手段だから。” (P13) 元来のDIYについて、ばるぼらさん。これは健全なZINEづくりマインドのヒントになりそう。昨今の赤字を出さないことを重視する風潮について、野中さんは「チープな贈与文化としてあるZINEのことも忘れないで! って言いたくなっちゃう」(P13)とも。 中村公彦さん・BELENEさん・山川直人さんの鼎談「コミティアという場所/マンガの周縁に在りつづけて」(P217-220)の中に、森博嗣さんが三重大助手時代参加されていた同人誌『JET PLOPOST』の話が出てきている。そのサークルの「東京支部長みたいな感じ」がコミティア初代代表・土屋真志さんだったとか。そんな繋がりもあるんだなぁ。 “「私は店で取り扱うにあたって,見栄えがしっかりしてることをすごく重視してました。手作りのものは本屋として扱いにくいんです。いろんな紙切れが袋に入ってるとかね。重ねられへんし,棚にも差せないし” 誠光社・堀部篤史さんのインタビューより。これはやっぱり、お店側からするとそうだよな〜と思う。逆に言うと独立系書店をフォローするだけでは出会えないZINEも限りなくある。 ZINEという言葉にはまだまだ「最近流行りの」という枕詞がつきがちだけれど、広く見ればもっと歴史はあるはずだよな〜と思っていた。ので、本書でその辺のことを色々と知れたのが良かった。 ポリティカルなもの、音楽的なもの、ファッション的なもの、サブカル的なもの……とそれぞれに歴史があって、デザイン性なんかは今の各ジャンルにも引き継がれているような気がした。 一方で、圧倒的に都会中心の文化だった。70年代以降のタウン誌の流れも、東京のカルチャーに触発されてという部分があるらしいし。そして現代では「タウン誌」っていったら毎月ポストに投函されてる、お店の広告とクーポンが付いてる冊子というイメージしかない。正直広告だけならSNSでもう十分なのだから、あえて紙でやるなら違ったことをやって欲しいな。 自分の納得感の落とし所としては、「自己表現」と「コミュニケーション」のバランスみたいなところを考えるのが良さそうだなと思った。読んでもらう、お店に置いてもらう、売れる……などを追求すると現在の最適解はエッセイアンソロジーみたいになるけど、もっとミニなコミュニケーションでいいのであれば古本市で五部配るでも全然いいわけで。派閥は違えども、そのどちらも「ZINE」と捉えるのに十分な歴史はあるということ。 最近はZINEイベントも細分化してきたので、ここらで「コピー本オンリー」があっても面白いかも。 本文書体:?(分かる方教えてください。本欄に似てるが濁点の処理が違う…。方正黒体には似てる) 装丁・デザイン:山田和寛(nipponia) イラスト:丹野杏香 - 2025年11月11日
 ぐつぐつ、お鍋安野モヨコ,岸本佐知子読み終わった二日間お鍋を食べながら(うちの鍋は味噌煮)読んだ。 池波正太郎が小鍋立ての良さを説いた後に東海林さだおが小鍋立ては陰気だなんて書いてて面白い(その孤独さを称揚している文章ではある)。もちろん狙って並べられてるんだろうが。 フグについて書いている面々も多く、山口あたりの武士はフグに当たったら不忠不孝で家名断絶だったみたいな話も初めて知った。 いきなり「アンコウのトモズの舌触りは少なくとも接吻よりは多様である」(P65)などと言い始める宇能鴻一郎も面白いし、小島政二郎の書く泉鏡花のエピソードもなんだか可愛らしいおじさんだし、池内紀は「ちくわは穴がおいしいのだ」(P88)なんて名言を残している。 ねじめ正一「すき焼き——父と二人だけの鍋」は父子水入らずの旅館の夜を回想した一作。これは良いなぁ。 「腹がくちくなる」っていうの、久々に聞いた。形容詞だから終止連体は「くちい」になるのか。そうなると「くるちい」から来てそうだなと分かる。 ラスボス的存在の北大路魯山人は、貝類は鍋に入れすぎると味を悪くするのでよろしくないと仰っており、貝苦手な私としてはそーだそーだと言いたくなるのだった。 しかし出汁の出るものと出汁を吸うものを交互に煮るとか毎回具材を綺麗に片付けてから次を入れるなんてのはご家庭のお鍋ではあまりに面倒なので、そこは寄せ鍋でいいです…。 筒井ともみ「寄せ鍋嫌い」では、家族が不安定だったゆえに鍋が嫌いになった話が書かれている。確かに、純粋に楽しい鍋の思い出を持っている人ばかりじゃないよなぁと思った。 料理の話は時に残酷なまでに格差を映し出す。(昨今はそういうアプローチの小説も多いよね) 最後の最後が岡島京子による鍋料理でなく鍋自体の話で終わっているのもおかしみがある。「メリークリスマス!」ということで、やはり今の時期に読むのが良い一冊だった。 (ただし、お鍋の文章をずっと読んでると胸焼けがしてくる。次はサラダとかを読みたい…) 本文書体:リュウミン カバー装画:植田まほ子 ロゴ・表紙デザイン:粟津潔
ぐつぐつ、お鍋安野モヨコ,岸本佐知子読み終わった二日間お鍋を食べながら(うちの鍋は味噌煮)読んだ。 池波正太郎が小鍋立ての良さを説いた後に東海林さだおが小鍋立ては陰気だなんて書いてて面白い(その孤独さを称揚している文章ではある)。もちろん狙って並べられてるんだろうが。 フグについて書いている面々も多く、山口あたりの武士はフグに当たったら不忠不孝で家名断絶だったみたいな話も初めて知った。 いきなり「アンコウのトモズの舌触りは少なくとも接吻よりは多様である」(P65)などと言い始める宇能鴻一郎も面白いし、小島政二郎の書く泉鏡花のエピソードもなんだか可愛らしいおじさんだし、池内紀は「ちくわは穴がおいしいのだ」(P88)なんて名言を残している。 ねじめ正一「すき焼き——父と二人だけの鍋」は父子水入らずの旅館の夜を回想した一作。これは良いなぁ。 「腹がくちくなる」っていうの、久々に聞いた。形容詞だから終止連体は「くちい」になるのか。そうなると「くるちい」から来てそうだなと分かる。 ラスボス的存在の北大路魯山人は、貝類は鍋に入れすぎると味を悪くするのでよろしくないと仰っており、貝苦手な私としてはそーだそーだと言いたくなるのだった。 しかし出汁の出るものと出汁を吸うものを交互に煮るとか毎回具材を綺麗に片付けてから次を入れるなんてのはご家庭のお鍋ではあまりに面倒なので、そこは寄せ鍋でいいです…。 筒井ともみ「寄せ鍋嫌い」では、家族が不安定だったゆえに鍋が嫌いになった話が書かれている。確かに、純粋に楽しい鍋の思い出を持っている人ばかりじゃないよなぁと思った。 料理の話は時に残酷なまでに格差を映し出す。(昨今はそういうアプローチの小説も多いよね) 最後の最後が岡島京子による鍋料理でなく鍋自体の話で終わっているのもおかしみがある。「メリークリスマス!」ということで、やはり今の時期に読むのが良い一冊だった。 (ただし、お鍋の文章をずっと読んでると胸焼けがしてくる。次はサラダとかを読みたい…) 本文書体:リュウミン カバー装画:植田まほ子 ロゴ・表紙デザイン:粟津潔 - 2025年10月29日
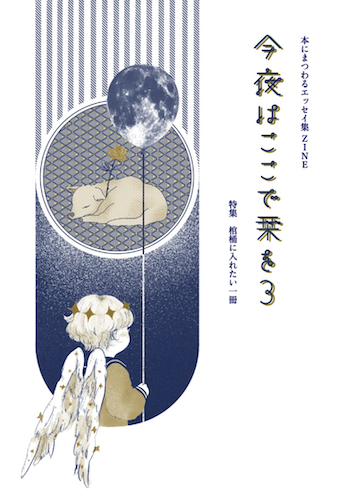 今夜はここで栞を3ぬこ,だんて,あたろう,ゆーかり,イチトセ,久納美輝,仲村景,北彗白朔,史依明,塒小太郎,パンダ大明神,守田樹,宗谷ヌマ,木澤曽元,海猫沢めろん,湯屋こゆ,真尋,矢凪エチカ,穂坂ユズハ,綿巻あまね読み終わった先日円頓寺で買った「本にまつわるエッセイ集ZINE」こと『今夜はここで栞を3』を読む。第一号は大阪文フリ、二号は岐阜駅本の市、そして円頓寺、と毎回いろんな場所で手に入れているのが面白い。そして今のところ唯一シリーズで勝っているZINEかも。 今作もレトロ印刷さんの特殊印刷カバーとリソ刷り本文がものとして素敵だ。 確かこのシリーズは元々FFとかのオンラインゲームで開催されている読書会メンバーが中心に参加されていたと思うのだが、今回は初っ端から海猫沢めろん先生で、確実に豪華になっていっている。 ZINEは感想を書いたらほぼ著者に届くので、一言ずつコメントしていきたい。敬称略。実際にどんな本が紹介されているかはネタバレなので、想像するか買って確認されたし。 海猫沢めろん「黒煙と鳩」。作家にとって最高傑作は最新作(夢枕獏がそう言っているらしい)はなるほど確かに作り手としてそうだよなぁと思った。自身の一冊が燃える描写で終わるのが作家らしく、美しい。 ぬこ「感性まで消費するか、消費を感性で乗り越えるか」。教育の罪業と美術館賞の意義について。何でもかんでもアウトプット前提で向き合おうとしてしまう(それはこのZINEを読むことについても言える。自己矛盾。。)態度。自分も消費社会、というより資本主義的意味第一主義社会の豚です…。 湯屋こゆ「傲慢ロリィタはこうして創られた」。乙女的反抗としてのロリィタ。なるほど、そういう在り方でもあるのか。ユリイカ2024年5月号とか読んだらもっと理解深まるだろうか。 仲村景「リビドーとフィロソフィー」。著者にとって恋愛と読書は似ているという。読書に向かうリビドーというのが面白いなと思った。でも確かに言われてみると自分もそこまで理性的に読んでないかも。 守田樹「柔らかくてあたたかい」。苦しみを忘れないでいるための読書。自分だったら辛い時期を思い出してしまう読書は避けるかもしれない(今のところ忘却曲線がそれを上回っているのであまり思い浮かばないが…)。それを分かりつつ向き合えるだけ、強いのだと思う。 綿巻あまね「日本における棺桶に入れるということは即ち燃やしたいということ」。肥大化した自意識…うっ頭が。その効能を聞いてしまうと、積読にあるこの本を直ちに読まねばならない気がしてきた。 久納美輝「梅を知る」。自身の経験から本の話に繋げ、そしてテーマの「棺桶に入れたい」まで持っていく流れがものすごく上手い。この方の書評をもっと読みたいと思った。 だんて「少年期の夜想曲」。小説を読んだかのような読後感。ご本人にとってはもちろんリアルな人生で、自分にはとても想像できない。が、こうして小説のように語れるようになった出会いというのは大きいのだろうと思った。 史依明「死に賭ける」。自身に降りかかった「死」と、見えてきた限界について。非常に重い経験をされているのに、どこか前向きさを感じられるのがすごい。 矢凪エチカ「あの魔女は竜になって別の空を飛んでいるよ」。“私たちは大人になると、死を遠ざけることを学ぶ”。本当に。向き合ってるようで向き合っていない、みたいな。児童文学、もっと読んでみたい。 パンダ大明神「拝啓」。「あなた」への手紙であり、読者への手紙でもあり、そしておそらく著者自身への手紙でもあるのだろう。なるほど、そういう本だったのかということを知った。 北彗白朔「おばけの漬物になりたい」。おばけになってしたいことの数々はどれもほっこり。由々しき噂は自分も初めて知ったが本当に由々しきである。自分の場合は、どうしたものか。。 木澤曽元「煙でも土でも食い物でもなく、ただ金になる」。そのノリでこの本(しかも原語)が出てくるの、面白すぎるな。読書会猛者(?)のかほり。 塒小太郎「英雄失格」。若さとともに失われてゆくものについて。でも年老いると逆に童心に帰るとも言うし、もしかしたらまだまだ分からないのではないだらうか。 真尋「盆暗青春狂騒曲(独居編)」。勢いが楽しい。まさに青春。しかしそれ程までの怖さなのか、積読にあるこの本は……。自分も読んだ暁には誰かにプレゼントしようかな(ふつうに嫌われそう)。 あたろう「好きな場所へ行こう、キミならそれが出来る」。ロックだ。曲として聴くのと、こうして文章で読むことはまた違う感覚がある。 イチトセ「ごめんね、とりさんが大活躍する話じゃなかったと思うんだけど……」。トリ判定の広さに思わず身近な方を想像してしまった。これはもう「墓場まで持って」行ってあげてくださいね。 宗谷ヌマ「あの世のお供はこれから作れ」。確かに自分も急にこのお題を出されたら悩むだろう。作ってやるという目標目指して生きていくというのも、それはそれで楽しいかもしれない。 ゆーかり「我が子の手で棺に入れてほしい本」。最も「棺」から遠い場所でともにあった本だからこそ、なのかもしれない。改めて、いろんな人生のさまざまな時に寄り添う本があるのだなぁと思う。 穂坂ユズハ「三ツ矢サイダーとサクレの夏に」。確かにこのテーマを考えられること、その余裕があることは「贅沢」なのかもしれない。人生には本なんて読めない時もままある。その苦しみを自分が理解することはできないけれど、生きてこうして「特別な一冊」を届けてくれてありがとうございます。 最後の25ページにはだんてさんの詩と矢凪さんの写真で締めくくられている。単純な連想だけれど中島みゆきを思い浮かべる。 「時間」と「言葉」という二つの要素がさまざまな結び目を作ってゆくのが興味深い。そういえばYesにも「Time and a Word」という曲があったではないか。
今夜はここで栞を3ぬこ,だんて,あたろう,ゆーかり,イチトセ,久納美輝,仲村景,北彗白朔,史依明,塒小太郎,パンダ大明神,守田樹,宗谷ヌマ,木澤曽元,海猫沢めろん,湯屋こゆ,真尋,矢凪エチカ,穂坂ユズハ,綿巻あまね読み終わった先日円頓寺で買った「本にまつわるエッセイ集ZINE」こと『今夜はここで栞を3』を読む。第一号は大阪文フリ、二号は岐阜駅本の市、そして円頓寺、と毎回いろんな場所で手に入れているのが面白い。そして今のところ唯一シリーズで勝っているZINEかも。 今作もレトロ印刷さんの特殊印刷カバーとリソ刷り本文がものとして素敵だ。 確かこのシリーズは元々FFとかのオンラインゲームで開催されている読書会メンバーが中心に参加されていたと思うのだが、今回は初っ端から海猫沢めろん先生で、確実に豪華になっていっている。 ZINEは感想を書いたらほぼ著者に届くので、一言ずつコメントしていきたい。敬称略。実際にどんな本が紹介されているかはネタバレなので、想像するか買って確認されたし。 海猫沢めろん「黒煙と鳩」。作家にとって最高傑作は最新作(夢枕獏がそう言っているらしい)はなるほど確かに作り手としてそうだよなぁと思った。自身の一冊が燃える描写で終わるのが作家らしく、美しい。 ぬこ「感性まで消費するか、消費を感性で乗り越えるか」。教育の罪業と美術館賞の意義について。何でもかんでもアウトプット前提で向き合おうとしてしまう(それはこのZINEを読むことについても言える。自己矛盾。。)態度。自分も消費社会、というより資本主義的意味第一主義社会の豚です…。 湯屋こゆ「傲慢ロリィタはこうして創られた」。乙女的反抗としてのロリィタ。なるほど、そういう在り方でもあるのか。ユリイカ2024年5月号とか読んだらもっと理解深まるだろうか。 仲村景「リビドーとフィロソフィー」。著者にとって恋愛と読書は似ているという。読書に向かうリビドーというのが面白いなと思った。でも確かに言われてみると自分もそこまで理性的に読んでないかも。 守田樹「柔らかくてあたたかい」。苦しみを忘れないでいるための読書。自分だったら辛い時期を思い出してしまう読書は避けるかもしれない(今のところ忘却曲線がそれを上回っているのであまり思い浮かばないが…)。それを分かりつつ向き合えるだけ、強いのだと思う。 綿巻あまね「日本における棺桶に入れるということは即ち燃やしたいということ」。肥大化した自意識…うっ頭が。その効能を聞いてしまうと、積読にあるこの本を直ちに読まねばならない気がしてきた。 久納美輝「梅を知る」。自身の経験から本の話に繋げ、そしてテーマの「棺桶に入れたい」まで持っていく流れがものすごく上手い。この方の書評をもっと読みたいと思った。 だんて「少年期の夜想曲」。小説を読んだかのような読後感。ご本人にとってはもちろんリアルな人生で、自分にはとても想像できない。が、こうして小説のように語れるようになった出会いというのは大きいのだろうと思った。 史依明「死に賭ける」。自身に降りかかった「死」と、見えてきた限界について。非常に重い経験をされているのに、どこか前向きさを感じられるのがすごい。 矢凪エチカ「あの魔女は竜になって別の空を飛んでいるよ」。“私たちは大人になると、死を遠ざけることを学ぶ”。本当に。向き合ってるようで向き合っていない、みたいな。児童文学、もっと読んでみたい。 パンダ大明神「拝啓」。「あなた」への手紙であり、読者への手紙でもあり、そしておそらく著者自身への手紙でもあるのだろう。なるほど、そういう本だったのかということを知った。 北彗白朔「おばけの漬物になりたい」。おばけになってしたいことの数々はどれもほっこり。由々しき噂は自分も初めて知ったが本当に由々しきである。自分の場合は、どうしたものか。。 木澤曽元「煙でも土でも食い物でもなく、ただ金になる」。そのノリでこの本(しかも原語)が出てくるの、面白すぎるな。読書会猛者(?)のかほり。 塒小太郎「英雄失格」。若さとともに失われてゆくものについて。でも年老いると逆に童心に帰るとも言うし、もしかしたらまだまだ分からないのではないだらうか。 真尋「盆暗青春狂騒曲(独居編)」。勢いが楽しい。まさに青春。しかしそれ程までの怖さなのか、積読にあるこの本は……。自分も読んだ暁には誰かにプレゼントしようかな(ふつうに嫌われそう)。 あたろう「好きな場所へ行こう、キミならそれが出来る」。ロックだ。曲として聴くのと、こうして文章で読むことはまた違う感覚がある。 イチトセ「ごめんね、とりさんが大活躍する話じゃなかったと思うんだけど……」。トリ判定の広さに思わず身近な方を想像してしまった。これはもう「墓場まで持って」行ってあげてくださいね。 宗谷ヌマ「あの世のお供はこれから作れ」。確かに自分も急にこのお題を出されたら悩むだろう。作ってやるという目標目指して生きていくというのも、それはそれで楽しいかもしれない。 ゆーかり「我が子の手で棺に入れてほしい本」。最も「棺」から遠い場所でともにあった本だからこそ、なのかもしれない。改めて、いろんな人生のさまざまな時に寄り添う本があるのだなぁと思う。 穂坂ユズハ「三ツ矢サイダーとサクレの夏に」。確かにこのテーマを考えられること、その余裕があることは「贅沢」なのかもしれない。人生には本なんて読めない時もままある。その苦しみを自分が理解することはできないけれど、生きてこうして「特別な一冊」を届けてくれてありがとうございます。 最後の25ページにはだんてさんの詩と矢凪さんの写真で締めくくられている。単純な連想だけれど中島みゆきを思い浮かべる。 「時間」と「言葉」という二つの要素がさまざまな結び目を作ってゆくのが興味深い。そういえばYesにも「Time and a Word」という曲があったではないか。 - 2025年10月21日
 わたしたちの怪獣久永実木彦読み終わった以前に読書会で紹介されていたので知った気がする。で、たまたま図書館で見かけたので借りたのだ。ジャンル的にはSF短編集? 四作収録されている。 表題作の「わたしたちの怪獣」。「わたし」が家族に隠れて免許を取得したその日、妹が父を殺し、舞浜には怪獣が出現する。「わたし」は父の古いカローラに乗り、怪獣騒動に乗じて父の遺体を遺棄しにいく……という展開。 そもそもなぜ父が殺されたのか、という理由が、父が職場でふざけた撮った写真がSNSで炎上し、子どもたちは虐められ、母は出ていき、父はストレスから子どもたちに暴力を振るうようになったから……というのがめちゃくちゃ現代的で救いがない。怖あ。 暴れ回る怪獣に対しては当然自衛隊が出動して、その戦況のようなものが合間に挟まれているのだが、ここは読んでてめっちゃ『シン・ゴジラ』だなと思う。ちなみに怪獣には脅威の自己再生能力と、触れたものを消滅させてしまうシャボン玉を放出する能力があるので、自衛隊も手が出ない。 この怪獣は死んだ父親なのではないかという匂わせがあり、いや、怪獣は私たちの心の中に……みたいなところで「あ〜」となるのだが、最終的にあんまり関係なさそうだぞという感じで終わるのが良かった。 個人的にこういう話は、実際はどうだったのか(怪獣は私たちの何かしらが具現化していたのか)よりも、作者が何を書きたかったのかが気になる。本作に関して言えば、やはりここなのだと思う。 “生きるということは、進むということなのだから。それが、正しい方向であればいいと思う。わたしもあゆむも、ずいぶんおかしなところへ行ってしまった。いまは引き返して、もう一度前に進む準備をしている。” (P70) 道を誤っても引き返せるということ。いや、現実世界であればもうかなり絶望的な状況ということになってしまうのだが、だからこその怪獣なのかもしれない。むしろ怪獣は社会の方だよな。ありきたりな言い方だけど。 続いて二作目「ぴぴぴ・ぴぴっぴ」。某シュールギャグ系漫画を思わせるタイトルだが、おそらく特に関係はない。 小型タイムマシンが発明された社会。主人公は「時間局」に勤務し、事故などで死亡する運命にあった人々を助ける「声かけ」の仕事をしている。 山奥での寮暮らしに退屈している主人公の唯一の楽しみは、動画投稿サイト〈パイプス〉に投稿されるとあるユーザーの動画である。事故が「声かけ」により改変される以前の様子を撮影するその動画には、様々な人物の死亡シーンが収められており……。 この時点である程度想像されるオチがあると思うが、実際はそんな綺麗なものではなく、不条理とまではいかないまでもモヤっとする感じだった。「ぼく」と小栗は表裏一体だったのだろうか。 三作目「夜の安らぎ」。飛行機事故で両親を失った少女・楓は伯父伯母の家に居候をしている。学校では虐められ、バイト先ではモラハラ気味の店長に小言を言われ、そして従姉妹の未佳に対しては報われない恋を抱いている。 そんな現実に苦しむ楓のもとに、どう見ても吸血鬼としか思えない男が現れる。楓は自分を吸血鬼にして欲しいと懇願するが……。 個人的にはこの作品がいちばんまとまりの良さを感じた。終わり方についてはそうなっちゃったかぁと思うところもあるけれど。 最後はこれまたクセの強い「『アタック・オブ・ザ・キラー・トマト』を観ながら」。とある出来事で手に怪我を負い、逃げるように小さな映画館に入った「ぼく」。そこでは伝説的“Z級”映画の「アタック・オブ・キラー・トマト」が上映されようとしていた。映写機のトラブルで客の大半が帰った後も残っていた「ぼく」と個性的な面々たちは、外で大きな爆発音を聞き、その後に発令されたJアラートに従い映画館に立て篭もる。外では人々の頭が2倍に膨らみ「ゾンビ」と化してしまう現象が発生していたのだった——。 ゾンビものの王道的展開をゆきつつ、表題作と一瞬繋がったところはテンション上がった(同じ世界線なのかは不明だが)。映画のタイトルがすごい出てくるのだけどほぼ分からないので、知っていたらもっと楽しめるだろう。恐竜神父は冒頭30秒だけ見たことあるけど……。 全編通してのテーマは割とはっきりしていて、現実と非現実ということなんだろう。登場人物たちは苦しい現実に置かれていて、そんな時、目の前に非現実への扉が開く。そこで彼らはどのような行動を取るのか。 “いつだつて現実も、世界も、わたしを拒絶してきたじゃん……普通に生きられないようにしてきたじゃん! だから、幻想の世界に行くしかなかったの” (P190) 「夜の安らぎ」で主人公が叫ぶ言葉が強く印象に残った。 本文書体:リュウミン 装画:鈴木康士 装幀:岩郷重力+WONDER WORKZ。
わたしたちの怪獣久永実木彦読み終わった以前に読書会で紹介されていたので知った気がする。で、たまたま図書館で見かけたので借りたのだ。ジャンル的にはSF短編集? 四作収録されている。 表題作の「わたしたちの怪獣」。「わたし」が家族に隠れて免許を取得したその日、妹が父を殺し、舞浜には怪獣が出現する。「わたし」は父の古いカローラに乗り、怪獣騒動に乗じて父の遺体を遺棄しにいく……という展開。 そもそもなぜ父が殺されたのか、という理由が、父が職場でふざけた撮った写真がSNSで炎上し、子どもたちは虐められ、母は出ていき、父はストレスから子どもたちに暴力を振るうようになったから……というのがめちゃくちゃ現代的で救いがない。怖あ。 暴れ回る怪獣に対しては当然自衛隊が出動して、その戦況のようなものが合間に挟まれているのだが、ここは読んでてめっちゃ『シン・ゴジラ』だなと思う。ちなみに怪獣には脅威の自己再生能力と、触れたものを消滅させてしまうシャボン玉を放出する能力があるので、自衛隊も手が出ない。 この怪獣は死んだ父親なのではないかという匂わせがあり、いや、怪獣は私たちの心の中に……みたいなところで「あ〜」となるのだが、最終的にあんまり関係なさそうだぞという感じで終わるのが良かった。 個人的にこういう話は、実際はどうだったのか(怪獣は私たちの何かしらが具現化していたのか)よりも、作者が何を書きたかったのかが気になる。本作に関して言えば、やはりここなのだと思う。 “生きるということは、進むということなのだから。それが、正しい方向であればいいと思う。わたしもあゆむも、ずいぶんおかしなところへ行ってしまった。いまは引き返して、もう一度前に進む準備をしている。” (P70) 道を誤っても引き返せるということ。いや、現実世界であればもうかなり絶望的な状況ということになってしまうのだが、だからこその怪獣なのかもしれない。むしろ怪獣は社会の方だよな。ありきたりな言い方だけど。 続いて二作目「ぴぴぴ・ぴぴっぴ」。某シュールギャグ系漫画を思わせるタイトルだが、おそらく特に関係はない。 小型タイムマシンが発明された社会。主人公は「時間局」に勤務し、事故などで死亡する運命にあった人々を助ける「声かけ」の仕事をしている。 山奥での寮暮らしに退屈している主人公の唯一の楽しみは、動画投稿サイト〈パイプス〉に投稿されるとあるユーザーの動画である。事故が「声かけ」により改変される以前の様子を撮影するその動画には、様々な人物の死亡シーンが収められており……。 この時点である程度想像されるオチがあると思うが、実際はそんな綺麗なものではなく、不条理とまではいかないまでもモヤっとする感じだった。「ぼく」と小栗は表裏一体だったのだろうか。 三作目「夜の安らぎ」。飛行機事故で両親を失った少女・楓は伯父伯母の家に居候をしている。学校では虐められ、バイト先ではモラハラ気味の店長に小言を言われ、そして従姉妹の未佳に対しては報われない恋を抱いている。 そんな現実に苦しむ楓のもとに、どう見ても吸血鬼としか思えない男が現れる。楓は自分を吸血鬼にして欲しいと懇願するが……。 個人的にはこの作品がいちばんまとまりの良さを感じた。終わり方についてはそうなっちゃったかぁと思うところもあるけれど。 最後はこれまたクセの強い「『アタック・オブ・ザ・キラー・トマト』を観ながら」。とある出来事で手に怪我を負い、逃げるように小さな映画館に入った「ぼく」。そこでは伝説的“Z級”映画の「アタック・オブ・キラー・トマト」が上映されようとしていた。映写機のトラブルで客の大半が帰った後も残っていた「ぼく」と個性的な面々たちは、外で大きな爆発音を聞き、その後に発令されたJアラートに従い映画館に立て篭もる。外では人々の頭が2倍に膨らみ「ゾンビ」と化してしまう現象が発生していたのだった——。 ゾンビものの王道的展開をゆきつつ、表題作と一瞬繋がったところはテンション上がった(同じ世界線なのかは不明だが)。映画のタイトルがすごい出てくるのだけどほぼ分からないので、知っていたらもっと楽しめるだろう。恐竜神父は冒頭30秒だけ見たことあるけど……。 全編通してのテーマは割とはっきりしていて、現実と非現実ということなんだろう。登場人物たちは苦しい現実に置かれていて、そんな時、目の前に非現実への扉が開く。そこで彼らはどのような行動を取るのか。 “いつだつて現実も、世界も、わたしを拒絶してきたじゃん……普通に生きられないようにしてきたじゃん! だから、幻想の世界に行くしかなかったの” (P190) 「夜の安らぎ」で主人公が叫ぶ言葉が強く印象に残った。 本文書体:リュウミン 装画:鈴木康士 装幀:岩郷重力+WONDER WORKZ。 - 2025年5月29日
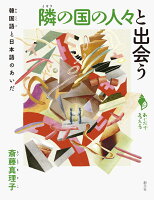 隣の国の人々と出会う斎藤真理子読み終わった
隣の国の人々と出会う斎藤真理子読み終わった
読み込み中...
