
とーひろ
@kajihirorz1316
2025年5月29日
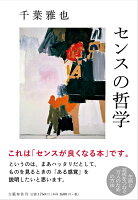
センスの哲学
千葉雅也
読み終わった
また読みたい
芸術の見方のヒントを得たいと思って手に取ったが、芸術に対して「意味」なんて考えなくて良い、という発想が目から鱗。最終的には何だか人間の可能性を肯定してくれる本だった。哲学者であり、かつ自らも文学・美術の作家である千葉先生だからこそ書ける本。また何年か後に読み返してみたい。
・鑑賞サイドのみにいると、「意味」ばかり気にしてしまう(自分)。制作サイドでは、材料を集めて組み立てるという意味が生まれる前段階がある。
・再現思考から降りることがセンスの目覚め。モデルは抽象化して要素を使うのが良い。
・意味から離れたリズムの面白さがわかる、それが最小限のセンサの良さ。リズム、対比、運動、反復、展開、凸凹を楽しむ。脱意味、即物。
・「いないいないばあ」は存在/不存在の対立とリズム。人間の根本的な寂しさを乗り越える。安定を求める生物が、遊びの中で不安定と安定の反復を楽しむ。そこに絡まる多様なうねりを楽しむ。ビートとうねり。(文学の描写の良さは意味から離れたところにあるのでは?と思った)
・人間はグラデーション。規則性から逸脱するとイキイキする
・安定(意味)を求めるのが本能であるにも関わらず、予想から外れている展開にも喜びを感じるのが人間。不快かつ快。不快だと思うのは思い込みがあり、自分の予測範囲を超えるから。
・具体で見るから関連性がわからなくなる。抽象化(気分を最大限に開放)すれば、すべては「存在する」という意味で繋がる。
・意味や目的に達する前の遊び/無駄の時間を楽しむのが芸術。
・ペットが可愛いのは予測誤差があるから。予測通り動くなら、ビリヤードの玉と同じ。安定を求めているのに、耐えられる予測誤差(偶発性)を欲する。



