
JUMPEI AMANO
@Amanong2
2025年6月29日
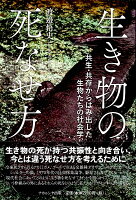
生き物の死なせ方
渡邉悟史
まだ読んでる
@ カフェ
第6章は序章で簡単に提示されていた言葉にまつわる理論的背景の整理。具体的な事例検証を経て理論的・概念的な話がくる構成、親切だし分かりやすい。
1. 死政治
〈ムベンビは現代の世界において、武器・凶器(weapons)が人間を最大限に破壊し、死の世界を創造するさまざまな仕方を説明するために死政治を提唱した。ムベンビが注目したのは、人びとを生かす政治においても複雑な要素がその成立に関わっているように、死政治においても人びとを死なせる手立てやその手立てが実行される空間が生成されていくことであり、そこには身体に対するさまざまな手管[...]や政治的戦略[...]、科学技術・兵器、インフラ、情念[...]、人口動態、そして地勢が絡み合っているということであった。/本書でもこの死政治を、死なせ方のデザインへ着目するために導入してみたい。〉(207頁)
2. 生態系とアッサンブラージュ
〈統一体の発想とは対照的に、アッサンブラージュは集合体を、誤解を恐れずに言えば、もう少し緩く、いい加減に捉える。集合体を構成している個々の要素は「全体」と不可分の関係にあるわけではない。[...]/このようにアッサンブラージュでは「全体」に見えるものはあくまで一時の仮設的なものと考える。同時に「一部」に見えるものは、たった一つの「全体」に献身・貢献するものなのではなく、他との組み合わせ、他の「全体」に組み込まれる可能性をつねに潜在させ、その機会を狙っていると考える。〉(210-211頁)
3. 死の共振性と死のデザイン
〈本書ではそこから[=農村社会学者の徳野貞雄の議論から]感情や活動の誘発という発想を借用し、死にゆく身体や死体を起点として、さまざまなものが寄せ集められ、組み込まれていくさまを表すために共振性という語を用いている。[...]/つまり、死にゆく身体や死んだ身体にはさまざまなものを引き込む「力」があると本書では主張したい。〉(214頁)
〈死は私たちの体をまさぐってくる。このような観点からすると、第一に、デザインを共振性のコントロールとして捉えることが可能である。〉(215頁)
〈第二に[...]死の共振性という観点の導入は、殺された死体への注目を促す。殺された死体にもそれを扱うためのさまざまな手管があるはずである。本書は死政治を「殺し方」の圏域の外へ拡張したかたちで用いる。〉(217頁)
文鳥の通院があったのでとりあえず2節まで。

