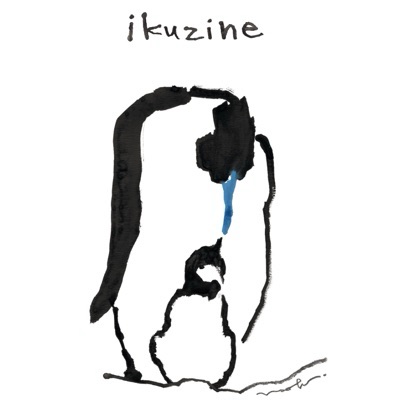
Yamada Keisuke
@afro108
2025年7月27日

生きる力が湧いてくる
野口理恵
読み終わった
おすすめしていただいたので読んだ。前情報を全く入れないまま読んだ結果、一人の女性の壮大な人生に巻き込まれていくような読書体験で驚いた。「世の中には色んな人がいる」と口で言うのは簡単だが、壮絶な環境において、それでも人生を続けていく覚悟が本著にはたっぷり詰まっていた。
著者は編集者を生業としているようで、文芸誌も自身で発行するようなバイタリティのある肩書きとは裏腹に、母を自死で亡くし、その後に父が病で他界、さらに兄を自死で亡くすという壮絶すぎる半生を過ごしたらしく、自分の過去から現在まで、あまりにも赤裸々なエッセイ、私小説の数々に読む手は止まらなかった。
フィクションではよく描かれる「天涯孤独な人」が、実際に存在し、ただ悲しみに沈むのではなく、「生きる」ことに向き合っている様子が生活の機微を含め、丁寧に描かれている。冒頭、実家のガーデニングにまつわるほっこりしたエッセイから始まり、装丁やタイトルからして、日常系のエッセイ集なのかと思いきや、いきなり母親の自死の話が始まり、そのギャップにも驚かされた。
これまでの人生で辛いことがたくさんあったことは経歴からして容易に想像つくわけだが、そんな御涙頂戴な展開の話は入っていない。むしろ、その逆境をどうやってタイトルどおり「生きる」ためのエネルギー源としていくか、肉親が不在の中でとにかく自己を肯定し、自分をブチ上げていく。無条件で愛してくれる存在がいないから、自分のことを愛する。まさにご自愛。そんなエピソードがたくさん入っているので、セルフケアの文脈に位置付けることが可能で、文字どおり「生きる力が湧いてくる」人もいるだろう。
ただ一つ、個人的にしんどく感じたのは、兄の自死をモチーフに、兄の視点から語られる小説があったことだ。他人の家族の話であり、どう書くかは著者の自由だ。ただ、自死に至るまで、相当な葛藤があっただろうと想像がつく中で、あまりにも自死を単純化しすぎている気がした。それは繰り返し述べられるように著者にとって「死」があまりにも日常的に存在することも影響しているのかもしれない。しかし、だとすれば、より自死に対して慎重な取り扱いが必要なように思う。
とはいえ、家族偏重主義に対するカウンターとしてはこれ以上機能するエッセイはないだろう。家族を大切にすること自体は否定されるべきではないが、他人に対して「家族を大切にする」価値観を一種のテンプレートとして押し付けることに違和感がある。先日見たバチェラー・ジャパンの最新シーズンで、やたらと「家族が〜」と連呼されていて、それが無条件に受け入れるべき価値観として提示されていることにモヤモヤしていたので、本著における家族観には溜飲が下がった。
歳を重ねれば重ねるほど、死との距離は自然と縮まっていく。しかし、死は順番どおりには訪れない。それは突然で、理不尽なものだ。そんな死と、私たちはどう向き合えばいいのか。壮絶な人生を生き抜いてきた人が書いた言葉だからこそ、本著はそのヒントをくれる一冊だった。



