
JUMPEI AMANO
@Amanong2
2025年8月5日
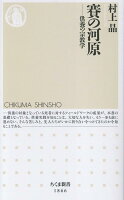
賽の河原
村上晶
読み始めた
お風呂読書
@ 自宅
川倉賽の河原の大祭の変遷(第3章)、型に従った口寄せができるイタコがほとんどいないのになぜ口寄せは続くのかという話(第4章)、あとは第2章のモノのところが面白かった。いくつかメモ。
◆仏教と民俗の分け難さ
〈「仏教」/「民俗」の間に境界が設けられ、両者がまじりあう実際の供養の現場〉(第2章、66頁)
◆モノの供養
〈モノがいつ死ぬのかは明確ではない。[...]モノの事例からは、死があるから供養があるのではなくて、供養があるから死があるということが見えてくる。[...]「死を与える」という側面は、実は人の供養においても重要である。〉(同、73頁)
◆生活宗教(佐々木宏幹の議論)
〈葬儀の場で、僧侶たちは死者を「成仏」させるという方向性を目指している。しかし、参列者たちが志向していることは[..]いわば「成祖」である。/ここには微妙なずれがある。〉(同、93頁)
◆川倉の大祭
〈指摘したいのは、川倉に見られるように、供養とは敬虔で神妙なものでなければいけないという規範意識が、現代社会において先鋭化しているのではないかということである。/娯楽と入り混じった複合的な感情は認められず、あえて強い言葉でいえば、悲しむことしか許容されない、そんな状況があるのではないか。〉(第3章、133頁)
◆地域の供養実践の変化(口寄せなど)
〈あの世での成長というイメージの弱まり〉(第4章、177頁)
〈現代社会では、死者を死者とするというイメージよりも、死者を(生きたままの姿で)記憶し続けていくほうがはるかに称揚されている。〉(同、178頁)
〈従来の供養実践がもっていた、死者を手放す技法〉(同、179頁)




