賽の河原
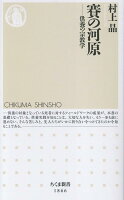
21件の記録
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年11月2日読み終わった結局営業中に一気読みしてしまった。1日で本を読み終えたのは久しぶり。 死者を手放すこと、つまり死者があちらの世界で成長していくという認識を持つこと、というくだりが印象的だった。現代はその感覚が薄れており、むしろ「生前のままの状態」を「記憶しておくこと」が意識されているのではないか、というところも。たぶん私は手放す側のタイプ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年11月2日読み終わった結局営業中に一気読みしてしまった。1日で本を読み終えたのは久しぶり。 死者を手放すこと、つまり死者があちらの世界で成長していくという認識を持つこと、というくだりが印象的だった。現代はその感覚が薄れており、むしろ「生前のままの状態」を「記憶しておくこと」が意識されているのではないか、というところも。たぶん私は手放す側のタイプ。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年11月2日読み始めた『失われたいくつかの〜』を家に忘れてきたためこちらを読む。 こうした抽象的な口寄せの内容が依頼者にとってリアルになるためには、聞いている側が具体的な人間や事件を組み入れる必要があるとする。そうした依頼者の参加がなければ口寄せは無意味になるという。(p.41) そうした曖昧な感覚を捉えるためには、むしろ真偽という尺度は邪魔になる。真偽を突き詰めようとすると、本当でも嘘でもないという次元が見えなくなってしまうためである。(p.45) イタコの語りを読み解くには、イタコと依頼者のあいだに「型」が共有されている必要があるとのこと。ゆえにそれが共有され得ない「有名人を降霊させる」といったものは虚無である。 生成AIによるフェイク動画のことを考えてみると、おそらくここにも「騙す/騙される」の型がある。フェイクだとわかって楽しむ、あるいは本気で騙されたとしても最後にはフェイクだとわかるような仕掛けがある。そういった型があるからこそ、我々は安全に楽しむことができる。しかしここ最近のフェイク動画はその型を失っていて、作り手は本気で騙すために作り、受け手は騙されていることに気づけないままでいることが増えている。もはやこれは娯楽ではない。「騙されている」ことに気がつかない者がミサイルのボタンを押す未来はすぐそこにある。「騙されていることに気がつかない者がミサイルのボタンを押している」フェイク動画を見た別の最高責任者が、それを本当だと信じてミサイルのボタンを押すかもしれない。こんな陳腐なストーリーで世界は滅ぶ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年11月2日読み始めた『失われたいくつかの〜』を家に忘れてきたためこちらを読む。 こうした抽象的な口寄せの内容が依頼者にとってリアルになるためには、聞いている側が具体的な人間や事件を組み入れる必要があるとする。そうした依頼者の参加がなければ口寄せは無意味になるという。(p.41) そうした曖昧な感覚を捉えるためには、むしろ真偽という尺度は邪魔になる。真偽を突き詰めようとすると、本当でも嘘でもないという次元が見えなくなってしまうためである。(p.45) イタコの語りを読み解くには、イタコと依頼者のあいだに「型」が共有されている必要があるとのこと。ゆえにそれが共有され得ない「有名人を降霊させる」といったものは虚無である。 生成AIによるフェイク動画のことを考えてみると、おそらくここにも「騙す/騙される」の型がある。フェイクだとわかって楽しむ、あるいは本気で騙されたとしても最後にはフェイクだとわかるような仕掛けがある。そういった型があるからこそ、我々は安全に楽しむことができる。しかしここ最近のフェイク動画はその型を失っていて、作り手は本気で騙すために作り、受け手は騙されていることに気づけないままでいることが増えている。もはやこれは娯楽ではない。「騙されている」ことに気がつかない者がミサイルのボタンを押す未来はすぐそこにある。「騙されていることに気がつかない者がミサイルのボタンを押している」フェイク動画を見た別の最高責任者が、それを本当だと信じてミサイルのボタンを押すかもしれない。こんな陳腐なストーリーで世界は滅ぶ。




- 長谷川半蔵@Kusasumi_hnz02025年10月26日読んでる本の内容とは直接関係ないが、辺獄がlimboで賽の河原がchildren's limboなのが腑に落ちないというか。 辺獄自体が洗礼を受けていない子供の為の物なわけで。 じゃあ夭折した子供が行くところであり日本独自である賽の河原はjapanese limboとかじゃないんかいと思いましたとさ。
 aida@9mor12025年8月10日読み終わった”五来によれば、賽の河原の「賽」は、もとは「塞ぎる」であり、賽の河原は、死者をこの世に戻さないための「塞の河原」であったという。つまり、そもそも死者を封印するための石積みであったものが、その形が崩れて、石の塔を建てるというものになっていったと解釈されている。“ 面白い。 イタコの口寄せは降ろすホトケの種類によって祭文が分かれていて、既婚か未婚かで子供か大人かを分けているという話、時代もあるだろうけどきついな。そして賽の河原は未成年者(未婚者)の霊魂の行くところなのだと。
aida@9mor12025年8月10日読み終わった”五来によれば、賽の河原の「賽」は、もとは「塞ぎる」であり、賽の河原は、死者をこの世に戻さないための「塞の河原」であったという。つまり、そもそも死者を封印するための石積みであったものが、その形が崩れて、石の塔を建てるというものになっていったと解釈されている。“ 面白い。 イタコの口寄せは降ろすホトケの種類によって祭文が分かれていて、既婚か未婚かで子供か大人かを分けているという話、時代もあるだろうけどきついな。そして賽の河原は未成年者(未婚者)の霊魂の行くところなのだと。 JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月6日読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅「彼岸の欠如」(中島岳志)が指摘される現代的な弔いに対し、〈一振りのあの世のイメージが伴うことで、死者の居場所を見つけることが容易になるかもしれない〉という可能性。自分の日頃の考え方とも近いため、結論部についてはきっとそうなんだろうなあ、と思う。仏壇、写真、記憶に関する整理が個人的には読めてよかった。 ◆仏壇という空間 〈興味深いのは、仏壇の中や周囲には実にさまざまなモノが置かれていることである。〉(第5章、192頁) 〈仏壇に置かれた種々のモノを通して不在のはずの死者が実体化して生者の生活に位置づけられる。たとえば「なんとなくの規範」によって新規に購入された仏壇も、こうして死者に属するさまざまなモノを装備することによって、死者の気配を感じさせる空間として成長していくことになるのだ。そして、代を重ねていけば[...]先祖という物理的圧が生活空間に誕生していくことになる。/ここには一種の緊張感系がある。〉(同、193-194頁) ◆死者の写真、ホトケとカミ 〈写真というメディアが従来の供養の形、そして人々の死者イメージを変容させているという[鈴木岩弓の]指摘は重要である。そして、死者がホトケではなくカミになっているとしたら、仏壇・位牌・供養というこれまでの物語の力がそれだけ弱まっているといえるのかもしれない。〉(同、211頁) ◆「弔いの多様化」? 〈人々は、あらかじめ用意されている家での供養だけではなく、利用できるものを総動員して、悲嘆に向き合ってきたといえよう。[...]現代社会の特徴のようにいわれる弔いの多様化は、今にはじまったことではないのかもしれない。ただ、その選択の幅は大きくなっている。[...]過去においても、現在においても、「死者の適切な居場所を見つける」ために、人は絶え間ない模索を続けてきた。〉(同、219頁) ◆記憶重視の死者イメージ 〈死者は記憶の中で生きているという発想と、亡き子が成長するという発想は相性がよくない。記憶とはあくまでも生前の過去の姿であり、それが変化するということは想定されていない。一方は、故人の生前という過去を向いたイメージであり、他方は死者の変化という時間の経過を含み込んだイメージである。[...]こうした記憶重視の死者のイメージは、写真や遺骨(手元供養品)といったわかりやすい表象の広まりと不可分である。〉(第6章、225頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月6日読み終わった就寝前読書お風呂読書@ 自宅「彼岸の欠如」(中島岳志)が指摘される現代的な弔いに対し、〈一振りのあの世のイメージが伴うことで、死者の居場所を見つけることが容易になるかもしれない〉という可能性。自分の日頃の考え方とも近いため、結論部についてはきっとそうなんだろうなあ、と思う。仏壇、写真、記憶に関する整理が個人的には読めてよかった。 ◆仏壇という空間 〈興味深いのは、仏壇の中や周囲には実にさまざまなモノが置かれていることである。〉(第5章、192頁) 〈仏壇に置かれた種々のモノを通して不在のはずの死者が実体化して生者の生活に位置づけられる。たとえば「なんとなくの規範」によって新規に購入された仏壇も、こうして死者に属するさまざまなモノを装備することによって、死者の気配を感じさせる空間として成長していくことになるのだ。そして、代を重ねていけば[...]先祖という物理的圧が生活空間に誕生していくことになる。/ここには一種の緊張感系がある。〉(同、193-194頁) ◆死者の写真、ホトケとカミ 〈写真というメディアが従来の供養の形、そして人々の死者イメージを変容させているという[鈴木岩弓の]指摘は重要である。そして、死者がホトケではなくカミになっているとしたら、仏壇・位牌・供養というこれまでの物語の力がそれだけ弱まっているといえるのかもしれない。〉(同、211頁) ◆「弔いの多様化」? 〈人々は、あらかじめ用意されている家での供養だけではなく、利用できるものを総動員して、悲嘆に向き合ってきたといえよう。[...]現代社会の特徴のようにいわれる弔いの多様化は、今にはじまったことではないのかもしれない。ただ、その選択の幅は大きくなっている。[...]過去においても、現在においても、「死者の適切な居場所を見つける」ために、人は絶え間ない模索を続けてきた。〉(同、219頁) ◆記憶重視の死者イメージ 〈死者は記憶の中で生きているという発想と、亡き子が成長するという発想は相性がよくない。記憶とはあくまでも生前の過去の姿であり、それが変化するということは想定されていない。一方は、故人の生前という過去を向いたイメージであり、他方は死者の変化という時間の経過を含み込んだイメージである。[...]こうした記憶重視の死者のイメージは、写真や遺骨(手元供養品)といったわかりやすい表象の広まりと不可分である。〉(第6章、225頁)
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月5日読み始めたお風呂読書@ 自宅川倉賽の河原の大祭の変遷(第3章)、型に従った口寄せができるイタコがほとんどいないのになぜ口寄せは続くのかという話(第4章)、あとは第2章のモノのところが面白かった。いくつかメモ。 ◆仏教と民俗の分け難さ 〈「仏教」/「民俗」の間に境界が設けられ、両者がまじりあう実際の供養の現場〉(第2章、66頁) ◆モノの供養 〈モノがいつ死ぬのかは明確ではない。[...]モノの事例からは、死があるから供養があるのではなくて、供養があるから死があるということが見えてくる。[...]「死を与える」という側面は、実は人の供養においても重要である。〉(同、73頁) ◆生活宗教(佐々木宏幹の議論) 〈葬儀の場で、僧侶たちは死者を「成仏」させるという方向性を目指している。しかし、参列者たちが志向していることは[..]いわば「成祖」である。/ここには微妙なずれがある。〉(同、93頁) ◆川倉の大祭 〈指摘したいのは、川倉に見られるように、供養とは敬虔で神妙なものでなければいけないという規範意識が、現代社会において先鋭化しているのではないかということである。/娯楽と入り混じった複合的な感情は認められず、あえて強い言葉でいえば、悲しむことしか許容されない、そんな状況があるのではないか。〉(第3章、133頁) ◆地域の供養実践の変化(口寄せなど) 〈あの世での成長というイメージの弱まり〉(第4章、177頁) 〈現代社会では、死者を死者とするというイメージよりも、死者を(生きたままの姿で)記憶し続けていくほうがはるかに称揚されている。〉(同、178頁) 〈従来の供養実践がもっていた、死者を手放す技法〉(同、179頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月5日読み始めたお風呂読書@ 自宅川倉賽の河原の大祭の変遷(第3章)、型に従った口寄せができるイタコがほとんどいないのになぜ口寄せは続くのかという話(第4章)、あとは第2章のモノのところが面白かった。いくつかメモ。 ◆仏教と民俗の分け難さ 〈「仏教」/「民俗」の間に境界が設けられ、両者がまじりあう実際の供養の現場〉(第2章、66頁) ◆モノの供養 〈モノがいつ死ぬのかは明確ではない。[...]モノの事例からは、死があるから供養があるのではなくて、供養があるから死があるということが見えてくる。[...]「死を与える」という側面は、実は人の供養においても重要である。〉(同、73頁) ◆生活宗教(佐々木宏幹の議論) 〈葬儀の場で、僧侶たちは死者を「成仏」させるという方向性を目指している。しかし、参列者たちが志向していることは[..]いわば「成祖」である。/ここには微妙なずれがある。〉(同、93頁) ◆川倉の大祭 〈指摘したいのは、川倉に見られるように、供養とは敬虔で神妙なものでなければいけないという規範意識が、現代社会において先鋭化しているのではないかということである。/娯楽と入り混じった複合的な感情は認められず、あえて強い言葉でいえば、悲しむことしか許容されない、そんな状況があるのではないか。〉(第3章、133頁) ◆地域の供養実践の変化(口寄せなど) 〈あの世での成長というイメージの弱まり〉(第4章、177頁) 〈現代社会では、死者を死者とするというイメージよりも、死者を(生きたままの姿で)記憶し続けていくほうがはるかに称揚されている。〉(同、178頁) 〈従来の供養実践がもっていた、死者を手放す技法〉(同、179頁)















