
JUMPEI AMANO
@Amanong2
2025年8月6日
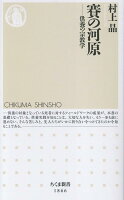
賽の河原
村上晶
読み終わった
就寝前読書
お風呂読書
@ 自宅
「彼岸の欠如」(中島岳志)が指摘される現代的な弔いに対し、〈一振りのあの世のイメージが伴うことで、死者の居場所を見つけることが容易になるかもしれない〉という可能性。自分の日頃の考え方とも近いため、結論部についてはきっとそうなんだろうなあ、と思う。仏壇、写真、記憶に関する整理が個人的には読めてよかった。
◆仏壇という空間
〈興味深いのは、仏壇の中や周囲には実にさまざまなモノが置かれていることである。〉(第5章、192頁)
〈仏壇に置かれた種々のモノを通して不在のはずの死者が実体化して生者の生活に位置づけられる。たとえば「なんとなくの規範」によって新規に購入された仏壇も、こうして死者に属するさまざまなモノを装備することによって、死者の気配を感じさせる空間として成長していくことになるのだ。そして、代を重ねていけば[...]先祖という物理的圧が生活空間に誕生していくことになる。/ここには一種の緊張感系がある。〉(同、193-194頁)
◆死者の写真、ホトケとカミ
〈写真というメディアが従来の供養の形、そして人々の死者イメージを変容させているという[鈴木岩弓の]指摘は重要である。そして、死者がホトケではなくカミになっているとしたら、仏壇・位牌・供養というこれまでの物語の力がそれだけ弱まっているといえるのかもしれない。〉(同、211頁)
◆「弔いの多様化」?
〈人々は、あらかじめ用意されている家での供養だけではなく、利用できるものを総動員して、悲嘆に向き合ってきたといえよう。[...]現代社会の特徴のようにいわれる弔いの多様化は、今にはじまったことではないのかもしれない。ただ、その選択の幅は大きくなっている。[...]過去においても、現在においても、「死者の適切な居場所を見つける」ために、人は絶え間ない模索を続けてきた。〉(同、219頁)
◆記憶重視の死者イメージ
〈死者は記憶の中で生きているという発想と、亡き子が成長するという発想は相性がよくない。記憶とはあくまでも生前の過去の姿であり、それが変化するということは想定されていない。一方は、故人の生前という過去を向いたイメージであり、他方は死者の変化という時間の経過を含み込んだイメージである。[...]こうした記憶重視の死者のイメージは、写真や遺骨(手元供養品)といったわかりやすい表象の広まりと不可分である。〉(第6章、225頁)

