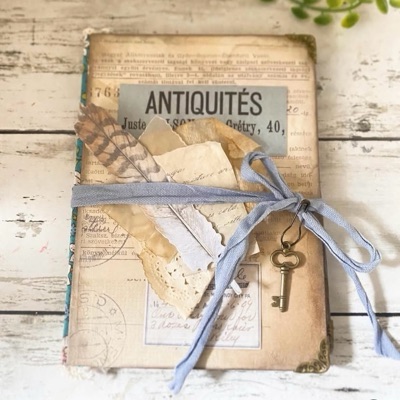DN/HP
@DN_HP
2025年8月7日

旅する練習
乗代雄介
本と日記のある人生
目当ての本がなかった図書館にて、数年前におすすめして頂いたまま読み渋っていたこの小説を手に取った。読みはじめて数行で、ああ、この文章は好きかもしれない、とおすすめの確かさを思う。
中盤までにはこの物語の終わり、あるいは語り手によってこの文章が書かれる理由の予想がつき始める(ように書かれている)。そこから読み進めるのには、作中で言及のされていた柳田國男が語る「忍耐」にも少し似ているようなものがあった気がする。予想された物語の終わりに感じるはずの感傷や感動を安易に先走って感じてしまうことを律するような「忍耐」。といって、そこで本を閉じてしまったり読み進めるのが苦痛になるわけでもないそれは、ページを捲るのももどかしいような物語のドライヴやずっと浸っていたいような心地の良い文章のグルーヴのように、本を読むことで得られる大切なもののような気もしてきていた。している。
そうやってたどり着いた最後のページには、予想された、それでもやはり心を動かされる哀しみがあって。良い小説を読んだという悦びも合って。予想された上にしかないカタルシスもあった。
帰り道は少し遠回りしてこの小説の中で叔父と姪が歩いたような川沿いの堤を歩きながら、記憶を、確かにその人がいた景色、世界を書き残す意味について考えた。書いたものは残る。残したものを読めばいつでも思い出すことが出来る。思い出すことが出来るうちは、その人は居なくならない。会えないとしても。何人かの人の顔を思い浮かべる。
行きは曇り空だったけれど、今は絵みたいな夏の空だ。暑い。冷房で冷え切ったと思っていた身体からもすぐに汗が吹き出してきた。舞台は早春だけれど、今このタイミングで、夏に読むことが出来て良かったような気もしてきた。という文章を河原に降りる階段に腰掛けて書いていたら、めちゃくちゃ蚊に刺されていた。痒いぜ。
短めの中編とはいえ、図書館で一冊読み切る、という体験をはじめてした。なかなか新鮮で良い体験だった。ちょっと夏っぽい気もした。図書館って本を読むのは、私にも向いているかもしれない。なかなかそんな余裕がある日もないけれど、次はこの小説に登場する小島信夫の『鬼』という短編が収録された短編集も読み切りにいきたい。