
阿久津隆
@akttkc
2025年8月3日
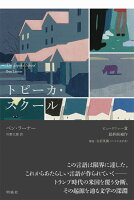
トピーカ・スクール
ベン・ラーナー,
川野太郎
読み始めた
短い導入部の次は「スプレッド(アダム)」というパートでアダムのパートで湖上のボートから恋人のアンバーが消えてアダムはテンパった。アンバーの家に入って寝ている家族の横を抜け、アンバーの部屋にアンバーが寝ていることが確認できると安心してトイレに入っておしっこをした。「見慣れないドライフラワーが下がっていた。記憶が一瞬でよみがえり、身震いとともに家の印象は一変した」。
p.14
間違った家にいるのに気づいて圧倒的な恐怖を感じたが、そんな家々の差異と同時にそれらの同一性も認識したことで、自分が湖を囲むすべての家に一時にいるという感覚におちいった。まったく同じレイアウトがもたらす崇高さ。それぞれの家で、彼女や彼女に似ただれかがベッドにいて、眠っているか、眠ったふりをしている。彼女の保護者が廊下の奥にいて、大きな身体でいびきをかいている。炉棚の家族写真の表情とポーズは変わるかもしれないが、その表情とポーズの文法はどれも同じだろう。絵画に描かれた場面の要素は異なるだろうが、そんな違いも、見慣れた感覚と単調さを変えるほどではない。巨大なステンレス製の冷蔵庫を開け、あるいは人造大理石のキッチン台を見渡せば、よく似通った、組み合わせがわずかに違うだけのモジュール式の製品に出くわすだろう。
認識がいちどきに組み変わる感じ。ほんの少し違う感じ。殺人者としての自分、強盗としての自分、間違えているだけの自分、状況から導き出されるあらゆる可能性が全部重なって存在する感じ。だいぶ窮地という場面でこんなことを考えている感じ。全部が愛おしいというか、ベン・ラーナーを読んでいる、という強い実感がやってきてうれしい。
そのあとアンバーと再開してアンバーが語る液状化して椅子からゆっくり滑り落ちる、聴衆がいなくなったことに気づかずに延々としゃべり続ける義父を遠くから見る、その場面もまたすごくよくて、『10:04』の教室で子どもたちがヒステリックに笑い続けるところとか、悲劇を冗談にするところとか、そういうところを思い出しながら読んでいて、いやあ、と胸いっぱい。










