
大森弥希
@mitsukiomori
2025年8月19日
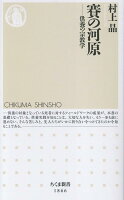
賽の河原
村上晶
買った
読み終わった
@ 電車
宗教社会学の立場からこれまで人々がどのように死者を供養してきたかを振り返りつつ、死者と生者のこれからを展望する内容。亡くなった子どもたちが向かうとされる賽の河原の初出は室町時代であり、江戸時代に地蔵信仰とともに広まっていく。日本のあちこちの河原で石が積まれ、なかでも青森県五所川原市金木町の河原の大祭はお酒を飲んで盆踊りではしゃいだり逢引が横行したりするような賑わいとなる。しかし時の流れとともに、2000年代頃からそうした大はしゃぎの一夜の性格は消失し死者の供養を目的とした祭へと姿を変えていく。また1980年代から1990年代までは、亡くなった子どもたちも成長していくという考え方から花嫁人形が奉納されたりしていたが、死者は生きていた時のままの姿で長く記憶し続けるべきであるという考え方に我々はシフトしつつある。死者に対してはお祭り騒ぎの要素は排して厳かに静かに悼むべきだ、いつまでも当時の姿を心に留めおくべきだ、という現代の感覚は、死者を忘却したり、生きている我々が日々を楽しんだり、ということがさも悪いことであるかのように、我々自身を縛ってしまう。本書の最後では、河鍋暁斎が描いた『地獄極楽めぐり図』(1869〜72年)が紹介される。亡くなった子どもたちが大はしゃぎしながら遊んでおり、その様子をお地蔵様が見守り、仏も天から眺めている。亡くなった子どもたちと生き残った我々との関係は、これからも変化していくだろう。できれば生者も死者も解放されていくような供養の仕方へと変わっていってほしい。


