

大森弥希
@mitsukiomori
医療に従事しているトランス女性。趣味で小説を書いたり、曲を作ったり、ベースを弾いたりしています。
- 2025年8月24日
 〈私〉を取り戻す哲学岩内章太郎読み終わった買った@ 電車宮台真司・東浩紀・國分功一郎と、日本の現代思想史上の三人を辿り直し、終わりなき日常・動物化・退屈というそれぞれのキーワードを再解釈したうえで、私たちはそのなかでサイバースペースが提供してくる世界に埋没し<私>を見失っている、と著者はいう。その上で、新デカルト主義の立場に立ち、まず自分自身とじっくり向き合い、拙速に決めつけるのではなく判断を保留することや、<私>を大切にするのと同様に、<私>の周囲やサイバースペースで出会うたくさんの<私>のことも大切にすることで<私>がゆたかになっていく、と論じられる。あとがきで「本書を書いている途中で、私はこれを家庭の中で実践できているのか、と何度も反省した」(p251)と著者は書いている。そういう姿勢が素晴らしいと思う。
〈私〉を取り戻す哲学岩内章太郎読み終わった買った@ 電車宮台真司・東浩紀・國分功一郎と、日本の現代思想史上の三人を辿り直し、終わりなき日常・動物化・退屈というそれぞれのキーワードを再解釈したうえで、私たちはそのなかでサイバースペースが提供してくる世界に埋没し<私>を見失っている、と著者はいう。その上で、新デカルト主義の立場に立ち、まず自分自身とじっくり向き合い、拙速に決めつけるのではなく判断を保留することや、<私>を大切にするのと同様に、<私>の周囲やサイバースペースで出会うたくさんの<私>のことも大切にすることで<私>がゆたかになっていく、と論じられる。あとがきで「本書を書いている途中で、私はこれを家庭の中で実践できているのか、と何度も反省した」(p251)と著者は書いている。そういう姿勢が素晴らしいと思う。 - 2025年8月21日
 読み終わった買った@ 電車子育てや介護は、する側がされる側に一方的にケアするものとして論じられやすい。でも実は、自身もまた、子どもや老いた親にケアされている側でもあるのだ。自らに子や老親が与えてくれているものに気がつくとき、ケアが双方向性を持つ行為であることがみえてくる。それを感じないまま一方的に自分が相手を支援していると思い込みつつケアをしていると、支援ではなく支配となっていく。労働を何よりも尊び生産性を至上のものとする昭和的価値観は、たしかに昭和においては焼け跡からの復興のために有効だった。ただし女性や障害者や性的マイノリティーなど多くの人々に犠牲を強い、社会から追いやるという結果も伴った。日本はとっくに衰退しているのにも関わらず昭和的価値観を引きずり続けているいまこそ、生産性至上主義の社会から、ケア的関係性を大切にする社会への転換の時期だと述べられる。医療や保育や介護にまで生産性向上を求めてくる厚生労働省の方々にも是非読んでほしい。
読み終わった買った@ 電車子育てや介護は、する側がされる側に一方的にケアするものとして論じられやすい。でも実は、自身もまた、子どもや老いた親にケアされている側でもあるのだ。自らに子や老親が与えてくれているものに気がつくとき、ケアが双方向性を持つ行為であることがみえてくる。それを感じないまま一方的に自分が相手を支援していると思い込みつつケアをしていると、支援ではなく支配となっていく。労働を何よりも尊び生産性を至上のものとする昭和的価値観は、たしかに昭和においては焼け跡からの復興のために有効だった。ただし女性や障害者や性的マイノリティーなど多くの人々に犠牲を強い、社会から追いやるという結果も伴った。日本はとっくに衰退しているのにも関わらず昭和的価値観を引きずり続けているいまこそ、生産性至上主義の社会から、ケア的関係性を大切にする社会への転換の時期だと述べられる。医療や保育や介護にまで生産性向上を求めてくる厚生労働省の方々にも是非読んでほしい。 - 2025年8月19日
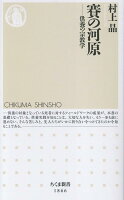 賽の河原村上晶読み終わった買った@ 電車宗教社会学の立場からこれまで人々がどのように死者を供養してきたかを振り返りつつ、死者と生者のこれからを展望する内容。亡くなった子どもたちが向かうとされる賽の河原の初出は室町時代であり、江戸時代に地蔵信仰とともに広まっていく。日本のあちこちの河原で石が積まれ、なかでも青森県五所川原市金木町の河原の大祭はお酒を飲んで盆踊りではしゃいだり逢引が横行したりするような賑わいとなる。しかし時の流れとともに、2000年代頃からそうした大はしゃぎの一夜の性格は消失し死者の供養を目的とした祭へと姿を変えていく。また1980年代から1990年代までは、亡くなった子どもたちも成長していくという考え方から花嫁人形が奉納されたりしていたが、死者は生きていた時のままの姿で長く記憶し続けるべきであるという考え方に我々はシフトしつつある。死者に対してはお祭り騒ぎの要素は排して厳かに静かに悼むべきだ、いつまでも当時の姿を心に留めおくべきだ、という現代の感覚は、死者を忘却したり、生きている我々が日々を楽しんだり、ということがさも悪いことであるかのように、我々自身を縛ってしまう。本書の最後では、河鍋暁斎が描いた『地獄極楽めぐり図』(1869〜72年)が紹介される。亡くなった子どもたちが大はしゃぎしながら遊んでおり、その様子をお地蔵様が見守り、仏も天から眺めている。亡くなった子どもたちと生き残った我々との関係は、これからも変化していくだろう。できれば生者も死者も解放されていくような供養の仕方へと変わっていってほしい。
賽の河原村上晶読み終わった買った@ 電車宗教社会学の立場からこれまで人々がどのように死者を供養してきたかを振り返りつつ、死者と生者のこれからを展望する内容。亡くなった子どもたちが向かうとされる賽の河原の初出は室町時代であり、江戸時代に地蔵信仰とともに広まっていく。日本のあちこちの河原で石が積まれ、なかでも青森県五所川原市金木町の河原の大祭はお酒を飲んで盆踊りではしゃいだり逢引が横行したりするような賑わいとなる。しかし時の流れとともに、2000年代頃からそうした大はしゃぎの一夜の性格は消失し死者の供養を目的とした祭へと姿を変えていく。また1980年代から1990年代までは、亡くなった子どもたちも成長していくという考え方から花嫁人形が奉納されたりしていたが、死者は生きていた時のままの姿で長く記憶し続けるべきであるという考え方に我々はシフトしつつある。死者に対してはお祭り騒ぎの要素は排して厳かに静かに悼むべきだ、いつまでも当時の姿を心に留めおくべきだ、という現代の感覚は、死者を忘却したり、生きている我々が日々を楽しんだり、ということがさも悪いことであるかのように、我々自身を縛ってしまう。本書の最後では、河鍋暁斎が描いた『地獄極楽めぐり図』(1869〜72年)が紹介される。亡くなった子どもたちが大はしゃぎしながら遊んでおり、その様子をお地蔵様が見守り、仏も天から眺めている。亡くなった子どもたちと生き残った我々との関係は、これからも変化していくだろう。できれば生者も死者も解放されていくような供養の仕方へと変わっていってほしい。 - 2025年8月14日
 他者といる技法奥村隆読み終わった買った@ 電車レインやゴフマン、ベイトソンやブルデューなどを引用しつつ、コミュニケーションの素晴らしさと苦しさが論じられる。社会というのは素晴らしくもあり、困難を抱えているものでもある。他者とは、わかりあえることもあり、わかりあえないこともある。無理に十全にわかりあおうとすると、それは他者に対し、自分と完全に一致する人格であることを求めることになり、容易に差別や暴力へと転じる。けっしてわかりあえない他者とともに過ごすことが、すなわち生きるということだ。親本が出たのは一九九八年だが、第5章「非難の語彙、あるいは市民社会の境界‐自己啓発セミナーにかんする雑誌記事の分析‐」(pp195-252)は今でもよくみる光景であるし、第3章「外国人は『どのような人』なのか」(pp111-151)は外国人排斥の言説が跋扈する二〇二五年現在、古びるどころか重要さを増している。
他者といる技法奥村隆読み終わった買った@ 電車レインやゴフマン、ベイトソンやブルデューなどを引用しつつ、コミュニケーションの素晴らしさと苦しさが論じられる。社会というのは素晴らしくもあり、困難を抱えているものでもある。他者とは、わかりあえることもあり、わかりあえないこともある。無理に十全にわかりあおうとすると、それは他者に対し、自分と完全に一致する人格であることを求めることになり、容易に差別や暴力へと転じる。けっしてわかりあえない他者とともに過ごすことが、すなわち生きるということだ。親本が出たのは一九九八年だが、第5章「非難の語彙、あるいは市民社会の境界‐自己啓発セミナーにかんする雑誌記事の分析‐」(pp195-252)は今でもよくみる光景であるし、第3章「外国人は『どのような人』なのか」(pp111-151)は外国人排斥の言説が跋扈する二〇二五年現在、古びるどころか重要さを増している。 - 2025年8月12日
 下駄の向くまま 新東京百景滝田ゆう読み終わった買った@ 自宅散歩エッセイというか呑み歩きエッセイのようなもの。日刊ゲンダイ連載。ここではKindle版のエディションしか出てこないが、実際には一九七八年講談社発行の単行本版で読んだ。訪れている町は新宿から始まり、立川に終わる。時代の流れを感じるのは、池袋を訪れた文章『夢の冷や酒池袋』(pp42-46)の「のれん越しに見上げる夜空に二つ三つ星などまたたいて、その向う、かつての巣鴨プリズン跡に目下建設中の超高層ビルは意外と近くにそびえて見える」という記述。サンシャイン60のこと。自分も当時既に物心ついていたので、建ったばかりの頃のお祭り騒ぎの記憶がうっすらとある。
下駄の向くまま 新東京百景滝田ゆう読み終わった買った@ 自宅散歩エッセイというか呑み歩きエッセイのようなもの。日刊ゲンダイ連載。ここではKindle版のエディションしか出てこないが、実際には一九七八年講談社発行の単行本版で読んだ。訪れている町は新宿から始まり、立川に終わる。時代の流れを感じるのは、池袋を訪れた文章『夢の冷や酒池袋』(pp42-46)の「のれん越しに見上げる夜空に二つ三つ星などまたたいて、その向う、かつての巣鴨プリズン跡に目下建設中の超高層ビルは意外と近くにそびえて見える」という記述。サンシャイン60のこと。自分も当時既に物心ついていたので、建ったばかりの頃のお祭り騒ぎの記憶がうっすらとある。 - 2025年8月10日
 新装版 虚無への供物(上)中井英夫借りてきた読み終わった@ 自宅ここではこのエディションしか出てこないけれど、実際には二〇〇〇年東京創元社刊行塔晶夫名義のエディション(全一巻)で読んだ。前半は登場人物たちの推理合戦が行われ、国内外の推理小説がふんだんに引用され、これはギャグではないか? と思うような、おもわず笑ってしまう台詞も多い。後半になるにつれシリアスな展開となり、一九五〇年代に実際に起きた事故や事件の引用が効果をあげ、我々推理小説を楽しむ読者のモラルが問い直される。
新装版 虚無への供物(上)中井英夫借りてきた読み終わった@ 自宅ここではこのエディションしか出てこないけれど、実際には二〇〇〇年東京創元社刊行塔晶夫名義のエディション(全一巻)で読んだ。前半は登場人物たちの推理合戦が行われ、国内外の推理小説がふんだんに引用され、これはギャグではないか? と思うような、おもわず笑ってしまう台詞も多い。後半になるにつれシリアスな展開となり、一九五〇年代に実際に起きた事故や事件の引用が効果をあげ、我々推理小説を楽しむ読者のモラルが問い直される。 - 2025年8月10日
- 2025年8月10日
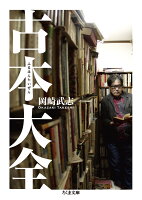 古本大全岡崎武志借りてきた読み終わった@ 自宅かつてちくま文庫から出ていて今は品切れの四冊に収録された文章と、未収録の文章を再編集した、ちくま文庫本。ちくま文庫好きとしては、それだけで、まず嬉しい。一番笑ったのは「『これはなんぼなんでもあきまへんやろ。本体がおまへん、函だけ』/『なんの、なんの。読む手間はぶけて大助かりや』」(p67)。上林暁の『聖ヨハネ病院にて』の舞台を散歩したり(pp186-193)、市川沙央の作中人物の「私は紙の本を憎んでいた」という台詞にドキッとしつつ、でも障害を持つ文学者は富田木歩や仁木悦子など過去にもいたことを冷静に指摘したり(pp386-387)、うんうんわかるわかる、と思いながら読み終えた。ああ、古本屋に行きたい。
古本大全岡崎武志借りてきた読み終わった@ 自宅かつてちくま文庫から出ていて今は品切れの四冊に収録された文章と、未収録の文章を再編集した、ちくま文庫本。ちくま文庫好きとしては、それだけで、まず嬉しい。一番笑ったのは「『これはなんぼなんでもあきまへんやろ。本体がおまへん、函だけ』/『なんの、なんの。読む手間はぶけて大助かりや』」(p67)。上林暁の『聖ヨハネ病院にて』の舞台を散歩したり(pp186-193)、市川沙央の作中人物の「私は紙の本を憎んでいた」という台詞にドキッとしつつ、でも障害を持つ文学者は富田木歩や仁木悦子など過去にもいたことを冷静に指摘したり(pp386-387)、うんうんわかるわかる、と思いながら読み終えた。ああ、古本屋に行きたい。 - 2025年8月9日
 敗戦日記串田孫一,二宮敬,渡辺一夫読み終わった買った@ 電車本編の『敗戦日記』は一九四五年三月十一日から八月十八日まで。『続敗戦日記』は同年八月十八日から十一月二十二日まで。どちらも、公刊を想定して書かれたものではない。合わせて収録されているのは戦中および戦後すぐに書かれた文章と書簡。作家の日記のような情景描写や街の人々の様子はこの日記からは窺われないが、渡辺自身が、敗戦へと国全体が向かうなか学者としていかに煩悶し時に自死をまで考えていたか、また八月十五日以降の時流に憂いを感じていたかが、赤裸々に記されている。
敗戦日記串田孫一,二宮敬,渡辺一夫読み終わった買った@ 電車本編の『敗戦日記』は一九四五年三月十一日から八月十八日まで。『続敗戦日記』は同年八月十八日から十一月二十二日まで。どちらも、公刊を想定して書かれたものではない。合わせて収録されているのは戦中および戦後すぐに書かれた文章と書簡。作家の日記のような情景描写や街の人々の様子はこの日記からは窺われないが、渡辺自身が、敗戦へと国全体が向かうなか学者としていかに煩悶し時に自死をまで考えていたか、また八月十五日以降の時流に憂いを感じていたかが、赤裸々に記されている。 - 2025年8月3日
- 2025年8月1日
 理由あって冬に出る似鳥鶏借りてきた読み終わった@ 電車学園ミステリ。舞台は放課後の、芸術棟と呼ばれる、文化系の部活や同好会の部室が並ぶ四階建て。主人公は美術部の少年。ある事件が起こり、吹奏楽部や演劇部、文芸部の少年少女が次々と登場して、事件を解決しようとする。学園ものが好きだ。特に文化系の連中がわちゃわちゃするものが好きだ。それは、自分がそうであったからでもある。もっとも、自分が学生の頃は、フィクションの中の連中がやたら眩しくみえ、それに比べて現実のなんと味気ないこと、と思いながら読んでいた。いまは、そうでもない。あの頃の自分たちも、それなりに眩しく振り返ることができる。自分たちはとっくの昔に大人になったが、あの頃読んだフィクションの中の連中は、閉じられたページの隙間でわちゃわちゃやり続けているだろう。永遠に。
理由あって冬に出る似鳥鶏借りてきた読み終わった@ 電車学園ミステリ。舞台は放課後の、芸術棟と呼ばれる、文化系の部活や同好会の部室が並ぶ四階建て。主人公は美術部の少年。ある事件が起こり、吹奏楽部や演劇部、文芸部の少年少女が次々と登場して、事件を解決しようとする。学園ものが好きだ。特に文化系の連中がわちゃわちゃするものが好きだ。それは、自分がそうであったからでもある。もっとも、自分が学生の頃は、フィクションの中の連中がやたら眩しくみえ、それに比べて現実のなんと味気ないこと、と思いながら読んでいた。いまは、そうでもない。あの頃の自分たちも、それなりに眩しく振り返ることができる。自分たちはとっくの昔に大人になったが、あの頃読んだフィクションの中の連中は、閉じられたページの隙間でわちゃわちゃやり続けているだろう。永遠に。 - 2025年7月29日
 夢殿殺人事件小栗虫太郎読み終わった買った@ 電車『黒死館殺人事件』でおなじみの刑事弁護士・法水麟太郎が活躍する短編六つ。どれもこれも、おどろおどろしく、悪趣味全開(いい意味で)。いわゆる推理小説としての、ああ! そういうカラクリだったのか! といった謎解きの爽快感はないかわりに、無茶苦茶な設定や、あやふやでいかがわしい歴史学的だったり生理学的だったりする説明の多用に、わけわからん! と感じつつも、煙に巻かれる快感を味わえる。表題作の、廻転し続けるあるものには、読んでいて大笑いしてしまった。
夢殿殺人事件小栗虫太郎読み終わった買った@ 電車『黒死館殺人事件』でおなじみの刑事弁護士・法水麟太郎が活躍する短編六つ。どれもこれも、おどろおどろしく、悪趣味全開(いい意味で)。いわゆる推理小説としての、ああ! そういうカラクリだったのか! といった謎解きの爽快感はないかわりに、無茶苦茶な設定や、あやふやでいかがわしい歴史学的だったり生理学的だったりする説明の多用に、わけわからん! と感じつつも、煙に巻かれる快感を味わえる。表題作の、廻転し続けるあるものには、読んでいて大笑いしてしまった。 - 2025年7月27日
 ぼく、バカじゃないよ藤野千夜借りてきた読み終わった時代は昭和四十年代から五十年代にかけて。団地住まいの保育園児の話。主人公のとっちゃんに、自分自身の幼年時代を重ね合わせて読んだ。とっちゃんは、周囲の子どもたちと一緒に過ごすことが嫌いで、一人でいるときが一番楽しそうだ。次が、お母さんやお父さんやおばあちゃんや弟と過ごしているときなのかな。生きづらそうではあるけれど、でも、家族はとっちゃんをわかってくれようとしているようだし、すごく幸せ者だなあ、と感じた。
ぼく、バカじゃないよ藤野千夜借りてきた読み終わった時代は昭和四十年代から五十年代にかけて。団地住まいの保育園児の話。主人公のとっちゃんに、自分自身の幼年時代を重ね合わせて読んだ。とっちゃんは、周囲の子どもたちと一緒に過ごすことが嫌いで、一人でいるときが一番楽しそうだ。次が、お母さんやお父さんやおばあちゃんや弟と過ごしているときなのかな。生きづらそうではあるけれど、でも、家族はとっちゃんをわかってくれようとしているようだし、すごく幸せ者だなあ、と感じた。 - 2025年7月27日
 海が見える家はらだみずき借りてきた読み終わった@ 電車父と息子の物語。かつて父に言い放った言葉が自分に返ってくる、というのは、少し私にも心当たりがある。とはいえ、このお話では、主人公にとって父親の生き方が、知れば知るほど眩しいものであるから、かつて自身が言い放った言葉の重みと深さに自身の生き方を変えられていくのであって、私にとっては父親の生き方は全くそういうものではないのだけれども。自分の人生を評価するのは、自分自身なのだ。他人には、好きに言わせておけばいい。その他人が恋人だとしても、父親だとしても。ここではKindle版しか出てこないけど、実際には文庫で読みました。
海が見える家はらだみずき借りてきた読み終わった@ 電車父と息子の物語。かつて父に言い放った言葉が自分に返ってくる、というのは、少し私にも心当たりがある。とはいえ、このお話では、主人公にとって父親の生き方が、知れば知るほど眩しいものであるから、かつて自身が言い放った言葉の重みと深さに自身の生き方を変えられていくのであって、私にとっては父親の生き方は全くそういうものではないのだけれども。自分の人生を評価するのは、自分自身なのだ。他人には、好きに言わせておけばいい。その他人が恋人だとしても、父親だとしても。ここではKindle版しか出てこないけど、実際には文庫で読みました。 - 2025年7月15日
 言葉の展望台三木那由他読み終わった買った@ 自宅現代分析哲学・言語哲学が専門の方によるエッセイ集。トランスジェンダー当事者によるエッセイ集としても読めるし、「『私』のいない言葉」(pp94-102)は、私自身もトランスジェンダーであることもあり、いろいろな幼少期の嫌で悲しい記憶が蘇ってきながら当時抱いていたどろどろした感情の渦に巻き込まれそうになったのだが、しかし、著者は、あくまでも学者なのである。ある方の著書を読み、その本を楽しみながらも、しかし、著者自身が子どもの頃から抱き続けている謎はまだ解けない、と、上記の文章は閉じられ、私も、負の感情に落ち込み続ける危険にはいたらず、むしろ、これまでとこれからを見つめ直すいいきっかけになった。
言葉の展望台三木那由他読み終わった買った@ 自宅現代分析哲学・言語哲学が専門の方によるエッセイ集。トランスジェンダー当事者によるエッセイ集としても読めるし、「『私』のいない言葉」(pp94-102)は、私自身もトランスジェンダーであることもあり、いろいろな幼少期の嫌で悲しい記憶が蘇ってきながら当時抱いていたどろどろした感情の渦に巻き込まれそうになったのだが、しかし、著者は、あくまでも学者なのである。ある方の著書を読み、その本を楽しみながらも、しかし、著者自身が子どもの頃から抱き続けている謎はまだ解けない、と、上記の文章は閉じられ、私も、負の感情に落ち込み続ける危険にはいたらず、むしろ、これまでとこれからを見つめ直すいいきっかけになった。 - 2025年7月6日
 エスノグラフィ入門石岡丈昇読み終わった買った@ 電車すごくわかりやすく、とても勇気づけられる入門書。最後まで読んで、それは、著者が本書で取り上げている日常生活批判という視座(p126)を徹底的に血肉化していることによるのだなあ、と感じ入った。北海道大学の遠友学舎(p271)、初めて知った。北大、札幌を訪れた十数年前、余った時間でキャンパスを歩きまわったことがあったけど、存在知らなかったなー。今度訪れることがあれば、ぜひ寄りたい。
エスノグラフィ入門石岡丈昇読み終わった買った@ 電車すごくわかりやすく、とても勇気づけられる入門書。最後まで読んで、それは、著者が本書で取り上げている日常生活批判という視座(p126)を徹底的に血肉化していることによるのだなあ、と感じ入った。北海道大学の遠友学舎(p271)、初めて知った。北大、札幌を訪れた十数年前、余った時間でキャンパスを歩きまわったことがあったけど、存在知らなかったなー。今度訪れることがあれば、ぜひ寄りたい。 - 2025年7月2日
 質的研究の方法小田博志,波平恵美子読み終わった買った@ 自宅質的研究をすすめている最中に手に取った本。医療の分野で質的研究を行う際の、示唆に富む記述が多く、とても勇気づけられた。後半ではアブダクションについて語られており、四半世紀ほど前に南方熊楠や鶴見和子の延長線上で少しかじったCharles Sanders Peirceに出会い直すこととなった。intermezzoとして第Ⅰ部と第Ⅱ部の間に置かれている『子どもの時の体験と「プロの『よそ者』」への道』がとても深い。子どもの頃の経験も、研究のための貴重な資源であるということ。「子どもが思ったり感じたことを全部言葉で充分相手に伝わるように話しはじめたら、世の中変わるだろうなといつも思うんですよ」(p111)。
質的研究の方法小田博志,波平恵美子読み終わった買った@ 自宅質的研究をすすめている最中に手に取った本。医療の分野で質的研究を行う際の、示唆に富む記述が多く、とても勇気づけられた。後半ではアブダクションについて語られており、四半世紀ほど前に南方熊楠や鶴見和子の延長線上で少しかじったCharles Sanders Peirceに出会い直すこととなった。intermezzoとして第Ⅰ部と第Ⅱ部の間に置かれている『子どもの時の体験と「プロの『よそ者』」への道』がとても深い。子どもの頃の経験も、研究のための貴重な資源であるということ。「子どもが思ったり感じたことを全部言葉で充分相手に伝わるように話しはじめたら、世の中変わるだろうなといつも思うんですよ」(p111)。
読み込み中...


